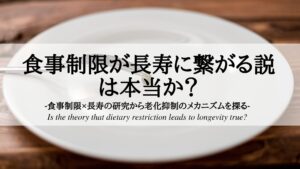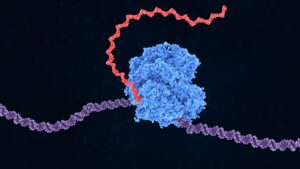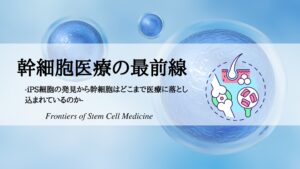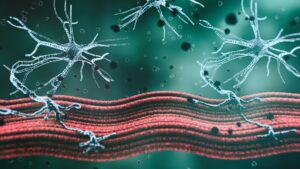はじめに
社会人になって、運動不足に悩んで筋トレを始める方は多くいらっしゃるかと思います。しかしながら、そもそも筋肉がどのようなものかご存知無い方は多いのではないでしょうか。本記事は筋肉の科学と題して、筋肉の種類やその中で骨格筋とはどのようなものかご紹介させていただきます。
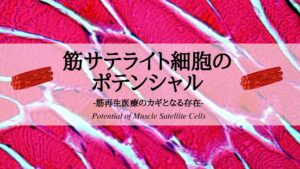
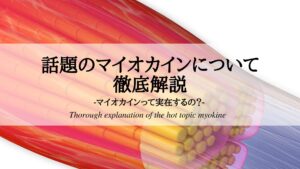
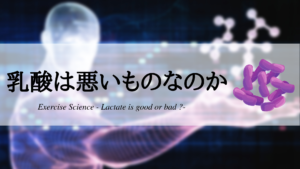
筋肉の種類とは?
まずは、筋肉の種類について解説していきます。
骨格筋の種類〜横紋筋と平滑筋〜
筋肉には横紋筋と平滑筋と呼ばれる二種類の筋肉があることが知られています。横紋筋はその名の通り横の文様が見える筋肉です。一方平滑筋は滑らかな筋肉で、内臓の筋肉などがそれに当たります。横紋筋はさらに大きく分けて骨格筋と心筋と呼ばれる二種類に分類されます。基本的に骨格筋以外は不随意筋と呼ばれ、自分で鍛えることが出来ない筋肉です。

横紋筋と平滑筋の構造
それでは、それぞれの筋肉の構造について見ていきましょう。平滑筋を構成する筋細胞は単核の細胞で、それぞれ入り混じったような形で存在します。そのため、横から見た時に一つ一つの筋細胞の核が確認できます。一方、横紋筋は英語でstriated muscleといい、その名の通り横に模様がある筋肉なので、横から見たときに縞模様が確認できます。
非常にざっくりとしたイメージとしては下の図のようになります。

このように、筋肉は種類によって見た目も大きく異なるのです。身体を鍛えるとなると骨格筋が重要となるので、骨格筋の構造についてもう少し細かく見ていきたいと思います。
骨格筋の構造
骨格筋は無数の筋繊維で構成されており、その筋繊維の中にはさらに無数の筋原線維が束になって存在しています。筋原線維を俯瞰してみると、その太さは1㎛(=0.001mm)ほどと非常に細いことがわかります。それぞれの筋原線維には、アクチンとミオシンというタンパク質が含まれており、それらが相互に作用して筋肉に張りを生み出しています。

筋肉に発生する張力は、神経系によって制御された筋原繊維の収縮と弛緩によって生み出されます。筋原繊維の収縮と弛緩を交互に繰り返すことで、骨格筋全体に安定した活動電位が伝わり、収縮することができるのです。次に、骨格筋の神経支配についてもう少し細かく見ていきましょう。
骨格筋の神経支配
骨格筋は神経によって支配されています。中枢神経である脳から脊髄、そして末梢神経という流れで骨格筋に繋がっています。一つひとつの骨格筋と神経のセットを運動単位(motor neuron)と呼びます。筋収縮の命令を行う場合、脳から命令が出されて脊髄を通って筋肉にまで届けられるわけです。
次に、運動単位の中の神経と筋肉の接合部分によりフォーカスして見てみましょう。神経と筋肉の接合部は神経筋接合部(neuromuscular junction)と呼ばれます。神経筋接合部では中枢神経から伝導されてきた刺激(活動電位)が化学物質(アセチルコリン)として神経→骨格筋へと伝えられます。刺激を受けた骨格筋は筋小胞体からのCaイオンの流出などを通じて筋収縮を行います。

骨格筋の種類
骨格筋にはさまざまな種類があり、様々な方法でタイプ分けされます。ここでは、日本でよく見る筋肉のタイプ分け赤筋(遅筋)、白筋(速筋)、そしてピンク筋の三種類の分け方で見ていきます。赤筋は持久力に優れている筋肉です。ミオグロビンが多く、ミトコンドリアも豊富に含まれているとされています。逆に白筋は収縮速度が速く、大きな力を出すことが出来る筋肉です。ピンク筋は白筋と赤筋の間のような性質を持っています。
赤筋が赤く見える理由はそのミオグロビンによるとされています。赤いほどミオグロビン、ミトコンドリアが多くて持久力に長けている、とすると理解しやすいです。
骨格筋は運動トレーニングを始めとした生理的な刺激によって性質が変わることが知られています。そのことを骨格筋の可塑性(かそせい)と呼びます。
白筋は運動トレーニングによって持久性を持ち、持久性を獲得した白筋をピンク筋と呼びます。ただ、赤筋はピンク筋、白筋へと基本的に変化しないことも知られていて、このあたりは運動トレーニングの非常に面白いところでもあります。

ミオグロビンが赤筋の色の理由と言われていますが、一方ミオグロビンが存在しないマウスでも運動トレーニング効果が確認されることが報告されています。つまり、「骨格筋にミオグロビンがあれば、持久力が高くなる」とは学術的には一概に言えないのです。
Functional and molecular adaptations in skeletal muscle of myoglobin-mutant mice
https://journals.physiology.org/doi/epdf/10.1152/ajpcell.2001.281.5.C1487
↑論文に記載されている結果としては、「ミオグロビンが存在しないマウスにおいて、運動トレーニングはヒラメ筋のtypeI→typeIIを促進する。」とのことです。
骨格筋のタイプ分けには本当に様々なタイプ分け方法があります。よくある方法はmyosinのATPaseの組織化学的染色による分類とmyosin heavy chainのisoformと代謝酵素の生化学的同定、この三種類です。
これら三種類の方法を組合わせて、骨格筋をtype I、typeIIa、type IIbの三種類に分ける方法が学術的によく用いられます。それぞれ簡単に分類を記載します。
type I(遅筋):酸化筋 収縮は遅いが持久力がある。ATPの生成も有機的
type IIA(遅筋):アナロビックな筋肉に変換可能な筋肉
type IIB(速筋):アナロビックな筋肉 筋収縮も速い
この記事での分類と対応させるとtype Iが赤筋、typeIIAがピンク筋、typeIIBが白筋という感じですね。
興味がある方は以下の論文を読んでみて下さい。骨格筋のタイプ分けの説明論文として非常に有名なものです。
https://academic.oup.com/ptj/article/81/11/1810/2857618
さて、いかがでしたでしょうか。今回は筋肉の概要を説明させていただきました。ざっくり筋肉の種類と骨格筋とはどのようなものであるかご理解いただけると嬉しいです。また次回でさらに骨格筋のマニアックな話と実際の運動トレーニングの話も記載していきたいと考えています。
乞うご期待。