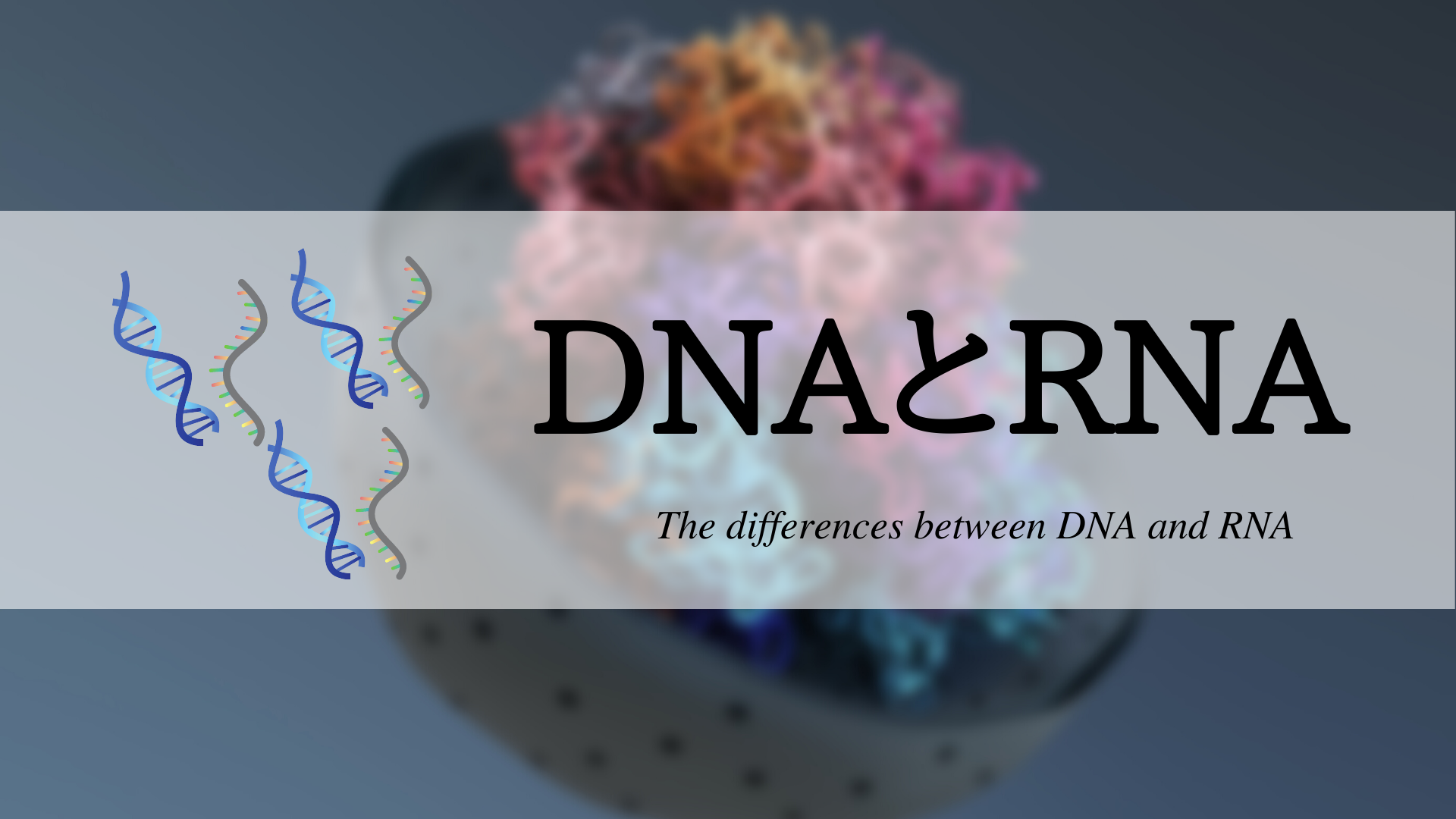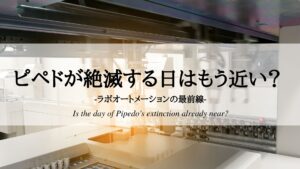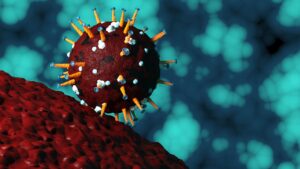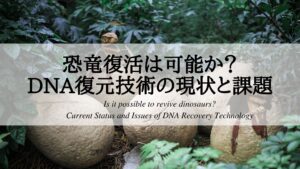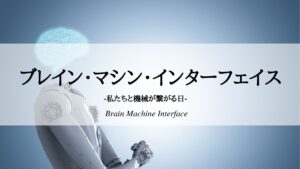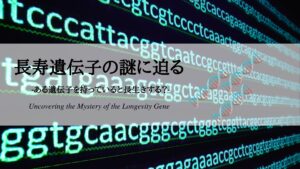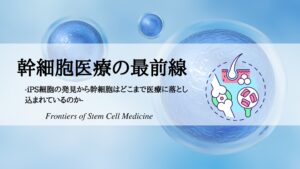はじめに
DNAとRNAは核酸分子と呼ばれる非常に似た物質です。
ともに分子生物界のセントラルドグマとして中心の物質でありながら、それぞれに様々な種類があることはあまり理解されていません。
具体的には、DNAにワトソンとクリックが定めたもの以外の形があることやRNAにnon-coding RNAと呼ばれるタンパク質の翻訳に関わる物質が存在することは知っている人の方が少ない印象です。
本記事では、DNA、RNAの基本から知られざる多様な種類について概要をご紹介いたします。


DNAとRNAをセントラルドグマから理解する

DNAは生命の設計図とも呼ばれるように、生命のすべてのベースです。基本的にDNAに記載のある情報を基に生命は形作られますが、DNAから直接そのまま生命体が「えいや」で出来るわけではなく、DNAはRNAへの転写を介して、蛋白質が生成(翻訳)されます。
この一連の流れはセントラルドグマと呼ばれ、生命活動のすべての根幹の理論となっています。基本的にこのセントラルドグマに当てはめた場合、分子の性質上DNAとRNAには大きな違いは無いように見えます。DNAがRNAの役割をしてRNAがDNAの役割をしても結局同じでは?とさえ思ったりします。なんならさらに、「転写と翻訳とかあまり大きな違いはないので、DNAから直接蛋白質が生成されたほうが効率が良いのでは?」なんて思ってしまったりもします。
しかしながら、より高精度で欠陥が少ない生命活動の実現のためにDNAやRNAは存在していると考えられており、DNAやRNAによる転写・翻訳プロセスは半世紀ほど前の発見当初よりも複雑なものであることが近年より明確になってきています。
加えて、DNAやRNA自体も多くの種類が存在することが明らかになってきており、基礎・臨床ともに多くの研究者の興味の対象となっています。
次からはDNAとRNAの具体的な種類について見ていきましょう。
様々なDNAとRNA

DNAとRNAには様々な役割があります。ワトソンとクリックがDNAの二重螺旋構造を提唱した1953年には明らかになっていなかったDNAとRNAが後の研究で明らかになっていきました。
例えば、mRNAはRNAの一種ですが、中でもDNAの遺伝配列からタンパク質の情報を伝達するために用いられます。また、tRNAはmRNAから受け取った情報をリボソームに届けるために重要な役割を担うRNAです。そしてさらに、このように転写と翻訳と呼ばれるDNAからタンパク質が生成される過程で役に立つRNAが存在する一方で、他の遺伝子のタンパク質発現制御に関わるmiRNA(マイクロRNA)と呼ばれるRNAも存在します。

そしてDNAやRNAはある一つ定まった形が存在するわけではなく、機能も形もそして構成する核酸も様々です。以下ではその代表的なものをリストとしてまとめています。
代表的なDNA、RNA
| 略称 | 正式名称 | 読み方 | 機能 |
| DNA | DeoxyriboNucleic Acid | ディーエヌエー | 遺伝情報を特に表すものをゲノムDNAと呼ぶこともある。 |
| mtDNA | mitochondria DNA | ミトコンドリアディーエヌエー | ミトコンドリア内にあるDNA。 |
| RNA | RiboNucleic Acid | アールエヌエー | リボースを糖成分とする核酸 |
| mRNA | messenger RNA | エムアールエヌエー, メッセンジャーアールエヌエー | 遺伝子の遺伝配列に対応する一本鎖のRNA |
| tRNA | transfer RNA | ティーアールエヌエー | mRNAとタンパク質のアミノ酸配列とを物理的に結びつける |
| rRNA | ribosome RNA | リボソームアールエヌエー | リボソームを構成するRNA。 |
| miRNA | micro RNA | マイクロアールエヌエー | 他の遺伝子発現の制御など |
| non-coding RNA | non-coding RNA | ノンコーディングアールエヌエー | タンパク質へ翻訳されずに機能するRNAの総称 |
| siRNA | small interfering RNA | エスアイアールエヌエー | 他のRNAに干渉し、遺伝子の発現を制御 |
| snRNA | Small nuclear RNA | 核内低分子アールエヌエー | 核内のmRNAの処理に関わる |
| lncRNA | long noncoding RNA | ロングノンコーディングアールエヌエー | タンパク質へ翻訳されないRNAの中でも200ヌクレオチド以上の長さのもの |
| piRNA | PIWI-interacting RNA | ピーアイアールエヌエー | 生殖細胞特異的に発現する小分子RNA |
DNAとRNAの構成分子の違い
DNAとRNAは根本的に何が異なるでしょうか。まずこれらはヌクレオチドと呼ばれますが、その基本構成単位を見ていきましょう。
リン酸+糖+塩基-> ヌクレオチド
リン酸+糖 ->ヌクレオシド と呼びます
模式図的には以下のようになります。

DNAとRNAの違いですが、この2つの違いはその名前の通りです。Deoxyribonucleic acid(DNA) とribonucleic acid(RNA)、この2つはDeoxyという文字があるか否かが異なります。赤字のOHがある糖がリボースで無い糖がデオキシリボースです。
つまり、DNAを構成する糖がデオキシリボースで、RNAを構成する糖がリボースであるということです。
DNAとRNAは構成する塩基も異なります。
アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)はDNAもRNAも共通ですが、DNAではチミン(T)であるのに対し、RNAはチミン(T)の代わりにウラシル(U)が塩基として用いられます。
化学式の構成上アデニン(A)、グアニン(G)はプリン塩基、シトシン(C)、チミン(T)、ウラシル(U)はピリミジン塩基と呼ばれるので、それを基にDNAとRNAを構成する塩基の違いをまとめると以下のようになります。
| プリン塩基 | ピリミジン塩基 | |
| DNA | A、G | C、T |
| RNA | A、G | C、U |
そしてDNAは二重らせん構造と呼ばれる構造のため、AとT、そしてGとCがペアとなって相補的になるわけですが、これは化学的な結合によります。
しかしながら、ここでDNAは必ず二重らせん構造を取るのか、という疑問が生じますね。
それだけじゃない核酸分子の構造
例えばDNAの中でワトソンとクリックに発見された二重らせん構造は実はB-DNAと呼ばれていて、あくまで1つのDNAの構造に過ぎません。以下のレビュー論文(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2022.959258/full)ではDNAの非定型構造として6つの形を紹介しています。
中でもTriplexDNAについて少し見ていきましょう。
Triplex(三重)DNAは3本の鎖からなるDNAの構造です。
Triplex DNAは転写や翻訳、スプライシング、そしてタンパク質の活性に影響を及ぼすとされています。
ハンチントン病、フリードライヒ失調症、脆弱X症候群、筋緊張性ジストロフィー、あるタイプの脊髄小脳変性症といった疾患との関連も研究されていて、癌や神経変性疾患の治療ターゲットとしても考えられています。
表に記載した以外にも様々なDNAの非定型構造が知られています。
| 構造 | はたらき | 治療への利用 | 関連疾患 | |
| Triplex DNA | single-stranded triplex-forming oligonucleotide (TFO) binds to the major groove of polypurine•polypyrimidine (Pu•Py) segments of a target duplex in a sequence-specific manner. | transcription (antigene strategy), translation (antisense strategy), splicing, or protein activityの抑制 遺伝子再編成 | cancer and other neurological diseases | Huntington’s disease, Friedreich ataxia, fragile X syndrome, myotonic dystrophy, and certain types of spinocerebellar ataxia |
| Cruciform DNA | Palindrome 配列がある箇所に発生する十字形もしくはヘアピン型の構造 | Hereditary angioneurotic edema、 Duchenne muscular dystrophy, Triplet repeat mediated diseaseなど | ||
| Hairpin DNA | ||||
| i-motif DNA | 治療ターゲットおよび創薬の促進 | Parkinson’s disease | ||
| Z-DNA | 左巻きの二重らせん構造 | 大規模なDNA配列の欠損 | ||
| G-quadruplex DNA | テロメアのメンテナンス、疾患関連遺伝子の転写、複製制御 | がん治療 | αサラセミア、Werner syndrome、Fanconi anemia、Bloom syndrom、fragile X syndrome、amyotrophic lateral sclerosis、frontotemporal dementia、primary progressive aphasia、depressive pseudo depressive dementia |
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2022.959258/full
まとめ
さて、いかがでしたでしょうか。
DNAとRNAは同じ核酸分子ではありますが、それぞれ役割が異なります。また、DNAはワトソンとクリックによって発見された二重螺旋構造だけではなく、TriplexDNAを始めとした複雑な高次構造を取り、それらは疾患との関連も報告されています。
今後のさらなる研究も期待されますね。
ではまた別の記事でお会いしましょう。