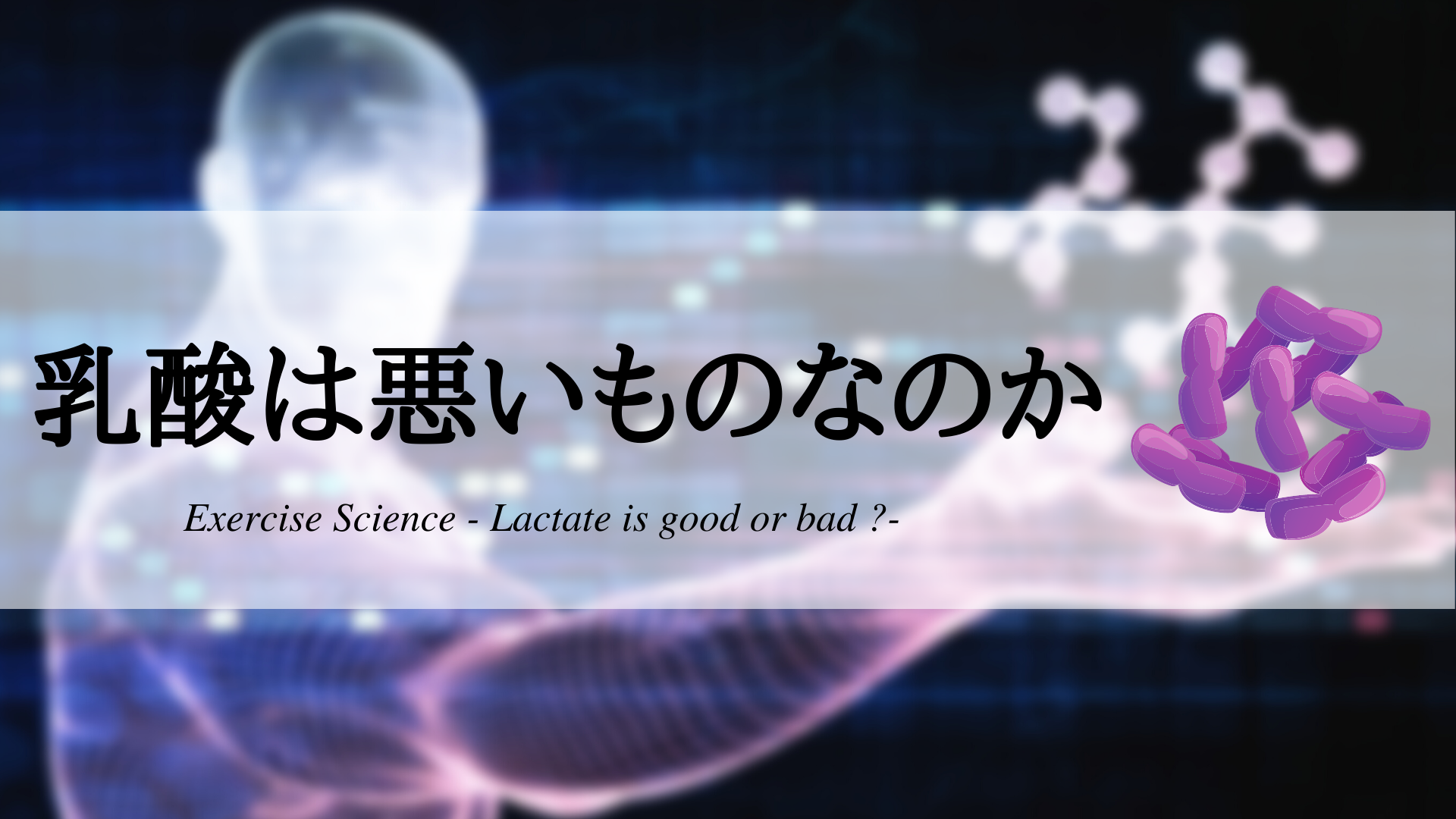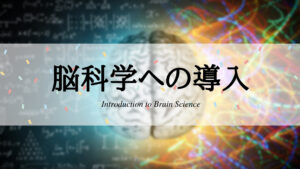はじめに:誰もが知るあの「灼熱感」―根深い神話を科学の目で見直す
激しい運動の最中、筋肉が焼け付くような感覚に襲われ、思わず動きを止めてしまった経験は誰にでもあるでしょう 1。全力疾走やウェイトトレーニングの最後のひと踏ん張りで感じる、あの独特の「灼熱感」。私たちは長年、この感覚やそれに続く筋疲労、そして翌日の筋肉痛の原因は、「乳酸」という疲労物質の蓄積によるものだと教えられてきました 1。
この考えは、スポーツの現場からフィットネスクラブ、さらには学校の体育の授業に至るまで、広く浸透しています。しかし、もしこの常識が、運動科学における最大級の誤解の一つだとしたらどうでしょうか。本稿の目的は、この根深い神話を科学的証拠に基づいて解き明かし、乳酸の真の姿を明らかにすることです。かつて代謝の「悪役」と見なされていた乳酸が、実は私たちの体を支える重要な「ヒーロー」であったという、驚くべき物語にご案内します 3。


第1章:悪役の誕生 ― 100年前に生まれた科学的誤解
乳酸が悪者とされた物語は、20世紀初頭の実験室から始まります。科学者たちが筋肉の謎に迫ろうとしていた時代、いくつかの重要な発見が、後に巨大な誤解を生む土台を築きました。
最初の発見:疲労と乳酸の相関関係
物語の幕開けは1907年、イギリスの科学者フレッチャーとホプキンスによる画期的な研究でした。彼らは、カエルの脚から取り出した筋肉を電気で刺激し、疲労困憊するまで収縮させる実験を行いました。そして、疲労した筋肉には「乳酸」が大量に蓄積していることを科学的に初めて突き止めたのです 6。これは、「筋肉の疲労」と「乳酸の蓄積」という二つの現象を直接結びつけた、決定的な発見でした。
ノーベル賞が与えた権威
この相関関係に、強力な「原因」というレッテルを貼るきっかけとなったのが、1920年代の二人のノーベル賞受賞者、ドイツのオットー・マイヤーホフとイギリスのアーチボルド・V・ヒルによる研究です 8。
マイヤーホフは、密閉容器に入れたカエルの脚を用いた実験で、筋肉が酸素のない状態(嫌気的条件)でグリコーゲン(糖の一種)を分解し、乳酸を生成することを示しました 1。一方、ヒルは筋肉が収縮する際に発生する熱を精密に測定し、マイヤーホフの生化学的な発見と結びつけました 9。彼らの研究は、筋肉のエネルギー代謝における好気的プロセスと嫌気的プロセスの違いを明らかにした功績として、1922年のノーベル生理学・医学賞を共同で受賞しました 9。
このノーベル賞という最高の権威が、「酸素が不足すると乳酸が作られ、それが筋肉を疲労させる」という「乳酸仮説」に絶大なお墨付きを与えたのです。
実験室から伝説へ
こうして確立された「乳酸仮説」は、瞬く間に科学界の定説となり、実験室の壁を越えて世の中に広まっていきました。スポーツ解説者、コーチ、ジャーナリストたちは、何十年にもわたって「乳酸との戦い」という物語を語り続け、一般の人々の意識の中に「乳酸=悪」というイメージを深く刻み込んでいったのです 2。
しかし、この説には当初から見過ごされた重大な前提がありました。それは、これらの実験が、生きた哺乳類ではなく、低温環境に置かれたカエルから摘出された筋肉で行われていたという点です 1。この単純な事実は、後に乳酸の評価を180度覆す重要な伏線となります。初期の研究者たちは、観察された現象、つまり疲労と乳酸の蓄積という「相関関係」を、性急に「因果関係」と結論づけてしまいました。ノーベル賞という権威がその結論を補強し、半世紀以上にわたって誰もが疑わない「科学的真実」として君臨し続けることになったのです。
第2章:乳酸革命 ― 老廃物からスーパー燃料へ
1980年代、長らく続いた乳酸の汚名に終止符を打つ、革命的な理論が登場します。その中心人物が、カリフォルニア大学バークレー校のジョージ・ブルックス博士です。彼が提唱した「乳酸シャトル説」は、乳酸の役割を根本から書き換え、代謝の世界における新たなパラダイムを打ち立てました 2。
細胞から細胞へ:乳酸シャトル説
ブルックス博士が提唱した「細胞間乳酸シャトル」は、乳酸が老廃物ではなく、体内で効率的に再利用される優れたエネルギー源であることを明らかにしました。この仕組みは、体内の見事なリサイクル・配送システムに例えることができます 15。
激しい運動中、私たちの筋肉の中では、瞬発力を得意とする「スプリンター線維」(速筋線維)が、エネルギーを素早く作り出すために解糖系という代謝経路をフル回転させ、その結果として大量の乳酸を産生します 18。しかし、この乳酸は捨てられるのではなく、血流に乗って全身へと「シャトル(輸送)」されます。
輸送された乳酸は、持久力を得意とする「マラソン線維」(遅筋線維)や、運動中に休むことなく働き続ける心臓、さらには脳といった、高い酸化能力を持つ組織に取り込まれます。これらの組織は、グルコース(ブドウ糖)よりも乳酸を優先的にエネルギー源として利用することを好みます。特に心臓は、運動中にエネルギー需要の大部分を乳酸で賄うことができる、優れた「乳酸消費者」なのです 15。
細胞の中のシャトル:ミトコンドリアとの連携
さらに驚くべきことに、乳酸シャトルは細胞と細胞の間だけでなく、一つの細胞の内部でも機能していることが明らかになりました。
細胞のエネルギー工場である「ミトコンドリア」には、乳酸を細胞質から内部へ直接取り込むための専用の輸送体(MCT1)が存在することが発見されたのです 15。これは、乳酸が単なる「嫌気的」代謝の産物であるという古い定説を覆す決定的な証拠でした。乳酸は、酸素を使わない解糖系と、酸素を使うミトコンドリアの呼吸系とを結びつける、代謝の重要な架け橋だったのです 16。
アシドーシスの真犯人
では、運動中に感じるあの「灼熱感」、すなわち筋肉のアシドーシス(酸性化)の原因は何なのでしょうか。最新の研究では、その主犯は乳酸ではないことがわかっています。
体内で生成された乳酸(Lactic acid)は、即座に乳酸イオン(Lactate)と水素イオン($H^+$)に解離します。筋肉のpHを低下させる直接の原因は、この水素イオンの蓄積です。しかし、この水素イオンの大部分は、乳酸の生成過程ではなく、ATP(アデノシン三リン酸)というエネルギー通貨が分解される過程で放出されます 5。
むしろ、ピルビン酸から乳酸が生成される化学反応($Pyruvate + NADH + H^+ \rightarrow Lactate + NAD^+$)では、水素イオンが1つ消費されます。つまり、乳酸の生成はアシドーシスをわずかに緩和する方向に働くのです。さらに、乳酸シャトルは、細胞内に溜まった水素イオンを乳酸イオンと共に細胞外へ運び出す役割も担っており、細胞内環境を急激な酸性化から守る働きもしています 5。
乳酸の生成は、酸素供給の「失敗」のしるしではなく、高いエネルギー「需要」に応えるための巧みな戦略なのです。激しい運動では、ミトコンドリアによるエネルギー産生が追いつかなくなります。そこで体は、素早くエネルギーを供給できる解糖系を活性化させます。この過程で生じるピルビン酸が蓄積すると解糖系自体が停止してしまうため、乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)という酵素がピルビン酸を速やかに乳酸に変換し、解糖系の高速回転を維持します 3。こうして作られた乳酸は、行き場のない老廃物ではなく、他の組織で効率的に利用されるための、移動しやすいエネルギー通貨なのです。
この革命的な視点の変化を、以下の表にまとめます。
| 項目 | 旧来の考え(1980年代以前) | 新しい考え(乳酸シャトル時代) |
| 主な役割 | 疲労を引き起こす老廃物 | 優れた燃料・シグナル分子 |
| 生成原因 | 酸素不足(嫌気的解糖) | 高い解糖速度(好気的解糖も含む) |
| 疲労との関係 | 直接の原因 | 間接的に関連、時に保護的に働く |
| アシドーシスとの関係 | 酸を生成し、原因となる | 水素イオンを消費し、緩衝・除去を助ける |
| 代謝の行方 | 老廃物として除去されるべきもの | エネルギーとして酸化、糖に変換される |
第3章:科学はいかにして真実を暴いたか ― 最新実験手法の威力
古い乳酸仮説がなぜこれほど長く信じられてきたのか、そして、何がその常識を覆すきっかけとなったのでしょうか。その答えは、実験条件の進化と、代謝研究に革命をもたらした画期的な技術にあります。
カエルの脚実験の限界
初期の研究が誤った結論に至った最大の理由は、前述の通り、実験モデルの限界にありました。生きた人間の体温(約37℃)に近い生理的な温度環境下では、アシドーシスが筋肉の収縮力に与える悪影響は、低温下での実験で考えられていたよりもはるかに小さいことが、後の研究で明らかになりました 13。さらに、特定の条件下では、乳酸がカリウムイオンの蓄積といった他の疲労要因から筋肉を保護する効果さえあることが示唆されています 8。
代謝研究のブレークスルー:同位体トレーサー法
乳酸革命を可能にした最大の立役者は、「安定同位体トレーサー法」という実験技術です 21。これは、体内の代謝の動きを「見える化」する画期的な方法でした。
この技術の原理は、対象となる物質に「目印」をつけることにあります。科学者たちは、通常の炭素原子(質量数12)の代わりに、わずかに重い炭素の同位体(質量数13の炭素、$^{13}C$)を持つ乳酸を人工的に合成します。この「ラベル付き乳酸」は、化学的な性質は通常の乳酸と全く同じですが、質量分析計という特殊な装置で検出することができます 22。
このトレーサー(追跡子)を、運動中の被験者の体内に注入することで、研究者たちは代謝の探偵のように、乳酸が体内のどこで生まれ、どこへ運ばれ、最終的に何に変わるのかを、リアルタイムで正確に追跡できるようになったのです 21。
トレーサー研究が明らかにした決定的事実
同位体トレーサー法を用いた研究は、乳酸に関する数々の定説を覆す、決定的な証拠を次々と明らかにしました。
- 乳酸は常に作られ、使われている:乳酸は激しい運動時だけに作られる緊急の副産物ではなく、安静にしている時でさえ、常に体内で産生・消費され続けていることが証明されました 17。
- 乳酸の主な行先は「燃焼」:運動中に産生された乳酸の大部分(75~80%)は、肝臓で糖に戻される(コリ回路)のではなく、筋肉や心臓でエネルギー源として直接「酸化」(燃焼)されて消費されることが明らかになりました 15。
- トレーニングの真の効果:持久力トレーニングを積んだアスリートは、乳酸の産生を抑えるのではなく、産生された乳酸をより速く、より効率的に除去・利用する能力(乳酸クリアランス能力)が劇的に向上していることが発見されました 2。優れたアスリートとは、すなわち優れた「乳酸燃焼マシン」だったのです。
この技術革新は、科学的理解におけるパラダイムシフトそのものでした。それまでの研究は、運動前後の筋肉サンプルを比較し、乳酸の「正味の蓄積量」を測るという静的なものでした。これは、店の営業開始時と終了時のレジの現金だけを見て、一日の商売を理解しようとするようなものです。同位体トレーサー法は、一日のすべての取引(乳酸の産生と除去)をリアルタイムで観察することを可能にしました。その結果、乳酸は常に活発にやり取りされており、私たちが見ている蓄積量は、その巨大な流れの中のわずかなバランスの崩れに過ぎないという、代謝のダイナミックな真実が明らかになったのです。
第4章:単なる燃料を超えて ― シグナル分子としての乳酸
乳酸の物語は、単なるエネルギー源にとどまりません。近年の研究は、乳酸が細胞間のコミュニケーションを司り、運動による身体の適応を促す「シグナル分子」としての重要な役割を担っていることを突き止めています。ブルックス博士は、このホルモンのような働きをする乳酸を「ラクトーモン(Lactormone)」と名付けました 4。
持久力を鍛えるシグナル
私たちがトレーニングによって持久力を向上させることができるのは、乳酸が引き金となる適応プロセスのおかげかもしれません。
運動によって血中の乳酸濃度が上昇すると、それが体へのシグナルとなります。体はこのシグナルを受け取り、「もっと効率的に乳酸を処理できるように、システムをアップグレードせよ」という指令を出すのです。具体的には、乳酸を輸送するMCTトランスポーターを増やしたり、乳酸を燃焼させる工場であるミトコンドリアを新たに作ったりするための遺伝子が活性化されます 5。
このプロセスには、ミトコンドリア生合成の「マスタースイッチ」として知られるPGC-1αなどの代謝調節因子が関与していると考えられています 5。つまり、乳酸自身が、「もっとエネルギー工場(ミトコンドリア)が必要だ!」と体に知らせるメッセンジャーの役割を果たしているのです。
適応へのポジティブ・フィードバック
この仕組みは、強力なポジティブ・フィードバックループを生み出します。
- トレーニングによって乳酸が産生される。
- 乳酸がシグナルとなり、体が適応(ミトコンドリアの増加など)を始める。
- ミトコンドリアが増えることで、乳酸をエネルギーとして利用する能力が向上する。
- その結果、アスリートはより高い強度で運動しても乳酸が蓄積しにくくなり、パフォーマンスが向上する。
このように、かつて疲労の原因とされた乳酸こそが、実は私たちの体をより強く、より持久力のあるものへと作り変えるための、重要な鍵を握る分子だったのです。運動中に感じるあの「灼熱感」は、失敗のサインではなく、体が適応を始めるための「スイッチが入った音」と捉えることができるでしょう。それこそが、成長を促す生産的なシグナルなのです。
第5章:新たなフロンティア ― 脳機能と疾患における乳酸の役割
乳酸研究の最前線は、筋肉の領域を越え、脳の健康や疾患といった、さらに広大な分野へと展開しています。そこでは、乳酸が持つ二面性、すなわち健康を増進する側面と、病を進行させる側面の両方が明らかになりつつあります。
脳が好む秘密の燃料
運動が脳に良い影響を与えることは広く知られていますが、そのメカニズムの一つに乳酸が関わっている可能性が指摘されています。
脳内には「アストロサイト-ニューロン乳酸シャトル(ANLS)」と呼ばれる独自のシャトルシステムが存在するという仮説が提唱されています 27。これは、アストロサイトという脳内の支持細胞が、血液から取り込んだグルコースを乳酸に変換し、それを神経細胞(ニューロン)にエネルギー源として供給するという仕組みです。特に、神経活動が活発な時には、ニューロンはグルコースよりも乳酸を好んで利用すると考えられています 28。
近年の研究では、乳酸が学習や記憶の形成、神経の保護といった認知機能の向上に直接関与していることを示す証拠が次々と報告されています 27。運動によって全身の乳酸濃度が高まると、脳へ供給される乳酸も増加します。これが、運動がもたらす認知機能向上効果の重要な鍵を握っているのかもしれません。
諸刃の剣:がんと乳酸の関係
一方で、乳酸は疾患、特にがんの領域で、その「ダークサイド」を見せます。
1920年代にオットー・ワールブルク(後にノーベル賞受賞)が発見した「ワールブルク効果」は、がん細胞が酸素の有無にかかわらず、異常なほど大量のグルコースを取り込み、そのほとんどを乳酸として排出する現象を指します 2。
当初、これはがん細胞のミトコンドリアが損傷しているためだと考えられていましたが、現代の研究は、これががん細胞の巧妙な生存戦略であることを明らかにしています。がん細胞は、大量に産生した乳酸を使って、自身の増殖を促進するだけでなく、腫瘍の周囲を酸性化させることで免疫細胞の攻撃を抑制し、転移しやすい環境を作り出しているのです 33。この乳酸代謝のハイジャックは、現在、新たながん治療薬を開発するための重要なターゲットとして、世界中で精力的に研究されています。
これらの事実は、乳酸が持つ本質的な役割を浮き彫りにします。乳酸は、それ自体が「善」でも「悪」でもなく、体の基本的な代謝通貨です。健康なアスリートの体という、高度に制御されたシステムの中では、エネルギーを効率的に分配し、ポジティブな適応を促す有益な分子として機能します。しかし、がん細胞のような制御を失ったシステムの中では、その同じ代謝経路が乗っ取られ、自己の増殖という利己的な目的のために悪用されてしまうのです。
第6章:科学を実践に活かす ― 乳酸閾値トレーニング
これまで見てきた乳酸の科学は、アスリートやフィットネス愛好家にとって、極めて実践的な示唆に富んでいます。トレーニングの質を高め、持久力を飛躍的に向上させる鍵は、「乳酸閾値(Lactate Threshold, LT)」をいかに高めるかにかかっています。
パフォーマンスを決定づける指標:乳酸閾値(LT)
乳酸閾値(LT)とは、運動強度を徐々に上げていった際に、血中の乳酸濃度が急激に上昇し始めるポイントを指します。これは、体内で乳酸が産生される速度が、それを除去・利用する速度を上回り始める分岐点です 19。
従来、持久力の指標としては最大酸素摂取量($VO_2max$)が重視されてきました。$VO_2max$がエンジンの「排気量」だとすれば、LTは、そのエンジンの何パーセントの力を長時間維持できるかという「実用燃費」に例えられます。たとえ$VO_2max$が非常に高くても、LTが低い位置にあれば、その潜在能力をレースで十分に発揮することはできません。そのため、多くの専門家は、LTこそが持久的パフォーマンスを最も正確に予測する指標であると考えています 39。
LTトレーニングの目的と生理学的適応
LTトレーニングの目的は、乳酸の産生を止めることではありません。むしろ、体を乳酸の産生に慣れさせ、産生された乳酸をより効率的に除去し、エネルギー源として再利用できる体質へと作り変えることです。これにより、LTが起こる運動強度、すなわち、高いペースを維持できるレベルが向上します 19。
効果的なLTトレーニングによって、体内では以下のような生理学的適応が起こります。
- 乳酸除去能力の向上:筋肉細胞内外への乳酸の輸送を担うMCTトランスポーターの数が増加します 19。
- 乳酸酸化能力の向上:筋肉内のミトコンドリアの数とサイズが増大し、乳酸を燃焼させる能力が高まります 19。
- 輸送効率の改善:筋肉周辺の毛細血管が発達し、酸素の供給と乳酸の輸送がよりスムーズになります 19。
実践的なトレーニング方法
LTを高めるためには、特定の強度ゾーンを狙ったトレーニングが効果的です。以下に代表的なトレーニング方法を紹介します。
- テンポ走(最大定常状態トレーニング):LTとほぼ同じか、わずかに低い強度(主観的運動強度で「ややきつい」と感じるレベル)で、20~40分程度の持続走を行います。これは、レースペースに近い強度で乳酸除去能力を高めるための、最も基本的なトレーニングです 38。
- クルーズインターバル:LTペースで5~15分間の疾走と、短い休息を繰り返すトレーニングです。1回の持続走よりも、合計でより長い時間をLT強度でトレーニングすることができます。
- 高強度インターバルトレーニング(HIIT):LTを大幅に超える高い強度で短い疾走と休息を繰り返します。これは、乳酸産生能力の最大値を高めると同時に、体の緩衝能力や回復能力を鍛え、総合的なパフォーマンス向上に繋がります。
これらのトレーニングを効果的に組み合わせるために、以下のトレーニングゾーンの考え方が役立ちます。
| ゾーン | 主観的運動強度(RPE) | LTとの関係 | 主な生理学的目的 |
| ゾーン1(イージー) | 11-12(楽である) | LTよりかなり低い | 有酸素的基礎能力の構築、積極的休養 |
| ゾーン2(テンポ/閾値) | 13-15(ややきつい) | LT周辺 | 乳酸除去・利用能力の向上、LTの引き上げ |
| ゾーン3(インターバル) | 16以上(きつい~非常にきつい) | LTよりかなり高い | $VO_2max$の向上、最大スピード・パワーの強化 |
この表は、複雑な生理学の概念を、日々のトレーニングに落とし込むための実践的なフレームワークです。自身の目標に応じて各ゾーンでのトレーニングを計画的に行うことで、乳酸代謝を最適化し、持久力を効果的に高めることが可能になります。
結論:乳酸のヒーローズ・ジャーニー
乳酸の科学的評価が辿ってきた道は、まさに一つの壮大な物語です。かつては筋疲労を引き起こす単純な「悪役」と見なされていた分子が、数十年を経て、私たちの体を支える多才な「ヒーロー」へとその姿を変えました。
乳酸は、単なる老廃物ではなく、激しい運動時に即座に利用できるプレミアム燃料であり、筋肉、心臓、そして脳の活動を支える重要なエネルギー源です。それだけでなく、トレーニングによるポジティブな適応を引き起こすマスターシグナル分子として、私たちの体をより強く、より効率的に作り変えるための指令を出しています。
この新たな理解は、私たちの運動との向き合い方を根本から変える力を持っています。トレーニング中に感じる筋肉の「灼熱感」は、もはや敗北や限界のサインではありません。それは、体が懸命に働き、成長しようとしている証であり、適応への扉を開く生産的なシグナルなのです。乳酸の真実を知ることで、私たちはより賢くトレーニングを行い、パフォーマンスを向上させ、人体が持つ精緻でダイナミックなシステムの複雑さと美しさへの理解を、一層深めることができるでしょう。
引用文献
- Science Fact or Science Fiction? Lactic Acid Buildup Causes Muscle Fatigue and Soreness, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.pfizer.com/news/articles/science_fact_or_science_fiction_lactic_acid_buildup_causes_muscle_fatigue_and_soreness
- Nerd Lab: How Dr. George Brooks Revolutionized our Understanding of Lactate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.fasttalklabs.com/fast-talk/nerd-lab-how-dr-george-brooks-revolutionized-our-understanding-of-lactate/
- Lactate metabolism: a new paradigm for the third millennium – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1664920/
- Lactate as a Signaling Molecule That Regulates Exercise-Induced Adaptations – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27740597/
- Lactate as a Signaling Molecule That Regulates Exercise-Induced …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5192418/
- www.jstage.jst.go.jp, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpehss/51/3/51_3_229/_article#:~:text=Repeated%20intense%20skeletal%20muscle%20contraction,fatigued%20muscles%20accumulate%20lactic%20acid.
- The role of lactic acid in muscle contraction – J-Stage, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpehss/51/3/51_3_229/_article
- Lactate doesn’t necessarily cause fatigue: why are we surprised? – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2278833/
- Scientific contributions of A. V. Hill: exercise physiology pioneer, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journals.physiology.org/doi/10.1152/japplphysiol.01246.2001
- The legacy of A. V. Hill’s Nobel Prize winning work on muscle energetics – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9304278/
- Archibald Hill | Department of Physiology, Development and Neuroscience, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.pdn.cam.ac.uk/about-us/history/centenary/archibald-hill
- The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1922 – NobelPrize.org, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1922/summary/
- Lactic acid and exercise performance : culprit or friend? – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16573355/
- Muscle Fatigue: Lactic Acid or Inorganic Phosphate the Major Cause? | Physiology, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journals.physiology.org/doi/10.1152/physiologyonline.2002.17.1.17
- Lactate shuttle hypothesis – Wikipedia, 11月 3, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Lactate_shuttle_hypothesis
- Cell–cell and intracellular lactate shuttles – PMC, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2805372/
- The-lactate-shuttle-during-exercise-and-recovery.pdf – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/profile/George-Brooks-10/publication/19639028_The_lactate_shuttle_during_exercise_and_recovery/links/59d976590f7e9b12b3687078/The-lactate-shuttle-during-exercise-and-recovery.pdf
- Role of mitochondrial lactate dehydrogenase and lactate oxidation in the intracellular lactate shuttle | PNAS, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.96.3.1129
- Lactate Threshold Training Program | ProSource™ | ACE, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.acefitness.org/continuing-education/prosource/february-2015/5243/how-to-design-a-lactate-threshold-training-program/
- Lactate Threshold – University of Minnesota, Morris Digital Well, 11月 3, 2025にアクセス、 https://digitalcommons.morris.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2308&context=jmas
- Tracing the lactate shuttle to the mitochondrial reticulum – PMC, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9534995/
- Stable Isotope Tracers for Metabolic Pathway Analysis | Springer Nature Experiments, 11月 3, 2025にアクセス、 https://experiments.springernature.com/articles/10.1007/978-1-4939-9236-2_17
- Metabolomics and isotope tracing – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6034115/
- Approaches to stable isotope tracing and in vivo metabolomics in the cancer clinic, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.embopress.org/doi/10.1038/s44318-025-00450-z
- Lactate metabolism: historical context, prior misinterpretations, and current understanding – CORE, 11月 3, 2025にアクセス、 https://core.ac.uk/download/pdf/345086219.pdf
- Lactate production cannot be measured with tracer techniques | American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journals.physiology.org/doi/10.1152/ajpendo.1987.252.3.E439
- Lactate Metabolism, Signaling, and Function in Brain Development, Synaptic Plasticity, Angiogenesis, and Neurodegenerative Diseases – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37686202/
- Lactate Is Answerable for Brain Function and Treating Brain …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9099001/
- Glucose and lactate metabolism during brain activation – PubMed – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11746408/
- Lactate-induced metabolic signaling is the potential mechanism for reshaping the brain function – role of physical exercise – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40551894/
- Lactate and Lactylation in the Brain: Current Progress and Perspectives – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36928470/
- Physiological significance of elevated levels of lactate by exercise training in the brain and body – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36681523/
- Lactate and Cancer: Revisiting the Warburg Effect in an Era of Lactate Shuttling – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4428352/
- The Warburg Effect: How Does it Benefit Cancer Cells? – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4783224/
- Reexamining cancer metabolism: lactate production for carcinogenesis could be the purpose and explanation of the Warburg Effect – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5862360/
- Glucose Metabolism in Cancer: The Warburg Effect and Beyond – NCBI – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK573693/
- Targeting the Warburg Effect in Cancer: Where Do We Stand? – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38542116/
- Mastering Lactate Threshold Training | Polar Global, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.polar.com/en/journal/lactate-threshold
- Using Lactate Threshold Data – NSCA, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.nsca.com/education/articles/kinetic-select/using-lactate-threshold-data/
- Lactate threshold training, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.unm.edu/~lkravitz/Article%20folder/lactatethreshold.html