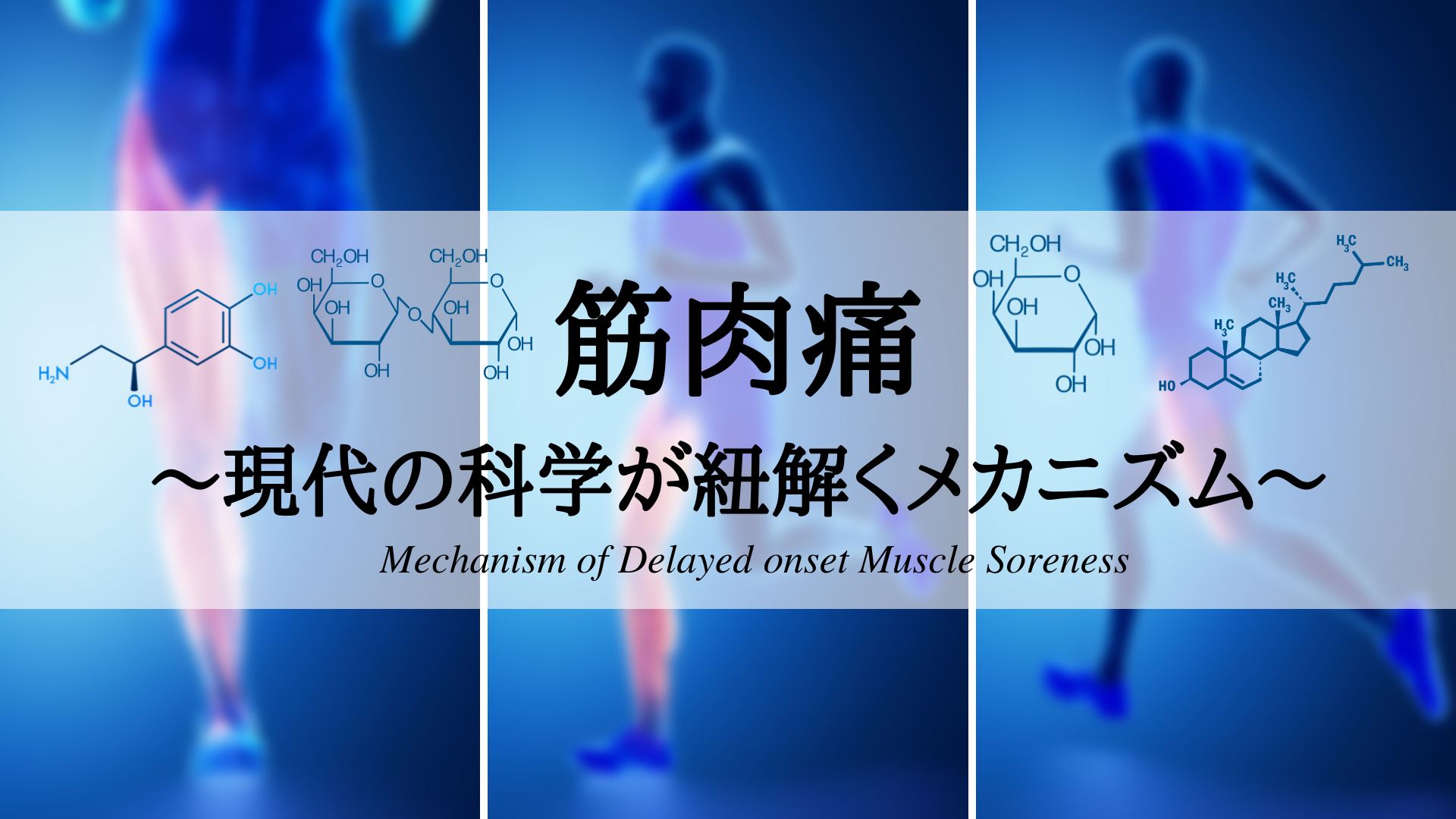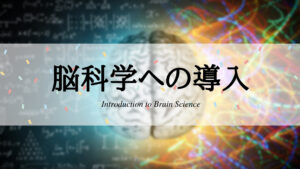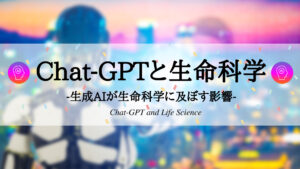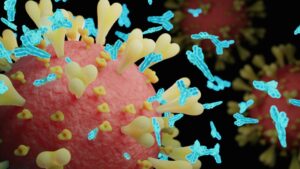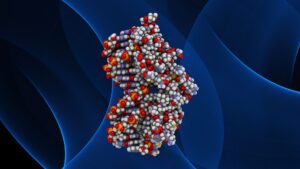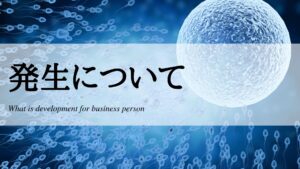I. 序論:筋肉痛(DOMS)の再定義と科学的誤解の打破
1.1. DOMSとは何か:急性筋痛との決定的な違い
遅発性筋肉痛(DOMS: Delayed Onset Muscle Soreness)とは、通常、不慣れな運動や激しい運動、特に遠心性(エキセントリック)収縮や等尺性(アイソメトリック)収縮を伴う運動後に生じる、複雑な傷害実体である 1。この痛みは、運動中に生じる急性筋痛とは根本的に異なる現象として区別される 4。
DOMSの症状は、鈍い、うずくような痛みとして認識され、患部の圧痛(機械的痛覚過敏)、可動域の減少、および一時的な筋力損失を伴う 3。この痛みは、運動後12~24時間で発現し始め、24時間から72時間でピークに達するという遅延性の経過を辿るのが特徴である 3。その後、症状は次第に軽減し、通常7日以内に消失する 3。臨床的には、DOMSは「遅発性筋痛」としてType 1b筋損傷に分類され、その病態生理は超微細構造上の損傷パターンに基づいている 2。
1.2. 過去の常識と現代科学:乳酸説の終焉
かつて、運動後の筋肉痛は、運動中に筋肉内に蓄積した乳酸が原因であるとする「乳酸説」が広く信じられていた 6。しかし、現代の運動生理学において、この説は完全に否定されている 4。乳酸(正しくは乳酸塩)は高強度運動中に生成される代謝物であるが、血流に乗って速やかに代謝されるため、痛みがピークに達する運動後24〜72時間後には体内に残存していない 4。
DOMSの真の原因は、乳酸蓄積ではなく、運動誘発性筋損傷(EIMD: Exercise-Induced Muscle Damage)と呼ばれる、微細な損傷とそれに続く炎症反応、そして神経伝達系の複合的な応答によって引き起こされることが、国内外の研究によって確立されている 2。この知識は、アスリートが効果的な回復戦略を選択するための基礎となる。
1.3. 遠心性収縮(エキセントリック運動)がなぜ鍵となるのか
筋肉の収縮様式の中で、DOMSを最も強く誘発するのは遠心性収縮である 3。遠心性収縮とは、筋肉が張力(負荷)に耐えながら伸長する動作(例:ダンベルを下ろす動作、坂道を下る際の太ももの筋肉の動き)を指す 4。対照的に、筋肉が短縮する求心性収縮や、静止状態を保つ等尺性収縮は、DOMSの誘発性が著しく低い 3。
遠心性収縮は、求心性収縮よりも少ないエネルギー消費でより大きな張力を発揮できる効率的な運動形式である一方で、筋線維に高い機械的ストレスをかける 7。特に、高強度または大量の遠心性収縮を初めて行う場合、深刻なDOMSと筋機能の長期的な低下を引き起こすことが知られている 8。したがって、トレーニングの負荷設定を検討する際、総負荷量だけでなく、遠心性フェーズの強度と頻度を管理することが、DOMS予防の核心となる。


II. 筋肉痛の深層メカニズム:細胞レベルの損傷と修復
2.1. EIMD(運動誘発性筋損傷)の発生機序:微細損傷の連鎖
DOMSの一次的なメカニズムは、不慣れな激しい運動による筋細胞の超微細構造上の損傷、すなわちEIMDにあると現在考えられている 5。この損傷は、筋原線維を構成する最小単位であるサルコメアの構造的弱点、特にZ帯(Z-disk)周辺で発生する 9。遠心性収縮時の高い張力下での伸長は、Z帯のストリーミングや破綻といった構造的な変化を引き起こす 9。
これらの微細損傷の結果、筋細胞の膜(サルコレマ)の透過性が変化し、細胞内の内容物、特にクレアチンキナーゼ(CK)やミオグロビン(Mb)などのタンパク質が血流中に流出する 5。血中CKレベルの上昇はEIMDの程度を評価するための重要な間接的マーカーの一つとして用いられる 10。
2.2. 炎症反応の役割:敵か味方か
DOMSの発生には、EIMDに続いて生じる炎症反応が不可欠な要素として関与している 5。炎症は historically、回復を妨げる有害なプロセスとして見なされてきたが、現代の科学では、適切に制御された炎症応答は、損傷した筋組織の修復と再生に不可欠な要素であると広く認識されている 9。
損傷した筋細胞から放出されるプロ炎症性の化学メディエーターが、局所の疼痛受容体を刺激し、DOMSの臨床症状を発現させる 12。DOMSの症状が運動後遅れて(ピークが48〜72時間後)現れるのは、この複雑な炎症カスケードと、それに続くタンパク質分解やアポトーシス(細胞死)の連鎖の結果である 5。ただし、筋損傷の程度と、筋内の炎症性サイトカイン(例:IL-6, IL-1$\beta$) の発現レベルの大きさとの間に、明確な関係を確立するには、現時点では十分な証拠がない 9。これは、サイトカインが単に損傷の指標としてだけでなく、細胞修復のシグナル分子として多面的に機能していることを示唆している。
2.3. 筋再生の主役:衛星細胞の初期応答
微細な筋損傷は、筋線維の再生プロセスを開始するための強力なシグナルとなる 13。この再生は、通常休止状態にある筋幹細胞、すなわち衛星細胞(Satellite cells)に強く依存している 13。
十分な刺激(運動や損傷)を受けると、衛星細胞は休止状態から脱して活性化し、増殖を開始する。その後、損傷部位に移動して筋線維の修復や新しい線維の形成に貢献する 14。興味深いことに、DOMSに伴う痛みの不快感が発現するタイミング(12~48時間後)は、損傷後の炎症プロセスと一致しており、これはまさしく筋線維再生の初期段階に相当する 13。したがって、DOMSは、単なる損傷の痛みではなく、生体が次回の負荷に耐えるためにより強く組織をリモデリング(作り替え)るための生体修復開始シグナルとしての側面も持っていると解釈することができる。
III. 筋肉痛の発生源再考:筋組織を越えた最先端研究
従来のDOMS研究は筋線維そのものに焦点を当ててきたが、近年の最先端研究は、疼痛の発生源が筋線維を取り巻く結合組織や、中枢神経系に深く関わっている可能性を示唆している。
3.1. 筋膜(Fascia)への焦点:痛みはどこから来るのか
DOMSの痛みのメカニズムに関する強力な新しい仮説の一つは、疼痛の主な発生源が筋線維内部ではなく、**深部筋膜(Deep Fascia)**を含む筋外側の結合組織にあるというものである 15。
筋膜は、不規則に配列されたI型およびIII型コラーゲン線維からなる全身に広がる結合組織であり、姿勢、運動、そして恒常性の維持に重要な役割を果たす 16。筋膜は、固有受容だけでなく、侵害受容(痛みの感覚)のための多様な感覚受容器を豊富に含んでいる 16。組織学的および実験的研究の結果、筋膜には痛みを誘発する侵害受容器が豊富に供給されており、筋線維自体の刺激よりも強い疼痛応答を誘発することが示唆されている 15。この知見は、スポーツおよびフィットネスの専門家に対し、DOMSの予防や治療を考える上で、筋線維だけでなく、筋膜を標的とした介入(例:筋膜リリース、フォームローリング 15)の重要性を強調する。
3.2. 末梢神経系と中枢神経系(CNS)の関与:筋—脳軸
DOMSに伴う痛みは、単なる局所的な信号ではなく、中枢神経系(CNS)の広範な応答を誘発する。DOMS関連の疼痛は、随意運動によって誘発されると、対側一次運動野および感覚皮質に広範囲な活性化を引き起こすことが示されている 18。
さらに、運動時のDOMS疼痛によって、小脳の活性化がより広範囲に観察された 18。小脳は随意運動のプログラミングを担っているため、これは、痛覚求心性入力によって四肢の随意運動が妨げられる際に、中枢神経系が防御的な恒常性を維持し、運動パターンを調整しようとする複雑な防御応答であることを示唆している。つまり、アスリートが感じる疲労感やパフォーマンスの低下は、単なる物理的損傷だけでなく、中枢神経系が発する「警告信号」としての側面も大きい。
3.3. 神経シグナルの過渡的スイッチ理論
最も革新的な研究として、DOMSの結果、末梢筋と脳を結ぶ軸に沿った神経シグナル伝達が一時的に切り替わるという仮説が提案されている 1。このメカニズムは、プロトン共役型の超高速シグナリングから、迅速なグルタミン酸ベースのシグナリングへの過渡的な切り替えとして説明される 1。
この神経スイッチが興味深いのは、この中枢リンクが、神経新生の中心である海馬への接続を含んでいる点である 1。研究では、このスイッチが将来的に神経変性や加速老化につながる一つの重要なメカニズムとなる可能性があり、今後の長期的健康アウトカムに関する研究領域として大きな注目を集めている 1。
DOMSのメカニズムに関する知見を整理するため、古典的な見解と現代科学のパラダイムシフトを以下に示す。
Table 1: DOMSメカニズム:古典的理論と最新のパラダイムシフト
| 理論の分類 | 主要な仮説 | 科学的現状と最新の知見 |
| 古典的誤解 | 乳酸蓄積説 | 完全に否定。急性筋痛の原因であり、遅発性の痛みとは関連しない 4。 |
| 構造的損傷説 (EIMD) | 超微細構造の損傷(Z帯破綻) | 主要なトリガー。再生プロセスの起動シグナルとして機能 [5, 9]。 |
| 筋膜起源説 (最新) | 筋外側結合組織の損傷と侵害受容器の刺激 | 疼痛の主な発生源は筋膜にあり、筋線維自体ではない可能性 15。 |
| 神経・信号説 (最先端) | 末梢筋—脳軸のシグナルスイッチ | プロトン共役からグルタミン酸ベースのシグナルへの過渡的切り替えがDOMSに寄与 1。 |
IV. 筋肉構造に依存する損傷メカニズムの差異
筋肉痛の感受性は、運動の種類や強度だけでなく、個々の筋肉が持つ固有の構造的特性、すなわち筋建築学(Muscle Architecture)によって大きく左右されることが示されている 10。筋建築学には、筋線維の長さや羽状角(Pennation Angle)が含まれ、これらは筋肉が発揮できる張力と、損傷に対する耐性に影響を与える。
4.1. 筋建築学の定義と筋群の分類
筋肉は線維の配列により、大きく二つに分類される。一つは、筋線維が腱にほぼ平行に縦方向に長く配置される**紡錘状筋(Fusiform/Longitudinal Muscles)であり、例えば上腕二頭筋や肘屈筋群に見られる。もう一つは、筋線維が腱に対して斜めに配置される羽状筋(Pennate Muscles)**であり、大腿四頭筋などの大きな筋群に見られる 10。羽状筋は生理学的断面積(PCSA)が大きく、より強い筋力を発揮できる傾向がある 19。
4.2. 紡錘状筋における損傷リスクの増大
近年の研究では、筋構造の違いが遠心性運動後のEIMD応答に決定的な影響を与えることが明らかになっている 10。この構造的な脆弱性は、「単位筋量あたりの遠心性収縮時の負荷(workload per unit muscle volume)」の違いによって説明される 10。
羽状角が低い、すなわち縦方向の線維配列を持つ紡錘状筋(例:肘屈筋)は、羽状角が高い多羽状筋(例:膝伸筋)と比較して、遠心性収縮時に単位筋量あたりに加わる負荷が有意に高くなる 10。この相対的に高い機械的ストレスが、紡錘状筋において筋損傷の発生率を増加させる主要な要因であると推測されている 10。羽状筋(膝伸筋など)は大きなPCSAを持つため、個々の筋単位にかかる機械的ひずみが、紡錘状筋よりも低くなる。
4.3. 実際の運動における影響:データによる裏付け
実際の比較研究では、肘屈筋(EF: 紡錘状筋)と膝伸筋(KE: 多羽状筋)を対象とした結果が、この構造的な差異の重要性を裏付けている 10。遠心性運動後、肘屈筋群は、膝伸筋群と比較して、運動後の疼痛レベル、可動域(ROM)の欠損、およびCK・Mbといった損傷マーカーの有意な上昇を示した 10。
肘屈筋(羽状角約$0.9^\circ$)や膝屈筋(羽状角約$1.3^\circ$)といった紡錘状筋は、膝伸筋(羽状角約$11.6^\circ$)に比べて顕著に高い損傷応答を示した 10。この結果は、アスリートやコーチがトレーニングプログラムを設計する際、特定の筋群(特に縦方向の線維を持つ筋群)に対して、遠心性トレーニングの導入をより慎重に行う必要性があることを示唆している。
V. エビデンスに基づく予防と回復戦略
DOMSの管理は、初期損傷を軽減する予防策と、発生した炎症と再生プロセスを効果的にサポートする回復戦略の二段階で構成される。
5.1. 予防の鍵:遠心性運動への段階的適応(Repeated-bout Effect)
DOMSの予防において、最も効果的かつ科学的に裏付けられた方法は、「反復発作効果(Repeated-bout Effect)」を利用することである 3。これは、一度遠心性収縮を含む運動を行うと、筋肉が急速に順応し、同じ運動を繰り返しても筋損傷や痛みが大幅に軽減される現象を指す 3。
この適応は、主に筋組織のリモデリング(特にZ帯の構造強化)と神経筋機能の改善によって達成される 9。アスリートは、高強度な遠心性トレーニングを導入する前に、低強度で目的の筋肉を慣れさせる段階的な負荷設定を行うべきであり、特に紡錘状筋のような構造的に脆弱な筋群に対する注意が必要である。
5.2. 物理療法の最新エビデンス:効果と適用時期
最新のメタアナリシスは、物理療法(PTMs)がDOMSの管理において効果を発揮するが、その有効性が時間依存的であり、特に運動後48時間以内が治療の最も重要な窓口であることを示している 21。
5.2.1. マッサージ:疼痛軽減と疲労回復の最優先事項
マッサージは、DOMSの軽減および知覚疲労の回復において、最も効果的な方法であると複数のレビューで示されている 22。マッサージ介入は血清CKレベルの低下に寄与し、これにより炎症と筋損傷が軽減され、筋パフォーマンスの回復が促進されることが示唆されている 11。マッサージの有効性は、運動後48時間時点で最も高く達成されるため、急性期の症状管理に非常に有用である 11。
5.2.2. 回復を加速させる光線療法と温熱療法の「48時間ルール」
ベイジアン・メタアナリシスなどの高エビデンス研究は、特定の介入が急性期に優位性を持つことを明確に示した。
- 光線療法(PBMT: Photobiomodulation Therapy): レーザーやLEDを用いた光線療法は、運動後24時間および48時間時点での疼痛軽減において、プラセボと比較して有意な優位性を示した 21。PBMTは、細胞内のミトコンドリア活性に影響を与え、炎症を軽減し、治癒を促進することで、細胞レベルでの修復をサポートする 23。
- サウナ/温熱療法: サウナもまた、運動後48時間時点の疼痛軽減において有意な効果を示した 21。
この分析から導かれる重要な結論は、PBMTとサウナの治療効果は初期の48時間以内が最も顕著であり、この期間を超えるとプラセボに対する統計的に有意な利益が見られなくなる点である 21。したがって、アスリートはこれらの技術をDOMS発現の急性期に集中的に適用することが推奨される。
5.2.3. その他の補助的な物理療法
- 寒冷療法(Cryotherapy): 運動直後のアイシングなどの寒冷暴露は、炎症を引き起こす化学メディエーターの濃度上昇を抑制することで、DOMSの影響を最小限に抑えることができる 12。炎症の解決を促し、血流の改善と関連付けられる可能性もある 24。
- アクティブリカバリー: 低強度の運動を取り入れたアクティブリカバリーは、血流を促進し、代謝物除去を助けることで、回復プロセスを促進する 23。
- フォームローリング/パーカッシブマッサージ: これらの介入は、筋緊張、硬さ、および弾力性の回復を加速させる効果が示されている 17。特に筋膜の硬さや機械的挙動を改善する上で重要であるが、疼痛軽減という点ではパッシブな安静に対する明確な追加の利益は示されていない可能性もある 17。
5.3. 栄養補助食品の真実:有効性が示されたものと低いもの
栄養介入の主な目標は、抗炎症作用や抗酸化能力を通じてEIMDの程度とDOMSを軽減することである 25。
5.3.1. BCAA(分岐鎖アミノ酸):訓練者における炎症解決の加速
BCAA補給に関するメタアナリシスでは、レジスタンス運動を行った訓練された男性に限定した場合、BCAAがCK(クレアチンキナーゼ)の血中流出を減少させ、筋痛を軽減する潜在的な効果を持つことが示された 26。BCAAは筋損傷を直接的に予防するわけではないが、細胞再生を活性化することで炎症の解消を加速させると考えられている 26。効果を最大化するためには、EIMDプロトコル後だけに投与するのではなく、運動前から継続的に摂取することが推奨される 27。
5.3.2. タルトチェリー(Tart Cherry):筋力回復に寄与
タルトチェリーのサプリメント摂取は、筋痛の軽減にわずかながら有益な効果を示し、特に筋力回復に対しては中程度の有益な効果が観察されている 28。タルトチェリーは、抗炎症作用、抗酸化能力、および血流増強効果を通じて、全身的な回復をサポートする 29。
5.3.3. オメガ3脂肪酸:炎症への影響とDOMS軽減の限界
オメガ3脂肪酸は、脂質過酸化のマーカーを減少させるなど、炎症反応には関連しているものの 25、サプリメント摂取が遠心性運動後の筋肉痛を臨床的に重要なレベルで軽減するというエビデンスは、現在のところ低品質である 30。DOMS症状の直接的な軽減よりも、全身的な抗酸化および抗炎症状態の維持に役立つものとして位置づけるのが適切である。確固たる推奨のためには、大規模なランダム化比較試験(RCT)によるさらなる検証が求められている 25。
5.3.4. クレアチン:長期的な筋損傷耐性への貢献
クレアチンは抗炎症作用を持つ可能性が示唆されているが 31、短期(7日間)の補給では、DOMSやCKレベルなどのEIMD指標に対して明確な急性効果は見られない 32。しかし、長期(30日間)の補給を継続した場合、最大等尺性筋力(MVC)が向上し、このエルゴジェニック効果が運動誘発性筋損傷に対する耐性を高め、結果的にポジティブな影響を与える可能性がある 32。
DOMS回復戦略の選択を支援するため、主要な介入策の比較を以下に示す。
Table 2: エビデンスに基づくDOMS回復介入策の比較
| 介入方法 | 主な効果 | 有効なタイミング | エビデンスレベルと注釈 |
| マッサージ | 疼痛軽減、CKレベル低下、疲労軽減 | 運動後48時間以内が最も効果的 11 | 高(メタアナリシス)。トップチョイス 22。 |
| 光線療法 (PBMT) | 疼痛軽減、炎症抑制 | 運動後48時間以内 21 | 中~高(ベイジアン分析)。急性期介入に優れる。 |
| サウナ/温熱療法 | 疼痛軽減 | 運動後48時間以内 21 | 中(ベイジアン分析)。 |
| 寒冷療法 | 炎症軽減、DOMS最小化 | 運動直後の適用が重要 12 | 中~低。急性炎症の発生を抑制 12。 |
| BCAA補給 | CKレベル低下、炎症解決の加速 | 運動前からの継続的投与が推奨 27 | 中(訓練された被験者に対して) 26。 |
| タルトチェリー | 筋力回復促進、疼痛軽減(小) | 継続的な補給 28 | 中(系統的レビュー)。抗酸化作用 29。 |
VI. 結論と実践的な推奨事項
6.1. アスリート・愛好家のためのDOMS管理ロードマップ
DOMSは、単なる損傷ではなく、筋線維の微細損傷(EIMD)から始まり、筋付随結合組織(筋膜)の侵害受容器の刺激、そして中枢神経系が関与する複雑な生体防御および再生プロセスである。DOMSの成功的な管理は、このメカニズムの全体像を理解し、時間的な窓を考慮に入れた戦略的なアプローチが必要である。
- 予防戦略(段階的適応):
遠心性トレーニングを新規に導入する際、特に上腕二頭筋や膝屈筋群など、羽状角が低く、単位筋量あたりの負荷が高い紡錘状筋に対しては、低強度から開始し、「反復発作効果」を意図的に利用して段階的に負荷を増やしていくことが、最も効果的な予防策である。 - 急性期介入戦略(0-48時間の集中管理):
DOMSがピークを迎える前の運動後48時間以内が、症状を軽減し、回復を加速させるための最も重要な「治療の窓」である。この期間に、マッサージやPBMT、サウナなどのエビデンスレベルの高い物理療法を集中して実行することが推奨される 11。 - 栄養サポート戦略:
訓練レベルに応じて、炎症の解決を加速させる可能性のあるBCAAを運動前から継続的に摂取し、タルトチェリーで筋力回復をサポートする。炎症を完全に抑制する(例:高容量の非ステロイド性抗炎症薬)ことは、長期的な筋修復を妨げる可能性があるため、マッサージやPBMTによる「炎症の解決促進」を通じて、再生と症状緩和のバランスを取ることが望ましい。
6.2. 今後の研究の方向性
筋肉痛の研究は、従来の損傷モデルから、神経科学と構造生物学の統合へと進化している。今後の研究の焦点は以下の領域に向かう。
- 神経変性とDOMSの関連性: 末梢筋—脳軸におけるシグナル伝達の過渡的なスイッチが、海馬への連結を通じて神経変性や加速老化につながる可能性は、DOMSが長期的な健康に与える影響を理解する上で非常に興味深い領域である 1。
- 筋膜を標的とした治療法の最適化: DOMSの疼痛発生源が筋膜にあるという仮説に基づき 15、筋膜の機械的特性と侵害受容体の詳細な解明が進むことで、筋膜をターゲットとした非侵襲的な治療介入(特定の筋膜リリース技術や、筋膜組織の構成成分をターゲットとした栄養補給)の最適なプロトコルが確立されることが期待される 16。
引用文献
- Delayed-Onset Muscle Soreness Begins with a Transient Neural Switch – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/1422-0067/26/5/2319
- UPDATE Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) – Muscle Biomechanics, Pathophysiology and Therapeutic Approaches – German Journal of Sports Medicine, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.germanjournalsportsmedicine.com/archive/archive-2024/issue-5/update-delayed-onset-muscle-soreness-doms-muscle-biomechanics-pathophysiology-and-therapeutic-approaches/
- Delayed onset muscle soreness – Wikipedia, 11月 3, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Delayed_onset_muscle_soreness
- What to Know About Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) – Healthline, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.healthline.com/health/doms
- Advances in Delayed-Onset Muscle Soreness (DOMS): Part I: Pathogenesis and Diagnostics – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30537791/
- Delayed onset muscle soreness : treatment strategies and performance factors – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12617692/
- What Type of Exercise Causes DOMS? Causes, Signs & Prevention – MedicineNet, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.medicinenet.com/what_type_of_exercise_causes_doms/article.htm
- Eccentric Contractions Are Responsible for Muscle Damage and Neuromuscular Fatigue, 11月 3, 2025にアクセス、 https://acsm.org/eccentric-contractions-muscle-damage/
- Muscle damage and inflammation during recovery from exercise …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journals.physiology.org/doi/10.1152/japplphysiol.00971.2016
- Effects of Muscle Architecture on Eccentric Exercise Induced Muscle …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8488843/
- Massage Alleviates Delayed Onset Muscle Soreness after Strenuous Exercise: A Systematic Review and Meta-Analysis – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2017.00747/full
- Effects of cryotherapy on muscle damage markers and perception of delayed onset muscle soreness after downhill running: A Pilot study | Revista Andaluza de Medicina del Deporte – Elsevier, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.elsevier.es/en-revista-revista-andaluza-medicina-del-deporte-284-articulo-effects-cryotherapy-on-muscle-damage-S1888754615000453
- The Role of Satellite Cells in Skeletal Muscle Regeneration—The Effect of Exercise and Age, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8533525/
- Satellite cell activity is differentially affected by contraction mode in human muscle following a work-matched bout of exercise – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2014.00485/full
- Is “Delayed Onset Muscle Soreness” a False Friend? The Potential Implication of the Fascial Connective Tissue in Post-Exercise Discomfort – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8431437/
- Response to Mechanical Properties and Physiological Challenges of Fascia: Diagnosis and Rehabilitative Therapeutic Intervention for Myofascial System Disorders – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2306-5354/10/4/474
- Foam Rolling or Percussive Massage for Muscle Recovery: Insights into Delayed-Onset Muscle Soreness (DOMS) – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2411-5142/10/3/249
- Central Projection of Pain Arising from Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) in Human Subjects – Research journals, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0047230
- Effect of strength training on muscle architecture (review) – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/317692309_Effect_of_strength_training_on_muscle_architecture_review
- Eccentric Muscle Contractions: Risks and Benefits – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6510035/
- Differences in the Effectiveness of Different Physical Therapy Modalities in the Treatment of Delayed-Onset Muscle Soreness: A Systematic Review and Bayesian Network Meta-Analysis – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12178262/
- An Evidence-Based Approach for Choosing Post-exercise Recovery Techniques to Reduce Markers of Muscle Damage, Soreness, Fatigue, and Inflammation: A Systematic Review With Meta-Analysis – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29755363/
- Physical Therapies for Delayed Onset Muscle Soreness: A Protocol for an Umbrella and Mapping Systematic Review with Meta-Meta-Analysis – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2077-0383/13/7/2006
- Whole-Body Cryotherapy in Athletes: From Therapy to Stimulation. An Updated Review of the Literature – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5411446/
- A review of nutritional intervention on delayed onset muscle soreness. Part I – PMC, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4294436/
- Does Branched-Chain Amino Acids (BCAAs) Supplementation Attenuate Muscle Damage Markers and Soreness after Resistance Exercise in Trained Males? A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/1880
- The use of BCAA to decrease delayed-onset muscle soreness after a single bout of exercise: a systematic review and meta-analysis – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34669012/
- Tart Cherry Supplementation and Recovery From Strenuous Exercise: A Systematic Review and Meta-Analysis – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/348452059_Tart_Cherry_Supplementation_and_Recovery_From_Strenuous_Exercise_A_Systematic_Review_and_Meta-Analysis
- Effect of Tart Cherry Concentrate on Endurance Exercise Performance: A Meta-analysis, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31986108/
- Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation for Reducing Muscle Soreness after Eccentric Exercise: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32382573/
- The effect of creatine and magnesium supplementation on delayed onset muscle soreness – Western CEDAR, 11月 3, 2025にアクセス、 https://cedar.wwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1319&context=wwuet
- Short and longer-term effects of creatine supplementation on exercise induced muscle damage – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3737793/