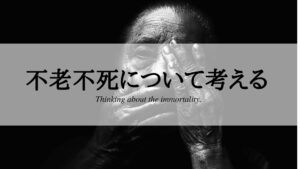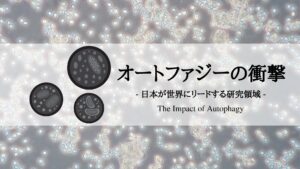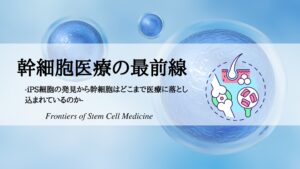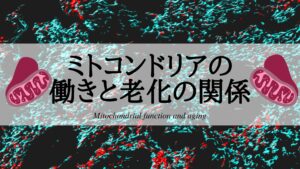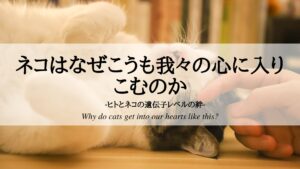はじめに
不老不死、永遠の命。
人々が古代から夢見るテーマですが、科学的にはなかなか解明されていない謎めいた存在です。
しかしながら、最近の研究によって、海の中に住むクラゲ(特にベニクラゲ)が驚くべき特性を持っていることが明らかになりつつあります。
クラゲは、その透明で美しい姿と、ゆったりとした泳ぎで私たちを魅了しますが、その生命のサイクルに秘められた秘密はいかに?
本記事では、クラゲの寿命や再生能力、そして不老不死との関連について深掘りし、驚くべき海洋生物の可能性を追求します。
果たして、ベニクラゲは不老不死の鍵を握っているのか?一緒に探求してみましょう。
クラゲはどんな動物?

クラゲは海水中又は淡水中で浮遊生活をする刺胞動物です。
海にも池にも川にも住んでいます。現在約3000種類が発見されています。
身体の形は傘型や箱型などがあり、大きさは数mmから10mを超えるものまであります。また、重さも1g以下から200㎏以上のものも見つかっており、身体の90%以上は水分で透明なジェリー状で骨はありません。
傘の回りに触手が生えていて、これで餌を捕食します。
眼を持つクラゲもおり、クラゲには雄と雌があり、卵を生みます。
卵が孵化して幼生(プラヌラ)が生まれ、ポリプというイソギンチャク状のものになり、成体(エフィラ)になります。※中にはポリプを形成しないクラゲもいます。
一般的なクラゲの寿命は、約1年〜2年ほどとされていますが、中には数十年のものもあります。
え、では不老不死じゃないのでは?という方、最後までぜひ読み進めてください。
猛毒を持っているクラゲもいて、その毒で自分が食べられる危険から自分を防御し、逆に魚を食べてしまうこともあります。一方クラゲは魚に食べられるばかりか、ペンギンやカメにも食べられます。他のクラゲにも食べられます。
人が食べられる食用クラゲもあり、中国人や日本人は昔から食用にもしてきました。直径2mで重さ200㎏にもなり、日本近海で大量発生することがあるエチゼンクラゲは食用にもされる一種として知られています。
クラゲには脳がない

クラゲは下等動物なので脳がありません。クラゲに限らず海綿動物、ヒトデ、ウニ、ナマコ、サンゴなども脳がありません。
しかし神経節という神経組織で脳の役割を果たしています。
クラゲにおける神経節は、神経系の重要な部分であり、神経細胞が集まって形成される集合体です。
クラゲの神経節は、感覚器官からの刺激を受け取り、それを中枢神経系に伝える役割を果たします。
また、中枢神経系からの指令を受け取り、体の各部分に対して適切な反応を引き起こす重要な中継器としても機能します。
これにより、クラゲは外部環境との情報の交換を行い、生存や捕食、避ける行動などを制御しています。
神経節は、クラゲの神経系の中心部であり、生物の行動や生理的なプロセスを調整し、適応性のある反応を可能にする重要な要素です。
クラゲでノーベル賞

長崎医科大学、プリンストン大学、名古屋大学、ボストン大学、ウッズホール海洋生物学研究所で研究をしてきた、下村脩博士はオワンクラゲから緑色蛍光たんぱく質を発見(GFP)し、2008年にノーベル化学賞を受賞しました。
オワンクラゲから得られた緑色蛍光たんぱく質(GFP)は、現在、医学生物学の研究ツールとして重用され、臨床医学でも活用されています。
たとえば緑色蛍光たんぱく質で標識をつけた抗がん剤を 注射した後に、患部に紫外線を当てると緑色蛍光たんぱく質が緑色蛍光を発するので、抗がん剤が患部に到達したことが分かります。
不老不死のクラゲ
いま「不老不死」のクラゲとして注目されているのがベニクラゲです。
ベニクラゲは消化器が赤いのでベニクラゲと名づけられています。
大きさは傘の直径が1 cm程度で、日本では3種類が見つかっています。
ベニクラゲは口柄(こうへい)部と呼ばれる以外が若返ることになります。そして、この若返りは繰り返し行なわれます。ということは不老不死になります。
日本では和歌山県にある京都大学瀬戸臨海実験所のベニクラゲ再生生物学体験研究所が2018年に設立されて、現在、久保田信准教授らが研究中です。
もしこの不老不死のメカニズムが解明されてヒトにも応用できるようになれば、大変なことになることは言うまでもありませんね。
ここからは現在までに明らかになっているベニクラゲの不老不死についてもう一つ踏み込んで見ていきたいと思います。
ベニクラゲの研究

ベニクラゲと不老不死の関連について、一番古いと思われる研究は以下のものです。
Reversing the Life Cycle: Medusae Transforming into Polyps and Cell Transdifferentiation in Turritopsis nutricula (Cnidaria, Hydrozoa) (1996) Biological Bulletin
この論文は題名の通り、ベニクラゲにおけるメデューサと呼ばれる成体からポリプと呼ばれる若い状態にライフサイクルが戻される現象を報告しています。
この論文において、興味深い記述がディスカッション箇所にあります。
This is the first known case of a metazoan being capable of reverting completely to a clonal life stage after having achieved sexual maturity in a solitaty stage.
そのまま直訳すると、「これは、単独で性成熟した後、クローン性のライフステージに完全に戻ることができる後生動物の最初のケースである。」
なんとも夢がある話ですね。
2003年の研究では、ベニクラゲのライフサイクル巻き戻し時の形態学的な分析が行われ、顕著な変性とアポトーシスの存在が、成体メデューサがポリプに変身する際の一種の変態の発生に関係している可能性があることが報告されています。
Morphological and ultrastructural analysis of Turriptopsis nutricula during life cycle reversal (2003) Tissue and Cell
関連した研究で、より分子レベルな内容に言及した研究が2022年にスペインのグループから報告されていました。
Comparative genomics of mortal and immortal cnidarians unveils novel keys behind rejuvenation (2022) Proc Natl Acad Sci U S A.
この論文では、死滅する刺胞動物と不滅(不死)の刺胞動物のゲノム解析から、若返りの背後にある新たな鍵を明らかにしています。
具体的には、彼らは論文の最後でPRC2と呼ばれる遺伝子のサイレンシングと多能性に関与する遺伝子群の活性化がベニクラゲの若返り能力に重要である可能性を示唆しています。
そして最後の一文でこんなかっこいいことを書いています。
Altogether, this work provides insights into the molecular mechanisms giving T. dohrnii the remarkable capacity to rejuvenate and escape death.
直訳すると、「本研究は、T. dohrnii(ベニクラゲ)が若返り、死から逃れるという驚くべき能力を持つ分子メカニズムに関する洞察を提供するものである。」
この報告が2022年であることを考えると、最先端に近いかなと思います。
ベニクラゲは進化的には我々と非常に遠いところにあるものであるとはいえ、その不老不死の分子メカニズムが明らかにされそうになっているのはたまりませんね。
今後の研究に期待です。
執筆者のリサーチがまだ若干足りていない感もありますので、このあたりの情報については新しい記事の執筆なり、この記事の更新なり、でどんどん新しくしていきます。
2022年に報告された研究が掲載されている論文雑誌はProceeding of the National Academy of Sciences (PNAS)と呼ばれていて、アカデミックな業界では知らない人はいない非常に有名なジャーナルです。必ずしもそうとも言えませんが、PNASに掲載されているということで、本論文が厳しい審査を受けたであろうことと、この論文の研究内容のインパクトが伺えます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%BC%E7%B4%80%E8%A6%81
※PNASには編集者の推薦枠があることはよく知られていますが、この論文はおそらく通常の投稿枠と思われます。
まとめ
クラゲの中でベニクラゲと呼ばれる種は成体になってからライフステージを繰り返す若返り機構を持っており、実質的に不老不死が可能なメカニズムを保有しています。
2023年現在、そのメカニズムのすべてが明らかになっているわけではありませんが、分子レベルで関与している分子が少しずつ同定されているようです。
多くのSF小説や漫画の題材とされる不老不死が全く不可能ではない領域にまで近づいているのかもしれませんね。
執筆者も例外なく不老不死に興味を持つ一人の人間として、これからも探求し、このサイトで皆さんにわかりやすく最先端の情報をお届けしていこうと思います。
それではまた次回お会いしましょう。