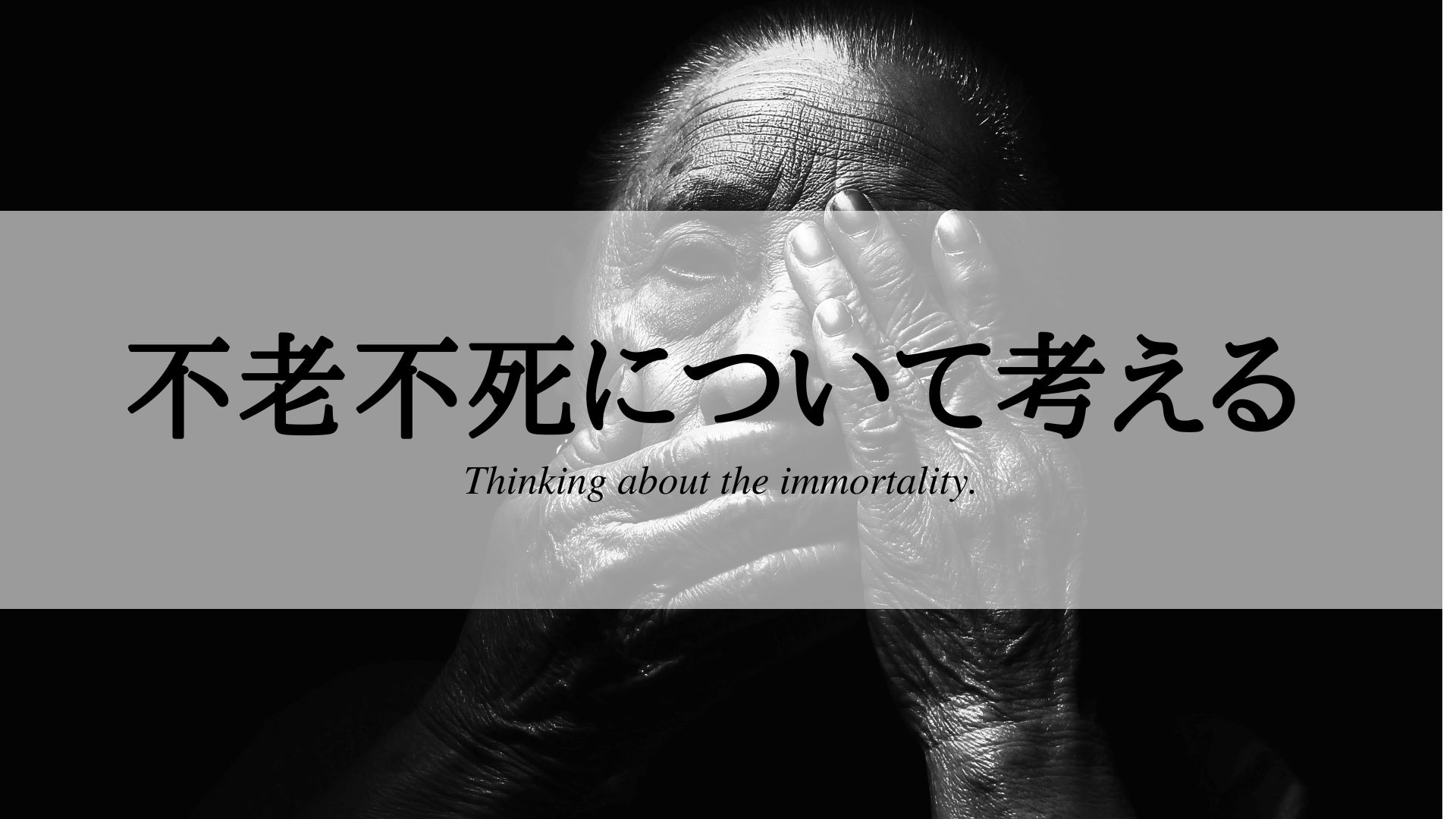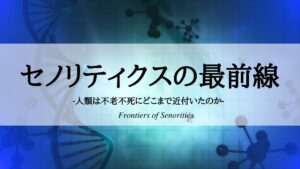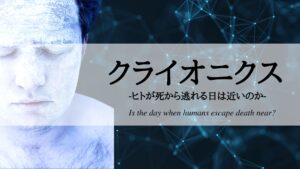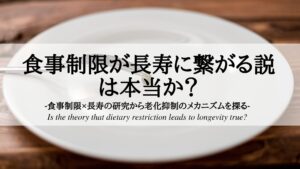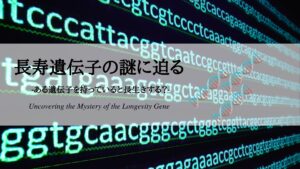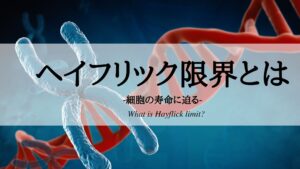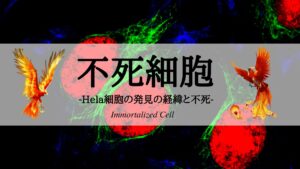はじめに
SFやアニメの世界でもしばしば話題になる不老不死。
皆さんも一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
本記事ではそんな不老不死について概念的な説明から近年話題のデジタルクローンについても少し触れ、不老不死の全体的なお話をします。
ぜひ不老不死について関心がある方は読み進めてください。

不老不死とは

不老不死とは、ある時点を境に肉体が決して老化することもなく、死ぬこともない状態を表します。学術的には、「不老」と「不死」は別々に考えるべきなのですが、古より「不老不死」を求めた権力者による研究が行われてきました。錬金術もそのうちのひとつです。
特に「死」については、生物学的な話とは別に、人の中には様々な考え方が生まれています。
例えば、「例え肉体は朽ち果てたとしても、人の精神は不朽である」とする文化は世界中で見ることができます。
「人には三度死が訪れる」という概念も同じような考え方の上に成り立っています。ちなみに三度の死の一度目は肉体的な死が訪れた時、二度目は自分のことを記憶している人に死が訪れた時、三度目は自分が生きていたことが歴史上からも忘れ去られてしまった時です。
とすれば、織田信長や松下幸之助などは精神的な概念上の「不老不死」を手に入れたといっても過言ではないでしょう。「歴史に名を遺す」ということは「不老不死を手に入れる」と同義であったんですね。
未来を予見したSFの名作「銀河鉄道999」

昭和40年代に生まれた日本人が「不老不死」と聞いて、真っ先に思い浮かべるのは松本零士先生の「銀河鉄道999」ではないでしょうか。当時、一年間にもわたりTV放送されただけでなく、2度も映画化された超人気作品です。
知らない人のために少しだけ物語の内容を説明しましょう。
未来の社会では、裕福な人間は機械の体を手に入れて不老不死となるが、貧しい人間は、機械の体になれずに虐げられて生きていかなければならない状況下にあります。地位もあり機械の体を持つ伯爵に母を殺された主人公は、母への復習を誓い、機械の体を得るために旅に出るというSF物語です。
自分の意識だけを機械の体(ロボット)に移して、肉体は消滅してしまう状態を、果たして生きていると言えるのか、という倫理的な問題にも発展するテーマを扱った作品でした。
主人公は最終的には「「限りがあるからこそ人は一生懸命に生きる。だからこそ人に対する優しさや思いやりが生まれる。」との思いに至り、機械の体になることを拒否します。
まるで未来を予見したかのような、「不死」について考えさせられる名作です。
機械の体での不老不死は2023年現在でも部分的に可能 -デジタルクローン-

自分の肉体を老いさせず、死なせないという「不老不死」ではなく、「銀河鉄道999」に出てくる機械人間の状態での不老不死であれば、2023年時点で既に一部実現可能であることをご存じでしょうか。
もちろん、自分の意志で二足歩行ができるロボットの体を得たわけではなく、あくまでもデジタル上の話です
AI(人工知能)にパーソナルな情報(SNS上にあるような今までの発言、執筆物、思考法、価値観などや、映像として残されている口癖やイントネーションなど)を学習させることで、自分にそっくりな「デジタル上のクローン人間」を生成するサービスが既に行われています。
この技術により、人は生物としての「死」が訪れた後も、「デジタル上のクローン人間」となって生き続けることができるようになります。不自然な感覚を与えずに会話が成立しますので、家族や友人らの「相談相手」になることも可能です。つまり、自分以外の周囲の人たちからすれば、正に生き続けているかのような状態になるわけです。

不老不死がもたらす危険性

もし仮に、生物学上の「不老不死」が実現してしまったら、誰も死ななくなるので、世界中に人間が溢れてしまい、食料だけでなく空気など生きるために必要なものが足りなくなり、絶滅するのではないかとも言われています。
デジタル上の話であれば上記のような問題は起こりませんが、別の問題が指摘されているという事実もあります。具体的に見ていきましょう。
不具合が発生しても外からはわからない
AIによる自動運転の技術は既に実用化のレベルに達していますが、どうしても解決しなければならない問題として「絶対に不具合が発生しないのか」という点が挙げられます。自動運転が不具合を起こすということは、人の死につながる事故に直結するからです。
2022年4月には、高速道路や一定の範囲など限られた環境下であれば、ドライバーを介さない位自動運転が可能となる法律の改正案が成立するなど、その信頼性はかなり進んでいます。
しかし、絶対に不具合が発生しないと断言することはできません。自動運転の場合、不具合が発生すれば外からの観察でわかりますが、「デジタル上のクローン人間」が不具合を起こしても、外からはわからないでしょう。対象が故人であれば本人に確認する術がありませんので、不具合かどうかを検証することはかなり困難になるでしょう。
本人が希望しなくても生き続けてしまう
仮に脳死した際、自分の臓器を医療に活かすかどうかを生前に自己申告するように、自分の「クローン人間」を作っても良いかどうかの意思表示を生前に申告する時代が来るかもしれません。
また、生前に自分の「クローン人間」を作った場合、自分の死とともに「クローン人間」も消滅させるのか、それとも生かしておくのかを意思表示しなければならないでしょう。
現時点においても、故人であれば本人確認する術がありませんので、他人が勝手に「デジタル上のクローン人間」を生み出すことが出来ます。
著名人でなくても、誰もがSNSなどに情報が残っている時代ですので、作り出すことは容易です。親族であれば勝手に作り出してもいのか、良いのであれば何親等までそれが許されるのか、法整備が急務となるでしょう。
誰の管理下にあるのか
小説や絵画などの創作物には著作権が認められており、死後70年間は保護されています。保護期間を過ぎると著作権は消滅します。それ以降は「パブリックドメイン(public domain)」として、誰もが許可なく使える創作物となります。
では、「デジタル上のクローン人間」も同じように扱っても良いのでしょうか。あくまで「物」であって「人」ではないという認識で問題ないのでしょうか。
意図的に加工される恐れ
パーソナルな情報を学習させることで「デジタル上のクローン人間」は完成するわけだが、それが本当にその人独自の情報のみを学習させたのかどうかは、誰がどのように監視すれば良いのでしょうか。
著名な故人を利用しようとした第三者が、意図的に何かの情報を学習させることで、発言などを都合の良い方向に持っていくことも十分考えられます。
故人での利用ではなく、公けに「デジタル上のクローン人間」を活用する場合、世界的に認定された機関において制作された「認定クローン」のみが使用可能といったようなルール作りが急務となります。
宗教観に与える影響
宗教において、故人との会話はとても重要なポジションにあります。
日本では、位牌やお墓の前で手を合わせ、故人と会話をする。それはイマジネーションの世界であり、自分と向き合う場でもあります。
しかし、「デジタル上のクローン人間」が存在していれば、故人との会話は生前と何も変わらない状況で行うことになります。
これが恒常的に行われるようになれば、死後の世界に関する宗教観に大きく影響することは避けられません。故人は常にデジタル上に存在しているのだから、極楽浄土に居る姿を想像するのは難しくなっていく筈です。
おわりに
実際に不老不死が仮に実現したとしても、多くの問題が発生しそうで、前途多難です。
とはいえ、実際に目の前に自分が不老不死になれるチャンスがあったとしたら、皆さんはどうされるでしょうか。
近年、生物学的には例えばクラゲの研究で不老不死のメカニズムを匂わせる研究成果が報告されています。

デジタルクローンも気になるところですが、実際の今の身体が若返る未来も絶対に実現できないわけではないかもしれません。
それではまた別の記事でお会いしましょう。