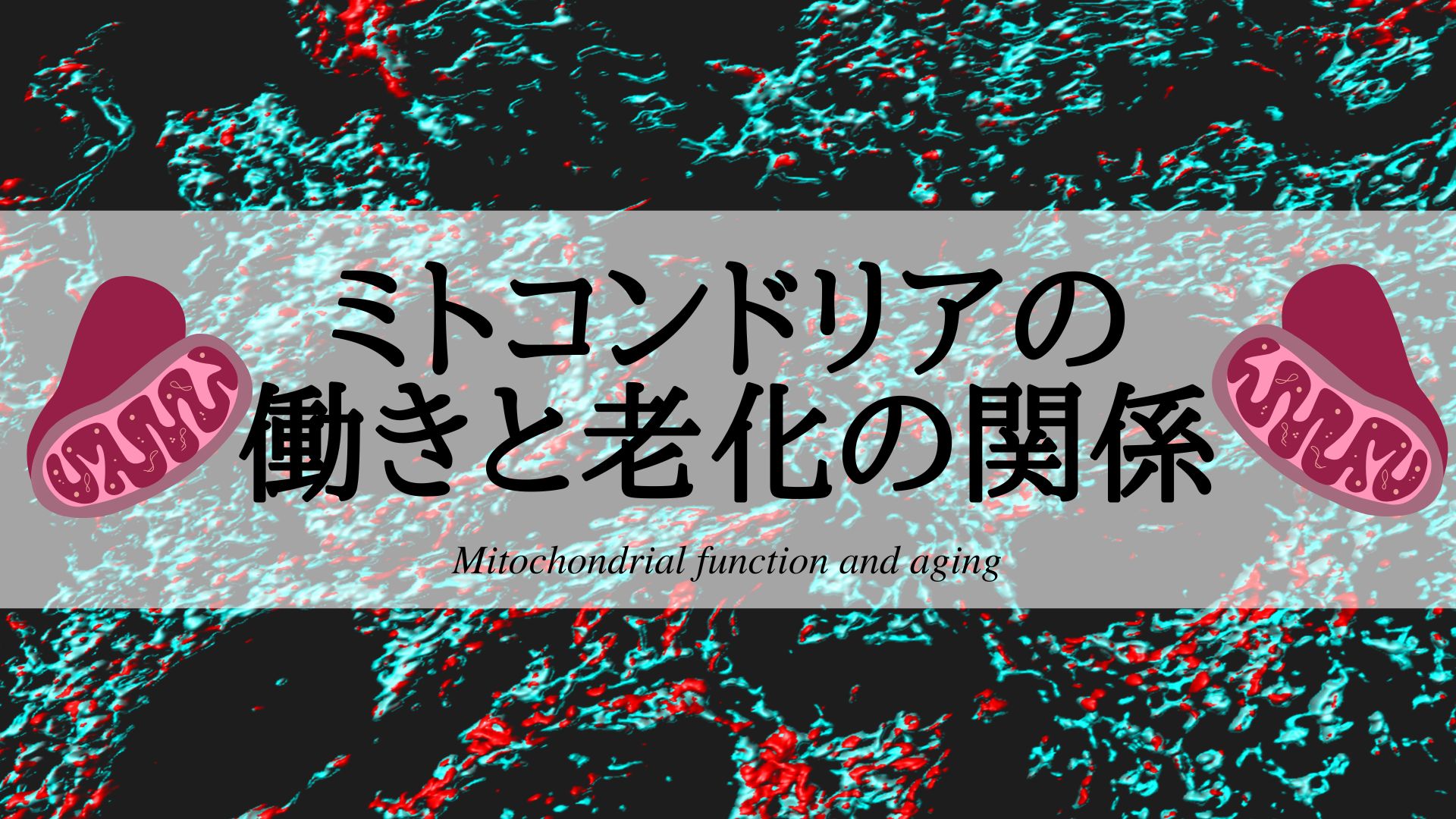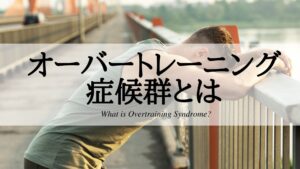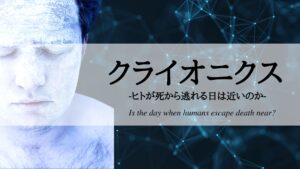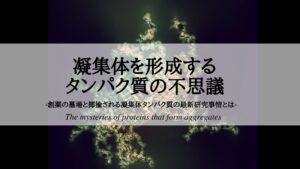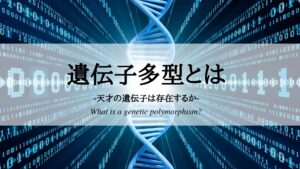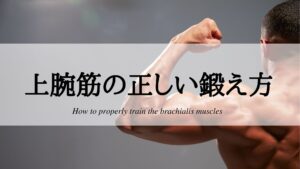私たちの身体の細胞にはミトコンドリアと呼ばれる細胞小器官(オルガネラ)があります。

ミトコンドリアが従来から重要な細胞小器官であることは知られていましたが、ミトコンドリアが寿命や老化とも深い関連があると注目されてきた歴史はそんなに長くありません。
本記事ではミトコンドリアの基本的な働きからミトコンドリアと老化の関連について記載していきます。細胞小器官の中で最も魅力的で興味関心を持つ研究者が多いと言われるミトコンドリア。こんな働きもあったのか、と新しい機能や役割にこの記事で出会うことが出来ましたら嬉しい限りです。
ミトコンドリアの働き

ミトコンドリアの最も代表的な働きは身体のエネルギーを生成することです。ミトコンドリアでのエネルギー生成は酸素を用いることから、好気呼吸と呼ばれています。
ミトコンドリアでのエネルギー生成は電子伝達系といい、そこには多くのタンパク質が関与しています。細胞の活動に必要なエネルギーの90%以上がミトコンドリアで生産されると言われており、生成されたエネルギーは細胞内に運搬されていきます。ミトコンドリアの働きによって、細胞が活動することが出来ていると言っても過言ではありません。
ミトコンドリアが生成するエネルギーをATPと呼びます。ATPとはアデノシン三リン酸の略で、ATPが分解されることによって、細胞はエネルギーを得て様々な活動を行うことができます。
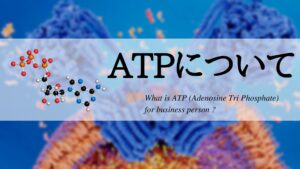
ミトコンドリアの電子伝達系
ミトコンドリアは他のATP生成経路に比較して最も効率よくATPを生成することができます。そのATP生成経路は電子伝達系と呼ばれ、グルコース1分子に対して最大34分子のATPが合成されると言われています。
ミトコンドリアは内膜と外膜の二層構造をしており、電子伝達系では内膜と外膜の間を水素イオンが行き来しながらATPが生成されます。この際、活用されるタンパク質は好気呼吸に関わっている複合体ということで呼吸鎖複合体と呼びます。
ミトコンドリアの電子伝達系はここで解説するには少し複雑すぎるので、説明を割愛します。またどこかでミトコンドリアの電子伝達系だけで区切って説明したいと思います。
ミトコンドリアはどこから来たのか -細胞内共生説-

さて、主にエネルギー生成の働きを行うミトコンドリアですが、そんなミトコンドリアをよく見ると、なんだかチャーミングな顔つきをしています。私たちの一つひとつの細胞の中に格納されていながら、まるでミトコンドリアそれ自体がひとつの生命体であるかのようです。
実は、ミトコンドリアは元々一つの生命体で何らかのきっかけで私たちの細胞と共生することになったという説が存在します(細胞内共生説)。今日においてもこのミトコンドリア共生説は結構有力で、ミトコンドリアの細胞内共生説は19世紀後半から提唱されていたと言われています。
ミトコンドリア細胞内共生説の最も有力な根拠はミトコンドリア単体でDNAを保有していることです。それはミトコンドリアDNA(mtDNA)と呼ばれ、核とともにミトコンドリアタンパク質の一部をコーディングしているとされています。
ミトコンドリアという一つの細胞内小器官のタンパク質を核とミトコンドリアそれぞれのDNAが分担して生成しているというのはなんとも共生感があって素敵です。
原始的にはミトコンドリアは細胞外にあったにせよ、今日の私たちはミトコンドリアがなくてはならない身体となってしまっているのです。
ミトコンドリアDNAが私たちに教えてくれること –

ミトコンドリアDNA(mtDNA)において、最も興味深い性質の一つに母方の親からのみ遺伝するというものがあります。私たち一人ひとりのミトコンドリアDNAはお母さん由来なのです。ミトコンドリア活性が運動トレーニング能力と非常に関与することから、母方の親の運動能力が子の運動能力に遺伝する、と言われたりもしますね。
また、ミトコンドリアDNA(mtDNA)は母方の先祖の情報も格納していると言われています。そのため、ミトコンドリアDNAを測定することで、自分の先祖の人種(コーカソイドか、モンゴロイドかなど)を分類することが出来るともされています。
さらに、ミトコンドリアDNA(mtDNA)は加齢とともに変異が起きると言われていて、ミトコンドリアの崩壊によってミトコンドリアDNAが細胞内にリリースされることも報告されています。
現在、遺伝子から個人の特性や病気へのかかりやすさを予測することは小さなブームとなっていますが、ミトコンドリアDNAはそういった観点からも多くの研究者、実業家、起業家の興味を惹く素材でもあるのです。
ミトコンドリアDNAは核内のDNAと違って環状構造をしています。タンパク質も13個ほどしかコーディングせず、核内のDNAとは色々と違いがあります。
ミトコンドリアと老化の関係

老化は様々な観点から研究されており、一口に原因を語ることは困難ですが、よく注目される老化因子として活性酸素(Reactive Oxygen Species)と呼ばれるものがあります。活性酸素は私たちの身体の中で様々なタンパク質、酵素群の働きを阻害し、私たちが持つ細胞を衰えさせていきます。
ミトコンドリアは電子伝達系において好気呼吸を行う際、活性酸素を出すことが知られていますが、これは酸化還元酵素によって通常処理されます。しかしながら、酸化還元酵素が酸化還元機能を失う、または弱まった場合活性酸素種は細胞内で他のタンパク質群に対して悪影響を及ぼしてしまいます。
適度な活性酸素は運動トレーニングにおいても重要であることが知られていますが、老化という観点で見たときにミトコンドリアはポジティブな要素ばかりではないという意味になります。
以下ではミトコンドリアと老化に関連付けながらPGC-1αと呼ばれるタンパク質とミトコンドリアそのままの代謝機構(マイトファジー)について解説していきます。
PGC-1α
PGC-1αは運動トレーニングが効果を示すにあたって重要とされるタンパク質です。PGC-1αが多く発現することによってミトコンドリアが生成され、運動トレーニングの効果が高まると言われています。
運動トレーニングによって、ミトコンドリアの酵素活性が高まることはよく知られていますが、その活性がPGC-1αを介しているという報告があります。また、PGC-1αを遺伝的に過剰発現するとミトコンドリア活性が高まることも報告されています。
運動トレーニングのアンチエイジング効果は各研究期間や個人からも報告されていて、一般でもよく知られていますが、その運動トレーニングによるアンチエイジング効果こそがPGC-1αによる、という説もあるのです。
マイトファジー
ミトコンドリアを含む細胞内小器官にはライフサイクルが存在します。生成され、成熟し、その後代謝されていきます。細胞内タンパク質はオートファジーと呼ばれる代謝機構によってタンパク質が分解され、その後再利用されていきますが、ミトコンドリアはミトコンドリア特異的なオートファジー、マイトファジーによって代謝されていくことが知られています。
マイトファジーはPINK1やPARKINというタンパク質などによって制御されていると言われています。マイトファジーそのものの細胞内メカニズムもまだまだ不明点は多いですが、「悪い」ミトコンドリアを取り除く機構が老化と関与しそう、ということは割と理にかなっていますね。
実際研究論文において、マイトファジーが加齢関連の疾患に影響しており、マイトファジーを抑制すると活性酸素が増えてミトコンドリアDNAの変異が増え、ATPの生成が落ちると報告されています。
マイトファジーの亢進がアンチエイジングになるという論調は一定の科学的なエビデンスがある、といって過言ではないでしょう。
オートファジーは日本人の大隅良典さんがノーベル賞を受賞したことからも知られているように日本が世界にリードしています。
まとめ
ミトコンドリアは多くの研究者を魅了する細胞内小器官で、加齢とも非常に関係が深いです。ミトコンドリアは原始的には私たちの細胞に共生していなかった説も根強いですが、今日の私たちの身体活動において、ミトコンドリアはなくてはならない存在です。
PGC-1αやマイトファジー、活性酸素など多くの登場人物がいますが、依然として私たちはミトコンドリアの機能を完全にコントロールすることは出来ずにいます。今後研究が進んでさらなる知見がもたらされたときは私たちはミトコンドリアをベースに加齢すらも支配下に置くことが出来るようになるかもしれません。