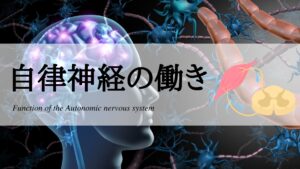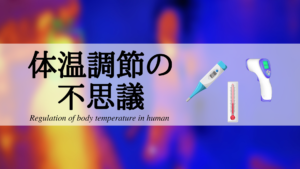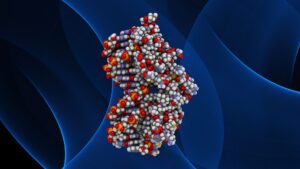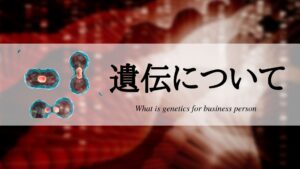抗生物質は「どのように効くのか」「MRSAとの関係性は何なのか」気になりますよね。
細菌や真菌などの発育を阻害する抗生物質の薬理作用は、微生物の発育や増殖を阻止する、あるいは微生物を殺滅する機序を持ちます。
本記事では、抗生物質の薬理作用について、ペニシリンをはじめとするβ-ラクタム系やテトラサイクリン系など、代表的な抗生物質の薬理作用とともに紹介します。抗生物質が引き起こすMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)への影響についても触れますので、抗生物質の薬理作用を深く理解したい方や抗生物質を適正使用すべき理由を知りたい方はぜひ参考にしてください。

抗生物質の薬理作用のメカニズム

抗生物質の薬理作用は、細菌を絶滅させる静菌作用と細菌の増殖を抑える殺菌作用に大別されます。感染症の治癒にはこの作用と人の免疫機構が重要です。微生物に選択毒性が高いものが抗生物質として使用され、以下の機序で分類されています。
・細胞壁合成阻害薬
・タンパク質合成阻害薬
・核酸合成阻害薬
・細胞膜機能障害薬
さらに、上記の作用機序のうち基本骨格でも類別しており、βーラクタム系薬やテトラサイクリン系薬は代表的な抗生物質です。具体的にみていきましょう。
β-ラクタム系抗生物質の薬理作用と特徴
β-ラクタム系抗生物質は、4員環であるβラクタム環を基本構造持つ細胞壁合成阻害薬です。一部の細菌は細胞壁がないと生存できず、細胞壁の合成に関わるペニシリン結合タンパク質に結合して架橋反応を抑制することで、細菌の細胞壁の合成を阻害して殺菌作用を示します。
β-ラクタム系薬は、ペニシリン系薬やセフェム系薬をはじめとしてモノバクタム系薬、ペネム系薬が代表的です。人の細胞に対する毒性が低く、古くから使用されているため、感受性があれば感染症治療の第一選択薬として利用されます。
テトラサイクリン系抗生物質の薬理作用と特徴
テトラサイクリン系抗生物質は、骨格に特有の4つの環をもつタンパク質合成阻害薬です。リボソーム30S分画に結合してアミノシルtRNAとmRNAの結合を阻害するため、タンパク質の合成を妨げて静菌的作用を示します。
テトラサイクリン系薬は、テトラサイクリンやミノサイクリンなどが代表的で抗菌スペクトルが広いことが特徴的です。
近年では耐性化がみられたり、他の抗生物質の開発が進行したりしています。そのため、感染症治療の第一選択薬として用いられる場面は、リケッチア科感染症やライム病、ビブリオ感染症などです。
ペニシリンと薬剤耐性菌の関係性

最も代表的な抗生物質の1つであるβ-ラクタム系薬のペニシリンは、問題に取り上げられている薬剤耐性菌の出現に大きく関係しています。
1929年にA.Flemingによって青カビからペニシリンを単離し、世界で最初に抗生物質が発見されました。ペニシリンは感染症の治療に優れた効果を発揮し利用されてきましたが、近年では薬剤耐性菌の出現が問題となり、抗生物質の適正使用が求められています。
抗生物質に耐性を持つ微生物である薬剤耐性菌は、過剰な抗生物質の使用や不適切な使用などが原因です。抗生物質の開発と細菌の耐性化はいたちごっこに例えられますが、近年では細菌の耐性獲得速度が上昇しています。抗生物質を開発してもすぐに耐性菌ができてしまうため、抗生物質の適正使用は重要です。
実際に現れた薬剤耐性菌には、院内感染菌として知られているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)が挙げられます。具体的にみていきましょう。
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)とは?
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)は、メチシリンをはじめとする多くのβーラクタム系抗生物質に対して耐性を持つ変異株の黄色ブドウ球菌です。黄色ブドウ球菌は通常、皮膚や鼻などの常在菌ですが、MRSAは変異しており感染症を引き起こすことがあります。
MRSAはβーラクタム系薬は結合しにくい新たなペニシリン結合タンパク質を産生することにより耐性化されています。日本では1980年代前半から爆発的に増加しましたが近年は減少傾向です。
MRSAに有効な抗生物質
一般的な抗生物質に対して耐性を持つMRSAに有効な抗生物質は、バンコマイシンが推奨薬です。薬剤も耐性菌の発生を防ぐために慎重な使用が求められるため、症例に合わせて以下の抗菌薬を使い分けます。
・グリコペプチド系薬(バンコマイシン、テイコプラニン)
・オキサゾリジノン系薬(リネゾリド)
・アミノグリコシド系薬(アルベカシン)
・リポペプチド系薬(ダプトマイシン)
MRSAは治療抵抗性が問題であり、黄色ブドウ球菌は接触感染によって広がります。感染拡大を防ぐためにも、標準予防策および接触予防策を行うことが重要です。
まとめ
本記事では、抗生物質の薬理作用やペニシリンをはじめとするβ-ラクタム系やテトラサイクリン系の特徴、薬剤耐性菌とMRSAなどを紹介しました。
抗生物質には静菌作用と殺菌作用があり感染症の治療に利用されます。しかし、院内感染菌として知られているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)などの薬剤耐性菌の出現により効果が限定的になるかもしれません。
感染症は身近な疾患なので、抗生物質について多くの方が関心をもっているのではないでしょうか。抗生物質の適正使用と薬剤耐性の予防には、医師と患者の協力が必要であり、抗生物質の薬理作用を理解することで感染症の予防と治療に役立てるために、ぜひ本記事を参考にしてみてください。