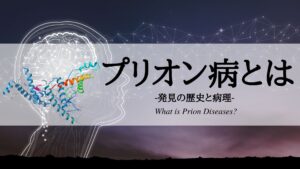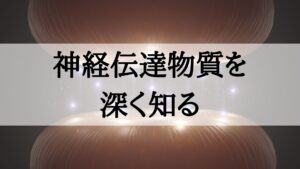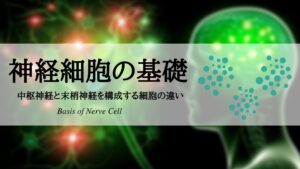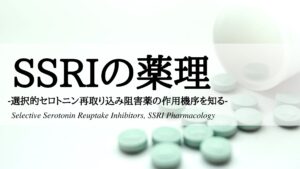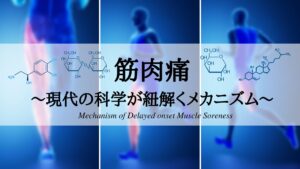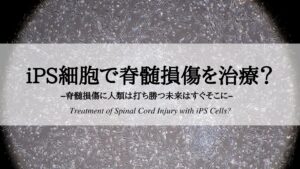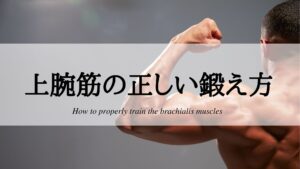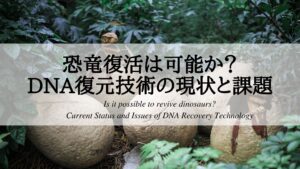パーキンソン病は「どんな病気なのか」「どのような治療薬が効果的なのか」気になりますよね。パーキンソン病は、黒質のドパミンが不足しスムーズに体を動かせなくなる神経変性疾患であり、不足したドーパミンを補充するレボドパが代表的な治療薬です。
この記事では、パーキンソン病と治療薬について詳しく解説します。黒質のドーパミン不足がどのように症状に影響を与えるのか、レボドパのメカニズムにも触れますので、パーキンソン病の知識を深めたい方や治療薬を使用する医療従事者の方はぜひ参考にしてください。
パーキンソン病とは?

パーキンソン病とは、黒質ー線条体のドーパミン作動性神経経路が変性することでドーパミンが欠乏し大脳基底核による運動の制御が障害される神経変性疾患の1種です。
脳内の神経伝達物質ドーパミンは体をスムーズに動かすために必要な機能を担うことから、ドーパミンが不足すると手足の震えや筋肉のこわばり、運動の遅さなどの症状が起こります。
片方の手足の震えや動作の鈍さなどの症状で気づくことが多く、やがて反対側に拡がるとともにバランスが保てなくなり歩行の変化が生じることもあります。進行性の病気であるパーキンソン病は、一旦発症すると自然治癒することはありません。
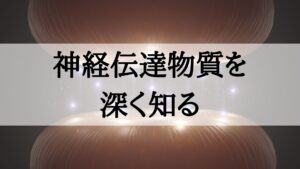
パーキンソン病は薬物療法が基本
パーキンソン病の治療方法は薬物療法が基本です。パーキンソン病の原因は不明であり根本的な治療方法はありません。QOLや生命予後の改善を得るために薬物療法や理学療法、手術療法といった対症療法があります。
基本の治療方法は薬の服用で、適切な薬を選択し量を調整することで症状の改善が図れます。手術療法は薬物療法の効果が不十分な場合に利用され、運動療法は他の治療方法と平行して行うことで運動障害を改善する効果を得られます。
パーキンソン病の治療法の一つに「脳深部刺激療法」というものがあります。世界で8万人以上のパーキンソン病患者が脳深部刺激療法を受けて良好な効果が得られているそうです。
https://www.m.chiba-u.ac.jp/dept/neurosurgery/disease/dbs/
https://www.nouge.net/approach/%E8%84%B3%E6%B7%B1%E9%83%A8%E5%88%BA%E6%BF%80%E7%99%82%E6%B3%95dbs-deep-brain-stimulation/
パーキンソン病治療薬とは?

パーキンソン病の治療薬は主にドーパミンを補充するレボドパ製剤が使用され、ドーパミンの前駆体であるレボドパは体内でドーパミンに変換されることで症状の改善を図ります。レボドパ製剤を中心に以下のパーキンソン病治療薬があります。
・ドパミンを補充するレボドパ製剤
・ドパミンアゴニスト
・脳内でのドパミン使用効率を上げるMAO-B阻害薬とCOMT阻害薬
・抗コリン薬
・ドパミン遊離促進薬
・レボドパ賦活薬
・ノルアドレナリン前駆物質
・アデノシンAー2A受容体拮抗薬
不足したドーパミンの働きを補うためにレボドパ製剤やドーパミンアゴニストを軸に、レボドパの吸収を助けたり、体内のドーパミンの分解を抑える補助薬などを組み合わせたりしてパーキンソン病を治療をするので、各々の薬の目的を理解して服用することが重要です。
代表的なパーキンソン病治療薬のレボドパとは

パーキンソン病の治療で非常に重要な役割をもつレボドパは、脳内でドーパミンに変換されることで不足したドーパミンを補充します。レボドパは、運動調節を行う神経伝達物質のドーパミンの前駆物質です。
ドーパミンを服用しても脳に移行しないため、レボドパを補給し症状の改善を図ります。消化器症状や長期服用時の不随意運動、精神症状などの副作用が出現しやすいかもしれません。しかし、運動症状改善効果が強力であり、使用頻度の高い代表的なパーキンソン病治療薬といえます。
レボドパの作用機序
レボドパはパーキンソン病の脳内で不足したドパミンの補充をします。レボドパは腸から吸収され、血液脳関門を通過して黒質-線条体でドパミンに変換されて作用する神経伝達物質の前駆物質です。
レボドパから変換されたドパミンはシナプス小胞に取り込まれて蓄積され、運動調節のために神経から遊離されます。放出されたドパミンはドパミン受容体に作用することでパーキンソン病の症状を改善します。
レボドパの多くは末梢を循環する間にドパ脱炭酸酵素により代謝されてしまい、十分な効果を得るにはレボドパの大量投与が必要となりかねません。脳内へ入る前の代謝を防ぐためにドパ脱炭酸酵素阻害薬と併用されます。
レボドパの副作用と注意点
レボドパの副作用は、消化器症状や不随意運動、精神症状の頻度が高く、以下の表に副作用の特徴と注意点をまとめています。
| 副作用症状 | 特徴と注意点 | |
| ドパミン過剰 によるもの | 消化器症状 | ・ドパミンが化学受容器引き金帯を刺激することで起こる ・服薬を食直後にする ・制吐剤の併用で対策可能 |
| 不随意運動 | ・自分の意思とは関係なく体が動くこと ・レボドパの量の調整や少量頻回投与に変更することで対策可能 | |
| 精神症状 | ・幻覚やせん妄症状などが出現する ・レボドパの減量して対策する | |
| 循環器症状 | ・動機や不整脈、立ち眩みなど ・心臓のドパミン受容体を刺激することで出現する | |
| 長期服用に 伴うもの | wearing off 現象 | ・薬効の持続時間が短縮し、症状の日内変動が起きること ・レボドパを分割投与したり、パーキンソン病の他の治療薬を併用して対策する |
| on-off 現象 | ・服用した時間に関わらず急激に症状が変動する ・医師や薬剤師に相談してください | |
| no on 現象 | ・効果が発現しないこと ・空腹時に服用することやレボドパの1回量を増量することで対策可能 | |
| delayed on 現象 | ・効果がでるまでに時間がかかる ・空腹時に服用することやレボドパの1回量を増量することで対策可能 | |
| 急な中断や 脱水によるもの | 悪性症候群 | ・高熱や意識障害、筋強剛などの症状が出現する ・十分な輸液の投与や体の冷却、ダントロレンの投与で対応する |
治療の際に副作用を心配されるかもしれません。しかしレボドパの副作用の多くは薬の減量で消失します。服用を自己判断で中止すると症状が悪化し、副作用がでることがあるため、副作用のリスクや適切な投与量を確認することが重要です。
まとめ
本記事では、パーキンソン病や治療薬の概要、レボドパのメカニズムを紹介しました。パーキンソン病は黒質のドパミンが不足することで起こる神経変性疾患で、治療には薬物療法が基本です。また、代表的な治療薬であるレボドパは、脳内でドパミンに変換されることで不足したドパミンを補充します。
パーキンソン病に携わる機会がある方は、パーキンソン病や治療薬に興味をもっているのではないでしょうか。治療の基礎知識やパーキンソン病の治療には欠かせないレボドパのメカニズムを理解するために、ぜひ本記事を参考にしてみてください。