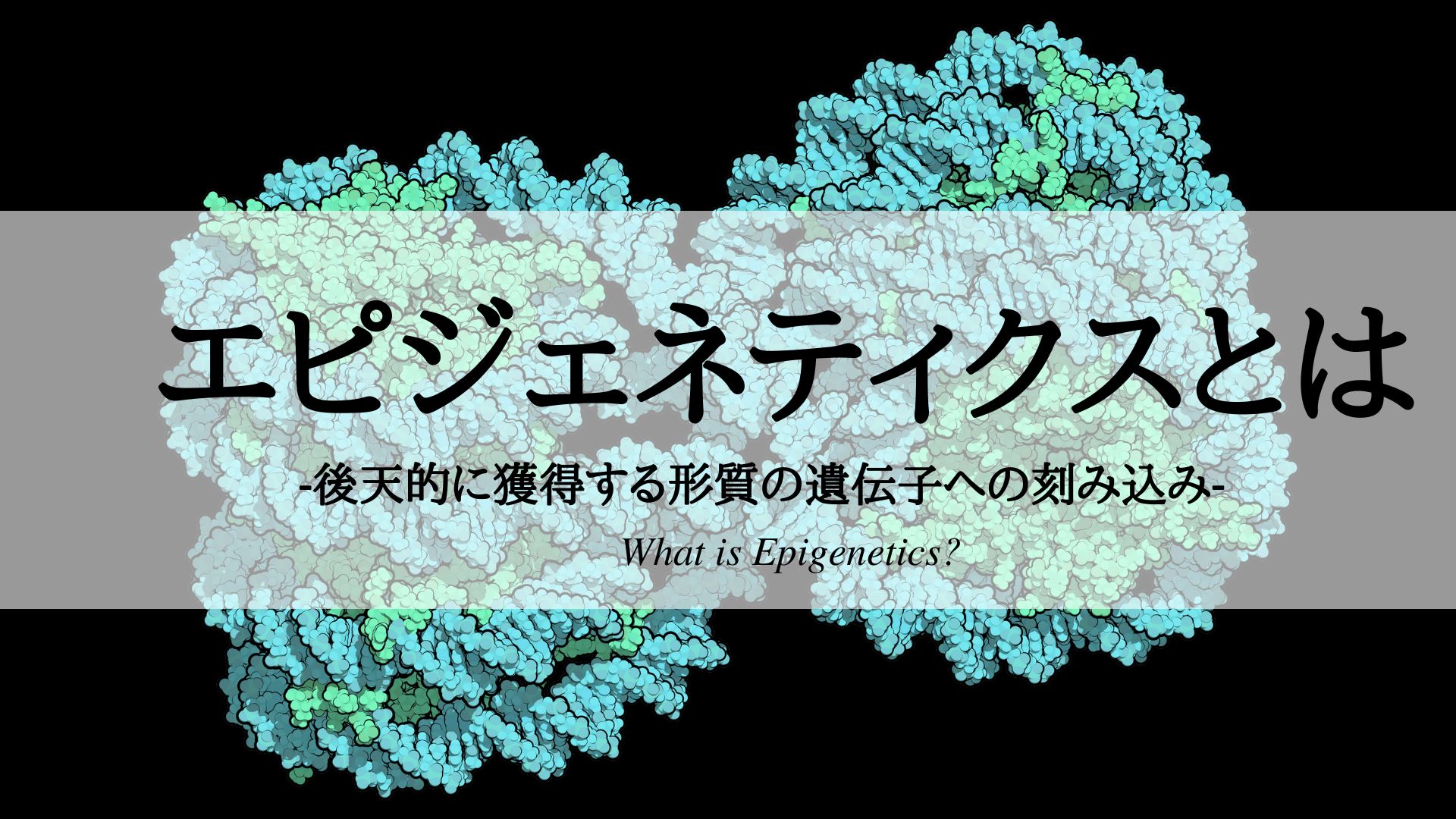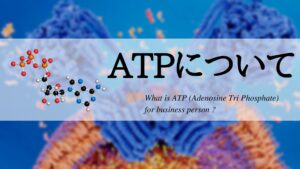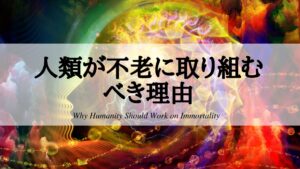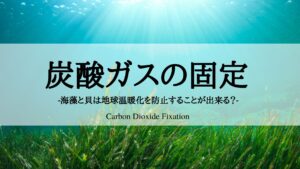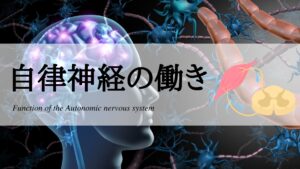エピジェネティクスとは?
私たちヒトを含む真核生物の細胞では、生命の設計図であるゲノムDNAは「クロマチン」と呼ばれる構造をとって、核の中にコンパクトに収納されています。ゲノムDNAが担う遺伝情報は塩基配列にあるとされてきたが、近年の研究で塩基配列が同じでも異なる情報を示すことがわかってきました。
私たちヒトは1個の受精卵から細胞分裂を経て多様な組織や器官に分化していきます。その際、ゲノムのDNA配列には変化は生じません。DNA配列の変化を伴わず、組織や細胞の種類に応じて異なり、細胞分裂後も継承される遺伝子発現の制御・維持の仕組みのことを、エピジェネティクスと呼びます。
エピジェネティクスの情報は、分子の付加や消去によってDNAの構造を変え、ゲノムDNAにある遺伝子の発現をオン、オフする、いわばスイッチの役割を果たしている。つまり個体を構成する多様な細胞が正しく働くためには、各細胞の持つエピジェネティクスが重要なのです。
エピジェネティクスの「エピ」はギリシャ語で「上に」や「後で」を意味する接頭語です。つまり、エピジェネティクスは通常の遺伝学の後の領域(後成)を意味します。
エピジェネティクスの関わり

多くの生命現象に関連し、人工多能性幹細胞(iPS細胞)・胚性幹細胞(ES細胞)が多様な器官となる能力(分化能)、哺乳類クローン作成の成否と異常発生などに影響する要因(リプログラミング)、がんや遺伝子疾患の発生のメカニズム、脳機能などにも関わっています。
その経年劣化は老化に、異常化は癌(がん)化に深く関与するため、エピジェネティクスはこれらの分野で極めて重要な研究分野となり、すでに診断や治療のバイオマーカーとして応用が始まっています。
エピジェネティクス研究の歴史
「エピジェネティックス」という言葉は、1942年にイギリスの生物学者コンラッド・ウォディントン(1905−1975)によってつくられましたが、「後生説(エピジェネシス)」と「遺伝学(ジェネティックス)」を組み合わせたものです。
エピジェネティクスは、DNA塩基配列の変化を伴わない後天的な遺伝子制御の変化を主な対象とした研究分野となり、各種生物のゲノムの解読が進んだ2000年代以降、エピジェネティクス研究が盛んになってきています。
一卵性双生児は同じDNAをもちますが、その後、まったく同じ運命をたどるかというと決してそうではありません。
確かに若い頃はそっくりな顔をしているものの、だんだん、見た目にも変化があらわれますし、たとえば一方はあるときがんになり、もう一方は病気知らず……というように、同じ年代で同じ病気を発症するわけでもありません。
エピジェネティクスの代表例

エピジェネティクスの代表例はDNAのメチル化とヒストンの修飾です。一つずつ見ていきましょう。
DNAメチル化
DNAメチル化は遺伝子転写の重要な調節要因であり、ヒトの多くの悪性腫瘍では正常組織とは異なった過剰メチル化あるいは低メチル化が見つかっています。
DNA脱メチル化が、その遺伝子を活性化させ大腸がんの発生に関与していることが判明しています。DNAメチル化の変化はヒトがんの多くで認められ、多段階発がんのステップとして関与している場合もあることが知られています。
ヒストン修飾
ヒストン修飾とは、ヒストンにアセチル基やメチル基などが付くことを言います。クロマチンの構造が変わることで遺伝子のオン・オフが調節されますが、その構造変化はDNAメチル化だけではなく、ヒストン修飾によっても制御されています。
がんに特異的なヒストンの化学的修飾も観察されます。
前述のがん抑制遺伝子プロモーターのCpGアイランドDNAメチル化は、ヒストン脱アセチル化酵素 (HDAC) をリクルートすることで当該がん抑制遺伝子の発現を抑制し、がんの発生の一因となります。
エピジェネティクスとがんの関わり

従来、がんの発症および進行は遺伝的疾患と考えられていましたが、現在では、遺伝子変化を伴うエピジェネティック異常を含むものと理解されています。
多くの成人のがんは、加齢やライフスタイル(喫煙、飲酒、ピロリ菌感染の有無など)による点突然変異とDNAのメチル化異常とが蓄積することで発症します。
エピジェネティックな医薬品は、放射線療法や化学療法など現在受け入れられている治療法に対して、置き換え可能あるいは補助的な療法であるかもしれないし、現在の治療法の効果を高めることができるかもしれないということを、近年の研究は示しています。
例えば、ヒストン脱アセチル化酵素 (HDAC) に関しては、医薬品ボリノスタットは既に実用化がなされています。
エピジェネティクスと老化の関連
エピジェネティクスが癌をはじめとする疾患のみならず、加齢や老化においても重要な役割を果たすことが明らかになってきました。
近年、加齢と共に幹細胞も機能が低下し、それによって組織の構築や維持ができなくなるというステムセルエイジ 仮説が唱えられています。
今後のさらなる研究により、エピジェネティクスと アンチエイジング医学が発展し、古今東西、多くの人々が 追い求めてきた「若返り」が実現することが期待されています。
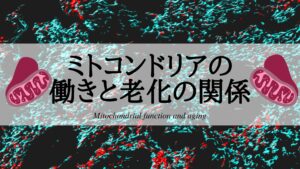
エピジェネティクス市場の成長
世界のエピジェネティクス市場は、2015年から2020年にかけて力強い成長を示しました。2021年から2026年にかけて、市場は約16%のCAGRで成長すると予測されています。

世界中でがんや自己免疫不全症候群(AIDS)が増加していることは、市場成長を促進する重要な要因の一つです。
がん以外の疾患に対するエピジェネティック・ソリューションの広範な採用が、市場成長の推進力となっています。
今後もがんや老化に関するエピジェネティクス的なアプローチの進化が期待されます。