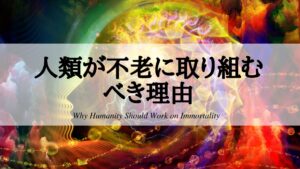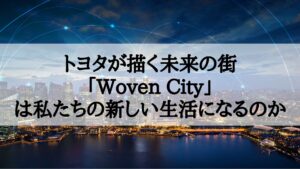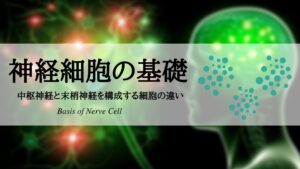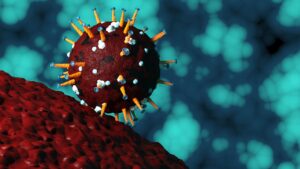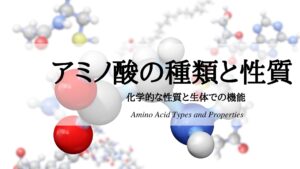バイミオメティクスは生物を真似した技術のことです。アメリカの神経生理学者のオットー・シュミットが1950年代に提唱しました。 人間は色々なものを発明してきましたが、生物は 何万年にもわたる進化の過程で、とても人間が考えもしない特殊な機能を獲得していることが分かってきました。それを模倣して人間の役に立てようというのがバイミオメティクスです。
バイオミメティクスの事例

バイミオメティクスの事例をご紹介しましょう。
ハスの葉の構造を模倣したヨーグルト容器の蓋
従来のヨーグルトの小さな容器の蓋はその内側にヨーグルトがついてしまいます。 これをなめるのはお行儀が悪いです。ところがビヒダスヨーグルトの技術者たちはヨーグルトはひっつかない蓋を開発しました。その時参考にしたのはハスの葉です。ハスの葉は雨が降っても濡れないで雨は弾かれてしまいます。それはハスの葉の表面にナノメートル単位の凹凸があってそこに空気が入り、 雨水が葉っぱにつかないのです。それを模倣してTOYAL LOTUSというものを作り、蓋の内側に貼り付けたのです。だからビヒダスヨーグルトの蓋にはヨーグルトがつきにくいのです。
https://bifidus.jp/products/cover.html
線虫で癌の診断
廣津氏は東京大学の博士課程で線虫の 嗅覚について研究をしました。 そこで 線虫はガンの匂いがわかることを 見つけました。多数の線虫を入れたシャーレに人の尿を一滴落とすと、その人がガンにかかっておれば 、線虫は尿に集まってきます。ガンにかかっていなければ、線虫は 尿に寄ってきません。 15種類のガンについて線虫は同じ行動をします。しかも 初期段階のステージ1のガンでも見つけてくれます。その精度は9割です。線虫は高等動物ではないので非常に安いです。 注射器で採血をするというような手間がなく簡単です。

2023年9月現在、線虫での癌診断には疑義があるのでは、と一部報道されています。
https://newspicks.com/news/8907416/body/
それに対して線虫での癌診断キット「N-NOSE®」開発元である株式会社HIROTSUバイオサイエンスは同年9/11付けで自社コーポレートサイト内にある種の声明を出しています。
https://hbio.jp/news/2023/09/0911/
実際に線虫での癌診断にどの程度妥当性があるのかは今後の調査・研究でさらに明らかになるところだと思います。
サメの体表を模倣した競泳用水着
競泳用水着メーカーのspeedoの研究開発機関「Aqualab®(アクアラボ)」が開発した「Fastskin」はサメが何故速く泳げるのかを研究して、それを模倣しました。サメは体の部位でうろこの密度が異なっています。肌の表面に凹凸があることで水の抵抗を減らしています。こうしたサメの肌の特徴を模倣することで水の抵抗を低減した水着を開発しました。
https://www.goldwin.co.jp/speedo/lzr_pure/
蚊の針の構造を模倣した痛くない注射針
関西大学システム理工学部の青柳誠司教授が蚊を模倣して、細くて痛みの少ない注射針「マイクロニードル」を開発しました。細いと刺された人の神経の痛点に当たらないので痛くないのです。蚊に刺された後で痒くなるので、刺されたことに気づきます。痒いのは蚊が吸った血が固まらないようにあらかじめ人に注射した唾液の一部が人に残るためです。
将来展望 -バイオミメティクスを活かして人類の夢を叶える-

カーボンナノチューブによる宇宙エレベーターの実現
宇宙エレベーターというアイデアは「宇宙旅行の父」ともいうべきロシアのコンスタンチン・ツィオルコフスキーが、今から100年以上前に考えたものです。 1991年 の カーボンナノチューブの開発が成功しこの人類の夢が実現に一歩近づきました。大林組がそのホームページに構想を発表しています。その時に構造材として用いられるのが原子レベルのハネ カム構造が有望とされています。これは重さはアルミニウムの半分、強さは鉄の100倍、硬さはダイヤモンドの2倍もあります。これも蜂の巣の模倣の一つです。
https://www.obayashi.co.jp/kikan_obayashi/detail/kikan_53_idea.html
電気ウナギを模倣した発電システムの開発
アマゾン川に住む 電気ウナギは電圧が600v から 800V、電流は1アンペアの発電をします。しかしその発電時間は1000分の1秒程度です。 この電気ショックで他の魚を気絶させて捕食します。あるいは自分より大きな動物が来た時に 、この電気ショックで相手を驚かせて、その隙に逃げます。もしこの発電システムが解明されて、人工的に模倣することができ、コスト的にもペイするものであれば、それを有効利用することが考えられます。
人工光合成による人類の食料危機の克服
植物は葉緑素で光合成を行い太陽光のエネルギーをでんぷん、タンパク質や脂肪に変えます。 もしこの光合成プロセスを人工的に模倣できれば、畑を使わない食料生産が可能になります。 天候に左右されない計画的食料生産ができます。現在の植物工場と比較してこの方が生産性が高ければ、人類の食糧危機は克服できる可能性があります。
あとがき
他社の技術を無断で模倣すると、訴えられて賠償金を 取られます。技術供与を受けるとライセンスフィーを支払わなければなりません。しかし生物は模倣されても賠償金を請求しません。バイミオメティクスを研究しましょう。