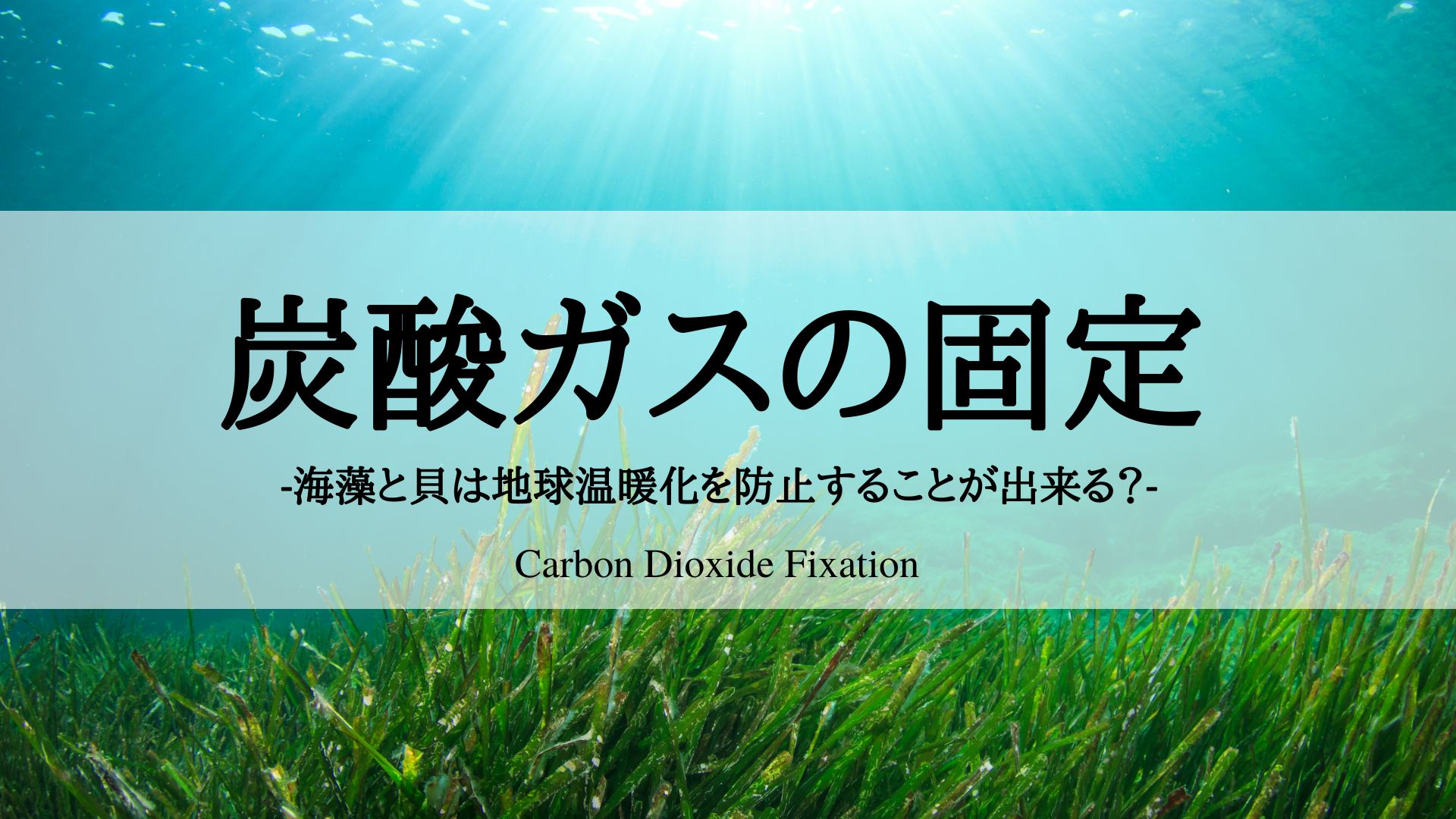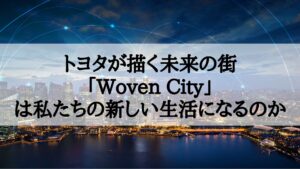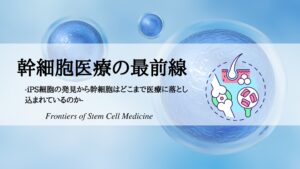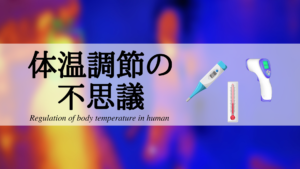地球温暖化が進み、南極と北極の氷が解け海面の上昇が顕著です。2100年には82cmも上昇すると予測されています。そうなると島嶼国やヴェネチア、アムステルダム、ニューヨーク、ロンドン、東京も水没します。
地球温暖化による海面上昇を抑えるために、海藻と貝による炭酸ガスの固定が注目されています。本記事では海藻と貝によって炭酸ガスを固定し、地球温暖化を防止し、海面上昇を抑えるという話を紹介いたします。
炭酸ガスによる悪影響と炭酸ガスを固定する意味

海藻と貝による大気中の炭酸ガスを固定する目的は、地球温暖化の防止です。産業革命以来、石炭・石油・天然ガスの使用は増えました。 そのため待機中の炭酸ガス濃度は増えました。 炭酸ガス、水田や牛のゲップから出るメタン、エアコンなどに使われるフロンなどが地球温暖化の大きな原因になっていると言われています。
そのため 山に木を植えて炭酸ガスを固定することも有効です。しかしそれには土地が必要です。しかも樹木の成熟には数十年の長い年月が必要です。そこで海を利用して炭酸ガスを固定しようというのが、海藻と貝による 大気中の炭酸ガスの固定です。草木などの陸上植物による光合成を「グリーンカーボン」といい、海藻、海草やマングローブによる光合成は「ブルーカーボン」と呼ばれます。
炭酸ガスを固定する原理

海藻は海水に含まれる炭酸ガスを太陽光で炭酸同化作用を起こし植物を成長させます。海には多くの海藻が茂っています。 貝の中には海藻を食べるものがいます。貝は貝殻を作ります。 貝殻はカルシウム, 炭素及び酸素からできています(CaCO3)。このCO3は海水中の炭酸ガスから作られます。
貝は海藻を食べ尽くすと海底に沈んでしまいます。海の底が魚の骨や貝殻で埋め尽くされていることはありませんので、貝殻はいずれ 海水に溶けると思われます。貝殻は長期間にわたり炭素を固定してくれます。そこで大量に海藻を栽培し大量の貝に海藻を食べさせて大気中の炭酸ガスを減らし、地球温暖化を防止しようというのが本記事のテーマとなっているアイディアです。海水中の炭酸ガスの濃度は減ると大気中の炭酸ガスが海に溶け込むのです。
炭酸ガスを固定する海藻たち
日本の海岸には多くの海藻が繁茂しています。コンブ、ワカメ、ノリ、ヒジキ 、モズクなどは食用にもなります。海藻ではない海草の「アマモ」も広く分布し、 ウニやヒトデの餌になっています。ホンダワラ(カルガッサム)は世界中に繁茂しています。それが枯れると漂流してアメリカとアフリカの 間の海に大量に蓄積します。北緯25度 – 35度・西経40度 – 70度に集まり、長さ3,200km・幅1,100kmの広範囲に帯状に浮かんでいます。ここを「カルガッソ海」といいます。このホンダワラは腐敗し、炭酸ガスを排出します。このプロセスは陸上の樹木や草でも同じです。ホンダワラを 貝に食べさせれば 大量の炭酸ガスが固定されます。アメリカのアラスカ半島からカリフォルニア湾や、南米の高緯度にジャイアントケルプという長さ50mにもなる巨大な昆布が繁殖しています。これは成長も早いので 全世界の海岸に植えれば 炭酸ガスを固定するのに都合がいいと思います。
炭酸ガスを固定する貝たち
日本の海岸には多くの貝が住んでいます。アサリ、シジミ、カキ、アワビ、 ホタテ貝、サザエ、ハマグリなどは食用になり養殖もされています。アコヤ貝は真珠を作るのに利用されています。 川や池にはタニシもいます。大量の炭酸ガスを固定するためには貝殻が大きくて成長の早く、しかも 繁殖力旺盛な貝が適しています。しかも海藻の表面に付着する能力が必要です。 多くの二枚貝はこの海藻に付着できない点で失格です。 炭酸ガスを最もたくさん固定できる海藻とそれに相性の良い貝の組み合わせが重要です。
あとがき
もしこの海藻と貝による炭酸ガスの固定が成功すれば、日本は周りの海 を利用して大量の炭酸ガスを固定することができます。 そしてこの権利をアメリカや中国のように、炭酸ガスの排出量が多い国に対して排出権取引のように売買をすることができる可能性があります。これはひょっとすると日本の一大産業になる可能性がある、そんなことに思いを馳せながら本記事の結びとさせていただきます。