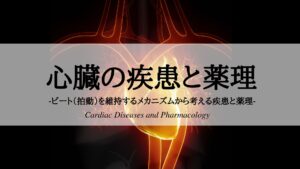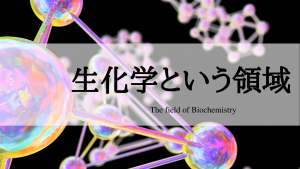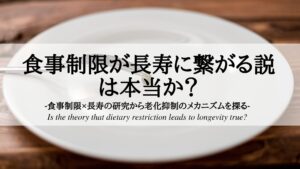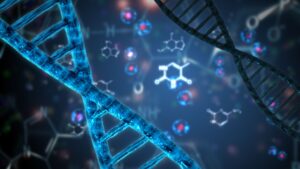日常生活や体調の変化によって引き起こされる痛みを和らげる鎮痛剤、いわゆる痛み止めは「どのように効果を発揮するのか」「市販の痛み止めの選び方はどうすればいいのか」気になりますよね。痛み止めには多くの選択肢があり、種類によって解熱作用や鎮痛作用、消炎作用などがあります。
本記事では、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やアセトアミノフェンなどのドラッグストアや薬局で手に入る非オピオイド鎮痛薬の薬理に焦点を当てて解説します。用途や選択方法にも触れますので、痛みを効果的に軽減できる方法を見つけたい方や痛み止めの違いを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
非オピオイド鎮痛薬の作用と仕組み
市販薬でも手に入る痛み止めには、ロキソプロフェンやイブプロフェンなどのNSAIDsやアセトアミノフェンがあります。NSAIDsやアセトアミノフェンは非オピオイド鎮痛薬に分類され、鎮痛の際に第一選択薬として広く使用される薬剤です。
非オピオイド鎮痛薬の作用は鎮痛作用と解熱作用があり、NSAIDsは末梢へ働きかけ、アセトアミノフェンは視床と大脳皮質へ働きかけることにより鎮痛作用を示します。また、NSAIDsとアセトアミノフェンの解熱効果は視床下部へ作用することで効果を発揮します。
NSAIDsとアセトアミノフェンについて具体的にみていきましょう。
NSAIDsとは?
NSAIDsとは、Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs(非ステロイド性抗炎症薬)の略称であり、解熱効果や鎮痛効果だけでなく抗炎症作用も有する非オピオイド鎮痛薬です。
NSAIDsはアラキドン酸カスケードのシクロオキシゲナーゼ(COX)を阻害することで、起炎物質や発痛増強物質となるプロスタグランジンの産生を抑え、解熱や鎮痛、抗炎症作用を発揮します。
しかし、胃や十二指腸を保護するプロスタグランジンの働きも抑制するため、胃腸障害の副作用を引き起こしやすいかもしれません。また、NSAIDsはアスピリン喘息の症状を誘発するため、喘息の診断をされた方には注意が必要です。
アセトアミノフェンとは?
アセトアミノフェンは解熱効果と鎮痛効果をもつ非オピオイド鎮痛薬です。解熱鎮痛剤として古くから使用されており、体温調節中枢や中枢神経に作用して解熱・鎮痛効果を発揮すると考えられています。しかし、詳細な作用機序は未だ解明されていません。
脳の視床下部の体温調節中枢に作用して皮膚血管を拡張することで体外へ熱を逃がし、解熱作用を発揮します。また、脳の中枢神経に作用して、視床と大脳皮質の痛覚閾値を上昇させることで鎮痛作用を示すと推測されています。
アセトアミノフェンは、プロスタグランジンの産生をほとんど抑制しないため抗炎症作用は非常に弱く、小児や妊娠中や授乳中の方に使用できます。多くの一般用医薬品にも含まれており、過剰摂取すると肝障害を生じるため注意が必要です。
NSAIDsとアセトアミノフェンの違い
NSAIDsとアセトアミノフェンは非オピオイド鎮痛薬に分類されますが、作用機序や副作用など下記の表のような違いがあります。
| NSAIDs | アセトアミノフェン | |
| 作用 | 解熱・鎮痛・抗炎症 | 解熱・鎮痛 |
| 作用点 | 末梢 | 脳の中枢 |
| 作用機序 | シクロオキシゲナーゼを阻害することでプロスタグランジンの産生を抑制する | 鎮痛効果:視床と大脳皮質の痛覚閾値を上昇させる |
| 解熱効果:視床下部の体温調節中枢に作用する | ||
| 主な副作用 | 胃腸障害、腎障害 | 過量投与による肝障害 |
| 小児の使用 | ほとんど使用しない | 乳幼児から使用できる |
| 妊婦に対する安全性 | 妊娠後期には禁忌 治療上の有益性が危険性を上回る場合にのみ投与可 | 最も安全とされる |
アセトアミノフェンは小児や妊婦、授乳婦にも安全に使用でき、解熱鎮痛剤の第一選択薬として広く利用される薬剤です。一方、NSAIDsは胃腸障害の副作用を起こしやすいものの、抗炎症作用がありアセトアミノフェンと比較すると強い鎮痛効果を発揮します。
痛み止めの用途と選び方
痛み止めには、鎮痛効果のほかに抗炎症作用や解熱作用があります。痛みの原因を直接取り除くことを視野に入れて、痛みの種類や状況に応じた鎮痛剤を選択することが重要です。痛み止めの選び方には以下のポイントがあります。
・小児や妊婦にはアセトアミノフェンを使用する
・ぜんそくの既往がある方は薬剤師に相談する
・痛みの種類によって鎮痛剤を選択する
上記のポイントを押さえて痛みに対処しましょう。それぞれのポイントを具体的に説明します。
小児や妊婦にはアセトアミノフェンを使用する
小児や妊婦は服用する薬剤に注意が必要なため、痛み止めを服用する場合はアセトアミノフェンを使用しましょう。一般用医薬品には複数の有効成分が配合されている薬もあるので、薬剤師に相談することをおすすめします。
一部のNSAIDsでは、小児のインフルエンザや水痘などの解熱に使用する場合にインフルエンザ脳症のリスクが高まるかもしれません。解熱効果を主目的とする場合にはアセトアミノフェンが適しています。
喘息の既往がある方は薬剤師に相談する
一部のNSAIDsを服用すると、喘息や鼻症状が強く出現するアスピリン喘息を引き起こす恐れがあるため、喘息の既往がある方は薬剤師に相談してください。
喘息発作を繰り返していたり喘息症状のコントロールがついていない場合は、重篤な発作につながりやすいので注意が必要です。
喘息の既往があるすべての方がアスピリン喘息を引き起こすわけではありません。しかし、過去に薬でアレルギーや喘息が起きた方は、アスピリン喘息を引き起こすリスクが高まる恐れがあるため薬剤師に相談しましょう。
痛みの種類によって薬を選択する
痛み止めにはそれぞれ特徴があり、痛みの種類によって自分自身の体質や病態に見合った薬を選択しましょう。
頭痛や筋肉痛といった軽度の痛みにはアセトアミノフェンが使われることが多く、関節炎や歯痛などの炎症に伴う激しい痛みにはNSAIDsが選ばれることが多いです。
一般用医薬品では、胃粘膜保護の働きのある成分や鎮痛効果を高める成分などが配合されている場合があるので、解熱鎮痛成分以外の配合成分にも目を向けることをおすすめします。痛みが長期的に持続する場合や自分自身での薬の選択が難しい場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。
まとめ
本記事では、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やアセトアミノフェンといった非オピオイド鎮痛薬の薬理や用途、選択方法などを解説しました。
痛み止めの薬には鎮痛作用や解熱作用、抗炎症作用などがあり、代表的な薬剤にNSAIDsとアセトアミノフェンがあります。NSAIDsは末梢に作用して鎮痛効果や消炎効果を発揮し、アセトアミノフェンは中枢に作用して解熱・鎮痛作用を示す薬剤です。
それぞれの薬の用途や選び方には注意が必要であるため、痛みの種類に応じて適切な薬剤を選び、適切な用量や投与期間を守りましょう。副作用や禁忌などにも注意が必要ですので、本記事を参考にしつつ、医師や薬剤師の指導を受けながら適切に使用してください。
参考書籍・サイト
・今日の治療方針
・薬が見える!
https://www.jsog.or.jp/modules/news_m/index.php?content_id=979
https://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/drugdic/article/556e7e5c83815011bdcf826c.html
https://www.jspc.gr.jp/igakusei/igakusei_keynsaids.html
https://tenroku-orthop.com/column/848/
https://health.eonet.jp/life/4104215.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00404.html