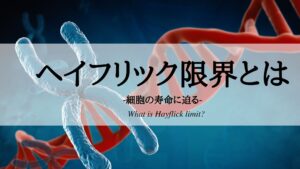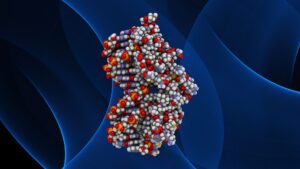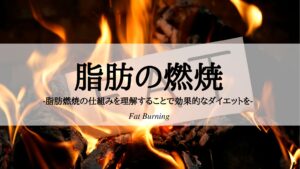そんなに動いていないのに、おなかは不思議とすいてくるという経験をされたことはありませんか?運動後におなかがすくのはわかるけれど、寝ているだけなのに朝起きたらもうおなかがすいていて、自然と何かを食べてしまう。なぜなのでしょうか?
本記事では、なぜ人間は食べなければならないのかについて、栄養学の視点から紐解いていきます。
日々人間(ヒト)の体に起こっていること
人間は、体を動かしながら日常生活を過ごしています。また、自分自身では体を動かしているつもりのない状態であっても、心臓は自然に血液を送り出し、肺では呼吸をしています。このように、意識的に運動していなくても、体の中では細胞や組織、器官が活動しています。
また、人間の体は約60兆個の細胞からできています。生命活動を維持していくために、古くなった細胞は新しい細胞に作り替えられます。1日で実に約1兆個近くの細胞が入れ替わっていると言われています。(※1)これだけの数の細胞が入れ替わり、生命活動を行うために不可欠なものが「栄養素」です。
人間をはじめとする動物は、植物と大きく異なる点があります。その1つに「栄養素の取得方法」が挙げられます。植物は光合成を行うことで、生きていくための「栄養素」を自らの体内で作り出すことができますが、動物は作り出すことができません。このことをそれぞれ、独立栄養と従属栄養と呼びます。従属栄養を行う動物は、体外から「栄養素」を摂取しなければなりません。そのために必要な手段が「食事」です。
食事から摂る「栄養素」

食事をすることで、体内に取り込まれた多様な「栄養素」は、体内での反応を経て、さらにさまざまな物質に形を変えます。体内での物質の化学反応を「代謝」と呼びます。人間をはじめとする全ての生物は、この「代謝」によって、「栄養素」を活用しながら生命を維持していくのです。
小学校の家庭科で習う「五大栄養素」とは、タンパク質、脂質、炭水化物、ミネラル、ビタミンを指します。これらの栄養素の代表的な働きは以下の3つです。
1)おもにエネルギーになるもの : 炭水化物、脂質
2)おもに体を作る元になるもの : タンパク質、ミネラル
3)おもに体の調子を整えるもの : ビタミン、ミネラル (※2)
それぞれの栄養素について、さらに詳しく見ていきましょう。
1) 炭水化物
炭水化物は糖分子が繋がってできており、その糖鎖の長さから糖質と食物繊維に分けられます。糖質は比較的糖鎖が短いもので、人間の消化器官で効率よく消化、吸収され、エネルギー効率のよい栄養素と言えます。糖が1つのものを単糖、2つ繋がったものを二糖といい、単糖と二糖のことを糖類と呼びます。
次に、食物繊維は糖鎖が長く連なっており、人間の消化器官ではなかなか消化されにくい物質です。消化されないということは、ほぼエネルギーにならず、役立たずないのではないかと思われるかもしれませんが、実は非常に重要な役割を担っています。食物繊維は「体の中の掃除屋」と呼ばれ、大腸の働きを良くします。食物繊維には、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維があり、水溶性食物繊維は文字通り水によく溶ける性質を持っています。これらは大腸に届くと、大腸内に住んでいる善玉菌のエサとなり、善玉菌が増えることで大腸内の環境が整います。一方、不溶性食物繊維は消化されず大腸に届き、大腸の中で水を含んで大きく膨らみます。その結果、大腸の運動(蠕動運動)を促進したり、便のかさを増したりすることで便秘を予防します。(※3) このように、炭水化物には直接的にエネルギーになるものだけでなく、人間の体内環境を整える役割を果たすものも含まれます。
2) 脂質
脂質は、1gあたり9kcalのエネルギーを算出します。このことから、脂質を摂りすぎると摂取カロリーオーバーとなり、太ってしまうことはみなさんもご存じかと思います。しかし、太りたくないからといって、脂質の摂取をゼロにすることは体にとって良くありません。脂質を構成している脂肪酸には、生体膜を構成する役割があります。生体膜とは、細胞膜や細胞内小器官の膜のことを指し、細胞が正常に存在するために必要です。脂肪酸は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けられます。肉類や乳製品等に多く含まれる飽和脂肪酸は、コレステロールと関わりが強いと言われますので、魚油やオリーブオイル等に含まれる不飽和脂肪酸を意識して、食事することが大切です。(※4)
3) タンパク質
筋肉も皮膚も髪も爪も、タンパク質が主成分です。タンパク質が足りないと、髪も皮膚もカサカサと荒れてきます。人間の体を作るタンパク質は、20種類のアミノ酸からなります。その20種類のうち9種類は、体内で合成することができず、食事から摂取しなければなりません。これら9種類のアミノ酸を「必須アミノ酸」と呼びます。人間の体を作るタンパク質の中にどのような割合でアミノ酸が含まれているかはすでにわかっており、それと比較することでタンパク質の「質」を評価することができます。これを「アミノ酸スコア」と呼びます。「アミノ酸スコア」は満点が100となり、卵や肉類のほとんどは100、精白米は81、小麦は42~48となっています。(※5)必須アミノ酸やアミノ酸スコアの観点から、食事で上手にタンパク質を摂取したいものです。
4) ミネラル
ミネラルとは、体を構成する主要な4元素(酸素、炭素、水素、窒素)以外のものの総称で、無機質とも言います。(※6)例えばカルシウムは骨や歯を作る元となります。骨粗鬆症という言葉を聞かれたこともあるかと思います。これはカルシウムやマグネシウムの不足等から骨の代謝バランスが崩れ、骨がもろくなる状態のことを指します。また、鉄はご存じのようにヘモグロビンの中心に存在し、酸素結合に大きな役割を担っています。体内の鉄が欠乏すると、貧血を発症します。ミネラルも体内で合成はできません。
5) ビタミン
「体の調子を整える」と言えば、ビタミンを真っ先に思い浮かべられるのではないでしょうか?タンパク質や炭水化物等に比べ微量ですが、体内の機能を調整するのに不可欠であり、かつ体内でほとんど合成できない有機物がビタミンです。ビタミンは、水溶性ビタミンと不溶性ビタミンに分かれます。ビタミンB群、ナイアシン、葉酸等は水溶性ビタミンと呼ばれ、これらは血液などの体液に溶け込んで体内を移動します。余分なものは尿として排出されるため、過剰摂取にはなりません。ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE等は不溶性ビタミンで、主に脂肪組織や肝臓に貯蔵されます。摂りすぎると過剰症を起こすこともあります。(※7)
栄養不足になるとどうなる?

生命活動を維持するため、食事からいろいろな栄養素を摂取する必要があることは、おわかりいただけたかと思います。では、栄養不足になるとどうなるのでしょうか?
例えば、体を作る栄養素であるタンパク質が不足した場合、それが子供であれば発育不良になります。大人であれば体重の減少はもちろん、組織や臓器の機能が低下します。タンパク質は抗体を作ります。血中タンパク濃度が低いと、予防接種を受けても抗体を作り出すことができないと言われる等、免疫力の低下も招きます。また、タンパク質とエネルギーが足りない栄養状態のことをPEM(Protein-energy malnutrition)と呼びます。PEMは、発展途上国において深刻な問題となっています。
また、ビタミンが足りない場合はどうなるでしょう?目の働きを助けるビタミンAが不足した場合は、暗くなると見えなくなる「夜盲症」という症状が起こります。骨形成に必要なビタミンDが不足した場合は、小児の「くる病」や成人の「骨軟化症」「骨粗鬆症」も発症します。ビタミンB群はエネルギー代謝に関わるため、ビタミンB1不足では「脚気」や「疲労症状」、ビタミンB2では「皮膚粘膜疾患」などを引き起こします。(※8)
このように、食事から摂取する栄養素が不足すると、多くの病気や重篤な症状を発症することとなります。
まとめ
人間が生きていくためには、たとえ意識的な運動をしていなくとも「エネルギー」が必要であり、また活動的に生活する上でも「栄養素」が必要です。人間をはじめとする動物は、自らの体内で多くの栄養素を作る出すことができないため、生きていくためには必ず「栄養素」を体外から摂取する必要があり、その手段が「食事」です。
太りたくないから糖質や脂質を制限をする方もいるかと思います。逆に、運動するためにタンパク質を摂取し過ぎるような方もいるかと思います。栄養素を体内で合成できない私達は、食事についてより深く意識し、必要な「栄養素」を適切に摂取するよう心がけましょう。
(※1) 栄養学の基本がわかる事典 p.11
(※2) 文部科学省 「食べ物の栄養」
(※3) 厚生労働省 e-ヘルスネット 「食物繊維の必要性と健康」
(※4) 栄養学の基本がわかる事典 p.86
(※5) 栄養学の基本がわかる事典 p.96
(※6) 厚生労働省 e-ヘルスネット 「ミネラル」
(※7) 栄養学の基本がわかる事典 p.50
(※8) 栄養学の基本がわかる事典 p.12