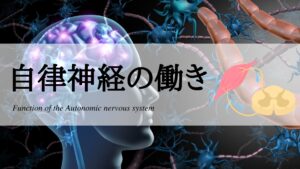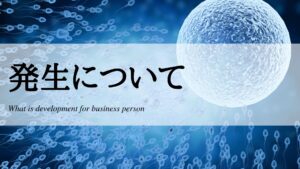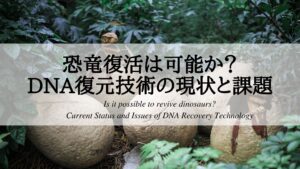ヒトだけではなく、生物は生命活動を維持するために様々な栄養を体外から摂取する必要があります。しかしながら、生物種、または個体によって一部のものしか接食しない偏食というスタイルが知られており、偏食でも通常の食事と同じレベルで生活を維持できることが明らかになっています。本記事では、ヒト以外の種も取り扱い偏食を行う生物をご紹介し、なぜ偏食でも変わらず生命活動を維持できるのか、その謎に迫ります。

偏食する動物の例

- カイコ:桑の葉しか食べません。桑の葉には、カイコの成長に必要なタンパク質や繊維質が豊富に含まれています。
- コアラ:ユーカリの葉しか食べません。ユーカリの葉には、コアラが必要な栄養素がすべて含まれています。ただし、ユーカリの葉にはシドニーサンの葉など、コアラにとって毒性のある種類もあります。
- パンダ:竹しか食べません。竹は、タンパク質や繊維質が豊富に含まれているにもかかわらず、消化率が低いため、パンダは大量の竹を食べなければなりません。
- シロアリ:木材しか食べません。シロアリは、木材を分解する酵素を体内に持っているため、木材を消化することができます。
- ナナフシ:葉っぱしか食べません。ナナフシは、葉っぱを消化するための消化器官が発達しています。
- ヤドカリ:海藻しか食べません。ヤドカリは、海藻を消化するための消化器官が発達しています。
なぜ偏食しても大丈夫なのでしょうか
ヒトが栄養失調にならないためには、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂取することが重要です。しかし、偏食性草食動物は、同じものばかり食べていても栄養失調にならないことが知られています。
その理由は、以下の3つが挙げられます。
消化器官の構造が異なる
ヒトの消化器官は、肉や魚を消化しやすいように設計されています。一方、偏食性草食動物の消化器官は、植物を消化しやすいように設計されています。そのため、偏食性草食動物は、同じものを繰り返し食べても、必要な栄養を効率的に吸収することができます。
栄養が豊富な植物を選んでいる
偏食性草食動物は、栄養が豊富な植物を選ぶように進化しています。例えば、シカは、タンパク質が豊富な若葉や芽を食べます。また、ウシは、繊維質が豊富な草を食べます。このように、偏食性草食動物は、必要な栄養を効率的に摂取できる植物を選んで食べることで、栄養失調を防いでいます。
体内のバクテリアが助けてくれる
偏食性草食動物の体内には、植物の栄養を分解するバクテリアが存在します。このバクテリアは、植物に含まれるセルロースやリグニンなどの難消化物質を分解して、ヒトでも吸収できる栄養素に変換してくれます。そのため、偏食性草食動物は、同じものを繰り返し食べても、必要な栄養を十分に摂取することができます。
もちろん、偏食性草食動物も、栄養失調になる場合があります。例えば、食べられる植物が少なくなると、栄養失調になる可能性があります。また、病気や老化によって消化器官やバクテリアの働きが低下すると、栄養失調になる可能性があります。
しかし、一般的に、偏食性草食動物は、同じものを繰り返し食べても栄養失調にならないように進化しています。
ヒトのベジタリアンの食事

ヒトにも肉や魚を一切食さず、野菜しか食べない「ベジタリアン」が知られています。
「ベジタリアン」とは、肉や魚を食べない人のことを指します。ベジタリアンには、植物性食品のみ食べる「ビーガン」、乳製品や卵を食べる「ラクト・オボ・ベジタリアン」など、が存在することが知られています。
個人の食生活の嗜好は他者に干渉されるべきではないところですが、栄養学的な観点に立つとやはり本来はバランスがよい食事が望まれます。
もし、ベジタリアンが1種類の植物だけしか食べられない場合には、栄養バランスを考えると、他の植物性食品を摂取することが選択肢として考えられます。例えば、豆類、穀物、野菜、果物など、様々な種類の植物性食品をバランスよく摂取することで、必要な栄養素を補うことができるでしょう。
まとめ
さて、いかがでしたでしょうか。
ヒト以外の動物には偏食性草食動物と呼ばれるようなある決まった草類を食べることで生命機能維持が可能な動物もいます。しかしながらヒトは雑食ですので、もし野菜中心の生活を行う場合は不足分の栄養素を何らかの手段で補うことを頭に入れておく必要があるといえるでしょう。