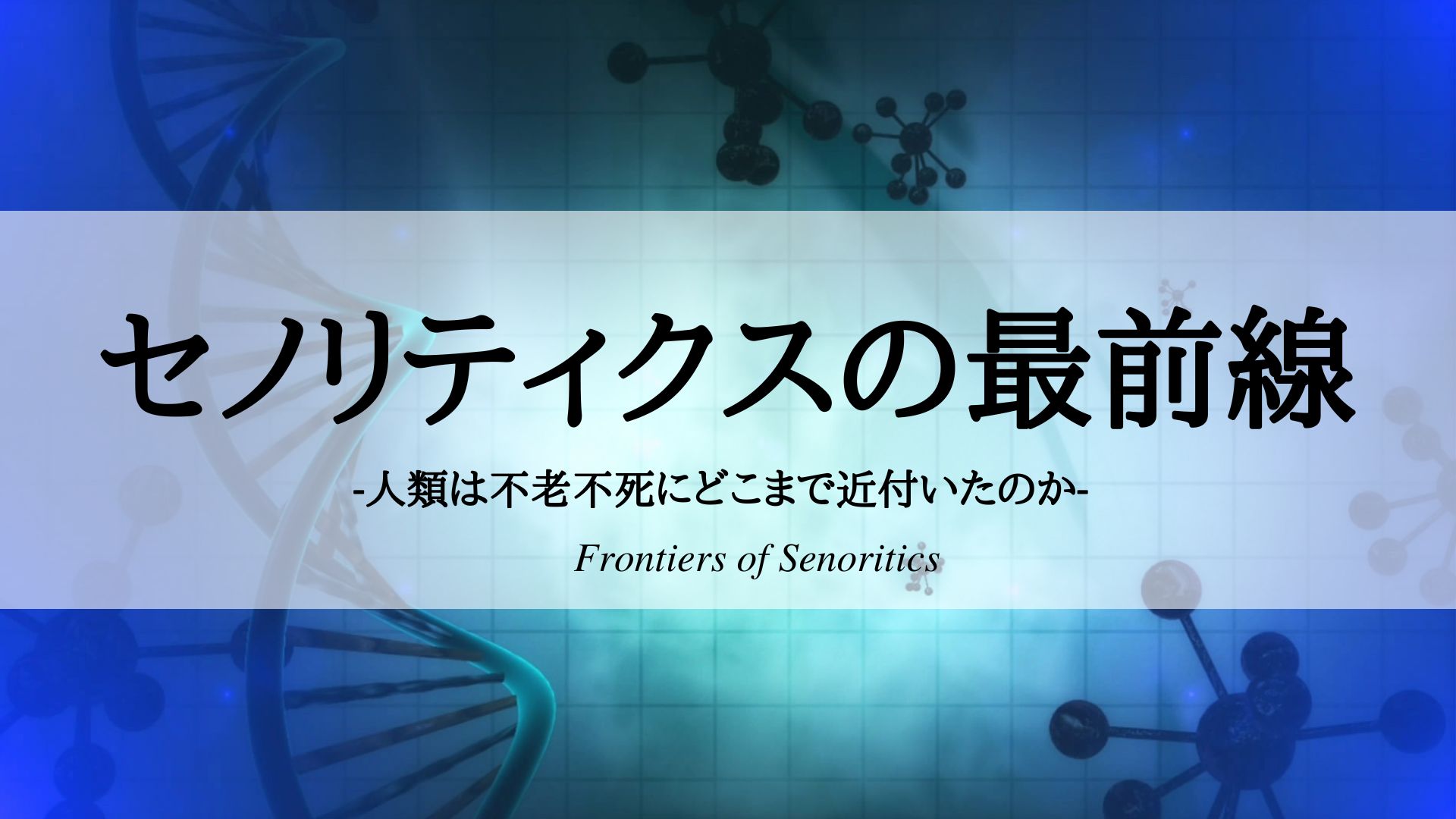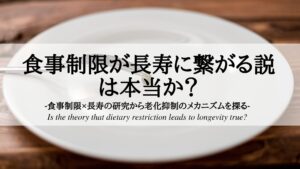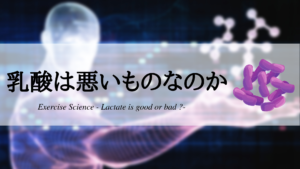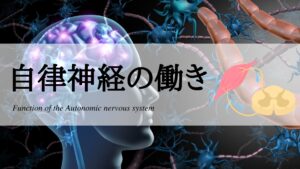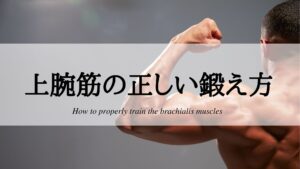人は皆老いて死ぬ。そんな常識がいま、科学で覆されようとしています。近年の老化医生物学分野での研究によって、老化は制御、治療できるものであるという認識が広がっています。中でも注目されているのがセノリティクス薬(老化細胞除去薬)です。この記事では、老化研究の最前線をオートファジーとグルタミナーゼ1(GLS1)阻害薬の観点から紹介しています。
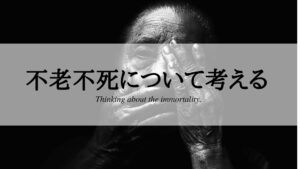

セノリティクスとは
セノリティクスという単語自体は、senescence(老化)と-lytics(対抗)を合わせたもので、老化細胞を除去する薬剤を指します。では老化細胞とは何なのか、なぜ老化細胞を除去することが老化治療に繋がるのでしょうか?
私たちの体では常に新陳代謝が行われています。新しい細胞が生まれ、古い細胞が死ぬことは成長と生命維持に欠かせませんが、細胞も無限に増殖できるわけではありません。染色体にダメージを負ったり、ヘイフリック限界という分裂回数の限界を迎えるとぴたりと増殖が止まります。このように増殖が止まった細胞を「老化細胞」と呼びます。これは、異常な細胞が増殖してしまうことを未然に防ぐ大切な仕組みの一つです。しかしその一方で、老化細胞は炎症性タンパク質を分泌する形質(SASP)を持ち、慢性的な炎症が加齢性疾患を誘発することが分かっています。そのため、SASP因子を阻害する薬剤や、老化細胞自体を除去するセノリティクス薬に期待が集まっているのです。例としてオートファジーとGLS1阻害薬について詳しく見ていきましょう。
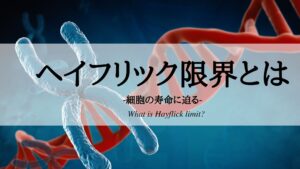
オートファジーから考える老化治療
オートファジーとはタンパク質分解経路の一つで、隔離した細胞内成分をリソソーム(酸性のオルガネラ)で分解する機能です。細胞内での新陳代謝を担っており、不要なタンパク質を分解することでアミノ酸をリサイクルしたり、老廃物の蓄積などを防止したりしています。老化細胞の特徴の一つとして、オートファジー機能の低下が挙げられます。その結果、異常なタンパク質が蓄積して神経変性を起こしたり、炎症物質の分泌を促進するタンパク質が分解されなかったりすることが分かっています。つまり、オートファジーを誘導することによって、老化細胞の負の特性を制御することが期待できるのです。オートファジーを誘導する薬剤として、抗腫瘍薬ラパマイシンが有望視されています。また、薬剤に頼らなくとも、食事制限でもオートファジーは誘導されます。ある臨床試験[1] ではオートファジーによる食事制限の寿命への影響は見られませんでしたが、健康状態の改善が認められています。
[1]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4841173
GLS1阻害薬から実現するセノリティクス
オートファジーは老化細胞の負の特性を制御しますが、セノリティクス薬は老化細胞自体をアポトーシスによって除去します。アポトーシスとはプログラムされた細胞死で、個体をより良い状態に保つために引き起こされます。これまでは老化細胞のアポトーシス抑制機構を解除させて死滅させるセノリティクス薬が主流でしたが、副作用が強いこと、アポトーシスという極めて厳密に制御されるべき機構に働きかけていることが課題でした。そこで登場したのがグルタミン代謝酵素GLS1阻害薬です。2021年、東京大学の研究チームは、マウスにGLS1阻害薬を投与することで老化細胞を除去し、加齢現象や老年病の発症を改善できることを発表しました[1] [2] 。老化細胞ではリソソームの膜に損傷が生じて細胞内pHが酸性になってしまうため、グルタミンの代謝で生じるアンモニアによって中和、恒常性を維持していることが分かったのです。GLS1阻害薬を投与することで老化細胞は細胞内pHを中和できず、アポトーシスが引き起こされる仕組みです。老化細胞の代謝に焦点を当てることで、これまでのセノリティクス薬と比べてより安全に、様々な組織由来の老化細胞を効果的に除去できると期待されています。
[1]https://www.amed.go.jp/news/release_20210115-01.html
[2]https://www.funakoshi.co.jp/contents/69947
現在、GLS1阻害薬はアメリカでがん治療薬として臨床試験が実施されています。がん治療薬としての有効性、安全性が認められれば、老化治療薬として転用されることも可能になるかもしれません。まるで不老不死の秘薬のような薬剤ですが、GLS1もあくまで筋力を維持したり、生活習慣病を抑制したりと、健康寿命を伸ばす「不老」効果が期待されるだけで、最大寿命を伸ばすことはできません。しかしながら、人生120年時代と言われる時代、健康寿命を伸ばすことは人生の質を高めるために欠かせないものであることは間違いないでしょう。
おわりに
私たちはいま、老化を治療する時代に突入しています。不死にはまだ遠いようですが、オートファジーやGLS1阻害薬などで、不老には確実に近づいています。セノリティクスによって最期まで元気に過ごせるピンピンコロリが実現するのもそう遠くない未来かもしれません。