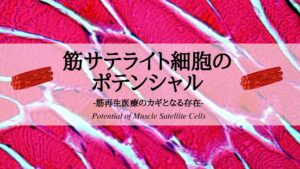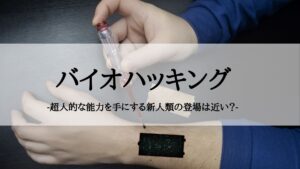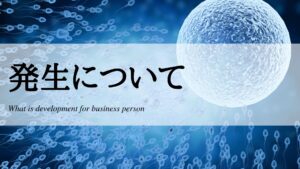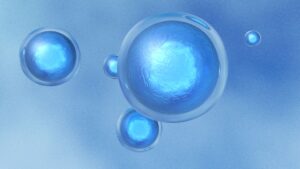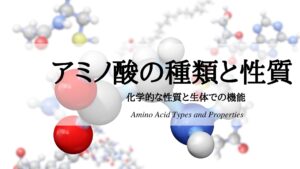私たちの脳や神経系は、数十億の神経細胞(ニューロン)から構成されており、これらの細胞間で情報を伝達するために「神経伝達物質」が重要な役割を果たしています。本記事では、神経伝達物質の発見とその歴史、そして最新の研究動向について解説します。
神経伝達物質の発見
オットー・レーヴィの実験
神経伝達物質の存在が初めて実証されたのは、1921年、オーストリアの薬理学者オットー・レーヴィによる実験でした。彼はカエルの心臓を用いた実験で、迷走神経を刺激すると心拍が遅くなること、そしてその刺激後の液体を別の心臓に適用すると同様に心拍が遅くなることを発見しました。このことから、神経刺激によって化学物質が放出され、それが他の細胞に影響を及ぼすことが示されました。この未知の物質は後にアセチルコリンと同定され、レーヴィは1936年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。 Japan Sports Business Management Group+2ウィキペディア+2おとなの科学+2
アセチルコリンの同定
アセチルコリンは、神経伝達物質として最初に同定された化合物であり、その発見は神経科学の発展に大きく寄与しました。この発見により、神経系における情報伝達が化学的な物質を介して行われることが明らかになりました。 Japan Sports Business Management Group+1ウィキペディア+1
神経伝達物質の多様性と分類
神経伝達物質は、その化学構造や機能により以下のように分類されます。
アミノ酸系
グルタミン酸やガンマアミノ酪酸(GABA)など、アミノ酸を基盤とする神経伝達物質です。これらは中枢神経系で主要な興奮性および抑制性の役割を果たします。NCNP+1科学技術振興機構+1
モノアミン系
ドーパミン、セロトニン、ノルアドレナリンなど、アミン基を持つ神経伝達物質です。これらは感情や覚醒、注意などの調節に関与しています。理化学研究所+1科学技術振興機構+1
ペプチド系
サブスタンスPやエンケファリンなど、短いアミノ酸鎖からなる神経伝達物質です。痛みの伝達や鎮痛作用など、多様な生理機能を持ちます。
最新の研究動向
ドーパミンとアミロイドβの分解機構
2024年、理化学研究所の研究チームは、ドーパミンがアミロイドβ(Aβ)ペプチドの分解酵素であるネプリライシンを制御していることを発見しました。これは、アルツハイマー病の新たな治療法開発につながる可能性があります。 理化学研究所
神経伝達物質の「見える化」技術
2021年、科学技術振興機構(JST)の研究グループは、ドーパミンを標識する新しい手法を開発し、脳内でのドーパミンの動きを可視化することに成功しました。これにより、神経伝達物質の動態解析が進み、脳の健康と疾患の理解が深まることが期待されています。 科学技術振興機構+1科学技術振興機構+1
シナプス外での神経伝達
2024年、ソーク生物学研究所の研究者らは、神経細胞がシナプス外でも神経伝達物質を放出できることを発見しました。この「異所性神経伝達」は、従来の神経コミュニケーションの概念を覆すものであり、神経系の新たな理解につながる可能性があります。 ウィキペディア+4サルク研究所+4理化学研究所+4
硫化水素と神経伝達物質の関係
2023年、国立精神・神経医療研究センターの研究グループは、硫化水素とポリサルファイドが主要な神経伝達物質であるGABAやグルタミン酸の放出を促進することを発見しました。これにより、記憶促進や統合失調症様行動の抑制が示され、新たな治療法の開発が期待されています。 NCNP
おわりに
神経伝達物質の発見から約100年が経過し、その多様性や機能、そして新たな役割が次々と明らかになっています。最新の研究は、神経伝達物質が私たちの脳と行動にどのように影響を与えるかをさらに深く理解する手がかりを提供しています。今後も神経伝達物質に関する研究が進むことで、神経疾患の根本的治療に寄与していくことが期待されています。