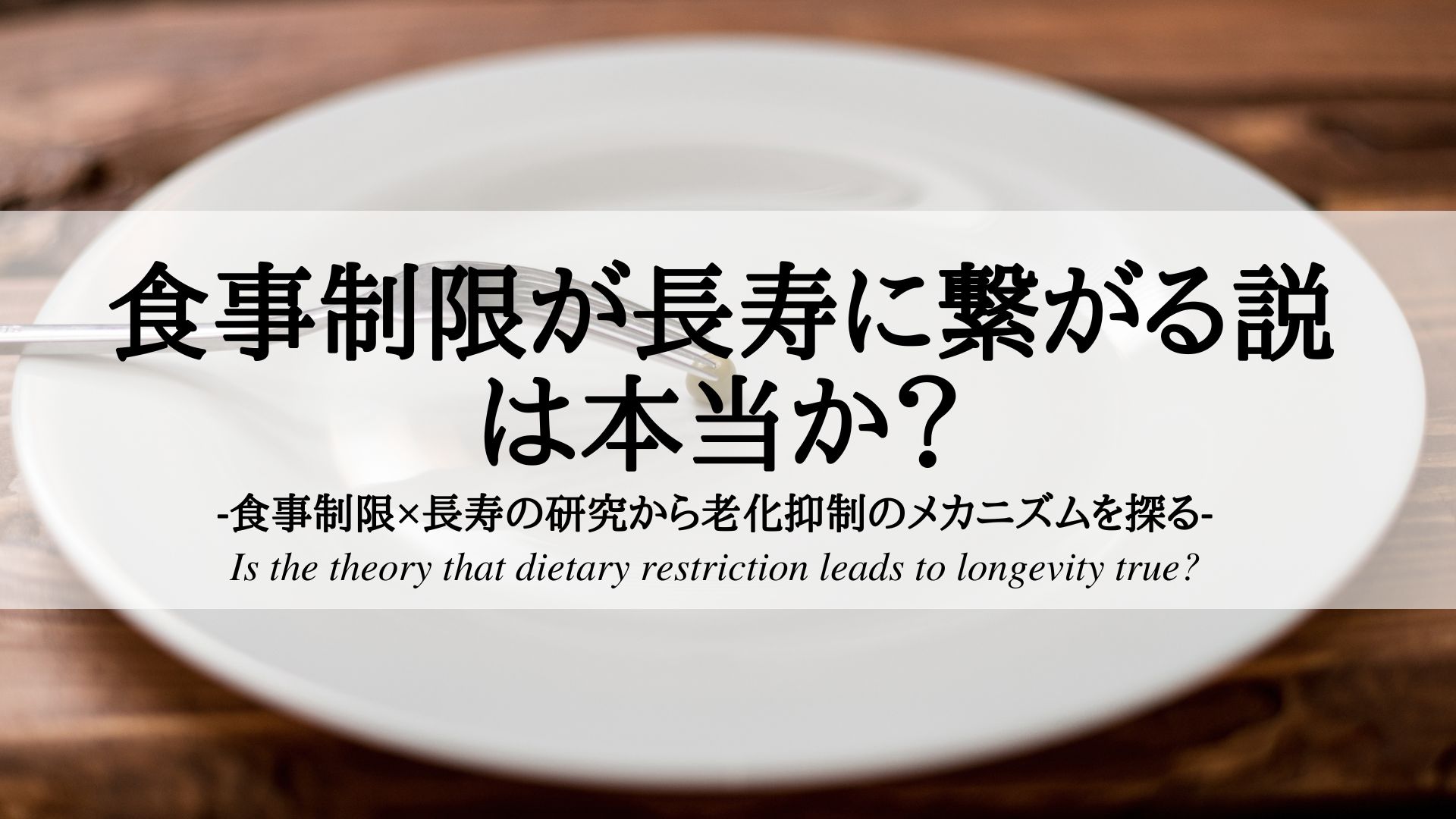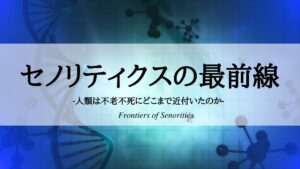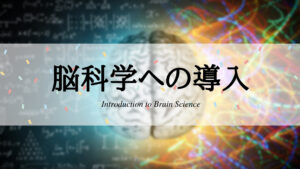「腹八分目」という言葉があるように、人は昔からなんとなく満腹の一歩手前が健康によいことを分かっていたのではないでしょうか。そして近年、食事制限と長寿を繋げる研究が数多く発表されています。この記事では、なぜ食事制限が注目されているのか、実際に食事制限が長寿に繋がるのか解説しています。


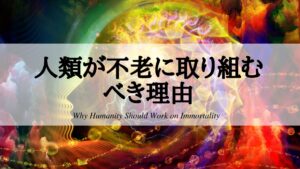
食事制限とは?
食事制限またはカロリー制限とは、栄養失調を伴わずに摂取エネルギーを10~40%ほど制限することです。食事制限によって線虫、ハエ、マウスなどの数々なモデル生物の寿命の延長が認められたことから、老化と寿命との関係性について注目されています。
食事制限が老化を遅らせる理由
ひと言で「老化」といっても何を指すのか曖昧なところがありますが、老化の指標の一つに異常なタンパク質の蓄積が挙げられます。たとえば、高齢者に多いアルツハイマー型認知症は、アミロイドβというタンパク質が脳内に蓄積することが原因であると考えられています。若いうちはタンパク質は合成と分解をくりかえして、絶えず新陳代謝が行われています。しかし、加齢によって分解機能が低下してしまい、古いタンパク質が蓄積してしまうのです。このことから、生命維持のためにはタンパク質の合成だけでなく、分解もとても大切であることが分かります。
タンパク質分解経路には、ユビキチンプロテアソーム系とオートファジーリソソーム系の二つがあります。ユビキチンプロテアソーム系はタンパク質のユビキチン化とプロテアソームによる選択的分解、オートファジーリソソーム系は隔離した細胞内成分をリソソームで分解する大規模な非選択的分解です。食事制限でしばしば注目されるのが、後者のオートファジーリソソーム系のマクロオートファジー(以下、オートファジー)です。詳しく見ていきましょう。
食事制限はいくつかの代謝経路を活性化または抑制することが分かっています。抑制される経路の一つにmTOR(ほ乳類ラパマイシン標的タンパク質)経路があります。mTORはオートファジーの重要な制御因子で、抑制されたmTORはオートファジーを誘導します。つまり、食事制限でmTORを抑制することによって、オートファジーによるタンパク質の分解機能を意図的に誘導することができるのです。その結果、細胞内浄化の促進と神経変性の抑制に繋がり、老化を遅らせることができると考えられています。抗腫瘍薬ラパマイシンが有望なアンチエイジング薬として注目されているのも、mTOR経路を選択的に阻害するからです。
食事制限で人の寿命は延びるのか?
結論からいうと、私たち人間のように寿命が長い生物にとって、食事制限が長寿に直結するかどうかは分かりません。オートファジー以外の系や、遺伝的、環境的要因が複雑に合わさって、寿命が決まるからです。たとえば、サルでの研究結果はまちまちで、食事制限が寿命の延長に繋がると報告するものもあれば[1] 、対照群との差が見られなかったと報告するものもあります[2] 。しかし、寿命に変化はなくとも、食事制限によって活性酸素によるストレスの低減が見られたり、若いうちに食事制限を取り入れることで加齢性疾患の発病を遅らせたりすることができるようです。また、非肥満者で2年間の食事制限を行った臨床試験[3] では、食事制限によって心血管代謝疾患のリスク因子と基礎代謝の低下が認められています。事後解析[4] では、食事制限で老化の進行が緩やかになっていることも判明しました。食事制限が長寿に繋がると言い切るのは時期尚早ですが、摂取カロリーを制限することは健康寿命を伸ばすのに有効のようです。
おわりに
モデル生物が食事制限で長生きするように、人間も食事制限で長生きできるかどうかはまだ分かりません。しかし、食事制限が何かしら健康寿命にプラスの影響を及ぼすことは分かってきています。今後、老化研究がさらに進むことによって老化の特効薬のようなものが開発されるかもしれませんが、それまではバランスの取れた食事、適度な運動などの規則正しい生活を心がけることが私たちが長寿になれる一番の近道なのかもしれません。
参考文献
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/56/11/56_561103/_pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19590001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3832985