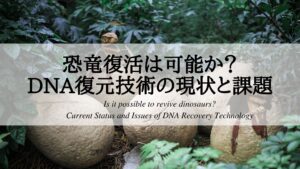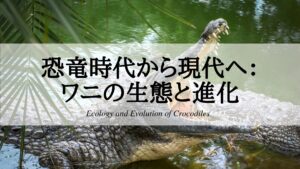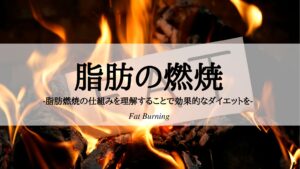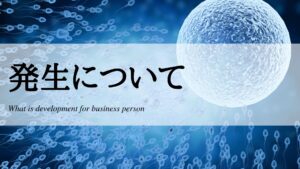人間とネコ(イエネコ、Felis catus)は長い年月にわたり生活を共にしてきました。本記事では、ヒトとネコの関係を遺伝子レベルで分析し、その共生メカニズムを最新の研究に基づいて探ります。遺伝的共通点から進化の歴史、コミュニケーション、生物学的作用、さらに倫理的・社会的側面まで、科学的視点で深掘りします。
ヒトとネコの遺伝的共通点と共生の遺伝子基盤
ヒトとネコは哺乳類として共通の祖先を持ち、ゲノム(全遺伝情報)の構造にも多くの共通点があります。ヒトとネコはいずれも約2万個のタンパク質コード遺伝子を持ち、そのうち約1万6000個は両者でほぼ同一だと報告されています (Cats’ Genomes Make Them Good Models for Human Disease – DNA Science)。これは約6500万年前にさかのぼる共通祖先から分岐したことに由来し、ゲノムの保存性が高いことを意味します 。染色体数はネコ19対、ヒト23対と異なるものの、遺伝子の配列順序や間隔といったゲノム全体の構造は非常によく似ており、霊長類以外ではヒトに最も近いゲノム構造を持つ生物の一つとされています (Feline Genetics Help Pinpoint First-Ever Domestication of Cats, MU Study Finds // College of Veterinary Medicine)。このようなゲノムの類似性のため、ネコはヒトの疾患モデルとしても有用であり、多くの遺伝病で共通の原因遺伝子変異が見つかっています(例:多発性嚢胞腎や網膜変性など)。
人と暮らすネコの「飼い猫化(家畜化)」の過程では、遺伝子レベルでどのような変化が起きたのでしょうか。最新のゲノム比較研究によると、野生のヤマネコと比べて飼い猫では脳内の記憶、恐怖反応、報酬追求に関わる遺伝子に変化が蓄積していることが明らかになりました (The cat’s meow: Genome reveals clues to domestication – The Source – WashU)。これらの遺伝子変化は、人間との共生に役立つ行動(人への警戒心の低下や、エサを得るための積極的なアプローチ)に影響すると考えられています。実際、人間は穀物を荒らすネズミ退治という役割でネコを歓迎し、ネコにエサを与えることで“報酬”を提供してきたと考えられます。その結果、人里に残ったネコは人間から餌をもらうことを学習し、より穏やかで人に懐きやすい個体が生き残りました。このように、ヒトとネコの共生は遺伝的素地としてヒトと環境に適応した行動特性をネコが進化させることで可能になったと言えるでしょう。
ネコとヒトの進化的共生の歴史
ネコとヒトの関係はいつ始まったのでしょうか。考古学的・遺伝学的証拠から、約1万年前にはすでにネコが人間社会に関与し始めていたとされています (Feline Genetics Help Pinpoint First-Ever Domestication of Cats, MU Study Finds // College of Veterinary Medicine)。中東の肥沃な三日月地帯(現在の中近東)の初期農耕社会では、穀物を貯蔵する集落にネズミなどの齧歯類が発生し、それを狩る野生のヤマネコが人間の集落に引き寄せられました。人間にとってネコは穀物を守る益獣となり、ネコにとっても餌が豊富な人間の環境は好都合でした。この相利共生的な関係が最初の家畜化のきっかけとなり、やがて人間はネコに餌を与え居場所を提供し、ネコは居ついて鼠捕りに貢献するという共生関係が成立したのです (The cat’s meow: Genome reveals clues to domestication – The Source – WashU)。
遺伝子研究からもネコの家畜化の起源が裏付けられています。2022年の包括的な遺伝調査では、世界中のネコの遺伝的多様性を分析した結果、ネコの家畜化は主に中東(肥沃な三日月地帯)で一度起こり、そこから人間と共に世界へ拡散した可能性が高いことが示されました (Feline Genetics Help Pinpoint First-Ever Domestication of Cats, MU Study Finds // College of Veterinary Medicine)。馬やウシのように各地で独立に家畜化されたわけではなく、ネコの場合は起源が限定的だったようです 。実際、古代の航海や交易にもネコは同伴し、農耕民の移動とともにヨーロッパやアジア、アフリカへと広まっていきました 。こうして世界各地でネコは人間社会に定着し、土地ごとのネコ集団間で遺伝的な分化(距離による隔離:isolation by distance)も生じていきました。
古代文明において、ネコは単なる害獣駆除の域を超えて特別な存在となっていきます。特に有名なのが古代エジプト文明です。エジプト人はネコを神聖視し、女神バステト(バスト)など神格と結び付けて崇拝しました。ネコは家庭で愛玩されただけでなく、その死後にミイラとして飼い主と共に埋葬される例もあり、飼い主が死後の世界でも愛猫と暮らせるようにと願われていたようです (How Cats Became Divine Symbols in Ancient Egypt | HISTORY)。エジプトの貴族や王族はネコに金の首輪をつけ、自らの皿から食事を与えたという記録もあり、ネコは社会的地位を持つ動物として扱われていました。また、古代エジプトの墓壁画には狩猟の場面でネコが鳥を捕まえている姿が描かれており、人とネコが一緒に狩りをするパートナーでもあったことが示唆されています。このように、古代におけるヒトとネコの関係は実利的な相互利益から精神的な結びつきへと発展し、人間文化の中でネコは特別な位置を占めるようになりました。
ヒトとネコのコミュニケーション能力の科学的根拠
現代の飼い猫は、鳴き声やしぐさを巧みに使って人間とコミュニケーションを図ります。その能力には科学的な裏付けがあります。まず、ネコの鳴き声(ニャー)は人間とのコミュニケーションのために進化したとも言われます。野生の成猫同士はあまり「ニャー」と鳴き合うことはありませんが、飼い猫は人に要求や感情を伝えるため積極的に鳴きます。興味深い研究として、ネコがエサをねだる際のゴロゴロ喉を鳴らす音(喉鳴らし)に人間の赤ん坊の泣き声に似た高周波成分を混ぜていることが報告されました (The cry embedded within the purr: Current Biology)。この「要求ゴロゴロ音」は通常のゴロゴロ音よりも人間にとって緊迫感があり不快にも聞こえると評価され、ネコは人間の感覚を巧みに刺激して世話を引き出している可能性があります。実験では、こうした要求混じりのゴロゴロ音から高周波成分を取り除くと、人間が緊急性を感じる度合いが大きく低下することも示されています 。これはネコが人間の養育本能(赤ちゃんの泣き声に反応する性質)を利用するよう鳴き方を調整している証拠と考えられています。
ネコのコミュニケーションは鳴き声だけではありません。しぐさや視線も重要です。例えば、飼い猫が飼い主に向けてゆっくりまばたき(スローブリンク)する行為は「猫の微笑」とも呼ばれ、友好と信頼のサインだと考えられてきました。2020年の研究で、このスローブリンクが実際に人と猫の双方向コミュニケーションに役立つことが実証されています。飼い主が猫に向かって目を細めてゆっくり瞬きをすると、猫も同じようにゆっくり瞬きを返しやすくなり (Study Confirms ‘Slow Blinks’ Really Do Work to Communicate With Your Cat : ScienceAlert)、さらにその後で人間が手を差し伸べると猫が近づいてくる頻度が増加しました 。これはスローブリンクが猫に「敵意はない、親愛の情がある」というメッセージを伝え、猫が安心して応答・接近するためと考えられます。実験者自身が初対面の猫に対して行った場合でも有効であったことから、スローブリンクは猫-ヒト間のポジティブな感情コミュニケーションであると言えるでしょう。
ネコは人間の言葉や行動もある程度理解しています。上智大学の研究チームによる2019年の論文は、ネコが自分の名前を他の言葉と聞き分けていることを実験的に示しました (ネコは自分の名前をちゃんと認識していることが研究で発覚 – GIGAZINE)。飼い主がまず猫に対し無関係な言葉を繰り返し呼びかけて慣れさせた後、猫の名前を呼ぶと、多くの猫が明確に反応を示したのです。この反応は飼い主の声だけでなく他人の声でも見られたことから、猫は自分の名前の音を認識し反応していると結論づけられました 。名前以外にも、猫は人間の視線や指さしをある程度理解できるという研究もあります。たとえば、人が指さした方向を猫が目で追ったり、その先に餌が隠されていれば見つけ出す割合が有意に高いことが報告されています(猫の指さし理解率はおよそ75%で、犬ほどではないものの確かに指示を読み取っています (Cats Get the Point of Pointing | Psychology Today))。さらに近年の研究では、猫が人間の感情を表情や声の調子から読み取り、自分の行動を調節している可能性も示されました。猫は他の猫および人間の表情と声を組み合わせて、その感情のポジティブ・ネガティブを認識できることが示唆されており ( Emotion Recognition in Cats – PMC )、飼い主の怒りや嬉しさに応じて猫の行動が変化することが観察されています。つまり、猫は人と自分の双方の意思疎通を図るため、進化的に身につけたコミュニケーション手段を駆使しているのです。
ホルモンや神経伝達物質の影響と遺伝子の関係
ヒトとネコの触れ合いがもたらす生理的変化にも科学的な知見が集まりつつあります。代表的なのが**オキシトシン(愛情ホルモン)**です。オキシトシンは哺乳類に広く存在する神経ペプチドホルモンで、社会的絆の形成(母子の愛着やペアのきずな)に重要な役割を果たします ( Exploring women’s oxytocin responses to interactions with their pet cats – PMC )。人と犬が見つめ合ったり触れ合ったりすると双方でオキシトシン濃度が上昇することが知られていますが、ではネコの場合はどうでしょうか。最近の研究で、ネコと飼い主のスキンシップがオキシトシン分泌に与える影響が調べられました。
(Cats Release Oxytocin When Cuddling With Humans—But Only on Their Terms · Kinship)図: 飼い主に甘える猫。ヒトとネコのスキンシップは互いの絆を深め、生理的な変化を引き起こす。例えば、わずか10分間猫や犬と触れ合うだけで、人のコルチゾール(ストレスホルモン)が有意に低下することが示されている ( Dogs and cats relieve academic stress and lift students’ mood, according to a new study )。
まず、人間側への効果として、ペットとの触れ合いはリラックス効果をもたらします。ワシントン州立大学の研究では、大学生が猫や犬を10分間なでたり遊んだりすると、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルが有意に低下したことが報告されています ( Dogs and cats relieve academic stress and lift students’ mood, according to a new study )。触れ合った学生は触れ合わなかった対照群に比べて明らかに唾液中のコルチゾール濃度が下がっており、短時間でもペットとのスキンシップがストレス軽減に効果的だと示されました 。このように、人にとって猫との触れ合いはストレス緩和や安心感につながる生理反応を引き起こします。一方、オキシトシンについては人間側では複雑な結果が出ています。ある研究では、女性参加者が自分の飼い猫と一定時間触れ合った場合と本を読んだ場合で唾液中オキシトシン濃度を比較しましたが、平均的には有意な差が見られませんでした ( Exploring women’s oxytocin responses to interactions with their pet cats – PMC )。しかし興味深いことに、触れ合い中の具体的な行動に注目すると、猫を撫でたり猫の方から近づいてくるといったポジティブな相互作用が多いほど女性側のオキシトシン値が高くなる傾向が確認されたのです。逆に猫が威嚇的な行動を示すような場合にはオキシトシン値が低く出る関連も見られました 。つまり、人間側では「猫との穏やかな触れ合い」がある時にオキシトシン分泌が促進され、主観的な幸福感や絆の強まりに寄与していると考えられます。
では猫側はどうでしょうか。最近発表された研究によると、猫もまた人とのスキンシップでオキシトシンが変動することが示唆されています。猫の愛着スタイル(飼い主への付き合い方)を評価した実験では、飼い主に対し自ら積極的にスリスリしたり膝に乗ったりする「安定型」の猫は、触れ合い後にオキシトシン濃度が上昇する傾向が見られました (Cats Release Oxytocin When Cuddling With Humans—But Only on Their Terms · Kinship)。興味深いことに、このタイプの猫は触れ合い前のオキシトシン値は低めですが、触れ合った後に明確な上昇が検出されたのです 。一方で、飼い主にベッタリで不安が強い「不安型」の猫では、もともとオキシトシン値が高めで、触れ合い後にむしろ低下する傾向がありました。また、人に無関心な「回避型」の猫では触れ合いによる変化はほとんど見られなかったといいます。この結果は、猫にも個性(愛着スタイル)によってホルモン反応が異なることを意味します。すなわち、人間とのポジティブな触れ合いを好む猫にとっては、オキシトシンが絆ホルモンとして働いている可能性があります。以上のように、ヒトとネコ双方でオキシトシン系が関与することは間違いなく、これが相互の愛着とストレス緩和に寄与する生物学的メカニズムと考えられます。
オキシトシン以外の神経伝達物質やホルモンについても、ヒトとネコは多くの共通点を持ちます。例えばドーパミンはヒトの報酬系(快感や動機づけ)を司る神経伝達物質ですが、ネコでも同様に美味しい餌を食べたり遊びで興奮したりするときにドーパミン作動経路が働くと考えられます。実際、前述のようにネコの家畜化過程では報酬系に関わる遺伝子の変化が起きており、人間から餌をもらうという報酬に対して敏感になる方向で進化が起きた可能性があります (The cat’s meow: Genome reveals clues to domestication – The Source – WashU)。またセロトニンは情動や気分を安定させる神経伝達物質で、ヒトでは幸福感に関与しますが、ネコにもセロトニン受容体が存在し気分や攻撃性の制御に関わっているとされます。このように、哺乳類として共有する神経化学的基盤がヒトとネコ双方にあるため、お互いの存在がストレス緩和や安心感、喜びといった感情面に良い影響を与えるのです。さらに高次の例では、老齢のネコがアルツハイマー病様の認知症になると、ヒトのアルツハイマー病と類似して脳内にアミロイドβプラークと神経原線維変化(タングル)が蓄積し、神経細胞の脱落パターンも人に近いという報告があります (Cats’ Genomes Make Them Good Models for Human Disease – DNA Science)。この点も含め、ヒトとネコは脳の老化や疾患のメカニズムまで共有する部分があることがわかってきました。遺伝子的にも生理学的にも共通する基盤を持つからこそ、ヒトとネコは共に暮らし互いに影響を及ぼし合える関係を築けていると言えるでしょう。

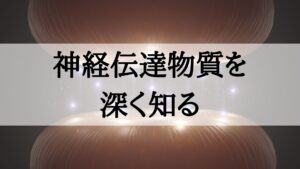
倫理的・社会的側面
ヒトとネコの共生関係には、倫理的・社会的な課題も存在します。まずペットとしてのネコの飼育倫理です。人間がネコを飼う以上、その福祉と管理には責任が伴います。世界的にネコは人気のあるペットですが、その結果として野良猫・野放しの飼い猫の増加が問題となっています。飼い主のいない野良猫は都市や農村に多数存在し、飢餓や病気、事故などで苦しむ個体も多いです。また、繁殖力が高いため放置すれば個体数は指数関数的に増え、保健所での殺処分数増加や生態系への悪影響にもつながります。この問題に対処するため、動物愛護団体や自治体は**避妊去勢手術(不妊化)**の徹底を呼びかけています。避妊去勢は望まれない子猫の誕生を防ぐだけでなく、繁殖行動に関連する問題行動(放浪や夜鳴き、スプレー行動)の軽減や、生殖器系の病気(乳腺腫瘍や精巣腫瘍)の予防にも有効です (Why Trap-Neuter-Return Feral Cats? The Case for TNR)。実際、ペットとして飼うネコは適切な時期に手術を施すことが国際的にも推奨されており、飼い主の責任の一つと考えられています。
一方、既に地域社会に定着している野良猫に対してはTNR(Trap-Neuter-Return:捕獲-不妊化-戻し)プログラムが各地で実施されています (Why Trap-Neuter-Return Feral Cats? The Case for TNR)。TNRとは、野良猫を捕獲して不妊手術を施し、元の場所に戻す取り組みで、繁殖を抑制しつつ猫の命を尊重する人道的解決策とされています。適切に実施すれば地域の猫個体数が徐々に減少し、群れが安定化する効果が報告されています。しかしTNRにも課題はあります。避妊去勢された猫を元の場所に戻すということは、その猫たちが引き続き野外で生活することを意味します。野外生活では猫自身が厳しい環境に晒されるだけでなく、在来の野生生物への影響も無視できません (Reply to Wolf et al.: Why Trap-Neuter-Return (TNR) Is Not an Ethical …)。例えば野良猫や放し飼いの猫は小動物を狩る本能があり、鳥類や小型哺乳類、爬虫類など様々な野生生物を捕食します。その影響は甚大で、ある推計によれば米国では野外猫によって毎年13~40億羽の鳥類と63~223億匹の哺乳類が捕殺されていると試算されています (The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United …)。また世界規模で見ると、野生化した猫は少なくとも2000種以上の生き物を捕食しており、その中には絶滅危惧種が350種近く含まれます (Cats Kill a Staggering Number of Species across the World | Scientific American)。実際に野良猫が主因となって絶滅したとされる島嶼固有種の例も複数記録されています。こうした事情から、自然保護の観点では野良猫を外に放したままにするTNRには批判的な意見もあります (Reply to Wolf et al.: Why Trap-Neuter-Return (TNR) Is Not an Ethical …)。動物愛護と生態系保全の板挟みであり、「命を救う」ことと「生態系への責任」のバランスをどうとるかが問われているのです。
(Cats Kill a Staggering Number of Species across the World | Scientific American)図: 夜行性のハンターであるネコ。自由に屋外を歩く猫は、小鳥から小型哺乳類まで様々な野生生物を狩ることができ、その捕食対象種は2000種を超えるとも報告されている。在来種保護の観点からは、猫の屋外活動を制限すべきとの意見も強い。
さらに、遺伝的多様性と繁殖管理の問題もあります。近年は純血種(ペルシャやシャムなど)のブリード(繁殖)が盛んですが、過度の近親交配により遺伝病の頻度が高まる懸念があります。例えばペルシャ猫では多発性嚢胞腎(PKD)という遺伝性の腎臓病がかつては高い割合で見られましたが、2004年にDNA検査法が開発されて以降、繁殖前に保因猫を選別することで有病率が劇的に低下しました (Feline Genetics Help Pinpoint First-Ever Domestication of Cats, MU Study Finds // College of Veterinary Medicine)。このケースは、適切な遺伝子スクリーニングと繁殖管理によって猫種の健康問題を改善できる好例です。倫理的には、人間の趣味嗜好のために極端な形態(極端に鼻の低い顔貌や無毛、極小サイズなど)を追求する繁殖にも批判があり、動物福祉の観点から遺伝的健康が損なわれないよう配慮すべきだとされています。去勢避妊の徹底、責任ある繁殖と里親制度の活用、そして飼い猫を終生適切に飼養すること——これらがペットとしてのネコの福祉と社会的調和を保つために求められる倫理と言えるでしょう。
最後に、野生種との関係に触れておきます。イエネコは元々近縁の野生種(リビアヤマネコなど)が人里に進出して生まれた存在ですが、現代でも野生のヤマネコとの交雑が問題となる場合があります。ヨーロッパヤマネコやスコットランドヤマネコは本来イエネコとは別種ですが、野外で両者が交配して混血が生まれることで純粋な野生種の遺伝子プールが脅かされています。最近の調査では、スコットランドの野生ヤマネコは過去数十年間でイエネコとの交雑が進み、もはや「ゲノム的に純粋な個体群は絶滅状態」にあるとの警告も出されています(Domestic Cats Could Breed Scottish Wildcats Out of Existence | Smithsonian)。このように人為的な環境変化によって生じた異種交配は、生物多様性保全上の新たな課題です。人とネコの共生が他の野生動物に負の影響を与えないよう、地域や環境に応じた管理策(屋内飼育の推進やアウトドア猫の見張り、猫が入れない保護区の設定等)を講じる必要があるでしょう。
おわりに
ヒトとネコの関係は、遺伝子・進化・行動・生理など多面的な要因によって支えられていることがわかってきました。遺伝的には共通の基盤がありつつ、ネコは人間社会に適応する形で行動進化を遂げ、歴史的に人類と共に歩んできました。コミュニケーション面では、お互いの意思を伝え合う手段を発達させ、ホルモンや神経伝達物質レベルでも絆を深め合っています。しかしその一方で、人間がネコを愛玩することには責任が伴い、生態系や動物福祉への配慮が欠かせません。科学的知見はこうした共生関係の理解を深め、問題の解決策を導く上で重要な役割を果たします。ヒトとネコの共生メカニズムを解明する研究がさらに進めば、人間と動物のより良い関係構築や、お互いの健康・幸福の増進につながることでしょう。
参考文献:
- Alex Fox, “Human Genomes Are Surprisingly Cat-Like”, Smithsonian Magazine, July 30, 2021 (Human Genomes Are Surprisingly Cat-Like | Smithsonian) (Feline Genetics Help Pinpoint First-Ever Domestication of Cats, MU Study Finds // College of Veterinary Medicine).
- Ricki Lewis, “Cats’ Genomes Make Them Good Models for Human Disease”, DNA Science (PLOS), Aug 12, 2021 (Cats’ Genomes Make Them Good Models for Human Disease – DNA Science) (Cats’ Genomes Make Them Good Models for Human Disease – DNA Science).
- Gaia Remerowski et al., “The cat’s meow: Genome reveals clues to domestication”, PNAS (Washington Univ. News), Nov 10, 2014 (The cat’s meow: Genome reveals clues to domestication – The Source – WashU) (The cat’s meow: Genome reveals clues to domestication – The Source – WashU).
- Brian Consiglio, “Feline Genetics Help Pinpoint First-Ever Domestication of Cats, MU Study Finds”, Univ. of Missouri, Dec 5, 2022 (Feline Genetics Help Pinpoint First-Ever Domestication of Cats, MU Study Finds // College of Veterinary Medicine) (Feline Genetics Help Pinpoint First-Ever Domestication of Cats, MU Study Finds // College of Veterinary Medicine).
- History.com Editors, “How Cats Became Divine Symbols in Ancient Egypt”, History, Sept 13, 2019 (How Cats Became Divine Symbols in Ancient Egypt | HISTORY) (How Cats Became Divine Symbols in Ancient Egypt | HISTORY).
- Karen McComb et al., “The cry embedded within the purr”, Current Biology 19(13), 2009 (The cry embedded within the purr: Current Biology) (The cry embedded within the purr: Current Biology).
- Michelle Starr, “Study Confirms ‘Slow Blinks’ Really Do Work to Communicate With Your Cat”, ScienceAlert, Oct 2020 (Study Confirms ‘Slow Blinks’ Really Do Work to Communicate With Your Cat : ScienceAlert) (Study Confirms ‘Slow Blinks’ Really Do Work to Communicate With Your Cat : ScienceAlert).
- 斎藤慈子ら, 「Domestic cats discriminate their names from other words」, Scientific Reports 9, 2019 (ネコは自分の名前をちゃんと認識していることが研究で発覚 – GIGAZINE) (ネコは自分の名前をちゃんと認識していることが研究で発覚 – GIGAZINE).
- Angelo Quaranta et al., “Emotion Recognition in Cats”, Animals 10(7), 2020 ( Emotion Recognition in Cats – PMC ).
- Patricia Pendry et al., “Animal Visitation Program (AVP) Reduces Cortisol Levels of University Students: A RCT”, AERA Open 5(2), 2019 ( Dogs and cats relieve academic stress and lift students’ mood, according to a new study ).
- Isabella Merola et al., “Exploring oxytocin responses to interactions with pet cats”, PeerJ 9:e12125, 2021 ( Exploring women’s oxytocin responses to interactions with their pet cats – PMC ).
- Ryo Okabe et al., “Effects of owner–cat interactions on the oxytocin secretion of cats”, Behavioural Processes 2023 (in press) (Cats Release Oxytocin When Cuddling With Humans—But Only on Their Terms · Kinship).
- Scott Loss et al., “The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States”, Nature Commun. 4:1396, 2013 (The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United …).
- Jack Tamisiea, “Cats Kill a Staggering Number of Species across the World”, Scientific American, Dec 12, 2023 (Cats Kill a Staggering Number of Species across the World | Scientific American).
- Margaret Osborne, “Domestic Cats Could Breed Scottish Wildcats Out of Existence”, Smithsonian Magazine, Nov 8, 2023 (Domestic Cats Could Breed Scottish Wildcats Out of Existence | Smithsonian) (Domestic Cats Could Breed Scottish Wildcats Out of Existence | Smithsonian).