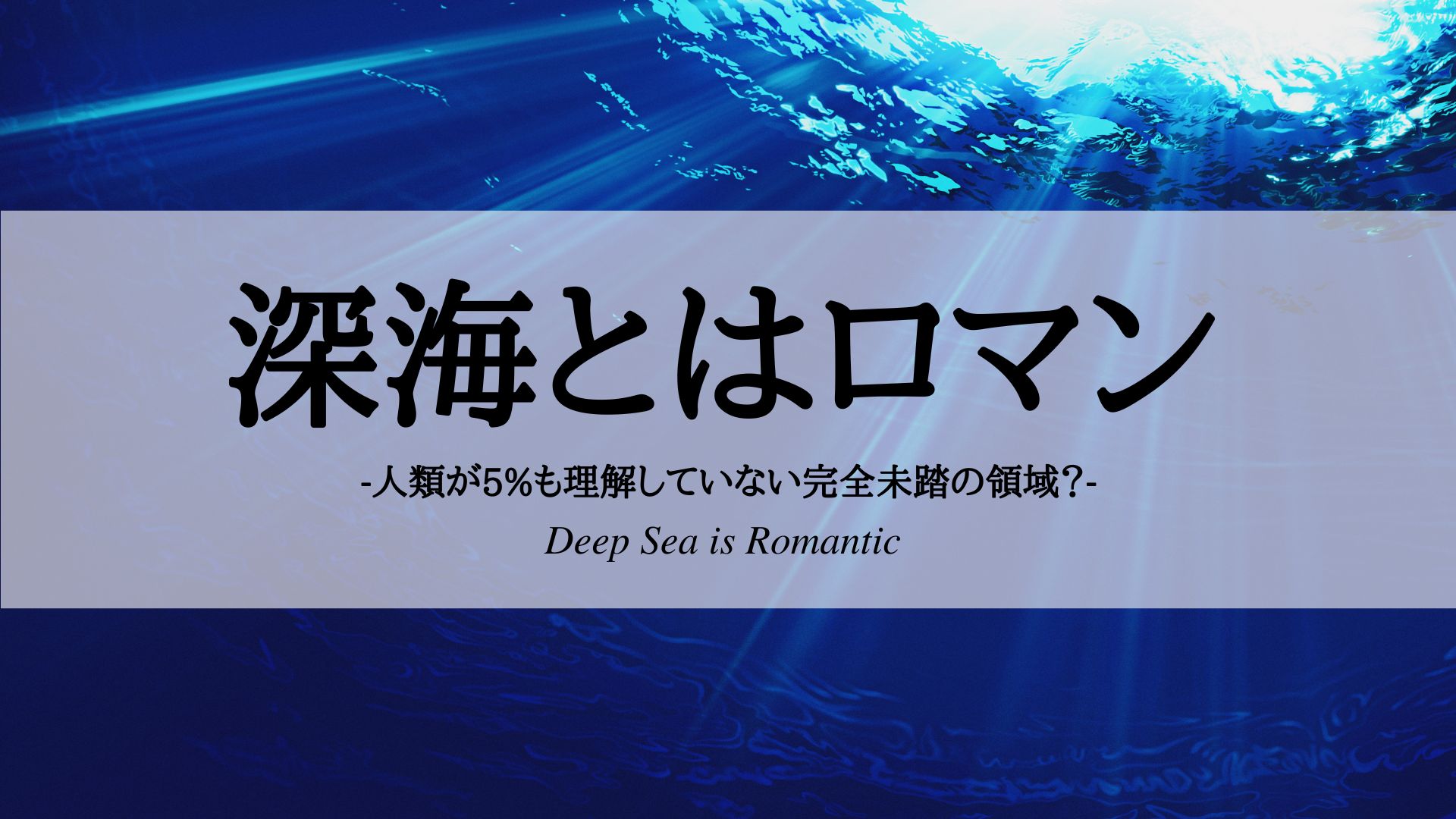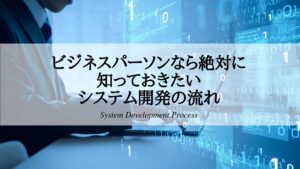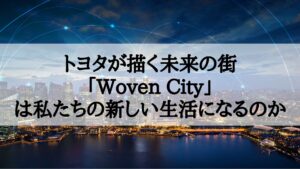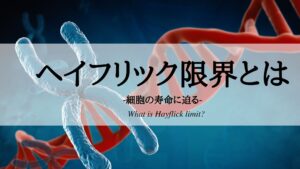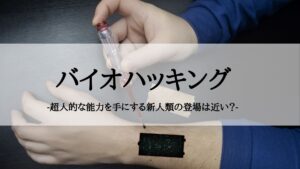地球の約7割を占める海。その大部分は、水深200メートル以深の「深海」と呼ばれる暗黒の世界であり、21世紀の現在でも人類が探査できたのはわずか5%程度と言われています。深海には未知の巨大生物や極限環境に適応した微生物がひそみ、最新の探査技術が進むにつれて新発見も相次いでいます。私たちがほとんど理解していない「最後のフロンティア」深海の神秘を科学的に紐解きます。
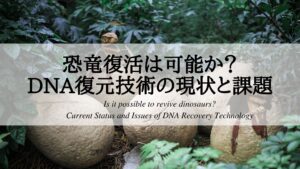
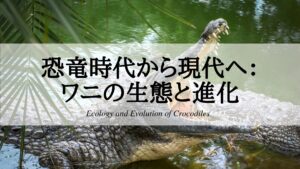
深海とは何か?
深海(しんかい)とは明確な定義があるわけではありませんが、一般には水深200メートルより深い海域を指します (深海 – Wikipedia)。この深さになると太陽光はほとんど届かなくなり、光合成に必要な光がないため表層海域とは環境や生態系が大きく異なる暗黒の世界になります。水温は極めて低く(一部の超深海では約1〜2℃まで低下します)、水圧は10m深くなるごとに約1気圧ずつ増加し、200mの深さでは地表の20倍にも及ぶ高圧になります (深海とは?|深海魚の聖地 HEDA-戸田! 戸田地区深海魚活用推進協議会 公式ホームページ)。こうした高水圧・低水温・暗黒という過酷な条件に適応するため、深海の生物は独自の進化を遂げており、表層の生物からは想像もできない特異な形態・生態を持つものも存在します。
深海が「未踏の領域」と称されるのは、その大部分が今なお人類未踏・未探査だからです。地球の海の平均深度は約3,700mで、海面積の80%近くが深海に該当しますが、21世紀現在でも深海探査は超高水圧に阻まれて容易ではなく、極限の深度まで潜航できる有人・無人の潜水艇を保有する国もごくわずかであるため、深海のほとんどは依然として未知の世界なのです (深海 – Wikipedia)。実際、人類が実際に詳細に探査できている海域は全体のわずか5%程度に過ぎず、残り95%は未だよく分かっていないとも報告されています (NOAA Ocean Exploration and Research: World Oceans Day)。月や火星の地表面はすでに100%近く詳細にマッピングされているのに対し、海底地形図はいまだ2割程度しか作成されていないという指摘もあり、深海はまさに人類にとって最後のフロンティアと言えるでしょう (Mapping Our Planet, One Ocean at a Time | News | National Centers for Environmental Information (NCEI))。
深海生物の驚異
深海という極限環境にも、多種多様な生物が驚くべき適応を遂げて生息しています。例えば多くの深海魚では、超高圧への適応として体が柔軟で骨の密度が低くなっています。これにより内部からの圧壊を防ぎ、数百気圧にも及ぶ水圧に耐えることが可能です (深海魚の生存戦略:厳しい環境で進化した特異な特徴 | コラム | 深海魚のグッズなら深海Collectite)。また、深海魚は浮き袋(ガスを含む器官)を持たないか特殊な構造にして高圧で潰れない体を獲得しており、視界が利かない暗闇に適応するため大きな目や発光器官を発達させて生物発光で獲物や仲間を探す種もいます。餌が極端に乏しい環境に対応して、非常に大きな口や伸縮性の胃袋を持ち、一度の捕食機会を逃さず獲物を丸呑みできるよう進化したものもいます。深海生物たちのこうした驚異的な適応能力は、過酷な自然環境における生命の逞しさと多様性を物語っています。
深海では未知の生物の発見も相次いでいます。2024年にはチリ沖の深海山脈を調査した遠征で、わずか1か月の間に100種類以上もの新種の深海生物が記録されました (100+ New Species Discovered in the Deep Sea)。そこには深海サンゴやガラス海綿、イバラモエビ(イセエビの一種)などが含まれ、研究チームの予想をはるかに上回る豊富な新種が確認されています (100+ New Species Discovered in the Deep Sea)。また、2023年には日本近海の伊豆・小笠原海溝で、水深8,336mという記録的な深度にて世界最深の魚が撮影されました。これはクサウオ科に属する未記載種(新種)の可能性が高い魚で、8,000mを超える超高圧環境に適応した生物の存在が初めて映像で捉えられた意義深い発見です (Scientists find deepest fish ever recorded at 8,300 metres underwater near Japan | Fish | The Guardian)。このように近年の探査によって、我々の知らなかった大型生物が次々と報告されており、深海生物相の多様性が再認識されています。
(See the Breathtaking Ocean Life Found at Deep-Sea Vents | Smithsonian) 深海底から湧き出す熱水孔(ブラックスモーカー)周辺は、太陽光の届かない極限環境にも関わらず生命のオアシスとなっている。高密度の生物群集が見られ、探査するたびに新種が発見されることも珍しくありません (2016 Deepwater Exploration of the Marianas: Background: Hydrothermal Vents: NOAA Office of Ocean Exploration and Research)。
深海の微生物についても新発見が続いています。たとえば2023年、東太平洋の海底熱水噴出孔「クラブスパ」(水深約2,500m)で北海道大学の研究グループが新種の細菌を分離・発見しました。この細菌はキャンピロバクター綱(エプシロンプロテオバクテリア)の一種で、「Hydrogenimonas cancrithermarum(ハイドロゲニモナス・カンクリテルマルム)」と命名されています (A new bacterial species from a hydrothermal vent throws light on their evolution | ScienceDaily)。高温環境に適応した従来の同属菌とは異なり、中温で硫黄化合物を酸化する性質を持つ初の種であることが明らかとなり、深海微生物の進化的多様性や代謝能力の未知の側面が示されました (A new bacterial species from a hydrothermal vent throws light on their evolution | ScienceDaily)。このように極限環境に棲む微生物の研究は、地球上の生命が持つ適応戦略の幅広さを教えてくれるだけでなく、生命の起源や宇宙における生命存在の可能性を考える上でも重要な手がかりとなっています。
未発見の生命体の可能性
広大な深海には、まだ発見されていない巨大生物が存在する可能性について昔から議論がなされてきました。19世紀には巨大なイカや謎の海獣の伝説が語られましたが、それらの中には後に科学的に実在が確認されたものもあります。例えばダイオウイカ(アカイカ科の巨大種)は長らく半ば伝説上の生物でしたが、2004年に日本の研究者が世界で初めて生きたダイオウイカの写真撮影に成功し、2012年には深海で泳ぐ姿の映像も初めて記録されました (Haunting Video Is The First Footage Ever Recorded of a Giant Squid in US Waters : ScienceAlert)。近年になってようやくその実像が捉えられたダイオウイカの例は、深海には我々が知らない大型生物がまだ潜んでいる可能性を示唆します。しかし一方で、「未知の巨大生物」に関する噂の中には科学的に否定されたものもあります。1997年に太平洋で観測された超低周波音「Bloop(ブループ)」は、当初は正体不明で一部では「未確認生物の鳴き声ではないか」と話題になりましたが、後に南極付近で氷山が砕ける際の氷震(氷の地震)による音と判明しました (What is the bloop? – NOAA’s National Ocean Service)。このように深海には未解明ゆえのロマンがあるものの、具体的な証拠に基づく調査と検証によって神秘を解き明かしていくことが肝要です。
また、深海環境の研究は地球外生命体の可能性を考える上でも重要なヒントを与えてくれます。太陽光の届かない深海底でも、熱水噴出孔の周辺では化学エネルギーを利用した独自の生態系(化学合成生態系)が確立しています。この事実は、例えば木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラドゥスといった氷の下に海を持つ天体にも当てはまるかもしれません。エウロパでは厚い氷殻の下に深い塩水の海が存在しており、岩石の海底と直接接しています。さらに火山活動や潮汐による熱で海底に熱水循環が起こりうると考えられています。また氷と海水の相互作用で酸素が海に供給されている可能性も指摘されており、理論計算ではエウロパの海は地球の深海よりも高い酸素濃度を持つかもしれないという結果もあります (From the Deep Sea to Europa – Schmidt Ocean Institute)。つまりエウロパには地球の深海のように化学合成に基づく生態系が存在し得るということです (From the Deep Sea to Europa – Schmidt Ocean Institute)。実際、NASAなどは地球の深海で極限環境に生きる微生物や生物を調べることで、同様の条件下にあるかもしれない宇宙の海で生命を探す手がかりにしようとしています。深海で見つかった豊かな生命圏は、「太陽光がなくても生命は繁栄できる」ことを示す好例であり、宇宙における生命探査にも大きなインスピレーションを与えているのです。
深海探査技術の進歩
(File:Limiting Factor floating on the water surface.jpg – Wikimedia Commons) 最新の有人深海探査艇「リミティング・ファクター(Limiting Factor)」。繰り返し最深部まで潜航できる世界初の有人潜水艇で、深海探査技術の飛躍的進歩を象徴します。 (Microsoft Word – FDE Challenger Release FINAL .docx)
かつて人類が到達できる海の深さはごく限られていましたが、近年、深海探査技術は飛躍的な進歩を遂げています。1960年にはアメリカ海軍の深海潜水艇「トリエステ」が世界で初めてマリアナ海溝チャレンジャー深淵(約10,912m)に到達し、2012年には映画監督のジェームズ・キャメロン氏が「ディープシー・チャレンジャー」で単独潜航を成し遂げました (Microsoft Word – FDE Challenger Release FINAL .docx)。しかしこれらの潜航は一度きりの挑戦でした。現在では技術の発達により、繰り返し深海最深部まで潜ることが可能な有人潜水艇も登場しています。2019年のファイブ・ディープス探査では、最新鋭の有人潜水艇「DSVリミティング・ファクター」がチャレンジャー深淵の最深部(約10,928m)への潜航に世界で初めて成功し、しかもわずか数日の間に計4回も底床に到達するという偉業を成し遂げました (Microsoft Word – FDE Challenger Release FINAL .docx)。これは従来の記録(1960年のトリエステ号や2012年のディープシー・チャレンジャー号の潜航深度)を上回る新記録であり、パイロットのビクター・ベスコボ氏は人類史上初めて複数回にわたり1万メートル級の深海に到達した人物となりました (Microsoft Word – FDE Challenger Release FINAL .docx)。このような有人探査艇の進歩により、今まで不可能だった深海域での継続的な観測や調査が可能になりつつあります。
有人探査だけでなく、**無人探査機(ROVやAUV)の発達も深海探査を大きく前進させています。遠隔操作型無人探査機(ROV)は高感度カメラやロボットアームを搭載し、人間が立ち入れない極限の深度でも高精細な映像撮影や生物・岩石試料の採取が可能です。例えば2024年に実施された前述のチリ沖の深海遠征では、研究チームがROVと高解像度マルチビームソナーなどの先端技術を駆使して海底地形や生物相を詳細に調査しました (100+ New Species Discovered in the Deep Sea)。その結果、未知の深海生態系の姿が明らかになり、数多くの新種が発見されています。また、自律型無人探査機(AUV)は予めプログラムされたコースを自律航行しながら膨大なデータを収集できるため、広範囲の海底地形図作成や長期モニタリングにも威力を発揮します。近年では人工知能(AI)**を組み合わせて、取得した深海映像から生物種を自動認識・分類する試みも始まっており、データ解析の効率化も進んでいます。
もっとも、深海探査には依然として多くの課題が残されています。超高水圧に耐える探査機の開発・維持には高度な技術と莫大なコストが必要で、世界でもそれを実現できる組織は限られています。また深海はあまりに広大なため、個々の遠征でカバーできる範囲はごく一部に過ぎません。こうした課題に対処するため、国際協力プロジェクトも活発化しています。例えばSeabed 2030計画では、2030年までに世界の海底地形の完全マッピングを目指し各国の研究機関が協力しており、最新の音響測深技術や衛星重力データを駆使して未踏の海底地形を次々と明らかにしつつあります (Mapping Our Planet, One Ocean at a Time | News | National Centers for Environmental Information (NCEI))。2024年時点で全球海底の約26.1%が高解像度で測量されましたが (New marine discoveries underscore importance of ocean floor …)、これはここ数年の技術進歩と取り組みの成果です。今後は探査船の増強や民間企業の参入、さらには深海ステーション(海底に長期間設置する観測基地)の計画も視野に入っており、深海探査はますます効率的かつ持続的になると期待されています。深海探査技術の進歩により、人類はようやく地球という星の「最後のフロンティア」に本格的に踏み出し始めたのです。
未来の深海探査ミッション
今後さらに本格化する深海探査プロジェクトとして、オーシャン・センサス(Ocean Census)が挙げられます。これは2023年に日本財団と英国のネクストン財団(Nekton)を中心に立ち上げられた大規模な国際共同ミッションで、今後10年間で10万種の新種海洋生物を発見・記載するという壮大な目標を掲げています (Over 850 new marine species discovered by the Ocean Census – UNEP-WCMC)。この計画は国連の「持続可能な開発のための海洋科学の10年(Ocean Decade)」にも認定されており、世界中の海洋研究機関・博物館・大学・企業などからなるグローバルなネットワークによって推進されています。実際、開始から最初の16か月で早くも866種もの新種候補を記録する成果を上げており、未発見生物の発掘ペースが飛躍的に加速しています。過去に2000〜2010年にかけて行われた「海洋生物センサス計画」でも約6,000種の新種が報告されましたが、Ocean Censusはそれを桁違いに上回るスピードで海洋生物多様性の全貌解明に挑んでいます。こうした次世代の探査ミッションにより、これまで謎に包まれていた深海生態系の輪郭が鮮明になり、人類の知見はさらに広がっていくことでしょう。
深海探査の進展によって得られる知見は、地球環境への影響という点でも非常に重要です。深海は地球規模の気候システムの一部であり、海洋深層が熱や二酸化炭素を大量に吸収することで地表の気候を緩和する**バッファー(緩衝帯)**として機能しています (Rolling in the Deep: Climate Change and Deep Sea Ecosystems | MA in Climate and Society)。実際、海洋は人類が排出した余剰熱エネルギーの約91%を吸収し、その多くを深海が蓄えているとされます。また大気中のCO₂の25%前後が海に吸収され、その一部は深海の循環によって地表から隔離されています。このように深海は温暖化の影響を一時的に和らげていますが、その容量にも限界があり、もし海洋深層が許容量を超えてしまうと気候変動を加速させる可能性があります 。深海が果たす役割を正確に把握することは、将来の気候予測や地球環境モデルを改善する上で不可欠です。
さらに深海生態系は、地球環境の維持に直接寄与するサービスも提供しています。例えば海底から湧き出すメタンガスは強力な温室効果ガスですが、深海のメタン湧出域にはそれを餌とする特殊な微生物群集(バクテリアとゴカイの共生系など)が存在し、大気放出前に大量のメタンを消費しています。推計では、こうした深海微生物によって**3.82億トン(約382テラグラム)**ものメタンが地中で処理されているとされ、深海は「地球の炭素循環の番人」とも言える働きをしているのです (Rolling in the Deep: Climate Change and Deep Sea Ecosystems | MA in Climate and Society)。深海研究はこのような地球環境を支える目に見えないプロセスを解明し、気候変動への対策や予測に役立つ科学的知見を提供してくれます。加えて、深海生物由来の酵素や化合物は医療・工業分野で新素材や新薬の可能性を秘めており、人類社会への波及効果も期待されています。深海という未知の世界を探査し理解を深めていくことは、地球環境の保全と持続可能な利用にも直結する重要な使命と言えるでしょう。
【参考文献】
- 国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC): 「深海の環境と生態系」に関する解説資料
- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 他: 深海探査や深海生物に関する最新の研究報告・プレスリリース (深海 – Wikipedia) (100+ New Species Discovered in the Deep Sea) (Microsoft Word – FDE Challenger Release FINAL .docx)等