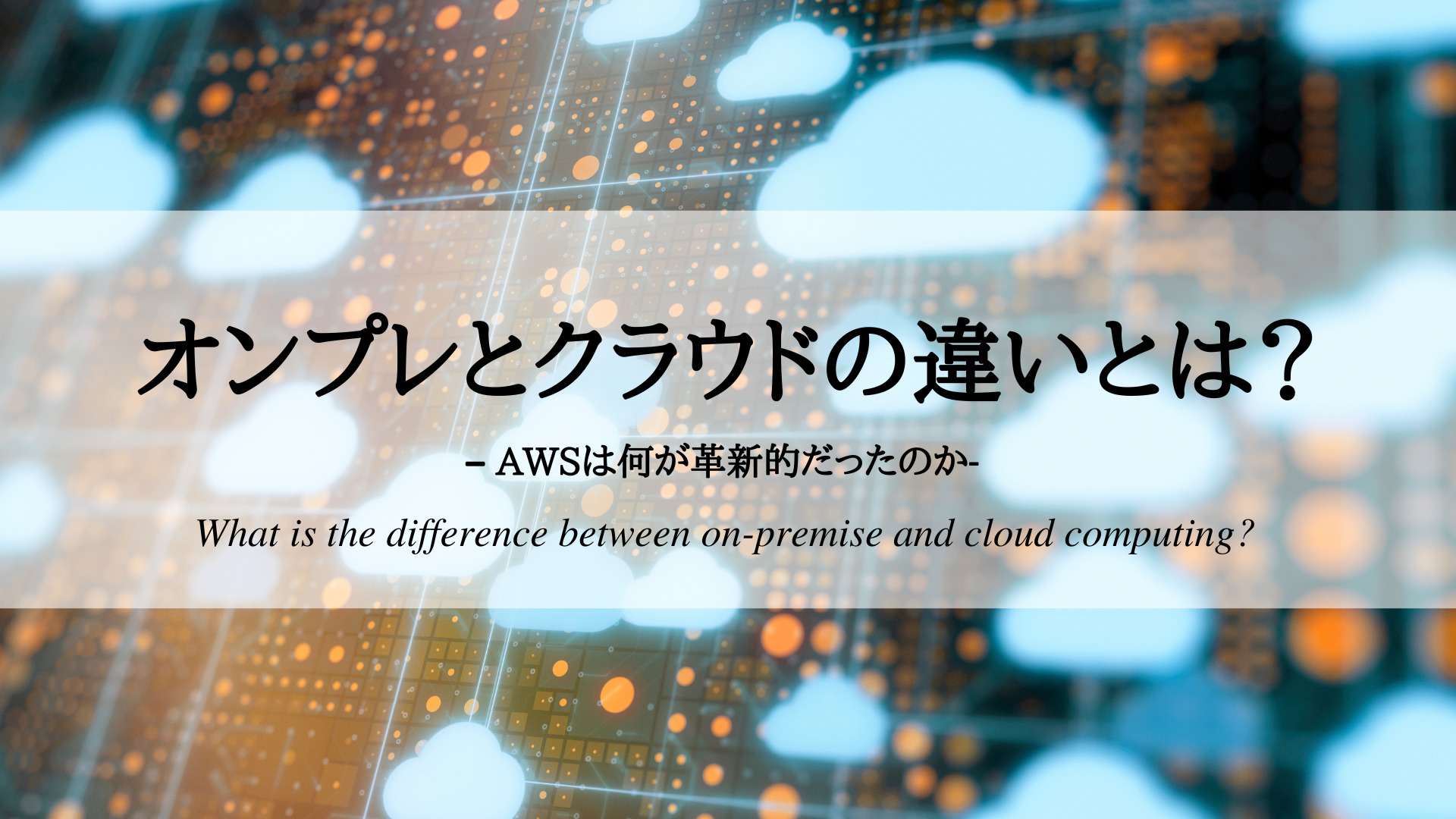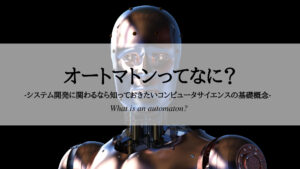現代のITインフラ選定では、「オンプレミス」と「クラウド」という二つの選択肢がしばしば比較検討されます。オンプレミスとは自社でサーバーやネットワーク機器を保有・運用する形態、クラウドとはインターネット経由で外部のサービス事業者が提供するコンピューティングリソースを利用する形態です (クラウドにするかオンプレにするか?|じゅういち/実践プレゼン資料作成術)。特に**Amazon Web Services (AWS)**はクラウドサービスの代表格であり、世界中の企業に革新的なITインフラ利用モデルをもたらしました。本記事では技術的観点とビジネス的観点の両面からオンプレミスとクラウドの違いを解説し、AWSが何を変革したのかに迫ります。さらに、AWSの主要サービス(EC2、S3、RDS)を紹介し、企業がオンプレミスとクラウドをどのように使い分けるべきか考察します。
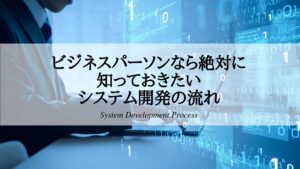
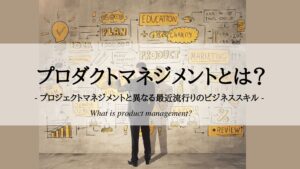
オンプレミスとクラウドの基本概念
オンプレミスとは何か?
オンプレミス(オンプレとも略されます)とは、サーバーやネットワーク機器、ソフトウェアなどシステムに必要な設備を自社の施設内に設置し、自社で運用・管理する形態を指します (クラウドにするかオンプレにするか?|じゅういち/実践プレゼン資料作成術)。会社のオフィスやデータセンターに自前のサーバーを置いてシステムを動かすイメージです。オンプレミス環境ではハードウェアからソフトウェアまですべて自社で用意・管理するため、自社の要求に合わせてシステムを細かくカスタマイズできる自由度の高さが特徴です (AWSとオンプレミスの違いとは?それぞれの利点と欠点を詳しく解説 | ITエンジニア派遣ならオープンアップITエンジニア)。一方で設備購入や設置にまとまった初期費用がかかり、システムを導入して稼働させるまでに時間と労力を要するという側面もあります。
クラウドとは何か?
クラウドとは、自社内にサーバーを持たず、インターネット経由で外部のクラウド事業者が提供するサーバーやストレージ、アプリケーションを利用する形態のことです (クラウドにするかオンプレにするか?|じゅういち/実践プレゼン資料作成術)。クラウド利用時には、ユーザー企業は必要なリソースをサービスとしてレンタルし、インターネットを通じて接続してシステムを利用します。例えば、検索エンジンを使う際に自宅に検索用サーバーを持つ必要がないように、クラウドではインターネット越しに必要な計算処理やデータ保存を提供してもらえます。クラウドではサーバーやネットワーク機器を自社で購入・設置する必要がなく、契約と設定だけですぐにシステム利用を開始できる手軽さが大きな特徴です (オンプレミスとクラウドの違いを7つの項目で徹底比較!おすすめなケース各3選も紹介)。また、利用した分だけ料金を支払う従量課金制が一般的で、使わなくなれば契約を解除してコストを止めることもできます (AWS の クラウドが選ばれる 10 の理由 | AWS)。
オンプレミスでは自社内にサーバーを設置し社内ネットワークから直接サーバーに接続します。一方、クラウドでは社外のクラウド事業者のサーバーにインターネット経由で接続してサービスを利用します (クラウドにするかオンプレにするか?|じゅういち/実践プレゼン資料作成術)。クラウドはオンプレミスに比べ初期導入が迅速で、物理的な設置スペースも不要な点が図からもイメージできます。
オンプレミスとクラウドの違い
オンプレミスとクラウドには、技術面・ビジネス面の双方で様々な違いがあります。ここでは技術的な違い(アーキテクチャ、セキュリティ、運用の観点)とビジネス的な違い(コスト、スケーラビリティ、導入メリット)の二つに分けて、それぞれを詳しく見てみましょう (オンプレミスとクラウドの違いを7つの項目で徹底比較!おすすめなケース各3選も紹介) (On-Premise vs. Cloud: Understanding the Differences)(AWS の クラウドが選ばれる 10 の理由 | AWS) (AWSとオンプレミスの違いとは?それぞれの利点と欠点を詳しく解説 | ITエンジニア派遣ならオープンアップITエンジニア) (なぜ、アマゾンは超爆速でサービスを進化させられるのか? AWS Summit Tokyo 2013で中の人に聞いてみた – エンジニアtype | 転職type)(〖ノーカット掲載〗3年に及ぶクラウド移行。「創造的な仕事へのフォーカス」がついに始まる | フルスイング by DeNA)。
技術的な違い(アーキテクチャ、セキュリティ、運用の観点)
- インフラ構築とアーキテクチャの違い: オンプレミスでは自社内にネットワークを構築し、サーバーや機器を自社のニーズに合わせて選定・組み合わせて設計します。自社設備ゆえに既存システムとの連携もしやすく、カスタマイズの自由度が高い反面、設備の容量を超える負荷に対応するには新たな機器調達やアプリケーションの改修が必要になります。クラウドでは事業者が用意した巨大な共用インフラ上に論理的な自社システムを構築します。必要なサーバーやストレージ資源を数クリックで追加でき、従来は数か月かかった調達・構築プロセスをわずかな時間で完了できます。例えばAWSではビジネスニーズの発生に応じて即座にサーバーを立ち上げられるため、システム構築のリードタイムを大幅に短縮できます。またクラウド事業者は世界各地にデータセンターを分散配置しているため、オンプレミスと比べて災害耐性や可用性の面でも優れています。オンプレミスでは自社設備が故障した場合に業務停止やデータ損失のリスクがありますが、クラウドでは複数拠点にデータが冗長化されており、一箇所の障害でも別の拠点からサービス継続が可能です。
- セキュリティの違い: オンプレミス環境ではサーバーやネットワークを含むすべてのインフラを自社で直接管理できるため、自社だけの閉じたネットワーク内で高い安全性を確保しやすいとされています。自社のポリシーに沿ったきめ細かなセキュリティ対策(ファイアウォール設定や物理的な入退室管理など)を実装できる反面、その構築・維持には専門知識を持った人材と継続的な労力が必要です。一方、クラウド環境ではデータをインターネット上に預けるため、一見セキュリティ面で劣るとも言われますが、実際にはクラウド事業者側で高度なセキュリティ対策が施されています。例えばAWSではエンタープライズ企業と同等かそれ以上のセキュリティ基盤が提供されており、ユーザーはそれらを利用することで高い安全性を実現できます。クラウド利用者自身による設定ミスがない限り、データ暗号化や不正アクセス検知などの機能を駆使して安全性を保つことが可能です。また、セキュリティアップデートやパッチ適用などもサービス事業者が担う部分が多く、自社ですべて対応するオンプレミスに比べ負担軽減につながります。総じて、どちらの形態であっても適切なセキュリティ対策の実施が不可欠ですが、クラウドでは大規模事業者のセキュリティ投資メリットを享受できる点がポイントです。
- 運用管理の違い: オンプレミスではシステム構築から運用・保守に至るまですべての作業を自社で実施しなければなりません。サーバーのセットアップ、ソフトウェアのインストール、ネットワーク設定、障害対応、バックアップ取得など、専門部署や担当者を置いて継続的に運用する必要があります。そのため運用開始までに多くの手間と時間がかかり、また運用を維持するための人的リソースも確保しなければなりません。クラウドの場合、サービス事業者側でインフラの保守・監視を行っているため、ユーザー企業はその上で動くアプリケーションやデータの管理に注力すればよく、インフラ管理負担を大幅に軽減できます。例えばAWSではハードウェアの故障対応やディスク増設といった作業は利用者に意識させず自動化されています。結果として、クラウド利用時は比較的少人数のチームでもシステム運用が可能であり、オンプレミスのように大勢のインフラ管理者を抱える必要がありません。また運用監視やログ管理、スケーリングの自動化などを支援する各種サービスもクラウド上には揃っており、運用負荷をさらに下げることができます。
ビジネス的な違い(コスト、スケーラビリティ、導入メリット)
- コスト構造の違い: オンプレミスは設備投資(CapEx)型のコスト構造です。サーバーやストレージ機器、ネットワーク機器など必要なものを購入する初期費用が高額になりがちで、導入後も保守管理に人件費や電気代など継続的な費用が発生します)。十分な性能を確保するために、実際に必要な容量以上のハードウェアを前もって買っておかなければならないケースも多く、資金繰りや設備の減価償却を考慮した長期的予算計画が必要です。一方、クラウドは運用経費(OpEx)型のコスト構造で、初期投資をほとんど必要とせずにサービス利用を開始できます。月額や時間単位の従量課金で、使った分だけ支払うモデルのため、スモールスタートが可能で不要になればすぐにリソースを解放してコストを削減できます。例えばAWSでは新規プロジェクト立ち上げ時にハード購入費がゼロで始められ、実験的なサービスを低コストで試して、成果が出なければすぐ撤退するといった柔軟な戦略が取りやすくなります。ただし長期間にわたり大量のリソースを使い続ける場合、月々の利用料が積み重なってオンプレミスより高くつく可能性もあるため、リソースの無駄遣いをしない運用工夫は必要です。近年では大規模利用時に割引を受けられる料金プランや、予測可能な一定負荷はオンプレミスかプライベートクラウドで賄い、変動部分だけパブリッククラウドを使うといったハイブリッド戦略でコスト最適化を図る企業もあります。
- スケーラビリティ(拡張性)の違い: ビジネス環境の変化に応じてシステム規模を拡張・縮小できる柔軟性もオンプレとクラウドで大きく異なります。オンプレミスの場合、利用者やデータ量の増加に伴いサーバーの性能を向上させたい時は、新たな機器の追加購入や既存サーバーから新サーバーへの置き換えが必要となります。この垂直方向のスケールアップ(CPU・メモリ増強)には上限があり、また機器調達から設置・切り替えまでに時間とコストがかかるため、需要に即座に追従するのは容易ではありません。一方でクラウドの場合、必要に応じて水平スケール(サーバー台数の増減)やリソースサイズ変更を短時間で行えます。例えばAWSでは繁忙期に合わせてサーバー台数を一時的に増やし、閑散期に減らすといった操作が管理画面やAPIから即座に可能です。これにより、従来は数か月先を予測して前もって設備投資していたものが、リアルタイムの需要に合わせたリソース供給へと変わりました 。また世界中のリージョンに展開しているクラウドなら、海外進出する際にも現地にサーバーを用意する代わりに該当地域のクラウド拠点を利用してサービスを提供できるため、グローバルなスケーラビリティも飛躍的に高まります。こうした柔軟性の高さは、新規サービスの急成長や一時的な大量アクセスにも対応しやすいというビジネスメリットにつながります。
- 導入スピードとビジネス上のメリット: オンプレミス環境の構築は、要件定義から設備調達、設置、環境設定に至るまで長いプロセスを経る必要があります。新しいシステムを立ち上げる際にも実機を準備するリードタイムがあるため、ビジネス上「やりたいこと」がすぐに実現できないもどかしさがありました。クラウドの登場によって、この状況は一変しました。クラウドでは必要な時に必要なだけリソースを即座に調達できるため、ビジネスのアイデアを素早く形にして市場投入するアジリティ(俊敏性)が飛躍的に向上します 。例えば新サービスのプロトタイプをAWS上で数日中に構築し、ユーザーの反応を見ながら機能を追加・変更するといったリーンな開発手法が可能になりました。柔軟で自由、そして高速なITインフラ構築を可能にしたクラウドプラットフォームは、「最も革新的で変革力のある発明」の一つと言われるほど、企業のビジネス推進スタイルに大きなインパクトを与えています。さらにクラウド利用により、自社でインフラ維持管理に割く労力を削減し、その分エンジニアやIT部門の人材を本来のコア業務(新機能の開発やクリエイティブな課題解決など)にフォーカスさせることができます。このリソースの再配分効果も見逃せないビジネス上のメリットです。総じて、オンプレミスは綿密な計画と投資による「安定志向」のアプローチ、クラウドはスピードと柔軟性による「変化対応志向」のアプローチと言えるでしょう。
AWSの登場とクラウドの革新性
AWSがもたらした変化
Amazon Web Services (AWS) は2006年に最初のサービスを開始したクラウドプラットフォームであり、それまでのITインフラ利用モデルに革命をもたらしました (AWS の クラウドが選ばれる 10 の理由 | AWS)。AWS登場以前、企業は自前でサーバーを購入しデータセンターに設置して運用するのが一般的でしたが、AWSはインターネット経由で誰でも使えるオンデマンドのITインフラを提供しました。これはまるで電力や水道のように、必要な時に必要なだけ供給される「ユーティリティ型」のコンピューティングサービスです。この新しいモデルにより、「柔軟で、自由で、高速なITインフラ構築」が現実のものとなりました (なぜ、アマゾンは超爆速でサービスを進化させられるのか? AWS Summit Tokyo 2013で中の人に聞いてみた – エンジニアtype | 転職type)。物理的・技術的な制約の中では実現が難しかったスピードとスケーラビリティが手に入り、スタートアップから大企業まで規模を問わず革新的なサービスを次々と生み出せる土壌が整いました。
AWSはまた、クラウドという概念を業界標準にまで押し上げ、他のクラウドプロバイダー(Microsoft AzureやGoogle Cloud Platformなど)が次々参入するきっかけを作りました。世界190か国に数十万以上のユーザーを持つと言われるAWS (なぜ、アマゾンは超爆速でサービスを進化させられるのか? AWS Summit Tokyo 2013で中の人に聞いてみた – エンジニアtype | 転職type)は、現在では 世界36のリージョンにわたるグローバルインフラ上で200以上のサービスを提供し、数百万にのぼる企業や開発者コミュニティに利用されています (Global Infrastructure – AWS)。クラウド市場の拡大スピードは凄まじく、2022年から2027年に市場規模が倍増するとの予測もあります (On-Premise vs. Cloud: Understanding the Differences)。AWSはサービス開始以来、需要の拡大に応じてインフラ規模を爆発的に拡張し続けており、そのスケールメリットによってサーバーやネットワークの単価を下げ、累計100回以上もの価格値下げを実施してきました (AWS の クラウドが選ばれる 10 の理由 | AWS)。これは従来のオンプレミスでは考えられなかったスピードでのコスト効率改善であり、クラウドならではの経済性と言えます。
技術面でも、AWSはAmazon社内で培われた最新鋭のシステム技術を外部向けに公開する形でスタートした経緯があります (AWSとオンプレミスの違いとは?それぞれの利点と欠点を詳しく解説 | ITエンジニア派遣ならオープンアップITエンジニア)。そのため、当初から大規模分散システムや仮想化技術、セキュリティ対策などが高い水準で実装されていました。以降も年に数千を超えるアップデートや新サービスのリリースを継続し、ビッグデータ解析、AI/機械学習、IoT、サーバーレスアーキテクチャなど最先端のIT技術をユーザー企業が手軽に活用できるようにしています (AWSとオンプレミスの違いとは?それぞれの利点と欠点を詳しく解説 | ITエンジニア派遣ならオープンアップITエンジニア)。言い換えれば、AWSによって企業は自前で巨額の投資をしなくても最新テクノロジーの恩恵にあずかれるようになったのです。これらの変化は、ITインフラを扱うエンジニアの役割にも影響を与えました。従来はハードウェア管理やトラブル対応に追われていたインフラ担当者が、今ではクラウド上でのアーキテクチャ設計や自動化、セキュリティポリシーの整備など、より付加価値の高い業務に時間を割けるようになっています。「クラウドファースト」「サーバーレス化」といったキーワードが示す通り、AWSがもたらした変革は単なる技術トレンドに留まらず、ビジネス戦略や働き方にも及んでいるのです。
企業がAWSを導入する理由
では、数あるクラウドサービスの中で企業がAWSを選択する主な理由にはどのようなものがあるでしょうか。いくつか代表的なポイントを挙げます。
- 初期費用ゼロで素早く始められる: 前述の通り、AWSはサーバー購入などの初期投資なしで利用開始でき、必要になったときにすぐリソースを確保できます (AWS の クラウドが選ばれる 10 の理由 | AWS)。ビジネスの立ち上げにおいて「スピードは命」です。例えば新規事業のアイデアを思いついたら、その日のうちにAWS上で開発環境を構築し検証を始めることもできます。これはオンプレミスでは到底真似できない俊敏性です。あるスタートアップ経営者は「AWSのおかげでサーバー調達に悩むことなく事業に集中できた」と語っており、クラウド導入によるタイムトゥマーケット短縮は多くの企業に共通するメリットです。
- 従量課金とスケーラビリティによるコスト最適化: AWSは使った分だけ料金を支払う従量課金制であり、リソースの増減も柔軟に行えるため、無駄な設備投資を避けられます (AWS の クラウドが選ばれる 10 の理由 | AWS)。需要に応じてサーバー台数や性能を増減できるので、「普段は小規模で運用し、繁忙期だけスケールアップ」「テスト期間だけ大量のサーバーを使い、終わったら停止するといったメリハリ運用」が可能です (AWS の クラウドが選ばれる 10 の理由 | AWS)。これにより、オンプレミスでは難しかったコストの弾力的コントロールが実現できます。大企業の中には「クラウドでもオンプレミスと同程度のコストにできる」という仮説を立てて全システムをAWSへ移行し、効率的な運用でそれを証明した例もあります (〖ノーカット掲載〗3年に及ぶクラウド移行。「創造的な仕事へのフォーカス」がついに始まる | フルスイング by DeNA)。AWSは利用状況に応じた割引プランやリザーブドインスタンス(長期利用割引)なども提供しており、正しく使えばコスト優位性を発揮できる仕組みが整っています。
- 豊富なサービスと最新技術へのアクセス: AWSは単なる仮想マシン提供に留まらず、データベース、ストレージ、ネットワーキング、機械学習、IoT、分析基盤、DevOpsツールなど200以上に及ぶ幅広いサービス群を提供しています (AWSとオンプレミスの違いとは?それぞれの利点と欠点を詳しく解説 | ITエンジニア派遣ならオープンアップITエンジニア)。そのため、企業はAWS上で必要なものを選ぶだけで、複雑なシステムも一つのプラットフォーム上に構築できます。例えば、ウェブアプリ開発であればEC2でサーバーを立て、RDSでデータベースを利用し、S3に画像など静的ファイルを保存する、といった形で基本的な構成要素がすべてAWS内で揃います。さらに、高度な分析にはAWSのAIサービス(Amazon SageMakerなど)を、グローバル展開にはクラウドフロントやマルチリージョン配置を、といった具合に必要に応じて最新技術を取り入れられます。オンプレミスでこれを実現しようとすると、莫大な費用と時間をかけて機材導入・技術習得をしなければなりません。AWSを利用することで、小さな企業でも世界トップクラスのITインフラと技術スタックにアクセスでき、イノベーションを起こしやすくなります。
- 高い信頼性と実績: AWSはクラウド市場をリードしてきた実績から、多くの企業や機関での採用例があります。そのコミュニティとナレッジの豊富さも安心材料です。AWSは14年以上連続でガートナーのクラウド分野マジッククアドラントでリーダーに選出されており、信頼性・セキュリティ・スケーラビリティにおいて高い評価を受けています (Global Infrastructure – AWS)。たとえば金融機関や官公庁などミッションクリティカルな分野でもAWSが採用されており、日本国内でも大手企業のAWS移行事例が数多く報告されています。AWSのデータセンターは世界でも屈指の厳格なセキュリティ対策と24時間365日の監視体制を敷いており、自社運用では実現が難しいレベルの可用性 SLA を提供しています。これほど多くの企業がAWSを選んでいる理由として、「自分たちでやるより安全で信頼できる」「世界中どこでも同じ品質のインフラを使える」といった安心感があることも大きいでしょう。実際、AWSには業種・規模を問わず数百万のアクティブユーザーがおり、スタートアップからエンタープライズ、公共部門に至るまであらゆるユースケースがAWS上で動いています (Global Infrastructure – AWS)。
以上のように、AWSが支持される理由はコスト、スピード、技術力、信頼性と多岐にわたります。もちろんクラウド導入にあたっては自社の要件や人材スキルを考慮する必要がありますが、AWSはそうした課題に対応するパートナー企業やサポートプログラムも充実させています。総合的なエコシステムが確立されている点もAWSを採用する大きなメリットと言えるでしょう。
AWSの主要サービス紹介(EC2、S3、RDS)
AWSには非常に多くのサービスがありますが、ここでは特に基盤となる代表的なサービスであるEC2、S3、RDSの3つを紹介します。これらはそれぞれ「サーバー」「ストレージ」「データベース」に相当するサービスで、オンプレミスでいうところの物理サーバーやNAS、データベースサーバーの役割をクラウド上で担います。AWS初心者の方はまずこの3つを押さえておくと、クラウドで何ができるのかイメージしやすくなるでしょう。
EC2とは?(仮想サーバーの役割とメリット)
Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) とは、AWSが提供するクラウド上の仮想サーバーサービスです。簡単に言えば、インターネット経由で利用できる「レンタルサーバー」であり、自分専用のサーバーマシンをソフトウェア的に作成・起動できます。Amazon EC2により、安全で必要に応じてサイズ変更可能なコンピューティング能力をオンデマンドで利用することができます (AWSとオンプレミスの違いとは?それぞれの利点と欠点を詳しく解説 | ITエンジニア派遣ならオープンアップITエンジニア)。利用者はCPUやメモリ、ストレージ容量、OS(Windows/Linux)などを選択して仮想マシン(インスタンス)を起動し、リモート接続でその中にアプリケーションをインストールして使います。従来、物理サーバーを手配すると設置からセットアップ完了まで数日〜数週間かかることもありましたが、EC2なら数分で準備が整います。また後から必要に応じてサーバーのスペック(CPU数やメモリ容量など)を柔軟に変更でき、負荷分散のために複数インスタンスを立てたり、障害に備えて別のデータセンターにインスタンスを複製するといった冗長化も容易です (AWSとオンプレミスの違いとは?それぞれの利点と欠点を詳しく解説 | ITエンジニア派遣ならオープンアップITエンジニア)。例えばWebアプリが好評でアクセスが急増した場合でも、EC2インスタンスを追加起動することで素早く対応でき、ピークが過ぎたら停止してコストを抑えることができます。これらのメリットから、EC2はAWSの中心的サービスとして広く使われており、社内システムのサーバー移行先や、新規サービスのホスティング先として真っ先に検討されます。
S3とは?(クラウドストレージの活用)
Amazon S3 (Simple Storage Service) とは、AWSが提供するオブジェクトストレージサービスです。オブジェクトストレージとは、インターネット経由で任意のファイル(オブジェクト)を格納・取得できるオンラインストレージのことで、容量無制限かつ高い耐久性を持つのが特徴です。Amazon S3は業界トップクラスのスケーラビリティ(拡張性)、データ可用性、セキュリティ、パフォーマンスを備えたストレージサービスであり、必要なだけデータを保存して必要な時に取り出すことができます (AWSとオンプレミスの違いとは?それぞれの利点と欠点を詳しく解説 | ITエンジニア派遣ならオープンアップITエンジニア)。例えば、バックアップファイルの保管場所としてS3にデータを置いておけば、自社サーバーに障害が発生してもデータを失うリスクを最小限にできます。実際、S3はデータを最低3つの異なる設備(AZ: アベイラビリティゾーン)に冗長化して保存しており、**99.999999999%(11ナイン)**という非常に高い耐久性を実現しています (個人的な備忘録:AWS認定試験で頻出のAmazon S3ストレージ …)。これは100億個保存したデータのうち年間で紛失する可能性が1個程度というレベルの驚異的な信頼性です。オンプレミスでここまでのデータ保護を行うには、大掛かりな冗長構成や遠隔地バックアップが必要ですが、S3なら標準機能として提供されます。
S3の用途は多岐にわたります。例えばWebサイトで配信する画像や動画ファイルをS3に置いておけば、大量アクセス時にもAWSの大容量帯域で高速に配信できます。またログデータや解析用データのアーカイブ先としても適しています。近年ではデータレイク(企業内の様々な生データを集約して蓄積する仕組み)の保管場所としてS3が使われるケースも増えています。さらに、S3に保存したファイルに対してアクセス権を細かく設定したり、暗号化やバージョン管理、ライフサイクル(一定期間後に自動で安価なストレージクラスへ移行する設定)を適用したりと、企業利用に必要なセキュリティ・コンプライアンス機能も充実しています (AWSとオンプレミスの違いとは?それぞれの利点と欠点を詳しく解説 | ITエンジニア派遣ならオープンアップITエンジニア)。これらを利用することで、「重要データは社内に置かないと不安」という懸念にも対応できるよう設計されています。料金面でも、S3は使った容量とリクエスト数に応じた課金で、低頻度アクセス向けの安価なストレージクラスも用意されているなど、コスト効率高く大量データを扱えるのも魅力です。
RDSとは?(データベース管理の簡略化)
Amazon RDS (Relational Database Service) とは、AWSが提供するマネージド型のリレーショナルデータベースサービスです。リレーショナルデータベース(RDB)は業務システムで広く使われるデータベースで、表形式のデータを扱いSQLで操作するものです。オンプレミス環境では、データベース用のサーバーにソフトウェア(例えばOracleやMySQLなど)をインストールし、チューニング・バックアップ・障害対策をDB管理者が行う必要がありました。RDSを使うと、そうしたデータベースの構築・運用をAWSが大部分肩代わりしてくれます。Amazon RDSは低コストかつ高パフォーマンスなリレーショナルデータベース環境を手軽に作成できるサービスであり、ユーザーは数クリックでクラウド上にデータベースを立ち上げられます (AWSとオンプレミスの違いとは?それぞれの利点と欠点を詳しく解説 | ITエンジニア派遣ならオープンアップITエンジニア)。対応しているデータベースエンジンも豊富で、Amazon Aurora(独自高速エンジン)や MySQL、MariaDB、Oracle Database、Microsoft SQL Server、PostgreSQLの計6種類から選択可能です。つまり、現在オンプレミスで使っているデータベースと同じ種類をAWS上で動かすこともでき、既存のアプリケーションやSQLクエリをほとんど変更せずにクラウドへ移行できます。
RDSを利用する利点としては、まず運用管理が格段に楽になる点が挙げられます (AWSとオンプレミスの違いとは?それぞれの利点と欠点を詳しく解説 | ITエンジニア派遣ならオープンアップITエンジニア)。AWS側で自動的にデータベースのバックアップを取得してくれたり、ソフトウェアパッチ適用や障害発生時のフェイルオーバー(自動切替)が組み込まれていたりするため、従来管理者が深夜に対応していたような作業が不要になります。次にスケーラビリティと可用性です。RDSではCPUやメモリを後から増強したり、読み取り専用のリプリカを追加して読取性能を水平展開したりすることが簡単にできます。また、同じデータのコピーを別のアベイラビリティゾーンに自動同期するマルチAZ配置を有効化すれば、片方のデータセンターが停電してももう片方でサービスを継続するといった高可用性構成もワンクリックで実現します。さらにストレージ暗号化やSSL接続、細かなアクセス権管理などセキュリティ機能も充実しており、機密データの扱いにも耐える設計です。こうした総合力の高さから、RDSは企業の基幹システムや大規模Webサービスのデータベースにも多数利用されています。要件に応じて最適なDBエンジンを選び、運用管理の負担を最小化しながら信頼性の高いデータベース基盤を得られるのがRDSの魅力です。
企業はオンプレミスとクラウドのどちらを選ぶべきか?
オンプレミスとクラウドにはそれぞれ利点・欠点があり、どちらが優れているかは一概には言えません。重要なのは、自社のビジネス要件やIT戦略に照らして最適な形態を選ぶことです。実際の企業では、両者を組み合わせたハイブリッド運用も一般的になりつつあります。ここでは「オンプレミスかクラウドか」の判断軸として、ハイブリッドクラウドという選択肢と、いくつかの適用事例(使い分けの例)を紹介します。
ハイブリッドクラウドという選択肢
一つの解決策として、オンプレミスとクラウドを併用するハイブリッドクラウドがあります。ハイブリッドクラウドとは、自社運用の環境(オンプレミスやプライベートクラウド)とパブリッククラウド(AWS等)をネットワークで接続し、一つのシステムを分散して運用する形態です (ハイブリッドクラウドとは?3つのメリットと運用課題を解説!導入 …)。たとえば、基幹データは社内サーバーに置きつつ、Webアプリケーションのフロントエンド部分はAWS上で稼働させる、といった構成が可能です。このようにすれば、機密性の高いデータは社内に留めセキュリティを担保しつつ、外部向けのサービス部分にはクラウドのスケーラビリティを生かすことができます。また、既存のオンプレミス資産を活かしながら徐々にクラウドに移行していく「段階的クラウド化」の戦略も取りやすくなります。もしオンプレミスかAWSかどちらか一方に決めきれない場合は、両者を連携利用するハイブリッドクラウドを検討してみるのもよいでしょう (AWSとオンプレミスの違いとは?それぞれの利点と欠点を詳しく解説 | ITエンジニア派遣ならオープンアップITエンジニア)。実現したいシステム像やコスト要件に合わせて最適な部分に最適なプラットフォームを割り当てることで、メリットの良いとこ取りが可能です。AWSもオンプレミスとの接続サービス(AWS Direct Connect など)や、一部AWSサービスを自社設備内で実行できる仕組み(AWS Outposts など)を提供しており、ハイブリッド環境を積極的に支援しています。将来的に完全クラウドへ移行するにせよ、当面は併用するにせよ、ハイブリッドクラウドという柔軟な選択肢を持っておくことはリスクヘッジと技術検証の面で有益です。
ビジネスにおける適用事例
最後に、オンプレミスとクラウドの使い分けについて、どのようなケースでどちらを選ぶと適しているかいくつか例を挙げます。
- 高度なセキュリティや規制遵守が最優先のケース(オンプレミスが有利): 金融機関や官公庁など、扱うデータの機密性が極めて高く厳格なセキュリティ対策が求められる場合、オンプレミスを選ぶ企業もあります。自社要件に合った強固なセキュリティ対策を自分たちの手で柔軟に実装でき、外部から直接アクセスされる心配がないオンプレ環境は安心感があります (オンプレミスとクラウドの違いを7つの項目で徹底比較!おすすめなケース各3選も紹介)。また既存のレガシーシステム(メインフレームなど)と密接に連携する必要がある場合や、データを社内に閉じたままリアルタイム処理したい産業制御システムなども、オンプレミスで構築する例が見られます。ただし近年はクラウドでも金融業界向けのセキュリティ基準を満たすサービスが提供されており、必ずしもオンプレ一択ではなくなっています。そこで一部機密データのみオンプレミスに残し、一般データやWebサーバーはクラウドへ移すといったハイブリッド構成が採られることも多いです。
- 新規事業立ち上げやスタートアップのケース(クラウドが有利): ビジネスのスタート段階では、とにかく初期費用を抑えてスピーディにサービスインすることが重要です。この場合、AWSのようなクラウドはまさに理想的な選択肢です。新しいプロジェクトを思い立ったら、サーバー発注を待つ必要はなくAWS上で即座に環境を準備できるため、リリースまでの期間を大幅に短縮できます (オンプレミスとクラウドの違いを7つの項目で徹底比較!おすすめなケース各3選も紹介)。また需要が未知数でも、ローリスクで始めて人気が出れば自動でスケールアウトし、失敗しても大きなサンクコストを残さず撤退できます (オンプレミスとクラウドの違いを7つの項目で徹底比較!おすすめなケース各3選も紹介)。スタートアップ企業の多くが自前ではなくクラウドでサービスを提供しているのは、初期コストとスピードの点で合理的だからです。
- IT人材や運用リソースが不足しているケース(クラウドが有利): 社内に専門のITインフラ要員がいない、または人数が少ない場合もクラウドが適しています。クラウドサービスでは前述の通り保守・管理作業の多くを事業者側で担ってくれるため、限られた人員でもシステムを運用可能です (オンプレミスとクラウドの違いを7つの項目で徹底比較!おすすめなケース各3選も紹介)。たとえば中小企業で社内システム担当が兼任で1人しかいないような場合、オンプレミスでサーバーを何台も維持するのは現実的ではありません。そのような企業がメールサーバーやファイルサーバーをクラウド(AWSやSaaS)に移行し、日々の運用負荷を減らしている例は珍しくありません (オンプレミスとクラウドの違いを7つの項目で徹底比較!おすすめなケース各3選も紹介)。このように、自社リソースが限られている場合はクラウドのマネージドサービスを活用することで、“任せられるところは任せてしまう”のが得策です。
- 既存資産を活かしつつ段階的にクラウド活用を進めたいケース(ハイブリッド): 大企業などで過去に巨額の投資をして構築したデータセンターやオンプレミスシステムがある場合、いきなり全部をクラウドに捨てて移すのは現実的でないことがあります。そうした場合に、まず新規システムや一部システムからクラウド化し、徐々にクラウドへの移行比率を増やしていく戦略が考えられます。この際、既存オンプレ環境とAWS等クラウドを専用線やVPNで接続し、一体化したシステムとして運用することで、ユーザーから見て違和感のない形で移行を進められます。例えば社内の認証基盤はオンプレのActive Directoryを使いつつ、新しく導入する業務アプリケーションはAWS上で動かし、認証連携だけ社内と繋げる、といった方法です。ハイブリッドにしておけば、問題発生時には一部機能だけオンプレにフォールバックするといった柔軟な対応もできます。大規模企業の中には3年程度かけて全システムをクラウドに移行した事例もあり (〖ノーカット掲載〗3年に及ぶクラウド移行。「創造的な仕事へのフォーカス」がついに始まる | フルスイング by DeNA)、そのようなプロジェクトではハイブリッド期間をうまく活用して社員のスキル習得やシステム改修を並行して行っています。
- 完全クラウドへの移行を遂げたケース(クラウドフル活用): 近年では、最初はオンプレミス中心だった企業がすべてのシステムをクラウド(主にAWS)に移行し終える例も出てきました。例えば国内大手IT企業のDeNAは約300ものサービスを自社オンプレミスで運用していましたが、2021年にそれらを100%クラウド(AWS)へ移行完了しました。この移行により、同社はインフラ運用負荷の大幅な軽減と、「創造的な仕事へフォーカスできる環境」の実現をアピールしています (〖ノーカット掲載〗3年に及ぶクラウド移行。「創造的な仕事へのフォーカス」がついに始まる | フルスイング by DeNA)。クラウド全面移行は容易ではありませんが、実現できればシステムの弾力性や災害耐性が飛躍的に向上し、グローバル展開や事業継続計画(BCP)の面でも優位に立てます。ただし全クラウド化が必ずしも最適解ではない場合もあるため、自社のIT戦略に照らして段階的・選択的に判断することが重要です。
以上のように、企業の事情や目的によって最適な形は異なります。オンプレミスとクラウドのいずれかを排他的に選ぶのではなく、適材適所で組み合わせる発想がこれからの主流になっていくでしょう。大切なのは、両者の特徴を正しく理解し、自社のビジネスにとって最も価値を生む形でITインフラを設計することです。
まとめ – AWSを理解しクラウドの未来を考える
オンプレミスとクラウドの違い、およびAWSがもたらした革新について、技術面・ビジネス面の双方から詳しく解説しました。オンプレミスはカスタマイズ性や自社コントロールの高さが魅力であり、クラウドは俊敏性やスケーラビリティ、イニシャルコストの低さが強みです。AWSはクラウド利用を世の中に普及させ、この10数年で企業ITの常識を塗り替えてきました。IT未経験の方にとっても、本記事で述べたポイントをおさえればオンプレとクラウドの違いをイメージできたのではないでしょうか。
経営層やマネージャーの視点では、クラウドの登場によってIT投資の考え方が「設備資産の購入」から「サービスの活用」へとシフトしつつあることを理解することが重要です。AWSのようなクラウドサービスを上手に使えば、ビジネスのスピードアップやコスト最適化、新規技術への迅速な対応が可能となり、競争力強化につながります。一方で、自社の重要データ管理や既存システムとの整合性など、クラウドに移せない(移さない)部分とのバランスも考慮しなければなりません。その答えの一つがハイブリッドクラウドであり、多くの企業が試行錯誤しながら最適解を模索しています。
最後に、クラウドの未来について触れれば、AIやIoTの普及、リモートワークの拡大などにより、クラウド活用は今後さらに進むと予想されます。AWSをはじめ主要クラウド事業者はますますサービスを拡充し、多様なニーズに応えるプラットフォームへと進化していくでしょう。オンプレミスとクラウドのどちらが優れているかを論じる時代は終わりつつあり、「どう組み合わせて価値を創出するか」を考えるフェーズに入っています。ぜひ本記事の内容を参考に、自社にとって最適なITインフラ戦略を検討してみてください。オンプレミスもクラウドも正しく理解し使いこなすことで、これからのビジネスの可能性は大きく広がっていくはずです。