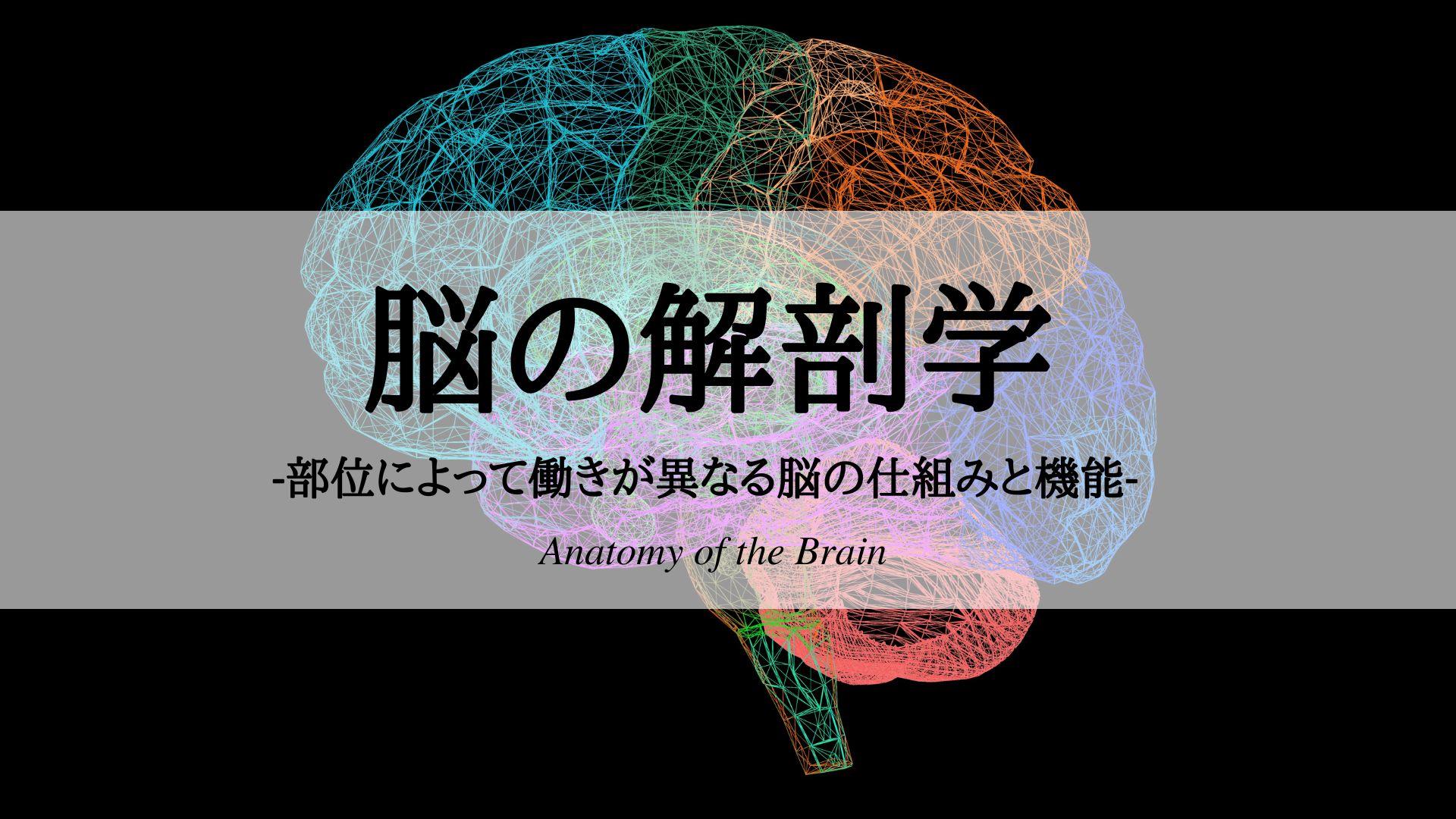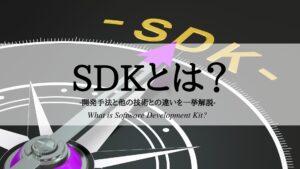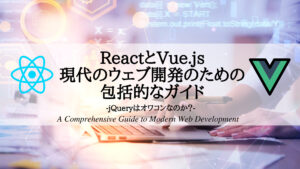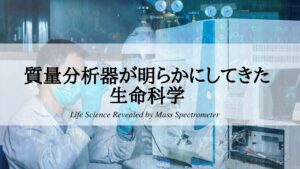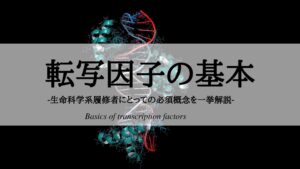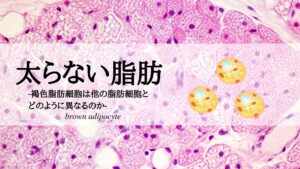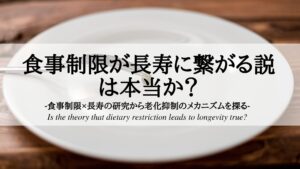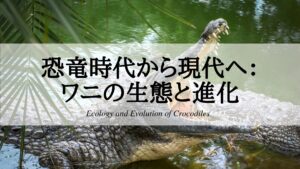脳の機能は21世紀の科学においても未解明な部分が多くあります。
しかしながら、解剖学という観点においては、多くの知見が蓄積されていて、脳のどの領域がどういった機能を司っているか、多くは明らかとなっているのです。
本記事では、脳の解剖と部位によって働きが異なる脳の仕組み、そして機能についてご紹介していきます。
本記事は医療系の国家試験を対象としたものではありません。ヒトの脳について興味を持たれた方に目を通していただきたい脳部位の機能を記載していっています。
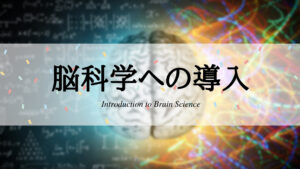
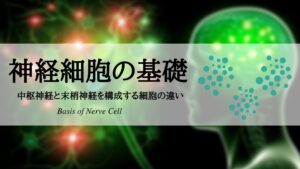

ヒトの脳の解剖
ヒトの脳は握りこぶし2つ分のサイズとよく言われるように、サイズ的にはそこまで大きくありません。知能の差と脳のサイズには関連性が無いこともわかっています。ただ、ヒトの脳は部位によって機能が異なることがわかっているのです。
以下では脳の解剖学的名称と役割について見ていきます。
- 大脳(Cerebrum):
- 大脳は脳の最大の部分であり、認知機能や情報処理を担当しています。
- 思考、感情、記憶、学習、意思決定など、高次の神経活動が行われる場所です。
- 大脳は左右の半球に分かれており、それぞれが異なる機能を持っています。左半球は言語処理や論理思考に、右半球は空間認識や芸術的な活動に関与しています。
- 小脳(Cerebellum):
- 小脳は運動制御と協調を担当しています。
- 身体の運動や姿勢の調整、バランスの維持などに重要な役割を果たしています。
- 小脳の障害は、運動の不調やバランスの問題を引き起こす可能性があります。
- 中脳(Midbrain):
- 中脳は視覚、聴覚、運動反応など、さまざまな感覚情報の処理を担当しています。
- 視床として知られる一部は、視覚情報の中継や処理を行います。
- 起床や注意の制御にも関与しています。
- 脳幹(Brainstem):
- 脳幹は自律神経系の制御や生命維持機能を担当しています。
- 呼吸、心拍、血圧、消化など、自動的な体内機能の調整を行います。
- 脳幹の一部である延髄(Medulla Oblongata)は、基本的な生命維持機能を制御する重要な役割を果たしています。
このように、脳は部位によってそれぞれ担当している役割が大きく異なることがわかります。
興味深いことに、脳の役割はそれぞれの部位の中でもさらに細分化されています。例えば、大脳の中でもある部位は視覚に関する機能を担っていて、ある部位は聴覚に関する部位を担っている、という具合にです。
次からは各脳のさらに部位の違いによる機能を見ていきましょう。
大脳の部位による機能の違い-ブロードマンの脳地図-
機能による脳の呼び名の違いを見る前に、まずは解剖学的な部位による脳の名称の違いを見ていきましょう。
脳は大きくは前、頂点、横、後、の4部位で分けられ、それぞれlobe(葉)という言葉を用いて前頭葉、後頭葉、頭頂葉、側頭葉と表現されます。
各部位ごとの大雑把な役割も含めて見てみましょう。
- 前頭葉(Frontal Lobe):
- 高次の認知機能、意思決定、判断力、行動制御、社会的行動などに関与しています。
- 前頭前野(Prefrontal Cortex)は、思考の計画と実行、情報の保持、注意の制御などを担当します。
- 後頭葉(Parietal Lobe):
- 身体感覚、空間認識、身体の位置や方向の把握などに関与しています。
- 触覚や温度感覚、痛みなどの感覚情報を処理する部位も含まれます。
- 頭頂葉(Occipital Lobe):
- 視覚情報の処理と解釈を担当します。
- 視覚野(Visual Cortex)がこの葉に位置し、色や形、動きなどの視覚的な特徴を解析します。
- 側頭葉(Temporal Lobe):
- 聴覚情報の処理や、言語理解、記憶、感情制御などに関与しています。
- 聴覚野(Auditory Cortex)や言語関連の部位(Wernicke’s Area)も含まれます。
これらの部位は今日に至っても脳の解剖学において、最も最初に学ぶ箇所の一つであり、脳の機能を語る上では外せない重要語句です。
この解剖学的な区分に合わせて、大脳を機能で分類する呼び方もあります。
ブロードマンの脳地図と大脳の機能分類
20世紀初頭、アメリカにコーネル・ウォーレン・ブロードマン(Korbinian Brodmann)という神経学者がいました。彼はヒトの大脳を詳細に調べ上げることで、各脳部位ごとに働きが異なることを脳の地図としてまとめ上げました。今日でもその脳地図はブロードマンの脳地図として非常に有名です。
ブロードマンの脳地図では50以上の番地がつけられていますが、解剖学の導入においては、まずは有名どころの脳領域のみ見ていきましょう。
視覚野(Visual Cortex)、聴覚野(Auditory Cortex)、運動野(Motor Cortex)、前頭前野(Prefrontal Cortex)の4つの領域について各領域の場所と機能を見ていきます。
- 視覚野(Visual Cortex):
- これは大脳の後頭葉に位置し、視覚情報を処理する役割を果たしています。
- 視覚野は、光の刺激を脳が理解できる形式に変換し、視覚的な情報を解釈します。
- 視覚野は、色や形、動きなどの視覚的な特徴を識別し、物体や環境を認識するのに重要です。
- 聴覚野(Auditory Cortex):
- これは大脳の側頭葉に位置し、聴覚情報を処理する役割を果たしています。
- 聴覚野は、音の振動を脳が理解できる信号に変換し、音の高さ、音色、音の方向などを解釈します。
- 聴覚野は、言語の理解や音楽の鑑賞など、音に関する様々な能力に関与します。
- 運動野(Motor Cortex):
- これは大脳の前頭葉に位置し、運動制御を担当しています。
- 運動野は、身体の筋肉を制御するための信号を送り、意志的な運動を可能にします。
- 運動野は、細かな運動制御や運動計画の立案に関与し、運動の正確さと協調性を維持します。
- 前頭前野(Prefrontal Cortex):
- これは大脳の前頭葉の一部であり、高次の認知機能や行動の調整を担当しています。
- 前頭前野は、意思決定、計画、社会的な行動、判断力、注意力の管理などに関与します。
- 人格形成や社会的な行動パターンの形成にも重要な役割を果たしています。
これらの脳部位は、各領域によって形成する細胞も処理する情報も、そして情報処理の方法も異なり、領域ごとに理解する必要があります。
視覚や聴覚一つをとっても人間が科学の力を借りても理解しきれない理由がこの複雑性であったりします。
大脳の基底部の解剖と機能 -大脳基底核(Basal Ganglia)-
ブロードマンの脳地図を始め、脳の解剖学的な理解の古典は大脳皮質(表面の脳)をベースに論じるものが多い印象です。
もちろん大脳皮質においても、重要な機能は多く存在しますが、脳の興味深いところはその階層構造で、脳の中心にはより人間らしい機能を司る中枢が存在します。
この脳の深部を脳の基底部と呼び、その神経構造の総称を大脳基底核(Basal Ganglia)と呼びます。
大脳基底核(Basal Ganglia)
大脳基底核(Basal Ganglia)は脳の深部に位置する神経構造の総称で、主に大脳の基底部に位置しています。
主に、と呼ぶのは大脳だけの関わりでは無いためです。中脳や脳幹の構造とも密接に関わりながら、高次機能を担う大脳基底核は形成されます。
以下では、大脳基底核の主要な登場人物を見ていきましょう。
- 線条体(Striatum):
- 線条体は大脳基底核の主要な部分で、大脳の基底部に位置しています。
- 重要な役割の一つは運動制御であり、運動の開始と抑制を調整します。また、報酬系にも関与し、学習と動機付けに関連しています。
- 球状核(Globus Pallidus):
- 球状核は線条体の下に位置し、運動の調整と抑制を補完する役割を果たします。
- ダイレクト経路とインダイレクト経路を通じて、運動の適切な制御を支援します。
- 黒質(Substantia Nigra):
- 黒質は中脳の一部であり、ドーパミンを産生します。
- 黒質のドーパミンは運動制御に重要な役割を果たし、パーキンソン病などの運動障害が起こる原因となることがあります。
- 被殻核(Nucleus Accumbens):
- 被殻核は報酬系に関与し、快楽や動機付け、学習、褒賞に関連する神経伝達物質の放出を調節します。
これらの解剖学的な部位は報酬系や運動制御、学習といった脳の高次機能と関連付けられます。
大脳基底核の神経細胞が何らかの理由で障害を受けると、このような高次機能の一部または全部が奪われてしまうということになります。
大脳辺縁系-海馬・帯状回・扁桃体-
表面の脳の部位を大脳皮質と呼ぶということは先程少し触れました。
この文脈において、脳の機能を解剖学的に見ていくとそれぞれ脳の場所によって視覚、聴覚といった感覚に対してマッピングされているという話も先程しましたね。
ただ、この説明はいくつか詳細な内容が不足しています。
というのも、大脳皮質は実際には脳の表面だけの話ではなく、大脳基底核と脳の表面の間の部分も大脳皮質にあたるからです。
特に大脳皮質の中で古皮質、旧皮質、中間皮質、皮質下核を総称して大脳辺縁系と呼び、高次機能の多くを担っています。
それこそ、脳の部位の中で最も有名な部位の一つである海馬も大脳辺縁系に含まれています。
以下では大脳辺縁系に含まれるいくつかの部位を役割とともに見ていきましょう。
海馬の働きと機能
海馬はより詳細には、側頭葉内に位置し、大脳辺縁系に含まれています。海馬は、ご存知の通り新しい情報の記憶の形成と整理に関与します。
「記憶=海馬」というのは皆様も一度は耳にされたことがあると思います。
実際に記憶の話をするともう少し複雑な記憶の種類やメカニズムについて触れないといけないわけですが、ここでは海馬についてだけもう少し触れていきますね。海馬は、新しい記憶の定着と記憶の維持に関わっています。例えば、新しい場所、人物、事象等の記憶に関しては海馬が主たる働きを担っています。
また、海馬は空間認識やナビゲーションの機能も有しているとされています。
自分たちが空間的にどこに位置するか、そしてどこに向かうかのナビゲーションを海馬の細胞に記憶するようなイメージです。
帯状回の働きと機能
帯状回は感情の形成と処理、学習と記憶に関わりを持つ部位です。大脳辺縁系の各部位を結びつける機能を持っています。
帯状回の一部の領域は自律神経系への作用や、発声(単語の発声、歌)への関与も報告されています。
扁桃体の働きと機能
扁桃体は感情の中枢とも呼ばれ、不安や情動への関与が最も機能として報告されています。
扁桃体の障害によって、これまで恐かったものが恐くなくなったり、経験によって恐くなるはずの対象に対して恐くならなかったりするなどの情動異常行動が生じると言われています。
まとめ
非常にかいつまみながら進めてきた脳の解剖と機能ですが、いかがでしたでしょうか。
脳の各部位における機能や働きは医学生や医療系の学生であれば記憶が必須なものの、他の領域の方々は「なるほどそんな領域もあるんだ」というレベルで問題ないと思います。
ただ、重要なことは各領域がごとにあまりにも異なる機能を担っており、我々の脳機能は非常に複雑であるという点です。
本記事は概論として、今後領域特異的に何か話になるたびに膨らませていきます。
それではまた別の記事でお会いしましょう。