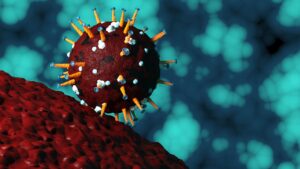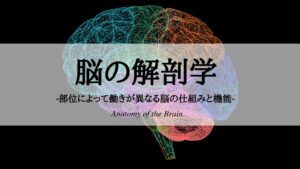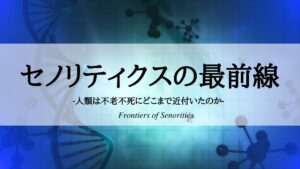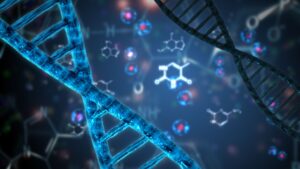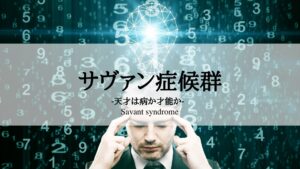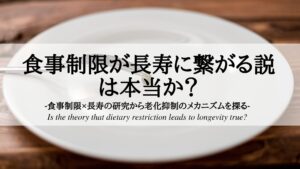はじめに:疫学研究とは?私たちの健康を支える科学
私たちの健康は、日々の生活習慣、環境、そして遺伝的要因など、様々な要素によって複雑に影響を受けています。疫学研究は、特定の集団において、病気の頻度、分布、そして原因を統計学的に調査・研究する学問分野であり、これらの複雑な関係性を解き明かすための重要なツールです 1。公衆衛生の分野において、疫学は病気の予防、健康増進、そして効果的な医療政策の策定に不可欠な情報を提供し、社会全体の健康水準の向上に貢献しています.2 生活習慣病、がん、認知症といった現代社会における主要な健康課題に対し、疫学研究は多くの重要な知見をもたらしてきました 1。
特定の地域住民を対象とした長期的な研究は、病気の発生要因や予防法を明らかにする上で特に重要な役割を果たします 5。なぜなら、私たちの生活習慣や環境要因が、時間をかけてどのように健康に影響を与えるのかを詳細に把握することができるからです 2。このような長期的な視点を持つ研究によって、初めて慢性的な病気の進行や、生活習慣のわずかな変化が数十年後に及ぼす影響などを理解することが可能になります。
日本における疫学研究の代表的な例として挙げられるのが、福岡県糟屋郡久山町で1961年から継続されている「久山町研究」です 1。この研究は、当初脳卒中の実態調査を目的として開始されましたが 1、その後、虚血性心疾患、糖尿病、脂質代謝異常、認知症など、生活習慣病全般をテーマとする大規模な疫学調査へと発展しました 1。高い追跡率と世界的に見ても稀な高い剖検率を誇る久山町研究は、国内外から注目を集める、日本の疫学研究を牽引する存在です 2。

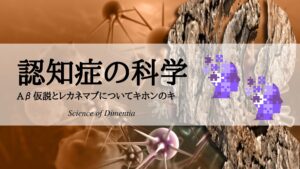
久山町研究:福岡県久山町における半世紀を超える健康調査
研究開始の背景と目的:脳卒中研究から生活習慣病全般へ
久山町研究が開始された背景には、1960年代に日本の脳卒中による死亡率が世界的に見て非常に高かったことに対する疑問がありました 2。1960年のローマで開催された世界神経学会議で、日本の脳卒中死亡率が33カ国中最も高く、特に脳出血の割合が高いことが示され、日本の医師が作成する死亡診断書の記載に問題があるのではないかという指摘がなされました。しかし、当時の日本にはこの指摘に反論する明確な証拠がありませんでした。そこで、地域における脳卒中の実態を詳細に調べることを目的として、久山町研究が開始されたのです 3。
研究開始から50年以上の歳月が流れる中で、久山町研究のテーマは脳卒中の疫学調査から、虚血性心疾患、糖尿病、脂質代謝異常、メタボリックシンドローム、動脈硬化の病理学的検討、認知症、慢性腎臓病、肝疾患、眼科疾患など、生活習慣病全般へと大きく広がりました 1。この研究の発展は、単に特定の病気を調べるだけでなく、生活習慣と様々な病気との関連性を総合的に理解しようとする、研究者たちの熱意の表れと言えるでしょう。
研究の方法:住民全体を対象とした継続的な健康診断、追跡調査、そして高い剖検率
久山町研究は、福岡市の東に隣接する糟屋郡久山町において、原則として40歳以上の全住民を対象に実施されています 2。研究開始当初の久山町の年齢構成は日本の平均とほぼ同じであり、特定の偏りのない集団として、長期にわたる追跡調査に適していると考えられました 3。1961年の第1集団を皮切りに、数年ごと(近年は5年ごと)に一斉健診が実施され、これまでに計13のコホートが継続的に追跡されています 3。
この研究の大きな特徴の一つは、高い受診率(約80%)と99%以上の追跡率です 2。研究スタッフによる丁寧な検査や対応、そして住民の積極的な協力によって、このような高い精度でのデータ収集が実現しています 2。また、久山町研究が世界的に注目される最も大きな理由の一つが、75%から80%という驚異的な剖検率です 2。住民が亡くなった場合、研究スタッフが自宅を訪問し、直接剖検への協力を依頼することで、正確な死因究明を行い、生活習慣病の病態解明に非常に重要な役割を果たしています 2。
さらに、久山町研究は、公衆衛生の専門家だけでなく、臨床医が中心となって疫学調査を実施するというユニークな体制を採っています 6。初代の勝木司馬之助教授から受け継がれる「住民一人ひとりを自分の患者と思いなさい」という教育のもと、脳卒中をはじめとする病気の発症例を臨床医の目で詳細に診断し、その情報を大切に蓄積することで、臨床研究と疫学が融合した質の高いデータベースが構築されています 6。
研究は、九州大学と久山町の共同事業として進められており、健診から得られたデータは研究に活用され、その成果は住民の健康管理のために町に還元されるという「ひさやま方式」と呼ばれる地域連携体制が構築されています 3。具体的には、健診、医療相談、追跡調査、そして剖検までを地域全体で連携して行う体制が、半世紀以上にわたり維持されています 3。
2002年の第4集団からは、生活習慣病のメカニズムをより深く理解するため、対象者の96%から同意を得てゲノム疫学研究も開始されました 3。これにより、生活習慣などの環境要因だけでなく、遺伝的要因も考慮した多角的な研究が進められています 3。
主な発見:生活習慣病(糖尿病、高血圧など)、がん、認知症に関する重要な知見
生活習慣病
久山町研究は、生活習慣病の有病率の変化や、様々な危険因子との関連性について、多くの重要な知見を提供してきました。1988年には、対象者全員に75g経口糖負荷試験が導入され、当時すでに男性15%、女性10%と予想以上に高かった糖尿病有病率が、2002年にはそれぞれ24%、13%へと増加していることが明らかになりました 1。さらに、1988年の集団における解析では、糖尿病だけでなく、空腹時高血糖(IFG)や耐糖能異常(IGT)といった糖代謝異常のレベルから、悪性腫瘍による死亡リスクが有意に増加することが示唆され、糖尿病が悪性腫瘍の危険因子となる可能性が示されました 1。
一方、高血圧に関しては、1961年から2002年までの健診成績を比較すると、高血圧の頻度自体には大きな変化は見られませんでしたが、高血圧治療の普及によって脳卒中発症率が低下したことが明らかになりました 6。また、メタボリックシンドロームに着目した研究では、日本の内科学会の診断基準で用いられている腹部肥満の基準(男性85cm以上、女性90cm以上)で判定された腹部肥満が、将来の心血管病の発症と有意に関連することが示されました 3。肥満との関連では、肥満でなかった人が肥満になった場合、心筋梗塞や脳卒中になるリスクが高い傾向があること、また、早食いをする人は肥満になるリスクが高い傾向があることも示唆されています 11。さらに、自転車や徒歩など活動的な通勤をする人は、糖尿病になるリスクが低い傾向があることも明らかにされています 11。
がん
久山町研究は、がんの発生と生活習慣との関連についても重要な知見を提供しています。高血糖が長期間続くと、がん、アルツハイマー病、血管性認知症、脳梗塞といった病気の発症リスクが増加することが示唆されており 9、特に糖尿病だけでなく、糖尿病予備軍である境界型糖尿病の人でも、がんによる死亡のリスクが1.5倍高くなることが明らかになりました 9。これは、健診で血糖値が高めと指摘された場合、暴飲暴食を避け、定期的な運動を行うなど、血糖値を上げないような生活習慣を心がけることの重要性を示唆しています 10。
認知症
認知症研究においても、久山町研究は世界をリードする成果を挙げています。1985年から認知症の調査を開始し、1985年から2002年にかけて認知症の有病率が6.7%から12.5%へと急増していることが明らかになりました 1。これは、単なる高齢化の影響を超えて、認知症を増加させる何らかの要因が存在する可能性を示唆しています。追跡調査のデータからは、健常な高齢者が生涯に認知症になる確率が約55%と試算されており 1、60歳以上の高齢者では2人に1人が認知症を発症する可能性があるという衝撃的な結果も報告されています 1。
危険因子に関する研究では、糖尿病の人がアルツハイマー型認知症を発症するリスクは通常の2.1倍、脳血管性認知症を発症するリスクは1.6倍に、また、高血圧の人は脳血管性認知症になりやすいことが示されています 1。さらに、中年期から老年期の喫煙者は、非喫煙者に比べて脳血管性認知症の発症リスクが約2.8倍、アルツハイマー認知症の発症リスクが約2倍に上昇することも明らかになりました 1。
一方、予防因子に関する研究も進んでおり、運動が認知症の予防に効果的であり、発症リスクを38~45%低下させることが報告されています 1。食事との関連では、大豆製品、野菜、海藻類、乳製品などを多く摂取し、米(糖質)の摂取量が少ない食事パターンが認知症予防に良い可能性が示されています 1。また、この食事パターンには、果物、芋類、魚の摂取量が多く、酒の摂取量が少ないという傾向も確認されています 1。さらに、牛乳・乳製品の摂取が血管性認知症とアルツハイマー病のリスク低下に関連する可能性も示唆されています 12。認知症のきっかけとなる糖代謝異常の有病率を1961年と2002年で比較すると、男性は5倍以上、女性は7倍以上に増加しており 1、インスリン抵抗性や血糖変動も認知症の危険因子である可能性が示唆されています 13。
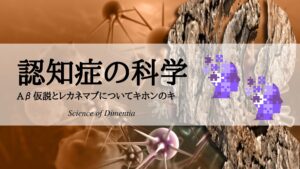
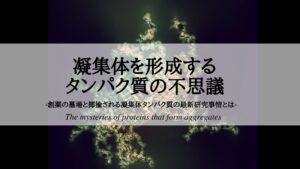
他の国内外の研究と比較した久山町研究の独自性
久山町研究は、他の国内外の疫学研究と比較して、いくつかの独自の特徴を持っています。まず、臨床医が臨床の視点をもって疫学調査を行っている点が挙げられます 6。これは、初代の勝木司馬之助教授から続く伝統であり、住民一人ひとりを自分の患者と思いながら、脳卒中などの病気の発症を臨床医の目で見て診断し、その情報を大切にしていることが、精度の高いデータにつながっています 6。
二つ目の特徴は、世界的に見ても非常に高い剖検率です 2。研究の精度を臨床研究のレベルで行うためには、死因や隠れた疾病を剖検で確認するという考えに基づき、現在でも約80%という高い剖検率を維持しています 6。
三つ目の特徴は、地域住民全体を対象とした悉皆調査であることです 2。40歳以上の全住民を対象に、定期的に健康診断を実施し、時代推移に伴う変化にも対応しながら追跡調査を行うことで、地域全体の健康状態を正確に把握しています 2。
さらに、長期にわたる丁寧な追跡調査も久山町研究の大きな特徴です 2。数例の行方不明者を除き、追跡率は99%以上に達しており、住民の健康状態や生活習慣の変化を長期間にわたり把握することが可能です 2。
そして、九州大学と久山町、地元の開業医が連携して研究を進める「ひさやま方式」は、地域に根ざした研究体制として、住民の積極的な参加と高い協力体制を築き上げています 3。
日本におけるもう一つの重要な疫学研究:JPHC研究
研究の目的:生活習慣とがんなどの慢性疾患との関連を明らかにする
日本におけるもう一つの重要な疫学研究として、「多目的コホート研究(JPHC研究)」が挙げられます。この研究は、日本人の生活習慣と、がん、心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病との関連を解明することを目的として、1990年に開始されました 5。食習慣、運動、喫煙、飲酒などの生活習慣がこれらの疾病の発症に深く関わっていると考えられている背景のもと、生活習慣の改善によってこれらの疾病の発症をある程度防ぐことが可能であるという考えに基づいています 5。
研究の方法:全国規模での大規模なコホート調査と長期追跡
JPHC研究は、全国の約10万人の住民を対象とした大規模な前向きコホート研究です 5。研究開始時に、質問票を用いて喫煙や飲酒、食事などの生活習慣に関する情報や、健康診断の結果、血液などの生体試料を収集し 17、その後20年以上にわたり、これらの人々の疾病発症状況を追跡調査しています 5。追跡調査においては、市町村からの異動情報や死亡小票、がんや脳卒中などの罹患情報を集める疾病登録システムなどを活用し、対象者との継続的なコミュニケーションとしてニュースレターを送付するなどの工夫も行われています 17。
主な発見:がん、生活習慣病、認知症などに関する知見
がん
JPHC研究は、がんの予防に関する多くの重要なエビデンスを提供しています。喫煙、飲酒、食生活、身体活動、体重、感染といった要因とがんとの関連について詳細な分析が行われており 18、例えば、仕事や運動などで身体活動量が多い人ほど、何らかのがんになるリスクが低下する傾向があることが示されています(男性では大腸がん、女性では乳がん) 16。また、コーヒー摂取とがん死亡リスクとの関連性や 19、血清鉄代謝マーカー濃度とがんリスクの関連 5、アクリルアミド摂取と子宮内膜がん・卵巣がんリスクの関連 5、血清CRP濃度とがんリスクの関連 5、喫煙とアルコール摂取と甲状腺がんリスクの関連 5 など、様々な要因と特定のがんとの関連性が明らかにされています。
生活習慣病
JPHC研究は、生活習慣病の予防やリスク軽減に関する知見も豊富です。習慣的なコーヒーの摂取が、全死亡および心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患による死亡リスクを減らす可能性が示唆されています 19。また、出生体重が低いほど、成人後期に心血管疾患、高血圧、糖尿病のリスクが高いことも明らかになりました 20。その他、非アルコール飲料摂取と血糖値の関連 5、ピーナッツ摂取と脳卒中・虚血性心疾患の関連 5、食物繊維摂取と死亡リスクの関連 5、大豆食品・発酵性大豆食品摂取と死亡リスクの関連 5、海藻類摂取と脳卒中・虚血性心疾患リスクの関連 5、勤務時間と急性心筋梗塞・脳卒中リスクの関連 5、食事パターンと死亡リスクの関連 5、血清ビタミンD濃度とがんリスクの関連 5、主観的ストレスとがんリスクの関連 5、食事性マグネシウム摂取と虚血性心疾患の関連 5、ナトリウム・カリウム摂取量と死亡リスクの関連 5 など、多岐にわたる生活習慣要因と生活習慣病との関連が研究されています。
認知症
認知症との関連では、野菜・果物の摂取量が多いほど認知症リスクが低下する可能性が示されており、特にビタミンCの摂取量が多いと認知症リスクが低い傾向にあることがわかりました 21。さらに、趣味を持つことが認知症、特に脳卒中既往のない認知症のリスクを低下させる可能性や 23、人生を楽しむ度合いが高いほど認知症発症リスクが低い傾向にあることも報告されています 24。その他、血漿尿酸値と認知症の関連性 5、緑茶・コーヒー摂取と認知機能低下リスクの関連 5 なども研究されています。
世界をリードする疫学研究:フラミンガム研究とNurses’ Health Study
フラミンガム研究 (The Framingham Study)
研究の目的と歴史:心血管疾患の危険因子の特定から多岐にわたる疾患の研究へ
アメリカ合衆国マサチューセッツ州のフラミンガム町で1948年に開始されたフラミンガム研究は、心血管疾患の原因を究明するために始まった、世界で最も長く継続されている疫学研究の一つです 25。当初は30歳から62歳の住民5209人を対象に 26、2年ごとの詳細な医学的検査と生活習慣に関するインタビューを実施し、心血管疾患の発生に関連する要因を特定することを目的としていました 26。その後、研究対象は当初の参加者の子供たちの世代(第二世代コホート)、そして孫たちの世代(第三世代コホート)へと拡大され 27、心血管疾患だけでなく、脳卒中、認知症、骨粗鬆症、糖尿病、がん、眼疾患、聴覚障害、肺疾患、遺伝性疾患など、幅広い疾患を研究対象とする多世代研究へと発展しています 29。また、1994年からは、より多様な人種構成を反映したオムニコホートも設立され、人種や民族が心臓病のリスク要因に与える影響についても研究が進められています 28。
研究の方法:地域住民を対象とした世代を超えた長期的な追跡調査
フラミンガム研究では、参加者に対して2年ごとに詳細な医学的検査と生活習慣に関するインタビューを実施し、生活習慣、病歴、身体所見、臨床検査データなどを長期にわたり収集しています 26。高い追跡率を維持し 27、亡くなった参加者については剖検による病理学的情報を収集することで、より正確な疾患の病態を解明しようとしています 27。近年では、遺伝子情報や様々なバイオマーカーの分析も積極的に行われており 28、遺伝的要因と生活習慣要因が疾患の発症にどのように影響するのか、分子レベルでの研究も進んでいます 28。
主な発見:心血管疾患、生活習慣病、認知症などに関する重要な知見
心血管疾患
フラミンガム研究は、高血圧、高コレステロール、喫煙、運動不足、肥満が心血管疾患の主要な危険因子であることを世界で初めて明らかにしました 25。これらの発見は、心血管疾患の予防戦略の基礎となり、公衆衛生に多大な貢献をしました。また、HDLコレステロールが高いと死亡リスクが低下すること 28、心房細動が脳卒中リスクを大幅に増加させること 28、高血圧が脳卒中と心不全のリスクを高めること 28 など、多くの重要な知見がこの研究から得られています。フラミンガム研究から生まれたフラミンガムリスクスコアは、個人の10年間の心血管疾患発症リスクを予測するツールとして、世界中で広く利用されています 31。
生活習慣病
フラミンガム研究は、心血管疾患だけでなく、他の生活習慣病との関連性についても重要な発見をしています。喫煙と2型糖尿病、心血管疾患、がんなどの関連 32、肥満と心血管疾患、がん、2型糖尿病などの関連 34、高血圧と脳卒中、心不全などの関連 28 など、様々な生活習慣要因が複数の慢性疾患のリスクを高めることが示されています。
認知症
認知症研究においても、フラミンガム研究は重要な役割を果たしています。高血圧、糖尿病、喫煙、身体活動の低下などが認知症リスクに関連する可能性が示唆されており 29、特に中年期の高血圧が認知症リスクを高める可能性が指摘されています 31。また、親に認知症の既往があると、中年期の記憶障害リスクが高まることも示されています 34。興味深いことに、過去30年間で認知症発症率が低下しているという発見もありましたが、これは高学歴層に限られる可能性も示唆されています 39。心血管疾患リスク因子が認知症や認知機能低下に寄与することも明らかになっており 39、運動習慣が認知症リスクを低下させる可能性も示唆されています 45。さらに、赤身肉、特に加工肉の摂取量が多いと認知症リスクが高まる可能性や、ナッツ類や豆類の摂取が認知症リスクを低下させる可能性も示唆されています 46。
Nurses’ Health Study
研究の目的:女性の健康と生活習慣が慢性疾患に与える影響を調査
1976年に開始されたNurses’ Health Studyは、アメリカの女性看護師を対象とした大規模な前向き研究であり、女性の健康と生活習慣が慢性疾患に与える影響を調査することを目的としています 30。当初は経口避妊薬とがんの関連性を調査していましたが 38、その後、食事、運動、喫煙、ホルモン療法、環境要因など、多くの要因と、がん、心血管疾患、糖尿病、認知症など30以上の慢性疾患との関連を研究するまでに発展しました 38。研究は第一期(NHS)、第二期(NHS II)、第三期(NHS 3)と継続され、さらに参加者の子供を対象としたGrowing Up Today Study(GUTS)も実施されており、世代を超えた健康状態の変化を追跡しています 48。
研究の方法:アメリカの看護師を対象とした大規模な長期追跡調査
Nurses’ Health Studyでは、参加者である看護師に対して2年ごとに質問票を送付し、生活習慣、病歴、服薬状況などに関する詳細なデータを収集しています 49。また、4年ごとには食事摂取頻度調査票(FFQ)を用いて、より詳細な食事情報を収集しています 49。さらに、研究の進展に伴い、血液、尿、爪などの生体試料の収集・保管も行われるようになり 38、バイオマーカーを用いたより詳細な分析も可能になっています。米国死亡指数(NDI)との連携により、参加者の死亡情報も正確に追跡しています 52。
主な発見:がん、心血管疾患、糖尿病、認知症など、女性の健康に関する広範な知見
がん
Nurses’ Health Studyは、女性におけるがんのリスク要因に関する多くの重要な発見をしています。喫煙、肥満、ホルモン療法と乳がんリスクの関連 38、食事性脂肪と乳がんリスクの関連 58、葉酸やビタミンB6が乳がんリスクを低下させる可能性 58、ビタミンDと大腸がんリスクの関連 55、ナッツ類の摂取が乳がん予防に役立つ可能性 59 など、様々な要因とがんリスクとの関連が明らかにされています。
心血管疾患
心血管疾患との関連では、喫煙、肥満、経口避妊薬、ホルモン療法と心血管疾患リスクの関連 38、トランス脂肪酸摂取と心血管疾患の関連 38、身体活動と心血管疾患リスクの関連 53 などが示されています。特に、トランス脂肪酸の摂取が心血管疾患のリスクを高めるという画期的な発見は、食品業界の政策にも影響を与えました 54。
糖尿病
糖尿病との関連では、喫煙、肥満、食事と2型糖尿病リスクの関連 38、妊娠前の肉や卵の摂取が妊娠糖尿病リスクを高める可能性 59 などが示唆されています。
認知症
認知症との関連では、身体活動と認知症リスクの関連 53、赤身肉、特に加工肉の摂取量が多いと認知症リスクが高まる可能性 46、ナッツ類や豆類の摂取が認知症リスクを低下させる可能性 46、ベリー類、アブラナ科野菜、緑葉野菜の摂取が認知機能低下を抑制する可能性 59 などが研究されています。
これらの疫学研究から見えてきたこと:生活習慣病、がん、認知症の予防と対策
これらの国内外の主要な疫学研究から得られた知見は、生活習慣病、がん、認知症といった現代社会の主要な疾患の予防と対策を考える上で、非常に重要な示唆を与えてくれます。
| 研究名 | 生活習慣病 | がん | 認知症 |
| 久山町研究 | 糖尿病有病率の増加、高血圧治療による脳卒中低下、メタボリックシンドロームと心血管病・腎臓病リスクの関連、肥満と心筋梗塞・脳卒中リスクの関連、活動的な通勤と糖尿病リスク低下の傾向 | 高血糖とがんリスクの関連、糖尿病だけでなく境界型糖尿病でもがん死亡リスク上昇、中年期の高血圧は老年期の高血圧よりも脳血管性認知症リスクを高める、喫煙はアルツハイマー型・脳血管性認知症の発症リスクを高める | 認知症有病率の急増、糖尿病がアルツハイマー型認知症と脳血管性認知症のリスクを高める、高血圧が脳血管性認知症のリスクを高める、喫煙が認知症のリスクを高める、運動が認知症の予防に効果的、特定の食事パターンが認知症予防に良い可能性、中年期の高血圧は老年期の高血圧よりも脳血管性認知症のリスクを高める、生涯に認知症になる確率の試算(約55%) |
| JPHC研究 | コーヒー摂取と心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患による死亡リスク低下の可能性、低出生体重と成人後期における心血管疾患、高血圧、糖尿病のリスク上昇の関連 | 身体活動量が多いほど、がん全体のリスクが低下する傾向(男性では大腸がん、女性では乳がん)、コーヒー摂取とがん死亡リスクの関連性、血清鉄代謝マーカー濃度とがんリスクの関連 | 野菜・果物の摂取量が多いほど認知症リスクが低下する可能性、特にビタミンCの摂取量が多いと認知症リスクが低い傾向、趣味を持つことが認知症、特に脳卒中既往のない認知症のリスクを低下させる可能性、人生を楽しむ度合いが高いほど認知症発症リスクが低い傾向 |
| フラミンガム研究 | 高血圧、高コレステロール、喫煙、運動不足、肥満が心血管疾患の主要な危険因子、HDLコレステロールが高いと死亡リスクが低下、心房細動が脳卒中リスクを大幅に増加、高血圧が脳卒中と心不全のリスクを高める | 喫煙とがんリスクの関連 | 高血圧、糖尿病、喫煙、身体活動の低下などが認知症リスクに関連する可能性、中年期の高血圧が認知症リスクを高める可能性、親に認知症の既往があると、中年期の記憶障害リスクが高まる、過去30年間で認知症発症率が低下しているという興味深い発見(ただし、高学歴層に限られる可能性)、心血管疾患リスク因子が認知症や認知機能低下に寄与する、運動習慣が認知症リスクを低下させる可能性、赤身肉、特に加工肉の摂取量が多いと認知症リスクが高まる可能性、ナッツ類や豆類の摂取が認知症リスクを低下させる可能性 |
| Nurses’ Health Study | 喫煙、肥満、経口避妊薬、ホルモン療法と心血管疾患リスクの関連、トランス脂肪酸摂取と心血管疾患の関連、身体活動と心血管疾患リスクの関連、喫煙、肥満、食事と2型糖尿病リスクの関連 | 喫煙、肥満、ホルモン療法と乳がんリスクの関連、食事性脂肪と乳がんリスクの関連、葉酸やビタミンB6が乳がんリスクを低下させる可能性、ビタミンDと大腸がんリスクの関連、ナッツ類の摂取が乳がん予防に役立つ可能性 | 身体活動と認知症リスクの関連、赤身肉、特に加工肉の摂取量が多いと認知症リスクが高まる可能性、ナッツ類や豆類の摂取が認知症リスクを低下させる可能性、ベリー類、アブラナ科野菜、緑葉野菜の摂取が認知機能低下を抑制する可能性 |
これらの研究結果から、健康的な食生活の重要性(野菜、果物、全粒穀物、豆類、魚などを中心としたバランスの取れた食事 1)、適度な運動の推奨(定期的な身体活動が、生活習慣病、がん、認知症のリスクを低下させる 1)、禁煙の重要性(喫煙は多くのがん、心血管疾患、認知症のリスクを高める 1)、適度な飲酒 18、適切な体重管理(肥満は多くの慢性疾患のリスク要因となる 11)、そして定期的な健康診断の重要性(早期発見と早期介入が重要 2)が改めて強調されます。
例えば、糖尿病はアルツハイマー病と血管性認知症のリスクを高めることが複数の研究で示されており 1、運動は認知症予防に効果的であり、発症リスクを低下させることが明らかになっています 1。また、特定の食事パターン、特に野菜や果物を多く摂取する食生活が、認知症予防に役立つ可能性が示唆されています 1。
疫学研究はどのように私たちの健康に貢献しているのか:公衆衛生と予防医学への貢献
これらの疫学研究から得られた貴重な知見は、国の健康政策や医療ガイドラインの策定に大きな影響を与えています 1。生活習慣病予防のための国の指針は、これらの研究成果に基づいて作成されており、地域住民への健康指導や予防活動にも応用されています 1。フラミンガム研究から生まれたフラミンガムリスクスコアのように、疾患リスクを評価するツールも開発され、個人のリスクに応じた予防戦略を立てる上で役立っています 31。久山町研究における研究成果が住民に還元され、住民の健康意識の向上につながっていること 1、「ひさやま方式」のような地域に根ざした健康管理システムが構築されていることも、疫学研究が地域住民の健康に直接的に貢献している好例と言えるでしょう 7。
未来への展望:今後の疫学研究への期待
今後の疫学研究には、ゲノム疫学やAI技術の活用など、さらなる発展が期待されています。遺伝子と環境要因の相互作用をより詳細に解明することで 3、個人の体質や生活習慣に合わせた、より個別化された予防戦略の開発が可能になるかもしれません 3。ビッグデータ解析やAIの活用は、これまで見過ごされてきた新たな知見の発見につながる可能性を秘めています 28。より詳細な生活習慣情報の収集と解析 17、そして多様な集団を対象とした研究の推進 28 は、疫学研究の成果をより多くの人々に役立てるために不可欠です。
おわりに:疫学研究が拓く、より健康な未来
疫学研究は、私たちの健康を取り巻く様々な要因を科学的に解明し、より健康な未来を築くための道しるべとなるものです。久山町研究をはじめとする国内外の疫学研究が長年にわたり蓄積してきた知見は、私たちの生活習慣を見直し、病気を予防し、健康寿命を延ばすための貴重な情報を提供してくれます。今後も疫学研究が発展し、より多くの健康課題が解明され、その成果が私たちの社会に還元されることが期待されます。
引用文献
- 疫学調査によって認知症を紐解く「久山町研究」とは – 太陽生命, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.taiyo-seimei.co.jp/net_lineup/colum/ninchi/017.html
- 久山町研究とは?研究から分かった認知症に関する7つの認知症の事実, 4月 6, 2025にアクセス、 https://cog-selfcheck.jp/column/t32/
- [久山町研究50周年記念講演会] 基調講演「変貌する生活習慣病の …, 4月 6, 2025にアクセス、 http://www.epi-c.jp/entry/e001_0_hisayama50.html
- 久山町研究とは?~認知症の追跡調査 | 認知症ねっと, 4月 6, 2025にアクセス、 https://info.ninchisho.net/mci/k140
- 多目的コホート研究(JPHC Study) | 国立がん研究センター がん …, 4月 6, 2025にアクセス、 https://epi.ncc.go.jp/jphc/
- 久山町研究の40年で何が分かったか | カタリーベ, 4月 6, 2025にアクセス、 http://www.kataliebe.com/yutaka_kiyohara.html
- www.eph.med.kyushu-u.ac.jp, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.eph.med.kyushu-u.ac.jp/uploads/information/0000000014.pdf?1741276757
- 世界が注目する「ひさやま方式」!生活習慣病から守る独自の健康 …, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.minnanokaigo.com/news/visionary/no85/
- 高血糖が続くと「がん」や「認知症」になる危険が増える …, 4月 6, 2025にアクセス、 https://bs-clinic.or.jp/diabetes-8/
- www.hisayama.med.kyushu-u.ac.jp, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.hisayama.med.kyushu-u.ac.jp/genki/pdf/vol_9.pdf
- 『「久山町研究」からの健康アドバイス』を作成しました! – 福岡県庁, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hisayamamachikenkyu.html
- 研究テーマ|認知症|久山町研究|九州大学大学院 医学研究院, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.hisayama.med.kyushu-u.ac.jp/research/disease02.html
- rouninken.jp, 4月 6, 2025にアクセス、 http://rouninken.jp/member/pdf/22_pdf/vol.22_06-32-07.pdf
- 多目的コホート 研究の成果, 4月 6, 2025にアクセス、 https://epi.ncc.go.jp/files/01_jphc/archives/JPHCpamphlet201612-4.pdf
- 研究の目的 | JPHC-NEXT, 4月 6, 2025にアクセス、 https://epi.ncc.go.jp/jphcnext/about/purpose/index.html
- 多目的コホート研究 (JPHC Study) – 大阪大学医学系研究科, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/envi/a1/
- 第6章 病気の原因を調べるための疫学研究2:コホート研究, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.icrweb.jp/mod/resource/view.php?id=30
- 科学的根拠に基づくがん予防:[国立がん研究センター がん情報 …, 4月 6, 2025にアクセス、 https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/evidence_based.html
- コーヒー摂取量と死亡リスク~日本人9万人の前向き研究|CareNet.com, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.carenet.com/news/general/carenet/39925
- 本件プレスリリースのPDFダウンロード – 国立成育医療研究センター, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.ncchd.go.jp/press/2023/1121.pdf
- 野菜・果物摂取と認知症リスクとの関連 | 現在までの成果 | 多目的 …, 4月 6, 2025にアクセス、 https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/9501.html
- 日本人における果物や野菜の摂取と認知症リスク~JPHC研究|医師 …, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.carenet.com/news/general/carenet/58535
- 趣味と要介護認知症との関連について | 現在までの成果 | 多目的 …, 4月 6, 2025にアクセス、 https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/8955.html
- 「人生をエンジョイ」する人は認知症発症リスクが低い~JPHC研究 …, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.carenet.com/news/general/carenet/57332
- 疫学, 4月 6, 2025にアクセス、 http://minato.sip21c.org/epidemiology.html
- 循環器疫学サイト epi-c.jp 【動画で見る Framingham Heart Study …, 4月 6, 2025にアクセス、 http://www.epi-c.jp/framingham_movie/history/summary.html
- Framingham研究<第1章> | JPT ONLINE, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.lifescience.co.jp/yk/jpt_online/framingham/framingham2.html
- Framingham Heart Study (FHS) | NHLBI, NIH, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.nhlbi.nih.gov/science/framingham-heart-study-fhs
- History | Framingham Heart Study, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.framinghamheartstudy.org/fhs-about/history/
- Framingham: The study and the town that changed the health of a generation | American Heart Association, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.heart.org/en/news/2018/10/10/framingham-the-study-and-the-town-that-changed-the-health-of-a-generation
- Framingham Study | Boston Medical Center, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.bmc.org/stroke-and-cerebrovascular-center/research/framingham-study
- Framingham Heart Study – 羊土社, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/keyword/index.html?id=3625
- Framingham Heart Study | Chobanian & Avedisian School of Medicine, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.bumc.bu.edu/camed/giving/where-can-i-give/explore-our-research/framingham-heart-study/
- Framingham Heart Study – Wikipedia, 4月 6, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Framingham_Heart_Study
- 新しいトピックス|フラミンガム心臓研究 – 循環器疫学サイト epi-c.jp, 4月 6, 2025にアクセス、 http://www.epi-c.jp/entry/e201_0_interview_newtopi.html
- 大学の調査研究:5つの興味深いケース – QuestionPro, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.questionpro.com/blog/ja/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%9A5%E3%81%A4%E3%81%AE%E8%88%88%E5%91%B3%E6%B7%B1%E3%81%84%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9/
- 心房細動の有病率4倍に、転帰は改善~フラミンガム研究50年/Lancet|CareNet.com, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.carenet.com/news/journal/carenet/40006
- Nurses’ Health Study – Wikipedia, 4月 6, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Nurses%27_Health_Study
- Contributions of The Framingham Study to Stroke and Dementia Epidemiology at 60 years, 4月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3380159/
- 欧米で認知症発症が低下傾向, 4月 6, 2025にアクセス、 https://arc.asahi-kasei.co.jp/member/watching/pdf/w_261-14.pdf
- フラミンガム心臓研究における 30 年間での認知症発症率 | 日本語 …, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.nejm.jp/abstract/vol374.p523
- 認知症発症率は過去30年間で低下:フラミンガム心臓研究/NEJM|CareNet.com, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.carenet.com/news/journal/carenet/41491
- 健康的な食事が老化を遅らせ認知症リスクを低下 運動も効果的 糖尿病の人は認知症リスクが高い, 4月 6, 2025にアクセス、 https://dm-net.co.jp/calendar/2024/038174.php
- Gender and incidence of dementia in the Framingham Heart Study from mid-adult life – PMC, 4月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4092061/
- Cardiovascular health, genetic risk, and risk of dementia in the Framingham Heart Study, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000010306
- Long-Term Intake of Red Meat in Relation to Dementia Risk and Cognitive Function in US Adults – Neurology.org, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000210286
- Nurses’ Health Study |, 4月 6, 2025にアクセス、 https://nurseshealthstudy.org/
- History | Nurses’ Health Study 3, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.nhs3.org/about/history/
- History | Nurses’ Health Study, 4月 6, 2025にアクセス、 https://nurseshealthstudy.org/about-nhs/history
- About NHS | Nurses’ Health Study, 4月 6, 2025にアクセス、 https://nurseshealthstudy.org/about-nhs
- The Nurses’ Health Study: Celebrating 40 years of vital contributions to public health, 4月 6, 2025にアクセス、 https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/2016/08/16/nurses-health-study-40-year-anniversary-ajph/
- (PDF) The Nurses’ Health Study: Lifestyle and health among women – ResearchGate, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/7874481_The_Nurses’_Health_Study_Lifestyle_and_health_among_women
- The Impact of the Nurses’ Health Study on Population Health: Prevention, Translation, and Control – PMC – PubMed Central, 4月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4981811/
- Long-running Nurses’ Health Study seeking to diversify funding, 4月 6, 2025にアクセス、 https://hsph.harvard.edu/news/long-running-nurses-health-study-at-risk-of-shutting-down/
- Vitamin D and Cancer – Nurses’ Health Study |, 4月 6, 2025にアクセス、 https://nurseshealthstudy.org/sites/default/files/pdfs/n2008.pdf
- Origin, Methods, and Evolution of the Three Nurses’ Health Studies – PMC – PubMed Central, 4月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4981810/
- Scientific findings – Nurses’ Health Study |, 4月 6, 2025にアクセス、 https://nurseshealthstudy.org/about-nhs/key-contributions-scientific-knowledge
- The Impact of Weight on Cancer Risk – Nurses’ Health Study |, 4月 6, 2025にアクセス、 https://nurseshealthstudy.org/sites/default/files/pdfs/n2003.pdf
- Harvard Nurses’ Health Study | Health Topics – NutritionFacts.org, 4月 6, 2025にアクセス、 https://nutritionfacts.org/topics/harvard-nurses-health-study/
- 第1回糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ研究会 – 国立国際医療研究センター, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.ncgm.go.jp/news/2016/20161117153025.html
- 厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) – non-HDL 等血中脂質評価指針及び脂質標準化システムの構築と基盤整備に関する研究, 4月 6, 2025にアクセス、 https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2013/133061/201315054A/201315054A0009.pdf
- Vigorous Physical Activity and Cognitive Trajectory Later in Life: Prospective Association and Interaction by Apolipoprotein E e4 in the Nurses’ Health Study – PubMed Central, 4月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8974346/
- Framingham Heart Study Brain Aging Program, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.bumc.bu.edu/fhs-bap/