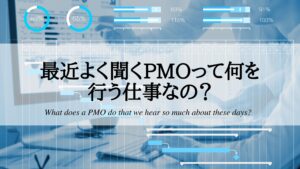1. はじめに:シニョリッジと通貨発行権力の解明
1.1. シニョリッジの定義:封建領主から現代中央銀行まで
通貨発行益、すなわちシニョリッジとは、政府や中央銀行が通貨を発行する権利を行使することによって得られる利益を指す 1。この言葉の起源は中世フランスに遡り、封建領主(Seigneur)が享受していた特権の中でも特に重要だったのが、通貨の発行権とその差益であったことに由来する 1。
歴史的には、領主は額面価値よりも低いコスト(金属の価値や鋳造費用)で硬貨を製造し、その差額を収入としていた 1。この、通貨の額面価値とその製造コスト(内在価値)との差額が、古典的な意味でのシニョリッジである 4。資本主義経済の初期段階では、銀行制度や租税制度が未発達であったため、財政基盤の弱い政府が歳入不足を補うために政府紙幣を発行し、シニョリッジを獲得することもあった 4。
現代においては、通貨の形態は金属貨幣から紙幣、そして中央銀行預金へと進化したが、シニョリッジの基本的な概念は引き継がれている。特に政府による硬貨発行益は、依然として伝統的なシニョリッジの考え方が適用される 4。しかし、現代の通貨供給の大部分を占めるのは中央銀行が発行するマネタリーベース(現金通貨と中央銀行当座預金)であり、これに伴う収益が現代におけるシニョリッジの中心的な議論対象となっている。
1.2. なぜ今、シニョリッジを理解することが重要なのか
現代経済においてシニョリッジを理解することは、いくつかの理由から重要である。第一に、シニョリッジは中央銀行や政府にとって潜在的な財政収入源となり得る 2。特に、大規模な金融緩和策が実施される中で、中央銀行のバランスシートが拡大し、それに伴う収益や国庫への納付金が注目されるようになった 5。
第二に、シニョリッジは金融政策の運営と密接に関連している。中央銀行がマネタリーベースを操作する過程でシニョリッジが発生するため、その規模や性質は金融政策の有効性や波及効果を考える上で無視できない要素となる。
第三に、政府債務が累積する状況下で、シニョリッジを財政再建に活用できるのではないかという議論が存在する 5。しかし、その可能性と限界、そして潜在的なリスク(例えばインフレーション)を正しく評価するためには、シニョリッジのメカニズムを深く理解する必要がある。
第四に、デジタル通貨、特に中央銀行デジタル通貨(CBDC)の登場は、シニョリッジのあり方に新たな問いを投げかけている。デジタル化された通貨がどのように発行され、それが中央銀行の収益構造や政府財政にどのような影響を与えるのかは、今後の金融システムの重要な論点である。
1.3. 本レポートの構成:定義、国際比較、デジタル最前線
本レポートでは、まずシニョリッジの経済学的な定義とメカニズムを掘り下げ、現代における測定方法やインフレ税との関係を明らかにする。次に、主要国(日本、米国、ユーロ圏、英国、中国)における通貨発行主体の違いを比較分析し、各国の中央銀行制度や独立性がシニョリッジのあり方にどう影響するかを考察する。さらに、シニョリッジが政府財源としてどの程度の規模を持つのかを国際比較データを用いて概観する。
続いて、デジタル通貨の先進事例としてカンボジアの「バコン」を取り上げ、その仕組み、目的、そしてCBDCとの違いを分析する。バコンがカンボジアの通貨事情やシニョリッジに与える間接的な影響についても考察し、デジタル通貨がもたらす新たな可能性と課題を探る。最後に、これまでの分析を踏まえ、デジタル化が進む現代においてシニョリッジがどのように変容していくのか、その将来展望を提示する。
2. シニョリッジの経済学:通貨はいかにして収益を生むか
2.1. 基本概念:通貨価値と創造コストの差額
シニョリッジの根源は、発行される通貨の額面価値とその製造・流通にかかるコストとの差額にある 1。政府が発行する硬貨の場合、この関係は比較的単純である。例えば、額面100円の硬貨を製造するのに20円のコストがかかるとすれば、差額の80円が政府の収入(シニョリッジ)となる 4。
しかし、現代の通貨供給の中心は、物理的な硬貨よりも中央銀行が発行する銀行券(紙幣)や、市中銀行が中央銀行に保有する当座預金(準備預金)である。これら中央銀行の負債(マネタリーベース)から生じるシニョリッジの捉え方は、より複雑な側面を持つ。
2.2. 現代のメカニズム:中央銀行、バランスシート、マネタリーベース拡大
現代の中央銀行は、主にマネタリーベース(市中に出回る現金通貨+日銀当座預金)を拡大させることを通じて通貨を供給する 4。このプロセスは、中央銀行のバランスシート操作を通じて行われる。
例えば、中央銀行が公開市場操作(買いオペレーション)で市中銀行から国債などの資産を購入する場合、その代金は市中銀行が中央銀行に持つ当座預金口座に振り込まれる 4。これにより、市中銀行の準備預金が増加し、マネタリーベースが拡大する。銀行券(紙幣)は、市中銀行がこの当座預金を引き出す形で中央銀行から受け取り、それが企業や個人に渡ることで市中に流通する 7。
このように、中央銀行は資産(国債など)を増加させると同時に、負債(当座預金や銀行券)を増加させることで、マネタリーベースを拡大する。この負債側の増加が、現代におけるシニョリッジ発生の源泉となる。
日本の硬貨発行においては、政府(財務省)が製造した硬貨を日本銀行に交付した時点で、その額面金額が一旦政府の日銀当座預金に振り込まれるが、すぐに別口預金に振り替えられる。そして、日本銀行がその硬貨を市中銀行に払い出した時点で、別口預金から当座預金に組み戻され、政府の当座預金が増加することでシニョリッジが実現する、という特殊な会計処理がなされる 4。
2.3. シニョリッジの測定:マネタリーベース増加額 vs 機会費用アプローチ
現代のシニョリッジ、特に中央銀行が生み出すそれを測定する方法には、主に二つの考え方が存在する 5。
- マネタリー・シニョリッジ(フロー・アプローチ):
これは、年々のマネタリーベースの増加額そのものをシニョリッジと捉える考え方である 4。数式で表すと、実質ベースマネーを M、価格水準を P とした場合、実質通貨発行益 S は S=(M−M−1)/P となる 2。この定義では、例えば日本銀行が年間80兆円のペースでマネタリーベースを増加させている場合、その年のシニョリッジは80兆円と計算される 5。これは、新たに創造された通貨の量(フロー)に着目する考え方である。 - 機会費用シニョリッジ(ストック・アプローチ):
これは、中央銀行が通貨(特に利子の付かない現金通貨)を発行することで得られる「資金調達コストの節約分」をシニョリッジと捉える考え方である 5。中央銀行は、発行した通貨(負債)の見合いとして国債などの資産を購入し、利子収入を得る。一方で、発行した現金通貨には利子を支払う必要がない(ゼロ金利での資金調達)。この資産運用利回りと負債調達コスト(ゼロ)の差額が利益となり、これがシニョリッジとされる 1。計算式としては、「金利 × マネタリーベース(特に現金通貨発行高)」に近い形となる 5。日本銀行はこちらの定義に基づき、資産運用等から得た利益(経費等を控除後)を国庫納付金として政府に納めている 5。
これら二つの定義は、利益を認識するタイミングの違いと解釈できる 5。フロー・アプローチ(定義1)は、マネタリーベースの増加が将来生み出すであろう収益の現在価値を、増加時点で一括して認識する考え方と言える。一方、ストック・アプローチ(定義2)は、実際に利子収入などが生じる都度、利益を認識していく考え方である 5。
どちらの定義を用いるかによって、特に量的緩和などでマネタリーベースが急増する局面において、認識されるシニョリッジの額は大きく異なる。フロー・アプローチでは巨額の利益が計上されるように見える一方、ストック・アプローチでは利益は将来にわたって分散される。この違いは、シニョリッジを財政資源として利用する議論において重要な意味を持つ。フロー・アプローチに基づくと、金融緩和によって直ちに巨額の財源が生まれるかのような印象を与えかねないが、ストック・アプローチ(および中央銀行の実際の会計処理)に基づけば、利益はあくまで将来にわたる資産運用から生じるものであり、かつマネタリーベース自体は中央銀行の負債であるという側面が強調される 5。
2.4. シニョリッジとインフレ税:関連性と相違点
シニョリッジと密接に関連する概念として「インフレ税」がある。インフレ税とは、インフレーションによって貨幣の実質的な価値が目減りすることにより、貨幣の保有者から発行者(政府・中央銀行)へと実質的な購買力が移転する現象を指す 2。これは、政府が国民に明示的な課税を行うことなく実質的な収入を得るため、「税」と見なされる 3。計算式としては、「インフレ率 × 実質マネー残高 (πm)」で表される 2。
シニョリッジとインフレ税の関係は、実質シニョリッジ(フロー・アプローチ)の分解によって理解できる。実質シニョリッジ S=ΔM/P は、実質マネタリーベースの変化 (Δm) とインフレ税 (πm−1) の和として表すことができる (S=Δm+πm−1) 2。
- Δm:実質的な経済成長などに伴う貨幣需要の増加に応じた通貨発行部分。
- πm−1:インフレーションによる既存貨幣価値の低下を通じて得られる部分(インフレ税)。
つまり、シニョリッジ収入の一部はインフレ税によって構成されうる 2。政府・中央銀行は、意図的にインフレを引き起こすことで、実質的な政府債務の価値を減らし、財政収入を得ることができる 11。第二次世界大戦後の日本における高インフレは、結果的に政府債務を大幅に削減したが、これは巨額のインフレ税(およびシニョリッジ)が発生した例と見ることができる 5。
しかし、シニョリッジとインフレ税は同一ではない。経済成長に伴う実質的な貨幣需要の増加 (Δm) があれば、インフレ率がゼロであってもシニョリッジは発生する 2。国際比較研究によれば、シニョリッジ収入が高い国が必ずしも高インフレ国であるとは限らず、インフレ税への依存度とシニョリッジ全体の規模の間には明確な相関が見られない場合もある 2。
インフレ税に依存した財政運営は、実質的には国民、特に現金や預金を持つ家計や低所得者層に対する負担増となる 5。インフレは貨幣価値の不安定化を招き、経済活動に悪影響を与える可能性もある。そのため、安易にインフレ税に頼る財政政策は、経済的・社会的なコストが大きいとされる 5。
3. 誰が通貨を発行するのか? 主要国の比較分析
通貨発行の権限と主体は、国や地域によって異なる制度設計がなされている。ここでは、主要な国・地域を取り上げ、その特徴を比較分析する。
3.1. 通貨発行のモデル:中央銀行、政府、民間主体
現代においては、ほとんどの国で中央銀行が銀行券(紙幣)の発行を独占的に担い、政府が硬貨(貨幣)を発行するという分担が一般的である 7。しかし、歴史的には民間銀行が競争的に銀行券を発行していた時代もあり 14、現在でも一部の国・地域では特殊な形態が見られる 12。
3.2. ケーススタディ:日本
- 銀行券(日本銀行券):日本銀行(BOJ)が日本銀行法に基づき独占的に発行する 7。製造は独立行政法人国立印刷局が行い、日銀が費用を支払って引き取る 7。日銀券は法貨としての強制通用力を持つ 7。
- 貨幣(硬貨):日本政府(財務省)が発行権限を持つ 7。製造は独立行政法人造幣局が行う 12。発行された貨幣は、日銀を通じて市中に流通される 7。硬貨発行によるシニョリッジは政府収入となる 4。
3.3. ケーススタディ:米国
- 銀行券(Federal Reserve Notes):連邦準備制度(Federal Reserve System, Fed)を構成する12の地区連邦準備銀行(地区連銀)が発行する 12。紙幣には発行元の地区連銀を示す記号(A~L)が印刷されている 22。製造は財務省の一部局である製版印刷局(Bureau of Engraving and Printing)が行う 12。
- 貨幣(硬貨):米国政府(財務省傘下の造幣局、US Mint)が製造・発行する 12。
- Fedの特異な構造:Fedは「政府内の独立した機関」とされ、公的機関(大統領が任命し上院が承認する理事会メンバーで構成される連邦準備制度理事会、FRB)と民間的要素(地区連銀は域内の加盟民間銀行が出資)を併せ持つ「準公的(quasi-public)」な組織である 23。その権限は議会が制定した連邦準備法に由来する 23。
- 独立性を巡る議論:Fedは、金融政策決定において大統領や議会の承認を必要とせず、政府からの予算配分も受けないため、高い運用上の独立性を有するとされる 25。これは、短期的な政治的圧力から金融政策を隔離し、長期的な物価安定を図るためである 29。しかし、その強大な権限と「民間銀行カルテル」とも評される構造 24 から、その独立性や説明責任のあり方については、常に政治的な議論や批判が存在する 24。例えば、大統領がFRB議長の解任権を持つべきか、金融政策決定に大統領が関与すべきか、といった提案がなされることもある 31。Fed自身は、議会に対して定期的に報告義務を負っており、政府から独立しているのではなく「政府の中で独立している」と説明している 25。このFedの公的統制と運用上の独立性、そして民間要素が混在する複雑な構造は、その権力と説明責任を巡る政治的緊張の源泉となっている。金融政策が経済全体に与える影響の大きさ故に、短期的な政治サイクルから意図的に隔離された機関であるFedのあり方は、繰り返し政治的な争点となり得るのである。
3.4. ケーススタディ:ユーロ圏
- 銀行券(ユーロ紙幣):発行の認可権限は欧州中央銀行(ECB)が独占的に有する 34。実際の紙幣発行は、ECBおよびユーロ圏加盟国の各国中央銀行(NCBs)が行う 12。ユーロ紙幣はユーロシステム(ECBとユーロ圏NCBsで構成)全体の負債となる 35。製造は各国の中銀や政府、民間企業などが担う 12。
- 貨幣(ユーロ硬貨):ユーロ圏加盟各国の政府が発行する。ただし、発行量についてはECBの承認が必要 12。製造は各国の造幣局が行う 12。
- ユーロシステム:ECBがユーロ圏全体の金融政策を決定し、その実施(公開市場操作や銀行券の流通管理など)は各国のNCBsが担うという役割分担が特徴である 34。
- デジタルユーロ計画:ECBは現在、リテールCBDCである「デジタルユーロ」の導入に向けた準備を進めている 38。無料での利用、高いプライバシー基準、現金との共存、金融包摂などが基本コンセプトとして掲げられている 38。発行にはEUレベルでの法整備が必要となる 38。
3.5. ケーススタディ:英国
- 銀行券(ポンド紙幣):中央銀行であるイングランド銀行(BoE)が発行するものが主流である 12。しかし、歴史的な経緯から、スコットランドの3つの民間銀行と北アイルランドの3つの民間銀行も、それぞれ独自の意匠を持つポンド紙幣を発行する権限を保持している 12。BoE発行の紙幣はイングランドとウェールズで法定通貨とされるが、スコットランドと北アイルランドの銀行が発行する紙幣は、英国内で広く受け入れられているものの、法的な強制通用力は限定的である 14。BoE紙幣の製造は民間企業が行っている 12。
- 貨幣(硬貨):英国政府(王立造幣局、Royal Mint)が発行する 12。
- BoEの歴史:1694年設立の民間銀行として出発し、1844年のピール銀行法によってイングランドとウェールズにおける発券銀行としての地位を確立、その後中央銀行としての機能を強化し、1946年に国有化された 39。
- 混合発行システム:英国における中央銀行と民間銀行による銀行券の並行発行は、他の主要国には見られない特徴である。これは、中央銀行制度が確立される過程で、既存の民間銀行の発券権が完全には廃止されずに残存した歴史的経緯(path dependency)を反映している。機能的にはポンドという単一通貨システムに統合されているものの、スコットランドや北アイルランド発行の紙幣が他の地域で受け取りを渋られるケースがあるなど 40、若干の複雑さをもたらしている。これは、現代的な中央銀行制度が普及した後も、歴史的な制度安排がどのように存続しうるかを示す事例と言える。
3.6. ケーススタディ:中国
- 通貨(人民元):中央銀行である中国人民銀行(PBoC)が発行する(その役割から推察される) 42。
- PBoCの構造と独立性:PBoCは国務院(内閣に相当)の指導の下で運営される 42。中国人民銀行法は、PBoCが法に基づき独立して金融政策を執行し、地方政府や他の政府部門、社会団体、個人の干渉を受けないと規定している 42。しかし、金利、為替レート、年間通貨供給量目標といった重要事項に関する決定は、国務院への報告と認可が必要とされる 42。このため、PBoCの独立性は、多くの西側諸国の中央銀行に比べて低いと評価されている 46。金融政策委員会も存在するが、その役割は諮問的なものに留まる 42。
- デジタル人民元(e-CNY):中国はCBDCの開発・導入において世界をリードしており、デジタル人民元の実証実験が進んでいる 43。これはリテール向けであり、PBoCが現金(M0)の代替として発行し、指定された民間事業者(銀行など)を通じて利用者に提供される二層構造(two-tier system)を採用している 43。管理可能な匿名性、オフライン決済機能などが特徴とされる 43。
3.7. 主要経済圏における通貨発行主体の比較
以下の表は、本セクションで概観した主要経済圏における通貨発行主体の概要をまとめたものである。
表1:主要経済圏における通貨発行主体(銀行券・貨幣)の比較
| 国・地域 | 銀行券 発行主体 | 銀行券 製造者 | 貨幣 発行主体 | 貨幣 製造者 |
| 日本 | 日本銀行 (BOJ) | 独立行政法人 国立印刷局 | 日本政府 | 独立行政法人 造幣局 |
| 米国 | 連邦準備銀行 (地区連銀) | 政府 (製版印刷局) | 米国政府 | 米国政府 (造幣局) |
| ユーロ圏 | ECB及び各国中央銀行 (NCBs) | 各国中央銀行、政府、民間 | 各国政府 | 各国政府 (造幣局) |
| 英国 | イングランド銀行 (BoE)、スコットランド・北アイルランドの民間銀行 | 民間 | 英国政府 | 英国政府 (王立造幣局) |
| 中国 | 中国人民銀行 (PBoC) | (情報なし) | 中国人民銀行 | (情報なし) |
出典:12 および各ケーススタディの記述に基づく。中国の製造者については利用可能な情報なし。中国の貨幣発行主体は慣例的にPBoCとされることが多いが、明確な情報源はなし。
3.8. 中央銀行の独立性の重要性
通貨発行主体に関する国際比較を通じて、中央銀行の独立性(Central Bank Independence, CBI)の重要性が浮かび上がる。CBIとは、中央銀行が政治的な圧力や干渉から独立して金融政策を決定・実行できる度合いを指す 25。
多くの実証研究が、より高いCBIと、より低位で安定したインフレ率との間に強い相関関係があることを示している 28。独立した中央銀行は、短期的な政治的利益(例えば選挙前の景気刺激策)のために金融政策が歪められるリスクを低減し、物価安定という長期的な目標に対するコミットメントの信頼性を高めることができる 29。この信頼性が、人々のインフレ期待を安定させ、実際のインフレ抑制に繋がる 29。
世界的に見ても、特に1970年代のインフレ経験を経て、CBIを強化する法制度改革が進められてきた 48。しかし、CBIは絶対的なものではなく、法的な独立性が保証されていても、実際の運用においては政治的な圧力がかかる可能性がある 31。また、独立性を維持するためには、中央銀行自身の透明性と国民に対する説明責任が不可欠である 26。さらに、CBIの効果は、その国の民主主義の度合いや財政規律といった他の制度的要因にも左右される 49。したがって、中央銀行の独立性は、法制度によって確立されるだけでなく、それを支える社会全体の理解と政治的な意思によって維持される、動的な政治的構築物であると言える。独立性への挑戦は、金融政策の信頼性を損ない、マクロ経済の安定を脅かす可能性があるため、その動向は常に注視されるべきである。
4. 政府財源としてのシニョリッジ:規模、意義、限界
4.1. 中央銀行利益から国庫へ:利益分配の仕組み
中央銀行は、シニョリッジ(特に機会費用アプローチに基づくもの)や保有資産からの利子収入などにより、通常は利益を生み出す構造となっている 8。この利益は、中央銀行自身の運営経費や、将来の損失に備えるための準備金・引当金などに充当された後、その残余が政府(財務省)に納付されるのが一般的である 5。
日本では、日本銀行の決算剰余金から法定準備金や配当金(出資者に対して)などを控除した残額が、国庫納付金として政府に納められる 5。米国でも、Fedは運営経費や法定配当金(加盟銀行に対して)を支払った後の利益を財務省に送金している 26。英国のイングランド銀行も同様に、利益を財務省に納付する仕組みがある 58。
ただし、利益の計算方法や分配ルールは国によって異なり、損失が発生した場合の処理(政府による資本注入など)に関する取り決めも様々である 8。
4.2. 国際比較:シニョリッジと中央銀行納付金(対GDP比)
シニョリッジや中央銀行から政府への納付金が、マクロ経済的にどの程度の規模を持つのかを把握するために、対GDP比で国際比較を行うことが有効である。ポーランド国立銀行の研究者による分析 55(表1、および55で要約)は、主要7中央銀行について、2003年から2020年までの期間における年平均の利益、シニョリッジ(機会費用アプローチに近い計算と推察される)、政府への移転(納付金)を対GDP比で示している。
表2:中央銀行の利益、シニョリッジ、政府移転の国際比較(対GDP比、2003-2020年平均)
| 中央銀行 | 平均年間利益 (% GDP) | 平均年間シニョリッジ (% GDP) | 平均年間政府移転 (% GDP) |
| 連邦準備制度 (Fed) | 0.38% | 0.19% | 0.37% |
| ユーロシステム (ECB等) | 0.18% | 0.12% | 0.14% |
| 日本銀行 (BOJ) | 0.15% | 0.08% | 0.13% |
| イングランド銀行 (BoE) | 0.07% | 0.06% | 0.07% / 0.39%<sup>a</sup> |
| スイス国立銀行 (SNB) | 1.24% | 0.22% | 0.61% |
| スウェーデン中銀 (Riksbank) | 0.10% | 0.03% | 0.14% |
| ポーランド国立銀行 (NBP) | 0.20% | 0.15% | 0.25% |
出典:55 (Table 1)55。<sup>a</sup> 2009年以降のイングランド銀行資産購入ファシリティ(BEAPFF)からの政府への送金を含む数値。
このデータからは、いくつかの点が読み取れる。まず、シニョリッジ収入(対GDP比)は、多くの先進国において概ね0.1~0.2%程度であり、比較的安定している 55。一方で、中央銀行全体の利益や政府への納付金は、特に2008年の世界金融危機以降、量的緩和(QE)によるバランスシート拡大に伴い増加傾向が見られた国もある 55。スイス国立銀行(SNB)の数値が突出して高いのは、巨額の外貨準備を保有しており、その為替評価損益が大きく影響するためと考えられる 54。
しかし、近年の急速な金利上昇局面においては、状況が逆転しつつある。QEで購入した長期国債などの低利回り資産を抱える一方で、市中銀行から預かる準備預金への付利(金利支払い)が上昇したため、多くの中央銀行で収益が悪化、あるいは損失が発生している 54。例えば、イングランド銀行の資産購入ファシリティ(APF)は赤字に転じ、財務省から損失補填を受けている 58。オーストラリア準備銀行(RBA)、オランダ銀行(DNB)、ニュージーランド準備銀行(RBNZ)、SNB、チェコ国立銀行(CNB)なども損失を計上または見込んでいる 54。日本銀行についても、将来的な金利上昇局面では、準備預金への付利負担が国債からの受取利息を上回り、「逆ザヤ」や損失、さらには債務超過に陥る可能性が指摘されている 59。
この現象は、シニョリッジや中央銀行利益が常に安定した政府収入源であるとは限らないことを示唆している。特に、大規模な非伝統的金融政策(QEなど)は、平時には中央銀行の利益と政府への納付金を増加させる可能性がある一方で、その後の金融政策正常化局面においては、逆に中央銀行が損失を被り、政府による財政支援が必要となるリスクを内包している。これは、非伝統的金融政策の財政的な影響が双方向であり、長期的な視点での評価が必要であることを意味する。
4.3. シニョリッジ依存の便益と制約
シニョリッジを政府収入源として活用することには、いくつかの便益と制約がある。
- 便益:国民に対する直接的な増税を行うことなく、政府が収入を得られる点にある 2。
- 制約1(インフレリスク):シニョリッジ収入を増やすために過度な通貨発行を行うと、インフレーションを引き起こすリスクがある。特にインフレ税に依存する形でのシニョリッジ獲得は、貨幣価値を不安定にし、経済活動を歪め、特に低所得者層に負担を強いるため、持続可能で望ましい方法とは言えない 2。インフレ率を引き上げてインフレ税を増やそうとしても、実質貨幣需要の減少や経済成長への悪影響を通じて、他のシニョリッジ源泉(成長に伴う部分)を減少させてしまう可能性もある 10。
- 制約2(規模の限界):表2が示すように、通常の経済状況下における先進国のシニョリッジ収入(対GDP比)は、一般的にそれほど大きくない 55。したがって、シニョリッジ収入だけで巨額の財政赤字を賄ったり、財政再建を達成したりすることは困難である 5。
- 制約3(負債としての性格):中央銀行がマネタリーベースを拡大して得るシニョリッジは、「打ち出の小槌」のように無から富を生み出すものではない。マネタリーベースはあくまで中央銀行の負債であり、将来的に金融政策を正常化する過程(例えばQEの出口戦略)では、増加させたマネタリーベースを吸収(減少)させる必要が生じ、その際には通貨発行「損」が発生する可能性もある 5。
5. デジタル革新とシニョリッジ:カンボジア「バコン」の事例
5.1. デジタル通貨とCBDCの台頭
近年、一部の国での現金利用の減少、フィンテック企業や巨大IT企業による民間デジタル決済サービスの普及、そして暗号資産やステーブルコインの登場などを背景に、世界の中央銀行は中央銀行デジタル通貨(CBDC)の研究・開発に注力している 60。
CBDCとは、一般的に、中央銀行が発行するデジタル形式の負債であり、その国の法定通貨単位で表示され、交換媒体や価値貯蔵手段として機能するものを指す 61。個人や企業が利用できるリテールCBDCと、金融機関間の決済に用いられるホールセールCBDCの二種類が議論されている 60。
5.2. プロジェクト・バコン:カンボジアのデジタル決済アプローチ
こうした世界的な潮流の中で、カンボジア国立銀行(NBC)は2020年10月、「プロジェクト・バコン」と呼ばれる独自のデジタル決済システムを正式に開始した 63。バコンは、日本のフィンテック企業ソラミツ社との協力のもと開発され、パーミッション型のブロックチェーン技術であるHyperledger Irohaを基盤としている 64。
バコン導入の目的
NBCがバコンを導入した背景には、カンボジア特有の経済・社会的事情がある。主な目的は以下の通りである。
- 金融包摂の促進:銀行口座を持たない国民が多い(特に地方)状況を改善し、デジタル技術を通じて金融サービスへのアクセスを拡大する 63。
- 決済システムの効率化と相互運用性の向上:国内に多数存在する銀行や決済サービス事業者(PSP)間の接続性を高め、リアルタイムかつ低コストでの送金・決済を実現する 63。これにより、国家全体の決済インフラを簡素化し、コストを削減する 63。
- 自国通貨(リエル)利用の促進:カンボジア経済は米ドルへの依存度(ドル化)が非常に高い 76。利便性の高いデジタル決済手段を提供することで、自国通貨リエル(KHR)の利用を促し、中長期的には通貨主権を強化する 63。
- インフラの近代化と将来への備え:急速に進展するデジタル化に対応し、決済インフラを近代化するとともに、将来的に登場する可能性のある外国のデジタル通貨(例えばデジタル人民元)などの影響力に対抗する狙いもある 63。
バコンの仕組み
バコンは、統一された決済プラットフォームであり、スマートフォンアプリを通じて利用できる 65。利用者は電話番号で登録し、提携している銀行やPSPを選択する。送金や支払いは、相手の電話番号を指定するか、統一規格のQRコード(KHQR)をスキャンすることで、リアルタイム(約2秒)かつ原則無料で行われる 63。システムはカンボジア・リエル(KHR)と米ドル(USD)の両方に対応しているが、アプリ内で直接両替することはできない(利用者が選択した金融機関が為替サービスを提供) 68。
技術的には、Hyperledger Irohaブロックチェーンを基盤とし、銀行間のホールセール決済から個人間のリテール決済までをリアルタイム・グロス決済(RTGS)で処理する 68。既存の銀行システムやPSPのシステムとは、オープンAPIを通じて接続される 63。
CBDCとの重要な違い
バコンはしばしばCBDCの事例として紹介されるが、厳密な定義からは外れる点がある。最も重要な違いは、負債の所在である。
- 一般的なリテールCBDCは、中央銀行が発行する直接的な負債である 61。
- 一方、バコンの利用者が保有するデジタルマネーは、利用者が登録時に選択した**民間金融機関(銀行やPSP)の負債(預金や前払式支払手段)**を表現したものである 65。NBCは、これらの民間金融機関の負債をブロックチェーン上で効率的に移転させるための決済システム(バックボーン)を提供するが、NBC自身が一般利用者に対して直接的な負債を発行しているわけではない。
このため、バコンは「準CBDC(quasi-CBDC)」や「CBDC様の技術を用いた決済システム」と表現されることが多い 65。NBC自身も、バコンは厳密にはCBDCではなく決済システムであると説明していることがある 65。
なぜこのような設計が採用されたのか?主な理由は、(1) CBDC発行に必要な法改正を経ずに迅速に導入できたこと、(2) 既存の金融機関のインフラやサービスをそのまま活用できたこと、である 74。
バコンの設計は、カンボジアが直面する特有の課題(ドル化、金融包摂、決済非効率)に対応するため、既存の二層構造の金融システム(中央銀行と民間金融機関)の枠内でブロックチェーン技術の利点(効率性、相互運用性)を最大限に活用しようとした、現実的(プラグマティック)な妥協策と評価できる。これは、中央銀行が直接負債を発行するという、より抜本的で潜在的なリスクも伴う真のリテールCBDC導入とは異なるアプローチである。バコンは、中央銀行が必ずしも全面的なCBDCを発行せずとも、DLT(分散型台帳技術)を活用して既存の決済システムを改善し、政策目標を達成しうる可能性を示すモデルケースとなっている。
5.3. バコンのシニョリッジと通貨主権への間接的影響
バコンの設計上、NBCが一般向けに新たなマネタリーベースを発行するわけではないため、伝統的な意味での直接的なシニョリッジ収入をNBCにもたらすものではないと考えられる 65。バコンの収益構造は、システム全体の効率化によるコスト削減や、参加金融機関からの手数料(もしあれば)などに依存すると考えられ、通貨発行益とは性質が異なる。
しかし、バコンは間接的にカンボジアのシニョリッジ獲得能力や通貨主権に影響を与える可能性がある。その鍵は、バコンの目標の一つである自国通貨リエル(KHR)の利用促進にある 66。
もしバコンが、米ドルに比べて利便性の低いリエルの利用を促進し、国内経済におけるリエル建て取引の割合を高めることに成功すれば、長期的にはリエルに対する需要が高まり、リエル建てマネタリーベースの規模が経済規模に対して相対的に拡大する可能性がある。シニョリッジ(フロー・アプローチでもストック・アプローチでも)はマネタリーベースを源泉とするため 4、リエル需要の拡大は、将来的にNBC(あるいは政府)がリエル発行から得られるシニョリッジの潜在的な規模を増大させることに繋がる。これは、ドル化からの脱却と通貨主権の回復という、カンボジアにとっての長年の課題に貢献しうる。
したがって、バコンは直接的なシニョリッジ創出メカニズムではないものの、その普及を通じて、自国通貨発行益を生み出すための前提条件を強化する戦略的なツールとして位置づけることができる。これは、高度にドル化された経済において、デジタル決済イノベーションが単なる効率化のためだけでなく、通貨主権とそれに伴う利益(シニョリッジを含む)を段階的に取り戻すための手段として活用されうることを示唆している。
5.4. 「デジタル・シニョリッジ」の出現可能性
一方で、もし中央銀行が真のリテールCBDCを発行し、それが物理的な現金や銀行預金を代替するようになれば、「デジタル・シニョリッジ」とでも呼ぶべき新たな収益源が生まれる可能性がある 8。
その源泉は、物理的な現金と同様に、CBDC(中央銀行の負債)に対して支払われる利子(ゼロまたは低金利)と、その見合いとして保有する資産(国債など)から得られる運用収益との差額(スプレッド)であると考えられる 8。
ただし、CBDCが広く普及し、物理的な現金の需要が大幅に減少すれば、伝統的な現金発行に伴うシニョリッジは減少する可能性がある 8。CBDCに利子が付与される場合(その是非は議論があるが)、その利払いコストも収益を圧迫する要因となる。CBDC導入が中央銀行の純収益に与える最終的な影響は、CBDCの設計(利子の有無、保有上限など)、普及度、そしてそれが現金や預金をどの程度代替するかによって複雑に変化するだろう。
5.5. 広範な影響:デジタル時代の金融安定性
CBDCの導入は、シニョリッジ以外にも金融システム全体に広範な影響を及ぼす可能性がある。特に懸念されるのは、金融不安時に預金者が民間銀行の預金から安全な中央銀行の負債であるCBDCへと資金を急速に移動させる「デジタル取り付け(Digital Bank Run)」のリスクである 60。これは、従来の取り付け騒ぎよりもはるかに速いスピードで起こる可能性がある。
また、CBDCが銀行預金を恒常的に代替する場合、銀行の資金調達構造が変化し、貸出などの金融仲介機能に影響を与える(ディスインターミディエーション)可能性も指摘されている 60。
これらのリスクを管理するため、CBDCの設計においては、利用対象者、保有上限額、取引上限額、付利の有無などを慎重に検討する必要がある 60。国際決済銀行(BIS)や国際通貨基金(IMF)などの国際機関は、CBDCの設計、採用戦略、プライバシー保護、国境間決済への応用、金融安定性への影響などについて、活発な調査研究と政策議論を進めている 8。
6. 結論:変化する金融環境におけるシニョリッジ
6.1. シニョリッジと通貨発行慣行に関する主要な発見の要約
本レポートでは、通貨発行益(シニョリッジ)の概念、その測定方法、そして現代経済における意義を多角的に分析した。シニョリッジは、歴史的には硬貨鋳造益に起源を持つが、現代では主に中央銀行によるマネタリーベース発行に伴う収益として理解される。その測定には、マネタリーベースの増加額自体を捉えるフロー・アプローチと、中央銀行の資産運用益(機会費用)を捉えるストック・アプローチがあり、利益認識のタイミングが異なる。シニョリッジはインフレ税と関連するが、同一ではなく、経済成長に伴う実質貨幣需要の増加によっても生じる。
通貨発行の主体は国によって多様であり、中央銀行が銀行券を、政府が硬貨を発行する分担が一般的だが、米国Fedの準公的構造や英国の民間銀行による銀行券発行併存など、独自の制度も存在する。中央銀行の独立性は、物価安定と金融政策の有効性にとって重要な要素であるが、常に政治的な文脈の中に置かれている。
シニョリッジは中央銀行の利益を通じて政府財源に貢献しうるが、その規模は通常、GDP比で見て限定的であり、特に近年の金利上昇局面では、非伝統的金融政策の後遺症として中央銀行が損失を被るリスクも顕在化している。
6.2. バコンとデジタル通貨革新の意義
カンボジアのバコンは、CBDCそのものではないものの、ブロックチェーン技術を活用して国内の決済システムの効率性、相互運用性、金融包摂を向上させ、同時に自国通貨リエルの利用促進を図るという、特定の経済的課題に対応した革新的な取り組みである。バコンは、中央銀行が必ずしも直接的なデジタル負債を発行せずとも、デジタル技術を用いて通貨・決済システムの近代化と政策目標の達成を目指せることを示唆している。バコン自体は直接的なシニョリッジを生み出さないが、リエル利用を促進することで、間接的にカンボジアの通貨主権と将来的なシニョリッジ獲得能力の基盤を強化する可能性を秘めている。
6.3. 将来展望:ますますデジタル化する世界におけるシニョリッジ
シニョリッジという古くからの概念は、金融システムのデジタル化という大きな潮流の中で、新たな意味合いを帯びつつある。もし将来、リテールCBDCが広く普及すれば、「デジタル・シニョリッジ」という新たな収益形態が確立されるかもしれないが、同時に伝統的な現金シニョリッジの減少や、金融安定性への新たなリスクも考慮する必要がある。
CBDCの設計、採用インセンティブ、プライバシーとデータ利用のバランス、金融仲介への影響、国境間決済への応用可能性など、解決すべき課題は多い 60。これらの論点に関する国際的な研究と政策議論は緒に就いたばかりであり、各国の中央銀行は自国の状況に合わせて慎重な検討を進めている。
結論として、シニョリッジは通貨発行権に伴う経済的利益として、今後も重要な概念であり続けるだろう。しかし、その形態、規模、そして政策的な意味合いは、技術革新と金融環境の変化とともに、進化を続けていくと考えられる。通貨の未来を考える上で、シニョリッジの変容を注視していくことが不可欠である。
引用文献
- 通貨発行益(シニョリッジ) | 時事用語事典 | 情報・知識&オピニオン imidas – イミダス, 5月 4, 2025にアクセス、 https://imidas.jp/genre/detail/A-106-0220.html
- 第 9 章 通貨発行益(シニョリッジ)と途上国財政, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Reports/InterimReport/pdf/2007_04_24_09.pdf
- 通貨発行益 – 貨幣 – みずほ証券 ファイナンス用語集, 5月 4, 2025にアクセス、 https://glossary.mizuho-sc.com/faq/show/2294
- shudo-u.repo.nii.ac.jp, 5月 4, 2025にアクセス、 https://shudo-u.repo.nii.ac.jp/record/2091/files/KK17107.pdf
- 政府・日銀の通貨発行益 財政再建に活用は困難 – RIETI, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/oguro/06.html
- 中央銀行通貨を巡る – 滋賀大学経済学部, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.econ.shiga-u.ac.jp/ebrisk/Ronso-438_oguri.pdf
- 銀行券・貨幣の発行・管理の概要 : 日本銀行 Bank of Japan, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/outline/index.htm
- Central bank profit distribution and recapitalisation, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2024/central-bank-profit-distribution-and-recapitalisation.pdf
- An accounting-based model of seigniorage, and recent monetary developments – Bank i Kredyt, 5月 4, 2025にアクセス、 https://bankandcredit.nbp.pl/content/2021/05/BIK_05_2021_01.pdf
- インフレ税,成長に伴う通貨発行益, 5月 4, 2025にアクセス、 https://ir.ide.go.jp/record/42404/files/KSS058300_008.pdf
- インフレ税 | 目からウロコの経済用語「一語千金」 | 連載コラム – 情報・知識&オピニオン imidas, 5月 4, 2025にアクセス、 https://imidas.jp/ichisenkin/g01_ichisenkin/?article_id=a-51-090-13-09-g204
- お金が発行される仕組みについて解説します! – ときわ総合サービス, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.tokiwa-ss.co.jp/journal/knowledge-of-money/money-issue-plot.html
- わが国の通貨制度(幣制)の 運用状況について – 財務省, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.mof.go.jp/currency/link/201208c.pdf
- 「中央銀行と通貨発行を巡る法制度に ついての研究会」報告書, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/kk23-h-1.pdf
- 民間銀行が発行する紙幣 – ニッセイ基礎研究所, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=67536?site=nli
- ペンス(p)はどこの国の通貨単位?イギリスのお金にまつわる情報をチェックしよう!, 5月 4, 2025にアクセス、 https://nativecamp.net/blog/20241225_study_abroad_pence
- マンガレポート 海外投資への道「イギリス前編 ~4つの国がひとつになった不思議な国~」, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.smbc.co.jp/kojin/money-viva/kaigaitoshi-michi/0003/
- 【小学生でもわかる!】日本銀行とは?役割や業務内容も – Spaceship Earth, 5月 4, 2025にアクセス、 https://spaceshipearth.jp/bank-of-japan/
- お札は誰が発行しているのですか? : 日本銀行 Bank of Japan, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/about/education/oshiete/money/c02.htm
- 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 – e-Gov 法令検索, 5月 4, 2025にアクセス、 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000042/
- FRB(アメリカ合衆国連邦準備制度)|用語集 – GRANDIT miraimil, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.miraimil.jp/glossary/frb/
- 連邦準備制度理事会(FRB) | 目からウロコの経済用語「一語千金」 | 連載コラム, 5月 4, 2025にアクセス、 https://imidas.jp/ichisenkin/g05_ichisenkin/?article_id=a-51-009-07-05-g204
- 連邦 – 邦 準 準備法 (その1) – 日本銀行支店・事務所ホームページ一覧, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www3.boj.or.jp/josa/past_release/chosa195711g.pdf
- 第442回「トランプはFRB(連邦準備制度理事会)に手を入れるのか!?」石原 順, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.iwaicosmo.net/report/442frb.html
- Federal Reserve – Wikipedia, 5月 4, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve
- How the Federal Reserve Operates: Independence, Structure, and Accountability Explained, 5月 4, 2025にアクセス、 https://208.properties/real-estate-insights/federal-reserve-structure-independence-accountability
- Federal Reserve System: What It Is and How It Works – Investopedia, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.investopedia.com/terms/f/federalreservebank.asp
- Why is the Federal Reserve independent, and what does that mean in practice? – Brookings Institution, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.brookings.edu/articles/why-is-the-federal-reserve-independent-and-what-does-that-mean-in-practice/
- Central Bank Independence, Transparency, and Accountability – Federal Reserve Board, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20100525a.htm
- FRBの独立性に挑むトランプ政権 – PIMCO, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.pimco.com/jp/ja/insights/challenges-to-fed-independence
- もしトラでFRBの独立性が大きく脅かされるリスクが浮上:中央銀行の独立は人類の英知の産物, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.nri.com/jp/media/column/kiuchi/20240501.html
- 「FRBの独立性毀損で米トリプル安」は本当か FRB議長解任騒動の「危機の本質」, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.smd-am.co.jp/market/shiraki/2025/devil250428gl/
- 「パウエル議長を解任する」トランプ大統領発言の実現性と市場・経済への影響とは?, 5月 4, 2025にアクセス、 https://bloomo.co.jp/learn/library/market-update/powell-trump_250417/
- ECB(欧州中央銀行)とは?役割・組織概要・歴史について解説 – 東証マネ部!, 5月 4, 2025にアクセス、 https://money-bu-jpx.com/news/article050379/
- 欧州中央銀行システムについて – 国際通貨研究所, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.iima.or.jp/docs/newsletter/2012/NLNo_19_j.pdf
- 欧州中央銀行制度(European System of Central Banks) – 日立総合計画研究所, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.hitachi-hri.com/research/researchreport/short/k075.html
- ユーロ圏の金融政策と欧州中央銀行制度|外務省 – Ministry of Foreign Affairs of Japan, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/ecb_gaiyou.html
- ECBがデジタルユーロ発行に向け調査段階から準備段階に移行, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.nri.com/jp/media/column/kiuchi/20231019_2.html
- イングランド銀行(イングランドギンコウ)とは? 意味や使い方 – コトバンク, 5月 4, 2025にアクセス、 https://kotobank.jp/word/%E3%81%84%E3%82%93%E3%81%90%E3%82%89%E3%82%93%E3%81%A9%E9%8A%80%E8%A1%8C-3143562
- イギリスの通貨 – ブリティッシュ・カウンシル, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.britishcouncil.jp/studyuk/planning/money-costs/currency
- イングランド銀行の中央銀行化過程 – -1839年恐慌による検証一, 5月 4, 2025にアクセス、 https://kwansei.repo.nii.ac.jp/record/19825/files/KJ00002450273.pdf
- 中国人民銀行の金融政策の枠組みと 最近の運営動向, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.fsa.go.jp/singi/chuukinken/siryou/0606fukumoto.pdf
- 中央銀行デジタル通貨の発行を目指す中国 -予想されるマクロ面での影響-, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2020/2020win17.pdf
- 中央銀行デジタル通貨(CBDC) に関する取り組み, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/paym/digital/d_forum/dfo230720c.pdf
- 世界の中銀デジタル通貨(CBDC)の現状 | 木内登英のGlobal Economy & Policy Insight, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.nri.com/jp/media/column/kiuchi/20210204.html
- なぜ当局は利上げをためらったか― 問われる中央銀行の独立性 – RIETI, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.rieti.go.jp/users/china-tr/jp/ssqs/041105ssqs.html
- 中国人民銀行の独立性 – 関西学院大学リポジトリ, 5月 4, 2025にアクセス、 https://kwansei.repo.nii.ac.jp/record/19070/files/68-1-3.pdf
- 25 Central Bank Independence and Central Bank Functions in – IMF eLibrary, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557751850/ch026.xml
- Working Paper Series – Do central bank reforms lead to more monetary discipline?, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp3049~bca750cd0a.en.pdf
- Strengthen Central Bank Independence to Protect the World Economy, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/03/21/strengthen-central-bank-independence-to-protect-the-world-economy
- Central Bank Independence and Inflation in Latin America—Through the Lens of History – Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.cemla.org/actividades/2022-final/2022-11-xxvii-meeting-of-the-central%E2%80%93bank%E2%80%93researchers-network/pdf/3.1.2%20Jacome%20&%20Pienknagura%20-%20CBI%20and%20Inflation%20in%20Latin%20America.pdf
- It matters even more: Central bank independence, long-run inflation, and persistence, 5月 4, 2025にアクセス、 https://cepr.org/voxeu/columns/it-matters-even-more-central-bank-independence-long-run-inflation-and-persistence
- 日本銀行の独立性再考 – 滋賀大学経済学部, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.econ.shiga-u.ac.jp/ebr/Ronso-411oguri.pdf
- Why are central banks reporting losses? Does it matter?, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.bis.org/publ/bisbull68.pdf
- static.nbp.pl, 5月 4, 2025にアクセス、 https://static.nbp.pl/publikacje/materialy-i-studia/348_en.pdf
- 日本銀行の財務と先行きの試算 – 日銀レビュー, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2024/data/rev24j15.pdf
- 中央銀行の財務と金融政策運営, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/research/brp/ron_2023/data/ron231212a.pdf
- Research Report – 日本総研, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.jri.co.jp/file/report/researchreport/pdf/15455.pdf
- 日本銀行はどのくらい利上げすると債務超過になるのか | 研究プログラム | 東京財団, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4360
- Working Paper Series – The economics of central bank digital currency, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2713~91ddff9e7c.en.pdf
- 世界で検討が進むCBDCの動向と 今後の方向性について, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.iima.or.jp/docs/newsletter/2021/nl2021.01.pdf
- Central Bank Digital Currency: Background Technical Note, 5月 4, 2025にアクセス、 https://documents1.worldbank.org/curated/en/603451638869243764/pdf/Central-Bank-Digital-Currency-Background-Technical-Note.pdf
- なぜカンボジア中銀はデジタル通貨を発行するのか? 「3つの理由」を開発企業が語る【ソラミツ】, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.coindeskjapan.com/35167/
- 日本企業と共同開発した中銀デジタル通貨「バコン」、正式運用開始 – Nulo, 5月 4, 2025にアクセス、 https://nulo.co.jp/ja/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%A8%E5%85%B1%E5%90%8C%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E4%B8%AD%E9%8A%80%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E9%80%9A%E8%B2%A8%E3%80%8C%E3%83%90%E3%82%B3/
- Cambodia CBDC – Human Rights Foundation Site, 5月 4, 2025にアクセス、 https://cbdctracker.hrf.org/currency/cambodia
- Design of a CBDC in a Highly Dollarized Emerging Market Economy: The Case of Cambodia – CARF Working Paper, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.carf.e.u-tokyo.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/F579.pdf
- Development of Central Bank Digital Currency in the Asia-Pacific Region – Discuss Japan, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.japanpolicyforum.jp/economy/pt2024041523151814191.html
- Background Notes on “Cambodia’s national mobile payments and digital currency platform- Bakong” – The Asian Banker, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.theasianbanker.com/press-releases/background-notes-on-cambodias-national-mobile-payments-and-digital-currency-platform-bakong?__hstc=36817983.6fa385653ecd7c9674ba06f08984886d.1740268800357.1740268800358.1740268800359.1&__hssc=36817983.1.1740268800360&__hsfp=1152905967
- Project Bakong 2020 – A Dollar Free Cambodia? – Nelito Blog, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.nelito.com/blog/project-bakong-2020-a-dollar-free-cambodia.html
- bakong.nbc.gov.kh, 5月 4, 2025にアクセス、 https://bakong.nbc.gov.kh/download/NBC_BAKONG_White_Paper.pdf
- The National Bank of Cambodia boosts financial inclusion with Hyperledger Iroha, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.lfdecentralizedtrust.org/case-studies/soramitsu-case-study
- 〜スタートアップ発の技術と世界・日本での取組み〜, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/fy2022/lm20220512.pdf
- ベストプラクティスからみるバハマとカンボジアのCBDC導入戦略 | 地域・分析レポート – ジェトロ, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2021/93af43aeec2839e7.html
- www.boj.or.jp, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/paym/digital/d_forum/wg4/dfo250203b.pdf
- カンボジア国立銀行デジタル通貨 「バコン」とブロックチェーンの最前線 – システム監査学会, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.sysaudit.gr.jp/gakkaishi/ronbun/202006/article_miyazawa.pdf
- 中央銀行デジタル通貨の基本的特性と実証実験, 5月 4, 2025にアクセス、 https://ryuka.repo.nii.ac.jp/record/1550/files/059-083hamorinaokosensei.pdf
- Cambodia’s central bank unveils cross border digital currency payments from Malaysia, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.ledgerinsights.com/cambodia-central-bank-cbdc-cross-border-digital-currency-payments-from-malaysia-bakong/
- Why a retail digital currency is working in Cambodia – Kapronasia, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.kapronasia.com/asia-payments-research-category/why-a-retail-digital-currency-is-working-in-cambodia.html
- Central Bank Digital Currency: program and further considerations, IMF policy papers, October 10, 2024, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2024/English/PPEA2024052.ashx
- 世界初のCBDC はなぜ消えたのか?(PDF), 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2022/2022win04.pdf
- Central Bank Digital Currency (CBDC) – Virtual Handbook – International Monetary Fund (IMF), 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/en/Topics/digital-payments-and-finance/central-bank-digital-currency/virtual-handbook
- BIS Working Paper 989: Central bank digital currencies (CBDCs) in Latin America and the Caribbean, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.bis.org/publ/work989.pdf
- Committee on Payments and Market Infrastructures Markets Committee Central bank digital currencies – Bank for International Settlements, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf
- デジタル通貨の現状と今後の展望~CBDC, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.iima.or.jp/docs/newsletter/2025/nl2025.18.pdf
- 中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する調査, 5月 4, 2025にアクセス、 https://www.iima.or.jp/docs/newsletter/2020/nl2020.06.pdf