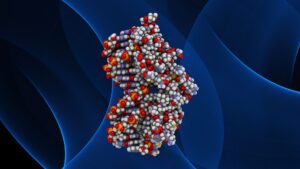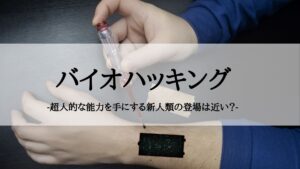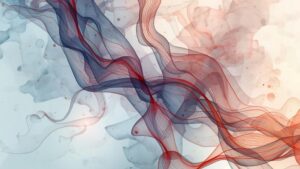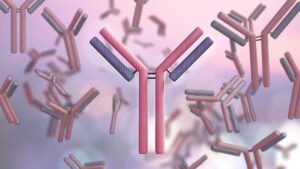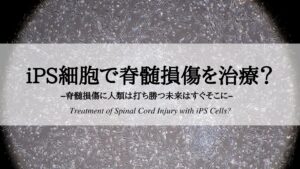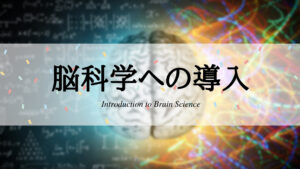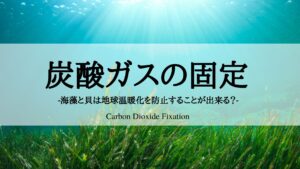1. はじめに
「ポップコーンジャンプ」という言葉について
私たちの周りの動物たちは、時に驚くような、そして興味深い行動を見せることがあります。ユーザーの皆様から寄せられた「ポップコーンジャンプ」という言葉は、特定の確立された学術用語ではありませんが、動物が見せる特徴的な跳躍行動を指す一般名、あるいは俗称として理解することができます。この言葉から連想されるのは、まるでポップコーンが弾けるかのように、突発的でエネルギッシュなジャンプでしょう。
この記事では、この「ポップコーンジャンプ」という表現が最も一般的に関連付けられるモルモットやチンチラの「ポップコーニング(Popcorning)」と呼ばれる行動と、形態や観察される文脈は異なりますが、ガゼルやシカなどが見せる類似した跳躍行動である「ストッティング(Stotting)」または「プロンキング(Pronking)」を取り上げ、これらの行動の背後にある生物学的メカニズム、すなわち生体力学(バイオメカニクス)、神経生物学、そして進化的な意義や機能について、深く掘り下げていきます。
ポップコーニングとは?
ポップコーニングは、主にモルモット(学名: Cavia porcellus)やチンチラ(学名: Chinchilla)といった齧歯類のペットにおいて観察される行動です 1。これらの動物が喜びや興奮といったポジティブな感情を抱いているときに、文字通りポップコーンが弾けるように、突然、垂直方向に高く跳び上がるのが特徴です 2。この行動は、彼らの幸福度を示すサインとも考えられています 5。
ストッティング/プロンキングとは?
一方、ストッティング(またはプロンキング、プロンギングとも呼ばれます)は、主にガゼル、シカ、ヒツジ、スプリングボックなどの有蹄類において観察される跳躍行動です 7。これは、四本の脚すべてを同時に、比較的硬直させた状態で地面から離し、空中に跳ね上がる独特の動きを指します 7。この行動は、特に捕食者の存在を感知した際など、特定の状況下で顕著に見られます 7。
本記事の目的と構成
本記事の目的は、これら二つの興味深い跳躍行動、「ポップコーニング」と「ストッティング/プロンキング」の背景にある生物学的メカニズムを、科学的な知見に基づいて、できる限りわかりやすく解説することです。具体的には、行動を支える物理的な仕組みである生体力学、行動の引き金となり制御する神経生物学的なプロセス、そしてこれらの行動が進化の過程でどのような意味を持ち、どのような機能を果たしてきたのか(あるいは果たしているのか)という進化的意義について、国内外の研究成果を参照しながら探求します。
構成としては、まず各行動(ポップコーニング、ストッティング/プロンキング)をより詳細に定義し、どのような状況で観察されるのかを述べます。次に、跳躍を可能にする生体力学的なメカニズムと、行動の発現に関わる神経生物学的な基盤について深く掘り下げます。最後に、これらの行動が持つ機能や進化的な意味について考察し、まとめと今後の展望を述べます。

2. ポップコーニング:喜びの跳躍
行動の詳細な記述
ポップコーニングは、モルモットやチンチラが見せる、非常に特徴的で見ていて楽しい行動の一つです。この行動は、動物が静止している状態から、あるいは元気に走り回っている最中に、何の前触れもなく突然始まります 3。文字通り、垂直方向に「ポン!」と跳び上がるのです 1。跳躍中には、体をひねったり、空中で向きを変えたりすることもあります 3。そして、着地後すぐにまた走り出したり、連続して何度もポップコーニングを繰り返したりすることもあります 1。重要な特徴は、跳躍の際に四肢すべてが同時に地面から離れる点です 3。時には、まるでロデオの馬のように、前脚と後脚を交互に蹴り出すような動きを見せることもあります 1。さらに、この行動中にはしばしば「キーキー」といった高い鳴き声を伴うことが報告されています 1。
観察される状況と感情との関連
ポップコーニングが観察される状況は、その行動が持つ意味を理解する上で重要です。この行動は、圧倒的にポジティブな感情、すなわち喜び、幸福感、興奮といった状態と強く関連付けられています 1。例えば、ケージに新しいおもちゃが入れられた時、新鮮な干し草や大好きなおやつが与えられた時、あるいは飼い主が近づいてきて撫でたり遊んだりしようとした時などに、ポップコーニングが見られることがよくあります 1。
この行動は特に若い個体で頻繁に観察されますが、成熟した個体でも見られないわけではありません 1。若い個体の方がより高く、より頻繁に跳ぶ傾向があるようです 13。
ただし、非常に稀なケースとして、ポップコーニングが恐怖や驚きの反応として現れる可能性も指摘されています 1。例えば、突然の大きな音や、見慣れないもの(他のペットなど)の出現に対して、驚いて跳び上がる場合です。そのため、ポップコーニングを観察した際には、その時の状況を注意深く評価することが重要です。周囲に怖がらせるような要因がなく、リラックスした様子で跳んでいるのであれば、それは喜びの表現と解釈して良いでしょう。しかし、何か特定の刺激の直後に、怯えた様子と共に跳んでいる場合は、恐怖反応の可能性も考慮する必要があります 1。
遊び行動としてのポップコーニング
動物行動学の観点から見ると、ポップコーニングは「移動遊び(Locomotor Play)」と呼ばれるカテゴリーに分類される行動と考えられます 3。移動遊びとは、走る、跳ぶ、回転する、追いかけるといった、身体の移動を伴う遊び行動全般を指します。
遊び行動は一般的に、「直接的な生存上の目的を持たず、自発的に行われ、それ自体が楽しい、あるいは報酬となるような活動」として定義されます 15。ポップコーニングは、特定の餌を得るためや捕食者から逃れるためといった明確な機能的文脈で常に行われるわけではなく、むしろ内的なポジティブな状態に応じて自発的に発現するように見えることから、この遊びの定義によく合致しています。
この行動が幸福感と強く結びついているという事実は、モルモットやチンチラのポジティブな福祉状態を示す、観察可能な指標となりうる可能性を示唆しています 6。動物福祉の研究では、動物の内的状態を客観的に評価するための信頼できる行動指標が求められており 18、ポジティブな状態と強く関連する行動は、その候補となり得ます。ただし、ポップコーニングを全くしない個体でも幸福である可能性は十分にあり 1、個体差も考慮する必要があるため、ポップコーニングが見られることはポジティブな状態を示す十分条件かもしれませんが、必要条件ではない点に注意が必要です。
さらに、ポップコーニングが特に若い個体で頻繁に見られる移動「遊び」であるという点は、その行動が持つ潜在的な発達上の機能を示唆しているかもしれません。移動遊びは、運動能力の発達、特に協調性やバランス、迅速な方向転換といったスキルの洗練に寄与するという仮説があります 20。ポップコーニングで見られる複雑で素早い動き 3 は、まさにこれらの能力を鍛える機会を提供している可能性があります。したがって、たとえその直接的な引き金が喜びや興奮といった感情であったとしても、ポップコーニングという行動自体が、成長過程にある動物にとって重要な運動学習の機会となっているのかもしれません。これは、遊びが将来必要となるスキルを練習する場を提供するという、より広範な遊びの機能に関する理論とも一致します 22。
3. ストッティング/プロンキング:生存戦略としての跳躍
行動の詳細な記述
ストッティング、あるいはプロンキングは、ガゼル、シカ(ミュールジカ、オグロジカなど)、プロングホーン、スプリングボック、インパラ、さらには家畜化されたヒツジやヤギの若い個体など、様々な有蹄類で観察される非常に特徴的な跳躍行動です 7。この行動の最も顕著な特徴は、四本の脚すべてを同時に地面から蹴り、空中に跳び上がることです。その際、脚は比較的まっすぐに、硬直したように保たれることが多いです 7。跳躍中に背中を丸くアーチさせ、頭を下に向ける姿勢をとることもあります 9。スプリングボックなどでは、跳躍の高さが2メートルにも達することが報告されており 24、非常にダイナミックな行動です。
観察される状況:対捕食者文脈
ポップコーニングが主にポジティブな感情と結びついているのとは対照的に、ストッティング/プロンキングは、多くの場合、捕食者の存在というネガティブ、あるいは危険な文脈で観察されます 7。チーターやリカオンといった捕食者を視認した際や、実際に追跡されている最中に、この行動を示すことが知られています。
興味深いことに、トムソンガゼルの場合、捕食者が非常に近い距離(約40メートル未満)にいるときにはストッティングを行わず、ある程度の距離がある場合にのみ行うという報告があります 7。これは、ストッティングが単なるパニック的な逃走行動ではない可能性を示唆しています。
若い個体においては、ストッティングが遊びの一環として見られることもありますが 7、成獣がこの行動を示す場合は、ほとんどが捕食者に対する反応であると考えられています。
生体力学(バイオメカニクス)的特徴
ストッティングにおける四肢を同調させ、硬直させて跳躍する動きは、通常のギャロップ(襲歩)やトロット(速歩)といった、脚を交互に繰り出す効率的な走行様式とは大きく異なります 7。この独特な跳躍は、エネルギーと時間を著しく消費します。さらに、高く跳び上がることで自身の存在を捕食者に対してより目立たせてしまうというリスクも伴います 7。
一見すると、捕食者から逃れる上で不利にしか見えないこの行動が、なぜ進化の過程で保存され、多くの種で見られるのでしょうか。この疑問は、ストッティング/プロンキングが、そのコストを上回る何らかの重要な利益(機能)を動物にもたらしているはずだという推測につながります。
ポップコーニング(喜び/遊びの文脈)とストッティング(危険/対捕食者の文脈)は、表面的な跳躍パターン(突発的、四肢同時)に類似性が見られるにもかかわらず 1、その典型的な発生状況が著しく対照的であることは注目に値します。これは、齧歯類と有蹄類という系統的に離れたグループにおいて、類似した運動パターンが全く異なる機能的理由から独立に進化した(収斂進化)可能性を強く示唆しています。進化の過程では、既存の運動パターンが転用されたり、異なる問題解決のために類似した解決策が独立に進化したりすることがしばしばあります。したがって、この突発的な四肢同時跳躍という動作自体は、生体力学的に達成可能な爆発的な動きであり、あるグループでは感情表現のために、別のグループでは捕食者との相互作用のために、それぞれ選択・洗練されてきたのかもしれません。
また、ストッティングがその明らかなコスト(エネルギー消費、被視認性の増加)にもかかわらず行われるという事実は、それが伝えるシグナル(例:適応度、捕食者検知)が非常に効果的であるか、あるいは特定の状況下での直接的な利益(例:障害物地形での逃走効率向上)が、これらのコストを大幅に上回る必要があることを意味します。これは、捕食者・被食者間のダイナミクスにおいて、シグナリング戦略や特殊な逃走戦略がいかに強力な選択圧となりうるかを物語っています。多くの種が捕食圧に晒されながらもストッティング行動を維持していること 7 は、その利益がコストを相殺するのに十分大きいことを示唆しています。
4. 跳躍の生物学的メカニズム:生体力学
動物が見せる跳躍行動は、単なる筋力の発揮だけではなく、身体の構造を巧みに利用した洗練されたメカニズムに基づいています。ポップコーニングの爆発的な動きや、ストッティングの力強い跳躍を理解するためには、生体力学(バイオメカニクス)の原理、特に弾性エネルギーの利用について考えることが不可欠です。
弾性エネルギーの貯蔵と解放
多くの動物が跳躍や走行を行う際、筋肉が直接生み出す力に加えて、腱(tendon)や腱膜(aponeurosis)といった結合組織の弾性を利用しています 28。これらの組織はバネのように機能し、運動中にエネルギーを一時的に蓄え、それを急速に解放することで、より大きなパワーや効率性を実現します。
このプロセスは次のように説明できます。まず、筋肉が収縮し、それに繋がる腱を引き伸ばします。この伸長によって、腱には弾性的な歪みエネルギー(strain energy)が蓄積されます(エネルギー貯蔵)。次に、筋肉の活動が変化したり、関節の角度が変わったりすることで、伸ばされた腱が元の長さに戻ろうとして急速に収縮します。この急速な収縮(反跳、recoil)によって、蓄えられていたエネルギーが一気に解放され、大きな力やパワーとして身体の動きに変換されます(エネルギー解放) 28。このメカニズムの利点は、筋肉が単独で収縮する場合に比べて、より大きなパワーを発揮できる点にあります。筋肉の収縮速度には生理的な限界がありますが、腱の反跳速度はこの限界を超えることができるため、瞬間的に非常に大きなパワーを生み出すことが可能になるのです 28。
この弾性エネルギーの貯蔵・解放メカニズムは、驚くほど多様な動物の運動で見られます。例えば、バッタの驚異的な跳躍力の一部は、脚の関節にある半月状突起(Semi-Lunar Process, SLP)と呼ばれる特殊なクチクラ構造にエネルギーを蓄えることで実現されています 35。カンガルーやウマ、ガゼルといった走行や跳躍を得意とする哺乳類では、特にアキレス腱などの脚の長い腱が効率的なエネルギー貯蔵・解放に貢献しています 30。意外なことに、私たちヒトの日常的な歩行や走行、ジャンプにおいても、アキレス腱や膝蓋腱などが弾性エネルギーを利用して、運動の効率を高めたり、パワーを増強したりしていることが分かっています 29。
腱がどれだけのエネルギーを蓄えられるかは、その物理的な特性、すなわち剛性(stiffness)、長さ、断面積といった形態学的特徴に依存します 32。一般的には、長くて細い腱ほど、同じ力に対してより大きく伸びるため、より多くのエネルギーを蓄えるのに適していると考えられてきました 30。しかし、最近の研究では、カンガルーネズミのような小型の跳躍動物においても、以前考えられていたよりも腱が柔軟であり、大型動物と同様に速度に応じて弾性エネルギーの貯蔵量を変化させる、機能的に類似したメカニズムが働いている可能性が示唆されています 30。これは、体のサイズや腱の太さに関わらず、弾性エネルギー利用が跳躍・走行において普遍的に重要な役割を果たしている可能性を示しています。
跳躍パワーの増幅と神経筋制御
腱などの弾性要素を利用することは、筋肉が生み出すパワーを効果的に増幅させるメカニズムとして機能します。これはしばしば「カタパルト機構」に例えられます 29。筋肉が比較的ゆっくりとした収縮で時間をかけて弾性要素にエネルギーを溜め込み、それを一気に解放することで、瞬間的に大きなパワーを生み出すのです。
しかし、この強力な跳躍を実現するためには、単に弾性的な部品があれば良いというわけではありません。神経系による精密な制御と、身体の機械的特性との絶妙な相互作用、すなわち「神経機械的(neuromechanical)カップリング」が不可欠です 35。
例えば、前述のバッタの跳躍では、跳躍準備段階で脚を曲げる筋肉(屈筋)と伸ばす筋肉(伸筋)が同時に収縮し(co-contraction)、腱やSLPにエネルギーを蓄積します。そして、跳躍の瞬間、神経系からの指令で屈筋への抑制信号が送られ、屈筋が急激に弛緩します。これにより、伸筋側に蓄えられたエネルギーが一気に解放され、爆発的な脚の伸展が起こるのです 35。
また、カエルなどの脊椎動物の跳躍においては、解剖学的な「掛け金(catch)」が見当たらないにも関わらず、効果的に弾性エネルギーを溜め込む仕組みが存在すると考えられています。一つの仮説として、跳躍の初期段階では、足首を伸ばす筋肉の「機械的有利性(mechanical advantage)」、すなわち、てこの原理における力の伝達効率が意図的に低く保たれるというものがあります。これにより、筋肉が高い力を発生してもすぐには足首が伸びず、エネルギーが腱に効率的に蓄積されます。そして、跳躍の後半になると、関節角度の変化などにより機械的有利性が高まり、蓄積されたエネルギーが効率的に足首の伸展運動へと変換・解放されるのです。これは「変化する機械的有利性によるラッチ機構」とも呼ばれます 31。
さらに、複数の脚を持つ動物においては、四肢の協調(coordination)も極めて重要です 40。ストッティング/プロンキングで見られるような、四肢すべてを同調させて跳躍する動きは、脚を交互に動かす通常の歩行や走行とは全く異なる神経制御パターンを必要とします 7。
ポップコーニングとストッティングへの適用
これまでの議論を踏まえると、ストッティング/プロンキングで見られる高く、力強い跳躍は、腱などの弾性エネルギー貯蔵・解放メカニズムに大きく依存している可能性が非常に高いと考えられます。特に、ガゼルやシカなどの有蹄類は、走行に適した長い腱を持っており、この弾性機構を最大限に活用していると推測されます。
一方、モルモットやチンチラのポップコーニングについてはどうでしょうか。その突発的で「弾ける」ような動きの性質は、弾性エネルギーの急速な解放が関与している可能性を示唆しています。しかし、これらの動物の腱の特性や、跳躍中の詳細な筋活動、エネルギーの流れに関する具体的な研究データは、現時点では限られています 4。ストッティングを行う動物ほど高度に最適化された弾性機構ではないかもしれませんが、ポップコーニングの爆発的な性質を生み出す上で、ある程度の弾性エネルギーの利用が寄与している可能性は十分に考えられます。この点は、今後の研究によって明らかにされるべき興味深い課題です。
提案テーブル:ポップコーニングとストッティング/プロンキングの比較
| 特徴 (Feature) | ポップコーニング (Popcorning) | ストッティング/プロンキング (Stotting/Pronking) |
| 主な動物種 (Typical Species) | モルモット, チンチラ 1 | ガゼル, シカ, ヒツジ, スプリングボック等 7 |
| 主な文脈 (Typical Context) | 遊び, 興奮, ポジティブな感情 (稀に恐怖) 1 | 対捕食者 (防御, シグナル) 7 |
| 跳躍の特徴 (Jump Characteristics) | 爆発的, しばしば垂直, 体のひねりや方向転換を伴う 1 | 硬直した四肢, 同時離陸, 高い垂直跳躍 7 |
| 主な機能仮説 (Likely Primary Function) | 感情表現, 遊び (移動遊び) 1 | 捕食者抑止/検知, 逃走, 遊び (若い個体) 7 |
| 弾性機構への依存度 (Reliance on Elastic Mechanisms) | 爆発性に寄与する可能性が高いが、最適化の度合いは不明 (推測、研究不足) 1 | パワー/高さのために高く依存 (生体力学 28 及び行動 7 から推測) |
この比較表は、本レポートで議論されている二つの行動の主な違いと類似点を明確に示しています。特に、弾性メカニズムへの依存度に関する現在の知見の差(ストッティングでは高い依存が推測される一方、ポップコーニングでは更なる研究が必要)が浮き彫りになります。
有蹄類におけるストッティングのような行動を可能にする、非常に効率的な弾性メカニズム(長いアキレス腱など)の進化は、この行動自体の進化を促す重要な「基盤」であったと考えられます。筋肉単独のパワーだけでは実現不可能な、エネルギー的にコストの高いシグナル伝達や、強力な逃走マニューバを可能にしたのです。これは、形態(身体の構造)、生理(筋肉や腱の特性)、そして行動が相互に影響し合いながら進化してきた(共進化)ことを示唆しています 39。つまり、弾性組織が提供する物理的な能力が、ストッティングという特異な行動戦略の進化を促進した可能性が高いのです。
また、神経機械的制御という概念は、跳躍行動が決して事前にプログラムされた単純な反射ではなく、感覚からのフィードバックや、身体の物理的特性と環境との相互作用によって動的に形成されるアクションであることを示唆しています 37。これは、一見自発的に見えるポップコーニングと、特定の文脈(捕食者の存在)に依存するストッティングの両方に当てはまります。動物は、自身の内部状態や外部環境の変化に応じて、跳躍のタイミングや強さを微妙に調整している可能性があります。この動的な制御システムこそが、様々な状況下での適応的な跳躍行動を可能にしているのです。
5. 跳躍の生物学的メカニズム:神経生物学
動物が特定の行動をとる背景には、その行動を引き起こし、制御し、そしてその行動に伴う感情や動機付けを司る、複雑な神経系の働きがあります。ポップコーニングやストッティングといった跳躍行動も例外ではありません。ここでは、これらの行動に関連する神経生物学的なメカニズムを、遊びや報酬、恐怖といった側面から探ります。
(A) 遊びと報酬系の神経基盤
ポップコーニングが主に「遊び」や「喜び」といったポジティブな感情の文脈で観察されることから、これらの情動や行動を制御する脳内の神経メカニズム、特に報酬系の関与が強く示唆されます。
- ドーパミン (Dopamine): ドーパミンは、快感、意欲、学習、運動制御など、多岐にわたる機能に関与する重要な神経伝達物質です 41。動物の遊び行動、特にラットを用いた研究では社会的遊び(じゃれつき遊びなど)の動機付け(「やりたい」という気持ち)にドーパミンが重要な役割を果たしていることが示されています 15。ドーパミン神経系の活動を高める薬物が遊び行動を変化させることからも、その関与が裏付けられています 43。ポップコーニングのような自発的で楽しそうな行動も、ドーパミンによってその動機付けが制御されている可能性があります。
- 報酬系 (Reward System): 脳内で報酬情報を処理し、快感や意欲を生み出す神経回路網を報酬系と呼びます。その中核をなすのが、中脳の腹側被蓋野(VTA)から大脳基底核の一部である側坐核(NAcc)へと投射するドーパミン神経経路(中脳辺縁系ドーパミン経路)です 41。側坐核は「報酬の中枢」とも呼ばれ、ドーパミンだけでなく、内因性オピオイド(モルヒネ様物質)やエンドカンナビノイド(大麻様物質)といった他の神経調節物質の作用点としても知られています 43。ラットの社会的遊びの研究では、この側坐核が遊びの快感(報酬的価値)や、遊びたいという動機付け(インセンティブ)を制御する上で、極めて重要な部位であることが特定されています 43。ポップコーニングに伴う喜びや興奮も、この側坐核を中心とした報酬系の活性化によって生み出されていると考えられます。
- その他の神経系/脳部位: 報酬系は単独で機能しているわけではなく、他の神経系や脳領域と複雑なネットワークを形成しています。内因性オピオイド系は遊びに伴う快感の生成に 43、エンドカンナビノイド系は情動調節や遊び行動の促進に 43、ノルアドレナリン系は覚醒レベルや注意、遊びの認知的側面に 43、それぞれ関与していることが示唆されています。また、脳領域としては、情動処理に重要な扁桃体 43、意思決定や行動の柔軟性に関わる前頭前野 43、報酬や罰の処理に関わる手綱核 43、視床や視床下部なども、遊び行動の調節に関わる広範なネットワークの一部を構成しています 43。
- 遊びと学習・ストレス: 興味深いことに、遊び行動は、ストレス反応を引き起こすことなく報酬回路を活性化すると考えられています 15。通常、強いストレス状況下ではコルチゾールなどのストレスホルモンが分泌されますが、遊びの最中にはこのような反応が見られにくいのです。むしろ、遊びは学習を促進するような神経状態を作り出す可能性が指摘されています 15。これは、遊びがリラックスした状況で行われ、失敗に対するペナルティが少ないため、新しい行動パターンを試したり、環境を探索したりするのに適した状態を提供するからかもしれません。
ポップコーニングが主に喜びや遊びの文脈で生じ、その行動自体が報酬系(特に側坐核におけるドーパミンやオピオイドの作用)を活性化するという神経生物学的な知見は、なぜモルモットたちが「楽しそうに」この行動を繰り返すのか、そのメカニズム的な基盤を提供します。報酬系の活性化は快感を生み出し、その行動を再び行いたいという動機付け(強化)につながるため 41、ポップコーニングは自己報酬的な行動となり、ポジティブな内的状態と直接的に結びつくと考えられます。これは、ポップコーニングが良好な動物福祉の指標となりうるという考えを、神経メカニズムのレベルからも支持するものです。
(B) 恐怖・対捕食者反応の神経基盤
ストッティング/プロンキングが主に対捕食者という脅威的な文脈で生じること、そしてポップコーニングも稀に恐怖反応として現れる可能性があることから、恐怖やストレス、防御行動に関わる神経メカニズムも、これらの跳躍行動の理解に関連してきます。
- 扁桃体 (Amygdala): 扁桃体は、情動、特に恐怖や不安といったネガティブな感情の処理において中心的な役割を担う脳領域です 48。危険を察知し、過去の恐怖体験(恐怖記憶)を呼び起こし、そして迫りくる脅威に対して適切な防御反応(例:すくみ固まる、逃走する、攻撃するなど)を引き起こす上で不可欠です。捕食者の匂いのような、学習を必要としない生得的な脅威刺激に晒されると、扁桃体は強く活性化します 48。ストッティングが捕食者の存在によって引き起こされることを考えると、扁桃体の活性化がそのトリガーの一つとなっている可能性が高いです。
- 扁桃体の可塑性とストレス: 捕食者に遭遇するような強いストレス体験は、扁桃体の神経回路に長期的な変化(神経可塑性)を引き起こすことが知られています 49。例えば、一度強い恐怖を経験すると、扁桃体の神経細胞がより興奮しやすくなったり(感作)、神経細胞の形態(樹状突起の長さや分岐)が変化したりすることがあります 50。これにより、将来類似の脅威に遭遇した際に、より過敏な恐怖反応を示すようになる可能性があります。これは、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの病態とも関連付けられています 48。
- 恐怖反応に関わるネットワーク: 扁桃体は、恐怖反応の実行に関わる他の脳領域と密接に連携しています。例えば、視床下部はストレスホルモンの分泌を制御し、中脳水道周囲灰白質(PAG)はすくみ反応などの防御行動の表出に関わり、青斑核は覚醒レベルを高めるノルアドレナリンを放出します 48。扁桃体からの信号がこれらの領域に伝わることで、全身的な恐怖・防御反応が引き起こされます。
- ドーパミンと恐怖: ドーパミンは主に報酬系との関連で知られていますが、脅威に対する反応や、接近と回避の間の葛藤(approach-avoidance conflict)の調節にも関与している可能性が示唆されています 55。特に、扁桃体の一部である内側扁桃体(MeA)にはドーパミン受容体が存在し、この領域のドーパミン神経系が、脅威刺激に対する探索的な接近行動と防御的な回避行動のバランスを調節している可能性が指摘されています 55。ストッティングのような、危険を冒してシグナルを送る行動には、このような接近・回避の葛藤を解決する神経メカニズムが関わっているのかもしれません。
ストッティングは脅威(捕食者)によって引き起こされるため、扁桃体を中心とした恐怖・防御回路の活性化がその基盤にあると考えられます 48。しかし、もしストッティングが捕食者をうまく追い払ったり、自身の適応度を効果的に伝えたりすることに成功した場合、その「成功体験」自体が報酬となり、行動が強化される可能性も考えられます。これは、脅威反応の最中にも、ドーパミンを中心とした報酬・学習回路が関与しうることを示唆します 42。つまり、ストッティングの持続には、恐怖回路によるトリガーと、成功体験による報酬回路を介した強化という、二つの神経メカニズムが相互作用しているのかもしれません。
(C) 運動制御に関わる神経回路
ポップコーニングであれストッティングであれ、実際に跳躍という運動を実行するためには、脳と脊髄にある運動制御システムが正確に機能する必要があります。
- 運動指令の生成と伝達: 跳躍のようなリズミカルな運動パターンの一部は、脊髄内に存在する中枢パターン生成器(CPG: Central Pattern Generators)と呼ばれる神経回路網によって基本的なリズムが生成されると考えられています 26。しかし、実際の跳躍の開始、力の調整、着地などは、大脳皮質の運動野、運動の協調やバランスに関わる小脳、運動の開始や調節に関わる大脳基底核など、より高次の脳領域からの指令が統合されて実行されます。これらの指令は、最終的に脊髄の運動ニューロンを介して、適切なタイミングで適切な筋肉へと伝えられます。
- 神経機械的相互作用とフィードバック: 神経系からの指令(電気信号)は、神経筋接合部で化学信号に変換され、筋肉の収縮を引き起こします。この筋収縮によって発生した力が、骨格(レバー)を介して身体の動きを生み出します。しかし、運動制御は一方通行ではありません。身体が動くと、筋肉や腱にあるセンサー(筋紡錘やゴルジ腱器官など)や、皮膚、関節にあるセンサーが、動きの状態(位置、速度、力など)を検出し、その情報を感覚神経を介して脳や脊髄に送り返します(感覚フィードバック)。このフィードバック情報は、進行中の運動を微調整したり、次の動作を計画したりするために利用されます 37。このように、神経系、筋肉、骨格、そして感覚系が相互に作用しあいながら、滑らかで協調した運動が実現されているのです。
遊びや報酬に関わる回路、恐怖や防御に関わる回路、そして運動制御に関わる回路が、それぞれ異なる役割を担いつつも、相互に連携していることは明らかです。ポップコーニングという単一の跳躍行動が、ある時は喜びの表現として報酬系によって動機づけられ、またある時は(稀に)恐怖反応として扁桃体系によって引き起こされる可能性があるという事実は、脳が状況に応じて異なる神経回路を選択的に利用し、同じ運動出力(跳躍)を生み出す柔軟性を持っていることを示しています。これは、脳機能のモジュール性(専門化)と、それらのモジュール間の高度な相互接続性(ネットワーク)を反映していると言えるでしょう。
6. 跳躍行動の進化的意義と機能
動物が見せる行動は、多くの場合、その動物の生存や繁殖成功率を高めるための何らかの適応的な意味(機能)を持っています。一見奇妙に見えるポップコーニングやストッティングも、進化の過程で何らかの利益をもたらしてきたからこそ、現在の動物たちに受け継がれていると考えられます。ここでは、これらの跳躍行動が持つとされる機能や、その進化的な意義について考察します。
ストッティング/プロンキングの機能仮説
ストッティング/プロンキングは、エネルギーを消費し、捕食者に目立つという明らかなコストがあるため、その機能については多くの仮説が提唱され、議論されてきました 7。
- 正直なシグナル (Honest Signal) 仮説: これはおそらく最も有力視されている仮説の一つです。ストッティングは、自身の健康状態や身体能力(特に逃走能力)の高さを捕食者に対して「正直に」伝えるシグナルであるという考え方です 7。高く、力強くストッティングできる個体は、実際に捕まえにくい相手であることを示しています。捕食者は、このシグナルを受け取ることで、成功率の低い追跡を避け、より捕まえやすい獲物を探すことにエネルギーを振り向けることができます。一方、ストッティングを行った被食者は、無駄な追跡を受けずに済みます。このように、正直なシグナルは、シグナルを送る側(被食者)と受け取る側(捕食者)の双方に利益をもたらすため、進化的に安定しやすいと考えられています。この仮説は、アモツ・ザハヴィが提唱した「ハンディキャップ原理」の一例としても解釈できます 7。つまり、ストッティングという一見不利な行動(ハンディキャップ)をあえて行うことで、自身の質の高さを証明しているというわけです。
- 捕食者検知通知 (Predator Detection Signal) 仮説: この仮説は、ストッティングが捕食者に対して「あなたの存在に気づいている」ということを伝えるシグナルであると考えます 7。多くの捕食者、特に待ち伏せ型や忍び寄り型の捕食者(例:チーター)は、獲物に気づかれずに接近することが狩りの成功に不可欠です。もし獲物が捕食者の存在に気づいていることを示せば、捕食者は奇襲効果を失い、狩りを諦める可能性が高まります。実際に、チーターはストッティングを行うトムソンガゼルに対する狩りを、行わないガゼルに対する狩りよりも頻繁に中断するという観察結果が、この仮説を支持しています 7。これも正直なシグナルの一種(追跡抑止シグナル)と見なすことができます。
- 逃走戦略 (Escape Strategy) 仮説: 近年、特に注目されているのが、ストッティング/プロンキングが特定の環境下での効果的な逃走手段である可能性です。シミュレーションを用いた研究により、低木や岩などが散在する障害物の多い草原環境において、ある閾値以上の障害物密度になると、ストッティング(あるいは類似の跳躍であるバウンディング)が、障害物を飛び越えながら最も速く、かつ安全に(衝突せずに)移動するための最適な歩容(走り方・跳び方)になることが示されました 8。この仮説は、ストッティングが単なるシグナルではなく、直接的な逃走の利益をもたらす可能性を示唆しています。
- その他の仮説: 上記以外にも、いくつかの仮説が提唱されています。例えば、群れの仲間に危険を知らせる警戒信号 7、群れ全体で一斉にストッティングを行うことで捕食者が特定の個体を狙いにくくする社会的結束・混乱効果 7、背の高い草むらの中で跳び上がって周囲の捕食者を確認する待ち伏せ回避行動 7、そして若い個体における遊び行動 7 などです。警戒信号説や社会的結束説は、個体の利益よりも群れの利益を優先する「群選択」的な説明であり、進化生物学的には批判的に見られることが多いです 7。
現在では、正直なシグナル仮説や捕食者検知通知仮説が、多くの研究者によって有力な説明として支持されています 7。しかし、ストッティングが観察される状況や種によって、あるいは個体の年齢によって、これらの機能が複合的に働いていたり、異なる機能が主になっていたりする可能性も十分に考えられます。
ポップコーニングの機能
ポップコーニングの機能は、ストッティングほど多様な仮説が立てられているわけではありませんが、主に以下の点が考えられます。
- 情動表出 (Emotional Expression): 最も明白な機能は、ポジティブな感情(喜び、幸福感、興奮)の表出です 1。モルモットやチンチラが飼い主や仲間に対して自身のポジティブな状態を伝える、非常にわかりやすい行動シグナルと言えます。
- 遊び行動 (Play Behavior): 前述の通り、ポップコーニングは移動遊びの一形態であり、行動それ自体が自己報酬的で楽しい活動であると考えられます 3。遊び行動には、それ自体が目的であるという側面があります。
- 遊び行動の広範な機能への寄与: ポップコーニングは、遊び行動が持つとされる、より広範な発達上の機能(後述)の一部を担っている可能性も否定できません。
遊び行動の一般的機能
ポップコーニングが遊び行動の一種であることを考えると、一般的に動物の遊び行動にどのような機能があると考えられているかを知ることは有益です。遊びの機能についても、単一の説明で全てを網羅することは難しく、複数の仮説が提唱されています 16。
- スキル獲得 (Skill Acquisition): 遊びは、将来の生存や繁殖に役立つ様々なスキルを練習し、習得するための重要な機会を提供すると考えられています 20。
- 運動能力の向上: 走る、跳ぶ、よじ登る、バランスをとる、といった遊びを通じて、筋力、持久力、敏捷性、協調性などの身体能力が向上します 20。これは「運動トレーニング仮説」とも呼ばれます 21。
- 社会的スキルの発達: 特に社会的遊び(じゃれつき遊びなど)は、他個体とのコミュニケーション方法、協力や競争のルール、攻撃の抑制、社会的順位の認識などを学ぶ上で重要です 20。
- 認知スキルの発達: 遊びは、問題解決能力、環境の変化に対応する柔軟性、新しい状況への適応力といった認知能力の発達を促進する可能性があります 16。遊びを通じて、環境や物体の特性を学び、新しい行動パターンを試すことができます。
- 社会的絆の形成・維持 (Social Bonding): 遊びは、特に社会的な動物において、親子間、兄弟姉妹間、あるいは仲間同士のポジティブな関係(社会的絆)を形成し、維持する上で重要な役割を果たします 20。共に遊ぶ経験は、信頼関係を築き、将来の協力行動の基盤となる可能性があります。
- ストレス軽減・対処能力向上 (Stress Reduction/Coping): 遊びは、それ自体が楽しい活動であるため、ストレスを軽減する効果があると考えられています 22。また、遊びの中で経験する、予期せぬ出来事や軽いストレス(例:追いかけられる、バランスを崩す)への対処を通じて、将来、より深刻なストレス状況に効果的に対処する能力(コーピング能力)を高める可能性も指摘されています 16。
- 自己評価・他者評価 (Self/Other Assessment): 遊び、特に競争的な要素を含む遊びは、自分自身の身体能力や社会的スキルを試したり、他個体の能力を評価したりする機会を提供します 61。これは、将来の競争相手や協力相手を見極める上で役立つ可能性があります。
- 好奇心の副産物 (Byproduct of Curiosity): 近年、注目されている新しい考え方として、遊び行動は特定の適応的な機能のために直接的に選択されて進化したのではなく、むしろ、新しいものや未知のものに対する探求心、すなわち「好奇心」に関わる神経心理学的なメカニズムの進化的副産物として出現したのではないか、という仮説があります 63。この説では、好奇心と遊びを引き起こす刺激や、それらの根底にある神経基盤(報酬系など)に共通性が見られることが指摘されています 63。
ストッティングと遊び行動の両方に対して、複数の機能仮説が存在し、かつそれらが相互に排他的ではないという事実は、進化プロセスの複雑さを物語っています。単一の行動が、発達の異なる段階で、あるいは異なる状況下で、複数の選択圧によって形成され、複数の機能を同時に、あるいは連続的に果たしている可能性があるのです。例えば、若い個体におけるストッティングは主に運動能力の発達(遊び)に寄与し、それが成体になると捕食者へのシグナル伝達という異なる機能のために洗練・利用されるようになる、といったシナリオも考えられます。これは、行動の進化がしばしば層状的で複雑なプロセスであることを示唆しています。
ストッティングに関する「正直なシグナル」仮説は、生物学におけるコミュニケーション理論の好例です。シグナルを送る側(被食者)と受け取る側(捕食者)の間に利害の対立があるにもかかわらず、どのようにして信頼できる(正直な)シグナルが進化しうるのか、という問題に対する一つの解答を与えています 64。ストッティングが進化的に安定なシグナルであるためには、その行動を実行するためのコストが十分に高く、本当に適応度の高い個体だけが効果的に行えるような性質を持つ必要があります(ハンディキャップ原理との関連 7)。これにより、シグナルの「正直さ」が保証されるのです。この原理は、配偶者選択における求愛ディスプレイや、縄張り防衛における威嚇行動など、他の多くの動物コミュニケーションシステムにも広く適用可能です 65。
一方、ポップコーニングの主な機能は、即時的な感情表現や遊びそのものにあるように見えますが、それが運動能力の発達に寄与する可能性(前述)を考えると、遊び行動が持つ広範な適応的意義と無関係ではありません。一見「目的がない」ように見える喜びの表現行動でさえ、長期的には個体の適応度(生存や繁殖の成功)に、たとえ間接的にであっても、貢献している可能性があるのです。これは、遊びが個体を成体期の生活に向けて準備させるという、遊びの機能に関する古典的な考え方とも一致します 16。
7. おわりに
本記事のまとめ
本記事では、「ポップコーンジャンプ」という言葉を手がかりに、モルモットやチンチラに見られる「ポップコーニング」と、ガゼルなどの有蹄類に見られる「ストッティング/プロンキング」という、二つの特徴的な跳躍行動について、その生物学的メカニズムと進化的意義を探求してきました。
- ポップコーニングは、主にモルモットやチンチラが喜びや興奮といったポジティブな感情を表す際に見せる、突発的で垂直的な跳躍行動であり、動物行動学的には「移動遊び」に分類されます。この行動の背景には、ドーパミン作動性の報酬系を中心とした、快感や動機付けに関わる神経回路の活動が関与していると考えられます。生体力学的には、その爆発的な性質に腱などの弾性エネルギー利用が寄与している可能性が示唆されますが、詳細は未解明です。
- ストッティング/プロンキングは、主にガゼルなどの有蹄類が捕食者に遭遇した際に見せる、四肢を硬直させて高く跳び上がる行動です。その機能については、自身の適応度を伝える「正直なシグナル」仮説や、捕食者に検知を伝える「捕食者検知通知」仮説、あるいは特定の環境下での「逃走戦略」仮説などが提唱されています。この行動は、扁桃体を中心とした恐怖・防御反応に関わる神経回路によって引き起こされ、跳躍のパワーは腱の弾性エネルギー貯蔵・解放メカニズムに大きく依存していると考えられます。
- 両行動に共通して言えるのは、それらが単なる筋肉の収縮だけでなく、神経系による精密なタイミング制御と、骨・関節・筋肉・腱といった身体の物理的・機械的特性とが相互に作用しあう「神経機械的プロセス」によって実現されているということです。
今後の研究への展望
これらの興味深い跳躍行動に関する我々の理解は進んできましたが、まだ多くの謎が残されています。
- 特にポップコーニングに関しては、その詳細な生体力学的メカニズム、例えば、跳躍中の各関節の動きや筋活動、腱の弾性エネルギーが実際にどの程度寄与しているのか、といった点を明らかにする研究が必要です。また、脳活動を直接計測する技術(例:fMRI、電気生理学的手法など、ただし小型動物への適用は技術的課題がある)を用いて、ポップコーニング中の報酬系や情動関連領域の活動を詳細に調べることで、その神経基盤に関する理解が深まるでしょう。
- ストッティング/プロンキングに関しても、提唱されている様々な機能仮説を検証するためには、より多様な状況下(異なる捕食者の種類、地形、群れの構成など)での詳細な行動観察や、生理学的指標(心拍数、ストレスホルモンなど)の計測、あるいはバイオロギング技術を用いた運動データの収集などが有効です。
- さらに、異なる動物種で見られる類似した行動(この場合は跳躍)が、それぞれどのように異なる神経的、生理的、生態学的な基盤を持つに至ったのかを比較研究することも重要です。ポップコーニングとストッティングのような例は、行動の収斂進化や、既存の運動パターンが異なる機能のために転用されるプロセスを理解する上で、貴重な示唆を与えてくれます。このような比較アプローチを通じて、動物の行動がどのように進化してきたのか、その多様性と共通性の背景にある原理についての理解が一層深まることが期待されます。
これらの跳躍行動は、一見すると単純な動きに見えるかもしれませんが、その背後には、エネルギー管理、情動と動機付けの神経生物学、捕食者と被食者の共進化、そして遊びの適応的意義といった、生物学における根源的で重要なテーマが隠されています。ポップコーニングの愛らしい跳躍も、ストッティングの劇的な跳躍も、それぞれが動物たちの生と進化の物語を雄弁に物語っているのです。これらの行動に対する科学的な探求は、私たちが動物の世界をより深く理解するための、尽きることのない興味の源泉であり続けるでしょう。
これらの行動の研究が依然として進行中であり、多くの疑問が残されているという事実は、動物行動の「なぜ」(機能・進化)と「どのように」(メカニズム)を解明することの固有の難しさを浮き彫りにしています。特に、跳躍のような瞬間的な行動の研究は、行動生態学、生体力学、神経生物学といった複数の分析レベルを統合する必要があります 68。それぞれのレベルからの知見を組み合わせることで初めて、行動の全体像が明らかになるのです。今後の研究が、これらの魅力的な跳躍行動の謎をさらに解き明かしてくれることを期待します。
引用文献
- Have You Ever Seen Your Pet Chinchilla or Guinea Pig Popcorning …, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.petmd.com/exotic/behavior/have-you-ever-seen-your-pet-chinchilla-or-guinea-pig-popcorning
- Guinea Pig Noises and Body Language: The Ultimate Guide – PBS Pet Travel, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.pbspettravel.co.uk/blog/guinea-pig-noises-and-body-language-the-ultimate-guide/
- Guinea Pigs can perform ‘popcorning’, which is a rapid locomotion where they jump into the air with all four limbs off the ground. This locomotory play behavior is thought to indicate positive affective states. : r/Awwducational – Reddit, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/Awwducational/comments/jtizhg/guinea_pigs_can_perform_popcorning_which_is_a/
- Why Do Guinea Pigs Popcorn? – Lafeber Co. – Small Mammals, 5月 6, 2025にアクセス、 https://lafeber.com/mammals/guinea-pigs-popcorn/
- Keep Your Guinea Pigs Happy – Supreme Petfoods, 5月 6, 2025にアクセス、 https://supremepetfoods.us/blog/keeping-your-guinea-pigs-popcorning-happy/
- Popcorn And Wheek: British Guinea Pigs Are Doing Well – Faunalytics, 5月 6, 2025にアクセス、 https://faunalytics.org/popcorn-and-wheek-british-guinea-pigs-are-doing-well/
- Stotting – Wikipedia, 5月 6, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Stotting
- Pronking and bounding allow a fast escape across a grassland populated by scattered obstacles – ResearchGate, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/373895839_Pronking_and_bounding_allow_a_fast_escape_across_a_grassland_populated_by_scattered_obstacles
- Stotting – Simple English Wikipedia, the free encyclopedia, 5月 6, 2025にアクセス、 https://simple.wikipedia.org/wiki/Stotting
- What is Deer Pronking or Stotting? – The Natural Navigator, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.naturalnavigator.com/news/2024/09/what-is-deer-pronking-or-stotting/
- Why does my guinea pig jump? What is ‘popcorning’?’ – Vet Help Direct, 5月 6, 2025にアクセス、 https://vethelpdirect.com/vetblog/2021/06/01/why-does-my-guinea-pig-jump-what-is-popcorning/
- Understanding Guinea Pig Sounds & Body Language – Petco, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.petco.com/content/content-hub/home/articlePages/pet-guides/understanding-guinea-pig-sounds-and-body-language.html
- Popcorning and jumping – Guinea Pig Corner, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.guineapigcorner.com/popcorning-and-jumping
- 10 Common Guinea Pig Behaviors Explained | Chewy – Blog, 5月 6, 2025にアクセス、 https://be.chewy.com/guinea-pig-behavior/
- Play, Stress, and the Learning Brain – PMC, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3574776/
- Play Behavior Varies with Age, Sex, and Socioecological Context in Wild, Immature Orangutans (Pongo spp.) – PubMed Central, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11339113/
- Current Perspectives on the Biological Study of Play: Signs of Progress, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/656903
- What behavior is important behavior? A systematic review of how wild and zoo-housed animals differ in their time-activity budgets – Frontiers, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/ethology/articles/10.3389/fetho.2025.1517294/full
- (PDF) Animal Play and Animal Welfare – ResearchGate, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/236944493_Animal_Play_and_Animal_Welfare
- The relationship between social play and developmental milestones in wild chimpanzees (Pan troglodytes schweinfurthii) – PubMed Central, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5728447/
- Locomotor play drives motor skill acquisition at the expense of growth: A life history trade-off, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4643810/
- The Pleasures of Play: Pharmacological Insights into Social Reward Mechanisms – PMC, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2946511/
- Reactive anti-predator behavioral strategy shaped by predator characteristics – PMC, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8372962/
- “Stotting” (or “Pronking”) is a behavior exhibited by many types of gazelles, including the Springbok shown here, in which the gazelle jumps up to two meters into the air while arching its back and keeping its legs stiff. Scientists aren’t sure exactly why gazelles stot. : r/Awwducational – Reddit, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/Awwducational/comments/96t9di/stotting_or_pronking_is_a_behavior_exhibited_by/
- Antelope pronking – Why Evolution Is True, 5月 6, 2025にアクセス、 https://whyevolutionistrue.com/2013/01/03/antelope-pronking/
- Rapid Online Optimization of Continuous Quadruped Jumping – arXiv, 5月 6, 2025にアクセス、 https://arxiv.org/html/2403.06954v1
- Pronking and bounding allow a fast escape across a grassland …, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10498029/
- Plasticity of the gastrocnemius elastic system in response to decreased work and power demand during growth – PubMed Central, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10659036/
- Muscle-tendon interaction and elastic energy usage in human walking, 5月 6, 2025にアクセス、 https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00189.2005
- Elastic energy storage across speeds during steady-state hopping of desert kangaroo rats (Dipodomys deserti) – Company of Biologists Journals, 5月 6, 2025にアクセス、 https://journals.biologists.com/jeb/article/225/2/jeb242954/274051/Elastic-energy-storage-across-speeds-during-steady
- The mechanics of elastic loading and recoil in anuran jumping, 5月 6, 2025にアクセス、 https://journals.biologists.com/jeb/article/217/24/4372/12983/The-mechanics-of-elastic-loading-and-recoil-in
- Influence of elastic properties of tendon structures on jump performance in humans, 5月 6, 2025にアクセス、 https://journals.physiology.org/doi/10.1152/jappl.1999.87.6.2090
- Sport-Specific Capacity to Use Elastic Energy in the Patellar and Achilles Tendons of Elite Athletes – Frontiers, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2017.00132/full
- Modeling the Determinants of Mechanical Advantage During Jumping: Consequences for Spring- and Muscle-Driven Movement – Oxford Academic, 5月 6, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/icb/article/59/6/1515/5545521
- Neuromechanical simulation of the locust jump – PMC, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2837733/
- Predictive Simulations of Musculoskeletal Function and Jumping Performance in a Generalized Bird – PMC, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8341896/
- Linking neural circuits to the mechanics of animal behavior in Drosophila larval locomotion, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10499525/
- The Brain in Its Body: Motor Control and Sensing in a Biomechanical Context, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.jneurosci.org/content/29/41/12807
- the evolution of ungulate locomotion, 5月 6, 2025にアクセス、 https://ncf.sobek.ufl.edu/NCFE004732/00001
- The impact of wide step width on lower limb coordination and its variability in individuals with flat feet – PubMed, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40273180/
- The Roles of Dopamine and Related Compounds in Reward-Seeking Behavior Across Animal Phyla – PubMed Central, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2967375/
- Dopamine in motivational control: rewarding, aversive, and alerting – PMC – PubMed Central, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3032992/
- The neurobiology of social play and its rewarding value in rats – PMC, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5074863/
- The neurobiology of social play and its rewarding value in rats – PubMed, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27587003/
- The neurobiology of social play behavior in rats – PubMed, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9168267/
- A Brain Motivated to Play: Insights into the Neurobiology of …, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5646690/
- Affective neuroscience of pleasure: reward in humans and animals – PMC – PubMed Central, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3004012/
- Neurobiology of fear and specific phobias – PMC – PubMed Central, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5580526/
- Neuronal Plasticity in the Amygdala Following Predator Stress Exposure – PubMed Central, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6391327/
- Resilience against predator stress and dendritic morphology of amygdala neurons – PMC, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4022315/
- Predator stress induces behavioral inhibition and amygdala somatostatin receptor 2 gene expression – PubMed Central, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2776032/
- Predator odor fear conditioning: Current perspectives and new directions – PMC, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2634743/
- The smell of danger: a behavioral and neural analysis of predator odor-induced fear – PubMed, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16095694/
- Brain, behavior, and physiological changes associated with predator stress–An animal model for trauma exposure in adult and neonatal rats – PubMed Central, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10938396/
- Divergent medial amygdala projections regulate approach-avoidance conflict behavior, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6446555/
- The functions of stotting: a review of the hypotheses | Semantic Scholar, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.semanticscholar.org/paper/The-functions-of-stotting%3A-a-review-of-the-Caro/474811c4e0388f583cc9b1ce9dbfaeb6007878d4
- Outstanding issues in the study of antipredator defenses – PMC – PubMed Central, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10714066/
- References – Adaptive Herbivore Ecology – Cambridge University Press & Assessment, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.cambridge.org/core/books/adaptive-herbivore-ecology/references/EEDCB091A200FD423B3A16A16AFC825F
- The practicality of practice: A model of the function of play behaviour – PMC, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10507573/
- Nuancing ‘Emotional’ Social Play: Does Play Behaviour Always Underlie a Positive Emotional State? – MDPI, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2076-2615/14/19/2769
- In wolves, play behaviour reflects the partners’ affiliative and dominance relationship – PMC, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6058079/
- The role of skill in animal contests: a neglected component of fighting ability – PMC, 5月 6, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5627213/
- 20250310-sakumi | EHUB – 京都大学ヒト行動進化研究センター, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.ehub-kyoto-u.com/20250310-sakumi
- (PDF) Personnel Selection as a Signaling Game – ResearchGate, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/51757646_Personnel_Selection_as_a_Signaling_Game
- The function of contrasting pelage markings in artiodactyls – Oxford Academic, 5月 6, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/beheco/article/21/1/78/181248
- Choice, competition, and interactions between episodes of sexual selection, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.su.se/polopoly_fs/1.622914.1661245475!/menu/standard/file/Charel%20Reuland_Choice%20competition%20and%20interactions%20between%20episodes%20of%20sexual%20selection.pdf
- Top 303 Animal Behaviour papers published in 2024 – SciSpace, 5月 6, 2025にアクセス、 https://scispace.com/journals/animal-behaviour-2jqk78cq/2024
- 動物はなぜ動く? 「動物はなぜ動く?」 の 考え方 動物行動学の先達 神経行動学(neuro – 静岡大学理学部, 5月 6, 2025にアクセス、 https://www.sci.shizuoka.ac.jp/sci/wp-content/uploads/2021/06/20120511_02.pdf