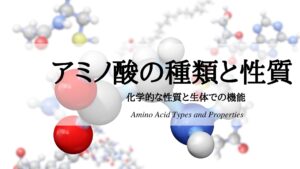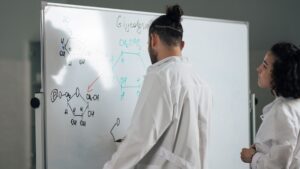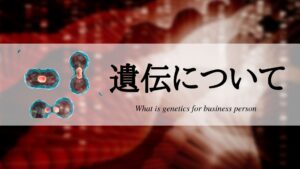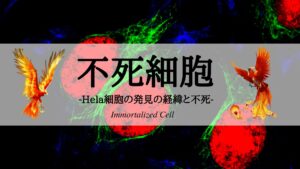I. はじめに:ダイエットコーラは本当にダイエットの味方?
「カロリーゼロ」や「糖類ゼロ」を謳うダイエットコーラ。甘いものがやめられないけれど、体重も気になる…そんな時、つい手を伸ばしてしまう方も多いのではないでしょうか 1。まるで魔法のような響きの「ゼロカロリー」は、ダイエット中の人々にとって、罪悪感なく楽しめる飲み物として、長年にわたり魅力的な選択肢とされてきました。実際、ダイエット飲料の歴史は古く、カロリーを気にする消費者のニーズに応える形で20世紀半ばには登場しています 2。
しかし、この「ゼロカロリー」という表示は、本当にダイエット成功の鍵となるのでしょうか?あるいは、その背後には、私たちがまだ十分に理解していない複雑な側面が隠されているのでしょうか?この記事では、ダイエットコーラの成分から、そのダイエット効果や健康への影響に関する国内外の科学的研究、専門機関の見解、そして実際のマーケティング戦略や個人の体験談に至るまで、多角的に情報を掘り下げていきます。ダイエットコーラとの賢い付き合い方を見つけるための一助となれば幸いです。
ダイエットコーラの根強い人気は、単にその味やカロリーの低さだけによるものではありません。それは、「甘いものを楽しみたい」という欲求と、「健康でいたい、痩せたい」という願いを同時に満たしてくれるかのような、いわば「いいとこ取り」を期待させる点にあります。この「喜び」と「結果(カロリーゼロ)」を両立させるという約束は、特にダイエット製品において強力な訴求力を持っています。消費者は、厳しい食事制限や運動の努力なしに、手軽に目標を達成できるかのような期待感を抱きやすいのです。
さらに、ダイエットコーラのような「ダイエット版」製品の存在自体が、現代社会における体重への強い関心と、手軽な解決策を求める風潮を映し出しているとも言えます。特定の食品や成分(この場合はカロリー)に注目が集まりがちですが、本来、健康的な体重管理は、食事全体のバランスや生活習慣全体を通じて考えるべきものです。しかし、「ダイエット」という言葉を冠した製品は、あたかもそれ自体が問題解決の特効薬であるかのような印象を与え、より包括的なアプローチから目を逸らさせてしまう可能性も指摘されています。

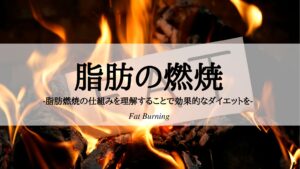
II. ダイエットコーラの正体:何が入っているの?
ダイエットコーラの「ゼロカロリー」の秘密は、砂糖の代わりに「人工甘味料」を使用している点にあります。通常のコーラ飲料には、例えば500mlあたり約60gもの砂糖や異性化糖が含まれており、これがカロリーの主な源です 4。一方、ダイエットコーラは、これらの糖類をほぼ含まず、製品によっては100mLあたり0kcalと表示されています 5。
このカロリーゼロを実現しているのが、人工甘味料(非糖質甘味料 – NSS)です。これらは、ごく少量で砂糖の何百倍もの甘さを感じさせることができるため、カロリーをほとんど加えずに製品に甘味を付けることが可能です。ダイエットコーラによく使用される代表的な人工甘味料には、以下のようなものがあります。
- アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物 (Aspartame): 砂糖の約160~220倍の甘味度を持ち、世界中で広く使用されています 5。
- アセスルファムカリウム (Acesulfame-K, アセスルファムK): 砂糖の約200倍の甘味度を持ち、熱に強く、他の甘味料と組み合わせて使われることが多いのが特徴です 5。
- スクラロース (Sucralose): 砂糖から作られますが、化学的に構造を変化させてあり、砂糖の約600倍の甘味度を持ちます 5。
これらの人工甘味料の他にも、ダイエットコーラには炭酸水、カラメル色素、酸味料、香料、そしてカフェインなどが一般的に含まれています 1。製品によっては、「コカ・コーラ ゼロフリー」のようにカフェインを含まないものや、「コカ・コーラ プラス」のように難消化性デキストリン(食物繊維)を添加しているものもあります 5。
ここで、主な人工甘味料の種類、特徴、そして専門機関が定める「一日摂取許容量(ADI)」の目安をまとめた表を示します。ADIとは、人が生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと考えられる一日あたりの量のことです。
表1:主な人工甘味料の種類、特徴、ADI(一日摂取許容量)の目安
| 甘味料名 (Sweetener Name) | 砂糖との甘味度の比較 (Sweetness vs. Sugar) | カロリー (Calories) | ADI (mg/kg body weight/day) | 主な特徴・備考 (Key Characteristics/Notes) |
| アスパルテーム (Aspartame) | 約160~220倍 | ほぼゼロ (実質) | 0-40 (JECFA, EFSA, 日本) | 熱に不安定な場合がある。フェニルケトン尿症患者は注意が必要。 5 |
| アセスルファムK (Acesulfame Potassium) | 約200倍 | ゼロ | 0-15 (JECFA, 日本) | 熱に安定。他の甘味料と併用されることが多い。 5 |
| スクラロース (Sucralose) | 約600倍 | ゼロ | 0-15 (JECFA, 日本) | 熱に安定。幅広い食品に使用。 5 |
| サッカリン (Saccharin) | 約300倍 | ゼロ | 0-5 (JECFA) | 歴史の古い人工甘味料。過去に発がん性の議論があったが、現在は安全と評価されている国が多い。5 |
| ステビア (Stevia) | 約200~300倍 | ゼロ | 0-4 (JECFA, ステビオール配糖体として) | 天然由来の甘味料として知られる。5 |
「ゼロカロリー」という表示は、一見シンプルですが、その実態は複雑です。人工甘味料自体はごくわずかなカロリーしか持ちませんが、私たちの体がその強烈な甘味に対してどのように反応するかは、単純なカロリー計算だけでは測れません。体は本来、甘味をエネルギー源(カロリー)のサインとして認識するように進化してきました。そのため、強烈な甘味を感じるにもかかわらず、それに見合うカロリーが摂取されないという状況は、生理的・心理的に様々な反応を引き起こす可能性があり、これがダイエットコーラの効果を巡る議論の出発点となります。
また、一部のダイエットコーラにカフェインや食物繊維といった成分が加えられている点も興味深いところです 1。これは、単なるカロリー削減という訴求点を超えて、消費者の多様な健康志向に応えようとする製造側の戦略の表れかもしれません。例えば、食物繊維の添加は満腹感のサポートや整腸作用といった付加価値を、カフェインは覚醒効果や集中力向上といった機能性を期待させます。こうした動きは、ダイエット飲料市場が単なる「砂糖の代替」から、より多機能的な「ウェルネス飲料」へと進化しようとしている可能性を示唆しています。
III. ダイエット効果の真相:世界の研究と専門機関の見解
ダイエットコーラが本当に体重管理に役立つのか、その科学的根拠は長年にわたり議論の的となっています。ここでは、最新の研究成果や主要な専門機関の見解を詳しく見ていきましょう。
A. ダイエットコーラは直接的に体重を減らすのか?科学的根拠の検証
「カロリーゼロなら痩せるはず」という直感的な期待とは裏腹に、科学的な研究結果は一筋縄ではいきません。
ランダム化比較試験(RCT)の結果
ランダム化比較試験(RCT)は、介入効果を評価する上で信頼性の高い研究手法とされています。人工甘味料の体重への影響を調べたRCTでは、いくつかの異なる結果が報告されています。
- 健康な標準体重の成人を対象とした12週間のRCTでは、アスパルテーム(1日350mgまたは1050mg)の摂取は、血糖値、食欲、体重のいずれにも影響を与えなかったと報告されています 11。この研究は、アスパルテーム単独の影響を健康な人で見たものであり、既に体重過多の人や長期的な影響については限定的です。
- 複数のRCTを統合したメタアナリシス(統計的手法を用いて複数の研究結果を統合・分析する研究)の中には、砂糖を人工甘味料に置き換えることで、特に体重過多や肥満の人が自由な食事(カロリー制限なし)をしている場合に、体重減少につながることを示唆するものがあります 12。これは、人工甘味料が「置き換え」によってカロリー摂取量を減らす効果を強調しています。
- しかし、別のRCTのメタアナリシスでは、人工甘味料はBMI(体格指数)に有意な影響を与えなかったと結論付けています。一方で、同じレビューに含まれる観察研究(後述)では、人工甘味料の摂取がBMIの緩やかな「増加」や心血管代謝リスクの上昇と関連していたと報告しており、RCTと観察研究の間で結果に食い違いが見られます 13。この食い違いは、研究期間の長さ(RCTは比較的短期、観察研究は長期)や、研究デザインの違い(介入の有無)に起因する可能性があります。
観察研究の結果
観察研究は、特定の介入を行わず、人々の習慣や健康状態を長期間追跡する研究です。人工甘味料の摂取と健康に関する観察研究の多くは、人工甘味料の常用が、むしろ肥満、体重増加、ウエスト周囲径の増加、メタボリックシンドローム、2型糖尿病のリスク上昇と関連していることを示唆しています 13。
ただし、これらの結果を解釈する際には注意が必要です。観察研究では、「相関関係は因果関係を意味しない」という原則があります。つまり、人工甘味料が直接これらの健康問題を引き起こしているのか、あるいは、元々体重が多い人や健康リスクが高い人がダイエット目的で人工甘味料をより多く摂取している(逆の因果関係)のか、または他の生活習慣要因(食事全体の内容、運動習慣など)が影響しているのかを区別することが難しいのです。
「置き換え」戦略の有効性
ダイエットコーラの効果を考える上で重要なのは、「何を置き換えるか」という視点です。
- CHOICE研究というRCTでは、1日に200kcal以上のカロリーを清涼飲料から摂取していた過体重・肥満の成人が、これらの飲料を水またはダイエット飲料に置き換えた場合、6ヶ月で平均2~2.5%の体重減少が見られました。水とダイエット飲料のグループ間で体重減少量に大きな差はありませんでしたが、ダイエット飲料グループの方が、対照群(食事指導のみ)と比較して5%の体重減少を達成する可能性が高いという結果でした 16。これは、高カロリー飲料からのカロリー削減が体重減少に繋がることを支持しています。
- 一方、別のRCTでは、減量プログラム中にダイエット飲料を水に置き換えたグループの方が、ダイエット飲料を飲み続けたグループよりも体重減少が大きく、インスリン抵抗性も改善したと報告されています 17。これは、特定の状況下(既に低カロリー食を実践中など)では、水の方がより有益である可能性を示唆しています。
これらの研究結果の矛盾やニュアンスは、一見すると混乱を招くかもしれません。しかし、これは科学が常に進化し、より複雑な真実を追求している証でもあります。RCTは特定の条件下での効果を見るのに適していますが、実生活での長期的な影響や、多様な人々の行動パターンを捉えるのは難しい場合があります。一方、観察研究は実生活に近い状況を反映しますが、因果関係の特定には限界があります。ダイエットコーラが「砂糖の代わり」として機能する場合は短期的なカロリー削減に繋がるかもしれませんが、それが持続的な健康的な体重管理に結びつくか、また他の長期的な影響がないかという点については、より慎重な評価が必要とされているのです。
B. 世界保健機関(WHO)など専門機関の勧告
近年、人工甘味料の健康への影響に関する議論が活発になる中、世界保健機関(WHO)をはじめとする専門機関も、その使用に関する見解や勧告を発表しています。
世界保健機関(WHO)の2023年ガイドライン
2023年5月、WHOは人工甘味料(非糖質甘味料、NSS)の使用に関する新たなガイドラインを発表し、大きな注目を集めました 18。このガイドラインの主な勧告は以下の通りです。
- 体重管理や非感染性疾患(NCDs)のリスク低減を目的としたNSSの使用は推奨しない(成人および小児対象)15。
- 推奨の根拠:
- NSSの使用が、成人または小児において体脂肪を減らす上で長期的な利益をもたらさないことを示唆するエビデンスがあること 15。
- NSSの長期使用により、2型糖尿病、心血管疾患、および成人の全死亡率のリスクが増加するなどの望ましくない影響の可能性があること 15。
- NSSは必須栄養素ではなく、栄養価もないこと 10。
- 重要な例外: この勧告は、既に糖尿病と診断されている人には適用されません 15。
WHOのこの勧告は、人工甘味料が体重管理の万能薬ではないこと、そして長期的な摂取には潜在的なリスクが伴う可能性を指摘した点で画期的でした。これは、科学的知見が蓄積され、人工甘味料の複雑な生理作用への理解が深まる中で、公衆衛生の観点からより慎重なアプローチが求められていることを示しています。特に、栄養価のない製品が、健康的な食生活の基本である「バランスの取れた食事」や「未加工食品の摂取」といった原則から目を逸らさせる可能性への警鐘とも言えるでしょう。
その他の規制機関・専門機関の見解
- 日本(食品安全委員会、厚生労働省): 日本の規制当局は、主に承認された人工甘味料の「一日摂取許容量(ADI)」内での安全性を重視しています。WHOのガイドラインを認識しつつも、JECFA(後述)による安全性評価を尊重する立場を取っています 8。日本人の平均的な人工甘味料摂取量はADIを大幅に下回っているとのデータも示されています 8。
- JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議): アスパルテームなどの甘味料について、現行のADI(例:アスパルテームは体重1kgあたり40mg/日)は安全であり、通常の摂取レベルでは健康への懸念はないとの見解を維持しています 8。
- IARC(国際がん研究機関): 2023年7月、アスパルテームを「ヒトに対して発がん性がある可能性がある」(グループ2B)に分類しました 8。この分類は、ヒトでの証拠は限定的であり、実験動物での証拠も十分ではないが、作用機序に関する強い証拠がある場合などに用いられます。これは「ハザード(危害要因)の特定」であり、実際の「リスク評価(特定の摂取量での危険性の程度)」とは異なるため、JECFAの見解と合わせて理解する必要があります。
- EFSA(欧州食品安全機関): アスパルテームなどの甘味料を再評価し、現行のADIの範囲内であれば安全であると結論付けています 8。
- 米国心臓協会(AHA)および米国糖尿病協会(ADA): 2012年の共同声明では、NSSを賢明に使用すれば、砂糖の摂取量を減らし、体重管理に役立つ可能性があると示唆していました 15。これはWHOの2023年のより慎重な勧告とは異なる側面もあり、専門家の間でもエビデンスの解釈や重点の置き方に違いが見られることを示しています。
「ゼロカロリー」という表示は、消費者に「健康的」という印象を与えがちです(いわゆる「ヘイロー効果」)。しかし、WHOが指摘するように、砂糖を人工甘味料に置き換えたとしても、その食品や飲料が依然として超加工食品である場合、食事全体の質が向上するわけではありません 10。ダイエットコーラを飲むことで安心して他の高カロリーな食品を過剰に摂取してしまう「埋め合わせ行動」も懸念されます。カロリーという一点に注目するあまり、より広範な食生活の改善という本質が見失われてしまうことは避けなければなりません。
表2:ダイエットコーラ(人工甘味料)の体重管理効果に関する研究の論点整理
| 論点 (Aspect) | 肯定的な知見・主張 (Potential Positive Findings/Arguments) | 否定的な知見・懸念事項 (Potential Negative Findings/Concerns) | 科学的コンセンサス/議論の状況 (Overall Scientific Consensus/Debate) |
| 短期的な体重減少 (Short-term Weight Loss) | カロリーの高い加糖飲料を置き換えることで、摂取カロリーを減らし、短期的な体重減少に繋がる可能性 12 | 健康な標準体重者ではアスパルテーム摂取による体重変化なし 11。減量プログラム中にダイエット飲料を水に置き換えた方が減量効果が高い場合も 17。 | 置き換えによるカロリー削減効果は認められるが、人工甘味料自体に積極的な減量効果があるかは議論あり。 |
| 長期的な体重管理 (Long-term Weight Management) | 一部のメタ解析では砂糖代替による体重減少を示唆 12。 | WHOは長期的な体脂肪減少効果のエビデンスなしと指摘 15。観察研究では長期摂取と体重増加・肥満リスク上昇の関連を示唆 13。 | 長期的な有効性についてはコンセンサスが得られていない。WHOは推奨せず。観察研究の関連性は因果関係を意味しない可能性も考慮が必要。 |
| 食欲・満腹感への影響 (Impact on Appetite/Satiety) | 一部の短期研究ではアスパルテーム摂取による食欲変化なし 11。 | 甘味刺激とカロリーの不一致が脳を混乱させ、食欲増進や過食に繋がる可能性 5。腸内細菌叢の変化を通じた影響も 14。 | 複雑で一貫した見解なし。メカニズム解明には更なる研究が必要。 |
| 代謝への影響 (Metabolic Effects) | 短期的には血糖値やインスリン値に直接影響しないとの報告が多い 24。 | 長期使用で2型糖尿病や心血管疾患のリスク増加の可能性 13。腸内細菌叢の変化による耐糖能悪化の可能性 14。頭相インスリン反応抑制の可能性 26。 | 短期的には血糖への影響は少ないが、長期的な代謝への影響、特に間接的な経路(腸内細菌、脳の反応など)については懸念が示されており、研究が進行中。 |
IV. ダイエットコーラと健康:知っておきたい影響
ダイエットコーラの議論は、カロリーや体重だけに留まりません。人工甘味料が私たちの体に与える可能性のある、より広範な影響について理解を深めることが重要です。
A. カロリーだけじゃない!人工甘味料が体に与えるかもしれない影響
食欲、味覚、そして「埋め合わせ行動」
- 脳と体の不協和音: 人工甘味料の強烈な甘味は、脳に「エネルギー(カロリー)が来た」という期待を抱かせます。しかし、実際にはカロリーがほとんど供給されないため、脳と体の間で混乱が生じ、結果として「もっと食べろ」という指令が出て食欲が増進したり、甘いものへの渇望が強まったりする可能性があるという説があります 5。
- 味覚の鈍化: 日常的に人工甘味料の強い甘さに慣れてしまうと、果物などの自然な甘味では満足できなくなり、より強い甘味を求めるようになる可能性があります 5。これは、結果的に糖分の過剰摂取につながる恐れも指摘されています。
- インスリン反応を巡る議論:
- 直接的な影響: 多くの短期研究では、人工甘味料の摂取が直接的に血糖値を上昇させたり、インスリンの大量分泌を引き起こしたりすることはないと報告されています 24。このため、糖尿病患者の血糖管理において、砂糖の代替として利用されることがあります。
- 間接的な影響・頭相反応: しかし、甘味を感じること自体が、ごく初期のインスリン分泌(頭相インスリン反応)を引き起こす可能性が指摘されています。京都大学の佐々木努氏らのマウスを用いた研究では、人工甘味料の長期的な摂取が、実際の糖を摂取した際のこの頭相反応を鈍らせ、結果的に耐糖能(血糖値を正常に保つ能力)を悪化させる可能性が示唆されました 26。これは、人工甘味料が直接血糖値を上げなくても、体の糖代謝システムに間接的に影響を及ぼす可能性を示しています。また、一部では、人工甘味料がインスリン分泌を刺激し、血糖値が下がることで空腹感を増強するという意見もありますが 28、これはまだ議論の余地がある点です。
- 埋め合わせ行動と心理的要因: ダイエットソーダの摂取が、食事や体型に関する悩み、過食行動と関連していることを示す研究もあります 29。ただし、これも相関関係であり、ダイエットソーダがこれらの行動を引き起こすのか、元々そうした傾向のある人がダイエットソーダを選びやすいのかは不明です。「ダイエット飲料を飲んだから、少しくらいケーキを食べても大丈夫だろう」といった心理的な「免罪符」として機能し、結果的にカロリー摂取量が増えてしまう「埋め合わせ行動」も考えられます。
腸内環境(腸内フローラ)への影響
近年、腸内細菌叢(腸内フローラ)が健康に多大な影響を与えることが明らかになりつつあり、人工甘味料と腸内細菌の関係も活発に研究されています。
- 腸内細菌叢の変化: 2014年に科学雑誌Natureに掲載された研究をはじめ、いくつかの研究で、特定の人工甘味料(例:サッカリン、スクラロース、アスパルテーム)が腸内細菌のバランスを変化させる可能性が示唆されています 5。
- 変化がもたらす影響: このような腸内細菌叢の変化が、耐糖能異常や肥満、その他の代謝性疾患のリスク上昇と関連している可能性が指摘されています 5。一部の説では、人工甘味料が特定の腸内細菌(いわゆる悪玉菌)の「エサ」となり、それらが増殖することで腸内環境が悪化し、有害物質が体内に漏れ出しやすくなる(リーキーガット)といったメカニズムも提唱されています 32。
- 複雑性と今後の研究: 一方で、慶應義塾大学の研究では、特定の糖アルコール(人工甘味料の一種)を摂取した際に、一部の腸内細菌(大腸菌など)がそれを分解し、下痢などの副作用を防ぐ働きをすることも示されています 33。これは、人工甘味料の種類や個人の腸内細菌叢によって影響が異なる可能性を示唆しており、この分野の研究はまだ発展途上です。
人工甘味料が、甘味という強力な感覚刺激をカロリーや栄養素なしに提供することは、いわば体内の正常な代謝シグナル伝達系を迂回する「トロイの木馬」のようなものかもしれません。この感覚と代謝のミスマッチが長期にわたって繰り返されることで、食欲調節やエネルギー代謝のシステムに微妙な混乱が生じ、すぐには現れないものの、長期的には体重増加や代謝異常といった予期せぬ結果に繋がる可能性が考えられます。これは、従来の毒性学的な観点からの安全性評価(ADI)だけでは捉えきれない、より生理学的な影響と言えるでしょう。
長期的な健康への懸念
- 心血管疾患: いくつかの観察研究では、人工甘味料の日常的な摂取が、脳卒中や心筋梗塞といった心血管イベントのリスク上昇と関連していることが報告されています 13。フランスの大規模コホート研究(NutriNet-Santé研究)では、特にアスパルテーム、アセスルファムK、スクラロースの摂取量が多いほど、心血管疾患および脳血管疾患のリスクが増加したとされています 15。
- 2型糖尿病: 人工甘味料は直接血糖値を上げないとされながらも、逆説的に、長期的な使用が2型糖尿病の発症リスクを高めるとの観察研究結果が複数存在します 13。このメカニズムとしては、前述の腸内細菌叢の変化やインスリン感受性の低下、あるいは長期的な体重増加などが考えられています。
- 腎機能: ハーバード大学が3000人以上の女性を11年間追跡した調査では、ダイエットソーダを1日に2缶以上飲んでいた人は、飲んでいなかった人に比べて腎機能が30%低下していたというデータがあります 35。
- がんリスク(アスパルテームを例に):
- 前述の通り、IARCはアスパルテームを「ヒトに対して発がん性がある可能性がある」(グループ2B)と分類しました 8。これは主に肝細胞がんに関する限定的なエビデンスに基づいています。
- NutriNet-Santé研究では、人工甘味料(特にアスパルテームとアセスルファムK)の摂取が、全がん、乳がん、肥満関連がんのリスク上昇と関連していたと報告されています 15。
- これらの情報に対しては、JECFAや各国の規制当局が「現在のADIの範囲内であれば安全」との見解を示していることも併せて理解することが重要です。IARCの分類はハザードの特定であり、通常の摂取量におけるリスクの大きさを評価するものではありません。
- その他の可能性: 頭痛、めまい、不眠、アレルギー、気分の落ち込みなど、様々な副作用が報告されることもありますが、これらについては科学的根拠が確立していないものも多く含まれます 37。
人工甘味料の影響は、すべての人に一様に現れるわけではないと考えられます。遺伝的背景、元々の腸内細菌叢の構成、基礎的な代謝状態、さらには心理的な傾向など、多くの個人的要因が複雑に絡み合い、反応の仕方に違いを生む可能性があります。一部の人にとってはカロリー置換のメリットがあるかもしれませんが、他の人にとっては食欲や代謝に好ましくない影響が出ることもあり得るのです。これが、研究結果が一様でなかったり、個人の体験談にばらつきが見られたりする一因かもしれません。
B. 安全性について:ADI(一日摂取許容量)と実際の摂取量
人工甘味料の安全性について語る上で欠かせないのが、「一日摂取許容量(ADI: Acceptable Daily Intake)」という指標です。
- ADIとは: ADIは、ある物質を人間が一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康に悪影響がないと考えられる一日あたりの量のことです。通常、動物実験で有害な影響が全く観察されなかった最大量(無毒性量)に、さらに安全係数(通常100倍)をかけて設定されます。
- 主な人工甘味料のADI: 表1に示した通り、例えばアスパルテームのADIは、JECFAや日本の基準では体重1kgあたり0~40mg/日、アセスルファムKは0~15mg/日、スクラロースは0~15mg/日とされています 8。
- 日本における実際の摂取量とADIの比較:
- 厚生労働科学研究などの調査によると、日本人のアスパルテームの平均的な一日摂取量は、ADIの1%にも満たない非常に低いレベルであると報告されています 8。例えば、ある推計ではアスパルテームの一日摂取量は6.58mg/人であり、これは体重58.6kgの人にとってADIの0.3%に過ぎません 8。
- 具体的に、体重60kgの人のアスパルテームのADIは2400mgです。仮に500mlのダイエット飲料にアスパルテームが200~300mg含まれているとすると、ADIに達するには1日に8~12本飲む計算になります 21。
- 「ADIの範囲内なら安全」という見解: 多くの規制当局は、ADIの範囲内での摂取であれば、これらの人工甘味料は安全であると結論付けています 8。
- 「低用量・長期摂取」に関する議論: ADIは主に毒性学的な観点から設定されます。しかし、人工甘味料を巡る議論の中には、ADIを下回る量であっても、長期的な摂取が味覚や食欲、代謝、腸内環境などに微細な影響を及ぼす可能性が指摘されており、これらは従来の毒性試験では捉えにくい側面です。
ダイエットコーラのような強烈な甘味を持つ低カロリー製品が広く普及することは、社会全体の味覚にも影響を与える可能性があります。私たちの舌が人工的な強い甘さに慣れてしまうと、果物などの自然な甘味や、より穏やかな味付けの食品では物足りなさを感じるようになるかもしれません。このような「甘味の基準の上昇」は、無意識のうちにさらに甘いものを求める行動につながり、結果として糖分や人工甘味料の総摂取量を増やしてしまうという悪循環を生むことも懸念されます。これは、ダイエットコーラ単体の問題というよりは、現代の食環境における甘味との付き合い方全体に関わる課題と言えるでしょう 10。
V. 日本国内外の事例と体験談:ダイエットコーラとの向き合い方
ダイエットコーラが私たちの食生活にどのように浸透し、人々にどう受け止められているのか。マーケティング戦略と個人の体験談、そして日本における研究や視点から探ります。
A. マーケティング戦略:いかにして「ダイエットの味方」になったか
ダイエットコーラが「ダイエットの味方」というイメージを確立した背景には、巧みなマーケティング戦略があります。
- 初期の戦略: 1950年代から60年代にかけて登場した初期のダイエット飲料は、主にカロリーを気にする消費者、特に女性をターゲットに、「コーラの風味を楽しみながらカロリーを抑えられる」というメッセージで訴求しました 2。ロイヤルクラウン社の「ダイエットライト・コーラ」はその先駆けの一つです 3。
- ブランド戦略の進化(例:コカ・コーラ ゼロ):
- 「ダイエット」という言葉に抵抗を感じる可能性のある若年層の男性などをターゲットに、「コカ・コーラ本来の味、しかもゼロカロリー・ゼロシュガー」という点を強調して登場したのが「コカ・コーラ ゼロ」です 7。
- パッケージデザインも、従来のダイエット飲料の白基調から、黒を基調としたスタイリッシュなものへと変更し、ターゲット層に合わせたイメージ戦略が展開されました 41。
- 有名タレントやスポーツ選手、映画とのタイアップなど、アクティブで現代的なライフスタイルとの関連付けも積極的に行われています(例:日本ではEXILEや倖田來未さんを起用 42、「007」とのタイアップ 7)。
- 近年では、Z世代など若年層へのアプローチとして、TikTokなどのSNSやAIを活用したキャンペーンも展開されています 44。
- 日本市場特有の動き:
- 日本では、女性向けの「ノーカロリー コカ・コーラ」と男性向けの「コカ・コーラ ゼロ」といった形で、ターゲットを明確に分けた商品展開がなされた時期もありました 7。
- 「ゼロリミット」といったキャッチコピーで、限界なく楽しめるイメージを打ち出したり、味の良さを前面に出したりと、マーケティングメッセージも時代と共に変化しています 43。
- 日本への人工甘味料の輸入量は膨大で、例えば2023年にはスクラロースが32万kg、アスパルテームが12万kg、アセスルファムKが52万kgに達し、これらを砂糖の甘味度に換算すると国内の砂糖供給量の約18%に相当すると報じられています 46。これは、人工甘味料が日本の食品市場に深く浸透していることを示しています。
これらのマーケティング戦略は、「罪悪感なく楽しめる」「我慢しなくてもよい」といった消費者の心理に巧みに訴えかけ、ダイエットコーラを「ダイエット中でも許される特別な存在」として位置づけることに成功してきました。その結果、多くの人々にとって、ダイエットコーラは食事制限中の息抜きや、甘いものへの欲求を満たすための便利な選択肢として、生活の中に定着していったのです。
B. 個人の体験談:効果はあった?なかった?
科学的なデータとは別に、ダイエットコーラを実際に飲んでいる人々の声は、その多様な受け止め方を示しています。ただし、個人の体験談はあくまで主観的なものであり、科学的根拠とは区別して考える必要があります。
- 肯定的・中立的な体験(または効果を実感したという声):
- ダイエット中に甘い炭酸飲料が飲みたくなった際、カロリーを気にせずに欲求を満たせるため重宝しているという声は多く聞かれます 1。
- 「カロリーゼロでこの味なら満足」「素晴らしい発明だ」といった肯定的な意見も見られます 48。
- 通常のコーラよりもダイエット版の味を好む人や、カロリーゼロのメリットのために味の違いは許容できるという人もいます 47。日本国内ではコカ・コーラ ゼロが主流ですが、海外ではダイエットコークを好んで飲むという人もいます 49。
- 否定的・懐疑的な体験、または飲用をやめたケース:
- あるYouTuberのジョエル・ウッド氏は、1日に2リットル近く飲んでいたダイエット系炭酸飲料を100日間断つという挑戦をしました。最初の数日はカフェイン離脱症状に苦しんだものの、最も大きな変化は味覚だったと語っています。以前は大好きだったダイエット飲料がそれほど美味しく感じなくなり、炭酸水や昆布茶のようなシンプルな味を好むようになったそうです。また、この経験を通じて、他の甘いものへの欲求も減り、健康全般に良い影響があったと感じています 37。これは、人工甘味料への依存から脱却し、味覚がリセットされる過程を示す興味深い事例です。
- 一部のダイエットブログなどでは、ゼロカロリー食品(飲料に限らず)に頼りすぎると、かえって過食につながったり、体重が増えたりした経験が語られることもあります 50。
- 人工甘味料の健康への影響を懸念し、味は好きでも摂取を控えるようにしているという人もいます 38。
- 日本のブログやレビューサイトから:
- 化粧品口コミサイト「@cosme」のコカ・コーラ ゼロのレビューでは、ダイエット中のユーザーが愛飲している様子がうかがえますが、やはり通常のコーラの味を好む声も混在しています 47。
- ダイエット関連のブログでは、専門家(トレーナーなど)がゼロカロリー飲料について「問題ないが注意点もある」とし、インスリン反応による空腹感の助長などを指摘するケースも見られます 28。
- 「ホネホネ式カロリー貯金」といった個人のダイエット記録ブログでは、ゼロカロリー製品が食事管理の一環として登場することもありますが、あくまで全体的な戦略の一部として位置づけられています 51。
個人の体験談は、ダイエットコーラが心理的に「助け」になる場合があることを示唆しています。甘いものを完全に断つことのストレスを和らげ、ダイエットの継続をサポートする側面もあるかもしれません。しかし、それが長期的な体重管理や健康にどう結びつくかは、個人の体質や生活習慣、そしてダイエットコーラ以外の食事内容に大きく左右されると言えるでしょう。ウッド氏の事例のように、人工甘味料から離れることで味覚が変化し、より健康的な食生活へとシフトするきっかけになる可能性も示唆されています。
C. 日本における研究や視点
日本国内でも、人工甘味料に関する研究や議論は進められています。
- 日本人集団における体重への影響に関するデータ: 人工甘味料と肥満の関連について、日本人を対象とした大規模で一貫した結論はまだ少ないのが現状です。BMIの基準が欧米と異なることや、メタボリックシンドロームの病態の複雑さなどが、研究の難しさの一因となっている可能性があります 52。
- 腸内細菌叢に関する研究(慶應義塾大学など): 前述の慶應義塾大学の研究のように、人工甘味料(この場合は糖アルコール)と腸内細菌の相互作用に関する基礎研究は日本でも行われています 33。これらの研究は、将来的に人工甘味料の個別化された影響評価や、腸内環境を介した健康効果の解明につながる可能性があります。
- 短期的な代謝への影響(血糖値・インスリン):
- 健常な日本人を対象とした研究でも、アスパルテーム、アセスルファムK、スクラロースといった人工甘味料の摂取が、短期的には血糖値やインスリン値を直接的には上昇させないという結果が、国際的な知見と同様に報告されています 24。
- しかし、ある研究では、健康な若い女性が空腹時に人工甘味料(スクラロース、アスパルテーム、アセスルファムK)を摂取した場合、水と同様に2時間後には血糖値が摂取前よりわずかに低下し、空腹感が増加する傾向が見られました。特に、砂糖水を摂取した場合と比較して、人工甘味料の方が早く空腹感が高まる可能性が示唆されました 27。これは、人工甘味料が必ずしも満腹感を持続させず、むしろ次の食事への欲求を早める可能性を示唆しています。
- 専門家のコメント: WHOのガイドライン発表後、日本の専門家からは、承認された人工甘味料のADI内での安全性や、日本人の平均摂取量がADIを大幅に下回っている点、そして糖尿病患者への適用は別であるといった点が強調される傾向にあります 21。
グローバルな製品であるダイエットコーラも、日本市場においては独自のマーケティング戦略や商品ラインナップ(例:「コカ・コーラ ゼロフリー」の存在や、かつての「ノーカロリー コカ・コーラ」と「コカ・コーラ ゼロ」の男女別ターゲティング 7、国内タレントの起用 42)が見られます。これは、製品の基本的な特性(甘味料を使用したゼロカロリー飲料)は同じでも、消費者の嗜好や文化的な背景に合わせて、その見せ方や訴求点が調整されていることを示しています。
VI. 結論:ダイエットコーラと賢く付き合うために
これまで、ダイエットコーラの成分、ダイエット効果に関する科学的根拠、健康への影響、そして国内外の事例や専門機関の見解を多角的に見てきました。これらを踏まえ、ダイエットコーラとどう向き合っていくべきか、結論と実践的なアドバイスをまとめます。
A. 総括:ダイエットコーラはダイエットに効果的か?
ダイエットコーラがダイエットに効果的かという問いに対する答えは、残念ながら単純な「はい」か「いいえ」ではありません。
- 限定的な条件下での可能性: ダイエットコーラが、高カロリーな砂糖入り飲料の「置き換え」として利用され、かつ、それによって一日の総摂取カロリーが減少し、さらに「埋め合わせ行動」によるカロリー摂取増がない場合には、短期的な体重管理に貢献する可能性はあります 12。つまり、あくまでカロリー収支をマイナスにするための一つの手段として機能する場合です。
- 長期的な効果や単独での効果は疑問: しかし、人工甘味料自体に積極的な痩身効果があるわけではありません。WHOをはじめとする多くの専門機関や長期的な研究は、人工甘味料を主な戦略とした持続的な体重管理を支持しておらず、むしろ長期使用による潜在的な健康リスクへの懸念を示しています 13。
- 「なぜ飲むのか」が重要: ダイエットコーラを飲む目的が重要です。もし、不健康な食生活を続けるための「免罪符」として利用したり、かえって甘いものへの渇望を強めたりするようであれば、ダイエットの助けにはならないでしょう。
最終的に、ダイエットコーラがダイエットの「味方」になるか「敵」になるかは、個々の状況、飲み方、そして全体的な食生活やライフスタイルに大きく左右されると言えます。
B. 消費者への実践的なアドバイス
ダイエットコーラとの付き合い方を考える上で、以下の点を参考にしてください。
- もしダイエットコーラを飲むならば:
- 適量を心がける: 日常的な水分補給の手段としてではなく、あくまで嗜好品として、たまに楽しむ程度に留めましょう 6。平均的な摂取量はADIを大きく下回るとはいえ、個人が大量に飲み続けることの是非は別問題です。
- 潜在的な影響を理解する: カロリーゼロであっても、体に何らかの影響(食欲、味覚、腸内環境など)を与える可能性があることを認識し、自身の体の反応に注意を払いましょう。
- 「ヘイロー効果」に注意: 「ダイエットコーラを飲んだから大丈夫」と、他の不健康な食品の摂取を正当化しないようにしましょう。
- より健康的な選択肢:
- 水: 最も理想的な水分補給源です。味気なければ、レモンやきゅうりのスライスで風味をつけるのも良いでしょう。
- 無糖のお茶やコーヒー: 風味があり、抗酸化物質などの有益な成分も期待できます。
- 炭酸水(無糖・無香料または自然な風味付け): 炭酸の刺激が欲しい場合に、甘味料なしで満足感を得られます。
- 甘いものへの欲求への対処法:
- 徐々に甘い食品や飲料の摂取を減らし、味覚を自然な甘さに慣らしていくことが推奨されます 10。
- 甘味が欲しい時は、食物繊維やビタミンも摂れる果物を選びましょう。
- 持続可能な体重管理の基本:
- 真の体重管理は、バランスの取れたホールフード(未加工・低加工の食品)中心の食事、定期的な運動、質の高い睡眠、ストレス管理といった、地道な生活習慣の改善によって達成されます。近道はありません。
- 特定の食品のカロリーを減らすことだけに注目するのではなく、食事全体の質を高めることを目指しましょう 10。
ダイエットコーラを巡る議論は、私たち消費者にとって、製品のマーケティングメッセージを鵜呑みにせず、科学的根拠に基づいて情報を吟味し、自身の健康について主体的に考える良い機会を与えてくれます。最終的な目標は、人工的な強い甘味への依存を減らし、より自然でバランスの取れた食生活を送ることにあると言えるでしょう 10。個人の選択は自由ですが、その選択が長期的な健康と幸福にどう繋がるのか、という視点を持つことが賢明です。公衆衛生の観点からは、WHOのように、効果が不確かで潜在的リスクのある製品よりも、より確実で安全な方法(例:糖分摂取総量の削減、バランスの取れた食事)を推奨する動きがあることも理解しておくべきです。
引用文献
- 痩せたい方必見!ゼロコーラはダイエット向き?太らないのは本当なのか調査 – パーフェクトライン, 5月 7, 2025にアクセス、 https://perfect-line.jp/blog/?p=6135
- 技術によって「砂糖」は代替できるのか? 〜代替甘味料を提供するスタートアップ6社, 5月 7, 2025にアクセス、 https://japan.plugandplaytechcenter.com/blog/sugar-substitutes/
- ダイエット戦線異常アリ! ~ダイエットコーラの新展開~, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.colawp.com/seasonal/200704/diet_ss/index.html
- 飲みものから摂るカロリーは全体の10%以内に!コーラは人工甘味料以外にカラメルも超危険, 5月 7, 2025にアクセス、 https://diamond.jp/articles/-/42206?page=2
- ダイエットコーラは太らない? |くにちか内科クリニック, 5月 7, 2025にアクセス、 https://kunichika-naika.com/information/hitori202005
- コーラのカロリー&糖質は高め?〜コーラゼロや太りにくい飲み方も …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://health2sync.com/ja/blog/cola-calorie-carbohydrates/
- コカ・コーラ ゼロ – Wikipedia, 5月 7, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%AB%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%A9_%E3%82%BC%E3%83%AD
- 令和5年度「自ら評価」検討資料 – 食品安全委員会, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20231117ki1&fileId=320
- 人工甘味料と肥満や糖尿病などの関係についての最新情報 – 市民のためのがん治療の会, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.com-info.org/medical.php?ima_20120606_oonishi
- WHOが「人工甘味料」など砂糖代替品に警告を発するガイドラインを発表, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.anti-a.org/news/jp/artificial-sweetener
- Aspartame Consumption for 12 Weeks Does Not Affect Glycemia, Appetite, or Body Weight of Healthy, Lean Adults in a Randomized Controlled Trial – PubMed, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29659969/
- Effects of nonnutritive sweeteners on body weight and BMI in …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32216045/
- Nonnutritive sweeteners and cardiometabolic health: a systematic …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28716847/
- 肥満につながる砂糖飲料と人口甘味飲料:システマテックレビューとメタアナリシス, 5月 7, 2025にアクセス、 https://low-carbo-diet.com/sweetener/sugar-and-artificially-sweetened-beverages
- 人工甘味料と健康 – 名古屋学芸大学, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.nuas.ac.jp/IHN/report/pdf/15/05.pdf
- Replacing caloric beverages with water or diet beverages for weight …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22301929/
- Effects on weight loss in adults of replacing diet beverages with …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26537940/
- 食品安全関係情報詳細, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06060720294
- 2.WHOのノンシュガー甘味料の使用に関するガイドラインを読む – 消費者庁, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fscc_cms101_241127_15.pdf
- 人口甘味料は危険?種類や特徴をはじめWHOのガイドラインも解説 …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://tokubai.co.jp/news/articles/6804
- 人工甘味料の使用に関する WHOガイドライン … – 農畜産業振興機構, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.alic.go.jp/content/001235328.pdf
- 欧州食品安全機関(EFSA:European Food Safety Authority), 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.nihs.go.jp/hse/food-info/chemical/aspartame/EFSAaspartame.pdf
- 代用甘味料とは?~|ブログ – 北24条かやの歯科クリニック, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.sapporo-dental-clinic.com/information/blog/%EF%BD%9E%E4%BB%A3%E7%94%A8%E7%94%98%E5%91%B3%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%EF%BD%9E.html
- 人工甘味料と糖代謝|農畜産業振興機構, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_001494.html
- 人工甘味料を勧めない!WHOガイドライン : 体重管理に非糖質甘味料を使用しないよう勧告, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.yuiclinic.com/information/13843/
- Vol.224 (2) 2020年度ダノン学術研究助成金受贈者による研究報告 …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.danone-institute.or.jp/mailmagazine/28483/
- www.urakamizaidan.or.jp, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.urakamizaidan.or.jp/research/jisseki/vol27/vol27urakami_09nakajima.pdf
- ゼロカロリー飲料はダイエット中に飲んでOK?|松下 式・ボディメイク論 – Tarzan Web, 5月 7, 2025にアクセス、 https://tarzanweb.jp/post-275719
- Examining the Relationship Between Soda Consumption and Eating Disorder Pathology, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3807751/
- Examining the Relationship Between Soda Consumption and Eating Disorder Pathology | Request PDF – ResearchGate, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/258118148_Examining_the_Relationship_Between_Soda_Consumption_and_Eating_Disorder_Pathology
- What Contributes to Excessive Diet Soda Intake in Eating Disorders: Appetitive Drive, Weight Concerns, or Both? – PMC, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3670085/
- 人工甘味料は腸内環境を悪化させることがあるので注意です! – 福岡天神内視鏡クリニック, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.fukuoka-tenjin-naishikyo.com/blogpage/2022/12/12/12082/
- 腸菌細菌が人工甘味料の過剰摂取によって引き起こされる下痢を防ぐことを発見 – Keio University, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2021/6/18/28-80757/
- 腸菌細菌が人工甘味料の過剰摂取によって引き起こされる 下痢を防ぐことを発見, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2021/6/18/210618-2.pdf
- 「カロリーゼロ」、太って病気まっしぐら! 人工甘味料の3大恐怖、知らずに飲むな | 5日連続特集 ヤバすぎる!ドリンクの裏側 | 東洋経済オンライン, 5月 7, 2025にアクセス、 https://toyokeizai.net/articles/-/48584?display=b
- 人工甘味料の発癌リスクは:フランス発最大のコホート研究 – メディカルオンライン, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.medicalonline.jp/review/detail?id=6134
- 100日間、「ダイエットコーラ(炭酸飲料)断ち」を続けて起きた身体の変化と効果 – Esquire, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.esquire.com/jp/menshealth/wellness/g36043386/a-man-shared-what-happened-when-he-quit-diet-soda-for-100-days/
- ダイエットコークでダイエットしようと思ったんですが…という話 …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://note.com/mate_t/n/nc1a038263ce5
- コカ・コーラはどのように成長したか, 5月 7, 2025にアクセス、 http://pub.sgu.ac.jp/~nakamura/zemiron10-6.htm
- 1970-1980年代-コカ・コーラ社のボトリング契約を中心として, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.seijo.ac.jp/pdf/faeco/kenkyu/153/153-yamaguti.pdf
- コカコーラ・ゼロとグローバルリサーチ – 明日のマーケティング, 5月 7, 2025にアクセス、 https://newmktg.lekumo.biz/blog/2008/02/post-19f1.html
- コカ・コーラ – Wikipedia, 5月 7, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%AB%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%A9
- コカ・コーラゼロの「思いっきり味わおう」に隠された「選択」 | GLOBIS学び放題×知見録, 5月 7, 2025にアクセス、 https://globis.jp/article/1047/
- 商品が話しかけてくる店舗 Z世代の注目集める、コカ・コーラシステム, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.advertimes.com/20240206/article448234/
- コカ・コーラゼロシュガー、NSYNCとTikTokを活用したマーケティング戦略 – 株式会社CATTAIL, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.cattail.co.jp/3826/
- 人工甘味料危険周知を/田村貴昭議員が調査要求 – 日本共産党, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-06-05/2024060504_05_0.html
- 日本コカ・コーラ / コカ・コーラ ゼロの口コミ一覧 – アットコスメ, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.cosme.net/products/2921642/review/
- 山本義徳先生がダイエットコーラを飲んでいたので甘味料について聞いてみました。 – YouTube, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=Q3-ODPKjftY
- ダイエットコークとコークゼロの関係性|浜田寿人 / WAGYUMAFIA – note, 5月 7, 2025にアクセス、 https://note.com/wagyumafia/n/n0e55457fc9a9
- ゼロカロリー食品で失敗しないために!効果的な取り入れ方と過食リスクを徹底解説, 5月 7, 2025にアクセス、 https://cb-berater.jp/post-1728831282/
- カロリー貯金ダイエット | ホネホネロック(東城薫) |本 | 通販 | Amazon, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%B2%AF%E9%87%91%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%9B%E3%83%8D%E3%83%9B%E3%83%8D%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF-%E6%9D%B1%E5%9F%8E%E8%96%AB/dp/4584138788
- www.maff.go.jp, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/attach/pdf/iyfv-59.pdf