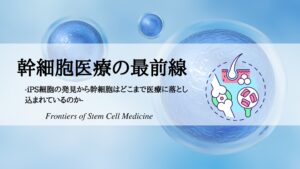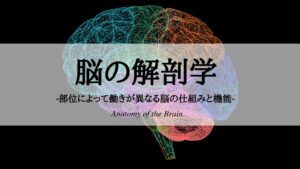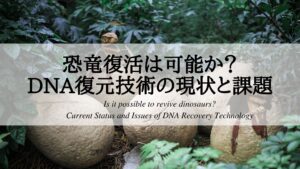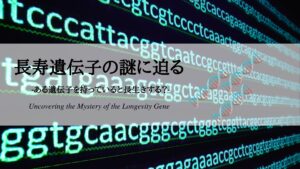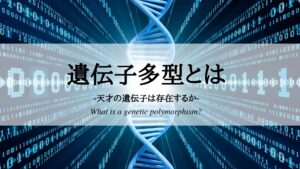I. ハリネズミとは?その魅力と人気の秘密
A. ペットとしてのハリネズミ:ヨツユビハリネズミを中心に
1. 人気の理由と飼育の基礎知識
近年、SNSなどを通じてその愛らしい姿が注目され、ペットとしてのハリネズミの人気が急速に高まっています 1。特に日本で一般的に飼育されているのは「ヨツユビハリネズミ」(学名:Atelerix albiventris)という種類で、その名の通り前足の指が4本しかないのが特徴です 2。彼らの原産地はアフリカ大陸の乾燥地帯です 2。
ハリネズミがペットとして選ばれる理由の一つに、マンションのような室内環境でも比較的飼育しやすく、飼い主が日中家を空けていてもお世話がしやすいという点が挙げられます 1。しかし、その愛らしい外見の裏には、野生動物由来の繊細な性質が隠されています。ハリネズミは基本的にデリケートで臆病な性格をしており、警戒心も強いため、新しい環境や飼い主に慣れるまでには時間と忍耐が必要です 1。信頼関係を築くためには、ストレスを与えない静かな環境を用意し、根気強く接することが求められます。
ハリネズミは夜行性であり、日中は薄暗く静かな場所で過ごすことを好みます 1。野生では単独で生活しているため、過度なスキンシップはストレスの原因となることもあります 1。飼育にあたっては、60cm×90cm程度の広さのケージ、隠れ家となる寝床、食器、給水器、床材、そして運動不足解消のための回し車などを用意する必要があります 1。特に重要なのが温度管理で、快適とされる温度は25℃~28℃、湿度は40%程度です 1。ハリネズミは寒さに非常に弱く、気温が低すぎると冬眠状態に入ってしまうことがあります。ペットとしてのハリネズミにとって冬眠は体に大きな負担をかけ、寿命を縮める原因にもなるため、冬場はヒーターなどを使って適切な温度を維持することが不可欠です 1。
食事は、ハリネズミ専用の総合栄養食ペレットを主食とし、おやつとして昆虫(ミルワームなど)や少量の果物、野菜を与えることができます 1。飼育下での寿命は約2~5年とされていますが 1、適切なケアと環境が整っていれば6~8年ほど生きることもあります 2。野生での寿命は3~5年程度です 4。飼育下では、ダニ症、腫瘍、歯周病、肥満などの病気に注意が必要です。特にダニ症は発症しやすいため、ケージ内を常に清潔に保ち、定期的な体のケアが重要となります 1。
ハリネズミの行動の中でも特にユニークなのが「アンティング」と呼ばれるものです。これは、初めて嗅ぐ匂いや口にするものに対して、唾液を泡立てて自分の体に塗りたくる行動です 1。この行動の正確な理由はまだ完全には解明されていませんが、新しい匂いを自分の体に馴染ませるため、あるいは何らかの化学物質を体に付着させて自己防衛やコミュニケーションに利用しているのではないかなど、様々な説が考えられています。アンティングは、ハリネズミが周囲の環境をどのように認識し、情報を処理しているのか、その感覚世界の一端を垣間見せてくれる興味深い行動と言えるでしょう。
B. 野生のハリネズミの素顔:分類、生態、多様性
1. 世界のハリネズミ:種類と分布
一般に「ハリネズミ」と呼ばれる動物たちは、実は多様な種の集まりです。彼らは生物分類学的には食虫目(Eulipotyphla)のハリネズミ科(Erinaceidae)に属しており、名前に「ネズミ」とありますが、実際にはネズミの仲間(齧歯類)ではなく、モグラに近いグループです 2。
世界には、ヨーロッパハリネズミや、ペットとしてお馴染みのヨツユビハリネズミなど、多くの種類が存在します 3。例えば、ハリネズミ属 (Erinaceus spp.) に分類される種は、西ヨーロッパから中東、東ヨーロッパ、そして東アジアから北東アジアにかけて広く分布しています 5。一方、ヨツユビハリネズミ (Atelerix albiventris) はアフリカ大陸が原産です 2。日本国内においては、本来生息していなかったアムールハリネズミ (Erinaceus amurensis) が、静岡県や神奈川県などで外来種として定着していることが確認されています 5。このように、一口にハリネズミと言っても、その起源や生息環境は種によって大きく異なり、それが各種の生態や形態の微妙な違いを生み出しています。
表1: 主なハリネズミの種類と特徴
| 和名 | 学名 | 主な分布域 | 体長(目安) | ペットとしての流通 | 特記事項 |
| ヨツユビハリネズミ | Atelerix albiventris | アフリカ中央部 | 15~20cm | 多い | ペットとして最も一般的。前足の指が4本。別名ピグミーヘッジホッグ。 2 |
| ナミハリネズミ | Erinaceus europaeus | 西ヨーロッパ、アゾレス諸島 | 23~37cm | 少ない | ヨーロッパ広域に分布。 5 |
| アムールハリネズミ | Erinaceus amurensis | 東アジア~北東アジア | 23~37cm | 極めて少ない | 日本では外来種として一部地域に定着。 5 |
| オオミミハリネズミ属 | Hemiechinus spp. | 中央アジア、北アフリカ、中東 | 15~28cm | 少ない | 名前の通り大きな耳が特徴。乾燥地帯に適応。 |
| インドハリネズミ | Paraechinus micropus | インド、パキスタン | 14~18cm | ほぼない | 砂漠や乾燥した草原に生息。 |
この表は、ハリネズミというグループ内の多様性の一端を示しており、各種が適応した環境の違いが、後の針の進化や生態的役割の議論にも繋がっていきます。
2. 生態学的特徴:食性、行動、寿命、天敵
野生のハリネズミは、その名の通り「針を持つネズミ(に似た小動物)」として知られていますが、その生態は非常に興味深いものです。彼らの食性は雑食性で、昆虫類(主食とされることが多い 2)、ミミズ、クモ、カタツムリなどの無脊椎動物から、時にはネズミの子供、カエル、トカゲ、ヘビといった小さな脊椎動物、鳥の卵、さらには果物や植物の根まで、機会に応じて様々なものを食べます 3。この幅広い食性が、多様な環境への適応を可能にしている一因と考えられます。
行動面では、ハリネズミは基本的に夜行性です 5。日中は草や落ち葉などで作った巣の中に隠れて休息し、夜になると活動を開始します。多くの種は単独で生活し、オス同士では縄張りを主張して争うこともあります 2。また、温帯域に生息するハリネズミ属 (Erinaceus spp.) などは、冬になると冬眠する習性があります 5。これは、食物が乏しくなる冬季のエネルギー消費を抑えるための重要な生存戦略であり、この能力の有無がハリネズミの分布域拡大にも影響を与えてきた可能性があります。
野生下でのハリネズミの寿命は、一般的に3年から5年程度とされていますが 4、2年から3年という報告もあります 7。飼育下では天敵や食糧不足の心配がないため、これよりも長く生きる傾向にあります 2。
ハリネズミは小さな動物ですが、その針のおかげで多くの捕食者から身を守っています。しかし、万能ではなく、アナグマ、キツネ、コヨーテ、イタチ、フクロウやミミズクといった猛禽類、タカ類、大型のワシ類、さらには人間と共存する環境ではネコやイヌなども天敵となり得ます 4。特にアナグマは、ハリネズミを捕食する能力に長けていると言われています 11。このような常に捕食者に狙われる環境が、ハリネズミの代名詞ともいえる「針」という顕著な防御機構を進化させる主要な原動力(選択圧)の一つとなったことは想像に難くありません。夜行性で単独行動という習性も、捕食リスクと隣り合わせであることを示唆しています。
II. ハリネズミの最大の特徴:針の謎に迫る
A. 針の正体:毛が進化した驚くべき構造
1. 針の材質と基本構造:ケラチンと内部の工夫
ハリネズミの最も際立った特徴である背中の針は、実は体毛が特殊に進化したものです 3。1匹のハリネズミが持つ針の数は非常に多く、約5000本から7000本 3、あるいは成体では約8000本にも達すると言われています 13。針の長さは、大人のもので2cmから3cmほどです 12。
この針の主成分は、私たちの髪の毛や爪と同じ「ケラチン」というタンパク質です 13。しかし、単なる硬い毛とは異なり、ハリネズミの針はその構造に驚くべき工夫が凝らされています。針の内部は空洞になっており、さらにその空洞は多数の横隔壁によって補強されています 12。この精巧な内部構造により、針は軽量でありながら非常に硬く、かつ衝撃に対して柔軟性があり、簡単には折れないという優れた物理的特性を実現しています。進化の過程で、軽量性、強度、そして衝撃吸収性という複数の機能要求を満たすよう最適化された結果と言えるでしょう。
針の根元は丸い球根状になっており、皮膚の奥深くにしっかりと埋め込まれ、周囲を筋肉が取り囲んでいます 13。それぞれの針には立毛筋と呼ばれる小さな筋肉が付いており、これによってハリネズミは意識的に針を逆立てたり、体に沿って寝かせたりすることができます 12。数千本もの針を個別に、あるいは協調して制御できる能力は、防御態勢(体を丸める)の効率性と柔軟性を飛躍的に高めています。全身を針で覆うだけでなく、状況に応じて針の角度を微調整することで、より効果的な防御戦略を可能にしているのです。ただし、頭のてっぺん(頭頂部)には針が生えていない「無針部」と呼ばれる部分があります 12。
2. 科学が解き明かす針の発生と生え変わり
ハリネズミの針は、一生同じものが使われるわけではなく、成長や状況に応じて生え変わります。その発生と世代交代のシステムは非常に巧妙です。ハリネズミの針には、大きく分けて3つの世代が存在すると言われています 13。
生まれたばかりのハリネズミの赤ちゃんは、約100本ほどの白くて柔らかい第一世代の針を持っています。これらの針は、出産時に母親の産道を傷つけないように、体液で膨らんだ皮膚の下に一時的に隠されています。これは、硬い防御器官を持つ子供を安全に出産するための、哺乳類特有の繁殖戦略と皮膚付属器の発生プログラムが見事に連携した結果と言えるでしょう。生後数時間もすると、この第一世代の針の先端が皮膚から現れ始めます。そして、生後4~5日もすると、色素を持った少し硬い第二世代の針が生え始め、最初の白い針は徐々に抜け落ちていきます 13。
さらに成長し、生後2~4週間ほどになると、より太く硬い、縞模様のある成体の針(第三世代)が生え始め、それまでの幼い針と置き換わっていきます 13。この成体の針の寿命は少なくとも18ヶ月程度とされ、その後も定期的に抜け落ちては新しい針が再生されます 13。1日に10本から15本程度の針が自然に抜け落ちることもあるようです 14。この定期的な生え変わりは、摩耗したり損傷したりした針を新しいものに交換し、常に最適な防御機能や衝撃吸収機能を維持するための重要なメカニズムと考えられます。また、人間や他の動物の毛髪と同様に、ハリネズミも病気や強いストレスを感じると針が通常よりも多く抜けることがあると報告されており 15、針の状態が体全体の健康状態を反映する一種のバロメーターにもなり得ると言えるかもしれません。
B. 針の多機能性:防御、衝撃吸収、そして体温調節?
1. 身を守るための究極の鎧
ハリネズミの針の最もよく知られた機能は、言うまでもなく捕食者からの防御です。危険を察知すると、ハリネズミは瞬時に体を丸め、背中や側面を硬い針で覆われたボールのような状態になります 3。このとき、針は外側に向けて鋭く逆立ち、捕食者が容易に手出しできない強力なバリアを形成します。
この特異な防御姿勢を可能にしているのが、発達した背中の筋肉、特に皮膚の直下にある強力な輪状筋(皮筋)です 12。この筋肉を収縮させることで、頭や手足、腹部といった柔らかく無防備な部分を完全に内側に隠し、全身を針の鎧で固めることができるのです。ヤマアラシも針を持つ動物として知られていますが、彼らが針を逆立てて威嚇し、時には相手に体当たりして針を突き刺すのに対し、ハリネズミは針を立てて丸くなり、ひたすら敵が諦めるのを待つという受動的な防御戦略をとります 21。また、ハリネズミの針はヤマアラシの針のように簡単には抜け落ちません 22。この針と体を丸める行動、そしてそれを支える特殊な筋肉系の組み合わせは、受動的防御としては極めて洗練されたシステムと言えるでしょう。
この防御方法は多くの捕食者に対して有効ですが 11、絶対的なものではありません。例えば、アナグマはハリネズミの重要な天敵の一つであり、丸まったハリネズミをこじ開けたり、弱点である顔や腹部を狙ったりする方法を学習しているか、あるいは進化の過程で獲得している可能性があります 11。これは、捕食者と被食者の間で繰り広げられる終わりのない進化的軍拡競争の一例を示唆しており、どんな防御手段も万能ではないことを物語っています。
2. 落下も怖くない?衝撃吸収メカニズム
ハリネズミの針は、外敵からの防御という主要な役割に加え、もう一つ非常に重要な機能を持っています。それは、優れた衝撃吸収能力です 12。ハリネズミは意外にも木に登る行動が報告されており、その際に誤って落下することがあります 13。そのような時、背中の針がクッションのように働いて衝撃を吸収し、体を守るのです。
この驚くべき衝撃吸収能力の秘密は、前述した針の内部構造にあります。中空でありながら横隔壁や縦方向の補強材で強化された構造は、軽量でありながら高いエネルギー吸収効率を実現しています 13。実際に、実験室での動的衝撃試験によってハリネズミの針の優れた衝撃吸収性能が確認されており、湿潤条件や針が固定される基質の硬さなどが、その性能や耐久性に影響を与えることも分かっています 23。
この針の衝撃吸収機能は、ハリネズミが樹上を含む多様な環境で探索行動や逃避行動をとることを可能にし、彼らの行動範囲の拡大や生存戦略の多様化に寄与してきたと考えられます。防御だけでなく、日常的な活動中の事故からも身を守るこの機能は、針の進化における重要な選択圧の一つであった可能性が高いでしょう。
ハリネズミの針が持つ軽量かつ高効率なエネルギー吸収特性は、バイオミメティクス(生物模倣技術)の観点からも大きな注目を集めています。例えば、アメリカンフットボール用のヘルメット内部の衝撃吸収材として、ハリネズミの針の構造を応用する研究開発が進められています 18。これは、生物の進化が数百万年かけて生み出した優れた工学的解決策を、人間の技術開発に活かそうとする試みの一例と言えます。
3. 針と体温:隠された役割の可能性
ハリネズミの針には、防御や衝撃吸収以外にも、体温調節を助ける機能があるのではないかという指摘があります 12。哺乳類の体毛の主要な機能の一つは断熱であり、体温の維持に貢献しています。ハリネズミの針が毛から進化したものであることを考えると、この断熱機能が完全に失われたとは考えにくいでしょう。
実際に、密集して生えている針の層が空気を含むことで、ある程度の断熱効果をもたらし、体温の維持に寄与している可能性が考えられます 16。また、針が水を弾きやすい性質を持っていれば、体が濡れるのを防ぎ、それによって気化熱による体温低下を間接的に抑制する効果も期待できるかもしれません。ハリネズミは小型の哺乳類であり、体積に対する表面積の割合が大きいため、体温を失いやすいという生理的特徴を持っています。実際に、麻酔処置の際には低体温に陥りやすく、保温が非常に重要であることが知られています 27。
有名な「ハリネズミのジレンマ」という寓話は、寒い冬にハリネズミたちが暖を求めて集まろうとするものの、近づきすぎるとお互いの針で傷つけ合ってしまい、適度な距離を見つけるのに苦労するという話です 28。これは、体温維持の重要性と針の存在がもたらす物理的な制約を象徴的に示しています。
現時点では、ハリネズミの針が体温調節にどの程度直接的に貢献しているのかを明確に示した研究は限られていますが、その構造(中空である可能性や密集度)を考慮すると、防御や衝撃吸収といった主要機能に付随する、副次的ではあるものの生存にとって重要な利点となっている可能性は十分に考えられます。この点は、今後の生理学的研究によってさらに解明されるべき興味深い課題と言えるでしょう。
III. 針の進化:遺伝子と分子が語る物語
A. 「毛から針へ」進化のシナリオ
1. 収斂進化の傑作:ハリネズミ、ヤマアラシ、ハリモグラの針
動物界を見渡すと、ハリネズミ以外にも体に鋭い針やトゲを持つ哺乳類がいくつか存在します。代表的な例として、ヤマアラシやハリモグラが挙げられます。これらの動物は、一見するとハリネズミと似たような防御手段を持っているように見えますが、進化の道のりは全く異なります 22。
まず、ハリモグラはカモノハシと同じ単孔類に属し、卵を産むという原始的な特徴を持つ哺乳類です。一方、ヤマアラシはネズミやリスと同じ齧歯類(げっしるい)の仲間です。そして、ハリネズミは前述の通りモグラに近い食虫類に分類されます 2。このように、彼らは哺乳類の中でも系統的に大きく離れたグループに属しているのです。
この事実は、ハリネズミ、ヤマアラシ、ハリモグラが、共通の「針を持つ祖先」から進化してきたわけではないことを意味します。そうではなく、元々は針を持たなかったそれぞれの祖先が、独立に、それぞれの進化の過程で針というよく似た形質を獲得したと考えられています。このような現象を、進化生物学では「収斂進化(しゅうれんしんか)」と呼びます 22。捕食者からの防御という共通の環境要因(選択圧)が、異なる遺伝的背景を持つ生物群に対して、結果的に類似した形態的解決策(針の獲得)を促した顕著な例と言えるでしょう。これは、自然選択の力の強さを示す強力な証拠となります。
さらに興味深いことに、マダガスカル島に生息するテンレック類の中にも、ハリネズミに酷似した姿と針を持つものがいます(例:ヒメハリテンレック)。しかし、DNA解析の結果、テンレック類はハリネズミとは遠縁で、むしろゾウに近い仲間であることが示されています 29。これもまた、収斂進化の驚くべき一例です。
針の使い方も、これらの動物群で異なります。例えば、ヤマアラシは危険を感じると針を逆立てて体を大きく見せて威嚇し、それでも敵が怯まない場合は針を相手に向けて体当たりすることがあります。一方、ハリネズミは体を丸めて針を外側に向け、ひたすら防御に徹します 21。
収斂進化の事例は、特定の形質が進化するための「道筋」が一つではないこと、そして外見上の類似性が必ずしも近縁関係を意味しないことを私たちに教えてくれます。ハリネズミとテンレックのように外見がそっくりでも 30、分子系統解析が全く異なる系統的位置を示すことは、表現型(目に見える形質)と遺伝子型(遺伝情報)の関係の複雑さを示しています。
表2: ハリネズミの針と他の「針を持つ哺乳類」との比較
| 動物群 | 分類学的位置(目) | 針の起源(推定) | 主な防御戦略 | 針の構造的特徴(例) |
| ハリネズミ | 食虫目 | 毛の変形 | 体を丸めて針を立てる(受動的防御) 21 | 中空、内部に隔壁、抜けにくい、逆棘なし 13 |
| ヤマアラシ | 齧歯目 | 毛の変形 | 針を立てて威嚇、体当たり、針が抜けやすい 21 | 長く太い、中実または髄腔あり、逆棘を持つ種も、抜けやすい 17 |
| ハリモグラ | 単孔目 | 体毛の特殊化 | 地中に潜る、丸まって針を向ける 22 | 短く太い、中実、体毛が変化、逆棘なし 22 |
| ヒメハリテンレック | テンレック目 | 毛の変形 | ハリネズミに類似(体を丸める) | ハリネズミの針に酷似した構造を持つが、系統は遠い 22 |
この表は、収斂進化という概念を具体的な動物例で示し、各動物の針の特徴と戦略の違いを際立たせることで、なぜこれらが「収斂」進化と呼ばれるのかを理解する助けとなります。
B. 針を作り出す遺伝暗号:分子生物学的アプローチ
ハリネズミの針が体毛から進化したものであるならば、その変化は遺伝子のレベルでどのようにして起きたのでしょうか。近年の分子生物学の発展は、この謎を解き明かすための強力な手がかりを提供し始めています。
1. ケラチン遺伝子群(KRT, KRTAP)の重要性
針の主成分がケラチンであることは既に述べましたが 13、体毛もまたケラチンからできています。では、同じケラチンから、なぜ柔らかい毛と硬い針という異なる構造が生み出されるのでしょうか。その答えの鍵を握るのが、ケラチンタンパク質そのものをコードする遺伝子群(KRT遺伝子)と、ケラチン線維同士を結びつけたり、毛の物理的特性を決定したりするのに重要な役割を果たすケラチン関連タンパク質をコードする遺伝子群(KRTAP遺伝子)です。
近年の研究では、RNAシーケンス(RNAseq)という技術を用いて、ハリネズミの針が作られる領域と通常の体毛が生える領域で、どのような遺伝子の活動(発現量)に違いがあるのかが網羅的に調べられています 32。その結果、ハリネズミの針の領域では、特定のKRT遺伝子群(例えば、KRT25, KRT27, KRT28, KRT32, KRT34, KRT35, KRT71, KRT72, KRT73, KRT75, KRT85など)やKRTAP遺伝子群(例えば、KRTAP3-1, KRTAP8-1, KRTAP15-1, KRTAP24-1など)が、通常の体毛の領域に比べて著しく活発に働いている(高発現している)ことが明らかになりました 32。特に、KRT34という遺伝子の発現量は針で非常に高かったと報告されています 32。これらの遺伝子群が、針特有の硬さや、中空で隔壁を持つといった複雑な内部構造の形成に深く関与している可能性が強く示唆されています 32。
さらに、ヨツユビハリネズミ (Atelerix albiventris) のKRT1というケラチン遺伝子には、他の多くの哺乳類の同じ遺伝子と比較して、45塩基対分のDNA配列が欠失していることが見つかっており、この遺伝的変異が針の発生や分化に何らかの役割を果たしているのではないかと考えられています 33。また、哺乳類全体で見ても、体毛の形態的多様性(例えば、羊毛の太さや縮れ具合、あるいはイルカのようにほとんど毛がない状態など)は、KRTAP遺伝子の種類や数の違い(レパートリーの変化)や、それらの遺伝子の使われ方の違いと密接に関連していることが分かっており、ハリネズミの針のような特殊な毛の形質も、KRTAP遺伝子の進化的な変化と相関していることが指摘されています 34。
これらの研究成果は、ハリネズミの針の驚くべき物理的特性(硬さ、弾力性、特異な構造)が、特定のケラチン遺伝子およびケラチン関連タンパク質遺伝子の巧妙な組み合わせと、それらの遺伝子の活動レベルの精密な制御によって生み出されていることを示しています。これは、毛から針への進化が、これらの構造タンパク質をコードする遺伝子の進化(DNA配列の変化や遺伝子の使われ方の変化)を通じて起きたことを強く示唆するものです。KRT1遺伝子の欠失やKRTAP遺伝子群の構成変化といった具体的な遺伝的変異は、針という新しい形質の獲得における「遺伝的イノベーション」の候補であり、これらの遺伝子の機能をさらに詳しく調べることで、針の進化的起源を分子の言葉で理解する道が開かれると期待されます。
2. 発生を司るシグナル伝達:ソニック・ヘッジホッグ(Shh)経路の役割
体の形や器官が作られる胚発生の過程では、細胞同士が情報をやり取りするための様々な化学物質(シグナル分子)が重要な役割を果たします。その中でも、「ソニック・ヘッジホッグ(Shh)経路」と呼ばれる一連のシグナル伝達システムは、動物の発生において極めて重要な役割を担っています。
Shhタンパク質をコードするSHH遺伝子は、胚発生の初期段階から働き始め、細胞の増殖や分化(特定の機能を持つ細胞へと変化すること)、そして体全体の正しい形作り(パターン形成)を指示する化学シグナルとして機能します 36。特に、脳や脊髄といった中枢神経系、眼、手足などの形成には不可欠な存在です 36。
興味深いことに、このShh経路は、鳥類の羽毛が伸びたり枝分かれしたりといった複雑な形態を作り上げる過程でも中心的な役割を果たすことが知られています 39。実験的にShh経路の働きを抑えると、羽毛の形が正常に作られなくなることが示されています 39。哺乳類の皮膚に生える毛や、爬虫類の鱗、鳥類の羽毛といった皮膚付属器は、進化的に共通の起源を持つと考えられており、これらの発生にはShh経路の他にも、BMPやFGFといった共通の分子シグナルが関与していることが分かっています 41。
実は、「ソニック・ヘッジホッグ」というユニークな名前は、発生生物学の研究でよく用いられるショウジョウバエの実験に由来します。このHedgehog(ハリネズミ)遺伝子に変異が起きると、幼虫の体の表面のパターンに異常が生じ、まるでハリネズミの針が一面に生えているかのような表現型を示したことから、この名が付けられました 42。
これらの知見を総合すると、Shh経路は、昆虫から哺乳類に至るまで、発生過程におけるパターン形成や付属器(手足、毛、羽など)の形成に広く関与する、進化的に非常によく保存されたシグナル伝達経路であると言えます。ハリネズミの針もまた、体毛が進化した皮膚付属器の一種です。したがって、Shh経路がハリネズミの針の発生や形態形成、特にその数や配置、基本的な構造の決定に重要な役割を果たしている可能性は極めて高いと考えられます。Shh経路の進化的な役割は、単に付属器の「有る・無し」を制御するだけでなく、その「形」や「パターン」の多様化にも寄与していると考えられます。ハリネズミの針のような特殊な構造は、Shh経路を含む発生に関わる遺伝子群の働くタイミングや量の微妙な変化によって、進化の過程で生み出されたのかもしれません。これは、進化発生学(エボデボ)という分野の中心的なテーマの一つです。
3. 針のサイズと形成に関わるその他の遺伝子たち
ハリネズミの針というユニークな構造は、ケラチン遺伝子群やShh経路だけで全てが説明できるわけではありません。近年の研究により、針の太さや長さといった「サイズ」の制御や、毛から針へと分化する過程には、さらに他の遺伝子や分子メカニズムが複雑に関与していることが明らかになってきました。
例えば、「Eda-Edarシグナル伝達経路」は、皮膚付属器が作られ始める初期段階で、表皮細胞と間充織細胞(皮膚の深層にある細胞)の間で交わされる情報伝達に不可欠であり、毛や歯、汗腺などの正常な発生に重要な役割を果たしています。この経路は、別の重要な発生シグナルであるWNT経路とも密接に相互作用することが知られています 43。ハリネズミの針も皮膚付属器であるため、Eda-Edar経路がその発生に関与している可能性が考えられます。
また、ハリネズミの針を生み出す毛包(毛や針を産生する皮膚の器官)は、マウスなどの一般的な哺乳類の毛を生み出す毛包と比較して、著しく大きいことが観察されています。この「サイズ」の違いがどのようにして生まれるのかという疑問に対して、中国の研究グループが興味深い報告をしています。彼らの研究によると、細胞のエネルギー産生に深く関わるミトコンドリア内の遺伝子であるCOX2と、エネルギー通貨であるATPを合成する酵素(ATP合成酵素)が、ハリネズミの針の毛包のサイズ制御に重要な役割を果たしていることが示されました 44。具体的には、COX2の働きを阻害するとATP合成酵素の発現量が低下し、その結果として針の毛包の細胞増殖が抑えられ、最終的に針の毛包が小さくなることが確認されたのです 44。この発見は、器官のサイズが細胞レベルのエネルギー代謝と密接に連携していることを示す美しい例であり、進化の過程で生物がどのようにして物理的なスケール(この場合は針の太さや長さ)を調整するのかという普遍的な問いに手がかりを与えます。
さらに、ゲノム(全遺伝情報)の中には、タンパク質の設計図である遺伝子領域以外にも、様々な機能を持つ配列が存在します。その一つに「トランスポゾン(TE)」または「動く遺伝子」と呼ばれる反復配列があり、これらはゲノム上を移動したり、自身のコピーを増やしたりする能力を持っています。近年の研究では、ハリネズミのゲノムにはSINE(短い散在反復配列)と呼ばれるタイプのトランスポゾンが特に多く存在し、これらのトランスポゾンの一部が、針の発生に関わる可能性のある遺伝子(例えば、表皮の分化や骨格の発達に関連する遺伝子)の近くで活発に働いたり、あるいは働きを抑えたりすることで、遺伝子の発現量に影響を与え、結果として針の形成に関与している可能性が示唆されています 45。トランスポゾンの関与は、ゲノムの非コード領域や「動く遺伝子」が形質進化においてこれまで考えられていた以上に重要な役割を果たしている可能性を示唆し、今後の研究の新たな方向性を示すものです。
この他にも、FGF(線維芽細胞増殖因子)と呼ばれる一群のシグナル分子が、針様の組織で特に活発に働いており、MAPK経路やRap1経路といった細胞内の情報伝達システムを介して、器官形成やパターン形成に関与していることが報告されています 33。
これらの知見は、ハリネズミの針の形成が、単一の「針遺伝子」によって決まるのではなく、構造タンパク質をコードする遺伝子群、発生のパターンを制御するシグナル経路、器官のサイズを決定するエネルギー代謝関連遺伝子、さらにはゲノムの反復配列に至るまで、多種多様な遺伝的要因が複雑に絡み合い、協調して働くことによって制御される、壮大な進化的産物であることを物語っています。
表3: ハリネズミの針形成に関与が示唆される主要遺伝子・経路
| 遺伝子/経路の名称 | 針形成における推定される役割 | 関連する研究ソース (主なSnippet ID) |
| KRT遺伝子群 | 針の主要構造タンパク質(ケラチン)をコードし、硬度や弾力性などの物理的特性を付与する 32 | 32 |
| KRTAP遺伝子群 | ケラチン線維間を架橋し、針の強度や特性を微調整する 32 | 32 |
| Shh (ソニック・ヘッジホッグ) 経路 | 皮膚付属器の初期発生、パターン形成、細胞増殖・分化を制御する 36 | 36 |
| Eda/Edar経路 | 皮膚付属器形成時の初期の表皮-間充織相互作用、WNT経路との連携 43 | 43 |
| COX2-ATP合成酵素軸 | ミトコンドリアでのエネルギー産生を介して細胞増殖を制御し、針毛包のサイズを決定する 44 | 44 |
| FGF (線維芽細胞増殖因子) | 針様組織で高発現し、MAPK/Rap1経路を介して器官形成やパターン形成に関与 33 | 33 |
| SFN (Stratifin) | 針様組織で高発現し、ケラチノサイト分化や毛幹構造に関与、p53経路と関連 33 | 33 |
| トランスポゾン (SINEs) | ゲノム内に多数存在し、近傍遺伝子の発現調節を介して針発生関連遺伝子に影響を与える可能性 45 | 45 |
この表は、ハリネズミの針という特異な形質がいかに多くの遺伝的要素の協調によって成り立っているかを示しており、生命の設計図の複雑さと進化の奥深さを物語っています。
C. 進化発生学(エボデボ)が解き明かす針の起源と研究の最前線
1. 最新研究動向:ゲノム解析から見える未来
ハリネズミの針がどのようにして進化し、どのようにして作られるのかという謎に迫る研究は、近年、「進化発生学(エボデボ:Evolutionary Developmental Biology)」という学際的なアプローチによって大きく進展しています。エボデボは、生物の進化(Evolution)の過程と、個体の発生(Development)のメカニズムを結びつけて理解しようとする学問分野です。つまり、「遺伝子がどのように変化して新しい形質が生まれたのか(進化)」と、「その遺伝子が個体発生の過程でどのように働いてその形質を作り出すのか(発生)」を同時に解き明かそうとするのです。
日本の東京工業大学(現・東京科学大学)の二階堂雅人研究室をはじめとするいくつかの研究グループは、まさにこのエボデボ的視点から、哺乳類において体毛が硬い針や棘(とげ)へと進化した「平行進化」(収斂進化と類似するが、より近縁なグループ内で独立に同様の形質が生じる場合などに使われる)の分子メカニズム解明に取り組んでいます 30。特に、外見が酷似していながら系統的には遠いハリネズミとテンレックに着目し、これらの動物の針が持つ精巧な内部構造(縦横に配置されたリブ構造など)が、どのような発生過程を経て作り上げられるのか、そしてその背景にはどのような遺伝的変化があったのかを調べています 30。
具体的な研究目的としては、ハリネズミの針が複数の体毛が融合してできたものなのか、それとも1本の体毛が著しく太く硬く変化(肥大化)したものなのかを組織学的に検証することや、前述のRNAシーケンス(RNAseq)のような網羅的遺伝子発現解析技術を用いて、針と通常の体毛との間で形態的な違いを生み出す原因となる遺伝子を特定することなどが挙げられます 32。研究手法としては、針や皮膚の組織切片を作製して顕微鏡で詳細に観察する形態学的アプローチに加え、次世代シーケンサーを用いたゲノムワイドな遺伝子発現解析(トランスクリプトーム解析)、特定のタンパク質の局在を調べる抗体染色法などが駆使されています 30。
このような研究をさらに推し進めるための重要な基盤となるのが、対象生物の全ゲノム情報(DNAの全塩基配列)です。二階堂研究室では、「Project Kalunguyeye(カルングイェイェ)」と名付けられたヨツユビハリネズミの全ゲノム解読プロジェクトを推進しています(Kalunguyeyeはスワヒリ語でハリネズミを意味します)30。このプロジェクトは、体毛の針化に関与すると考えられる候補遺伝子の機能を詳細に解析したり、将来の様々な研究(例えば、ハリネズミの疾患原因遺伝子の探索や、集団内での遺伝的多様性の解析など)のための強固な研究基盤を構築したりすることを目指しています。このプロジェクトは、タンザニア野生動物研究所(TAWIRI)との国際共同研究として進められており、欧米や中国の研究グループが主に注目しているナミハリネズミとは異なる種を用いることで、日本主導の独自性の高い研究展開が期待されています 30。全ゲノム情報が整備されれば、ハリネズミという、実験動物としてはまだ馴染みの薄い(非モデル)生物を対象とした研究が飛躍的に進展し、針の進化の謎だけでなく、ハリネズミの生理、生態、疾患に関する様々な生物学的疑問の解明に貢献するでしょう。
実際に、ヨツユビハリネズミの皮膚付属器(針と毛)の発生段階や分化段階における遺伝子発現を網羅的に比較したトランスクリプトーム解析からは、既にいくつかの興味深い候補遺伝子(例えば、前述のSFN遺伝子やFGF遺伝子、KRT1遺伝子など)や、それらが関与する可能性のあるシグナル伝達経路(p53経路やMAPK経路など)が同定されています 33。また、アフリカンハリネズミ(ヨツユビハリネズミ)のゲノムにおけるトランスポゾン(特にLINEおよびSINEと呼ばれるレトロトランスポゾン)の分布や特徴、そしてそれらが3次元的なゲノム構造や遺伝子の発現(特に針の発生に関連する遺伝子の発現)にどのような影響を与えているのかを解析した研究も報告されています 45。
これらの最先端の研究は、ハリネズミの針形成の進化発生学的起源を解明することを目的としており、黒瀬成美氏、田中亮輔氏、小林汐織氏、重谷安代氏、岡部正隆氏、長澤竜樹氏、二階堂雅人氏といった研究者らによって、日本国内の複数の学会(日本進化学会、日本遺伝学会、日本動物学会など)でその成果が発表されています 49。
これらの研究動向は、ハリネズミの針の進化と発生の研究が、ゲノミクス(ゲノム情報科学)、トランスクリプトミクス(遺伝子発現情報科学)、比較発生学、進化生物学といった多分野の最先端技術と知識を融合させた、まさに「進化発生学(エボデボ)」的アプローチによって力強く推進されていることを示しています。これにより、単に「どの遺伝子が針と毛で違うのか」という問いに留まらず、「その遺伝的な違いが、具体的にどのような発生プロセスを変化させ、体毛というありふれた構造から針という全く新しい形質を生み出すに至ったのか」という、生命進化の根本的な謎に迫ることが可能になりつつあるのです。
IV. まとめ:小さな体に秘められた進化の奇跡
A. ハリネズミの針が示す生命の適応戦略
本稿で見てきたように、ハリネズミの背中を覆う無数の針は、単なる珍しい特徴ではなく、生命の驚くべき適応戦略と進化の巧妙さを物語る生きた証拠です。その起源を辿れば、私たち自身の体毛と同じケラチンというタンパク質から作られた、ありふれた皮膚付属器に行き着きます。しかし、ハリネズミは進化の過程で、この体毛を素材として、捕食者からの防御という明確な目的、そして高所からの落下という物理的衝撃に耐えるという副次的ながら重要な機能を持つ、軽量かつ強靭で、衝撃吸収性に優れた精巧な構造物へと進化させました。
この「毛から針へ」の変身は、決して一朝一夕に起きたわけではありません。それは、ハリネズミが生きる厳しい自然環境、特に絶え間ない捕食圧という淘汰の力に晒されながら、気の遠くなるような長い時間をかけて、遺伝子の小さな変化を一つ一つ積み重ねてきた結果です。特定のケラチン遺伝子やケラチン関連タンパク質遺伝子の種類や働き方が変わり、ソニック・ヘッジホッグ経路のような発生を司るシグナル伝達システムが微調整され、さらには細胞のエネルギー代謝に関わる遺伝子までもが針のサイズ形成に関与するなど、実に多くの遺伝的要素が複雑に絡み合い、協調することで、このユニークな形質は実現されました。
ハリネズミの針の進化は、既存の材料と遺伝的ツールキットを巧みに再利用・改変し、生存に有利な新しい形質を生み出すという、ダーウィンが提唱した自然選択による進化の核心的なプロセスを見事に体現しています。それは、生命がいかにして多様な環境に適応し、その姿を変えてきたかという、壮大な進化の物語の一端を私たちに示してくれるのです。
B. ハリネズミとの共生を考える
ハリネズミという小さな生き物への科学的な理解を深めることは、彼らをペットとして愛育する私たちにとって、その習性やニーズに合わせた適切な飼育環境を提供する責任を果たす上で非常に重要です。彼らが本来持っている繊細な性質や、野生下での生態(夜行性、単独性、特有の食性など)を知ることは、ストレスの少ない健康的な生活をハリネズミに提供するための第一歩となります。
同時に、野生生物としてのハリネズミに目を向けることも忘れてはなりません。彼らはそれぞれの生息環境において、生態系の一員として重要な役割を担っています。しかし、人間の活動は、時に彼らの生息地を脅かし、また、意図せず持ち込まれた外来種としてのハリネズミが在来の生態系に予期せぬ影響を与える可能性も指摘されています(例えば、日本に定着したアムールハリネズミなど 5)。さらに、都市部やその近郊に生息するハリネズミが、環境中に存在する様々な化学汚染物質に曝露されているという報告もあります 52。
ハリネズミの針一本一本に刻まれた進化の歴史と、その小さな体に秘められた生命の適応の物語に触れることは、単に知的好奇心を満たすだけでなく、私たちが他の生物とどのように関わり、どのように共生していくべきかという、より広範な問いについて考えるきっかけを与えてくれます。彼らのユニークな生態と進化の背景を理解し、尊重すること。それが、愛らしい隣人であるハリネズミと、そして私たちを取り巻く自然全体とのより良い関係を築くための基礎となるのではないでしょうか。
引用文献
- ハリネズミの飼い方・特徴・種類〜初心者向け〜 | 小動物系のペット …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.porta-y.jp/feature/small_animals/hedgehog
- ハリネズミの飼い方と魅力を徹底解説!寿命や特徴など初心者向け …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.tcaeco.ac.jp/contents/animalbook/hedgehog/
- 6/3(月)ハリネズミまつわる話 | スタッフブログ – ナビット, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.navit-j.com/blog/?p=70958
- ハリネズミの飼い方ガイド!種類や罹患しやすい病気も紹介 – 保険の比較, 5月 7, 2025にアクセス、 https://hoken.rakuten.co.jp/pet/column/hedgehog/
- ハリネズミ属 / 国立環境研究所 侵入生物DB, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10010.html
- 環境報告書2016 – 静岡大学, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.shizuoka.ac.jp/outline/koho/publication/kankyo/document/Em2016.pdf
- 家庭動物等飼養保管技術マニュアル – 環境省, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/house.pdf
- ハリネズミの憂鬱 | 持続可能な林業のために, 5月 7, 2025にアクセス、 https://kinshizen-ringyo.com/archives/438
- ハリネズミさん~長生きの秘訣 – ちくちくCAFE, 5月 7, 2025にアクセス、 https://hedgehoghome.cafe/2018/04/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%82%BA%E3%83%9F%E3%81%95%E3%82%93%EF%BD%9E%E9%95%B7%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%AE%E7%A7%98%E8%A8%A3%EF%BD%9E/
- ハリネズミの寿命は?飼育下での平均寿命と正しい飼育方法 – ピュアアニマル, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pure-animal.com/blog/hedgehog/hedgehog-lifespan.html
- European Hedgehog Mortality – Predators | Wildlife Online, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.wildlifeonline.me.uk/animals/article/european-hedgehog-predators
- ハリネズミってどんな動物(知らないといけない生態と特徴) – 飼育 …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.exoinfo.jp/care/910/
- Spiny coat – Pro Igel | Verein für integrierten Naturschutz …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.pro-igel.de/spiny-coat/?lang=en
- ハリネズミさんの飼育方法~針のおはなし – ちくちくCAFE, 5月 7, 2025にアクセス、 https://hedgehoghome.cafe/2018/03/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%82%BA%E3%83%9F%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AE%E9%A3%BC%E8%82%B2%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BD%9E%E9%87%9D%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%97%EF%BD%9E/
- ハリネズミさん 「ハリネズミの抜針」 – 川口市 – どうぶつのセンター病院, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.animalpro.jp/2017/06/28/675/
- Spines and Quills – Animal Diversity Web, 5月 7, 2025にアクセス、 https://animaldiversity.org/collections/spinesquills/
- (PDF) Mechanical design of hedgehog spines and porcupine quills, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/229674283_Mechanical_design_of_hedgehog_spines_and_porcupine_quills
- Bioinspirational understanding of flexural performance in hedgehog spines – PubMed, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31129360/
- ハリネズミについて – ハート動物病院, 5月 7, 2025にアクセス、 http://www.7651122.com/exotic/pg199.html
- Animals with spines and quills – IFAW, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.ifaw.org/journal/animals-spines-quills
- ハリネズミとヤマアラシの違い | ハリネズミ HAGU CAFEブログ, 5月 7, 2025にアクセス、 https://ameblo.jp/hagucafe-shinjyukuhonten/entry-12346528026.html
- 図1 天王寺動物園のヒメハリテンレック, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.tennojizoo.jp/nakigoe/2009/04/report01.html
- Dynamic Impact Testing of Hedgehog Spines Using a Dual-Arm Crash Pendulum | Request PDF – ResearchGate, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/299443862_Dynamic_Impact_Testing_of_Hedgehog_Spines_Using_a_Dual-Arm_Crash_Pendulum
- Dynamic impact testing of hedgehog spines using a dual-arm crash pendulum – PubMed, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27082130/
- ハリネズミ – Wikipedia, 5月 7, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%82%BA%E3%83%9F
- COX2-ATP Synthase Regulates Spine Follicle Size in Hedgehogs – PMC – PubMed Central, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10539703/
- ヨツユビハリネズミの全身麻酔に伴う低体温と保温の効果, 5月 7, 2025にアクセス、 https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2030903198.pdf
- 第388回 ビジネスでは適切な距離感をもって信頼関係を築こう – 大阪産業創造館, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.sansokan.jp/akinai/reports/staff_blog/no388.html
- ハヤブサはタカやワシよりもオウムに近い!?収斂進化の解説。 – note, 5月 7, 2025にアクセス、 https://note.com/silentbluehorse/n/n6310c8cd95cd
- Research | Nikaido Lab. – 二階堂研究室 – 東京工業大学, 5月 7, 2025にアクセス、 http://www.nikaido.bio.titech.ac.jp/about.html
- madagascan hedgehog tenrec: Topics by Science.gov, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.science.gov/topicpages/m/madagascan+hedgehog+tenrec
- kaken.nii.ac.jp, 5月 7, 2025にアクセス、 https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-17K19422/17K19422seika.pdf
- Transcriptome analysis reveals the genetic basis underlying the …, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7435191/
- (PDF) Mammalian keratin associated proteins (KRTAPs) subgenomes: Disentangling hair diversity and adaptation to terrestrial and aquatic environments – ResearchGate, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/265610737_Mammalian_keratin_associated_proteins_KRTAPs_subgenomes_Disentangling_hair_diversity_and_adaptation_to_terrestrial_and_aquatic_environments
- molecular characterisation of keratin- associated protein-7 (krtap7) gene for hair quality in indian – Camels and Camelids, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.camelsandcamelids.com/uploads/journal-manuscript/molecular-characterisation-of-keratin-associated-protein-7-krtap7-gene-for-hair-quality-in-indian-dromedary-camel.pdf
- SHH gene: MedlinePlus Genetics, 5月 7, 2025にアクセス、 https://medlineplus.gov/genetics/gene/shh/
- Development of the central nervous system – Kenhub, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/development-of-the-central-nervous-system
- Neural – Spinal Cord Development – UNSW Embryology, 5月 7, 2025にアクセス、 https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Neural_-_Spinal_Cord_Development
- In vivo sonic hedgehog pathway antagonism temporarily results in ancestral proto-feather-like structures in the chicken | PLOS Biology, 5月 7, 2025にアクセス、 https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3003061
- (PDF) In vivo sonic hedgehog pathway antagonism temporarily results in ancestral proto-feather-like structures in the chicken – ResearchGate, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/390032182_In_vivo_sonic_hedgehog_pathway_antagonism_temporarily_results_in_ancestral_proto-feather-like_structures_in_the_chicken
- Mammalian skin evolution | Request PDF – ResearchGate, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/10694440_Mammalian_skin_evolution
- 発生生物学の静かな革命, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.brh.co.jp/upload/journal/111/rensai.pdf
- (PDF) Interplay between EDA-EDAR and WNT signalling pathways in the development of skin appendages in hypohidrotic ectodermal dysplasia – ResearchGate, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/391047793_Interplay_between_EDA-EDAR_and_WNT_signalling_pathways_in_the_development_of_skin_appendages_in_hypohidrotic_ectodermal_dysplasia
- COX2-ATP Synthase Regulates Spine Follicle Size in Hedgehogs, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.ijbs.com/v19p4763.htm
- Identification and Characterization of LINE and SINE Retrotransposons in the African Hedgehog (Atelerix albiventris, Erinaceidae) and Their Association with 3D Genome Organization and Gene Expression – PubMed Central, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12026660/
- Identification and Characterization of LINE and SINE Retrotransposons in the African Hedgehog (Atelerix albiventris, Erinaceidae) and Their Association with 3D Genome Organization and Gene Expression – PubMed, 5月 7, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40282356/
- 【研究室紹介】 二階堂研究室 | 生命理工学系 News – 学院・系及びリベラルアーツ研究教育院 – 東京工業大学, 5月 7, 2025にアクセス、 https://educ.titech.ac.jp/bio/news/2016_11/052868.html
- 二階堂研究室 | Nikaido Lab., 5月 7, 2025にアクセス、 http://www.nikaido.bio.titech.ac.jp/index.html
- 重谷 安代 (Yasuyo Shigetani) – マイポータル – researchmap, 5月 7, 2025にアクセス、 https://researchmap.jp/yasuyoshigetani
- 長澤 竜樹 (Tatsuki Nagasawa) – マイポータル – researchmap, 5月 7, 2025にアクセス、 https://researchmap.jp/N_Tatsuki
- Publications | Nikaido Lab. – 二階堂研究室 – 東京工業大学, 5月 7, 2025にアクセス、 http://www.nikaido.bio.titech.ac.jp/publications.html
- Surprising number of environmental pollutants in hedgehogs – ScienceDaily, 5月 7, 2025にアクセス、 https://www.sciencedaily.com/releases/2025/04/250401131532.htm