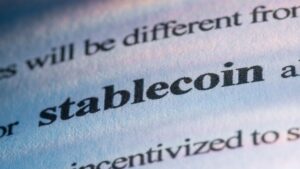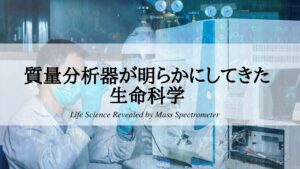I. 欧州5大リーグの現状:世界最高峰の戦術とビジネス
欧州5大リーグ(イングランド・プレミアリーグ、スペイン・ラ・リーガ、ドイツ・ブンデスリーガ、イタリア・セリエA、フランス・リーグ・アン)は、世界のサッカー界において戦術的革新と巨大なビジネスモデルの双方で最先端を走り続けている 1。これらのリーグが持つ圧倒的な競争力と影響力を理解することは、Jリーグが目指すべき姿を明確にする上で不可欠である。

A. 戦術的特徴と進化の最前線
5大リーグは、それぞれ独自の戦術的特徴を持ちながらも、常に進化を続けている。
1. 各リーグの主要な戦術フィロソフィーと近年のトレンド
- プレミアリーグ (Premier League): 近年、試合のインテンシティは極めて高く、特にトランジション(攻守の切り替え)の速さとダイレクトな攻撃が顕著になっている 2。ペップ・グアルディオラ監督がマンチェスター・シティで体現したポゼッション志向のサッカーも依然として影響力を持つが、多くのチームがハイプレスからのショートカウンターや、素早い縦への展開を志向する傾向にある 4。リヴァプールでは、ユルゲン・クロップ監督の後任であるアルネ・スロット監督が、前任者の戦術をさらに進化させ、よりダイレクトなプレースタイルで成功を収めているとの分析もある 2。2024/25シーズンにおいては、シュートに至る速攻(fast breaks)の数が1試合平均1.84回と、2006/07シーズン以降の記録で最多となっており、その得点数も1試合平均0.30と高い水準にある 3。これは、ポゼッションを重視するチームが増える中で、相手の守備が整う前に素早く攻撃することの有効性が再認識されていることを示している。
- ラ・リーガ (La Liga): 伝統的に高いテクニックとポゼッションを重視するスタイルが特徴的である 5。かつてFCバルセロナが見せた「ティキ・タカ」に代表されるように、ショートパスを多用し、選手間の流動的な動きとインテリジェントなポジショニングによってゲームをコントロールしようとするチームが多い 6。フィジカルの強さよりも、戦術的な理解度やゲームIQの高さがより求められるリーグと評されることも少なくない 5。個々の選手の創造性やドリブルでの打開も重要な要素となっている 7。
- ブンデスリーガ (Bundesliga): 試合全体のインテンシティが高く、特にハイプレスとそこからの素早いトランジションが際立っている 8。ユルゲン・クロップ監督がボルシア・ドルトムントで成功させた「ゲーゲンプレス」(カウンタープレス)の概念はリーグ全体に浸透し、多くのチームが相手陣地深くまで積極的にプレッシャーをかける攻撃的な守備戦術を採用している 8。また、戦術的な柔軟性も特徴の一つであり、選手には複数のポジションや役割をこなす多機能性が求められる。3-4-3や4-2-3-1といった多様なフォーメーションが試合状況に応じて用いられる 8。かつてラルフ・ラングニック氏がホッフェンハイムやRBライプツィヒで示した戦術哲学も、現代のブンデスリーガに影響を与えている 9。
- セリエA (Serie A): 歴史的に戦術的な洗練度が高く、堅固な守備組織を構築するチームが多いことで知られている 10。近年はより攻撃的な戦術を採用するチームも増えてきているが、依然として高度な戦術理解と組織的なプレーが求められるリーグである 7。アタランタを率いるジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が見せる3-4-3フォーメーションにおける多彩な攻撃パターンなど、革新的な戦術も注目される 11。
- リーグ・アン (Ligue 1): パリ・サンジェルマン(PSG)が攻撃的・守備的指標のほぼ全てにおいて他を圧倒しており、豊富なタレント力を背景にしたポゼッション志向のサッカーを展開している 7。一方で、リーグ全体としてはフィジカルコンタクトの強さが指摘されることもあり、堅守からの速攻を主体とするチームも少なくない 12。かつてニースを率いたフランチェスコ・ファリオーリ監督(現アヤックス)のように、中央からの丁寧なビルドアップと組織的なハイプレスを志向する戦術も見られる 13。
これらのリーグに共通するトレンドとしては、データ分析の積極的な活用、セットプレーの重要性の高まり、攻守のトランジションのさらなる高速化、そしてプレッシング強度の向上が挙げられる 2。
2. トップレベルのコーチングと戦術革新
5大リーグの戦術レベルの高さは、世界的に著名な監督たちの存在と無縁ではない。彼らは日々新たな戦術を生み出し、リーグ全体の戦術的革新をリードしている 3。例えば、ドイツサッカー連盟(DFB)はコーチ教育プログラムの充実に力を入れており、新しい戦術哲学の導入を積極的に支援している 8。これにより、指導者の質が向上し、ひいてはリーグ全体の戦術レベルの底上げに繋がっている。UEFAの各級コーチングライセンス(プロ、A級、B級)を持つ指導者の層の厚さも、戦術レベルの高さと密接に関連していると考えられる 16。
3. 選手育成エコシステムとタレント輩出
5大リーグのクラブは、大規模なアカデミー(育成組織)を運営し、若手選手の育成に多額の投資を行っている 8。特にドイツでは、ブンデスリーガの全クラブに対して、DFBが定める基準を満たしたユースアカデミーの保有が義務付けられており、国全体で体系的な選手育成に取り組んでいる 8。
5大リーグ以外でも、オランダのエールディビジに所属するアヤックスや、ポルトガル・プリメイラ・リーガのベンフィカ、FCポルトといったクラブは、世界的に見ても非常に優れた育成システムとスカウティングネットワークを構築している 18。これらのクラブは、育成した多くのトップ選手を5大リーグのクラブへ高額な移籍金で輩出するという、育成とビジネスを両立させたモデルを確立しており、5大リーグにとっても重要なタレント供給源となっている。
また、国際サッカー連盟(FIFA)も、「FIFA Forwardプログラム」を通じて、世界211の加盟協会や各大陸連盟に対し、サッカーの発展(インフラ整備、選手育成、大会運営資金など)を目的とした多額の資金援助を行っており、2016年から2022年末までに約28億米ドルが提供された 22。
スイスのCIES Football Observatoryのような研究機関のレポートは、若手選手の国際的な移籍の動向や、育成クラブが果たす役割の重要性を継続的に指摘している 24。
5大リーグの戦術的な優位性は、単に個々の優れた選手や監督の存在によってのみ支えられているわけではない。リーグ全体で活発に行われる戦術的な革新、高度なコーチング教育システム、そして継続的な若手育成への巨額の投資といった要素が相互に作用し合う「エコシステム」が、その強固な基盤を形成している。各リーグに見られる多様かつ進化の速い戦術トレンド 2 は、質の高い指導者 8 と、その指導者を育成する体系的なシステム(例:DFBの取り組み 8)があってこそ可能になる。さらに、優秀な若手選手がアカデミーから継続的に供給されること 8 が、新しい戦術を試す土壌を育み、リーグ全体の戦術レベルを絶えず引き上げているのである。
また、5大リーグ内部でも、それぞれのリーグが持つ戦術的トレンドには明確な差異が存在する。この差異が、リーグ間の相対的な競争力や、国際移籍市場における選手の評価にも影響を与えている可能性は否定できない。例えば、プレミアリーグで求められるフィジカルインテンシティの高さとトランジションの速さ 2 は、他リーグでプレーする選手が適応する上での一つのハードルとなる。一方で、ラ・リーガで重視される戦術的緻密さやポゼッション能力 5 は、異なるタイプの選手に高い価値を見出す土壌を提供している。ブンデスリーガのハイプレスと戦術的柔軟性 8 もまた独特の選手像を求める。これらの戦術的特徴は、各リーグで活躍するために必要な選手像を規定し、移籍する選手の適応の難易度や、スカウトが特定のリーグの選手を評価する際の基準に影響を及ぼす。Jリーグの選手が持つ「スピードとインテンシティ」28 は、プレミアリーグやブンデスリーガで活きる可能性がある一方で、ラ・リーガのポゼッションを主体としたゲームへの適応は、また異なる種類の課題を伴うかもしれない。
B. 巨大ビジネスモデルとグローバルな収益構造
5大リーグは、戦術面だけでなく、ビジネス面においても世界をリードしている。その収益規模、グローバルなブランド戦略、多様なクラブ所有形態、そして財務的持続可能性への取り組みは、他のリーグが追随すべき多くの示唆を含んでいる。
1. 収益規模と内訳
2022/23シーズンにおいて、欧州5大リーグの総収益は196億ユーロ(約3兆1556億円*)に達し、前シーズンから14%の増加を記録した 29。このうち、イングランド・プレミアリーグが単独で61億ポンド(約71億ユーロ、約1兆1431億円*)と他を圧倒的な差で引き離している 29。特筆すべきは、ドイツ・ブンデスリーガとイタリア・セリエAがそれぞれ前年比22%増と、5大リーグの中で最も高い収益成長率を達成したことである 29。
*1ユーロ=161円で換算(以下同様)
収益の内訳を見ると、放映権収益が最も大きな割合を占めており、5大リーグ合計で約92億ユーロ(約1兆4812億円)に上る(2022/23シーズン)30。プレミアリーグの放映権収益は約37億ユーロ(約5957億円)と突出しており、そのうち国際放映権料は国内放映権料を上回る規模にまで成長している 30。
商業収入も重要な収益源であり、5大リーグ合計で約76億ユーロ(約1兆2236億円)に達する(2022/23シーズン)32。これには、グローバル企業との大型スポンサーシップ契約、世界規模でのマーチャンダイジング展開、さらにはスタジアムをコンサートや他のスポーツイベントに活用することによる収入などが含まれる 29。
入場料収入は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックからのファン回帰により大幅に増加し、5大リーグ合計で約28億ユーロ(約4508億円)となった(2022/23シーズン)30。特にブンデスリーガは、1試合あたりの平均観客動員数で5大リーグ中トップを誇り、スタジアムの熱気が収益にも貢献している 30。
Jリーグと5大リーグの経済規模には依然として大きな隔たりがある。以下の表は、各リーグのクラブ平均収益を比較したものである。
Table 1: 欧州5大リーグとJリーグのクラブ平均収益比較 (2022/23シーズン)
| リーグ | クラブ平均総収益 (億ユーロ) | クラブ平均入場料収入 (億ユーロ) | クラブ平均放映権収入 (億ユーロ) | クラブ平均商業収入 (億ユーロ) |
| プレミアリーグ | 3.55 | 0.40 | 1.85 | 0.95 |
| ブンデスリーガ | 2.11 | 0.28 | 0.83 | 1.00 |
| ラ・リーガ | 1.75 | 0.25 | 0.90 | 0.60 |
| セリエA | 1.45 | 0.20 | 0.75 | 0.45 |
| リーグ・アン | 1.20 | 0.05 | 0.35 | 0.20 |
| J1リーグ (2023) | 0.32 (52.01億円) | 0.06 (9.61億円) | N/A | N/A |
出典: 5大リーグは 30 (2022/23シーズンデータを使用し、各リーグの総収益をクラブ数で割った概算値。プレミアリーグは20クラブ、他は18-20クラブのため、ここでは簡略化のため20クラブで計算)。J1リーグは 33 (2023年データ、1ユーロ=161.3円で換算 34)。J1リーグの放映権・商業収入のクラブ平均内訳は提供資料からは特定できず。
この表が示すように、Jリーグのクラブ平均収益は、5大リーグのそれと比較して著しく低い。この経済規模の差が、トップレベルの選手獲得競争力、最新鋭のインフラへの投資能力、そしてグローバルなマーケティング展開力といった、リーグの総合的な力に直接的な影響を及ぼしていることは明らかである。Jリーグが真に5大リーグに迫るためには、このビジネス規模の差をいかにして縮小していくかが極めて重要な課題となる。
2. グローバルブランド戦略と国際的リーチ
5大リーグのトップクラブは、単なるサッカーチームを超えたグローバルブランドとしての地位を確立している。これらのクラブは世界中に広大なファンベースを有し、主要なソーシャルメディアプラットフォームにおける累計フォロワー数は数十億の規模に達する 35。各リーグの試合は180カ国以上で放送されており、これがクラブのブランド価値を国際的に高める強力な後押しとなっている 35。
クラブ自身も、独自のメディアハウスとして機能し、試合映像だけでなく、選手の日常やクラブの舞台裏といったオリジナルコンテンツを積極的に制作・配信することで、ファンとのエンゲージメントを深めている 35。さらに、アジアや北米などでのプレシーズンツアーの実施、海外でのファンイベントの開催、そして現地の言語や文化に合わせた情報発信といったローカライズ戦略も積極的に展開している 35。例えばラ・リーガは、アジア市場において「その国で2番目に良いリーグ」としてのポジションを目指し、現地のKOL(キーオピニオンリーダー)を起用したプロモーションを行うなど、きめ細かい戦略を推進している 38。
ブランド価値評価を行うBrand Financeのレポートによれば、レアル・マドリード、マンチェスター・シティ、FCバルセロナといったクラブが、ブランド価値ランキングの上位を常に争っている 40。
3. クラブ所有形態の多様性とガバナンス
欧州5大リーグにおけるクラブの所有形態は、それぞれの国の歴史的背景、文化、経済状況、そして法規制の違いを反映し、多様な進化を遂げてきた 42。
イングランド・プレミアリーグやイタリア・セリエAでは、クラブの所有権が特定の個人や企業グループに集中する傾向が見られ、近年は特にアメリカや中東の外国資本による買収が活発化している 42。
対照的に、ドイツ・ブンデスリーガでは「50+1ルール」という独自の規則が存在する。これは、クラブの議決権の少なくとも51%をファンで構成される会員組織が保有することを義務付けるものであり、外部資本による完全な買収を防ぎ、サポーターがクラブ経営に一定の影響力を持ち続けることを可能にしている。このルールは、クラブと地域社会との強固な結びつきを維持する上で重要な役割を果たしていると評価されている 8。
スペイン・ラ・リーガでは、1990年のスポーツ法改正により多くのクラブが株式会社化を義務付けられたが、レアル・マドリードやFCバルセロナといった一部の歴史あるクラブは、例外的に会員制ソシオ制度を維持している 42。フランス・リーグ・アンでは、メディア企業や外国資本による投資が見られる 42。
21世紀に入りグローバル化が加速する中で、国際的な投資家によるクラブ所有は一層増加している。これには、純粋な財政的リターンを求める投資だけでなく、国家のイメージ向上やソフトパワー行使を目的とした、いわゆる「スポーツウォッシング」と見なされるケースも含まれる 42。
4. 財務的健全性と持続可能性への取り組み
クラブ経営の財務的健全性を確保し、持続可能な発展を促すため、欧州サッカー連盟(UEFA)はファイナンシャル・フェアプレー(FFP)規則を導入し、その後、より包括的な財務持続可能性規則(FSR)へと発展させた 44。これらの規則の主な目的は、クラブの過度な支出を抑制し、収入に見合った経営を促すことにある。具体的には、選手やコーチの人件費、移籍金、代理人への手数料といった支出を、クラブの総収益の一定割合(例えば70%)以内に収めることなどが求められている 46。
しかし、FFPやFSRの効果については様々な議論がある。特に、競争均衡への影響や、既に収益力の高いビッグクラブの優位性を結果的に固定化してしまうのではないかといった批判も存在する 47。実際に、多くのリーグ、特に下位リーグにおいては、依然として財務的な課題を抱えるクラブが少なくないのが現状である 45。例えばイングランドでは、2部リーグに相当するEFLチャンピオンシップのクラブの多くが、UEFAが推奨する賃金対収入比率70%のガイドラインを超過しているとの報告もある 45。
5大リーグの巨大な収益力は、グローバル市場での放映権料(特に国際放映権)と商業収入の展開能力に大きく依存している。プレミアリーグの収益規模 29 とその国際放映権料の巨額さ 31 は、他のリーグを寄せ付けないレベルにある。この圧倒的な収益力によってトップクラスの選手や監督を獲得し、それがさらにリーグの魅力を高め、結果として放映権料や商業収入を増大させるという「勝者総取り」に近い好循環が生まれている。この構造は、リーグ内およびリーグ間の経済格差を助長する側面も持つ。UEFAによるFFPやFSRといった財務規制 46 は、クラブの無謀な支出を抑制する試みではあるが、根本的に収益力の高いクラブが有利な構造を変えるまでには至っておらず、格差はむしろ固定化、あるいは拡大する傾向にあるとの指摘もある 47。
クラブの所有形態もまた、経営戦略やリーグ全体のガバナンスに大きな影響を及ぼしている。ドイツの「50+1ルール」8 は、ファンの影響力を保持し、地域密着と比較的安定した財政運営を志向するクラブ文化を育んでいる。これに対し、外国資本による買収が頻繁に見られるプレミアリーグ 42 などでは、オーナーの投資目的(純粋なビジネスとしての利益追求、国家的な威信発揚、あるいは「スポーツウォッシング」など)によってクラブの経営方針が大きく左右されることがある。これは、短期的な成功を求めるプレッシャーを高め、クラブの長期的な財務健全性やファンとの伝統的な関係性に影響を与える可能性もはらんでいる。
さらに、5大リーグのグローバルブランド戦略は、単に試合映像を世界中に配信するというレベルを超え、デジタルプラットフォームを駆使したファンエンゲージメントや、各地域の文化に合わせたローカライズされたコンテンツ提供を通じて、より深い文化的なつながりを構築しようとする試みへと進化している。各クラブのソーシャルメディアにおける膨大なフォロワー数 35 や、複数言語での情報発信、現地のインフルエンサー(KOL)の活用 38 といった動きは、一方的な情報伝達ではなく、ファンとの双方向のコミュニケーションと共感の醸成を目指していることの表れである。これは、ブランドへの忠誠心を高め、マーチャンダイジング収入やスポンサーシップ契約といった商業的成果に結びつくだけでなく、「文化としてのフットボール」を輸出し、世界中にファンコミュニティを形成することで、長期的な収益基盤を確立しようとする戦略と言える。Jリーグが国際市場での存在感を高めようとする際、この「文化の輸出」という視点は重要な示唆を与えるだろう。
II. Jリーグの現在地:ポテンシャルと克服すべき壁
Jリーグは、1993年の開幕以来、日本サッカーのレベル向上と普及に大きく貢献してきた。近年では、アジアチャンピオンズリーグ(ACL)でのクラブの活躍や、多くの日本人選手が欧州リーグへ移籍するなど、国際的な評価も高まりつつある。しかし、世界のトップリーグである5大リーグと比較した場合、戦術レベル、ビジネス規模、育成システムなど、多くの面で依然として大きな隔たりが存在するのも事実である。
A. 戦術的側面:独自の進化と国際基準への挑戦
1. Jリーグのプレースタイル、戦術的特徴
Jリーグのプレースタイルは、近年著しい進化を遂げている。特筆すべきは、その試合インテンシティとスピードである。英国のスポーツデータ分析企業SkillCornerの分析によれば、Jリーグの試合におけるスピードとインテンシティのレベルは高く、イタリアのセリエAをも上回ると評価されている 28。この事実は、Jリーグでプレーする日本人選手が、フィジカル的な要求が高い欧州のリーグへ移籍した際に、比較的スムーズに適応できる可能性を示唆している。
また、同社のデータは、Jリーグのミッドフィルダーの中に、相手からのプレッシャーが厳しい状況下でもボールを失わずに保持する能力(プレッシング耐性)に長けた選手が存在することも明らかにしている 28。
戦術的な側面では、Jリーグ内でも多様なアプローチが見られる。例えば、ヴィッセル神戸は高強度なプレッシングと素早い攻撃を志向するハイインテンシティな戦術で成功を収め 49、名古屋グランパスは創造性豊かでアグレッシブな攻撃サッカーを展開している 49。また、ポゼッションを重視するチームとカウンターを得意とするチームの対戦 49 や、町田ゼルビアのようにセットプレーを大きな武器とするチーム 49 など、各クラブが独自の戦術的アイデンティティを追求している様子がうかがえる。
データ活用の動きも進んでおり、選手評価や戦術分析にデータ分析を用いるクラブが増えている 49。学術研究の分野でも、チームの戦術的フォーメーションを客観的に特定する手法や、攻撃の有効性に影響を与える戦術的・文脈的要因を分析する研究など、Jリーグを対象とした高度な分析が行われている 14。
2. コーチングの質と育成システム:JFAの指針と国際比較
日本サッカー協会(JFA)は、指導者の質的向上を目指し、S級、A級、B級といった段階的なコーチライセンス制度を整備し、各レベルに応じた指導者養成コースを提供している 52。これらの取り組みはアジア諸国からも注目されており、JFAはAFC加盟国の指導者を対象とした国際コーチングコースを定期的に開催し、日本の指導者育成ノウハウをアジア全体に広める活動も行っている 54。
しかし、指導者の絶対数という観点から国際比較を行うと、Jリーグが抱える課題が浮き彫りになる。JFAが公表している資料によれば、プロフェッショナル(S級に相当か)、A級、B級の各ライセンスを保有する指導者の総数、および人口比において、日本はドイツ、スペイン、イタリア、フランス、イングランドといった欧州のサッカー先進国に大きく水をあけられているのが現状である 55。
Table 3: 指導者ライセンス保有者数国際比較(日本 vs 欧州主要国)
| 国 | プロ級 (Pro相当) | A級 (A) | B級 (B+) | 総数 (Total) | 人口当たり (Per Capita) |
| ドイツ | 5,633 | 1,304 | 21,731 | 28,698 | 0.035 |
| スペイン | 9,319 | 13,070 | 2,353 | 24,742 | 0.053 |
| イタリア | 27,430 | 1,556 | 725 | 29,711 | 0.050 |
| フランス | 12,200 | 3,030 | 278 | 15,508 | 0.023 |
| イングランド | 9,548 | 1,190 | 205 | 10,943 | 0.016 |
| 日本 | 6,194 | 1,807 | 498 | 8,499 | 0.007 |
出典: 55。注: 欧州各国の「総数」は出典資料の記載に従ったが、プロ級・A級・B級の単純合計と一致しない場合がある。日本の「プロ級」はS級、「A級」はA級ジェネラル、「B級」はB級と解釈。人口当たりは、各国の総指導者数を総人口で割ったもの。
この表は、Jリーグの戦術レベルや選手育成の質を支えるべき指導者の「量」において、欧州トップ国との間に大きな差があることを明確に示している。この差を埋めることが、Jリーグ全体のレベルアップに向けた重要な課題の一つと言えるだろう。
選手育成に関して、JFAは「Players First!」というモットーを掲げ、目先の勝利よりも選手の将来を見据えた長期的な視点での一貫指導、そして各年代の発育発達段階に応じた適切な指導を行うことを重視している 57。また、「世界基準」を常に意識し、日本人選手が持つ固有の強み(高い技術力、俊敏性、組織的な団結力、勤勉な姿勢、フェアプレー精神など)を最大限に活かした「Japan’s Way」と呼ばれる独自のサッカースタイルの確立を目指している 56。
3. 選手育成の現状:アカデミーと大学サッカーの連携、若手選手の出場機会と成長環境
Jリーグにおける若手選手の育成環境については、いくつかの特徴と課題が指摘されている。国際比較研究によれば、Jリーグは選手の平均年齢が比較的高く、U17、U20、U23といった若年カテゴリーの選手のトップリーグにおける出場機会が、欧州や南米の主要リーグと比較して少ない傾向にある 59。2014年のデータでは、Jリーグ選手の平均年齢は26.85歳であり、U23選手の出場割合は14.01%に留まっていた 59。
Table 4: Jリーグにおける若手選手の出場機会と平均年齢 (2014年シーズン)
| 年齢カテゴリー | 構成比 (%) | 出場割合 (%) |
| U17 | 0.57 | 0.02 |
| U20 | 9.28 | 3.43 |
| U23 | 15.34 | 14.01 |
| 平均年齢 | \multicolumn{2}{c | }{26.85歳} |
出典: 59。構成比はリーグ登録選手中の割合、出場割合は総出場時間中の割合と推察される。
この背景には、「日本独自システム」とも言える、大学サッカーを経由してプロキャリアをスタートさせる選手が多いという日本の選手育成パスウェイの特徴が影響している可能性が指摘されている 59。実際に、中国の研究者からも、日本の学校サッカー(高校・大学)がプロリーグや各年代の代表チームを支える重要な役割を担っているとの分析がなされている 58。
JFA自身もこの点を認識しており、U-12からU-16までの各世代に応じた指導ガイドラインを作成し、全国規模での指導フィロソフィーの共有と、育成年代の強化に取り組んでいる 57。JFAは「世界トップ10」入りという明確な目標を掲げ、世界大会のトレンド分析と、その知見を国内の育成プログラムや指導者養成へフィードバックするというサイクルを重視している 56。
Jリーグクラブもそれぞれアカデミー組織を運営し、U23年代の有望株も輩出してはいるが 49、オランダのアヤックス 20 やポルトガルの強豪クラブ 19 のように、アカデミーで育成した選手を国内外のトップリーグへ高額で移籍させ、その収益を再投資するという明確な育成・移籍モデルがJリーグ全体で確立されているかについては、さらなる詳細な分析が必要である。
4. 日本人選手の欧州移籍:成功事例と課題、欧州リーグでの適応
近年、Jリーグは欧州のクラブにとって魅力的な選手供給市場としての地位を高めつつある。長年にわたりドイツのクラブが日本人選手に注目してきたが、その流れはベルギー、オランダ、イングランド、イタリアといった国々へも拡大している 28。
日本人選手が欧州で成功を収める要因の一つとして、Jリーグで培われる試合インテンシティの高さとスピードが挙げられる。これにより、フィジカル的な要求の高い欧州のサッカーにも比較的スムーズに適応できるケースが見られる 28。
移籍先のリーグとしては、依然としてドイツが最も人気が高いが、ベルギー、スペイン、オランダ、ポルトガルなども主要な目的地となっている 70。多くの場合、5大リーグに次ぐレベルの中堅リーグが、日本人選手にとって欧州でのキャリアをスタートさせる最初のステップとなることが多い 71。
欧州リーグでプレーする日本人選手の数とその活躍(出場時間や成績など)は、日本代表チームのFIFAランキングと正の相関関係があることが研究によって示唆されており、代表強化の観点からも海外移籍は重要な意味を持つ 70。
一方で課題も存在する。Jリーグから欧州へ移籍する選手の年齢は、欧州の一般的な基準と比較してやや高い傾向が見られるとの指摘もある 28。これは、才能ある選手がより若い段階で国際的な競争環境に身を置く機会を逸している可能性を示唆している。
Jリーグが持つ戦術的な強み、例えば試合のインテンシティの高さや一部選手のプレッシング耐性は、国際的にも通用するポテンシャルを秘めている。しかし、そのポテンシャルを最大限に引き出し、欧州トップレベルとの差を縮めていく上では、いくつかの構造的な課題が存在する。若手選手をトップチームへ引き上げ、十分な出場機会を与えるという点では、欧州の育成型リーグと比較して改善の余地が大きい 59。これは、大学を経由してプロになる選手が多いという日本特有の育成パスウェイ 59 とも関連している。同時に、質の高い指導者の絶対数が欧州のサッカー先進国に比べて不足しているという現実 55 も、個々の選手の才能開花やリーグ全体の戦術レベルの向上を制約している可能性がある。これらの要素が複合的に作用し、Jリーグ全体の成長の伸びしろを限定していると言えるだろう。
JFAが掲げる「Japan’s Way」の確立という育成指針 57 は、日本独自の強みを追求するという点で非常に価値がある。しかし、「世界基準」とのギャップを真に埋めるためには、この指針を具体的な育成プログラムに落とし込み、特に育成年代において、より早い段階から国際的な競争経験を積ませること、そして多様な戦術的アプローチに対応できる能力を養うことが不可欠である。フィジカルコンタクトの強さや、目まぐるしく変わる試合展開の中で的確な判断を下す能力など、グローバルな舞台で戦うために求められる要素を、日本の強みを損なうことなくいかにして育成年代から組み込んでいくかが問われる。現状のJリーグにおける若手選手の出場機会の少なさ 59 や、指導者数の国際的な差 55 は、こうした国際基準への適応力を高める上で不利に働く可能性があるため、育成年代から海外の異なるプレースタイルや戦術に触れる機会を積極的に増やしていく必要がある。
日本人選手の欧州移籍は、日本代表チームの強化には確実に貢献している 70。しかし、その成功がJリーグ自体のブランド価値向上や競争力強化に十分に還元されているかという点では、まだ改善の余地がある。多くの選手が欧州へ移籍する一方で 28、Jリーグの収益構造において移籍金収入が、例えばポルトガルやオランダといった欧州の主要な「育成型輸出国」のリーグほど大きな柱となっていない可能性が考えられる(Jリーグ全体の詳細な移籍金収支データは本稿で参照した資料群からは明確ではないが、一部クラブ経営の脆弱性から推測される)。単に選手を「輸出」するだけでなく、その過程で得られる経済的価値や国際的な評価を、リーグ全体の成長へと戦略的に繋げるサイクルを強化する必要がある。近年見られるレッドブルグループによる大宮アルディージャの買収 71 は、海外から見た日本のタレント発掘・育成拠点としてのJリーグへの関心の高まりを示す一方で、国内クラブがその主導権をいかに握り、リーグ全体の利益に繋げていくかという新たな課題も提示している。
B. ビジネス面:成長戦略と構造的課題
Jリーグは、アジアを代表するプロサッカーリーグとしての地位を確立しつつあるが、ビジネス規模や国際的な収益力においては、欧州5大リーグとの間に依然として大きな差が存在する。国内市場への依存からの脱却と、グローバル市場での競争力強化が、今後の持続的な成長に向けた鍵となる。
1. 収益構造分析:国内市場への依存と海外市場開拓の進捗
Jリーグ(公益社団法人日本プロサッカーリーグ)の収益構造を見ると、国内市場、特に放映権料への依存度が高いことがわかる。2023年度のJリーグの経常収益予測は約299億円であり、そのうち公衆送信権料収入(主としてDAZNとの契約によるもの)が約194億円と、全体の約65%を占めている 72。スポンサーシップ収入は約56億円(全体の約19%)、その他収入が約49億円(全体の約16%)と続く 72。GlobalDataのレポートでは、Jリーグ全体の年間スポンサーシップ収入を2364万ドル(2023年、当時のレートで約33億円前後)と推定しており、明治安田生命が長年にわたりタイトルスポンサーを務めている 73。
Jリーグの放映権ビジネスにおいて中核を成すのは、2016年から続くDAZNとのパートナーシップである。2023年3月には、この契約が2033年までの11年間にわたって延長・改定されたことが発表された 73。この新契約はJ1、J2リーグおよび昇格プレーオフの配信をカバーするものであり、報道によれば契約総額は12年間で2239億円(年平均約187億円)に上るとされる 74。この契約には、視聴者数などに応じたインセンティブベースの利益分配モデルが含まれている可能性も指摘されており、DAZNとJリーグ双方の成長に連動する形を目指していると考えられる 74。
国際放映に関しては、DAZNとの契約は主に国内市場を対象としているが、Jリーグは海外市場の開拓にも積極的に取り組んでいる。具体的には、放映権がまだ販売されていない地域(いわゆるダークマーケット)向けにJリーグ公式YouTubeチャンネルでの試合配信を行ったり、アジア、欧州、アフリカなどの各国放送局やプラットフォームと個別に契約を結んだりしている 73。現在、香港、中国、マカオ、オーストラリア、タイ、インドネシア、ドイツ、ナイジェリア、インドといった国々でJリーグの試合が視聴可能となっている 75。
Table 5: Jリーグの主な国際放映状況とDAZN契約概要
| 国・地域 (代表例) | 主要放送局・プラットフォーム | DAZN国内契約期間 | DAZN国内契約総額(報道ベース) |
| 香港 | myTV SUPER, TVB | 2023年~2033年 | 12年間で約2239億円 |
| 中国 | K-BALL, Penguin Sports, Tianjin TV | (11年間) | (年平均 約187億円) |
| オーストラリア | Optus Sport | ||
| タイ | PPTV, SIAMSPORT on AIS Play, BG SPORTS | ||
| ドイツ、スイス等 | Sportdigital | ||
| インド亜大陸 | Fancode | ||
| その他広域 | J.LEAGUE International (YouTube) (放映権未販売地域) |
出典: 国際放映状況は 75、DAZN契約詳細は 73。契約総額は報道に基づくものであり、公式発表ではない点に留意。
この表は、Jリーグが国際的な露出度を高めようと努力していることを示しているが、同時に、最大の収入源である放映権契約が依然として国内中心であることを浮き彫りにしている。
2. 国際戦略とJリーグブランドの価値向上
Jリーグは、2012年以降、アジア諸国(タイ、インドネシア、ベトナムなど)や、遠くはケニア、ブラジルといった国々で国際プロジェクトを展開し、現地のコミュニティやクリエイター、諸団体と協力しながら日本サッカーの魅力を積極的に発信してきた 77。
近年の成長戦略としては、2024年シーズンからJ1、J2、J3の各リーグのクラブ数をそれぞれ20に統一し、リーグカップ戦(YBCルヴァンカップ)もJ1からJ3までの全カテゴリのクラブが参加するトーナメント方式に変更するという大きな改革を断行した 78。この改革は、「60クラブがそれぞれのホームタウンで輝く」ことと、「トップティア(J1)がナショナル(グローバル)コンテンツとして輝く」という2つの成長テーマを掲げ、Jリーグ全体の価値向上を目指すものである 78。
ファンエンゲージメントの強化にも力を入れており、JリーグIDを基盤とした顧客体験の向上(認知促進、興味喚起、スタジアム来訪、リピート率向上、そして定着化)を推進している 79。その結果、2024年シーズンのJリーグ公式戦(リーグ戦・カップ戦合計)の年間総入場者数は、過去最高の1254万人超を記録した 79。2023年シーズンも1096万人超と過去2番目の多さであり、国内での人気は着実に高まっている 80。
しかし、国際的なブランド価値という点では、依然として大きな課題を抱えている。例えば、英国のブランド評価会社Brand Financeが毎年発表している世界のサッカークラブブランド価値ランキング「Football 50」では、レアル・マドリードやマンチェスター・シティといった欧州のメガクラブが上位を独占しており、Jリーグのクラブはトップ50にランクインしていないのが現状である 40。これは、Jリーグブランドの国際的な認知度や商業的価値が、欧州トップクラブと比較してまだ低いことを示唆している。
3. クラブ経営の財務状況:収益性、投資動向、財務的課題
Jリーグクラブの経営状況を見ると、いくつかの構造的な課題が浮かび上がってくる。英国ポーツマス大学などの研究機関による分析では、J1およびJ2に所属するクラブの約半数から75%が倒産リスクに直面している可能性があると指摘されている。特に、J1リーグに長期間在籍したクラブほど財務状況が悪化する傾向が見られるという 81。
多くのクラブが慢性的な赤字体質にあり、親会社からの広告収入や自治体からの支援金などに依存した経営を余儀なくされているケースが少なくない。浦和レッズは2024年度決算で事業収入102億円に対し営業費用98億円と黒字を計上しているが 33、これはJリーグクラブの中でも例外的に大きな事業規模を持つクラブの事例である。日本プロサッカー選手会(JPFA)の指摘によれば、女子プロリーグであるWEリーグでは、多くのクラブが財政的に自立できておらず、選手がサッカー以外の仕事で生計を立てる必要があるという厳しい状況も伝えられている 83。
このような財務的脆弱性の一因として、欧州のリーグで導入されているファイナンシャル・フェアプレー(FFP)や財務持続可能性規則(FSR)のような、クラブの過度な支出を抑制し財務規律を促すための統一的なルールがJリーグには存在せず、累積赤字の許容額などに関する監視が不十分であるとの指摘がある 81。Jリーグは独自のクラブライセンス制度を運用し、クラブ経営の健全化を目指してはいるものの、多くのクラブで財務状況の抜本的な改善には至っていないのが実情である 81。
外国資本の動向としては、2024年8月にオーストリアのレッドブルグループがJ2の大宮アルディージャを買収したことが大きな話題となった。これは、2020年に行われたJリーグの外資規制緩和(外国法人等が議決権の過半数を取得することを可能にするもの)以降で、外国企業がJリーグクラブの経営権を完全に取得した初のケースとなる 71。また、マンチェスター・シティなどを傘下に持つシティ・フットボール・グループも、横浜F・マリノスに少数株主として関与している 71。これらの動きは、Jリーグに対する海外からの投資関心の高まりを示す一方で、今後のリーグ運営やクラブ経営に新たな力学をもたらす可能性もある。
4. インフラ投資の状況:スタジアム、トレーニング施設
Jリーグのインフラ投資に関しては、近年いくつかの進展が見られる。特にスタジアムについては、サンフレッチェ広島が2024年に開業したサッカー専用スタジアム「エディオンピースウイング広島」が、観客動員数の大幅な増加に貢献するなど、成功事例も生まれている 79。しかし、リーグ全体で見ると、欧州トップリーグのクラブが所有・運営する最新鋭のスタジアムと比較した場合、規模、収容能力、そして試合日以外の収益を生み出す多機能性といった面で見劣りするスタジアムが依然として多い可能性がある。
トレーニング施設についても、JFAはナショナルトレーニングセンター(Jヴィレッジなど)を整備し、各年代の代表チームの強化や指導者養成の拠点として活用している 54。しかし、各Jリーグクラブが保有するトレーニング施設のレベルについては、欧州のトップクラブが最新の科学的知見に基づいた施設に多額の投資を行っているのに対し 19、Jリーグクラブの状況はクラブごとの財政状況によって大きく異なると推察される。
Jリーグ(社団法人)自身もインフラ投資の重要性は認識しており、例えば2023年度の予算では「地域露出戦略への投資」として約12億円を計上し、リーグ全体の魅力向上やファンベース拡大に繋がる施策に資金を投じている 72。
5. 選手年俸水準の国際比較と影響
Jリーグでプレーする選手の年俸水準は、欧州5大リーグと比較して著しく低いのが現状である。2019年のデータによれば、Jリーグ選手の平均年俸は約31万5000ドル(当時のレートで約3400万円)であったのに対し、イングランド・プレミアリーグでは約393万ドル(約4億3000万円)、スペイン・ラ・リーガでは約290万ドル(約3億1600万円)と、文字通り桁違いの差が存在した。これは、北米のメジャーリーグサッカー(MLS)の平均年俸(約41万5000ドル、約4500万円)よりも低い水準である 85。
Table 2: Jリーグと欧州主要リーグ・MLSの選手平均年俸比較 (2019年)
| リーグ | 平均年俸 (米ドル) |
| プレミアリーグ | 3,935,197 |
| ラ・リーガ | 2,896,151 |
| セリエA | 1,999,865 |
| ブンデスリーガ | 1,837,613 |
| リーグ・アン | 1,302,342 |
| MLS | 414,803 |
| Jリーグ | 315,043 |
出典: 85。データは2019年時点のもの。
この表が示すように、選手の年俸水準は、リーグの経済力、トップタレントを獲得・維持する能力、そして国際的な競争力を測る上で重要な指標となる。Jリーグがグローバルなタレント市場においてどのようなポジションにいるのか、また選手にとっての魅力度を客観的に示している。
さらに、クラブの収益に占める選手人件費の割合を見ると、2017年のデータでは、Jリーグの選手報酬対収益比率は27%であり、MLSの28%とほぼ同水準であった。これは、欧州トップリーグの多くが52%から72%の範囲にあることと比較すると著しく低い 86。この背景には、それぞれの国においてサッカーが国内トップスポーツであるか否かが影響している可能性が指摘されている。つまり、国内でサッカーの人気が他のスポーツと比較して絶対的でない国では、リーグの質に対する一般的な期待値が相対的に低く、結果としてクラブオーナーが選手報酬に多額の資金を投じるプレッシャーが弱いのではないか、という分析である 86。
Jリーグの収益構造は、依然として国内市場、特にDAZNからの放映権料に大きく依存している実態が明らかになった 72。国際的な収益源の多角化は喫緊の課題であり、海外放映は進められているものの 75、プレミアリーグが国際放映権だけで年間10億ユーロ以上を稼ぎ出す現状 31 と比較すると、その規模には雲泥の差がある。この国内依存体質が、Jリーグ全体の成長ポテンシャルを限定し、海外のビッグクラブとの資金力の差を埋められない大きな要因となっている。
また、多くのJリーグクラブが抱える財務的な脆弱性、例えば倒産リスクや慢性的な赤字体質といった問題 81 は、欧州で導入されているFFP(ファイナンシャル・フェアプレー)やFSR(財務持続可能性規則)のような統一的な財務規律が存在しないこと 81、そして日本特有のクラブ所有構造(親企業や地方自治体による支援を前提とした経営)と深く関連している可能性がある。このような構造が、クラブの自律的な収益力向上へのインセンティブを弱め、積極的な長期投資や大胆な経営戦略の実行を妨げている面は否定できない。レッドブルグループによる大宮アルディージャの買収 71 のような外国資本の本格的な参入は、こうした既存の構造に一石を投じる可能性を秘めている。
Jリーグの選手年俸水準の低さ 85、そしてクラブ収益に占める人件費比率の低さ 86 は、一見するとクラブ経営の健全性を示しているように見えるかもしれない。しかし、これは同時に、世界トップクラスのタレントを獲得し、あるいは国内の有望な選手をリーグに引き留めておくことを困難にし、結果としてリーグ全体の国際競争力やエンターテインメントとしての魅力を削いでいる可能性がある。「鶏が先か、卵が先か」という議論にも通じるが、リーグの魅力を高めるための質の高い選手への投資なくして、放映権料やスポンサーシップ収入の大幅な増加を期待することは難しい。この比較的低い投資レベルが、国際市場におけるJリーグの成長を遅らせる一因となっている可能性は十分に考えられる。
III. 5大リーグへの道:ギャップ分析とJリーグ飛躍への提言
Jリーグが欧州5大リーグに伍していくためには、戦術レベルの向上とビジネス規模の拡大という両輪を力強く回転させる必要がある。現状のギャップを正確に把握し、具体的な改革案と戦略的優先順位を設定することが、Jリーグ飛躍の鍵となる。
A. 戦術レベル向上へのロードマップ
1. 世界基準のタレントを継続的に輩出する育成システムの改革案
Jリーグから世界基準のタレントを継続的に輩出するためには、育成システム全体の抜本的な改革が求められる。まず、Jリーグにおける若手選手の出場機会の少なさ 59 は深刻な課題であり、これを改善するために、リーグやクラブレベルでの具体的な目標設定が必要である。例えば、U21(あるいはそれ以下の年齢層)の選手の最低出場時間枠を設けることや、若手育成に特化したリーグ(リザーブリーグや育成リーグ)の創設を本格的に検討することも一案であろう。
アカデミーと大学サッカーとの連携強化と、それぞれの役割分担の明確化も重要である。日本の大学サッカーは高いレベルを維持しており、多くのプロ選手を輩出してきた実績があるが 59、トッププロを目指す特に才能ある選手に対しては、より早期からプロクラブのアカデミーで専門的かつ集中的な指導を受けられるようなパスウェイを整備する必要がある。現状では大学経由の選手がJリーガーの平均年齢を押し上げる一因となっている可能性も指摘されており 59、トップタレントの早期プロ化を促進する仕組み作りが望まれる。
育成型リーグとして世界的に評価の高いオランダのエールディビジ(特にアヤックス 20)やポルトガルのプリメイラ・リーガ(ベンフィカ、ポルト、スポルティングCPなど 19)の成功事例を徹底的にベンチマークし、Jリーグ版のタレント輩出・輸出戦略を構築すべきである。これには、国内外のスカウティング体制の抜本的な強化、育成年代からの国際試合経験の付与(海外遠征や国際大会への積極的参加)、そして選手の海外移籍交渉における専門的なノウハウの蓄積と共有が含まれる。
これらの改革は、JFAが掲げる育成指針「Japan’s Way」57 との整合性を保ちつつ進められるべきである。つまり、日本人選手の持つ技術的な優位性や規律性といった強みを活かしながらも、フィジカル面の強化や戦術的な柔軟性といった、グローバルな舞台で戦うために不可欠な要素を育成年代から効果的に組み込んでいく必要がある。
2. 指導者の質的・量的向上と戦術研究体制の強化
選手の才能を最大限に引き出し、リーグ全体の戦術レベルを向上させるためには、指導者の質的・量的な向上が不可欠である。前述の通り、日本のプロレベルおよびA級・B級ライセンス保有指導者数は、欧州主要国と比較して著しく少ない 55。この差を埋めるため、JFAはコーチ養成プログラムを一層拡充し、受講機会を大幅に拡大する必要がある。特に、トップレベルの指導を担うS級(プロ級)やA級ライセンス指導者の数を増やすことが急務である。
指導者の「質」の向上も同様に重要である。最新の戦術理論、スポーツ科学、データ分析手法などを習得するための継続的な研修制度を整備し、指導者が常に学び続けられる環境を提供しなければならない。海外の先進的な指導者との交流プログラムや、海外クラブ・協会への研修派遣などを積極的に促進することも有効であろう。JFAがアジア諸国向けに開催している国際コーチングコース 54 の内容をさらに深化させ、国内指導者向けのトップレベル研修としても活用することが考えられる。
さらに、リーグや協会が主導する形で、Jリーグの戦術トレンド分析、海外リーグの戦術研究、データ分析手法の開発といった活動を行う専門的な戦術研究機関を設立するか、既存の関連機関を強化することも検討すべきである。大学や研究機関との連携を深め、学術的な知見をサッカーの現場に積極的に取り入れていく姿勢が求められる 14。
3. リーグ全体の競争レベルと戦術的多様性を高める施策
リーグ全体の競争レベルと戦術的な多様性を高めることも、Jリーグの魅力向上に不可欠である。現在Jリーグでは、外国籍選手の登録・出場枠に制限が設けられているが(J1では5人まで同時出場可能、別途アジア提携国枠あり 87)、より質の高い外国人選手や指導者を積極的に招聘しやすくするために、これらの枠規定を見直すことも一つの選択肢として検討すべきである。優れた外国人選手の存在は、リーグ全体のレベルアップに貢献し、日本人選手にとっても大きな刺激となる。また、多様なバックグラウンドを持つ指導者が増えることは、戦術的な多様性の促進にも繋がる。
クラブ間の競争均衡策についても議論が必要である。Jリーグは現在、理念強化配分金制度などを導入し、クラブ間の財政格差是正と競争力向上を図っているが 72、将来的にはサラリーキャップ制度や、それを超過した場合に課徴金を課すラグジュアリータックス制度の導入など、より踏み込んだ戦力均衡策と財務健全化策を両立させるための議論も必要になるかもしれない。ただし、その際には欧州のFFP制度が抱える課題や教訓 47 も十分に踏まえる必要がある。
選手のコンディションを維持し、常に質の高いパフォーマンスを引き出すためには、試合スケジュールの最適化も重要な要素である。過密日程の緩和や、十分なシーズンオフ期間の確保は、選手の心身の回復と成長に不可欠である。2026年からのJリーグのシーズン秋春制への移行 83 は、気候面でのメリットに加え、国際的なカレンダーとの整合性を高め、選手の移籍や代表活動をスムーズにするという点でも、この一環と捉えることができる。
Jリーグの戦術レベル向上は、個々のクラブの努力だけに依存するのではなく、リーグ全体の「育成エコシステム」の改革が不可欠である。若手選手の登用に対するインセンティブ設計の導入、指導者の量的・質的な拡充、そして伝統的に選手の供給源となってきた大学サッカーとの連携のあり方の見直しなどが含まれる。現状では、若手選手のトップチームでの出場機会が欧州の育成型リーグと比較して少ないこと 59、そして指導者の絶対数が欧州のサッカー先進国に比べて不足していること 55 が、リーグ全体のタレントプール拡大と戦術的進化を阻害する要因となっている。大学サッカーからの選手供給 59 は、これまで一定の役割を果たしてきたが、世界のトップレベルを目指すのであれば、より早期からのプロフェッショナルな育成環境の提供が重要となる。オランダのアヤックス 20 やポルトガルの主要クラブ 19 のように、アカデミーからトップチームへ、そして才能ある選手は海外のトップリーグへとスムーズに繋がる明確な育成パイプラインを、Jリーグ全体として戦略的に構築していく必要がある。
Jリーグが真に戦術レベルで5大リーグに迫るためには、単なる欧州の「模倣」ではなく、「日本独自の強みを活かした上での戦術的革新」こそが求められる。JFAが掲げる「Japan’s Way」57 という理念を、具体的な戦術論へと昇華させ、それをピッチ上で実践できる質の高い指導者を育成し、そのフィロソフィーを若手選手に浸透させるという一貫したサイクルを確立することが極めて重要である。Jリーグの試合で見られる高いインテンシティ 28 や、日本人選手が持つ技術レベルの高さは、国際的にも評価されている。これらを基盤とし、日本人選手の特性(例えば、俊敏性、規律性、協調性、献身性など)を最大限に活かす独自の戦術モデルを開発し、進化させていくことが重要となる。単に欧州で流行している戦術を後追いするのではなく、例えば、より高度に組織化されたプレッシングシステム、緻密なパスワークとコンビネーションプレーのさらなる追求、セットプレーにおける戦術的深化など、日本ならではの強みを発揮できる分野で世界をリードするような独創的な戦術を生み出すポテンシャルを探求すべきである。
B. ビジネス規模拡大と国際競争力強化への戦略
1. 海外放映権収入とグローバルスポンサーシップ獲得の最大化戦略
Jリーグのビジネス規模を拡大し、国際競争力を強化するためには、海外からの収益、特に放映権収入とグローバルスポンサーシップの獲得を最大化する戦略が不可欠である。現状、Jリーグの国際放映は、国内向けのDAZN契約が主軸であり、海外市場に対しては一部の国・地域との個別契約やYouTubeでの無料配信といった形に留まっている 75。これに対し、欧州5大リーグ、特にプレミアリーグは、国際放映権だけで年間10億ユーロ(約1600億円)を超える巨額の収入を得ている 31。この差は歴然であり、Jリーグが本気で5大リーグに迫るためには、国際放映権販売戦略を抜本的に見直し、高度化する必要がある。
具体的には、まずターゲット市場(特に成長著しいアジア市場、次いで欧米のコアなサッカーファン層)を明確に特定し、それぞれの市場の視聴者ニーズに合わせた魅力的なコンテンツ制作と配信戦略を強化することが求められる。これには、単なる試合中継だけでなく、質の高いハイライト映像、選手や監督のドキュメンタリー、リーグの魅力を伝える特集番組などを多言語で制作し、多様なプラットフォームを通じて配信することが含まれる。
リーグ全体の競争力を向上させると同時に、国内外で注目を集めるスター選手を育成・獲得し、彼らを中心とした魅力的なストーリーテリングを通じて、Jリーグコンテンツそのものの「商品価値」を高めていく努力も欠かせない。
グローバルスポンサーの獲得に向けては、Jリーグブランドの国際的な認知度向上と並行して、多国籍企業をターゲットとした魅力的なスポンサーシップパッケージを開発する必要がある。特に、Jリーグが持つアジア市場における地理的・文化的な強みを活かし、アジア地域への事業展開を目指すグローバル企業に対して、Jリーグとのパートナーシップがもたらす価値を具体的に訴求していくべきである。現在のJリーグ(社団法人)のスポンサー収入は約56億円 72、リーグ全体でも約35億円程度と推定されるが 73、これを大幅に増加させるポテンシャルは十分にあるはずだ。
2. Jリーグブランドの国際的価値を高めるための具体的なマーケティング・広報戦略
Jリーグブランドの国際的な価値を高めるためには、より戦略的かつ具体的なマーケティング・広報活動を展開する必要がある。まず、「アジアNo.1リーグ」としてのブランドイメージを国内外で確固たるものにすることが重要である。そのためには、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)においてJリーグクラブが継続的に好成績を収め、アジアのクラブランキングで常に上位を独占するような状況を目指すべきである。
デジタル戦略の強化も不可欠だ。公式ウェブサイトやソーシャルメディアアカウントの多言語対応を徹底し、海外のサッカーインフルエンサーとの連携を深め、魅力的な動画コンテンツ(試合ハイライト、選手インタビュー、クラブやリーグの特集映像など)をグローバルに配信していく必要がある。ラ・リーガがアジア市場でKOL(キーオピニオンリーダー)を積極的に活用している事例 38 は参考になるだろう。
また、海外、特にアジアの戦略的重点市場において、Jリーグのプレシーズンマッチやファン参加型のイベント、コーチングクリニックなどを積極的に開催し、現地のファンと直接的な接点を増やすことも有効である。これにより、Jリーグへの関心を高め、ロイヤルティを醸成することができる。
さらに、Jリーグが持つ独自性を積極的に発信していくことも重要だ。日本文化(例えば、礼儀正しさ、スタジアムの安全性や清潔さ、地域社会との密接な連携、独自の応援スタイルなど)とサッカーを融合させたユニークな観戦体験を、海外のファンにとって魅力的な「体験型コンテンツ」として訴求していくべきである。
3. クラブ経営の安定化と戦略的投資を促すリーグ全体のガバナンス改革
Jリーグ全体の持続的な発展と国際競争力強化のためには、個々のクラブ経営の安定化と、将来に向けた戦略的投資を促すためのリーグ全体のガバナンス改革が不可欠である。多くのJリーグクラブが依然として財務的な課題を抱えている現状 81 を踏まえ、欧州のFFP(ファイナンシャル・フェアプレー)やFSR(財務持続可能性規則)の事例を参考にしつつも、Jリーグの実情に即した独自の財務健全化ルールの導入を本格的に検討すべきである。これには、クラブの支出総額に対する制限や、許容される債務上限の設定などが含まれうる。このようなルールを導入することで、クラブ経営の透明性を高め、無謀な投資を抑制し、持続可能なクラブ経営と計画的な将来投資(育成、インフラなど)を促進する効果が期待できる。
現在の理念強化配分金制度 72 に加え、リーグ全体の競争力向上や魅力向上に具体的に貢献したクラブに対して、より大きなインセンティブを与えるような収益分配モデルの最適化も検討すべきである。これにより、各クラブがリーグ全体の価値向上に向けて積極的に取り組む動機付けとなる。
近年見られる外国資本によるJリーグクラブへの投資(例:レッドブルグループによる大宮アルディージャ買収 71)の動きを踏まえ、クラブの持続的な発展とJリーグが掲げる理念に合致する形での外国資本受け入れに関する明確なガイドラインや審査基準を整備することも重要である。これにより、リーグ全体の健全な成長を損なうことなく、外部からの投資を有効に活用することが可能になる。
さらに、オランダ、ポルトガル、ベルギーといった、いわゆる「タレント輸出型リーグ」のクラブ経営モデルを徹底的に研究することも有益である。これらのリーグのクラブが、いかにしてアカデミーで育成した選手を欧州のビッグクラブへ高額な移籍金で売却し、その資金をクラブ経営の安定化やさらなる育成・強化への再投資に繋げ、国際的な競争力を維持しているのか。その成功事例とノウハウを学ぶことは、Jリーグクラブの経営戦略にとって大きな示唆を与えるだろう 19。
4. 魅力的なスタジアム体験とインフラ整備による収益機会の創出
スタジアムを中心としたインフラ整備は、ファンエンゲージメントの向上と新たな収益機会の創出に不可欠である。サッカー専用スタジアムの建設や既存スタジアムの改修をリーグ全体で支援し、観戦環境の劇的な向上を目指すべきである。サンフレッチェ広島の「エディオンピースウイング広島」79 のような成功事例を参考に、ピッチと観客席の距離が近く、臨場感あふれる観戦体験を提供できるスタジアムを増やすことが求められる。また、多様なニーズに応えるためのホスピタリティ施設の充実や、試合日以外にもスタジアムを活用したイベント開催(コンサート、地域イベントなど)による収益機会の多角化も重要である。
スタジアムにおける最新テクノロジーの導入も積極的に進めるべきである。高速なスタジアムWi-Fi環境の整備、完全キャッシュレス化、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)といった技術を活用した新しい観戦体験の提供などは、特に若い世代のファンエンゲージメントを高め、新たな収益源を生み出す可能性を秘めている。
トップレベルの選手育成とチーム強化のためには、最新鋭のトレーニング施設の整備も不可欠である。クラブがこうした施設へ戦略的に投資できるよう、リーグとして何らかの支援策やインセンティブを設けることも検討に値する。
Jリーグのビジネス規模拡大戦略においては、国内市場のさらなる深耕と並行して、特にアジア市場における「No.1リーグ」としての確固たる地位を確立し、そこを足がかりとしてグローバルなニッチ市場を開拓していくという二段階戦略が現実的である。5大リーグとの直接的な経済規模での体力勝負は、現時点では困難と言わざるを得ない。Jリーグの現在の収益規模 72 は、5大リーグのそれ 29 に遠く及ばず、国際放映権料においても同様の構図が見られる 31。しかし、アジア地域に目を向ければ、Jリーグは地理的・文化的な近接性、AFCチャンピオンズリーグでの実績などを背景に、他国のリーグに対して優位性を築くことが可能である。Jリーグが推進する国際戦略 77 やアジア諸国のサッカー協会・リーグとの連携強化 54 は、まさにこの方向性を示唆している。アジアにおける「No.1ブランド」としての地位を確立した後、欧米のコアなサッカーファン層に対して、「アジア発の質の高い、ユニークなサッカーリーグ」としてその魅力を訴求していく戦略が考えられる。
クラブ経営の安定化なくして、リーグ全体の持続的な成長と国際競争力の強化はあり得ない。Jリーグ版のFFP(ファイナンシャル・フェアプレー)やFSR(財務持続可能性規則)の導入は、一部クラブに見られる短期的な成績追求のための無謀な投資を抑制し、育成やインフラ整備といった長期的な視点での戦略的投資を促す健全な土壌を作るために不可欠である。Jリーグクラブの多くが倒産リスクを抱えているという指摘 81 は、この問題の深刻さを物語っている。これは、目先の勝利のために過度な支出を行うクラブが存在しうること、そしてそれをリーグレベルで効果的に抑制する強力な財務規律が欠けていることを示唆している。欧州で導入されているFFP/FSR 46 は完璧な制度ではないかもしれないが、クラブ経営に一定の規律をもたらしたことは事実である。Jリーグも、各クラブが身の丈に合った健全な経営を行い、育成やインフラといった「未来への投資」に持続的に資金を振り向けられるような仕組みを導入する必要がある。
Jリーグが国際的なブランド価値を高めていくためには、単に「良いサッカー」を提供するだけでなく、「Jリーグならではの物語性(ストーリーテリング)」と「日本文化との魅力的な融合」を戦略的に打ち出し、海外のファンとの間に感情的なエンゲージメントを深めていく必要がある。5大リーグのトップクラブは、その長い歴史、数々のスター選手、そして地域社会との深い絆といった「物語」をブランドの重要な構成要素としている 35。Jリーグも、各クラブが持つ独自の歴史や地域性、選手の成長物語といった要素を丹念に掘り起こし、それらを魅力的なコンテンツとして国内外に発信していくことが重要である。また、日本のスタジアムが持つ独特の雰囲気、日本ならではのおもてなしの心、そして世界的に見ても高いレベルにある安全性といった要素は、他のリーグとの明確な差別化要因となり得る。これらを前面に押し出すことで、海外のサッカーファンにとって「一度は訪れてみたいリーグ」「安心して楽しめるリーグ」としての魅力を高めることができるだろう。DAZNとの連携 74 を通じた質の高いコンテンツ制作も、この「物語性」と「文化発信」を強化する上で重要な役割を果たすはずだ。
C. Jリーグ独自の価値創造と差別化戦略
1. 「アジアNo.1リーグ」の地位を確固たるものとし、その先のビジョンをどう描くか
Jリーグが世界で独自の地位を築くためには、まず「アジアNo.1リーグ」としての評価を絶対的なものにすることが最優先課題である。そのためには、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)において、Jリーグクラブが毎年のように優勝争いを演じ、アジアのクラブランキングで常に上位を独占するような圧倒的な強さを示す必要がある。
さらに、アジア全体のサッカーハブとしての機能を強化することも重要である。アジア各国の有望な若手選手が、キャリアの初期段階で最初に目指すリーグとしての地位を確立し、Jリーグで実力を磨き、そこから欧州のトップリーグへとステップアップしていくという成功事例を数多く生み出すことが求められる。Jリーグが設けている提携国枠 87 を戦略的に活用し、アジア各国のタレントを発掘・育成する仕組みを強化することも有効だろう。
また、アジア市場への貢献とリーダーシップの発揮も重要である。アジア各国のリーグの発展を支援するために、指導者の派遣や運営ノウハウの共有といった協力関係を深化させ 54、AFC(アジアサッカー連盟)との連携を一層強化することで、アジアサッカー全体のレベルアップに貢献する。その中でJリーグが主導的な役割を果たすことで、自ずとリーグの国際的な評価も高まるはずだ。
2. 日本サッカーの独自性と文化を活かしたグローバルな魅力の発信
Jリーグがグローバルな市場で独自の魅力を発信するためには、日本サッカーの独自性と日本文化の特性を最大限に活かすことが鍵となる。JFAが掲げる日本サッカースタイル「Japan’s Way」、すなわち高い技術力、厳格な規律、優れた組織力、そしてフェアプレー精神といった要素 57 を、リーグ全体で高いレベルで体現し、それを戦術的な魅力として世界に発信していく必要がある。
スタジアムでの観戦体験においても、日本ならではの差別化を図るべきである。安全で快適、そして家族連れでも安心して楽しめるスタジアム環境の提供、地域社会とクラブが一体となった温かい雰囲気の醸成、そして世界でもユニークとされる日本の応援文化などを、海外のサッカーファンにとって魅力的な「体験型コンテンツ」として積極的にアピールしていく。
選手や監督の人間的な魅力も、Jリーグブランドを形成する上で重要な要素である。日本人選手や監督が持つ真摯な姿勢、高いプロフェッショナリズム、そして彼らが紡ぎ出す感動的なストーリーなどを積極的に国内外に発信し、多くの人々の共感を呼ぶようなブランドイメージを構築していくことが望まれる。
Jリーグが国際的な舞台で独自のポジショニングを確立するためには、5大リーグを性急に模倣したり、経済規模で直接的に競争したりするのではなく、まず「アジアの盟主」としての地位を絶対的なものにすることが現実的な戦略となる。その上で、そこから派生する独自の価値、例えば「アジア市場へのゲートウェイとしての機能」や「アジア人選手のショーケースとしての役割」を、欧州や世界のサッカー界に対して明確に提供していくことが重要である。5大リーグとの経済規模の差(Table 1参照)はあまりにも大きく、短期間でこれを埋めることは極めて困難である。しかし、アジア地域に目を向ければ、Jリーグは競技レベルの高さ、運営ノウハウの蓄積、そして地理的・文化的な近接性といった点で、他国のリーグに対して明確な優位性を築くことができる。この「アジアNo.1」というブランドは、欧州のクラブやグローバル企業にとって、成長著しいアジア市場へのアクセスポイントとして、また将来有望なアジア人タレントの発掘・獲得ルートとして、非常に魅力的に映る可能性がある。Jリーグが推進している国際戦略 77 やアジア諸国のサッカー協会・リーグとの連携強化 54 は、まさにこの方向性を示していると言える。
Jリーグのグローバルな差別化は、単にピッチ上の競技レベルの高さだけでなく、「日本ならではのサッカー文化と観戦体験」を総合的に提供することによって達成されるべきである。サッカーの試合内容そのものは、ある程度普遍的な要素を持つが、それを取り巻く環境や「体験」は、開催される国や地域の文化によって大きく異なる。Jリーグは、海外のファンが安心して試合を楽しむことができる安全なスタジアム環境、日本的なきめ細やかなホスピタリティ、地域社会に深く根差したクラブのあり方、そして世界的に称賛されるフェアプレー精神といった要素を前面に押し出すことで、「クリーンで、安全で、かつ質の高いサッカーを提供するリーグ」という独自のブランドイメージを国際的に構築することができる。これは、特にファミリー層や、より洗練されたスポーツエンターテインメント体験を求める層に対して、強い訴求力を持つ可能性がある。他のリーグにはない、この独自の付加価値こそが、Jリーグの国際的な競争力の源泉となり得る。
IV. 結論:Jリーグの未来を拓くために
本分析を通じて、Jリーグが欧州5大リーグに迫るために克服すべき課題と、そのポテンシャルを活かすための成長機会が明らかになった。Jリーグの未来を拓くためには、これらの課題に真摯に向き合い、戦略的かつ継続的な取り組みを進めていく必要がある。
A. 本分析から明らかになった主要課題と成長機会の総括
主要課題:
- 経済規模の格差: 欧州5大リーグとの間には、収益規模、特に放映権料や商業収入において圧倒的な差が存在する 29。
- 国内市場への高い収益依存: Jリーグの収益は依然として国内市場、とりわけDAZNからの放映権料に大きく依存しており、国際的な収益源が十分に確立されていない 72。
- クラブ経営の財務的脆弱性: 多くのJリーグクラブが財務的な課題を抱え、倒産リスクや赤字体質からの脱却が急務である 81。
- 若手選手の出場機会の相対的な少なさ: 欧州の育成型リーグと比較して、Jリーグでは若手選手のトップチームでの出場機会が限られている 59。
- 指導者の量的不足: プロレベルの指導者の絶対数が、欧州のサッカー先進国に比べて著しく少ない 55。
- 国際的なブランド認知度の低さ: Jリーグおよびそのクラブの国際的なブランド価値は、欧州トップクラブと比較して依然として低い 40。
成長機会:
- アジアNo.1リーグとしての地位確立とアジア市場でのリーダーシップ発揮: 地理的・文化的な近接性を活かし、アジア市場におけるJリーグのプレゼンスをさらに高める。
- 高い試合インテンシティと技術レベルを活かした魅力的なサッカーの提供: Jリーグの戦術的な強み 28 をさらに磨き上げ、国内外のファンを魅了する。
- DAZNとの長期契約を活かした国内基盤強化とコンテンツ価値向上: 安定的な放映権収入を基盤に、国内ファンベースの拡大と、より魅力的なリーグコンテンツの制作・配信を推進 74。
- 日本独自のサッカー文化とスタジアム体験のグローバルな訴求: 安全性、ホスピタリティ、地域密着といった日本ならではの価値を、海外に向けて発信する。
- 育成システムの改革による国内外へのタレント供給力の強化: アカデミーと大学サッカーの連携見直しや指導者育成を通じて、より多くの優秀な選手を輩出し、国内外の移籍市場での価値を高める。
B. 5大リーグに伍していくための段階的目標設定と戦略的優先順位
Jリーグが5大リーグに迫るという壮大な目標を達成するためには、現実的な段階的目標を設定し、戦略的な優先順位に従ってリソースを配分していく必要がある。
- 短期目標(~5年):
- アジアNo.1リーグとしての地位の絶対化: AFCチャンピオンズリーグでのJリーグクラブによる継続的な上位進出と、アジア市場におけるJリーグ放映権の価値向上を目指す。
- 国内クラブの財務健全化の推進: Jリーグ版FFP(ファイナンシャル・フェアプレー)制度の段階的な導入と運用を開始し、クラブ経営の透明性と持続可能性を高める。
- 若手育成システムの基盤強化: アカデミーへの支援策強化、指導者養成プログラムの拡充による指導者数の増加、若手選手の出場機会増加に向けた具体的な施策の導入。
- 中期目標(~10年):
- Jリーグブランドの国際的認知度の大幅向上: アジア市場での確固たる地位を足掛かりに、欧米市場のニッチなサッカーファン層へもJリーグの魅力を浸透させる。
- 育成からのタレント輸出モデルの確立: 育成した選手を欧州の中堅リーグやトップリーグへ安定的に供給し、そこから得られる移籍金収入をリーグやクラブのさらなる発展に再投資するサイクルを確立する。
- リーグ全体の収益規模の着実な拡大: 国際放映権料、グローバルスポンサーシップ、マーチャンダイジングなど、海外からの収益比率を高める。
- 長期目標(10年~):
- 5大リーグに次ぐ「第6のリーグ」としての国際的評価の獲得: 競技レベル、ビジネス規模、ブランド力において、世界のトップリーグ群の一角として認識されることを目指す。
- 一部トップクラブの欧州強豪との伍して戦えるレベルへの到達: Jリーグのトップクラブが、欧州の主要大会(FIFAクラブワールドカップなど)で、5大リーグの強豪クラブと互角以上に渡り合える実力を持つ。
- 日本代表チームのFIFAランキングトップ10常入りとワールドカップ優勝争いへの貢献: Jリーグのレベルアップを通じて、日本代表チームの国際競争力を飛躍的に向上させる。
C. 持続的な発展と国際的評価向上のための、リーグ、クラブ、協会一体となった継続的取り組みの重要性
Jリーグがこれらの目標を達成し、持続的な発展と国際的評価の向上を実現するためには、Jリーグ(社団法人)、Jリーグに所属する各クラブ、そして日本サッカー協会(JFA)が、明確なビジョンと具体的な戦略を共有し、それぞれが担うべき役割を責任を持って果たしていくことが不可欠である。
目先の試合結果や短期的な収益に一喜一憂するのではなく、長期的な視点に立った地道な改革と戦略的な投資を継続していく覚悟が求められる。国内外の成功事例や失敗事例から謙虚に学び、常に自己変革を恐れない進取の気性が重要となる。
そして何よりも、ファン、スポンサー、地域社会といった、Jリーグを支える全てのステークホルダーとの間に強固な信頼関係を築き、彼らと共にJリーグの未来を創造していくという姿勢が、最も重要であると言えるだろう。
Jリーグが5大リーグに「迫る」という道のりは、決して平坦ではない。経済規模で単純に追いつくことを性急に目指すのではなく、まず「質の高い、独自の価値を持つリーグ」としてのブランドを国内外で確立し、その結果として経済的な成長と国際的な評価が自然とついてくる、という好循環を生み出す戦略が現実的である。5大リーグの現在の経済規模は、それぞれの国の長いサッカーの歴史、巨大な国内市場、そしてグローバル化の波に乗った先行者利益など、多くの複合的な要因によって形成されており、Jリーグが短期間でこれにキャッチアップすることは極めて困難である。むしろ、Jリーグが持つポテンシャル、すなわち日本人選手の高い技術レベルや規律性、試合のインテンシティの高さ、スタジアムの安全性、そしてアジアにおける地理的・文化的な優位性などを最大限に活かし、独自の魅力を徹底的に磨き上げることで、世界のサッカー市場においてニッチながらも確固たる国際的地位を築くことが先決である。その質の高さが世界に認められれば、放映権料やスポンサーシップといった経済的な価値も、自ずと高まっていくはずだ。
Jリーグの挑戦は、単に一国のサッカーリーグとしての成功に留まるものではない。それは、日本のスポーツ文化全体の国際化を牽引し、ひいては地域社会の活性化や国際交流の促進にも貢献しうる、壮大なプロジェクトとしての意義を持つ。その成功のためには、サッカー界内部の努力はもちろんのこと、政府、教育機関、産業界など、日本社会全体の深い理解と積極的な支援が不可欠となる。JFAが掲げる「Japan’s Way」57 や「スポーツを通じて豊かな国づくりに貢献する」といった理念は、サッカーという競技の枠を超えた社会的な価値を持つ。これらの壮大な目標を達成するためには、Jリーグや各クラブ、JFAだけでなく、教育現場におけるサッカーの振興、企業によるスポーツ支援文化のさらなる醸成、そして政府によるスポーツインフラへの戦略的投資など、より広範なレベルでの連携と支援体制の構築が求められるのである。Jリーグの未来は、サッカー界だけでなく、日本社会全体の未来とも深く結びついていると言っても過言ではない。
引用文献
- A Central Element of Europe’s Football Ecosystem: Competitive Intensity in the “Big Five”, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3097
- Premier League Data Analysis 2024/25 – Vertical Progression, 5月 10, 2025にアクセス、 https://totalfootballanalysis.com/data-analysis/premier-league-vertical-progression-transitional-threat-data-analysis-statistics
- Analysis: Fast breaks are back in style as tactics evolve – Premier League, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.premierleague.com/news/4272576#!
- Tactical trends and stylistic diversity across Europe’s top five leagues – Analytics FC, 5月 10, 2025にアクセス、 https://analyticsfc.co.uk/blog/2024/06/14/tactical-trends-and-stylistic-diversity-across-europes-top-five-leagues/
- Why Spanish Soccer Is Different: 3 Reasons That Set It Apart – Spain Rush-SPF, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.spanishprofootball.com/why-spanish-soccer-is-different-3-reasons-that-set-it-apart
- Tiki-Taka – Football Tactics Explained, 5月 10, 2025にアクセス、 https://the-footballanalyst.com/tiki-taka-football-tactics-explained/
- Champions League Quarter-Finals Preview: Tactical Trends, Data …, 5月 10, 2025にアクセス、 https://soccerment.com/it/champions-league-quarter-finals-preview-tactical-trends-data-insights-key-absences/
- The Tactical Evolution of German Football: How the Bundesliga is Innovating, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.getfootballnewsgermany.com/2024/the-tactical-evolution-of-german-football-how-the-bundesliga-is-innovating/
- Head Coach Analysis Tactical Analysis – Report, Stats, News, 5月 10, 2025にアクセス、 https://totalfootballanalysis.com/head-coach-analysis/page/19
- Igor Tudor – Juventus – Tactical Analysis – The Football Analyst, 5月 10, 2025にアクセス、 https://the-footballanalyst.com/igor-tudor-juventus-tactical-analysis/
- Serie A Tactical Analysis – Report, Stats, News, 5月 10, 2025にアクセス、 https://totalfootballanalysis.com/competitions/serie-a
- Luis Enrique: Tactical Breakdown : r/psg – Reddit, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/psg/comments/14rkxov/luis_enrique_tactical_breakdown/
- Francesco Farioli – Ajax – Tactical Analysis – The Football Analyst, 5月 10, 2025にアクセス、 https://the-footballanalyst.com/francesco-farioli-ajax-tactical-analysis/
- The principles of tactical formation identification in association football (soccer) — a survey, 5月 10, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11836022/
- Tactical analysis of direct attack from the English Premier League and Spanish La Liga, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2024.1473311/full
- Demographic analysis of professional football club coaches, 5月 10, 2025にアクセス、 https://football-observatory.com/Demographic-analysis-of-professional-football
- How strong is Serie A compared to other leagues? i.e Bundesliga, Premier League : r/seriea – Reddit, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/seriea/comments/1h6r9xn/how_strong_is_serie_a_compared_to_other_leagues/
- Champions Report 2025 – Football Benchmark, 5月 10, 2025にアクセス、 https://footballbenchmark.com/w/champions-report-2025
- Investing in Portuguese football: a prime spot for Multi-Club Ownership?, 5月 10, 2025にアクセス、 https://footballbenchmark.com/w/investing-in-portuguese-football-a-prime-spot-for-multi-club-ownership-
- Ajax’s Youth Academy: The Secret Behind World-Class Talent, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.ajaxdaily.com/2025/ajaxs-youth-academy-the-secret-behind-world-class-talent/
- FC Porto: The world’s most efficient “Moneyball” football club – Statathlon, 5月 10, 2025にアクセス、 https://statathlon.com/fc-porto-the-worlds-most-efficient-football-club-based-on-the-moneyball-model/
- FIFA Forward, 5月 10, 2025にアクセス、 https://inside.fifa.com/official-documents/annual-report-2023/around-fifa/fifa-forward
- Global report on development activities (2016-2022) Across the first two cycles of the FIFA Forward Development Programme, approximately USD 2.8 billion was made available for investment in our 211 member associations, as well as in the – Inside FIFA, 5月 10, 2025にアクセス、 https://inside.fifa.com/advancing-football/fifa-forward/fifa-forward-report
- Reports – CIES Football Observatory, 5月 10, 2025にアクセス、 https://football-observatory.com/-Reports-
- Reports – CIES Football Observatory, 5月 10, 2025にアクセス、 https://football-observatory.com/-Reports?nb=90&debut_articles_popup_jma=78
- Reports – CIES Football Observatory, 5月 10, 2025にアクセス、 https://football-observatory.com/-Reports?nb=96&debut_articles_popup_jma=78
- Reports – CIES Football Observatory, 5月 10, 2025にアクセス、 https://football-observatory.com/-Reports?nb=66&debut_articles_popup_jma=72
- SCOUTED: Scouting the J.League – SkillCorner, 5月 10, 2025にアクセス、 https://skillcorner.com/blog/j-league
- Deloitte’s Annual Review of Football Finance, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.deloitte.com/fi/fi/about/press-room/annual-review-of-football-finance-2024.html
- Annual Review of Football Finance: Europe’s Premier Leagues …, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.deloitte.com/uk/en/services/financial-advisory/research/annual-review-of-football-finance-europe-premier-league.html
- List of Premier League overseas broadcasters – Wikipedia, 5月 10, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Premier_League_overseas_broadcasters
- [Deloitte] Annual Review of Football Finance 2024 – Leagues with the Highest Revenue: 1. PL, 2. BL, 3. LL, 4. SA, 5. L1 : r/soccer – Reddit, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/soccer/comments/1do98u5/deloitte_annual_review_of_football_finance_2024/
- Management Information | Club | URAWA RED DIAMONDS OFFICIAL WEBSITE, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.urawa-reds.co.jp/en/club/managdata.php
- Real Madrid break billion Euro revenue record to top the 2025 Deloitte Football Money League, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.deloitte.com/uk/en/about/press-room/deloitte-football-money-league.html
- From Football Club to Global Brand – SBI Barcelona, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.sbibarcelona.com/news/from-football-club-to-global-brand
- Initernationlisation and branding strategy: A Case of the English Premier League’s success in an emerging market | Request PDF – ResearchGate, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/330983596_Initernationlisation_and_branding_strategy_A_Case_of_the_English_Premier_League’s_success_in_an_emerging_market
- LUISS Guido Carli “Game changers: Exploring Business Models of Premier League football”, 5月 10, 2025にアクセス、 https://tesi.luiss.it/37960/1/248901_CALIENNO_LEONARDO.pdf
- Building brand awareness in Asia: A LaLiga case study – World Football Summit, 5月 10, 2025にアクセス、 https://worldfootballsummit.com/building-brand-awareness-in-asia-a-laliga-case-study/
- U.S. Marketing & Fan Activation Manager – The Premier League – iSportConnect, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.isportconnect.com/marketplace/u-s-marketing-fan-activation-manager-the-premier-league/
- Football | Reports – Brandirectory, 5月 10, 2025にアクセス、 https://brandirectory.com/reports/football
- Which club is on top of football’s brand value league table? Here are answers, 5月 10, 2025にアクセス、 https://m.economictimes.com/news/international/us/which-club-is-on-top-of-footballs-brand-value-league-table-here-are-answers/articleshow/111839931.cms
- Full article: How did football ownership become from an emotional …, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23750472.2025.2457665?af=R
- Form of ownership by league | Download Scientific Diagram, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/figure/Form-of-ownership-by-league_fig1_344375289
- Full Text ( Final Version , 506kb ) – Erasmus University Thesis Repository, 5月 10, 2025にアクセス、 https://thesis.eur.nl/pub/30740/BA-Thesis-S.Candel.docx
- Financial sustainability and governance of English football – House of Commons Library, 5月 10, 2025にアクセス、 https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cdp-2025-0041/
- Effectiveness of UEFA’s regulation for European football financial management: A comprehensive systematic review and meta-analysis – PMC, 5月 10, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11620070/
- A Review of Competitive Balance in European Football Leagues before and after Financial Fair Play Regulations – ResearchGate, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/368911110_A_Review_of_Competitive_Balance_in_European_Football_Leagues_before_and_after_Financial_Fair_Play_Regulations
- Full article: The league system, competitive balance, and the future of European football, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23750472.2022.2137056
- J1 League Tactical Analysis – Report, Stats, News, 5月 10, 2025にアクセス、 https://totalfootballanalysis.com/competitions/j1-league
- Passing Networks and Tactical Action in Football: A Systematic Review – PubMed Central, 5月 10, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7559986/
- Tactical critical thinking program on the tactical efficiency index, declarative and procedural knowledge in male soccer players: a case study – Frontiers, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2024.1469347/full
- Licensed Coaches Training Course|JFA Official Coaches, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.jfa.jp/eng/coach/official/training.html
- Comparative Study on Football Professionalism Development Histories in China and Japan – ARC Journals, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.arcjournals.org/pdfs/ijspe/v3-i3/5.pdf
- JFA International Coaching Course | Social action programme, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.jfa.jp/eng/social_action_programme/international_exchange/coaching.html
- Japan’s Way – Our National Football Philosophy – JFA, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.jfa.jp/japansway/japan’sway_en_221219.pdf?ref=thinkcurve.co
- Japan’s Way – Our National Football Philosophy – JFA, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.jfa.jp/japansway/japan’sway_en_221219.pdf
- Concept of players development|Players Development|JFA, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.jfa.jp/eng/youth_development/outline/
- A study on the inspiration of Japan’s football youth training model on the cultivation of school football reserves in China – Type of the Paper (Article – UMK, 5月 10, 2025にアクセス、 https://apcz.umk.pl/QS/article/download/56551/40687/167590
- International Comparison between the J-League Division 1 and European/South American Top League Players Regarding Participation Opportunities, According to the Generation – ResearchGate, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/318871033_International_Comparison_between_the_J-League_Division_1_and_EuropeanSouth_American_Top_League_Players_Regarding_Participation_Opportunities_According_to_the_Generation
- A study on the inspiration of Japan’s football youth training model on the cultivation of school football reserves in China – ResearchGate, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/387074033_A_study_on_the_inspiration_of_Japan’s_football_youth_training_model_on_the_cultivation_of_school_football_reserves_in_China
- How Ajax’s Academy Conquered European Football – YouTube, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=2vBxwHpTrC4
- Column: The pitfalls when evaluating a successful academy– there is a holistic financial model that tells a significant story – Twenty First Group Limited, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.twentyfirstgroup.com/column-the-pitfalls-when-evaluating-a-successful-academy-there-is-a-holistic-financial-model-that-tells-a-significant-story/
- A world class academy in professional football: The case of Ajax Amsterdam – NTNU Open, 5月 10, 2025にアクセス、 https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2684735
- Primeira Liga Tactical Analysis – Report, Stats, News, 5月 10, 2025にアクセス、 https://totalfootballanalysis.com/competitions/primeira-liga
- FC Porto’s Commitment to the Intelligent Use of Data | Teamworks, 5月 10, 2025にアクセス、 https://teamworks.com/blog/fc-portos-commitment-to-the-intelligent-use-of-data/
- The Geostrategy of Youth Player Recruitment in Portuguese Clubs – ResearchGate, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/387953848_The_Geostrategy_of_Youth_Player_Recruitment_in_Portuguese_Clubs
- Player migration in Portuguese football: a game of exits and entrances – Estudo Geral, 5月 10, 2025にアクセス、 https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/80674/1/Nolasco%20-%202018%20-%20Player%20migration%20in%20Portuguese%20football.pdf
- Sporting is a slight favorite to win the title, Porto is a slight favorite for 3rd place. – Reddit, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/PrimeiraLiga/comments/1k9g4cp/sporting_ligeiramente_favorito_ao_t%C3%ADtulo_porto/?tl=en
- A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Master’s degree in Management from the Nova School of – RUN, 5月 10, 2025にアクセス、 https://run.unl.pt/bitstream/10362/177654/1/CORPORATE_REPORT_FOR_SPORT_LISBOA_E_BENFICA_S_BOARD_ANALYSIS_FINANCIAL_PERFORMANCE_AND_INFRASTRUCTURES.pdf
- East Asian expatriate football players and national team success: Chinese, Japanese, and South Korean players in Europe (2000–2024) – PMC – PubMed Central, 5月 10, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11779897/
- What’s driving Red Bull’s ambition to invest in Japanese football …, 5月 10, 2025にアクセス、 https://footballbenchmark.com/w/what-s-driving-red-bull-s-ambition-to-invest-in-japanese-football-
- 2023 Financial Report – Jリーグ, 5月 10, 2025にアクセス、 https://aboutj.jleague.jp/seasonreview2023/en/management152/
- Business of the J.League 2023 – Property Profile, Sponsorship and Media Landscape, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.globaldata.com/store/report/j-league-business-analysis/
- Assessing DAZN’s J.League play four years on – SportsPro, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.sportspro.com/insights/analysis/dazn-japan-j-league-rights-strategy-martyn-jones-interview/
- Where to watch J.LEAGUE Broadcast | J.LEAGUE, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.jleague.co/broadcast/
- J-League | SportBusiness, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.sportbusiness.com/organisation/j-league/
- Official International Website of Japan Football League. – J.LEAGUE, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.jleague.co/aboutj/
- League Structure and Competition Format from 2024 … – Jリーグ, 5月 10, 2025にアクセス、 https://aboutj.jleague.jp/corporate/en/pressrelease/post.php?code=IMPORTRELEASE00076173&y=&m=&q=
- J.LEAGUE SEASON REVIEW 2024 | Jリーグ シーズンレビュー2024 | 2024 Season to-C Marketing Strategy, 5月 10, 2025にアクセス、 http://aboutj.jleague.jp/seasonreview2024/en/fanengagement/fa_1/
- 2023 Season to-C Marketing Strategy – Jリーグ, 5月 10, 2025にアクセス、 https://aboutj.jleague.jp/seasonreview2023/en/fanengagement132/
- New study reveals significant risk of bankruptcy for Japanese professional football clubs | University of Portsmouth, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.port.ac.uk/news-events-and-blogs/news/new-study-reveals-significant-risk-of-bankruptcy-for-japanese-professional-football-clubs
- Spending money is like water soaking into the sand: anticipating financial distress in Japanese professional football clubs | Emerald Insight, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jaar-12-2023-0394/full/pdf?title=spending-money-is-like-water-soaking-into-the-sand-anticipating-financial-distress-in-japanese-professional-football-clubs
- Player-driven JPFA looking to build on impressive progress … – FIFPro, 5月 10, 2025にアクセス、 https://fifpro.org/en/who-we-are/fifpro-members/fifpro-asiaoceania/player-driven-jpfa-looking-to-build-on-impressive-progress
- Deloitte Football Money League 2025, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.deloitte.com/uk/en/services/financial-advisory/analysis/deloitte-football-money-league.html
- MLS Payrolls vs. the World : r/MLS – Reddit, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/MLS/comments/cghy8y/mls_payrolls_vs_the_world/
- CBA Talk: Comparing MLS Player Salaries to Leagues Around the …, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.americansocceranalysis.com/home/2019/4/22/cba-talk-comparing-mls-player-salaries-to-leagues-around-the-world
- J1 League – Wikipedia, 5月 10, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/J1_League
- Financial analysis of big-5 league clubs’ transfers, 5月 10, 2025にアクセス、 https://football-observatory.com/IMG/sites/mr/mr77/en/
- Case: Eredivisie – Maileon, 5月 10, 2025にアクセス、 https://maileon.com/solutions/cases/case-eredivisie/
- Professional Dutch football invests millions in social projects – Eredivisie, 5月 10, 2025にアクセス、 https://eredivisie.eu/news/professional-dutch-football-invests-millions-in-social-projects/
- Optimization of the Number of Teams and Format of the Portuguese Football Primeira Liga Industrial Engineering and Management – Fenix, 5月 10, 2025にアクセス、 https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1689244997262057/Dissertacao%20Carlos%20Marques%2076556.pdf
- The Belgian Pro League: A Hidden Gem of European Soccer, 5月 10, 2025にアクセス、 https://soccerwizdom.com/2025/01/14/the-belgian-pro-league-a-hidden-gem-of-european-soccer/
- Top 10 Football Leagues in the World – 2025 – Flick, 5月 10, 2025にアクセス、 https://soccerflick.com/blogs/for-parents/top-10-football-leagues-in-the-world-2025
- Punching above their weight? Examining player development pathways in Belgian football: a retrospective analysis | Emerald Insight, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/sbm-04-2024-0035/full/pdf?title=punching-above-their-weight-examining-player-development-pathways-in-belgian-football-a-retrospective-analysis
- CIES Football Observatory – Posts, 5月 10, 2025にアクセス、 https://football-observatory.com/-posts-?debut_articles_popup_jma=66&nb=66
- Talent Development and Labour Market Integration: The Case of EU Football Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson and Lars Persson, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.ifn.se/media/2tfhhzy4/wp1126.pdf
- FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF NETHERLANDS EREDIVISIE WITH THE HELP OF RESAMPLING METHODS | Request PDF – ResearchGate, 5月 10, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/318315107_FINANCIAL_PERFORMANCE_ANALYSIS_OF_NETHERLANDS_EREDIVISIE_WITH_THE_HELP_OF_RESAMPLING_METHODS
- Punching above their weight? Examining Player Development Pathways in Belgian Football: A Retrospective Analysis – Sheffield Hallam University Research Archive, 5月 10, 2025にアクセス、 https://shura.shu.ac.uk/34357/3/Bullough-Punching%20AboveTheir%20Weight%28AM%29.pdf
- Punching above their weight? Examining player development pathways in Belgian football, 5月 10, 2025にアクセス、 https://repository.uantwerpen.be/docstore/d:irua:26442