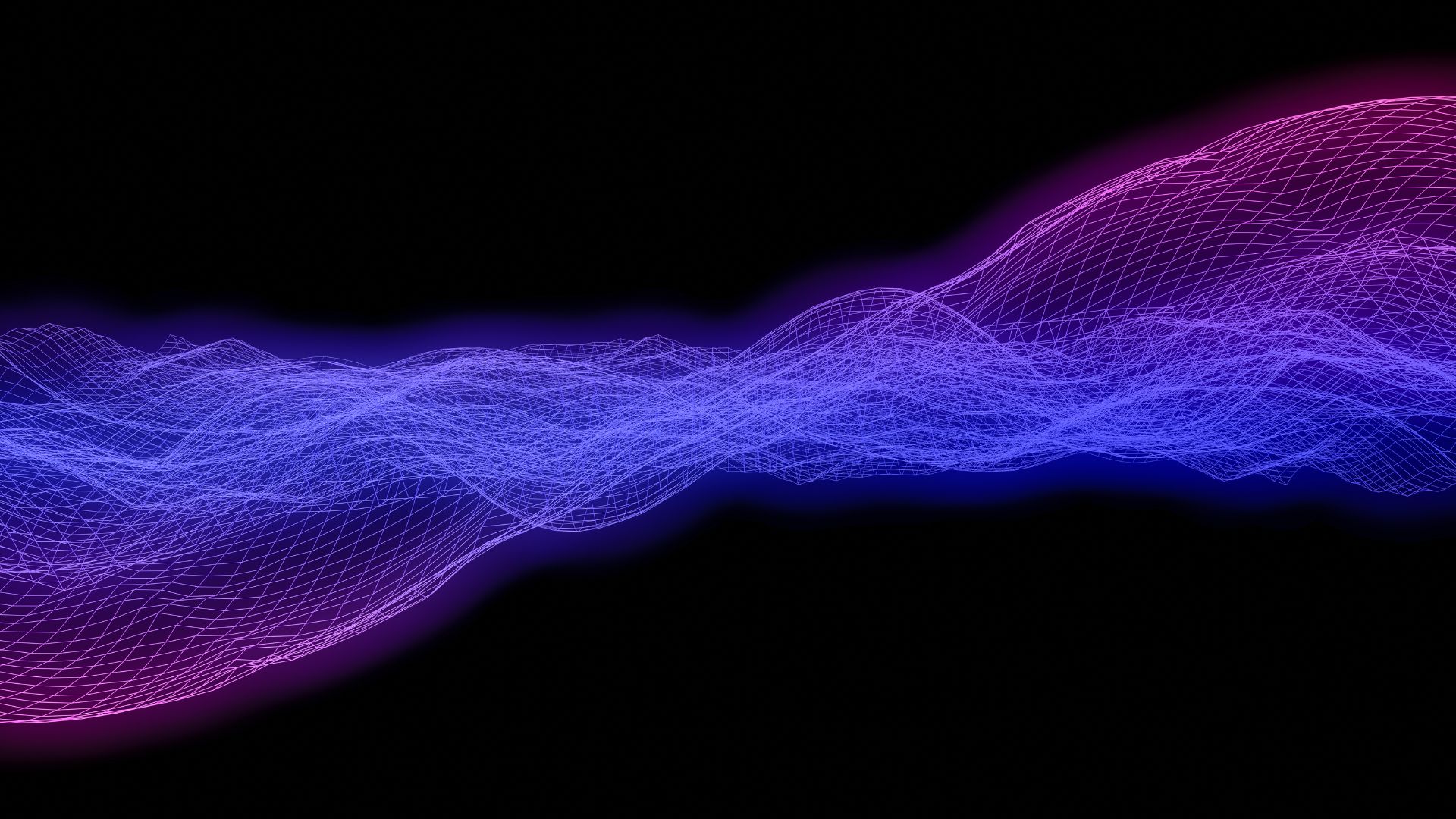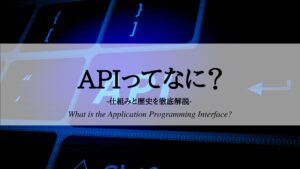I. はじめに:科学研究の新たな潮流「DeSci」とは?
現代の科学研究は、目覚ましい進歩を遂げる一方で、そのシステム自体がいくつかの深刻な課題に直面しています。これらの課題が、科学の発展を遅らせ、イノベーションの可能性を狭めているとの指摘は少なくありません。こうした中、Web3技術を活用して科学研究のあり方を根本から変革しようとする新たな潮流、「DeSci(Decentralized Science:分散型科学)」が大きな注目を集めています。本記事では、主に国外の文献や事例を参照しつつ、DeSciがこれからの科学のスタンダードとなり得るのか、その可能性と課題を日本語でわかりやすく解説します。
A. 伝統的科学が直面する壁:なぜ今、変革が求められるのか?
伝統的な科学研究システム(TradSci)は、長年にわたり人類の知のフロンティアを拡大してきましたが、今日、いくつかの構造的な問題を抱えています。例えば、研究資金の獲得競争は熾烈を極め、資金提供のプロセスは不透明で時間がかかり、有望な研究プロジェクトの実に80~90%がヒト臨床試験に至る前に頓挫する「死の谷」と呼ばれる現象が存在します 1。資金提供機関や産業界のインセンティブが、短期的な成果や収益性の高い研究に偏りがちなことも、基礎研究や長期的な視点が必要な研究を困難にしています 1。
また、研究成果へのアクセスも大きな課題です。多くの学術論文は高額な購読料を要求するペイウォールの背後にあり、特に資金の乏しい地域の研究者や一般市民が最新の知見に触れることを困難にしています 2。論文出版プロセス自体も時間がかかり、査読者の労力はしばしば無償で提供されているにもかかわらず、出版社は巨額の利益を上げています 3。さらに、研究結果の再現性の低さ、いわゆる「再現性の危機」も科学全体の信頼性を揺るがす問題として認識されています 1。これらの問題は、科学研究の効率性、透明性、公平性を損ない、イノベーションの速度を低下させる要因となっています。
このような背景から、伝統的な科学システムの限界を克服し、よりオープンで効率的、かつ信頼性の高い科学研究のあり方が模索されるようになりました。DeSciは、まさにこの変革の要請に応える形で登場したのです。DeSciの出現は、単に新しいツールが利用可能になったというだけでなく、数十年にわたり科学を支配してきた権力構造や経済モデルに挑戦する、より広範な哲学的転換を反映していると言えます。これは、Web3の他の応用分野で見られる分散化と仲介者排除の動きと軌を一にするものです。伝統的科学では大学、出版社、資金提供機関といった中央集権的な組織がゲートキーパーとしての役割を担ってきましたが 5、DeSciはDAOやブロックチェーンといった分散型技術を用いてこれらの仲介者を迂回することを目指しており 7、これはDeFiが伝統的銀行に、NFTが伝統的アート市場に挑戦する構図と類似しています。この大きな流れの中でDeSciを捉えることが、その本質を理解する上で重要です。
B. DeSci(分散型科学)の定義と核心的ビジョン
DeSci(分散型科学)とは、ブロックチェーン、DAO(分散型自律組織)、NFT(非代替性トークン)、スマートコントラクトといったWeb3技術を活用し、科学研究のプロセスをよりオープン、透明、協調的、かつ民主的なものに変革しようとするムーブメントです 2。その核心的なビジョンは、中央集権的な機関への依存を減らし、研究資金調達の多様化、研究データの自由な共有、査読プロセスの透明化、知的財産の新たな管理方法の確立などを通じて、科学的発見を加速し、その恩恵をより広範な人々にもたらすことにあります 7。
学術的な定義としては、Lukas Weidenerらによる研究が参考になります。彼らはDeSciを「分散型台帳技術(DLT)、Web3、暗号通貨、分散型自律組織(DAO)などの技術的・インフラ的進歩を活用し、許可不要でオープンかつ包括的な参加を可能にし、科学プロセスの集団的ガバナンス、公平なインセンティブ付与、無制限のアクセス、共有所有権、透明な資金調達を促進する、協調的かつ分散的な科学へのアプローチ」と定義しています 10。この定義は、DeSciが目指す多面的な変革を的確に捉えています。
DeSciが広く普及した場合、科学者のキャリアパスや求められるスキルセットが根本的に変わる可能性も秘めています。研究専門知識に加え、分散型ガバナンス、トークノミクス、コミュニティエンゲージメントに関する理解が価値を持つようになるかもしれません。DeSciはDAOによるガバナンスや資金調達 7、トークンによるインセンティブ設計 7 といった新しいメカニズムを伴います。このようなエコシステムで効果的に活動するには、科学的スキル以上のものが求められ、研究者はこれらの新しいシステムを理解する必要が生じます。結果として、研究者はより起業家的になり、これらの新しい科学コミュニティの構築と運営に積極的に参加することが求められるようになるかもしれません。これは、科学者の育成や専門能力開発における潜在的な進化を示唆しています。
C. 本記事の目的と構成
本記事の目的は、DeSciがこれからの科学のスタンダードとなり得るのかという問いに対し、主に国外の文献や事例を基に、その可能性と課題を多角的に検討し、日本の読者に向けて包括的かつ分かりやすい解説を提供することです。
記事の構成は以下の通りです。まず、DeSciを支える核心技術について解説し、次に伝統的科学の課題とDeSciによる変革の可能性を具体的に掘り下げます。続いて、DeSciが科学にもたらす主な利点、国外の具体的なプロジェクト事例を紹介し、DeSciが直面する課題についても議論します。さらに、専門家の視点を通じてDeSciの将来像を探り、最後に結論として、DeSciが科学の未来のスタンダードとなり得るかについての考察を述べます。
II. DeSciを支える核心技術
DeSciムーブメントは、既存の科学研究システムに変革をもたらすために、いくつかの革新的なWeb3技術を基盤としています。これらの技術は、それぞれが独自の機能を提供しつつ、相互に連携することでDeSciエコシステムの全体像を形成しています。
A. ブロックチェーン:透明性と不変性の基盤
ブロックチェーン技術は、DeSciの根幹をなすインフラです。分散型台帳とも呼ばれるブロックチェーンは、取引記録やデータを暗号技術によって連鎖的に記録し、ネットワーク参加者間で共有・検証する仕組みです。これにより、記録された情報は改ざんが極めて困難(不変性)となり、誰でもその内容を検証できる高い透明性が確保されます 7。DeSciにおいては、研究データ、論文、査読プロセス、資金の流れなどをブロックチェーン上に記録することで、研究活動全体の信頼性とトレーサビリティを向上させることが期待されています 7。例えば、研究データとその変更履歴が不変的に記録されることで、データの捏造や不正な操作を防ぎ、研究の再現性を高めることに貢献します 8。
B. DAO(分散型自律組織):コミュニティ主導の意思決定とリソース管理
DAO(Decentralized Autonomous Organization:分散型自律組織)は、特定の管理者や中央集権的な意思決定機関を持たず、プログラムされたルール(スマートコントラクト)とコミュニティの投票によって運営される組織形態です 7。DeSciにおいてDAOは、研究者、資金提供者、一般市民など、多様なステークホルダーが参加し、研究プロジェクトの選定、資金配分、運営方針の決定などを民主的かつ透明に行うためのプラットフォームとして機能します 2。DAOの参加者は、多くの場合、ガバナンストークンを保有することで意思決定プロセスに参加する権利を得ます。これにより、従来の研究機関や資金提供団体といった中央集権的なゲートキーパーを介さずに、ボトムアップでの研究テーマ設定やリソース管理が可能になると期待されています 7。
C. NFT(非代替性トークン):知的財産(IP-NFT)と研究成果の新たな形
NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)は、ブロックチェーン上で発行される、それぞれが固有の価値を持つデジタル資産です。アート作品やコレクターズアイテムの所有権証明に用いられることで広く知られるようになりましたが、DeSciの文脈では、特に知的財産(IP)の表現と管理において新たな可能性を提示しています 7。IP-NFTは、研究論文、データセット、特許、あるいは研究プロジェクト自体といった知的財産をトークン化したものです。これにより、研究者は自身の成果に対する所有権を明確にし、その権利をブロックチェーン上で安全に取引したり、ライセンスしたり、あるいは資金調達の担保としたりすることが可能になります 7。IP-NFTは、研究成果の流動性を高め、研究者への新たな収益機会を提供するとともに、研究プロジェクトへの早期投資を促進する手段としても注目されています。
D. スマートコントラクト:自動化された契約実行とインセンティブ設計
スマートコントラクトは、ブロックチェーン上で事前に定義された条件に基づいて自動的に実行されるプログラムです。契約の履行や取引の執行を仲介者なしに、かつ透明性の高い形で行うことができます 9。DeSciにおいては、スマートコントラクトが様々なプロセスを自動化し、効率化するために活用されます。例えば、研究資金の分配において、特定の研究マイルストーンが達成された場合に自動的に資金が拠出されるようにプログラムしたり 1、査読者への報酬支払いを査読完了後に自動的に行ったりすることが可能です 7。また、IP-NFTを通じたライセンス契約の条件をスマートコントラクトに組み込み、収益の分配を自動化することも考えられます。これにより、契約履行の透明性が高まり、管理コストの削減にも繋がります。
E. トークン:貢献へのインセンティブとエコシステム内経済
トークン(暗号通貨)は、DeSciエコシステム内での価値交換やインセンティブ付与、ガバナンス参加のための主要な手段です 7。研究者は、データセットの提供、論文の執筆、査読への参加、研究成果の検証といった貢献に対してトークンで報酬を得ることができます 7。これにより、従来は評価されにくかった活動にも経済的なインセンティブが与えられ、研究コミュニティ全体の活性化が期待されます。また、特定のDeSciプロジェクトのガバナンストークンを保有することで、そのプロジェクトの運営方針に関する投票権を得たり、プロジェクトの将来的な成功によるトークン価値の上昇から利益を得たりすることも可能です。トークンは、DeSciプラットフォームの持続可能性を支える経済的基盤としての役割も担います。
これらの核心技術は、それぞれが独立して機能するのではなく、相互に連携し合うことでDeSciという新しい科学の形を構築しています。ブロックチェーンは信頼性と不変性の基盤を提供し 7、その上でスマートコントラクトがルールやプロセスを自動実行します 9。DAOはスマートコントラクトを利用してコミュニティの意思決定や資金管理を行い 7、IP-NFTのようなデジタル資産の所有権や移転もスマートコントラクトとブロックチェーンによって管理されます 7。そして、トークンがこのシステム全体におけるインセンティブ付与やガバナンスの手段として機能し、DAOによってスマートコントラクトを介して管理されることもあります 7。DeSciの力は、これら構成要素の相乗効果から生まれるのです。
さらに、これらの技術によって可能になる透明で詳細な追跡は、従来の引用数に偏重した評価軸を超えて、科学的影響力を測定する新しい方法論を生み出す可能性があります。データセットへの貢献、査読の質(公開されている場合)、研究結果の検証成功など、これら全てがトークン化されたり、オンチェーンで記録されたりすることで、新たな評価指標が生まれるかもしれません 3。これにより、研究者や研究成果をより多角的に評価する、より健全な学術文化が醸成されることも期待されます。
III. 伝統的科学(TradSci)の課題とDeSciによる変革の可能性
伝統的な科学研究システム(TradSci)は、資金調達、データ共有、査読・出版、知的財産管理、国際協力といった多くの側面で課題を抱えています。DeSciは、これらの課題に対して、Web3技術を活用した革新的な解決策を提示し、科学研究のあり方を根本から変革する可能性を秘めています。
A. 研究資金調達:中央集権型からの脱却と新たなモデル
TradSciの課題: 伝統的な研究資金調達は、政府機関や大規模な財団といった限られた中央集権的な供給源に大きく依存しており、そのプロセスは不透明で時間がかかり、偏りが生じやすいという問題があります 1。資金提供者は商業的可能性や継続的な収益を生み出す能力のある研究を優先する傾向があり、これが革新的なアイデアや基礎研究への投資を抑制する可能性があります 1。特に、基礎研究から実用化への橋渡しとなるトランスレーショナルリサーチの段階では、資金不足により多くの有望なプロジェクトが「死の谷」で頓挫しています 1。助成金の審査プロセスも不透明で、同じ提案でも審査委員会によって結果が異なることがあり、審査員のバイアスや審査の遅れも指摘されています 1。
DeSciの解決策: DeSciは、このような中央集権的な資金調達モデルからの脱却を目指し、より民主的で多様な資金調達メカニズムを提案しています。DAOを通じたコミュニティベースの資金調達では、研究コミュニティ自身が支援すべきプロジェクトに投票し、資金の流れを透明に追跡できます 2。二次ファンディング(Quadratic Funding)や遡及的公共財ファンディング(Retroactive Public Goods Funding)といった新しいモデルも導入されつつあります 7。また、研究プロジェクトやその知的財産をトークン化し、IP-NFTとして販売することで、初期段階の研究に流動性を提供し、幅広い投資家からの資金調達を可能にします 11。これにより、研究者は伝統的な資金提供機関の意向に左右されにくくなり、より多様な研究テーマに取り組む機会を得られる可能性があります。実際、VitaDAOは900万ドル以上の資金を調達し 11、DAOによる資金調達の可能性を示しています。DeSciにおけるDAOは、科学的資金調達を自動化し、「死の谷」を埋める役割を果たすと期待されています 5。
B. データ共有と再現性:「死の谷」を越えて
TradSciの課題: 科学研究におけるデータの共有は、しばしば限定的です。研究データは個々の研究機関やデータベースにサイロ化され、アクセスが制限されていることが少なくありません 5。データ共有に対するインセンティブの欠如や、ネガティブな結果の公表を避ける出版バイアスも、研究の透明性を損ねています 1。これらの要因が複合的に作用し、研究結果の再現性・追試可能性の低下、いわゆる「再現性の危機」を引き起こしています。ある報告によれば、動物実験のわずか6%しかヒトでの反応に置き換えられないとされ、研究手法のわずかな違いが結果の再現を不可能にすることもあります 1。
DeSciの解決策: DeSciは、ブロックチェーン技術を活用して、研究データの透明性とアクセス性を飛躍的に向上させることを目指します。IPFSやArweaveのような分散型ストレージに研究データを保存し、ブロックチェーン上にその記録(ハッシュ値など)を刻むことで、データの完全性と来歴を保証します 2。これにより、誰でもデータにアクセスし、検証することが可能になります。また、データの共有や研究結果の検証・再現に貢献した研究者に対してトークンによるインセンティブを与えることで、積極的なデータ公開と再現研究を促進します 8。研究手法や実験計画もブロックチェーンに記録することで透明性を高め、成功しなかった実験結果も含めてすべての研究成果をオープンアクセスで公開するプラットフォームも構想されており、これにより出版バイアスを低減し、科学的知見の全体像をより正確に把握できるようになることが期待されます 1。
C. 査読と学術出版:透明性とインセンティブの導入
TradSciの課題: 伝統的な学術出版システムは、査読プロセスの遅延、不透明性、査読者の潜在的なバイアスといった問題を抱えています 5。査読者の多くは無償でその専門知識と時間を提供しているにもかかわらず、大手出版社は高額な論文掲載料(APC)や購読料によって莫大な利益を上げています 3。このようなシステムは、知識へのアクセスを制限し、特に資金力のない研究者や機関にとって大きな障壁となっています 14。
DeSciの解決策: DeSciは、査読と学術出版のプロセスに透明性と適切なインセンティブを導入することを目指します。査読の履歴や内容をブロックチェーン上に記録することで、プロセスの透明性を高め、責任の所在を明確にします 14。査読者や編集者に対してトークンで報酬を支払うことで、その貢献を正当に評価し、査読の質と速度の向上を促します 3。DeSci Publishのようなプラットフォームは、数週間での迅速な査読や、査読結果をプレプリントと共に公開するオプションを提供しています 17。また、中央集権的な出版社を介さずに研究成果を直接公開できる分散型出版プラットフォームや、購読料も掲載料も無料の「ダイヤモンドオープンアクセス」モデルも登場しています 18。ResearchHubがNature誌で取り上げられた事例では、RSCトークンによる有償査読モデルが紹介され、一部の科学者からは好意的に受け止められています 15。
D. 知的財産(IP):IP-NFTによる新たなアプローチ
TradSciの課題: 伝統的な科学研究において、知的財産(特許など)はしばしば大学や企業といった機関によって管理・所有され、その取得プロセスは複雑で費用もかかります 6。また、IPが科学的知見のオープンな共有や協力を妨げる要因となることもあります 4。
DeSciの解決策: DeSciは、IP-NFT(知的財産非代替性トークン)という新しいアプローチを提案しています。IP-NFTは、研究論文、データセット、特許などの知的財産権をブロックチェーン上でトークン化したものです。これにより、研究者は自身のIPに対する所有権をより直接的に持ち、その権利を分散型市場で取引したり、ライセンスしたり、資金調達に活用したりすることが容易になります 7。IP-NFTは、IPの流動性を高め、評価や価値移転を透明化し、さらにはIPの分割所有やコミュニティによる共同所有といった新たな形態も可能にすると期待されています 11。例えば、BioDAOの一つであるHairDAOがDAOとして初めて科学特許を申請した事例は、DAOベースのIP管理の可能性を示しています 20。
E. 国際共同研究の促進
TradSciの課題: 科学は本質的に国境のない活動ですが、伝統的な研究システムでは、国際共同研究が組織の壁、地理的な距離、相互運用性のないシステム、信頼関係の構築の難しさなどによって妨げられることがあります 6。
DeSciの解決策: DeSciは、地理的な制約を超えたグローバルな共同研究を促進するためのインフラを提供します。分散型プラットフォーム上で、世界中の研究者がシームレスに繋がり、リソースを共有し、共同で研究プロジェクトを進めることが可能になります 7。ブロックチェーン技術は、貢献度に応じた公正なクレジットの付与を透明に記録し、DAOは国境を越えた研究コミュニティの形成を支援します 7。これにより、多様な専門知識を持つ研究者が結集し、複雑な課題に対する革新的な解決策を生み出すことが期待されます 23。
これらの伝統的科学の課題とDeSciによる解決策は、個別の問題として存在するだけでなく、相互に深く関連しています。例えば、資金調達の圧力が出版バイアスを生み、それが再現性の問題に影響を与えることがあります 1。出版社のビジネスモデル(ペイウォールやIP管理)がデータアクセスを制限し、それが再現性や共同研究をさらに妨げることもあります 3。DeSciは、これらの相互に関連する課題に対して、Web3ツールを組み合わせた包括的なアプローチを取ることで、部分的な改革よりも効果的な変革をもたらす可能性があります。
しかし、DeSciが提案する変革は、既存の科学エコシステムにおける有力な主体(大手出版社や伝統的な資金提供機関など)の役割や収益構造に本質的に挑戦するものです。このことは、DeSciの広範な普及が、技術的なハードルだけでなく、複雑な政治的・経済的状況を乗り越える必要があることを示唆しています 24。
表1: 伝統的科学(TradSci)とDeSciの比較
| 側面 | 伝統的科学 (Traditional Science) | DeSci (分散型科学) |
| 研究資金調達 | 中央集権的、限定的アクセス、不透明 | 分散型・多様、オープンアクセス、透明 |
| データアクセスと共有 | 限定的アクセス、サイロ化 | オープンアクセス、分散型リポジトリ |
| 査読プロセス | 不透明、無償労働、遅延の可能性 | 透明、インセンティブ付与、迅速化の可能性 |
| 学術出版 | 出版社の壁(ペイウォール、高額なAPC) | オープンアクセス、低コストまたは無料 |
| 知的財産管理 | 機関所有が一般的、複雑なプロセス | 研究者・コミュニティ所有の可能性(IP-NFT)、流動性の向上 |
| 透明性 | 限定的 | ブロックチェーンにより高い透明性を実現 |
| 国際協力 | 機関依存、障壁あり | グローバル、プラットフォーム経由で容易 |
| 再現性へのインセンティブ | 低い、または存在しないことが多い | トークン等によるインセンティブ設計が可能 |
この表は、DeSciが伝統的な科学研究の様々な側面において、どのような変革をもたらそうとしているのかを明確に示しています。
IV. DeSciが科学にもたらす主な利点
DeSciは、伝統的な科学研究システムが抱える多くの課題に対処することで、科学の進め方や成果の共有方法に数多くの利点をもたらすと期待されています。これらの利点は、単独で存在するのではなく、相互に作用し合い、より健全で効率的な科学エコシステムの構築に貢献します。
A. 透明性の向上
DeSciの最も顕著な利点の一つは、科学研究プロセス全体における透明性の飛躍的な向上です 7。ブロックチェーン技術を活用することで、研究データ、資金の流れ、査読の履歴、知的財産の帰属といった重要な情報が、改ざん不可能な形で記録され、誰でも検証可能な状態で公開されます 8。例えば、研究資金がどのように配分され、実際にどのように使用されたかを追跡できるようになることで、資金提供の公平性や説明責任が高まります 2。また、査読プロセスが透明化されることで、査読者のバイアスが低減され、より建設的なフィードバックが促進される可能性があります。このような透明性は、科学コミュニティ内外からの信頼を醸成し、研究不正のリスクを低減する上で不可欠です 19。
B. アクセシビリティの拡大
DeSciは、科学的知識や研究リソースへのアクセスを劇的に拡大することを目指しています 2。伝統的な学術出版では、高額な購読料や論文掲載料が、多くの研究者や一般市民にとって情報アクセスの障壁となっています。DeSciは、オープンアクセスモデルを推進し、研究論文やデータを分散型リポジトリに保存することで、これらの障壁を取り払おうとしています 2。これにより、地理的な場所や所属機関の経済状況に関わらず、誰もが最新の科学的知見に触れ、それを利用して新たな研究やイノベーションを生み出す機会が広がります 7。知識の民主化は、科学の進歩を加速させるだけでなく、社会全体の科学リテラシー向上にも貢献すると考えられます。
C. 科学の民主化
透明性とアクセシビリティの向上は、科学の民主化という、より広範な目標へと繋がります 2。DeSciは、研究資金の提供、研究テーマの決定、研究成果の評価といったプロセスへの参加の門戸を、従来の専門家コミュニティだけでなく、より幅広い層(市民科学者、患者団体、小規模な研究機関など)に開くことを目指しています 2。DAOのような仕組みを通じて、コミュニティが主体となって研究プロジェクトを支援したり、運営に関与したりすることが可能になります。これにより、中央集権的なゲートキーパーの影響力が相対的に低下し、多様な視点やニーズが科学研究に反映されるようになると期待されます 2。
D. 効率性の向上とイノベーションの加速
DeSciは、科学研究の様々な段階における非効率性を解消し、イノベーションのペースを加速させる可能性を秘めています 3。例えば、分散型の資金調達モデルは、従来の助成金申請プロセスよりも迅速に研究資金を供給できる可能性があります 11。スマートコントラクトを活用することで、契約の締結や報酬の支払いといった事務的なプロセスが自動化され、研究者はより研究活動そのものに集中できるようになります。また、オープンなデータ共有やインセンティブ付きの共同作業は、新たな発見やアイデアの創出を促進し、研究成果が実用化されるまでの時間を短縮することにも繋がると考えられます 19。
E. 研究者のエンパワーメント
DeSciは、個々の研究者に対して、より大きな自律性とコントロールを与えることを目指しています 3。IP-NFTのような仕組みは、研究者が自身の知的財産に対する所有権をより明確に主張し、その価値を直接的に収益化する道を開きます 7。また、多様な資金調達チャネルへのアクセスが可能になることで、研究者は自身の研究テーマやアプローチを追求する自由度を高めることができます。さらに、貢献度に応じた公正な評価や報酬システムが確立されれば、研究者のモチベーション向上にも繋がるでしょう 6。
これらの利点は、互いに影響し合い、好循環を生み出す可能性があります。例えば、透明性の向上は信頼を高め、それがアクセシビリティと協力の促進につながり、最終的には科学の民主化とイノベーションの加速を後押しします。透明な資金調達 2 とデータ 8 は信頼を醸成し 9、データと出版物へのオープンアクセス 2 はより多くの人々の参加を可能にし(民主化 7)、広範な参加とデータへのアクセスはより多くの協力を生み出し 8、そしてより多くの協力と多様な視点がイノベーションを加速させる 3 という連鎖です。
さらに、これらの利点の組み合わせ、特に民主化された資金調達とグローバルな協力プラットフォームは、現在の中央集権的な構造では達成が困難な、全く新しい研究パラダイムを可能にするかもしれません。例えば、大規模な市民参加型の科学プロジェクトや、危機に対する迅速かつ世界的に調整された対応などが考えられます。DeSciは、グローバルな個人プールから資金を調達するクラウドファンディングやDAOベースの資金調達を可能にし 2、組織の壁なしにグローバルな協力を促進します 8。これは、専門家でない科学者を含む多くの人々が、関心のある研究(例えば、3や3で言及されている希少疾患の研究など)に資金を提供し、参加することを可能にするかもしれません。これにより、前例のない規模の「市民科学」や、DAOによって推進される非常に機敏な研究イニシアチブが生まれる可能性があります。
V. 国外のDeSciプロジェクト事例紹介
DeSciの理念や技術は、既に世界中で具体的なプロジェクトとして形になり始めています。これらのプロジェクトは、資金調達、学術出版、データ共有、コミュニティ形成など、DeSciが目指す変革の多様な側面を具現化しています。ここでは、特に注目すべき国外のDeSciプロジェクトをいくつか紹介します。
A. VitaDAO:長寿研究特化型DAO
VitaDAOは、健康寿命の延伸と老化研究の進展を目的とした分散型自律組織(DAO)です 14。このプロジェクトは、長寿研究分野における有望な初期段階の研究プロジェクトに資金を提供し、その過程で生じる知的財産の所有権を民主化することを目指しています 14。VitaDAOの運営は、VITAトークン保有者によるガバナンス投票によって行われ、どの研究プロジェクトに資金を提供するかがコミュニティによって決定されます 11。資金調達の手段としては、VITAトークンの販売、IP-NFTの活用、さらには製薬大手ファイザー(Pfizer Ventures)からの支援を含むパートナーシップなどが挙げられます 11。これまでに420万ドル以上を24の研究プロジェクトに提供し、1万人以上のコミュニティメンバーを擁するなど、DeSci DAOの先駆的かつ成功した事例としてしばしば引用されます 27。具体的な支援プロジェクトには、独自の老化スコアアプリ「Humanity」や、ハダカデバネズミの生物学を活用したヒトの長寿研究「Matrix Bio」などがあります 27。
B. ResearchHub:科学的議論とオープンな出版のためのプラットフォーム
ResearchHubは、科学論文のオープンアクセス出版、査読、そして科学的議論を促進するためのプラットフォームです 4。このプロジェクトの大きな特徴は、研究への貢献や査読に対して、独自トークンであるResearchCoin(RSC)でインセンティブを与える点です 11。CoinbaseのCEOであるブライアン・アームストロング氏の支援を受けており 15、その有償査読モデルは、世界的に権威のある科学雑誌Nature誌でも取り上げられ、一部の科学者から好意的な評価を得ています 15。Nature誌の記事によれば、ある研究者はResearchHubでの査読業務により、大学での教授職よりも多くの収入を得ていると報告されています 15。これまでに700万ドルの資金調達にも成功しており 11、DeSciが伝統的な科学コミュニケーションに与える影響の可能性を示す重要な事例となっています。
C. DeSci Labs (DeSci Publish):次世代オープンサイエンス基盤
DeSci Labsが提供するDeSci Publishは、プレプリント(査読前論文)の共有ネットワークを中心とした、次世代のオープンサイエンス基盤です 3。研究者は、論文原稿だけでなく、関連するデータやコードも一元的に共有し、バージョン管理を行うことができます 28。DeSci Publishのユニークな機能としては、AIを活用した研究の新規性分析(2億5000万件の論文と比較して新規性スコアを算出)や、査読前段階での検証済みバッジの付与、DOI(デジタルオブジェクト識別子)やORCID(研究者識別子)との連携、そしてdPID(分散型永続識別子)によるコンテンツの永続的な参照可能性の確保などが挙げられます 17。このプラットフォームもNature誌で紹介され、研究管理と出版の方法を再定義するものとして評価されています 28。DeSci Labsは、CODEXプロトコルというオープンなP2Pネットワーク上に構築されており、静的なPDFファイルではなく、動的で相互運用可能な研究オブジェクトの共有を目指しています 28。
D. bio.xyz (Bio Protocol):バイオテクノロジー分野のDeSciハブ
bio.xyz(Bio Protocol)は、特にバイオテクノロジー分野におけるDeSciの金融レイヤーとして機能し、科学の迅速な商業化を支援することを目的としています 11。このプラットフォームは、大学、企業、研究者などが保有するトークン化された科学的知的財産の資金調達、開発、ガバナンスを促進します。その中核となるのが、特定の科学分野に特化した複数のBioDAO(バイオテクノロジーDAO)のネットワーク形成支援です。これには、前述のVitaDAO(長寿研究)のほか、AthenaDAO(女性の健康研究)、HairDAO(脱毛症治療研究)などが含まれます 11。IPのトークン化や、独自の$BIOトークンを通じたガバナンスとステーキングが主なメカニズムです。BioDAOトークンの総時価総額は2023年11月に2億ドルを超え、HairDAOはDAOとして初の科学特許を申請、Binance Labsからの投資を受けるなど、目覚ましい成果を上げています 11。bio.xyzは、特定の科学領域(バイオテクノロジー)内で複数の専門化されたDAOを育成する、DeSciエコシステムビルダーの一例と言えます。
E. その他の注目すべきプロジェクト
上記のプロジェクト以外にも、DeSciの理念を体現する多様な取り組みが存在します。
- GenomesDAO: ユーザー自身がゲノムデータを所有し、研究目的での安全な共有を可能にするプラットフォームです 14。
- Molecule Protocol: IP-NFTを活用して、生物医学研究プロジェクトと資金提供者を結びつけるプラットフォームです 14。
- The DeSci Journal / deScier: 著者が著作権を100%保持したまま科学技術論文を出版できるプラットフォームで、論文をNFTとして発行し収益化することも目指しています 16。
これらの事例は、DeSciが単一のアイデアではなく、様々なアプローチで科学研究の変革を目指す多様な運動であることを示しています。初期のDeSciの概念は広範なものでしたが 7、VitaDAOのように特定の分野(長寿)に焦点を当てたプロジェクト 27 や、bio.xyzのように異なるバイオテクノロジー分野向けの専門BioDAOネットワークの構築を明確に目指すプロジェクト 20 が登場しています。これは、画一的なプラットフォームではなく、特定のニーズに対応した専門的な応用へと向かう傾向を示しており、特定の市場ニーズを特定しつつある発展途上の分野の兆候と言えます。
さらに注目すべきは、VitaDAOとファイザーの提携 11 や、ResearchHubやDeSci LabsのNature誌での紹介 15 など、成功しているDeSciプロジェクトが伝統的な科学界との関係を完全に断ち切るのではなく、積極的に検証、パートナーシップ、統合を模索している点です。この実用的なアプローチは、DeSciがより広範な採用と正当性を得る上で極めて重要かもしれません。完全な破壊ではなく、DeSciが伝統的なシステムの一部に価値を証明し協力するハイブリッドモデルや段階的な統合が、より現実的な道筋である可能性を示唆しています。
表2: 主な国外DeSciプロジェクトとその特徴
| プロジェクト名 | 主な焦点分野 | 主要技術・メカニズム | 特筆すべき成果・目標 |
| VitaDAO | 長寿研究 | DAO, VITAトークン, IP-NFT | 420万ドル超の資金提供、Pfizer Venturesとの提携 11 |
| ResearchHub | オープン出版・査読 | RSCトークン, 有償査読 | Nature誌掲載、有償査読モデルの確立 15 |
| DeSci Labs (DeSci Publish) | 研究共有基盤 | プレプリント, AI分析, dPID, CODEXプロトコル | Nature誌掲載、5000万件超の論文アクセス、2万超のdPID発行 28 |
| bio.xyz (Bio Protocol) | バイオテクノロジー資金調達・商業化 | BioDAOネットワーク, IPトークン化, $BIOトークン | BioDAOトークン時価総額2億ドル超、Binance Labsからの投資 11 |
| GenomesDAO | ゲノムデータ共有 | ユーザー所有データ、ブロックチェーン | プライバシーを保護しつつゲノムデータ研究を促進 14 |
| Molecule Protocol | 生物医学研究と資金のマッチング | IP-NFT, DAO | IP-NFTを介した研究資金調達の促進 14 |
| The DeSci Journal | 著作権保持型出版 | NFT論文、スマートコントラクト | 著者が著作権100%保持、NFTによる収益化 29 |
この表は、DeSciムーブメントがいかに多様な形で展開されているかを示しており、具体的な応用例を通じてDeSciの抽象的な概念を理解する助けとなります。
VI. DeSciが直面する課題と乗り越えるべき壁
DeSciは科学研究に革命をもたらす大きな可能性を秘めている一方で、その普及と実現に向けては、いくつかの重要な課題や障壁が存在します。これらの課題は相互に関連しており、DeSciムーブメントが真に成熟するためには、包括的な取り組みが求められます。
A. 法規制の不確実性
DeSciプロジェクトの多くは、DAOの法的地位、トークン化された知的財産の取り扱い、国境を越えたデータ共有(特にゲノム情報のような機密性の高いデータ)など、既存の法規制の枠組みでは明確に定義されていない領域で活動しています 6。例えば、DAOが法人格を持つのか、トークンが証券と見なされるのかといった問題は、国や地域によって解釈が異なり、プロジェクト運営に大きな不確実性をもたらします 6。また、標準化や規制の欠如は、異なる研究結果の比較を困難にしたり、誤った情報や質の低い研究が拡散するリスクを高める可能性も指摘されています 26。
B. 技術的課題:スケーラビリティとユーザービリティ
ブロックチェーン技術はDeSciの基盤ですが、現状ではトランザクションの処理速度やコスト(ガス代)、データストレージの容量といったスケーラビリティの問題を抱えています 6。大量の研究データを扱ったり、多数のマイクロトランザクションを処理したりする必要がある場合、これらの技術的制約がボトルネックとなる可能性があります。また、Web3ツールやプラットフォームの多くは、まだ技術的な知識を持たない科学者にとっては複雑で使いにくいものが多く、学習曲線が急であるとの指摘もあります 25。DeSciが広く普及するためには、よりユーザーフレンドリーなインターフェースやツールの開発が不可欠です。
C. 研究の質と信頼性の担保
中央集権的な管理機関が存在しない分散型のシステムにおいて、どのように研究の質と信頼性を担保するかは大きな課題です 25。伝統的な査読システムも完璧ではありませんが 24、DeSciにおけるコミュニティベースの査読やインセンティブ付きの査読が、常に厳格な基準を維持できるかについては懸念の声もあります 25。査読者の適格性をどのように検証するか、利益相反をどう管理するか、誤情報や質の低い研究の拡散をどう防ぐかといった点について、堅牢なメカニズムを構築する必要があります。
D. 普及と受容:伝統的科学コミュニティとの溝
新しい技術やパラダイムが受け入れられるには時間がかかります。DeSciも例外ではなく、伝統的な科学コミュニティからの懐疑的な見方や、既存の確立された機関からの抵抗に直面する可能性があります 24。多くの研究者はブロックチェーン技術に馴染みがなく 25、DeSciのメリットを理解し、新しいツールやプラットフォームを積極的に利用するようになるまでには、継続的な教育や啓発活動、そして成功事例の積み重ねが必要です。大学が信頼性を失い、科学が無関係なものになりつつあるという問題意識に対し、DeSciが解決策を提示できるとしても、その採用が鍵となります 4。
E. インセンティブ設計の難しさ
トークンを用いたインセンティブ設計は、DeSciエコシステムの活性化に不可欠ですが、その設計は非常に難しい課題です 7。持続可能で公正なトークノミクスを構築し、短期的な投機目的ではなく長期的な貢献を促すようなインセンティブを与える必要があります。また、意図しない行動を誘発するような不適切なインセンティブ(Perverse Incentives)を避け、研究コミュニティ全体の利益に資するような報酬分配メカニズムを設計することが求められます。TradSciにおける「インセンティブの不整合」がDeSciが解決しようとする核心的問題の一つであるだけに 1、DeSci自身のインセンティブ設計が不適切であれば、同様の問題を再現しかねません。
F. 知的財産権の複雑な取り扱い
分散型のグローバルな共同研究プロジェクトにおいて、誰が知的財産権(IP)を所有するのかを決定することは複雑な問題となり得ます 26。特に、複数の貢献者が関与する場合や、IPがトークン化されて流通する場合など、従来のIP法では想定されていなかった状況が生じる可能性があります。IP権の国際的な執行可能性や、オープンサイエンスの理念とIP保護のバランスをどのように取るかといった点も、慎重な検討が必要です 10。
これらの課題は、しばしば相互に関連しています。例えば、法規制の不確実性 6 は、研究者や機関がDeSciプラットフォームを採用することをためらわせる要因となり得ます 25。技術的なユーザビリティの問題 25 もまた、採用を遅らせ、品質管理能力に影響を与える可能性があります 25。したがって、一つの課題を解決すること(例えば、ユーザビリティの向上)が、他の課題(例えば、採用の増加)に好影響を与える可能性があります。
さらに、DeSciの強み(オープン性、パーミッションレス性)の多くが、同時にその最大の課題(品質管理、誤情報、規制の曖昧さ)の原因にもなり得るという「分散化のジレンマ」が存在します。DeSciムーブメントが成功するためには、急進的な分散化と、必要なセーフガードや基準との間で適切なバランスを見つけるという、きわどい綱渡りが求められるでしょう。DeSciはゲートキーピングを減らすためにオープンアクセスと分散化を推進しますが 2、このオープン性自体が、堅牢な検証メカニズムが整備されていなければ、質の低い情報や誤解を招く情報が広まりやすくなる可能性があります 25。完全な分散化は、基準や規制の施行を困難にする可能性もあります 26。このジレンマは、DeSci内でハイブリッドモデルや階層化されたシステムが生まれる可能性を示唆しています。
VII. 専門家の視点:DeSciは科学の未来をどう変えるか?
DeSciムーブメントはまだ初期段階にありますが、その革新的なアプローチと潜在的な影響力について、科学界内外の専門家から様々な意見が寄せられています。主要な学術誌での取り上げられ方、AIとの融合の可能性、DeSci推進者のビジョン、学術的な定義付け、そしてビジネス界への波及効果など、多角的な視点からDeSciの未来像を探ります。
A. Nature誌などの主要学術誌の注目
DeSciプロジェクトがNature誌のような権威ある科学雑誌で特集されることは、このムーブメントが主流科学界からも注目され始めている証と言えます。例えば、ResearchHubがNature誌でその有償査読モデルと共に紹介されたことは、DeSciの存在をより広範な科学コミュニティに知らせるきっかけとなった可能性があります 15。同様に、DeSci LabsもNature誌で「研究者が研究を管理し出版する方法を再定義している」と評価されており 28、これはDeSciの取り組みがある種の正当性を得つつあることを示唆しています。このような主要学術誌での露出は、DeSciに対する関心を高め、さらなる議論や実験を促進する上で重要なマイルストーンです。
B. AIとの融合による科学研究の加速
一部の専門家は、DeSciと人工知能(AI)の融合が、科学研究を飛躍的に加速させる触媒になると予測しています。YesNoErrorの共同創設者であるマット・シュリヒト氏やMira NetworkのCEOであるマグナス・ブラット氏は、AIが査読プロセスにおけるエラー検出を自動化し、原稿と適切な査読者のマッチングを行い、バイアスを低減することで、品質管理の信頼性と効率性を向上させると指摘しています 24。DeSciの透明で分散化されたフレームワーク上でAIを活用することで、査読コストを大幅に削減し、誰もが瞬時に無限の査読を受けられる未来も描かれています 24。さらに、AIは膨大な既存の科学データを人間には不可能な速度で分析し、創薬ターゲットの特定や疾患進行のモデリング、革新的な治療法の提案などに貢献できると期待されています。
C. DeSci Labs CEO (Philipp Koellinger) の見解
DeSci LabsのCEOであるフィリップ・ケリンガー氏は、DeSciが現代科学の「再現性の危機」や、ペイウォール、査読者の無償労働といった既存の出版システムの限界に対処するものであると述べています 3。彼によれば、DeSciはより民主的で協調的なアプローチを可能にし、科学者が自身の研究をコントロールし、新たな資金調達モデルが出現する道を開くとされています。DeSci Publishのようなオープンサイエンスソリューションは、仲介者なしに研究成果をオープンに共有することを促進し、透明で不変の研究記録を提供します。ケリンガー氏は、DeSciがオープンアクセス出版、インセンティブ付き査読、ブロックチェーンによる検証という3つの核となる原則に基づいており、これらが科学の進歩を加速させると強調しています 3。
D. 学術論文におけるDeSciの定義と原則
DeSciムーブメントの概念的基盤を固める学術的な取り組みも進んでいます。Lukas Weidenerらによる論文では、DeSciの正式な定義が提示され、その共有価値観と指導原則が明確化されています 10。共有価値観としては、「普遍的なオープン性と透明性」「完全性と説明責任」「共有所有権とインセンティブ付与」「イノベーションと継続的進歩」が挙げられています。また、指導原則としては、「信頼、検証、再現性」「集団的協力とコミュニティ主導」「自律的分散化と民主化」「実力主義に基づくインセンティブ付与と承認」が定義されています 10。このような学術的な枠組みは、DeSciムーブメントの目指す方向性をより明確にし、その健全な発展を促す上で重要です。
E. ビジネスおよび学術界への潜在的価値
専門家の中には、DeSciが学術界だけでなくビジネス界にも大きな価値をもたらすと考える向きもあります。DeSciは、時代遅れになった伝統的な科学プロセスを近代化し、科学の社会における relevancia(今日的意義)を回復させる可能性を秘めていると指摘されています 4。特に、Web3に関心を持つ起業家にとって、DeSciは意義深く、実世界へのインパクトが期待できるプロジェクトを構築する好機を提供するとされています 4。具体的な応用分野としては、データ共有プラットフォーム、研究関連の知的財産マーケットプレイス、研究者間の協力を促進するメカニズムなどが挙げられます 4。
これらの専門家の視点からは、DeSciに対する楽観的な期待と同時に、現実的な課題認識も見て取れます。Nature誌での特集は重要な一歩であるものの、トークンの現金化の難しさや新しいジャーナルの索引登録の遅れといった課題も指摘されています 15。これは、DeSciの変革への道が段階的な進展と既存システムとの継続的な対話を伴うことを示唆しています。
さらに、専門家や主要出版物によるDeSciに関する議論の活発化は、それ自体が強力な「ナラティブ(物語)」を構築する上で重要です(11ではDeSciがナラティブとして言及されています)。このナラティブは、DeSciの直接的な成功とは独立して、才能ある人材、資金、そして実験を引き寄せる自己強化的な触媒となり得ます。DeSciは「新たなムーブメント」8 や「ナラティブ」11 と表現され、専門家の意見 3 やメディアでの特集 15 がこのナラティブ構築に貢献しています。魅力的なナラティブは投資(11はVCの関心の高まりを示しています)、人材(研究者、開発者)、そしてユーザーを引き付けることができます。個々のプロジェクトが後退したとしても、強力な包括的ナラティブはDeSciムーブメント全体の勢いを維持し、さらなる探求と開発を奨励する可能性があります。
VIII. 結論:DeSciはこれからの科学のスタンダードになり得るか?
DeSci(分散型科学)は、伝統的な科学研究システムが抱える根深い課題に対処し、よりオープンで効率的、かつ民主的な科学事業を育成するという、変革の大きな可能性を秘めています。本記事では、国外の文献を中心に、DeSciの定義、核心技術、伝統的科学との比較、利点、具体的なプロジェクト事例、そして直面する課題について詳述してきました。最終的に、「DeSciはこれからの科学のスタンダードになり得るのか?」という問いに対して、現時点での考察を述べます。
A. DeSciの可能性の再確認
DeSciが提示するビジョンは魅力的です。ブロックチェーン、DAO、NFT、スマートコントラクトといったWeb3技術を活用することで、研究資金調達の透明化と多様化、研究データのオープンアクセス化と再現性の向上、査読プロセスの効率化とインセンティブ付与、知的財産管理の民主化、そしてグローバルな共同研究の円滑化が期待されます。これらの変革は、科学的発見のペースを加速し、その恩恵をより多くの人々に届けることに繋がる可能性があります。特に、中央集権的なゲートキーパーへの依存を減らし、コミュニティ主導で科学を進めるというDeSciの思想は、科学のあり方そのものにパラダイムシフトをもたらす可能性を秘めています。
B. 現実的な課題と普及への道のり
しかしながら、DeSciが科学のスタンダードとなるまでには、乗り越えるべき多くの現実的な課題が存在します。法規制の不確実性、技術的なスケーラビリティやユーザビリティの問題、分散型システムにおける研究の質と信頼性の担保、伝統的な科学コミュニティへの普及と受容、持続可能なインセンティブ設計の難しさ、そして複雑な知的財産権の取り扱いなど、その道のりは平坦ではありません。これらの課題は相互に関連しており、一つ一つ丁寧に対処していく必要があります。
C. 短期・中期・長期的な展望
DeSciの普及は、一朝一夕に起こるものではなく、段階的に進むと考えられます。
- 短期的展望: DeSciは、伝統的科学と共存しつつ、特定のニッチな分野や機能(例えば、希少疾患研究の資金調達、特定のデータセットのオープンリポジトリ、実験的な査読システムなど)でソリューションを提供し、様々なモデルを実験していく段階が続くと予想されます。堅牢なインフラストラクチャとユーザーフレンドリーなツールの開発が焦点となるでしょう。
- 中期的展望: 特定の科学分野や機能において、DeSciの採用が広がる可能性があります。例えば、特定の研究分野に特化したDAOが成功を収めたり、DeSciベースのオープンアクセスジャーナルが一定の評価を得たりするかもしれません。伝統的な研究機関や資金提供団体との連携やパートナーシップも進む可能性があります。
- 長期的展望: 主要な課題が解決され、DeSciがもたらす具体的な便益が一貫して実証されれば、DeSciは科学の多くの側面において重要な構成要素、あるいは新たなスタンダードとなる可能性も否定できません。ただし、それは伝統的科学の完全な置き換えというよりは、DeSciの原則やツールが既存のシステムに浸透し、科学研究のあり方を根本的に再形成していく形になるでしょう。
D. 「スタンダード」になるための条件
DeSciが主流となるためには、いくつかの条件が満たされる必要があると考えられます。
- 実証可能な成功事例の創出: DeSciの原則やプラットフォームを活用した画期的な科学的発見や、伝統的な手法では達成困難だった問題解決事例が生まれること。
- 明確な法規制とガバナンス: DAOの法的地位やトークンの取り扱いに関する明確な法的枠組みが整備され、DeSciコミュニティ内で効果的なガバナンスモデルが確立されること。
- 使いやすいプラットフォームとツール: 専門知識のない科学者でも容易に利用できる、直感的でスケーラブルなプラットフォームやツールが提供されること。
- 強力なコミュニティとエコシステム: 活発で多様な参加者からなるコミュニティが形成され、持続可能なエコシステムが構築されること。
- 主流科学界からの理解と協力: 伝統的な科学者、研究機関、学協会などからの理解と協力を得て、DeSciの取り組みが正当なものとして認知されること。
E. 最終的な考察:希望と現実のバランス
DeSciがこれからの科学のスタンダードになるかという問いに対して、現時点で断定的な答えを出すのは時期尚早です。しかし、DeSciが科学研究の未来に大きな影響を与える強力な触媒であることは間違いありません。DeSciは、オープンサイエンスの理想と合致し、伝統的科学が抱える多くの課題に対する具体的な解決策を提示しています。
その道のりは、革命的な一夜の変革というよりは、むしろ進化的なプロセスとなるでしょう。DeSciの様々な側面が異なる速度で成熟し、採用されていくと考えられます。伝統的な科学は長年にわたり深く根付いたシステムであり、DeSciがこれとどのように相互作用し、変革していくのかは、今後の技術開発、コミュニティの努力、そして社会全体の受容にかかっています。
DeSciの真価が問われるのは、単に新しい技術を導入することではなく、それによって実際に科学がより良く、より速く、より公正に進むようになるかという点です。その意味で、DeSciが「キラーアプリケーション」や画期的な科学的成功を生み出せるかどうかが、今後の普及の鍵を握るかもしれません。もしDeSci DAOが主要な疾患の治療法を迅速に発見・開発したり、DeSciプラットフォームが地球規模の課題解決に貢献したりすれば、それはDeSciの優位性を明確に示す強力な証拠となるでしょう。
DeSciは、科学研究の未来に対する大きな希望を提示しています。その理想と現実の間のギャップを埋める努力が続けられる限り、DeSciは科学のあり方をより良い方向へと導く重要な力であり続けるでしょう。この動きはまだ始まったばかりであり、その発展を注意深く見守り、建設的に関与していくことが求められています。
引用文献
- public.bnbstatic.com, 5月 11, 2025にアクセス、 https://public.bnbstatic.com/static/files/research/from-challenges-to-opportunities-how-desci-reimagines-science.pdf
- How Decentralized Science (DeSci) Improves Research – Ulam Labs, 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.ulam.io/blog/how-decentralized-science-is-revolutionizing-research
- The Rise of Decentralized Science – DeSci Labs, 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.desci.com/blogs/the-rise-of-decentralized-science
- DeSci – (How) Will It Make Research Great Again? | Onchain, 5月 11, 2025にアクセス、 https://onchain.org/research/desci-how-will-it-make-research-great-again/
- Exploring Decentralized Science (DeSci) with Aethir, 5月 11, 2025にアクセス、 https://blog.aethir.com/blog-posts/exploring-decentralized-science-desci-with-aethir
- What is Decentralized Science (DeSci)? A New Approach to Scientific Research – Blog | PancakeSwap, 5月 11, 2025にアクセス、 https://blog.pancakeswap.finance/articles/what-is-decentralized-science-de-sci-a-new-approach-to-scientific-research
- Decentralized Science [DeSci], Crypto Concepts: Beginner’s Guide, 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.diadata.org/crypto-narratives/decentralized-science-desci/
- What is DeSci (Decentralized Science) — Understanding The Hype!, 5月 11, 2025にアクセス、 https://metaschool.so/articles/what-is-desci-decentralized-science
- What Is Decentralized Science (DeSci)? | Binance Academy, 5月 11, 2025にアクセス、 https://academy.binance.com/en/articles/what-is-decentralized-science-desci
- (PDF) Decentralized Science (DeSci): Definition, Shared Values …, 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/377657504_Decentralized_Science_DeSci_Definition_Shared_Values_and_Guiding_Principles
- Decentralized Science (DeSci): A Narrative hidden in shadows? – TDeFi Blogs, 5月 11, 2025にアクセス、 https://tde.fi/founder-resource/blogs/tokenization/decentralized-science-desci-a-narrative-hidden-in-shadows/
- www.coinbase.com, 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.coinbase.com/learn/crypto-glossary/what-is-decentralized-science-desci-and-how-does-it-plan-to-fix-academic-research#:~:text=DeSci%20(Decentralized%20Science)%20seeks%20to,anyone%20can%20access%20them%20easily.
- What is Decentralized Science (DeSci)? Blockchain’s Next Big Use Case Beyond Finance and NFTs | BitPinas, 5月 11, 2025にアクセス、 https://bitpinas.com/learn-how-to-guides/decentralized-science-101/
- What Is Decentralized Science (DeSci)? | CoinGeko, 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.coingecko.com/learn/what-is-desci-decentralized-science
- Major scientific journal Nature features DeSci project ResearchHub, 5月 11, 2025にアクセス、 https://cointelegraph.com/news/desci-project-researchhub-featured-on-major-scientifc-journal
- The DeSci Journals | Giveth, 5月 11, 2025にアクセス、 https://giveth.io/project/the-desci-journals
- Expert Rapid Peer Review – DeSci Labs, 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.desci.com/peer-review
- DeSci for Journals – Streamline Submission and Boost Research Quality, 5月 11, 2025にアクセス、 https://desci.com/desci-for/journals
- Exponential Science (ES), 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.exp.science/education/decentralised-science-desci-new-era-research
- BIO • Home, 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.bio.xyz/
- WTF is DeSci? – DATA LAKE, 5月 11, 2025にアクセス、 https://data-lake.co/wtf-is-desci/
- What Is Decentralized Science (DeSci)? – OSL, 5月 11, 2025にアクセス、 https://osl.com/academy/article/what-is-decentralized-science-desci
- osl.com, 5月 11, 2025にアクセス、 https://osl.com/academy/article/what-is-decentralized-science-desci#:~:text=By%20decentralizing%20various%20aspects%20of,and%20equitable%20for%20researchers%20worldwide.
- Experts Reveal How AI and DeSci Can Reshape Science Forever …, 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.itiger.com/news/2509237647
- The Emergence of Decentralized Science (DeSci) Platforms – Coinmetro, 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.coinmetro.com/learning-lab/the-emergence-of-decentralized-science-desci-platf
- Introduction to Decentralised Science (DeSci) and our involvement in a disruptive and innovative space – what. AG Opportunities, Challenges, and Risks of Decentralised Science – Digital, 5月 11, 2025にアクセス、 https://what.digital/decentralised-science-opportunities-challenges-and-risks/
- VitaDAO | The Longevity DAO, 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.vitadao.com/
- DeSci Labs – Empowering Researchers from Data to Publication, 5月 11, 2025にアクセス、 https://www.desci.com/
- The DeSci Journal – Gitcoin, 5月 11, 2025にアクセス、 https://checker.gitcoin.co/public/project/show/the-desci-journal
- The DeSci Journals, 5月 11, 2025にアクセス、 https://platform.desci.reviews/