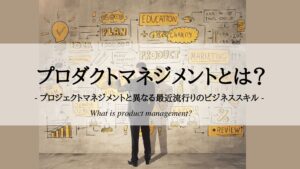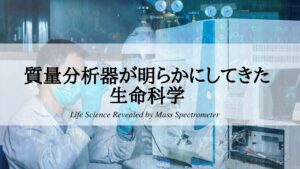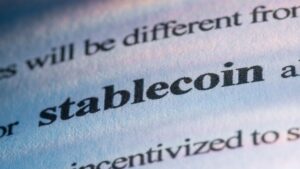I. はじめに:引退は「終わり」ではない、「移行(トランジション)」の始まり
アスリートのキャリアにおいて、現役からの引退は避けて通れない現実である。この「引退」という言葉は、しばしばキャリアの「終わり」というネガティブな響きを伴うが、現代のスポーツ科学や心理学では、これを「トランジション(移行)」と捉える見方が主流となっている 1。これは、競技生活という一つの段階から、次の人生のステージへと移行する、複雑で多面的なプロセスを指す 3。元プレミアリーグのストライカー、ロブ・ハルスが「フットボールの後にも人生がある。引退した後の時間は長い」と語るように、この移行期はすべてのアスリートにとって普遍的かつ極めて重要なライフステージである 4。
このトランジションは、単に新しい仕事を見つけるという職業的な問題に留まらない。それは、長年かけて築き上げられた「アスリート」としてのアイデンティティの再構築を伴う、深刻な心理的、社会的、そして経済的な再適応の過程である 2。成功の度合いや競技種目、国籍を問わず、すべてのアスリートがこの課題に直面する 7。
この課題に対するアプローチは、世界各国で、また各スポーツ団体で大きく異なる。本稿では、国内外の先進的な支援事例や個々のアスリートの成功・失敗事例を比較分析し、スポーツ種目によるキャリアパスの違いにも光を当てる。そして、これらの分析を通じて、アスリートが直面する課題の本質を深く掘り下げ、日本におけるアスリートのキャリア支援が目指すべき「あるべき論」を提言することを目的とする。
この議論の根底には、使用する「言葉」が問題の捉え方を規定するという考え方がある。「引退」という言葉は終着点を想起させ、喪失感を助長しかねない。一方で「トランジション」という言葉は、ある状態から別の状態への動き、すなわちプロセスを示唆する。この視点の転換こそが、キャリアの終わりに受動的に対処するのではなく、現役中から次なるステージを能動的に計画するという、建設的な文化を醸成するための第一歩となる。

II. アスリートが直面する心理的現実:アイデンティティの喪失と再構築
アスリートのセカンドキャリア問題を理解する上で、その根幹にある心理的課題を避けて通ることはできない。多くのトップアスリートにとって、自らのアイデンティティは競技と分かちがたく結びついている。「私はサッカー選手だ」「私は体操選手だ」という自己認識は、彼らの存在そのものを定義する 9。これは心理学で「アイデンティティ・フォアクロージャー(自己同一性の早期完了)」と呼ばれる状態で、競技以外の自己の側面が十分に発達しないまま、アスリートとしてのアイデンティティが過剰に形成されることを指す 10。
引退は、この強固なアイデンティティを根こそぎ奪い去る。その結果、アスリートは深刻な目的喪失感や混乱に陥り、「完全に道に迷った」と感じることが少なくない 11。この心理的な空白は、うつ病や不安障害といったメンタルヘルスの問題を引き起こす主要な要因となる 3。学術的なキャリア移行モデルでは、このプロセスを、生活様式の変化や新たな社会的ネットワークの構築といった特有の要求への「対処過程」と捉えている。そして、その成否は、アスリートが持つ資源や事前の準備に大きく左右されると分析されている 2。
特に、自らの意思で計画的に引退する「自発的引退」と、怪我や戦力外通告などによる「非自発的引退」とでは、移行の質が大きく異なる 12。後者は、より深刻な心理的ダメージをもたらす傾向がある。これらの心理的課題は、引退が迫ってからではなく、現役中から自己のアイデンティティを多角的に見つめ、バランスの取れた自己像を築くための能動的な支援がいかに重要であるかを物語っている 9。
ここには一つの逆説が存在する。競技で大きな成功を収め、献身的に打ち込んできたアスリートほど、その競技へのアイデンティティは強固になる。そして、その強固なアイデンティティこそが、引退後の移行における最大の心理的脆弱性となりうるのである。エリートとしてのパフォーマンスを可能にした強烈な集中力や献身性 15 が、引退後の人生においてはリスク要因に転化する可能性がある。これは、キャリア支援が苦境にある選手だけでなく、一見すると最も支援を必要としないように見えるトップ・オブ・トップの選手にこそ不可欠であることを示唆している。
さらに、アスリートが競技者として培った精神的スキルと、移行期に必要なスキルとの間には、しばしばミスマッチが生じる。チャンピオンを生み出す精神性、例えば、単一の目標への集中、痛みを無視する忍耐力、雑音を遮断する能力 17 は、移行期に求められる多様なスキルーーネットワーキング、自己探求、不確実性の受容ーーとは必ずしも一致しない 6。アスリートとしての誇りが、年下の同僚から謙虚に学ぶ姿勢を妨げる「プライド」として現れることもある 16。したがって、効果的なキャリア支援には、競技者としての特定の思考様式を一旦「アンラーニング(学習棄却)」し、より曖昧で構造化されていない社会で生き抜くための新たな対処戦略を「リラーニング(再学習)」するプロセスが含まれなければならない。
III. 日本におけるアスリートキャリア支援の現在地:制度と課題
日本国内におけるアスリートのキャリア支援は、各競技団体や関係機関が独自の取り組みを進めており、その形態は多様である。しかし、全体として見ると、いくつかの共通した特徴と課題が浮かび上がってくる。
3.1. Jリーグの先駆的取り組み:若手からのキャリアデザイン教育へのシフト
日本のプロスポーツ界において、Jリーグはキャリア支援の先駆者と言える。2002年には「キャリアサポートセンター(CSC)」を設立し、他団体に先駆けて組織的な支援を開始した 19。当初の活動は、引退選手の就職斡旋や、高卒でプロになった選手のための大学進学支援(就学サポート)が中心であった 19。
しかし、その活動は次第に、引退後の「対処」から現役中の「準備」へと重点を移していく。特に近年は、アカデミー(育成組織)に所属する若手選手からキャリアデザインを学ぶ機会を提供するなど、早期教育へとシフトしている 20。文部科学省の委託事業として実施された「Jリーグ版『よのなか』科」は、未来のJリーガーが社会の仕組みや職業観を学ぶ画期的なプログラムであり、国際的なベストプラクティスにも通じる能動的なアプローチの好例である 22。
3.2. JOC「アスナビ」の功罪:就職マッチングモデルの成果と限界
日本オリンピック委員会(JOC)が運営する「アスナビ」は、現役トップアスリートを対象とした就職支援制度として高い知名度を誇る 23。企業に社員として所属し、安定した経済基盤を得ながら競技を続けることを可能にするこのマッチングモデルは、これまでに多くのオリンピアンを支援し、大きな成果を上げてきた 24。
この制度の最大のメリットは、アスリートが目先の生活不安から解放され、競技に集中できる環境を提供することにある 23。採用企業側にも、アスリートを応援することによる社内の一体感の醸成や、企業イメージの向上といった利点がある 24。
一方で、その運用には課題も指摘されている。研究によれば、アスリート本人や指導者の間で、キャリアプランニングの重要性やアスナビの意義に対する認識が不足しているケースが見られる 1。また、支援の焦点が長期的なキャリア形成よりも、当面の「就職先の斡旋」に偏りがちであるため、競技引退後に企業内で孤立したり、キャリアパスを見失ったりするリスクも存在する 1。アスリートが将来の社員としてではなく、一時的な「広告塔」として見なされてしまう危険性も内包している。
3.3. プロ野球と大相撲:伝統と革新が交差するキャリアパス
団体競技の中でも、プロ野球と大相撲は、その歴史的背景から独特のキャリアパスを形成している。
**プロ野球(NPB)**では、伝統的に引退後の道は監督・コーチ、解説者、球団スタッフといった球界内部の役割に限られる傾向があった 13。しかし、近年では変化の兆しが見られる。日本プロ野球選手会(JPBPA)が立ち上げた「ファントモプロジェクト」は、OB選手によるメンター制度(PDM)の導入や学習機会の提供、就業支援などを盛り込んだ現代的なサポート体制であり、大きな前進と言える 27。また、SBヒューマンキャピタルが提供する「イーキャリアNEXTFIELD」のような民間の支援サービスも登場している 28。
対照的に、大相撲は極めて伝統的かつ閉鎖的な構造を持つ。力士にとって最も名誉あるセカンドキャリアは、相撲部屋の師匠となる「年寄(親方)」になることだが、その名跡は105名と厳格に定められており、就任には幕内上位での実績など非常に高い基準が課される 29。若者頭や世話人といった協会内の他の役職もごく少数に限られる 29。年寄名跡を取得できなかった大多数の力士は角界を去り、飲食業や介護、整体といった分野に進むことが多いが、そこでは力士時代の地位や名声が通用しない厳しい現実に直面することも少なくない 30。
3.4. スポーツ庁の役割:産官学連携によるエコシステム構築の試み
政府機関であるスポーツ庁は、個別の選手支援というよりも、アスリートのキャリア支援を取り巻くエコシステム全体の構築を目指している 32。その中核をなすのが、スポーツ界、教育界、経済界の連携を促進する「スポーツキャリアサポートコンソーシアム」の運営である 33。
このコンソーシアムは、年に一度カンファレンスを開催し、関係者間で知見や成功事例を共有するプラットフォームとして機能している 33。その役割は、JOCやJリーグのような直接的なマッチングや教育ではなく、より大局的な視点から、社会全体でアスリートを支える土壌を育むことにある。
これらの国内の取り組みを俯瞰すると、日本の支援体制は統一された戦略ではなく、各組織が個別に展開する施策の「寄せ集め(パッチワーク)」であることがわかる。JOCはオリンピック強化選手、Jリーグはサッカー選手、選手会は所属選手を対象とし、それぞれが異なる理念と手法で支援を行っている。その結果、アスリートが選択した競技によって受けられる支援の質と量に大きな格差が生まれる「支援の宝くじ」とも言える状況が生じている。これは、オーストラリアのような国家主導の統一モデルと比較した場合の、日本のシステムが抱える構造的な弱点である。
また、「アスナビ」の成功は、それが解決しようとしている問題の本質について、より深い問いを投げかける。この制度の主目的は、現役アスリートの競技生活を支えるための「現在の」雇用を確保することにあるのか、それとも競技引退後の「未来の」キャリアの礎を築くことにあるのか。現状は明らかに前者への傾斜が強い 23。これは短期的な資金問題を解決する一方で、長期的なキャリア移行に必要な心理的・実務的な準備を先送りにしてしまう可能性がある。結果として、競技生活が終わり、アスリートとしての役割を終えた瞬間に、断崖絶壁から突き落とされるような事態を招きかねない。
IV. 世界の先進モデルから学ぶ:海外のキャリア支援ベストプラクティス
アスリートのキャリア支援において、海外には日本が学ぶべき多くの先進的なモデルが存在する。特にオーストラリア、アメリカのプロスポーツ、そして国際オリンピック委員会(IOC)の取り組みは、世界的なベンチマークとされている。
4.1. 全人格的アプローチ:豪州「ACEプログラム」の哲学
オーストラリアスポーツ研究所(AIS)が提供する「アスリートキャリア&エデュケーション(ACE)プログラム」は、セカンドキャリア支援のモデルケースとして国際的に高く評価されている 37。その根底にあるのは、「ベストな人間がベストなパフォーマンスを生む(Best person makes the best performance)」という哲学である 37。この考え方では、学業や人格形成は競技の妨げではなく、むしろ競技力を高めるための重要な要素と位置づけられる。
ACEプログラムは、アスリートのキャリア初期から、教育、キャリア開発、ライフスキル(生活技術)のトレーニングを競技活動と並行して行う「デュアルキャリア」モデルを実践している 37。その包括的かつ先進的なアプローチは、ニュージーランドやイギリスといった他国がプログラムのライセンス契約を結んだり、一部を導入したりするほどの影響力を持っている 37。
4.2. 選手中心の強力な支援:米国「NFL選手会」の包括的サポート
アメリカンフットボールの選手会であるNFLPA(National Football League Players Association)は、世界で最も包括的で強力なアスリート支援体制を構築している組織の一つである 38。その活動資金は選手会自身によって賄われており、選手中心の視点が徹底されている。
特筆すべきは「キャリア・エクスペリエンス(旧称:エクスターンシップ)」と呼ばれるプログラムである。これにより、現役選手はFOX Sports、NASCAR、さらには政策コンサルティング会社といった多様な業界のトップ企業で、就業体験を積むことができる 38。これは単なる職場見学ではなく、実践的なスキルと人脈を構築する貴重な機会となっている。
さらに、NFLPAの支援は、キャリア相談、学費補助、ファイナンシャル教育、メンタルヘルスサポートにまで及び、選手の家族やパートナーを対象とした「The CORE」というプログラムも存在する 38。アスリートの移行が、選手個人だけでなく家族全体の問題であるという深い理解に基づいた、真に全人格的なサポートと言える。
4.3. グローバルスタンダード:IOC「Athlete365 Career+」が示す3つの柱
国際オリンピック委員会(IOC)は、人材サービス企業アデコ社と協力し、世界中のアスリートに向けたキャリアプログラム「Athlete365 Career+」を展開している 42。このプログラムは、各国のオリンピック委員会(NOC)がキャリア支援を導入・拡充するためのグローバルスタンダードとなっている。
その内容は、①教育(Education)、②ライフスキル(Life Skills)、**③雇用(Employment)**という3つの柱に基づいている 42。教育では競技と両立可能な学習機会を奨励し、ライフスキルでは資産形成や広報対応能力の向上を図る。そして雇用では、履歴書の書き方や面接の技術といった具体的な就職スキルを提供する。これらのコンテンツは「Athlete365」というオンラインプラットフォームを通じて、世界中の多くのアスリートがアクセス可能となっており、キャリア支援の基礎的な枠組みを示している 10。
これらの国際モデルを分析すると、日本の伝統的なアプローチとの間には、支援を「いつ」「どのように」行うかという点で根本的な違いが見えてくる。海外の先進モデルは、キャリア開発をアスリートの人生の一部として初期段階から統合する**「能動的・統合的」アプローチを取る。一方、日本のモデルは、引退という問題が発生してから対処する「受動的・分離的」**な側面が強かった。この能動的な統合こそが、アスリートがキャリアの移行期に直面する心理的・実務的な衝撃を和らげる鍵である。
また、支援体制の背景にある資金構造の違いも重要である。NFLPAの強力な支援は、数十億ドル規模の巨大産業における選手会の交渉力と潤沢な資金によって実現されている 38。このような構造は、中央集権的な収益源を持たない多くのオリンピック競技や、日本のスポーツエコシステムでは再現が難しい。日本の支援が、JOCやJSAといった統括団体、あるいは個別企業のスポンサーシップに依存せざるを得ないのは、この経済的背景の違いが大きく影響している。
V. 国内外の支援体制の比較分析:何が違うのか?
これまで見てきた日本と海外の支援体制には、単なるプログラム内容の違いを超えた、哲学、介入時期、支援の焦点における構造的な差異が存在する。国際モデルが、キャリア準備をアスリートの成長の一部と見なす**「能動的・発達的・全人格的」アプローチへと進化しているのに対し、日本の伝統的なモデルは、引退後の問題を解決するための「受動的・就職斡旋的」**な性格を帯びてきた。
この違いは、支援の具体的な焦点にも明確に現れる。日本の「アスナビ」に代表されるモデルは、現役アスリートが競技を継続するための経済的安定確保を主眼に置く。つまり、仕事はスポーツを支えるための「手段」である。対照的に、オーストラリアのACEプログラムや米国のNFLPAモデルは、競技引退後のキャリアで成功するためのスキル、学歴、アイデンティティの構築に焦点を当てる。ここでは、スポーツは未来の成功への「土台」と見なされる。
支援を主導する組織も異なる。米国では選手会(NFLPA)が、オーストラリアでは政府系機関(AIS)が強力なイニシアチブを発揮する。日本では、JOC、Jリーグ、スポーツ庁といった複数の組織がそれぞれ活動しており、前述の通り「パッチワーク」的な構造となっている。
これらの差異を以下の表にまとめる。
| 特徴 | 日本モデル(JOC/Jリーグ中心) | 米国モデル(NFLPA) | 豪州モデル(ACE) |
| 基本理念 | 競技生活の安定化、引退後の生活保障 | 選手個人の権利擁護、生涯にわたるウェルビーイング | デュアルキャリア、全人格的育成(Holistic Development) |
| 介入時期 | 伝統的には引退前後。近年、若年層への早期化が進む(Jリーグ) | 現役中から積極的 | キャリア初期から一貫して |
| 主要な焦点 | 就職斡旋、雇用確保 | スキル開発、学費補助、金融教育、メンタルヘルス | 教育との両立、キャリアプランニング、アイデンティティ形成 |
| 主なプログラム | アスナビ(就職マッチング)、新人研修、キャリア教育(Jリーグ) | 企業インターンシップ、学費補助制度、金融・法律相談、家族支援 | 個別カウンセリング、学業サポート、スキルアップ講座、移行支援 |
| 支援の主体 | JOC、各競技団体、スポーツ庁 | 選手会(Players’ Association) | 政府系スポーツ専門機関(AIS) |
| 資金源 | 企業スポンサー、団体予算、国の委託事業費 | リーグ収益からの分配金(選手会費) | 税金(政府予算) |
この表は、日本と海外の先進モデルとの間の体系的な違いを浮き彫りにする。それは単にプログラムの優劣ではなく、アスリートのキャリアをどのように捉え、社会全体でどう支えていくかという、より根本的なビジョンの違いを示している。この比較を通じて、日本のシステムが今後どのような方向に進化すべきかの輪郭が明確になる。
VI. 成功と失敗の分岐点:事例から学ぶセカンドキャリアの要諦
制度やシステムがいかに整備されようとも、最終的に移行を成功させるのはアスリート自身である。国内外の具体的な事例は、成功と失敗を分ける要因がどこにあるのかを雄弁に物語っている。
6.1. 成功への多様な道筋:競技で培ったスキルの転用
引退後のキャリアパスは、決して一つではない。成功者たちは、競技生活で培った経験やスキルを、多様な形で新たな舞台へと転用している。
- 起業家への転身:元サッカー日本代表の鈴木啓太氏は、現役時代から抱いていたコンディション管理への関心から、腸内細菌を研究する「AuB株式会社」を設立した 45。元中国代表のスン・チーハイ氏はスポーツデータ会社を共同設立し 4、伝説的ボクサーのジョージ・フォアマン氏は家庭用グリル機の販売で大成功を収めた 7。彼らは自らの知名度と経験を、新たなビジネスの駆動力へと変換した。
- 専門職への道:競技とは全く異なる分野で成功を収めるには、再教育への強い意志が求められる。元阪神タイガースの投手であった奥村武博氏は、9年間の猛勉強の末に公認会計士試験に合格した 24。元プレミアリーグFWのロブ・ハルス氏は、大学で理学療法を学び、国民医療サービス(NHS)の理学療法士として活躍している 4。
- スポーツ界での新たな役割:指導者や解説者、競技団体の職員として、引き続きスポーツ界に貢献する道も王道の一つである 13。
- 社会貢献・公職:元ボクシング世界王者のマニー・パッキャオ氏はフィリピンの上院議員となり 7、元五輪金メダリスト体操選手のケリー・ストラッグ氏は米国司法省のプログラムマネージャーとして社会に貢献している 7。彼らはその影響力を、より広い公共の利益のために活用している。
6.2. 避けるべき落とし穴:失敗事例に共通する要因分析
一方で、セカンドキャリアでつまずくアスリートも後を絶たない。その失敗には、いくつかの共通した要因が見られる。
- 準備不足と情報不足:現役時代の成功体験のまま、経営知識や市場調査なしに飲食店などを開業し、短期間で失敗に追い込まれるのは典型的なパターンである 47。
- 心理的な障壁:「元プロ」というプライドが邪魔をして、新しい環境で謙虚に学ぶ姿勢を持てなかったり 16、逆に「スポーツしかしてこなかった」という過度の卑下が、新たな挑戦への意欲を削いでしまったりする 18。
- 金融リテラシーの欠如:これは最も深刻な問題の一つである。現役時代の高額な収入を浪費やずさんな投資、信頼できないアドバイザーによって失い、引退後数年で破産に追い込まれる事例は枚挙にいとまがない 49。
- 競技への近すぎる距離感:引退後すぐに、同じ競技のコーチやスタッフなど、選手ではない立場で関わることは、心理的な切り替えを難しくすることがある。現役選手を間近に見ることで、過去への未練が断ち切れず、新しいキャリアに集中できなくなるリスクがある 16。
これらの事例から導き出される重要な示唆は、「アスリートが持つ強みは、自動的にビジネススキルにはならない」という事実である。規律や忍耐力といった資質は、あくまで「原材料」であり、それだけでは不十分だ。成功事例を見ると、奥村氏やハルス氏のように、専門教育を通じてその資質を新たな専門知識へと意識的に「翻訳」するプロセスを経ている 4。アスリートの強みがビジネスに「自然に」活かせるという安易な言説は、時に危険ですらある。支援プログラムは、この「翻訳プロセス」そのものに焦点を当てるべきである。
さらに、この議論では女性アスリートが直面する特有の課題が見過ごされがちである。ジェンダーによる偏見、メディアによる容姿への過度な注目、競技引退後の身体イメージの変化に伴う精神的苦痛、そして出産や育児といったライフイベントとの両立など、男性アスリートとは異なる、あるいはより複合的な困難が存在する 53。例えば、キャリアの継続と家庭形成の選択は、女性アスリートにとってより切実な問題となりうる。したがって、「ワンサイズ・フィッツ・オール(画一的)」な支援は不十分であり、女性アスリート特有の生物学的、社会的、経済的現実に配慮した、きめ細やかなサポート体制が不可欠である。
VII. 【あるべき論】アスリートのセカンドキャリアの未来に向けた提言
これまでの国内外の事例と支援体制の比較分析を踏まえ、アスリートのキャリア移行をより健全で持続可能なものにするための「あるべき論」を、アスリート自身、スポーツ団体、そして社会という3つの層に向けて提言する。
7.1. アスリート自身へ:「デュアルキャリア」意識の早期醸成と主体的計画
移行の主体は、あくまでアスリート自身である。受け身の姿勢では、いかなる支援も効果を最大化できない。
- 意識の変革:キャリアの早い段階から、「スポーツだけ」のアイデンティティではなく、「一人の人間」としてのアイデンティティを育む意識を持つことが重要である。競技以外の趣味や学習、社会との接点を積極的に持つべきである 9。
- 金融リテラシーの習得:高収入かつ短期間というプロアスリートのキャリアの特性を自覚し、資産管理を他者に丸投げせず、自ら主体的に学ぶ必要がある。予算管理、投資、そして引退後の生活設計に関する知識は、競技スキルと同様に重要である 49。
- 支援制度の能動的活用:問題が起きてからではなく、現役中からキャリアアドバイザーやメンターに相談し、利用可能な支援制度を積極的に活用するべきである。プライドが助けを求めることを妨げる最大の敵となりうることを認識する必要がある 18。
7.2. スポーツ団体へ:就職斡旋から全人格的育成へのパラダイムシフト
スポーツ団体は、アスリートのキャリア支援を「福利厚生」ではなく、「人材育成戦略」の中核と位置づけるべきである。
- 哲学の導入:オーストラリアのACEプログラムが示すように、「全人格的な育成が競技力を向上させる」という哲学を導入し、キャリア準備を競技の妨げではなく、パフォーマンス向上の一環として位置づけるべきである 37。
- 義務教育化:Jリーグが先鞭をつけたように、アカデミーやユース年代からキャリア教育や金融リテラシー教育を必須プログラムとして組み込むべきである 20。
- プログラムの進化:「アスナビ」のような就職マッチングに留まらず、NFLPAモデルを参考に、企業と連携した体系的な「就業体験プログラム」を創設し、実践的なスキルと人脈形成の機会を提供するべきである 39。
- メンタルヘルス支援の専門化:アイデンティティの喪失や移行期の不安に特化した、専門的なメンタルヘルスサポート体制の構築と、その利用の推奨が急務である 5。
7.3. 社会(企業・教育機関)へ:アスリートの価値の再定義と受入環境の整備
アスリートのキャリア移行は、スポーツ界だけで完結する問題ではない。社会全体の理解と協力が不可欠である。
- 企業:アスリート採用を、社会貢献(CSR)やマーケティング活動の一環としてのみ捉えるのではなく、彼らが持つリーダーシップや目標達成能力といったポテンシャルを評価し、将来のリーダー候補として育成する視点を持つべきである。ただし、そのためには、アスリートの特性を理解した上での体系的な研修や受け入れ体制の整備が前提となる。
- 教育機関:トップアスリートの厳しいトレーニングスケジュールに対応できる、より柔軟な学業プログラムを提供することが求められる。これは、ACEプログラムやIOCのモデルでも重要な要素とされている 37。
- メディア:競技での勝利や栄光だけでなく、引退後の多様なキャリアパスやデュアルキャリアの重要性についても光を当て、成功事例を広く報道するべきである。これにより、社会全体の認識が変わり、若いアスリートたちがキャリアについて考えるきっかけが生まれる。
究極的に、この問題の解決策は単一の完璧なプログラムにあるのではなく、アスリート、スポーツ団体、教育機関、企業、そして政府がそれぞれの役割と責任を共有し、効果的に連携する「エコシステム(生態系)」の構築にある。各主体が孤立して活動するのではなく、アスリートのキャリア移行を社会全体の共有財産として捉え、協働すること。これこそが、持続可能な未来に向けた最も重要な提言である。
VIII. 結論:アスリートの人生を豊かにすることが、スポーツの価値を高める
本稿で明らかにしてきたように、アスリートのセカンドキャリアにおける成功は、引退後に始まる偶発的な出来事ではなく、現役時代から始まる能動的かつ全人格的な育成プロセスの賜物である。その鍵は、引退という事象に反応して就職先を探す「受動的・斡旋的モデル」から、アスリートの生涯にわたる成長を見据えて準備を進める「能動的・発達的エコシステム」へと、発想を根本から転換することにある。
この転換は、単にアスリート個人の人生を救済するための福祉的な課題ではない。それは、スポーツそのものの価値と持続可能性を高めるための戦略的な投資である。アスリートが競技生活を終えた後も、社会の様々な分野で輝き、充実した人生を送ることができる。そのような姿を社会が目の当たりにするとき、スポーツを志すことは、若者にとってより魅力的で、尊敬されるべき道となる。
結果として、スポーツ界にはより多様な才能が集い、ファンやスポンサーからの支持も厚くなり、スポーツ文化全体が豊かになる。アスリート一人ひとりの人生を豊かにすること。それこそが、スポーツの価値を未来永続的に高めていくための、最も確かな道筋なのである。
引用文献
- トップ・アスリートへのセカンド・キャリア支援 – 福山大学学術情報リポジトリ, 6月 29, 2025にアクセス、 https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/record/8453/files/%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%94%AF%E6%8F%B4%EF%BC%8DJOC%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E7%AD%96%E3%82%92%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%AB%EF%BC%8D%E3%80%80%E7%9B%B8%E5%8E%9F%E6%AD%A3%E9%81%93%E3%83%BB%E4%BC%8A%E5%90%B9%E5%8B%87%E4%BA%AE.pdf
- ISSP POSITION STAND: CAREER DEVELOPMENT AND TRANSITIONS OF AThLETES, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.port.ac.uk/sites/default/files/2023-02/Career_Development_and_Transitions_of_Athletes.pdf
- (PDF) Athlete career transitions: a systematic review and future …, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/386998540_Athlete_career_transitions_a_systematic_review_and_future_directions_for_sport_management_research
- セカンドキャリアも充実…サッカー界以外で活躍する元スター選手たち, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.soccer-king.jp/news/world/eng/20230830/1803853.html
- Critical Issues in the Process of the Career Development and Transition of Athletes | Frontiers Research Topic, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/research-topics/59859/critical-issues-in-the-process-of-the-career-development-and-transition-of-athletes/magazine
- From the Field to the Future: Managing Athlete Transition – Success Coach, 6月 29, 2025にアクセス、 https://successcoach.com/from-the-field-to-the-future-managing-athlete-transition/
- 政治家から警備員まで!アメリカのプロスポーツに見るセカンドキャリア 15の先行事例【TranSport】, 6月 29, 2025にアクセス、 https://note.com/gokatsu/n/nc18b30fa4c0c
- アスリートのセカンドキャリアに関する考察 A Study of the Career of Athlete after Retirement 1K08B152-7 根 – tokorozawa, 6月 29, 2025にアクセス、 https://tokorozawa.w.waseda.jp/kg/doc/20//sotsuron2011/1K08B152.pdf
- Athlete Career Transition Services – Leslie Leadership, 6月 29, 2025にアクセス、 https://nateleslie.ca/athlete-career-transition-services/
- Life after Sports: a Career Transition Program for Graduating Collegiate Student-Athletes – ISU ReD, 6月 29, 2025にアクセス、 https://ir.library.illinoisstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2950&context=etd
- Full article: High-performance athletes’ transition out of sport: developing corporate social responsibility – Taylor & Francis Online, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19406940.2023.2242877
- Life After Sport: Athletic Career Transition and Transferable Skills – ResearchGate, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/228931530_Life_After_Sport_Athletic_Career_Transition_and_Transferable_Skills
- プロ野球選手の引退後は?セカンドキャリアについて徹底解説 – ATHLETE LIVE, 6月 29, 2025にアクセス、 https://athlete-live.com/category_jobchange/baseball-secondcareer/
- アスリートのキャリアに関する実態調査 結果まとめ, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.mext.go.jp/sports/content/20200508-spt_sposeisy-300001067_2.pdf
- Career transition – Olympics.com, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.olympics.com/athlete365/learning/career-transition
- セカンドキャリアに失敗するサッカー選手の10の特徴|白洲 – note, 6月 29, 2025にアクセス、 https://note.com/shirasuaimar21/n/n2c08309582fc
- 引退アスリートのキャリア成功の鍵 | レガシー共創 | 実践知の創造 | ナレッジ・コラム, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.mri.co.jp/knowledge/wisdom/legacy/column/index.html
- セカンドキャリアに失敗するアスリートの特徴から見る正しい就活のやり方 – キャリチャン, 6月 29, 2025にアクセス、 https://zca-service.com/column/22345/
- Jリーグにおけるキャリアの転機 – 労働政策研究・研修機構, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2010/10/pdf/016-026.pdf
- プロサッカー選手のキャリアサポート – CORE, 6月 29, 2025にアクセス、 https://core.ac.uk/download/pdf/228688898.pdf
- 【公式】Jリーグ公式サイト(J.LEAGUE.jp), 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.jleague.jp/sp/100year/cultivation/
- 【公式】キャリア・デザイン・サポート・プログラム:About Jリーグ, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.jleague.jp/sp/aboutj/secondcareer/
- アスリートのキャリア支援|アスリートサポート|JOC – 日本 …, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.joc.or.jp/for-athletes/career/
- スポーツ選手がセカンドキャリアで成功する秘訣を解説!実際の選択肢も紹介。 – 創業手帳, 6月 29, 2025にアクセス、 https://sogyotecho.jp/athlete-career/
- 企業のアスリート支援の現状と課題 SPORT POLICY INCUBATOR(48) – 笹川スポーツ財団, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.ssf.or.jp/knowledge/spi/48.html
- アスナビ5年間の軌跡と 今後のアスリートと 企業の関係を考える – 経済同友会, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.doyukai.or.jp/publish/2016/pdf/2016_6_06.pdf
- ファントモプロジェクト – 日本プロ野球選手会, 6月 29, 2025にアクセス、 https://jpbpa.net/fantomo/
- プロ野球選手のセカンドキャリア支援サービス「イーキャリアNEXTFIELD」を開始 | プレスリリース – SB Human Capital, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.softbankhc.co.jp/press/press_release/article/21
- 力士のセカンドキャリアを考えてみる① | 《毎日!大相撲!》Everyday!OZUMOU!, 6月 29, 2025にアクセス、 https://ameblo.jp/niwatani2015/entry-12867319930.html
- 合うかどうかはやってみないとわからない 元力士の上河啓介さんがセカンドキャリアで介護施設経営者を選んだワケ | WORK MILL, 6月 29, 2025にアクセス、 https://workmill.jp/jp/webzine/kamikawa-20230407/
- 相撲界のセカンドキャリア整備を。学生力士たちが公務員と迷う現状。(2 – Number Web, 6月 29, 2025にアクセス、 https://number.bunshun.jp/articles/-/830940?page=2
- スポーツキャリアサポート戦略:スポーツ庁, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/detail/1419295.htm
- 現役時代から始めるアスリートのキャリア形成〜スポーツキャリアサポート支援事業, 6月 29, 2025にアクセス、 https://sports.go.jp/tag/policy/post-133.html
- アスリートのキャリアに新たな光を! 競技の枠を超えアスリートと共に考えるアスリートの未来, 6月 29, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000073531.html
- スポーツキャリアサポート支援事業:スポーツ庁, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/detail/1419295_00003.html
- アスリート雇用について | パラ卓球 七野一輝 オフィシャルブログ, 6月 29, 2025にアクセス、 https://ameblo.jp/7kazushichi1102ptt/entry-12770384042.html
- トップアスリートのセカンドキャリア構築に関する検討, 6月 29, 2025にアクセス、 https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/15236/files/10.pdf
- Career Development | NFLPA, 6月 29, 2025にアクセス、 https://nflpa.com/active-players/career-development
- Career Experiences | NFLPA, 6月 29, 2025にアクセス、 https://nflpa.com/active-players/careerexperiences
- Career Advising Services | NFLPA, 6月 29, 2025にアクセス、 https://nflpa.com/active-players/career-action-plan
- The CORE | NFLPA, 6月 29, 2025にアクセス、 https://nflpa.com/the-core
- IOC Athlete Career Programme – ISSF – International Shooting Sport Federation, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.issf-sports.org/athletes/ioc-career-programme
- IOC Athlete’s Career Programme after 10 years – Olympics.com, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.olympics.com/en/video/ioc-athlete-s-career-programme-10-years
- IOC Athlete Career Programme – Inside FEI, 6月 29, 2025にアクセス、 https://inside.fei.org/system/files/Dual_Career_Forum_by_IOC.pdf
- スポーツ選手が悩みやすいセカンドキャリア!起業するメリットや注意点を解説 – 創業手帳, 6月 29, 2025にアクセス、 https://sogyotecho.jp/athlete-secondcareer/
- スポーツ選手のセカンドキャリア成功例、再現性はあるのか?, 6月 29, 2025にアクセス、 https://wlexpo.jp/athlete-career-success/
- アスリートのセカンドキャリア失敗例5選とその教訓 – WLEXPOスポーツナビ, 6月 29, 2025にアクセス、 https://wlexpo.jp/athlete-career-failure/
- アスリートがセカンドキャリアに失敗する3つの要因, 6月 29, 2025にアクセス、 https://athletica.j-sc.org/posts/TOPICS113
- The Costly Fall of Fame: 5 Professional Athletes Who Lost It All, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.onebridgewealth.com/blog/the-costly-fall-of-fame-5-professional-athletes-who-lost-it-all
- Personal finances of professional American athletes – Wikipedia, 6月 29, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_finances_of_professional_American_athletes
- 5 Athletes Who Went Broke After Retirement, and How You Can Avoid Doing This, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.thestreet.com/retirement/five-athletes-who-went-broke-after-retirement-14551395
- Pro athletes who are broke : r/stories – Reddit, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/stories/comments/1d2guj7/pro_athletes_who_are_broke/
- The Hidden Struggles of Female Athletes – What You Don’t See on Game Day, 6月 29, 2025にアクセス、 https://runningforwellness.com/hidden-struggles-of-female-athletes/
- Transitioning Out of Sport for Collegiate Female Athletes: Individual and Organizational Implications – Scholar Commons, 6月 29, 2025にアクセス、 https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1291&context=jiia
- 女性アスリートのセカンドキャリア問題について – 高田短期大学, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.takada-jc.ac.jp/files/activity/career/kiyou4/6.pdf
- Life After Sport – USOPC, 6月 29, 2025にアクセス、 https://www.usopc.org/lifeaftersport