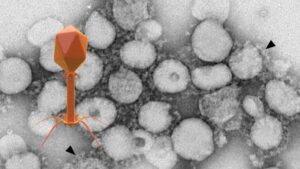はじめに:一つの時代の終わりと、あなたが使うブラウザの「知られざる物語」
2022年6月15日、MicrosoftはInternet Explorer(IE)のサポートを正式に終了しました。多くのユーザーにとって、それはデスクトップに長年存在した「e」のアイコンが、ついにその役目を終えた日でした。しかし、この出来事は単なる一ソフトウェアの引退以上の意味を持っています。それは、ウェブという広大な世界を切り拓き、一時はその95%以上を支配した巨大な帝国の終焉であり、一つの時代の終わりを象徴する歴史的な転換点でした 1。
かつて、インターネットに接続することは、IEを起動することとほぼ同義でした。しかし、今日の私たちはGoogle Chrome、Safari、Firefoxなど、多様な選択肢の中からブラウザを選んでいます。なぜ、あれほどまでに圧倒的な力を持っていたIEは歴史の舞台から姿を消したのでしょうか?そして、現在の覇者であるGoogle Chromeは、一体何が違ったのでしょうか?
その答えは、単なる機能の優劣やデザインの違いに留まりません。ウェブブラウザの約30年にわたる進化の歴史は、技術革新をめぐる熾烈な「戦争」、企業の野望がぶつかり合う戦略、そして「ウェブとはどうあるべきか」という思想的な対立が織りなす、壮大な物語なのです。この物語は、私たちが今日、当たり前のように利用しているインターネットの姿を直接的に形作ってきました。
本稿では、国外の文献や技術資料を基に、この「知られざる物語」を深く掘り下げていきます。ウェブの黎明期に現れた最初の覇者から、IE帝国の誕生と停滞、オープンソースの挑戦者、そしてChromeによる技術革命まで。私たちが毎日使うブラウザのアイコンの裏に隠された、壮絶な進化の歴史を、一挙に解説します。これは、過去のソフトウェアの単なる追悼記事ではありません。あなたのデジタルライフの「今」を理解するための、歴史の探求です。

第1章:ウェブの夜明けと最初の覇者――Netscape Navigatorの時代
今日の私たちが知る豊かなウェブの世界が誕生する前、インターネットは主に大学や研究機関で使われる、文字ベースの無骨なネットワークでした。しかし1990年代初頭、すべてを変える一つの技術が登場します。それがグラフィカル・ウェブブラウザです。
ウェブに火をつけた「キラーアプリケーション」:NCSA Mosaic
ウェブの爆発的な普及の引き金となったのは、1993年に米国立スーパーコンピュータ応用研究所(NCSA)で開発された「NCSA Mosaic」でした 4。それまでのブラウザがテキストと画像を別々のウィンドウで表示していたのに対し、Mosaicは世界で初めて、一枚のページ内にテキストと画像を一緒に表示(インライン表示)することに成功しました 5。
この革新は、ウェブを単なる学術文書の集合体から、視覚的な魅力を持つマルチメディア体験へと変貌させました。技術者ではない一般のユーザーでも、ダウンロードして簡単にインストールできるMosaicは、まさにインターネットの「キラーアプリケーション」となり、ウェブは「Mosaic以前と以後」で全く異なる世界になったのです 4。
最初の巨人:Netscape Navigatorの登場
この歴史的なプロジェクトを学生として率いていたのが、マーク・アンドリーセンという若きプログラマーでした。彼はMosaicの可能性を確信し、NCSAを去ると、シリコングラフィックス社の共同設立者であったジム・クラークと共に、1994年にMosaic Communications(後のNetscape Communications)を設立します 4。
そして同年末にリリースされたのが「Netscape Navigator」です。Mosaicをさらに洗練させたこのブラウザは、瞬く間に市場を席巻し、ピーク時には90%以上という驚異的なシェアを獲得しました 7。Netscape Navigatorは単に使いやすいだけでなく、今日のウェブ技術の基礎となる多くの革新をもたらしました。ウェブページに動的な機能を与える「JavaScript」、安全な通信を可能にする「SSL暗号化」、そしてユーザー情報を記憶する「Cookie」といった技術は、すべてNetscapeが導入したものです 7。
Netscapeの成功は技術的な側面だけにとどまりませんでした。1995年8月に行われた同社の新規株式公開(IPO)は、当時としては史上最大級の規模となり、ウォール街にインターネットの時代の到来を告げました 9。これは、後に「ドットコム・バブル」と呼ばれる熱狂の始まりを告げる号砲でもありました。
Netscapeの成功の根底には、技術力だけでなく、その哲学がありました。彼らはベータ版をウェブサイトで広く公開し、ユーザーからのフィードバックを積極的に取り入れることで、バグを迅速に修正しました 8。この手法は、当時まだ黎明期にあったウェブの「オープンで協調的な精神」と深く共鳴するものでした。Netscapeは単に優れた製品を作っただけでなく、ウェブと共に成長するコミュニティを築き上げたのです。この開放的な思想は、後に登場するMicrosoftの閉鎖的な戦略と、鮮やかな対比をなすことになります。
第2章:第一次ブラウザ戦争――Microsoftの逆襲とIE帝国の誕生
Netscape Navigatorがウェブの世界で絶対的な覇権を握っていた頃、パーソナルコンピュータ市場の巨人、Microsoftはインターネットの重要性を見過ごしていました。しかし、NetscapeのIPOが巻き起こした熱狂は、彼らを眠りから覚まさせます。
Microsoftの覚醒と「インターネットの津波」
1995年5月、Microsoftの共同設立者であるビル・ゲイツは、「The Internet Tidal Wave(インターネットの津波)」と題された有名な社内メモを発信しました 8。このメモの中で彼は、Netscapeを「インターネット上で生まれた新たな競争相手」と位置づけ、「彼らの製品に匹敵し、打ち負かさなければならない」と全社員に檄を飛ばしました。PC市場の王者が、ついにウェブという新たな戦場に目を向けた瞬間でした。
Microsoftの反撃は迅速かつ強力でした。彼らはまず、Mosaicのライセンスを持つSpyglass社から技術を買い取り、それをベースに自社ブラウザ「Internet Explorer 1.0」を開発。1995年8月、NetscapeのIPOからわずか数日後に、Windows 95の追加パッケージとしてリリースしました 4。
決定的な戦略:OSへのバンドルと無料配布
MicrosoftがNetscapeを打ち負かすために用いた戦略は、技術的な優位性ではなく、圧倒的なビジネスモデルの差でした。その核心は、IEを自社のOSであるWindowsに「バンドル(同梱)」し、「無料」で配布することでした 4。
当時、WindowsはPCのOS市場で95%以上のシェアを誇っていました 4。つまり、新しくPCを購入したほぼすべてのユーザーは、最初からIEがインストールされた状態で手に入れることになります。一方、Netscapeはブラウザを有料で販売することで収益を得ていました 10。OSとOffice製品のライセンス販売で莫大な利益を上げていたMicrosoftにとって、ブラウザを無料で提供することは痛くも痒くもありません。しかし、これがNetscapeにとっては致命傷となりました。ユーザーは、わざわざお金を払って別のブラウザをダウンロードする必要がなくなったのです 10。
Microsoftの戦略は、時に露骨なものでした。1998年の独占禁止法訴訟では、Microsoftの幹部が1995年に「Netscapeの空気供給を断つ(cut off Netscape’s air supply)」という意図を語っていたことが証言されています 4。
「機能炎」とウェブの分断
ここから、「第一次ブラウザ戦争」として知られる熾烈な開発競争が始まります 13。両社は互いを打ち負かすため、毎月のように新バージョンをリリースし、次々と新機能を追加していきました。この過剰な機能追加競争は「featuritis(機能炎)」と揶揄されました 10。
問題は、これらの機能の多くが、標準化されていない「独自拡張」だったことです。Netscapeでしか動かない機能、IEでしか動かない機能が乱立し、ウェブは二つの世界に分断されてしまいました。ウェブ制作者は、どちらかのブラウザで正しく表示されるようにサイトを作ることを強いられ、その結果、多くのサイトには「Best viewed in Netscape」や「Best viewed in Internet Explorer」といったロゴが掲げられるようになりました 4。この競争の激しさを象徴する出来事として、1997年にIE4.0をリリースしたMicrosoftが、高さ3メートルの巨大な「e」のロゴをNetscape本社の芝生に設置するという挑発行為を行ったエピソードは有名です 4。
IE帝国の完成と独占禁止法訴訟
Microsoftの圧倒的な物量作戦とバンドル戦略の前には、技術で先行していたNetscapeもなすすべがありませんでした。1998年、Netscapeはついにブラウザの無料化に踏み切りますが、時すでに遅く、主要な収益源を失った同社は同年、大手インターネットプロバイダーのAOLに買収されます 4。
一方、IEのシェアは急上昇を続け、2001年にはピークとなる96%に達し、IE帝国が完成しました 7。このMicrosoftの行為は、市場の公正な競争を阻害するとして、米国司法省と20州の司法長官から独占禁止法違反で提訴されるという大きな社会問題に発展しました 10。
この第一次ブラウザ戦争は、単なる製品のシェア争いではありませんでした。それは、OSという既存のプラットフォームの力を利用して、ウェブという新たなプラットフォームの支配権を握ろうとする戦いでした。ウェブサイトがIEでしか正しく動かないのなら、そのユーザーにとってIEこそがウェブそのものになります。Microsoftは、自社のブラウザをウェブへの唯一の「ゲートウェイ」にすることで、デジタル経済のインフラをコントロールしようとしたのです。そして、その戦いに彼らは勝利しました。
第3章:帝国の停滞とIEの本質――TridentエンジンとActiveXの功罪
第一次ブラウザ戦争に勝利し、市場を完全に手中に収めたMicrosoftでしたが、その勝利は皮肉な結果をもたらします。絶対的な王座に君臨したIEは、競争相手を失ったことで、その進化を止めてしまったのです。この「帝国の停滞」こそが、後にIEが「遅い、時代遅れ、危険」という不名誉な評判を背負うことになる根本的な原因でした 1。
技術的深掘り:IEの心臓部「Trident」エンジン
IEの中核をなしていたのが、「Trident」(MSHTMLとも呼ばれる)というMicrosoft独自のレンダリングエンジンです。1997年のIE4で初めて搭載されたこのエンジンは、単なるブラウザの部品ではありませんでした 15。Tridentは、Windowsの基本的なプログラム部品技術であるCOM(Component Object Model)コンポーネントとして設計されており、開発者は自分のアプリケーションにウェブブラウジング機能を簡単に組み込むことができました 15。
実際に、メールソフトのOutlook、百科事典ソフトのEncarta、さらには多くの企業の基幹システムなど、数え切れないほどのWindowsアプリケーションが、内部でTridentエンジンを利用してHTMLコンテンツを表示していました 15。このOSや他のアプリケーションとの深い統合こそが、IEが長年にわたってWindows環境に深く根を張り続けた理由であり、その最大の強みでした。
諸刃の剣:ActiveXの功罪
IEのもう一つの特徴であり、その功罪を最も象徴する技術が「ActiveX」です 12。これもCOMアーキテクチャをベースにした技術で、ウェブページ上でネイティブアプリケーションに近い強力なプログラム(ActiveXコントロール)を実行できるようにするものでした。
その「功」は、当時としては革新的なウェブ体験を可能にした点です。動画再生、複雑なデータ入力フォーム、インタラクティブなアニメーションなど、ActiveXはウェブを単なる情報閲覧の場から、リッチなアプリケーションプラットフォームへと引き上げました。多くの企業や政府機関が、業務システムをIE専用に構築したのは、このActiveXが提供する強力な機能があったからです 12。
しかし、その「罪」は、セキュリティにおける致命的な欠陥でした。今日のブラウザ技術が「サンドボックス」という安全な隔離環境でプログラムを実行するのとは対照的に、ActiveXコントロールはOS上でほぼ無制限の権限(フルパーミッション)で動作しました 15。これは「信頼ベース」のセキュリティモデルであり、一度信頼されたコントロールは、PC内のファイルへのアクセスや設定の変更など、何でもできてしまいます。もしそのコントロールに一つでも脆弱性があれば、それはシステム全体を危険に晒す「バックドア」となり得ました 17。
IEが「セキュリティホールだらけ」という悪評を得た最大の原因は、このActiveXの根本的な設計思想にあります。Microsoftは、既知の悪意あるコントロールを無効化する「Killbit」という仕組みを導入しましたが、それはあくまで対症療法に過ぎず、根本的な問題の解決にはなりませんでした 18。
技術的負債という名の呪縛
IEのOSとの深い統合という強みは、結果的にその最大の弱点となりました。Tridentエンジンの独自仕様やActiveXへの依存は、「IEでしか動かない」という膨大な数のレガシーな社内システムやウェブアプリケーションを生み出しました。これは「ベンダーロックイン」と呼ばれる現象であり、企業はIEから離れたくても離れられない状況に陥りました 1。
この問題は、IEの公式サポートが終了した現在でも続いています。Microsoftが最新ブラウザであるEdgeに、わざわざ「IEモード」という機能を搭載しているのは、このTridentエンジンを使って古いウェブサイトを正しく表示させるためです 16。IEが残した「技術的負債」は、今なお多くの企業を縛り付けているのです。
IEの勝利を確実にしたOSとの統合というアーキテクチャは、ブラウザの更新サイクルをOSのリリースサイクルに縛り付け、迅速な革新やセキュリティ対応を困難にしました。そして、ブラウザの脆弱性がOS全体の脆弱性に直結する構造は、絶えず変化し、より危険になっていくウェブの世界に対応できなくなっていきました。IEは、自らが作り上げた時代の変化に、自らが追いつけなくなったのです。
第4章:反撃の狼煙――オープンソースの雄、Firefoxの誕生
IEが市場を独占し、ウェブの進化が停滞していた2000年代初頭、水面下では反撃の準備が進められていました。その狼煙を上げたのは、かつての覇者Netscapeの「遺産」でした。
Netscapeの灰の中から
第一次ブラウザ戦争で敗色濃厚となったNetscapeは、自社のブラウザのソースコードをオープンソース化し、非営利団体「Mozilla Foundation」を設立するという、極めて重要な決断を下しました 5。これは、たとえ企業としては敗北しても、競争の火を絶やさず、オープンなウェブの精神を守り抜こうとする最後の抵抗でした。
このMozillaプロジェクトから生まれたのが、後に世界を席巻することになるブラウザです。当初、この新しいブラウザは、Netscapeの灰の中から蘇るという意味を込めて「Phoenix」というコードネームで呼ばれていました。商標の問題から「Firebird」へ、そして最終的に「Firefox」へと名前を変えることになりますが、その誕生の理念は一貫していました 4。2004年に正式リリースされたFirefoxは、IEの独占に終止符を打ち、ユーザーに選択肢を提供し、オープンなウェブを取り戻すという明確な目的を持っていました 22。
標準を掲げる「Gecko」エンジン
Firefoxの心臓部となったのが、「Gecko」と呼ばれるレンダリングエンジンです 24。その開発は、Netscape時代に、古く低速だった自社のエンジンを置き換えるために始まっていました 25。IEのTridentエンジンが独自拡張を優先したのとは対照的に、Geckoは開発当初からW3C(World Wide Web Consortium)が定めるウェブ標準への準拠を強く意識していました 25。
これにより、ウェブ開発者はブラウザごとの「癖」に悩まされることなく、一度書いたコードが異なるブラウザでも同じように動作することを期待できるようになりました。Geckoは、分断されたウェブを再び一つに繋ぎ合わせる、標準化の旗手となったのです。
帝国への挑戦と第二次ブラウザ戦争
Firefoxは、IEの独占にうんざりしていたユーザーから熱狂的に支持されました。その理由は、IEが失ってしまったもの、すなわち「スピード」「セキュリティ」「カスタマイズ性」にありました。軽快な動作、当時としては画期的だったポップアップブロック機能、そして「アドオン」と呼ばれる拡張機能によってユーザーが自由に機能をカスタマイズできる点が、大きな魅力となりました 7。
Firefoxは驚異的な速さでシェアを伸ばし、IEの牙城に風穴を開けました。2004年には90%以上あったIEのシェアを、2010年までには50%まで引き下げることに成功します 22。このFirefoxの台頭から、後にGoogle Chromeが参入して三つ巴となる時代を「第二次ブラウザ戦争」と呼びます 4。
「Quantum」による自己革新
時代が下り、今度はGoogle Chromeという新たな強敵が現れると、Mozillaは再び大きな自己変革に乗り出します。2016年に発表された「Quantum」プロジェクトは、Geckoエンジンを根本から再設計し、現代のマルチコアプロセッサに最適化する大規模な取り組みでした 24。このプロジェクトでは、実験的な次世代エンジン「Servo」から多くの技術が取り入れられ、特にパフォーマンスとメモリ安全性を重視してMozillaが開発した画期的なプログラミング言語「Rust」が活用されました 27。
Firefoxの成功は、Microsoftの独占と停滞が生み出した市場の空白に、的確な答えを提示した結果でした。IEが放棄したスピード、セキュリティ、そしてウェブ標準という価値を武器に、Firefoxはオープンソースコミュニティの力を結集して巨大な帝国に立ち向かったのです。それは単なる新製品の登場ではなく、ウェブの健全性を取り戻そうとする市場の自浄作用そのものでした。
第5章:新時代の支配者――Google Chromeの技術革命
FirefoxがIEの独占を切り崩し、第二次ブラウザ戦争が激化していた2008年、戦場に新たなプレイヤーが参入します。それがGoogle Chromeです。Chromeの登場は、単に競争相手が一つ増えたという以上のインパクトをウェブの世界にもたらしました。それは、ブラウザのアーキテクチャ(設計思想)そのものを根本から覆す、技術革命の始まりでした 7。
第一の柱「スピード」:V8 JavaScriptエンジン
Chromeがもたらした革命の一つ目は、圧倒的な「スピード」です。その心臓部となったのが、C++で書かれた高性能なJavaScriptエンジン「V8」でした 28。当時、GmailやGoogle Mapsのような、複雑でインタラクティブなウェブアプリケーションが台頭し始めていました。これらのアプリケーションは大量のJavaScriptコードに依存しており、従来のブラウザでは動作が重くなるという課題がありました。V8は、JavaScriptを極めて高速に実行することで、ウェブアプリケーションをまるでデスクトップのソフトウェアのようにサクサクと動かすことを可能にしました。これは、ウェブの可能性を大きく広げるブレークスルーでした。
第二の柱「安定性とセキュリティ」:マルチプロセス・サンドボックスアーキテクチャ
Chromeの最も重要で、かつIEとの決定的な違いとなったのが、そのアーキテクチャです。
旧来の方式(IE/Firefox)
従来のブラウザは、「シングルプロセス」アーキテクチャで動作していました。これは、ブラウザのすべての機能(UI、各タブ、プラグインなど)が、一つの大きなプログラムとして動く方式です。この方式の欠点は、一つのタブで問題が発生してクラッシュすると、ブラウザ全体が巻き込まれて落ちてしまうことでした。また、セキュリティ上も、一つの脆弱性がブラウザ全体、ひいてはPCシステム全体を危険に晒す可能性がありました 27。
Chromeの方式
Chromeは、ブラウザとして初めて本格的な「マルチプロセス」アーキテクチャを採用しました 29。これは、ブラウザ本体、各タブ、拡張機能、プラグインが、それぞれ独立した別の「プロセス」として動作する方式です。これにより、もし一つのタブがクラッシュしても、他のタブやブラウザ本体には影響が及びません。この高い安定性は、多くのタブを同時に開くのが当たり前になった現代のウェブ利用において、絶大なメリットとなりました。
さらに重要なのが「サンドボックス」というセキュリティモデルです。Chromeでは、各プロセスが「サンドボックス」と呼ばれる厳重に隔離された仮想環境の中で実行されます 30。サンドボックス内のプロセスは、PCの重要なシステムファイルにアクセスしたり、他のプロセスのメモリを覗き見たりすることが固く禁じられています。これは、ウェブから読み込むコードはすべて潜在的に悪意があるかもしれないという前提に立つ「ゼロトラスト」モデルです。万が一、ウェブページの脆弱性を突かれても、攻撃者はまずこのサンドボックスの壁を破らなければならず、そのためには第二、第三の別の脆弱性を見つける必要があります。これにより、セキュリティレベルは飛躍的に向上しました 30。これは、ActiveXのように信頼されたコードに全権限を与えてしまうIEの「フルトラスト」モデルとは、まさに正反対の思想でした。
第三の柱「革新」:Blinkレンダリングエンジン
Chromeは当初、AppleのSafariと同じ「WebKit」というオープンソースのレンダリングエンジンを採用していました。しかし、Googleは自らが目指すマルチプロセスアーキテクチャへの最適化や、より迅速な技術革新を推し進めるため、2013年にWebKitから分岐(フォーク)し、独自のレンダリングエンジン「Blink」を開発しました 29。これにより、Googleはブラウザの心臓部を完全に自社のコントロール下に置き、スピードとセキュリティのための最適化を自由に行えるようになりました。
Chromeの成功は、その背後にあるオープンソースプロジェクト「Chromium」の成功でもあります。現在、MicrosoftのEdge、Opera、Braveなど、市場の主要なブラウザの多くが、このChromiumをベースに開発されており、Blinkエンジンは事実上の業界標準となりつつあります 33。
Chromeの登場は、ブラウザの役割に関する根本的な認識の変化を促しました。IEがウェブページを「表示すべき文書」として捉えていたのに対し、Googleはそれを「安全に実行すべき、信頼できないアプリケーション」として捉えました。そのために、OSが複数のアプリケーションを安全に実行するのと同じ思想(プロセスの分離と権限の制限)をブラウザに持ち込んだのです。ブラウザを一種の「ミニOS」として再定義し、各タブを保護されたアプリケーションとして実行する。このアーキテクチャのパラダイムシフトこそが、Chromeがもたらした真の革命であり、その後のブラウザの進化の方向性を決定づけました。
第6章:IEとChrome、何が違ったのか?――思想からアーキテクチャまでの決定的差異
これまでの章で見てきたように、Internet ExplorerとGoogle Chromeの違いは、単なる機能や見た目の差に留まりません。その根底には、ウェブをどう捉えるかという「思想」、そしてそれを実現するための「アーキテクチャ」における、決定的かつ根本的な差異が存在します。この章では、両者の違いを改めて整理し、なぜ一方が消え、もう一方が覇者となったのかを明らかにします。
思想の対立:OSの一部か、ウェブのためのプラットフォームか
- Internet Explorerの思想
IEは、徹頭徹尾「WindowsというOSの統合コンポーネント」でした 4。その目的は、Microsoftが支配するデスクトップOSのエコシステムをウェブにまで拡張し、ユーザーを自社の環境に囲い込む(ロックインする)ことでした。ActiveXのような技術は、Windowsアプリケーションとの連携を深めるための強力な武器であり、ブラウザはOSの機能をウェブに持ち出すための「出張所」のような存在でした。 - Google Chromeの思想
一方、Chromeは「オープンソースのChromiumを基盤とする独立したアプリケーション」です 34。Googleはウェブサービスで成長した企業であり、彼らの目的は、特定のOSに依存することなく、「ウェブそのもの」をより高速で、より高機能なプラットフォームにすることでした。ウェブが進化すれば、自社のサービス(検索、Gmail、YouTubeなど)の価値も向上するからです。Chromeは、ウェブを主役にするための乗り物として設計されました。
アーキテクチャの対立:一枚岩か、集合住宅か
- Internet Explorerのアーキテクチャ
IEは、すべての機能が一体となった「モノリシックなシングルプロセス」アーキテクチャを採用していました 27。これは、一つの大きな建物にすべての機能が同居しているようなものです。シンプルですが、一箇所で火事(クラッシュや脆弱性)が起きると、建物全体が危険に晒されるという脆弱性を抱えていました。 - Google Chromeのアーキテクチャ
Chromeは、機能ごとに部屋が完全に独立した集合住宅のような「マルチプロセス・サンドボックス」アーキテクチャを採用しました 29。各部屋(タブや拡張機能)は、分厚い壁(サンドボックス)で仕切られており、一つの部屋で問題が起きても他の部屋には影響しません。この設計は、安定性とセキュリティを最優先した結果です。
セキュリティモデルの対立:性善説か、性悪説か
- Internet Explorerのセキュリティ
IEのActiveXが採用したのは、「信頼ベース」のモデル、いわば性善説です 15。信頼できる開発者が作ったコードであれば安全だろうと考え、システムへの広範なアクセス権限を与えました。しかし、この「信頼」が一度裏切られると、被害は甚大なものになりました。 - Google Chromeのセキュリティ
Chromeのサンドボックスが採用したのは、「ゼロトラスト」モデル、すなわち性悪説です 30。ウェブから来るコードはすべて潜在的に危険であるとみなし、デフォルトでは何もできないように厳しく制限します。この思想の違いが、両者のセキュリティレベルに天と地ほどの差を生み出しました。
開発と標準化の対立:停滞と独自路線か、高速化と協調か
- Internet Explorerの開発
IEの開発サイクルは、Windowsのリリースサイクルに縛られており、非常に低速でした 14。また、競争に勝つために独自拡張を多用し、ウェブ標準の普及を妨げる一因ともなりました 8。 - Google Chromeの開発
Chromeは、OSから独立した高速な「ラピッドリリース」サイクルを採用し、数週間ごとにアップデートを繰り返します。これにより、新機能の投入やセキュリティ修正が迅速に行われます。また、オープンなウェブ標準への準拠を重視し、相互運用可能なウェブの発展に貢献しました 29。
これらの違いを一覧にまとめると、両者の本質的な差異がより明確になります。
| 特徴 (Feature) | Internet Explorer | Google Chrome |
| 基本思想 (Core Philosophy) | Windows OSの統合コンポーネント (Integrated OS Component) | オープンソースベースの独立したアプリケーション (Standalone Open-Source Application) |
| アーキテクチャ (Architecture) | モノリシックなシングルプロセス (Monolithic Single-Process) | マルチプロセス・サンドボックス (Multi-Process Sandbox) |
| レンダリングエンジン (Rendering Engine) | Trident (MSHTML) | Blink (WebKitからフォーク) |
| JavaScriptエンジン (JavaScript Engine) | JScript / Chakra (Legacy) | V8 |
| セキュリティモデル (Security Model) | ActiveXによる信頼ベース (Trust-based via ActiveX) | サンドボックスによるゼロトラスト (Zero-trust via Sandbox) |
| ウェブ標準 (Web Standards) | 独自拡張を優先 (Prioritized Proprietary Extensions) | 標準規格への準拠を重視 (Emphasized Standards Compliance) |
| 開発サイクル (Development Cycle) | OSに連動し低速 (Slow, tied to OS) | 独立した高速なラピッドリリース (Independent, Rapid Release) |
結局のところ、Internet Explorerは「PCの時代」の思想から生まれたブラウザであり、Google Chromeは「ウェブの時代」の思想から生まれたブラウザでした。時代の変化が、両者の運命を分けたのです。
結論:IEが遺したものと、ウェブブラウザの未来
Internet Explorerの長い歴史を振り返ると、その功罪が複雑に絡み合っていることがわかります。IEは、Windowsとのバンドル戦略によって、何億人もの人々を初めてウェブの世界へと導きました 12。その意味で、インターネットの普及に大きく貢献したことは紛れもない事実です。しかし、その後の市場独占が生んだ技術的な停滞は、ウェブの進化を約10年近く遅らせたとも言われています 1。IEの物語は、技術における独占がいかに危険であるかを物語る、貴重な教訓なのです 3。
そして今、私たちは新たな独占の時代を迎えています。Google Chromeは、その優れた技術力で市場を席巻し、現在では65%を超える圧倒的なシェアを握っています 9。Chromeの基盤であるChromiumはオープンソースですが、その開発の主導権をGoogle一社が握っている状況は、ウェブの未来に対する新たな懸念を生んでいます。これは「Chromium独占」とも呼ばれるパラドックスです。
ここで、Firefoxが守り続けてきた「ブラウザの多様性」の重要性が改めて浮かび上がります 22。Blink(Chromium系)、Gecko(Firefox)、WebKit(Safari)という、それぞれ独立した複数のレンダリングエンジンが存在することは、ウェブがオープンで、健全な競争が行われるために不可欠です。もしエンジンが一つだけになってしまえば、そのエンジンの仕様やバグが、意図せずして事実上の「標準」となってしまう危険性があるからです 27。
ブラウザ戦争は、決して終わることがありません。仮想現実(VR)や拡張現実(AR)、人工知能(AI)といった新たな技術が次々と登場し、ウェブは今も進化を続けています 7。そして、その進化の中心にあるブラウザは、これからもインターネットの未来を賭けた、最も重要な戦場であり続けるでしょう。
Internet Explorerの物語は、単なる過去の出来事ではありません。それは、私たちが今使っている技術がどのような歴史の積み重ねの上にあるのかを理解し、そしてこれからのデジタル社会のあり方を考えるための、重要なレンズなのです。一つのブラウザの栄光と没落の物語は、ウェブが常に変化し、進化し続けるダイナミックな世界であることを、私たちに教えてくれています。
引用文献
- The Rise and Fall of Internet Explorer End of Support Impacts Retail …, 7月 13, 2025にアクセス、 https://www.bytagig.com/articles/the-rise-and-fall-of-internet-explorer-end-of-support-impacts-retail-businesses/
- Internet Explorer Discontinued: Is It for the Better? Exploring the Facts, Benefits, and Disadvantages – Bytagig, 7月 13, 2025にアクセス、 https://www.bytagig.com/articles/internet-explorer-discontinued-is-it-for-the-better-exploring-the-facts-benefits-and-disadvantages/
- Goodbye Internet Explorer – The Inevitable Downfall – GoodWhale, 7月 13, 2025にアクセス、 https://goodwhale.com/goodbye-internet-explorer-the-inevitable-downfall-of-a-flawed-giant/
- Browser wars – Wikipedia, 7月 13, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Browser_wars
- History of the web browser – Wikipedia, 7月 13, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_web_browser
- NCSA Mosaic – Wikipedia, 7月 13, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/NCSA_Mosaic
- The Evolution of Web Browsers: From Mosaic to Modern-Day Giants |, 7月 13, 2025にアクセス、 https://danielepais.com/journal/the-evolution-of-web-browsers-from-mosaic-to-modern-day-giants/
- The History of the Browser Wars: When Netscape Met Microsoft, 7月 13, 2025にアクセス、 https://thehistoryoftheweb.com/browser-wars/
- Thirty Years Ago This Week, the World Changed | by Russell McGuire | ClearPurpose, 7月 13, 2025にアクセス、 https://clearpurpose.media/thirty-years-ago-this-week-the-world-changed-bec271410d07
- What Were the “Browser Wars”? – Investopedia, 7月 13, 2025にアクセス、 https://www.investopedia.com/ask/answers/09/browser-wars-netscape-internet-explorer.asp
- Browser Wars: The History of Browsers and Chromium Victory – MaybeWorks, 7月 13, 2025にアクセス、 https://maybe.works/blogs/browser-wars-the-history-of-browsers-and-chromium-victory
- TIL about the “First Browser War”, which took place from 1995-2001, and ended with the up-and-coming Internet Explorer eliminating Netscape Navigator as a rival. By 2001, Internet Explorer had attained a peak of 96% Web Browser Usage Share. : r/todayilearned – Reddit, 7月 13, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/todayilearned/comments/13i7hdv/til_about_the_first_browser_war_which_took_place/
- en.wikipedia.org, 7月 13, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Browser_wars#:~:text=A%20browser%20war%20is%20a,%2C%20Firefox%2C%20or%20Google%20Chrome.
- The Demise of IE and Where Browsers are Headed – SmarterTools, 7月 13, 2025にアクセス、 https://www.smartertools.com/blog/2021/01/goodbye-ie-future-of-browsers
- Trident (software) – Wikipedia, 7月 13, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Trident_(software)
- Why do Internet Explorer settings still exist on Windows 11? – Super User, 7月 13, 2025にアクセス、 https://superuser.com/questions/1907164/why-do-internet-explorer-settings-still-exist-on-windows-11
- Microsoft MSHTML Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2021-40444) Threat Alert – NSFOCUS, Inc., a global network and cyber security leader, protects enterprises and carriers from advanced cyber attacks., 7月 13, 2025にアクセス、 https://nsfocusglobal.com/microsoft-mshtml-remote-code-execution-vulnerability-cve-2021-40444-threat-alert/
- Killbit – Wikipedia, 7月 13, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Killbit
- IE mode supports the following Internet Explorer functionality – Information Technology Support – Answers, 7月 13, 2025にアクセス、 https://answers.atlassian.syr.edu/wiki/spaces/ITHELP/pages/159942752/Internet+Explorer+mode+in+Microsoft+Edge
- What is Internet Explorer (IE) mode? – Learn Microsoft, 7月 13, 2025にアクセス、 https://learn.microsoft.com/en-us/deployedge/edge-ie-mode
- We Don’t Support Internet Explorer and Here’s Why – Georgia Digital Service, 7月 13, 2025にアクセス、 https://digital.georgia.gov/blog-post/2021-08-24/we-dont-support-ie
- Browser History: Epic power struggles that brought us modern …, 7月 13, 2025にアクセス、 https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/browser-history/
- History of the Mozilla Project, 7月 13, 2025にアクセス、 https://www-archive.mozilla.org/about/history
- Firefox – Wikipedia, 7月 13, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Firefox
- Gecko (software) – Wikipedia, 7月 13, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Gecko_(software)
- How Firefox Almost Won the Second Browser War. Almost. – HackerNoon, 7月 13, 2025にアクセス、 https://hackernoon.com/how-firefox-nearly-won-the-second-browser-war-pd113zim
- Is the Gecko engine the only reason Mozilla still exists? : r/firefox – Reddit, 7月 13, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/firefox/comments/1fnaunv/is_the_gecko_engine_the_only_reason_mozilla_still/
- V8 JavaScript engine, 7月 13, 2025にアクセス、 https://v8.dev/
- Developer FAQ – Why Blink? – The Chromium Projects, 7月 13, 2025にアクセス、 https://www.chromium.org/blink/developer-faq/
- Blink (Chromium’s Rendering Engine) vs. Gecko (Firefox’s … – Reddit, 7月 13, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/browsers/comments/1jz7bcm/blink_chromiums_rendering_engine_vs_gecko/
- Design of V8 bindings, 7月 13, 2025にアクセス、 https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/third_party/blink/renderer/bindings/core/v8/V8BindingDesign.md
- The V8 Sandbox, 7月 13, 2025にアクセス、 https://v8.dev/blog/sandbox
- What is Blink? | Web Platform – Chrome for Developers, 7月 13, 2025にアクセス、 https://developer.chrome.com/docs/web-platform/blink
- The Chromium Projects, 7月 13, 2025にアクセス、 https://www.chromium.org/