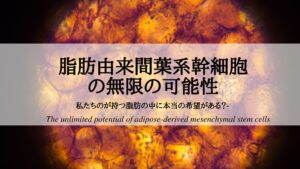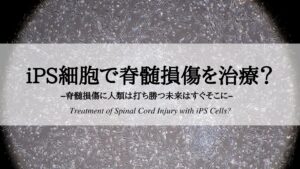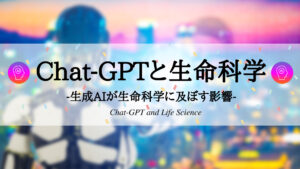はじめに:なぜ今、カール・ポパーなのか?
21世紀の現代社会は、情報、アイデア、そして主張の爆発的な増加によって特徴づけられています。インターネットとソーシャルメディアは、誰もが世界に向けて発信できるプラットフォームを提供しましたが、その結果、玉石混交のアイデアが氾濫し、信頼できる知識とそうでないものを見分けることがかつてなく困難になりました 1。気候変動、ワクチン、そして新たな治療法に至るまで、何が「科学的」で何が「非科学的」なのかという問いは、もはや学術的な議論の対象にとどまらず、私たちの日常生活、健康、そして社会の未来を左右する喫緊の課題となっています。
このような時代において、20世紀最高の科学哲学者の一人と称されるカール・ポパー(Karl Popper)の思想が、驚くべき現代的妥当性をもって私たちの前に現れます 2。ポパーが生涯をかけて取り組んだ中心的な問題は、「科学と非科学をいかにして区別するか」という「線引き問題(demarcation problem)」でした 3。彼は、この古くて新しい難問に対し、明快かつ強力な解決策を提示しました。それは、ある理論が科学的であるかどうかは、それが「検証」できるかどうかではなく、それが「反証」される可能性、すなわち間違いであると証明されるリスクを負っているかどうかで決まる、という革命的なアイデアでした 6。
ポパーの哲学は、単なる学術的な分類法ではありません。それは、あらゆる権威や定説を鵜呑みにせず、常に批判的な視点を持ち、「私は間違っているかもしれないし、あなたが正しいかもしれない」という知的謙虚さをもって真理に近づこうとする「批判的合理主義(critical rationalism)」という生き方そのものです 8。この精神は、偽情報が溢れる現代の情報生態系を生き抜くための、不可欠な知的ツールキットを提供してくれます。
本稿では、激動の20世紀ウィーンに生きたカール・ポパーの生涯とその時代背景を紐解き、彼の核心的思想である「反証可能性」を詳細に解説します。さらに、トーマス・クーンをはじめとする思想家たちとの活発な論争を通じて、彼の哲学がどのように洗練され、またどのような批判に晒されたのかを多角的に検討します。そして最後に、彼の思想が現代の最先端領域である人工知能(AI)の発展と、それに伴う倫理的課題にどのような示唆を与えるのかを探求し、AI時代の科学のあり方と私たちの向き合い方を展望します。これは、一人の哲学者の思想を巡る旅であると同時に、現代社会が直面する知的課題を乗り越えるための羅針盤を探す試みでもあります。
カール・ポパーとは誰か?ウィーンの知的土壌が生んだ批判的合理主義者
カール・ライムント・ポパーは、1902年7月28日、オーストリア=ハンガリー帝国末期のウィーンで生を受けました 6。彼の家庭はユダヤ系の裕福な中流階級で、弁護士であった父は1万冊以上の蔵書を誇る「極めて本好き」な人物でした 10。ポパーは、知的好奇心に満ちた環境で育ちましたが、彼の青年期は第一次世界大戦の終結と帝国の崩壊という激動の時代と重なります。この社会の混乱と、革命的な思想が渦巻く空気は、彼の後の社会哲学、特に全体主義への鋭い批判に深い影響を与えました 10。
ウィーン大学で数学、物理学、心理学を学んだポパーは、当時のウィーンの知的世界を席巻していたあるグループと対峙することになります 6。それが「ウィーン学団(Vienna Circle)」です。
ウィーン学団と論理実証主義
ウィーン学団は、モーリッツ・シュリックを中心に、哲学者、科学者、数学者が集い、1924年から1936年にかけて定期的に会合を開いていたグループです 13。彼らは「論理実証主義(Logical Positivism)」と呼ばれる哲学を掲げ、科学の論理的構造を分析し、形而上学的な主張を哲学から追放することを目指しました 14。
彼らの思想の核心にあったのが「検証原理(verification principle)」です 17。これは、「ある命題が意味を持つのは、それが経験的に検証可能である場合に限られる」という主張です 5。例えば、「このカラスは黒い」という命題は、観察によって真偽を確かめられるため意味があります。しかし、「神は存在する」や「絶対精神は歴史において自己を展開する」といった形而上学的な命題は、経験的に検証する方法がないため「無意味」であると彼らは断じました 16。
ポパー:学団のメンバーではなく、最も手ごわい批判者
ポパーが論理実証主義者であったというのは、よくある誤解です。実際には、彼はウィーン学団のメンバーではなく、その思想に対する最も鋭い批判者の一人でした 6。彼の最初の主著『科学的発見の論理』(
Logik der Forschung、1934年)は、ウィーン学団が後援するシリーズから出版されましたが、その内容は学団の中心的な教義に対する根本的な挑戦でした 6。彼は学団の主要メンバーとは親交がありましたが、その中核的な会合に正式に招待されることはありませんでした 15。
ポパーは、ウィーン学団の検証原理に致命的な欠陥があることを見抜いていました。
- 科学法則の排除:検証原理に従うと、「すべての白鳥は白い」のような普遍的な科学法則は、意味のない命題になってしまいます。なぜなら、世界中のすべての白鳥を観察し尽くすことは不可能であり、したがってこの法則を完全に「検証」することはできないからです 12。科学の根幹をなす法則を無意味だと切り捨てる基準は、科学の基準として不適切です。
- 偽科学の容認:「ユニコーンは存在する」といった存在命題は、検証原理の下では科学的になってしまいます。なぜなら、一頭でもユニコーンを発見できれば、この命題は検証されるからです 12。ポパーは、このような主張を科学と呼ぶことに強く反対しました。
- 自己論駁:検証原理それ自体が、「経験的に検証可能」ではありません。したがって、検証原理は自らの基準によって「無意味」な命題となってしまうという自己矛盾を抱えています 12。
ポパーの知的アイデンティティは、このように、当時の主流であった知的権威への反対意見の中で形成されました。彼の周りで起こっていた社会の崩壊と、ウィーン学団という知のドグマとの対決は、確実性を求めるあらゆる権威主義的な思想への深い懐疑を彼に植え付けたと言えるでしょう。彼の哲学全体を貫く、批判、可謬性(fallibility)、そして知的独断の拒絶という姿勢は、このウィーンでの経験にその源流を見出すことができます。後に彼が「論理実証主義を殺したのは私だ」と豪語した逸話は 21、単なる哲学的な主張ではなく、知的確実性に対する彼の生涯にわたる闘争を象徴しています。彼の哲学は、政治的全体主義であれ、知的ドグマであれ、あらゆる「閉じた」思考システムに対する「開かれた」精神の擁護として、統一的に理解することができるのです。
線引き問題:ポパーの革命的解決策「反証可能性」
科学と、科学のふりをした偽科学(Pseudoscience)を区別する「線引き問題」は、古くから哲学の難問でした 3。ウィーン学団が「検証可能性」でこの問題に挑んだのに対し、ポパーはまったく逆の方向から、鮮やかな解決策を提示します。それが彼の名を不朽のものにした「反証可能性(Falsifiability)」の原理です。
帰納の問題から反証へ
ポパーの出発点は、18世紀の哲学者デイヴィッド・ヒュームが提起した「帰納の問題(problem of induction)」にあります 4。帰納とは、個別の観察事例から普遍的な法則を導き出す推論方法です。例えば、「これまで観察したカラスはすべて黒かった。ゆえに、すべてのカラスは黒い」というのが帰納的推論です。しかしヒュームは、たとえ何百万羽の黒いカラスを観察したとしても、次に観察するカラスが黒いという論理的な保証はどこにもないと指摘しました 23。未来が過去と同じであるという保証はないからです。
ポパーはこのヒュームの批判を全面的に受け入れ、科学は帰納法によって「証明」されるものではないと結論付けました。では、科学の進歩は何によって支えられているのでしょうか?ここでポパーは、論理を180度転換させます。
ある普遍的な理論を、観察によって「真である」と証明することは不可能でも、「偽である」と証明することは可能です。たった一羽の黒い白鳥の観察は、「すべての白鳥は白い」という理論が決定的に間違っていることを示します 25。この論理的な非対称性こそが、ポパー哲学の核心です。
反証可能性こそが科学の証
ここからポパーは、科学の線引き基準を導き出します。ある理論が科学的であるための条件は、それが検証可能であることではなく、反証可能であること、つまり、その理論を反証する(覆す)ような観察や実験が、少なくとも論理的に想像できることです 1。
科学的な理論とは、大胆な予測を立て、それによって「特定のできごとが起こることを禁止する」ものでなければなりません 11。理論が禁止するものが多ければ多いほど、その理論はより良い(=よりテストしやすい)理論となります。逆に、どんな出来事が起きても「ほら、やはりこの理論は正しかった」と説明できてしまうような、決して反証されることのない理論は、科学ではないとポパーは断じました。彼にとって、反証不可能性は美徳ではなく、欠陥なのです 11。
アインシュタイン vs. フロイト:科学と偽科学の分水嶺
ポパーはこの考えを、具体的な事例を用いて鮮やかに説明しました。彼が特に感銘を受けたのは、アインシュタインの一般相対性理論でした 27。
- アインシュタインの理論(科学):一般相対性理論は、「重い物体の周りでは光が曲がる」という、当時の常識からは考えられない「リスキーな予測」を立てました 11。1919年、アーサー・エディントン率いる観測隊が日食を利用してこの予測を検証し、実際に星の光が太陽の重力によって曲げられていることを確認しました 11。ポパーが重要視したのは、このテストが「失敗する可能性があった」という点です。もし光が曲がらなければ、アインシュタインの理論は反証されていたでしょう。このように、自らを厳しいテストの危険に晒すことこそが、科学の証なのです。
- フロイトの精神分析とマルクス主義(偽科学):対照的に、ポパーはフロイトの精神分析やマルクス主義の歴史理論を、偽科学の典型例として挙げました 1。彼が問題にしたのは、これらの理論が間違っているかどうかではなく、原理的に
反証不可能であるという点です。
- ポパーによれば、精神分析はどんな人間の行動でも説明できてしまいます。例えば、ある男が子供を助ければ、それは「昇華」の現れだと説明され、逆に子供を溺れさせれば、それは「抑圧」された衝動の結果だと説明されるでしょう 12。どのような行動も理論の「検証事例」となり、理論を反証するような行動を想像することさえ困難です。
- 同様に、マルクス主義も当初は「資本主義は内的な矛盾によって崩壊し、先進工業国で労働者革命が起こる」といった反証可能な予測を立てていました。しかし、その予測が外れると、信奉者たちは理論を捨てる代わりに、「労働者は『偽りの意識』に囚われている」といった、テスト不可能なアド・ホックな仮説(その場しのぎの仮説)を導入して理論を延命させました 12。
このように、反証可能性は理論の起源や信憑性ではなく、その論理構造と、それに対する私たちの「態度」の問題です。夢や神話から生まれた突飛なアイデアであっても、それがテスト可能な予測を生み出し、反証の試みに耐えるならば、それは科学的な探求の対象となり得ます 20。逆に、どれほど多くの信奉者がいようとも、あらゆる反論を巧みに回避する理論は、科学の領域から外れるのです。
科学の進歩:「推測と反駁」のプロセス
この考え方に基づき、ポパーは科学の進歩を、真理を一つずつ積み上げていく建築のようなものではなく、ダーウィンの進化論にも似た、試行錯誤によるエラー除去のプロセスとして描き出しました 12。
科学者はまず、世界についての「推測(Conjecture)」として、大胆な仮説を立てます。次に、その仮説を可能な限り厳しいテストにかけ、それを「反駁(Refutation)」しようと試みます 8。
テストを生き延びた理論は「確証された(corroborated)」ものとして、一時的に受け入れられます。しかし、それは「証明された真理」ではなく、あくまで「まだ反証されていない、現時点で最良の仮説」に過ぎません 26。やがて、その理論では説明できない現象が見つかったり、より優れた(よりテスト可能性の高い)別の理論が登場したりすれば、古い理論は捨てられ、新たな「推測と反駁」のサイクルが始まります。
ポパーにとって、科学とは確実な知識の体系ではなく、絶え間ない批判と修正を通じて、より真理に近づいていこうとする、終わりなき探求なのです。この思想の根底には、人間の知識はすべて暫定的で誤りうるという「可謬主義(fallibilism)」の精神、そして自らの誤りを積極的に探求する知的謙虚さがあります。科学の目的は、自分が正しいことを証明することではなく、自分が「どこで間違っているか」を発見することにあるのです。
ポパー哲学への挑戦:反証主義は万能薬か?
ポパーの反証主義は、科学哲学に大きな影響を与えましたが、決して万能薬ではありませんでした。彼の明快な理論は、発表直後から数々の鋭い批判にさらされ、その後の科学哲学の議論を大きく方向づけました。ここでは、ポパー哲学が直面した主要な挑戦者たち、すなわちデュエム=クワイン、トーマス・クーン、イムレ・ラカトシュ、そしてポール・ファイヤアーベントの議論を見ていきましょう。
デュエム=クワイン・テーゼ:決定的な反証は不可能?
最も強力な論理的挑戦は、「デュエム=クワイン・テーゼ」または「確証のホーリズム(confirmation holism)」として知られています 25。このテーゼによれば、科学的な仮説は単独でテストされることは決してありません。実験を行う際には、検証したい中心的な仮説だけでなく、測定機器が正しく作動している、初期条件は想定通りである、背景にある他の物理法則は正しい、といった無数の「補助仮説(auxiliary hypotheses)」が暗黙のうちに仮定されています 32。
もし実験結果が予測と異なっていたとしても、それが中心的な仮説の誤りを示しているのか、それとも無数にある補助仮説のどれかが間違っていただけなのかを、論理的に特定することは不可能です 32。例えば、天王星の軌道がニュートン力学の予測からずれていることが発見されたとき、科学者たちはニュートン力学を捨て去るのではなく、「未知の惑星が存在する」という補助仮説を立て、結果的に海王星を発見しました 12。
これでは、理論家は常に補助仮説を修正することで、自説を反証から守ることができてしまいます。つまり、決定的な反証は原理的に不可能だ、というわけです。
ポパー自身はこの問題を認識しており、「規約主義者の戦略(conventionalist stratagems)」と呼んでいました 35。彼の応答は、反証可能性は純粋な論理だけでなく、科学者の
方法論的な決断の問題である、というものでした。科学者は、理論を延命させるためだけに、新たな予測を生まない「アド・ホックな」仮説を導入することを自制するというルールに従わなければならない、と彼は主張したのです 12。
トーマス・クーンの「パラダイム・シフト」:科学の歴史はポパー的ではない?
科学史家トーマス・クーンは、その画期的な著書『科学革命の構造』において、ポパーのモデルは実際の科学の歴史的実践とは異なると主張しました 36。
- 通常科学(Normal Science):クーンによれば、ほとんどの科学者は、ほとんどの時間、既存の理論を反証しようとはしていません。彼らは、広く受け入れられた「パラダイム」(理論、実験手法、価値観などを共有する枠組み)の中で、パズルを解くように研究活動を行っています。この「通常科学」の段階では、パラダイムに反する「変則事例(anomalies)」は、反証例としてではなく、いずれ解決されるべきパズルとして扱われるか、単に無視されます 37。
- 科学革命(Scientific Revolutions):科学の大きな進歩は、ポパーが描くような漸進的なエラー除去によってではなく、稀に起こる断絶的な「パラダイム・シフト」によってもたらされます。変則事例が蓄積し、パラダイムが機能不全に陥ると「危機」が訪れ、やがて古いパラダイムはまったく新しいものに取って代わられます。これは、ニュートン物理学からアインシュタイン物理学への移行のような、世界観そのものの転換です 37。クーンは、異なるパラダイムは「共約不可能(incommensurable)」であり、中立的な基準で優劣を比較することはできないとさえ示唆しました。
イムレ・ラカトシュの「リサーチ・プログラム」:ポパーとクーンの統合
ポパーの弟子であったイムレ・ラカトシュは、ポパーの論理的な厳密さとクーンの歴史的な洞察を統合しようと試みました 40。
彼は、科学者が活動する単位として「リサーチ・プログラム」という概念を提唱しました。リサーチ・プログラムは、反証から断固として守られる「ハード・コア」と呼ばれる基本的前提と、それを守るための補助仮説からなる「保護ベルト」で構成されています 40。
デュエム=クライン・テーゼが指摘したように、反証例が現れたとき、科学者はハード・コアを放棄するのではなく、保護ベルトの補助仮説を修正して対応します。ラカトシュによれば、この修正が新たな事実を予測し、その予測が経験的に確証されるならば、そのリサーチ・プログラムは「進歩的(progressive)」です。逆に、反証例を後追いで説明するためだけにアド・ホックな修正を繰り返すだけで、新たな予測を生まないプログラムは「退行的(degenerating)」であるとされます 40。
ラカトシュにとって、科学と偽科学の線引きは、ある理論が反証可能かどうかという静的な基準ではなく、リサーチ・プログラムが進歩的か退行的かという、より動的で歴史的な基準によって行われるのです。
ポール・ファイヤアーベントの「方法論的アナーキズム」:科学に方法などない
同じくポパーの元で学んだポール・ファイヤアーベントは、最も過激な立場を取りました 43。
著書『方法への抵抗』(Against Method)で、彼は科学の歴史を詳細に検討した結果、ガリレオのような偉大な科学的ブレークスルーは、既存の方法論のルールを破ることによって初めて可能になったと主張しました 45。
彼の挑発的な結論は、「なんでもあり(anything goes)」というスローガンに集約されます 43。科学に普遍的な単一の方法論など存在せず、ポパーの反証主義のような厳格な線引き基準を設けることは、科学の進歩に不可欠な創造性や多元性を抑圧する、ドグマに過ぎないと彼は批判しました。
これらの批判は、ポパーの明快な反証主義が、実際の科学の実践の複雑さや歴史的ダイナミズムを十分に捉えきれていない可能性を示唆しています。以下の表は、これら4人の哲学者の考え方を比較したものです。
| 哲学者 | 中心概念 | 科学の進歩の仕方 | 「悪い科学」/偽科学観 |
| カール・ポパー | 反証可能性 | 「推測と反駁」を通じて。大胆な理論が提案され、厳しくテストされる。進歩とは、誤った理論の除去である。 | 反証不可能な理論、またはアド・ホックな仮説によって反駁から保護されている理論。 |
| トーマス・クーン | パラダイム・シフト | 長い「通常科学」(パラダイム内でのパズル解き)の期間があり、革命的な危機とパラダイム・シフトによって断続的に進歩する。 | 確立されたパラダイムを欠く「未成熟な科学」。通常科学では、変則事例は反証とは見なされず、しばしば無視される。 |
| イムレ・ラカトシュ | リサーチ・プログラム | 「リサーチ・プログラム」間の競争を通じて。進歩的なプログラムは新たな予測を行い、退行的なプログラムは行わない。 | 新たな事実を予測できず、反証に対してアド・ホックな修正しかできない「退行的なリサーチ・プログラム」。 |
| ポール・ファイヤアーベント | 方法論的アナーキズム | 単一の方法はない。進歩は創造性、日和見主義、既存のルールを破ることによって起こる。「なんでもあり」。 | 線引きという考え方自体が、科学の進歩と多元性を害するドグマであるとして拒絶する。 |
科学から社会へ:「開かれた社会」とその敵
ポパーの思想の射程は、科学哲学にとどまりません。彼の科学に関する考え方は、彼の社会・政治哲学と分かちがたく結びついており、両者は「批判的合理主義」という一つの統一された世界観の異なる側面なのです 8。
批判的合理主義という土台
ポパー哲学の根幹をなすのは、知識は批判とエラーの修正を通じて成長し、いかなる信念も確実なものとして正当化されることはない、という「批判的合理主義」の立場です 46。科学理論が常に暫定的な「推測」であるのと同様に、社会に関する私たちの知識や政策もまた、誤りうるものとして扱われなければなりません。
歴史主義への批判
第二次世界大戦の暗い時代にニュージーランドで執筆された彼の主著『貧困の歴史主義』(The Poverty of Historicism)と『開かれた社会とその敵』(The Open Society and Its Enemies)で、ポパーは「歴史主義(historicism)」と呼ばれる思想を痛烈に批判しました 6。歴史主義とは、プラトン、ヘーゲル、マルクスといった思想家に見られる、歴史は発見可能な、不可避の法則に従って進行するという信念です 19。
ポパーにとって、歴史主義は政治における偽科学に他なりませんでした。その壮大な歴史予測は、精神分析やマルクス主義の理論と同様に反証不可能であり、全体主義へと至る危険な道筋をつけます。歴史の「鉄の法則」を発見したと信じる為政者たちは、自らの理論に合わせて社会を根本から作り変えるというユートピア的な計画を正当化し、その過程で生じる甚大な犠牲や苦しみを、輝かしい未来のための不可避な代償として片付けてしまうからです 20。彼らは、自らの理論に対する反証(=計画の失敗や民衆の不幸)を受け入れず、それを「反動分子の抵抗」や「歴史の必然的な痛み」として説明し、理論を免疫化してしまうのです。
「開かれた社会」の理念
歴史主義という「閉じた」思想システムに対し、ポパーが擁護したのが「開かれた社会(Open Society)」です。これは、彼の科学論と見事なまでに響き合っています。
- 可謬主義の受容:「開かれた社会」は、政府の政策や指導者が誤りを犯す可能性があるという「可謬主義」を前提とします 8。絶対的な正しさを主張する支配者は存在しません。
- 漸進的な社会改良:ユートピア的な社会の全面改造(utopian social engineering)を拒否し、「漸進的な社会工学(piecemeal social engineering)」を支持します 46。これは、社会が抱える特定の問題を解決するために、小規模で、検証可能で、そして何よりも
修正可能な改革を少しずつ進めていくアプローチです。 - 批判と自由の制度化:個人の自由と批判的な議論を尊重し、最も重要なこととして、悪い政府を暴力に頼らずに平和的に交代させる制度(例えば、普通選挙)を備えています 8。
この対応関係は明らかです。ポパーの政治哲学は、彼の科学方法論の社会への応用そのものです。「開かれた社会」とは、最良の状態にある科学者共同体の政治的等価物であり、合理的な誤りの発見と修正のために設計されたシステムです。一方で、「全体主義」は偽科学の政治的等価物であり、批判と反駁を許さない、閉鎖的で独断的なシステムなのです。
科学理論の価値がその「テスト可能性」にあるのと同様に、政治システムの価値は、国民による「反証可能性」、すなわち選挙などを通じて平和裏に変更できる可能性にあるのです。このように、ポパーの思想は科学と政治という二つの領域にまたがる別々の哲学ではなく、人間の知識と行動という二つの領域に適用された、一つの統合された「批判的合理主義」の哲学として理解することができます。これこそが、彼の知的プロジェクト全体を貫く最も深遠な視点と言えるでしょう。
ポパー哲学の未来:AI、科学、そして新たな線引き問題
カール・ポパーがその哲学を築き上げてから半世紀以上が経過し、科学技術は彼の時代には想像もつかなかった領域へと足を踏み入れています。特に人工知能(AI)の急速な発展は、科学のあり方、知識の定義、そして人間と社会の関係そのものを問い直しています。この新たな時代において、ポパーの思想は驚くほど強力な分析ツールとして、その価値を再び証明しつつあります。
AI:「推測と反駁」を加速するエンジン
AI、特に機械学習は、ポパー的な科学の進歩サイクルを劇的に加速させる可能性を秘めています。人間では到底処理不可能な膨大なデータを解析し、既存の理論では説明できない「変則事例」を発見したり、あるいは人間が思いもよらなかった斬新でテスト可能な仮説(「推測」)を自ら生成したりすることができます 48。これは、科学的発見のプロセスを根本から変えうるものです。
「ブラックボックス」問題:新たな偽科学の脅威か?
しかし、AIの発展は新たな「線引き問題」をもたらしました。現代の最も強力なAIモデル、特に深層学習(ディープラーニング)や大規模言語モデル(LLM)の多くは、「ブラックボックス」であると指摘されています。つまり、それらがどのようにして特定の結論に至ったのか、その内部の意思決定プロセスは、開発者自身にさえ完全には理解できません 51。
ポパーの観点から見れば、これは致命的な問題です。あるAIモデルが予測を下しても、その背後にある「理論」や「論理」が不透明であれば、私たちはその予測を厳密にテストし、反証するための決定的な実験を設計することができません。モデルの出力は、反証不可能な神託のようなものになってしまいます 55。これは、ポパーが偽科学と断じた精神分析が、あらゆる事象に対して説明をひねり出すことができても、その根底にある反証可能なルールを提示できなかった状況と酷似しています 11。
この問題に取り組むのが、「説明可能なAI(Explainable AI, XAI)」と呼ばれる研究分野です 51。XAIの目標は、AIのブラックボックスを開き、その判断根拠を人間が理解できる形で提示することです。したがって、XAIへの取り組みは、単なる技術的・倫理的な要請にとどまらず、AIがポパー的な意味で真に「科学的」なツールとなるための、哲学的な必須条件であると言えるでしょう 53。
「帰納的」機械学習のパラドックス
機械学習は、しばしば「データから一般的なルールを学習する」プロセス、すなわち「帰納的」なものとして説明されます。これは、帰納法を否定したポパーの哲学と真っ向から対立するように見えます 59。しかし、この矛盾は見かけ上のものである可能性があります。
多くの機械学習の訓練プロセス、例えば勾配降下法などは、古典的な意味での帰納的推論とは異なります。むしろ、それは「変動と選択」あるいは「試行錯誤」という進化論的なアルゴリズムとして理解する方が適切です。モデルはまずランダムな推測(重みの初期設定)を行い、データとの照合によってその推測をテストし(誤差を計算し)、悪い推測を反駁してわずかに良い推測へと修正する、というプロセスを何百万回も繰り返します。これは、ポパーの「推測と反駁」のモデルと完全に一致します 59。AIは帰納的に真理を発見しているのではなく、進化論的なエラー除去のプロセスを通じて、より良い(誤差の少ない)解へと適応しているのです。
AIの安全性と批判的合理主義
「AIの安全性(AI Safety)」は、高度なAIが引き起こすかもしれない壊滅的な事故や誤用を防ぐことを目的とする分野です 60。この分野の研究もまた、暗黙のうちにポパー的なアプローチを採用しています。
AIの安全性を研究する人々は、あるAIが「絶対に安全である」と証明することは不可能だと考えています。これは、あらゆる理論の正しさを証明することはできないとするポパーの「反証主義」や「非正当化主義」の立場と一致します。
その代わり、彼らが目指すのは、堅牢で(robust)、監視可能で(monitorable)、そして修正可能(aligned)なシステムを構築することです。具体的には、敵対的攻撃(adversarial attacks)に対する脆弱性をテストし(反証の試み)、異常な振る舞いを検知し(エラーの発見)、AIの目標が人間の意図から外れた場合にそれを修正できるメカニズムを組み込むこと(漸進的な政策修正)を目指します 61。これはまさに、「開かれた社会」が制度を通じて政策の誤りを修正していくプロセスと同じ構造を持っています。
このように、ポパーの哲学は、21世紀のAIがもたらす認識論的・社会的なリスクと機会を理解するための、極めて重要で不可欠な枠組みを提供しています。AIという新たな知識システムが、批判と修正を許さない「閉じた」神託となるのか、それとも人間の理性を拡張し、科学的探求を加速させる「開かれた」パートナーとなるのか。その岐路において、私たちを導くのがポパーの批判的合理主義の精神なのです。
結論:批判的理性を手に、未来へ
カール・ポパーの知的探求は、20世紀初頭のウィーンにおける論理実証主義への鋭い批判から始まり、科学哲学、社会哲学、政治哲学の領域を横断する、壮大で統一された思想体系へと結実しました。彼の哲学は、今なお色褪せることなく、現代社会が直面する根源的な問いに力強い光を投げかけています。
ポパーの最大の功績は、科学の焦点を、到達不可能な「確実性の証明(検証)」から、生産的な「エラーの除去(反証)」へと根本的に転換させたことにあります。彼は、「すべての白鳥は白い」という理論が、何百万の白い白鳥によっても証明されず、たった一羽の黒い白鳥によって覆されるという非対称性を見抜きました。これにより、科学は真理を積み上げる作業ではなく、大胆な推測を立て、それを厳しい批判に晒すことで、誤りを取り除きながら真理へと漸近していく、終わりなきプロセスとして再定義されました。
そして、この「批判的合理主義」の精神は、科学の領域を超え、彼の社会哲学の礎となりました。歴史の法則を信奉し、批判を許さない全体主義は「閉じた社会」であり、偽科学の政治的形態です。それに対し、自らの誤りを認め、漸進的な改良と平和的な政権交代を制度的に保証する「開かれた社会」は、科学的精神の社会への応用そのものです。
AIが新たな知のフロンティアを切り拓き、同時に「ブラックボックス」という新たな課題を突きつける現代において、ポパーの思想の重要性は増すばかりです。AIが信頼できる科学のパートナーとなるためには、その判断プロセスが説明可能であり、批判的なテスト、すなわち「反証」に開かれている必要があります。AIの安全性を確保する取り組みもまた、絶対的な安全の証明を求めるのではなく、エラーを発見し修正していくという、ポパー的な試行錯誤のプロセスに他なりません。
最終的に、カール・ポパーが私たちに残した最も貴重な遺産は、記憶されるべき一連の教義ではなく、実践されるべき一つの「態度」です。それは、自らの知識が常に暫定的で誤りうるものであることを認める知的謙虚さ、あらゆる主張を厳格な批判に晒す勇気、そして「私は間違っているかもしれないし、あなたが正しいかもしれない。そして、努力すれば、われわれは真理にさらに近づくことができるだろう」と語る、協力的な理性の精神です 9。複雑さと不確実性が増す世界の中で、この批判の精神こそが、私たちが未来をより良く形作っていくための、最も確かな羅針盤となるでしょう。
引用文献
- Falsifiability in medicine: what clinicians can learn from Karl Popper …, 7月 21, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8140582/
- Karl Popper (Stanford Encyclopedia of Philosophy/Summer 2020 Edition), 7月 21, 2025にアクセス、 https://plato.stanford.edu/archIves/sum2020/entries/popper/
- academic.oup.com, 7月 21, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/book/45901/chapter/403598107#:~:text=The%20%E2%80%9Cdemarcation%20problem%E2%80%9D%20is%20the,%2DBritish%20philosopher%2C%20Karl%20Popper.
- Pseudoscience and the Demarcation Problem | Internet …, 7月 21, 2025にアクセス、 https://iep.utm.edu/pseudoscience-demarcation/
- Demarcation problem – Wikipedia, 7月 21, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Demarcation_problem
- Karl Popper | Biography, Books, Theory, & Facts – Britannica, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.britannica.com/biography/Karl-Popper
- Falsifiability rule | EBSCO Research Starters, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.ebsco.com/research-starters/religion-and-philosophy/falsifiability-rule
- Karl Popper – Bibliography – PhilPapers, 7月 21, 2025にアクセス、 https://philpapers.org/browse/karl-popper
- ISSA Proceedings 2014 – Karl Popper’s Influence On Contemporary Argumentation Theory, 7月 21, 2025にアクセス、 https://rozenbergquarterly.com/issa-proceedings-2014-karl-poppers-influence-on-contemporary-argumentation-theory/
- The Open Society and its enemies: Karl Popper’s legacy – LSE History, 7月 21, 2025にアクセス、 https://blogs.lse.ac.uk/lsehistory/2024/11/20/the-open-society-and-its-enemies-karl-poppers-legacy/
- Popper’s Account of Scientific Theories – Simon Fraser University, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.sfu.ca/~swartz/popper.htm
- Karl Popper: Philosophy of Science, 7月 21, 2025にアクセス、 https://iep.utm.edu/pop-sci/
- The “Vienna Circle” („Wiener Kreis“) | 650 plus – Geschichte der Universität Wien, 7月 21, 2025にアクセス、 https://geschichte.univie.ac.at/en/articles/vienna-circle-wiener-kreis
- Vienna Circle – Wikipedia, 7月 21, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Circle
- Vienna Circle (Stanford Encyclopedia of Philosophy), 7月 21, 2025にアクセス、 https://plato.stanford.edu/entries/vienna-circle/
- Logical positivism | Philosophy of Science, Language & Knowledge – Britannica, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.britannica.com/topic/logical-positivism
- Logical Positivism | EBSCO Research Starters, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.ebsco.com/research-starters/religion-and-philosophy/logical-positivism
- Logical positivism – Wikipedia, 7月 21, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Logical_positivism
- Karl Popper Vindicated – Econlib, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.econlib.org/library/Columns/y2018/SchwartzPopper.html
- Karl Raimund Popper | EBSCO Research Starters, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.ebsco.com/research-starters/history/karl-raimund-popper
- Chapter Two Was Karl Popper a Positivist? – Brill, 7月 21, 2025にアクセス、 https://brill.com/previewpdf/book/9789401210454/B9789401210454-s004.xml
- Karl Popper – Wikipedia, 7月 21, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
- Popper’s Critical Rationalism – Reason Papers, 7月 21, 2025にアクセス、 https://reasonpapers.com/pdf/24/rp_24_1.pdf
- 6.1: Karl Popper – Humanities LibreTexts, 7月 21, 2025にアクセス、 https://human.libretexts.org/Bookshelves/Philosophy/An_Introduction_to_Philosophy_(Payne)/06%3A_Philosophy_of_Science/6.01%3A_Karl_Popper
- Falsifiability – Wikipedia, 7月 21, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Falsifiability
- Karl Popper: Falsification Theory – Simply Psychology, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.simplypsychology.org/karl-popper.html
- Karl Popper – Stanford Encyclopedia of Philosophy, 7月 21, 2025にアクセス、 https://plato.stanford.edu/entries/popper/
- en.wikipedia.org, 7月 21, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper#:~:text=Popper%20thought%20that%20Einstein’s%20theory,that%20gravity%20could%20deflect%20light
- Karl Popper’s Falsification – YouTube, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=wf-sGqBsWv4
- Karl Popper’s Concept of scientific change and development – ACJOL.Org, 7月 21, 2025にアクセス、 https://acjol.org/index.php/owijoppa/article/download/872/861
- What is the underlying critique Quine is making with his underdetermination thesis?, 7月 21, 2025にアクセス、 https://philosophy.stackexchange.com/questions/108774/what-is-the-underlying-critique-quine-is-making-with-his-underdetermination-thes
- Duhem–Quine thesis – Wikipedia, 7月 21, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Duhem%E2%80%93Quine_thesis
- Criticism of Falsifiability – PhilArchive, 7月 21, 2025にアクセス、 https://philarchive.org/archive/SFECOF-2
- Some Thoughts on Popper and the Duhem-Quine Thesis : r/PhilosophyofScience – Reddit, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/PhilosophyofScience/comments/16ijox/some_thoughts_on_popper_and_the_duhemquine_thesis/
- The Duhem-Quine Thesis Reconsidered – Part One – critical rationalism blog, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.criticalrationalism.net/2013/07/14/the-duhem-quine-thesis-reconsidered-part-one/
- en.wikipedia.org, 7月 21, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Kuhn%E2%80%93Popper_debate#:~:text=In%20the%20end%2C%20Popper%20was,with%20the%20history%20of%20science.
- Karl Popper vs. Thomas Kuhn — Jed Lea-Henry, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.jedleahenry.org/popperian-afterthoughts/2021/5/27/karl-popper-vs-thomas-kuhn
- Thomas Kuhn’s Skepticism Went Too Far — John Horgan (The Science Writer), 7月 21, 2025にアクセス、 https://johnhorgan.org/cross-check/thomas-kuhns-skepticism-went-too-far
- Popper vs Kuhn, Science and Progression – Philosophy Stack Exchange, 7月 21, 2025にアクセス、 https://philosophy.stackexchange.com/questions/38488/popper-vs-kuhn-science-and-progression
- ELI5: How does Imre Lakatos mean we should separate between science and pseudoscience? : r/PhilosophyofScience – Reddit, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/PhilosophyofScience/comments/l1zy1p/eli5_how_does_imre_lakatos_mean_we_should/
- Imre Lakatos (Stanford Encyclopedia of Philosophy), 7月 21, 2025にアクセス、 https://plato.stanford.edu/entries/lakatos/
- Karl Popper and Imre Lakatos (Chapter 12) – The Inexact and Separate Science of Economics – Cambridge University Press, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.cambridge.org/core/books/inexact-and-separate-science-of-economics/karl-popper-and-imre-lakatos/4F01E6F7FEB2376FA3ED8D732F3AEDF6
- My Encounter with Philosophical Anarchist Paul Feyerabend – John Horgan, 7月 21, 2025にアクセス、 https://johnhorgan.org/cross-check/my-encounter-with-philosophical-anarchist-paul-feyerabend
- Nicholas Maxwell, Observation, meaning and theory: Review of For and Against Method by Imre Lakatos and Paul Feyerabend – PhilArchive, 7月 21, 2025にアクセス、 https://philarchive.org/rec/MAXOMA-2
- Karl Popper vs. Paul Feyerabend — Jed Lea-Henry, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.jedleahenry.org/popperian-afterthoughts/2021/2/8/karl-popper-vs-paul-feyerabend
- Popper: Critical Rationalism | Internet Encyclopedia of Philosophy, 7月 21, 2025にアクセス、 https://iep.utm.edu/karl-popper-critical-ratiotionalism/
- karl popper’s critical rationalism and the quest for true democracy – ACJOL.Org, 7月 21, 2025にアクセス、 https://acjol.org/index.php/aksuja/article/download/4645/4516
- Scientific discovery in the age of artificial intelligence – Computer Science Cornell, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.cs.cornell.edu/gomes/pdf/2023_wang_nature_aisci.pdf
- Adaptive Monte Carlo Search for Conjecture Refutation in Graph Theory – arXiv, 7月 21, 2025にアクセス、 https://arxiv.org/abs/2306.07956
- The role of artificial intelligence in generating original scientific research – PubMed, 7月 21, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38181989/
- Explainability for Large Language Models: A Survey – New Jersey Institute of Technology, 7月 21, 2025にアクセス、 https://researchwith.njit.edu/en/publications/explainability-for-large-language-models-a-survey
- Exploring Explainability in Large Language Models – Preprints.org, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.preprints.org/manuscript/202503.2318/v1
- XAI Handbook: Towards a Unified Framework for Explainable AI – ResearchGate, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/356519846_XAI_Handbook_Towards_a_Unified_Framework_for_Explainable_AI
- From Understanding to Utilization: A Survey on Explainability for …, 7月 21, 2025にアクセス、 https://arxiv.org/abs/2401.12874
- A framework for falsifiable explanations of machine learning models with an application in computational pathology | Request PDF – ResearchGate, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/363210338_A_framework_for_falsifiable_explanations_of_machine_learning_models_with_an_application_in_computational_pathology
- Inductive Models for Artificial Intelligence Systems are Insufficient without Good Explanations – arXiv, 7月 21, 2025にアクセス、 https://arxiv.org/html/2401.09011v1
- [2501.09967] Explainable artificial intelligence (XAI): from inherent explainability to large language models – arXiv, 7月 21, 2025にアクセス、 https://arxiv.org/abs/2501.09967
- [2412.00800] A Comprehensive Guide to Explainable AI: From Classical Models to LLMs, 7月 21, 2025にアクセス、 https://arxiv.org/abs/2412.00800
- Induction, Popper, and machine learning – arXiv, 7月 21, 2025にアクセス、 https://arxiv.org/pdf/2110.00840
- AI Risks that Could Lead to Catastrophe | CAIS – Center for AI Safety, 7月 21, 2025にアクセス、 https://safe.ai/ai-risk
- AI safety – Wikipedia, 7月 21, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/AI_safety
- AI Safety, Ethics, and Society Textbook, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.aisafetybook.com/
- Critical Rationalism in Digital Age – Number Analytics, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.numberanalytics.com/blog/critical-rationalism-in-digital-epistemology