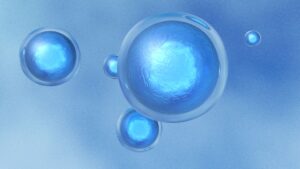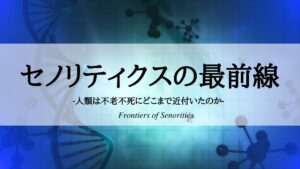第1部:シナプス可塑性の基礎 — 脳はなぜ「変わる」のか
1.1. シナプス可塑性とは?:脳の「学習」能力の源泉
私たちの脳は、固定された精巧な機械ではありません。それは、経験を通じて絶えず自らを再編成し、変化させ、適応していく、驚くべき「可塑性(Plasticity)」を持っています 1。この脳が持つ適応能力の根幹を成すのが、「シナプス可塑性(Synaptic Plasticity)」と呼ばれる現象です。
シナプスとは、約860億個あるとされる脳内の神経細胞(ニューロン)同士が情報を伝達するために形成する、微小な接合部のことです 1。思考、感情、行動、記憶といった私たちの精神活動のすべては、このシナプスを介したニューロン間の膨大な情報通信ネットワークによって支えられています。
シナプス可塑性とは、このシナプスにおける情報伝達の効率(「シナプス強度」や「結合強度」と呼ばれる)が、そのシナプスの活動(どれだけ頻繁に使われたか)に応じて、持続的に変化する能力そのものを指します 1。
この「使われるほどに変化する」という性質こそが、私たちが新しいスキルを学び、出来事を記憶する能力の物理的な基盤であると広く考えられています。そのため、シナプス可塑性は、発見以来、神経科学における最も集中的な研究対象の一つであり続けています 1。
この概念を一般の読者向けに解説する際、「森の中の小道」という比喩がしばしば用いられます 5。脳を広大な森に例えるならば、ニューロン間の特定の接続パターンは、森の中の潜在的な経路です。最初は草木に覆われて誰も通れませんが、誰か(特定の思考や行動)がそのルートを繰り返し通る(=ニューロンが繰り返し発火する)と、草が踏み固められ、次第に通りやすい「小道」(=強化されたシナプス)が形成されます。頻繁に使われる道は、やがて舗装された高速道路のように効率的な経路になります。逆に、長期間使われなくなった小道は、再び草木に覆われて自然に消えていきます(=弱化されたシナプス)2。
この比喩が示す重要な点は、脳の配線図が固定的なものではなく、経験そのものによってリアルタイムで常に書き換えられ続けているという事実です。シナプス可塑性は、学習の時だけオンになる「特殊機能」ではありません。それは、神経系が機能するための最も基本的な動作原理、すなわち脳の「デフォルトOS(オペレーティングシステム)」が「動的」であることを示しています。

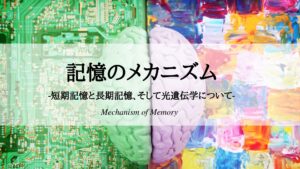
1.2. 短期可塑性と長期可塑性:数秒の「準備」と一生続く「記憶」
シナプス可塑性は、その変化が持続する時間スケールによって、大きく二つのカテゴリーに分類されます 3。
第一が「短期シナプス可塑性(Short-Term Plasticity, STP)」です。これは、数十ミリ秒から長くても数分程度しか持続しない、一時的な伝達効率の変化を指します 3。STPには、伝達効率が一時的に高まる「神経促通(neural facilitation)」や「増強(augmentation)」、逆に一時的に低下する「抑圧(depression)」などが含まれます 3。これらの短期的な変化は、主にシナプス前終末(情報を送る側)から放出される神経伝達物質の「放出確率」や「放出量」が一時的に変動することによって引き起こされます 3。
第二が「長期シナプス可塑性(Long-Term Plasticity)」です。これは、一度誘導されると数十分から数時間、数日、場合によっては一生涯にわたって持続する、非常に安定したシナプス強度の変化を指します 3。この持続性こそが、私たちが経験を「記憶」として長期間保持できることの物理的な基盤(記憶の基質)であると考えられています 4。この長期可塑性には、シナプス結合が持続的に強化される「長期増強(Long-Term Potentiation, LTP)」と、逆に持続的に弱化される「長期抑圧(Long-Term Depression, LTD)」の二つの主要な形態が存在します。
この短期と長期の区別は、単なる持続時間の違い以上の、重要な計算論的な意味を持っています。脳がなぜ両方の仕組みを必要とするのかを考えることで、その役割の違いが見えてきます。
長期可塑性(LTP/LTD)が、重要な情報を「永続的に保存」するためのストレージ(ハードディスク)としての役割を担うのは明らかです。では、短期可塑性(STP)の役割は何でしょうか。STPが動作する数十ミリ秒から数分というタイムスケール 3 は、私たちが電話番号を暗唱する間だけ覚えていたり、会話の文脈を一時的に保持したりする「作業記憶(ワーキングメモリ)」や、リアルタイムの情報処理のタイムスケールと一致します。
つまり、STPとLTP/LTDは、異なる計算的役割を担う、階層的なシステムを形成していると考えられます。STPは、リアルタイムの情報処理における「一時的な情報フィルター」や「プライミング(準備)」として機能します 3。これにより、ニューロンは直前の活動に応じて、後続の入力に対して一時的に敏感になったり(促通)、逆に鈍感になったり(抑圧)することができます。一方、LTP/LTDは、その一連の情報処理の結果が「重要である」と判断された場合にのみ発動し、その変化を「永続的に書き込む」ための保存メカニズムとして機能します。この洗練された階層構造により、脳は絶え間ない情報の洪水の中から、重要なものだけを選択して効率的に学習し、保存することができるのです。
1.3. すべては「理論」から始まった:ドナルド・ヘブの予言
今日のシナプス可塑性研究の巨大な潮流は、1949年にカナダの心理学者ドナルド・ヘブ(Donald O. Hebb)が出版した一冊の画期的な著書『行動の組織化(The Organization of Behavior)』から始まりました 1。当時、記憶が脳のどこに、どのように保存されているのかは全くの謎でした。ヘブは、この問いに対して、具体的な生物学的証拠がない時代に、純粋な論理的推論から学習と記憶の神経基盤に関する核心的な理論を提唱しました 10。
彼の核心的な仮説(ヘブの法則、またはヘブの公準と呼ばれる)は、次のように記述されています。
「細胞Aの軸索が細胞Bを興奮させるのに十分近く、繰り返しまたは持続的にその発火に関与するとき、AがBを発火させる細胞の一つとしての効率が増加するように、一方または両方の細胞で何らかの成長過程または代謝的変化が起こる」 8
このやや難解な一文は、今日では「共に発火するニューロンは結びつく(Neurons that fire together, wire together)」という、非常に有名かつ簡潔な言葉で要約されています 8。
これは、「もしニューロンAの発火が、ニューロンBの発火の原因となる(あるいはその発火に貢献する)ことを繰り返すなら、AからBへのシナプス結合は強化されるべきである」という、学習の基本原則を示しています。
驚くべきことに、ヘブは「AがBと同時に発火する」ことではなく、Bの「発火に関与する」こと、すなわちAがBの直前に発火するという「因果関係」の重要性を強調していました。この深い洞察は、それから約50年後に発見される「スパイクタイミング依存性可塑性(STDP)」という、まさにニューロン発火の前後関係(時間的先行性)が結合の変化方向を決定するという現象の基本原理を、正確に予見するものでした 8。
ヘブの法則の真の偉大さは、具体的な分子メカニズム(当時はLTPもAMPA受容体も未知だった)を特定する以前に、脳が学習という機能を実現するために、その構成要素(ニューロン)が論理的に満たさなければならない「計算ルール(学習アルゴリズム)」を定義した点にあります。彼は、「もし脳が学習するならば、そのハードウェアはこのようなルールに従って変化しなければならない」という論理的な必要条件を導き出したのです。
この「ヘブ学習(Hebbian learning)」8と呼ばれる理論は、その後の神経科学者たちにとっての「設計図」あるいは「宝の地図」となりました。彼らの使命は、このヘブが予言した抽象的なアルゴリズムを、脳内で物理的に実装している具体的な「ハードウェア」を発見することになったのです。
1.4. 「予言」の実験的証明:LTP(長期増強)の歴史的発見
ヘブの理論的予言から約20年の歳月が流れた1966年、その「ハードウェア」の発見に向けた決定的な一歩が、ノルウェー・オスロ大学のペル・アンデルセンの研究室で踏み出されました。若き日のテリエ・ローモ(Terje Lømo)は、麻酔をかけたウサギの脳内で、記憶形成に不可欠な領域として知られていた「海馬(hippocampus)」の電気生理学的研究を行っていました 4。
ローモは、海馬の主要な入力経路である「貫通線維(perforant path)」に電極を刺し、そこから下流にある「歯状回(dentate gyrus)」のニューロン群の応答を記録していました。その過程で、彼はある偶然の発見をします 13。
貫通線維に対し、ヘブが言うところの「繰り返しまたは持続的な」活動を模倣した、短時間(数秒間)の高頻度電気刺激(High-Frequency Stimulation, HFS; テタヌス刺激とも呼ばれる)を与えたところ、その刺激が終わった後も、通常の単発刺激に対する歯状回の応答(シナプス伝達の効率)が、劇的かつ何時間にもわたって持続的に増大することを発見したのです 12。
1968年、英国の研究者ティモシー・ブリス(Timothy Bliss)がローモの研究室に加わり、二人はこの謎めいた現象の系統的な解析に着手しました 12。そして1973年、彼らはこの持続的なシナプス強化現象を「長期増強(Long-Term Potentiation, LTP)」と名付け、その詳細な特性を報告する記念碑的な論文を『Journal of Physiology』に発表しました 11。
この発見は、瞬く間に神経科学界に衝撃を与えました。なぜなら、LTPという現象が、ヘブの理論的な「記憶」に求められる性質を完璧に満たしていたからです 15。それは、一度の強力な入力(学習)によって誘発され、非常に長期間持続し 4、かつ、刺激を与えられた特定のシナプス経路でのみ起こるという特異性を持っていました 15。
これは、まさに神経科学における「予言の成就」の瞬間でした 11。ブリスとローモが発見したLTPは、ヘブが抽象的に提唱した「共に発火し、結びつく」というアルゴリズムが、脳の特定の回路(海馬)において、電気生理学的に観測可能な「物理現象」として実在することを世界で初めて証明したのです 16。LTPこそが、ヘブの「アルゴリズム」を実行するための、具体的な「ハードウェア機構」そのものであったことが示されたのです。
第2部:シナプス可塑性の詳細なメカニズム — 分子レベルで見る「変化」の仕組み
LTPの発見は、「記憶はシナプス強度の変化である」という仮説を強力に支持しました。しかし、次の大きな問いは「どのようにして(How?)」でした。シナプスは、具体的にどのような分子メカニズムを使って、その結合強度を永続的に変化させるのでしょうか。この問いへの答えは、過去数十年にわたる分子生物学の目覚ましい進展によって、驚くべき解像度で解明されつつあります。
2.1. 可塑性の二大原理:LTP(長期増強)とLTD(長期抑圧)
学習と記憶のメカニズムは、単なる「強化」だけでは成り立ちません。前述のLTP(長期増強)が、シナプス結合を活動依存的に持続的に「強化」するプロセスであるのに対し 4、その対となる現象、すなわちシナプス結合を持続的に「弱化」させるプロセスも存在します。それが「長期抑圧(Long-Term Depression, LTD)」です 4。
LTPの発見から数年後、LTDもまた海馬で発見され、LTPと同様に学習と記憶(特に「忘却」や記憶の「消去」)において重要な役割を担うことが示唆されました 7。
興味深いことに、LTDの誘導メカニズムは、LTPと表裏一体の関係にあります。海馬のCA1領域と呼ばれる部位では、LTPが100 Hz(1秒間に100回)といった「高頻度刺激(HFS)」によって引き起こされるのに対し、LTDは1 Hz(1秒間に1回)といった「低頻度刺激(LFS)」を10~15分間といった長時間にわたって与え続けることで誘導されます 18。
LTPが記憶を「書き込む」ためのアクセルだとすれば、LTDは不要な記憶を「消去する」ためのブレーキ、あるいはLTPによって強くなりすぎた結合を「リセット」し、新たな学習に備えるための調整機構として機能すると考えられています 7。
このLTDの発見は、脳の学習システムを理解する上で極めて重要でした。もしヘブの法則「発火すれば結びつく」8というLTPのルールだけが存在した場合、学習を繰り返すたびにシナプス結合は際限なく強くなり続け、それがさらなる発火を呼び、最終的にはネットワーク全体が過剰に興奮し(てんかん発作のような状態)、飽和してしまう「暴走(runaway)」状態に陥るはずです。
LTD 17 は、脳がこの「暴走」を防ぎ、ネットワーク全体の活動レベルを安定した範囲内に保つ(ホメオスタティック可塑性 18)ための、洗練された「ブレーキ」機構を提供します。学習とは単なる「強化」ではなく、LTP(アクセル)による選択的な強化と、LTD(ブレーキ)による選択的な弱化が組み合わさった、言わば「彫刻」のようなプロセスなのです。不要な結合を削り落とし(LTD)、必要な結合だけを際立たせる(LTP)ことで、脳は限られたリソースの中で、膨大な情報を効率的に、かつ安定して保存することができるのです。
2.2. LTPの時間的フェーズ:数分の「強化」から、数時間の「再構築」へ
LTPは単一の現象ではなく、その誘導メカニズムと持続時間によって、複数の時間的な「フェーズ(段階)」に分類されます。このフェーズの違いは、記憶がどのようにして一時的なものから永続的なものへと「定着」していくかを分子レベルで説明する鍵となります 18。
LTPは、大まかに以下の段階に分けられます。
- PTP (Post-Tetanic Potentiation / 強直後増強): HFS刺激の直後から1~3分程度持続する、最も短命な増強。これは後述するNMDA受容体に依存せず、主にシナプス前終末からの神経伝達物質の放出が一時的に増加することによると考えられています 18。
- STP (Short-Term Potentiation / 短期増強; LTPaとも): PTPに続き、20~60分程度持続する中間的なフェーズ。これはNMDA受容体に依存します 18。
- E-LTP (Early LTP / 早期LTP; LTPbとも): 約1~3時間持続するLTPの初期段階。これはNMDA受容体に依存し、CaMKIIという酵素の活性化を必要としますが、決定的に重要なのは「新しいタンパク質の合成を必要としない」点です 18。
- L-LTP (Late LTP / 後期LTP; LTPcとも): 3時間以上、時には数日、数週間、あるいは一生持続する、LTPの永続的な段階。E-LTPと同様にNMDA受容体に依存しますが、E-LTPとの決定的な違いは「新しいタンパク質の合成と遺伝子の転写を必要とする」点です 18。このフェーズはPKAという別の酵素の活性化を介し、単なる既存タンパク質の修飾に留まらず、新しいシナプス構造の成長や再構築といった、物理的な変化を伴います 3。
この複雑なLTPの各フェーズの特性は、以下の表のようにまとめられます。
【表1:LTPの各フェーズの比較】
| フェーズ (Phase) | 持続時間 (Duration) | NMDA受容体依存性 | 主要なキナーゼ | タンパク質合成の必要性 | 主なメカニズム |
| PTP | 1-3分 18 | 独立 (Independent) 18 | – | 不要 (No) 18 | シナプス前・伝達物質放出増大 |
| STP (LTPa) | 20-60分 18 | 依存 (Dependent) 18 | – | 不要 (No) 18 | (詳細なメカニズムは研究中) |
| E-LTP (LTPb) | 1-3時間 18 | 依存 (Dependent) 18 | CaMKII 18 | 不要 (No) 18 | 既存AMPA受容体のリン酸化・挿入 |
| L-LTP (LTPc) | 3時間以上 18 | 依存 (Dependent) 18 | PKA 18 | 必要 (Yes) 18 | 新規タンパク質合成、遺伝子転写、シナプス構造変化 3 |
このE-LTPとL-LTPの区別は、心理学のレベルで古くから知られていた「短期記憶」と「長期記憶」の区別と、驚くほど見事に対応しています。
E-LTPは、既存のタンパク質を「修飾」するだけなので、迅速に(数分で)成立しますが、その効果は一時的(数時間)です 18。これは、今朝何を食べたかといった、すぐに形成されるが忘れやすい「短期記憶」の分子的実体に相当すると考えられます。
一方、L-LTPは、細胞核にシグナルを送り、DNAから新しい遺伝子を読み出し(転写)、新しいタンパク質を合成して、シナプスの「構造自体を物理的に作り変える」という、大掛かりなプロセスです 3。これは形成に時間がかかりますが、一度成立すると非常に永続的です。これは、自分の名前や自転車の乗り方といった、強固に定着した「長期記憶」の分子的実体(記憶の固定化、または固定化)に相当すると考えられています。
2.3. 分子の主役たち(1):NMDA受容体 —「学習の引き金」を引く検出器
では、このLTP/LTDという「変化」は、具体的にどの分子によって引き起こされるのでしょうか。
興奮性シナプスにおける可塑性の分子メカニズムの中心には、グルタミン酸(最も主要な興奮性の神経伝達物質)を受け取る二種類の受容体、「NMDA受容体」と「AMPA受容体」の絶妙な連携プレイが存在します 3。
中でも、LTPの「引き金(トリガー)」として決定的な役割を果たすのが、NMDA受容体です。
NMDA受容体は、他の多くの受容体とは異なる、非常にユニークな性質を持っています。それは、イオンを通すチャネルの内部が、ニューロンが静止している(興奮していない)通常の状況下では、**マグネシウムイオン($Mg^{2+}$)**によって物理的に「栓」をされている、という点です 21。
この$Mg^{2+}$の栓は、以下の二つの条件が「同時に」満たされたときにのみ、外れるようにできています 3。
- 条件1(化学的信号): シナプス前からグルタミン酸が放出され、NMDA受容体に結合する。(=「入力A」が来た)
- 条件2(電気的信号): シナプス後ニューロンが、他のシナプス(主にAMPA受容体)からの入力によって、すでに強く「興奮(脱分極)」している。(=「ニューロンB」が(ほぼ同時に)発火した)
この二つの条件が同時に満たされた瞬間、すなわち「ニューロンAが、ニューロンBの発火に貢献した」という偶然の一致を検出した瞬間にのみ、$Mg^{2+}$の栓が外れてチャネルが開き、大量の**カルシウムイオン($Ca^{2+}$)**がニューロンの内部へと滝のように流れ込みます 3。
この$Ca^{2+}$の流入こそが、LTPおよびLTDを引き起こすための、細胞内への「主要な引き金(トリガー)」シグナルとなります 3。
このNMDA受容体の仕組みは、生物学が生み出した最も驚異的な分子デバイスの一つと言えます。なぜなら、それはドナルド・ヘブが1949年に提唱した「共に発火すれば結びつく」という抽象的な心理学のルールを、単一の分子が持つ生物物理学的な特性(二重依存性)として、完璧に実装しているからです。
条件1(グルタミン酸結合)は「ニューロンAが発火した」ことを、条件2($Mg^{2+}$の除去)は「ニューロンBが発火した」ことを示します。NMDA受容体は、この二つの事象の「偶然の一致を検出するセンサー(Coincidence Detector)」として機能します。そして、この一致が検出された時にのみ、$Ca^{2+}$という「結びつけ!(Wire together!)」という細胞内への命令シグナルを送るのです。
2.4. 分子の主役たち(2):AMPA受容体 —「学習の成果」を担う実行部隊
NMDA受容体が「学習の引き金」を引くセンサーだとすれば、「学習の成果」を実際に実行し、シナプス強度を物理的に変化させる「実行部隊(Boots on the Ground)」が、もう一方の主役であるAMPA受容体です。
AMPA受容体は、LTPが起こる前の通常のシナプス伝達を主に担っている「作業部隊」であり、グルタミン酸が結合するとナトリウムイオン($Na^{+}$)を細胞内に入れ、ニューロンを興奮させます 20。
LTPの誘導プロセスは以下のように進行します 21。
- HFS(高頻度刺激)により、NMDA受容体が「偶然の一致」を検出し、大量の$Ca^{2+}$が細胞内に流入します。
- この大量の$Ca^{2+}$は、細胞内で「CaMKII(カルシウム/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼII)」と呼ばれる重要な酵素(リン酸化酵素)を活性化させます 3。
- 活性化したCaMKIIは、シナプス強度を高めるために、二つの主要な仕事を行います 3。
- 仕事1(質の向上): シナプス後膜(シナプス後肥厚部、PSDと呼ばれる)に既に存在しているAMPA受容体をリン酸化(特定の化学修飾)し、そのイオン伝導性を高めます。(=既存の受容体1個あたりの効率を上げる)
- 仕事2(量の増加): さらに重要なことに、CaMKIIは、細胞内に予備として蓄えられていた「新しいAMPA受容体」をシナプス後膜へと「運搬(トラフィッキング)」し、膜に「挿入(インサーション)」するプロセスを促進します 21。
LTPが「発現」した状態、すなわちシナプスが「強くなった」状態とは、最終的に、このシナプス後膜におけるAMPA受容体の数が物理的に増えることを指します 23。その結果、次に同じ量のグルタミン酸がシナプス前から放出されても、より多くのAMPA受容体がそれに応答し、より大きな興奮性電位(EPSP)をシナプス後ニューロンに発生させることができます。これが、LTP(シナプス強度の増強)の分子的な実体です。
このNMDA受容体とAMPA受容体の洗練された連携は、レストランの運営に例えると分かりやすいかもしれません。
- シナプスを「レストラン」に例えます。
- **グルタミン酸(神経伝達物質)**は、店にやってくる「客」。
- AMPA受容体は、客を実際に受け入れる「客席」。
- LTP前の状態: このレストランには客席(AMPA受容体)が5席しかありません。客(グルタミン酸)が来ても、5人分しか対応できず、店の活気(シナプス応答)は小さいままです。
- LTP誘導の瞬間: ある時、店に「ミシュランの覆面調査員(NMDA受容体)」がやってきます。彼は「客(グルタミン酸)がひっきりなしに来ており、かつ、店全体がすでに満席で賑わっている(=脱分極)」という二つの条件が揃っていることを確認します。この「偶然の一致」により、$Mg^{2+}$の栓が外れ、「この店は流行るに違いない!」という判断が下されます。調査員は、本部に連絡し、大量の「営業許可証($Ca^{2+}$)」を発行します。
- LTP発現(E-LTP): 許可証($Ca^{2+}$)を受け取った店長(CaMKII)は、「客席を増やせ!」と指示を出します。店の倉庫(細胞内)から予備の椅子(AMPA受容体)が次々と運び出され、シナプス後膜という「客席フロア」に挿入されます 21。
- LTP後の状態: その結果、このレストランの客席は5席から20席に増えました。次から、以前と同じ数の客(グルタミン酸)がやってきても、20人分対応できるため、店の活気(シナプス応答)は以前よりも恒久的に大きくなります。これがLTPです。
ちなみに、LTDはその逆のプロセスです。LFS(低頻度刺激)によって$Ca^{2+}$の流入が「少量」かつ「持続的」になると、CaMKIIではなく別の酵素(ホスファターゼ)が活性化し、「この店は流行っていない」と判断され、客席(AMPA受容体)が膜から「除去(エンドサイトーシス)」されてしまいます。その結果、シナプス強度は弱化するのです 3。
第3部:シナプス可塑性と「記憶エングラム」 — 記憶はどこに存在するのか?
3.1. LTPは本当に記憶のメカニズムか?
海馬でLTPが発見されて以来 12、それは「記憶の細胞メカニズムの最有力候補」として、神経科学の教科書の中心的な存在となってきました 4。しかし、試験管の中(in vitro)や脳スライスで観察される細胞現象が、生きた動物(in vivo)の「学習」や「記憶」という高次機能と本当に関係があるのか、という点は、長年にわたる厳密な検証を必要としました。
現在、LTPが記憶のメカニズムであるという仮説は、主に以下の三つの柱となる証拠によって、広く受け入れられています 4。
- 相関(Correlation): 動物が新しい課題(例えば、特定の場所を覚える空間記憶課題)を学習すると、記憶の中枢である海馬において、LTPを誘発した時と全く同じ分子的変化(AMPA受容体の増加など)が実際に観測されます 24。
- 必要性(Necessity): LTPの誘導に不可欠なNMDA受容体の機能を、APVと呼ばれる薬物でブロックすると、海馬でLTPが起きなくなります。そして、LTPをブロックされた動物は、新しい空間記憶を学習できなくなることが示されました(リチャード・モリスの水迷路課題が有名)4。これは、LTPが記憶の形成に「必要」であることを示しています。
- 十分性(Sufficiency): 近年のオプトジェネティクス(光遺伝学)のような高度な技術を用いると、特定のシナプス結合だけを人工的にLTP(またはLTD)させることができます。その結果、動物の記憶そのものを操作(例えば、特定の恐怖記憶を人工的に植え付けたり、消去したり)できることが示されつつあります 27。これは、LTPが記憶の形成に「十分」であることを示しています。
これらの証拠の蓄積は、神経科学における最大の成果の一つを意味します。なぜなら、それは「分子(NMDA受容体とAMPA受容体)」の微視的な挙動が、「細胞現象(LTP)」を引き起こし、それが最終的に「高次認知機能(記憶)」という抽象的な現象の原因となっていることを、実験的に証明したからです。LTPの研究は、「心(記憶)」と「脳(分子)」という、かつては哲学の領域であった二元論的な問いに、分子生物学の言葉で具体的な橋を架けたのです。
3.2. 記憶の物理的実体:「エングラム」
では、LTPによって強化されたシナプスは、脳内でどのように「記憶」を表現しているのでしょうか。
ここで登場するのが、「エングラム(Engram)」という概念です。エングラムとは、特定の記憶(例えば「昨日訪れたカフェの光景」)を保持するために、学習によってシナプス可塑性(LTPなど)による物理的・化学的な変化を遂げた、特定のニューロン集団(アンサンブル)のことを指します 27。すなわち、「記憶の物理的な痕跡」そのものです。
20世紀前半、心理学者のカール・ラシュレーは、ネズミの脳の様々な場所を切除しても、特定の記憶だけをきれいに消すことができなかったため、エングラムは特定の場所に「点」として存在するのではないと考え、その特定に失敗しました 27。しかし、ドナルド・ヘブが提唱した「細胞集合(Cell Assembly)」の理論 27 は、エングラムは特定の場所に局在するのではなく、脳の広範な領域に分散したニューロン群が「ネットワーク」として機能的に結合したものである、という現代的なエングラム観の基礎を築きました。
近年のオプトジェネティクスを用いた「エングラム標識技術」の革命的な進歩により、研究者はついに、ある特定の記憶(例:ある部屋で受けた恐怖体験)の学習中に活動したニューロン集団(=エングラム細胞)だけを、遺伝学的に「標識」し、後で可視化したり、操作したりすることが可能になりました 29。
その結果、以下のことが実証されました。
- 学習とは、脳内の特定のニューロン群が、その記憶の「エングラム細胞」として「割り当てられる」プロセスであること 29。
- そして、それらのエングラム細胞同士の間のシナプス結合が、LTPによって選択的に、かつ持続的に強化されること 27。
- 後に、そのエングラム細胞集団の一部が再活性化されると、強化された結合を介してネットワーク全体が発火パターンを「再生」し、それによって記憶が「想起」されること 28。
この一連の発見は、ヘブの法則を現代的にアップデートする必要性を示しました。もはや単に「ニューロンが共に発火し、結びつく」のではありません。より正確には、「エングラム細胞が共に発火し、結びつく(Engram cells that fire together, wire together)」のです 27。
このエングラムの概念は、私たちが「記憶」と呼ぶものの存在論を根本的に変えます。ラシュレーが探したように、記憶は、特定のニューロンの中に「モノ」として(例えば、ハードドライブ上のファイルのように)保存されているのではありません 27。
記憶とは、学習によって脳の複数の領域に分散して割り当てられたエングラム細胞の間に、LTPというプロセスによって形成された、強化された**「関係性(接続パターン)」**そのものなのです 27。LTPという「動詞」が、エングラムという「関係性の名詞」を創り出すのです。だからこそ、記憶は分散的であり、一部のニューロンが損傷しても(ある程度は)記憶が保持されるロバスト性(頑健性)を持つことができるのです。
3.3. LTPだけではない?:ニューロン自体の可塑性
長年にわたり、記憶研究の主役はシナプス可塑性(LTP/LTD)でした。しかし近年、それだけでは説明できない現象も報告されており、もう一つの重要な可塑性、「内在的可塑性(Intrinsic Plasticity)」の重要性が急速に注目を集めています 31。
内在的可塑性とは、シナプス(ニューロン間の「接続部」)の強さが変わるのではなく、ニューロン「自体」の電気的な性質、すなわち「興奮のしやすさ(発火のしきい値)」が変化する現象を指します 31。
例えば、動物が学習した後、その記憶を担うエングラム細胞を調べると、LTPによってシナプス入力が強化されているだけでなく、そのニューロン自体が、より弱い入力に対しても発火しやすくなるよう、「内在的な興奮性」が高まっていることが観察されています 31。
なぜ脳は、「シナプス可塑性」と「内在的可塑性」という、二重の学習メカニズムを必要とするのでしょうか。
これは、学習が効率的に行われるための、巧妙な協調作業である可能性を示唆しています。内在的可塑性 31 は、いわばニューロン全体の「感度ボリューム」を上げるように機能します。これにより、そのニューロンは「共に発火する」イベントに参加しやすくなり、その記憶のための「エングラム細胞」として選ばれやすくなる(プライミングされる)と考えられます 31。
そして、そのニューロンがエングラムとして「選ばれた」後で、シナプス可塑性(LTP) 4 が、より精密な「チューニング」として機能し、そのニューロンへの数千の入力の中から、特定の(その記憶に関連する)他のエングラム細胞からの入力だけを選択的に強化するのです。
学習とは、細胞全体の感度を上げる大まかな調整(内在的可塑性)と、接続一本一本の強度を精密に調整する(シナプス可塑性)という、二段階の見事な協調作業によって成り立っているのかもしれません。
第4部:可塑性を「見る」技術 — 実験手法の歴史と進化
シナプス可塑性という微小かつ複雑な現象の理解は、それを「見る」ための実験技術の革新と常に表裏一体の関係にありました。ブリスとローモの時代から現代に至るまで、技術の進歩が、私たちの脳理解の解像度を決定してきたのです。
4.1. 伝統的な手法:電気生理学
シナプス可塑性研究の基盤であり、今なお「黄金標準(ゴールドスタンダード)」とされるのが、ニューロンの電気活動を直接測定する「電気生理学(Electrophysiology)」です。
- 細胞外記録(Extracellular Recordings): ブリスとローモがLTPの発見に用いた古典的な手法です 14。微小な電極をニューロンの「外側」の細胞外液に配置し、近傍にあるニューロン集団の総合的な電気活動(フィールド電位、fEPSPと呼ばれる)を記録します。個々の細胞を区別することはできませんが、回路全体のシナプス応答の「総和」がLTPによってどう変化したかを調べるのに適しています 32。
- パッチクランプ法(Patch Clamp): 1970年代に開発され、神経科学に革命をもたらした技術です。先端が数マイクロメートルという極めて微細なガラス電極を、単一のニューロンの細胞膜に顕微鏡下で密着させ、その細胞「内」の電気活動を直接記録します 32。これにより、単一のニューロンがどのように発火するか、あるいは単一のシナプスから生じる微小な電気的応答(mEPSCsなど)を、サブミリ秒(1000分の1秒)以下という極めて高い時間分解能で測定することが可能になりました 32。
- ペア記録(Paired Recordings): パッチクランプ法の応用で、シナプスで接続していることがわかっている二つのニューロン(例:シナプス前細胞Aとシナプス後細胞B)から、二本の電極で同時に記録を行う技術です 32。研究者は、細胞Aを意図的に発火させ、それが細胞Bに引き起こす応答を直接測定できます。これにより、「AからBへ」という、特定された単一接続の可塑性(LTP/LTD)を直接、詳細に調べることが可能になりました 33。
これらの電気生理学的手法が、なぜ現代の華々しいイメージング技術の時代にあっても「黄金標準」であり続けるのでしょうか。それは、他の技術が測定するのが「活動の代理指標(例:カルシウム濃度の上昇)」32 や「静的な構造(例:電子顕微鏡写真)」34 であるのに対し、電気生理学は、脳の情報処理の根源的な通貨である「電気信号(シナプス後電位や活動電位)」そのものを、それが実際に起こっているサブミリ秒の時間スケールで、直接的に測定できる唯一の技術だからです 32。したがって、他のすべての新しい技術は、その測定結果の妥当性を、最終的にこの電気生理学のデータと照らし合わせて検証される必要があるのです。
4.2. 革命的技術(1):オプトジェネティクス(光遺伝学)
2000年代に登場した「オプトジェネティクス(Optogenetics)」は、電気生理学が「受動的に聞く」技術であったのに対し、「能動的に操作する」ことを可能にし、神経科学を根本的に変えました。
この技術は、光に反応してイオンを通すタンパク質(チャネルロドプシンなど、元は藻類などが持つタンパク質)の遺伝子を、ウイルスベクターなどを用いて、狙った特定の種類のニューロン(例:海馬の興奮性ニューロンだけ、あるいは特定の抑制性ニューロンだけ)に導入します 32。
その結果、研究者は、脳スライスや、さらには自由に動き回る生きた動物の脳内において、光ファイバーを通じて特定の色の光を当てるだけで、狙った細胞群だけをミリ秒単位の精度で「オン(発火)」させたり、「オフ(抑制)」させたりすることが可能になりました 32。
これがシナプス可塑性研究に何をもたらしたか。それは、「相関」から「因果」への飛躍です。
オプトジェネティクス以前は、「動物が学習する時、海馬が活動する」といった「相関関係」しか言えませんでした。しかしオプトジェネティクスを用いれば、「もし、学習中に海馬のこの特定の細胞群を光で抑制したら、学習は妨害されるか?」(=必要性の検証)、「もし、この特定の細胞群(エングラム細胞など)を、学習とは無関係に光で人工的に発火させたら、偽の記憶を作り出せるか?」(=十分性の検証)といった、ヘブの法則の因果関係を直接的に問う実験が可能になったのです 35。
4.3. 革命的技術(2):「オールオプティカル」アプローチ
電気生理学の「高時間分解能での読み取り」と、オプトジェネティクスの「細胞種特異的な書き込み」。これら二つの長所を融合させ、さらに「生きた動物の脳内(in vivo)」で実行しようとするのが、現代の最先端技術「オールオプティカル(All-Optical)」アプローチです。
このアプローチは、二つの主要な技術を「2光子顕微鏡(Two-photon microscopy)」という一つのプラットフォーム上で実行します。2光子顕微鏡は、光の散乱が少ない長波長の赤外線レーザーを用いることで、生きた動物の脳の表面下、数百マイクロメートルという深部を、細胞レベル、さらには単一のシナプス(樹状突起スパインと呼ばれる微小な突起)のレベルで、高解像度に観察することを可能にしました 36。
オールオプティカル・アプローチは、この2光子顕微鏡を使い、以下の二つを同時に行います 35。
- 光による「操作(書き込み)」: 2光子顕微鏡のレーザーを使い、オプトジェネティクスで特定のニューロンAを、単一細胞レベルの精度で狙い撃ちして発火させます 35。
- 光による「読み取り」: 同時に、遺伝子組み換えで導入された蛍光センサー(GECI: 遺伝子コード化カルシウムセンサー、またはGEVI: 遺伝子コード化電圧センサー)を使い、ニューロンAが接続している先のニューロンBの活動($Ca^{2+}$の上昇や膜電圧の変化)を、蛍光の輝度の変化として「読み取り」ます 35。
この技術により、神経科学者の長年の夢であった実験、すなわち「生きて行動している動物の脳内で、このニューロンAを光で刺激したら(書き込み)、その結果、接続先のニューロンBの単一のスパインでカルシウム信号(LTPの兆候)が検出される(読み取り)のを、リアルタイムで観察する」という実験が可能になりました 38。
ブリスとローモは麻酔下のウサギの「集団」の活動を 12、パッチクランプは脳スライスの「単一細胞」の活動を 32 見ていました。しかし、神経科学の究極の目標は、動物が「学習」している生理的な状態において、その瞬間にどのシナプスが変化するのかを捉えることでした 38。
オールオプティカル・アプローチは、この「単一シナプスの変化」と「動物の行動(学習)」との間の、最後のミッシングリンクを埋めるための「青写真(blueprint)」38 を提供します。研究者は今や、動物がある課題を学習しているまさにその瞬間に、特定のシナプス結合がLTPによって強化される様を観察し、同時にそのプロセスに光で介入することができるのです。
4.4. 究極の解像度:クライオ電子トモグラフィー(Cryo-ET)
オールオプティカル・アプローチが「機能」をリアルタイムで見る技術の頂点だとすれば、「構造」を見る究極の解像度を提供するのが、「クライオ電子トモグラフィー(Cryo-Electron Tomography, Cryo-ET)」です。
シナプスがどのように機能し、どのように可塑性を発現するかは、最終的に、AMPA受容体やNMDA受容体といったタンパク質が、シナプスという微小な空間内で、どのように「ナノスケール(分子レベル)で空間配置されているか」に依存します 34。
Cryo-ETは、生きた細胞や組織を「生きた」状態に近いまま(化学固定せずに)急速凍結させ、電子顕微鏡を使ってその3次元的な超微細構造を、分子レベルの解像度で直接可視化する技術です 34。
この技術が、従来のLTPの理解を覆す可能性のある、二つの重要な発見をもたらしました。
- PSDの「ナノブロック」構造: シナプス後膜のタンパク質が密集した領域(PSD)は、これまで均一な構造体と考えられてきました。しかしCryo-ETは、PSDが実際には、様々な受容体や足場タンパク質(PSD-95など)を含む、レゴブロックのような複数の「ナノブロック(nanoblocks)」または「ナノドメイン(nanodomains)」と呼ばれる、モジュール構造の集合体であることを明らかにしました 34。
- 受容体の精密な局在: AMPA受容体は、このPSD内で均一に分布しているのではなく、これらのナノドメイン内に「クラスター(集団)」を形成して偏在していることが示されました 25。
これらの発見は、シナプス可塑性に関する我々の理解に、重大なパラダイムシフトを迫るものです。
従来のLTPモデル(第2部のレストランの比喩)は、主に「シナプス後膜に挿入されるAMPA受容体の『数』を増やす」21 ことでシナプスが強くなる、という点に焦点を当ててきました。
しかし、Cryo-ETのデータ 34 が示唆しているのは、それと同じくらい、あるいはそれ以上に、**「受容体が『どこ』に配置されているか」**という「ナノスケールのトポグラフィー(空間配置)」が重要である、ということです。
シナプス前からグルタミン酸が放出される「放出部位(アクティブゾーン)」は、シナプス前膜のごく一部です。Cryo-ETを用いた研究は、AMPA受容体のクラスター 41 が、この放出部位の**「真向かい」という最適な位置に、どれだけナノメートル単位で正確に配置されているか**が、シナプス応答の強さを決定する上で極めて重要であることを示唆しています 41。
理論上、シナプスは、新しいAMPA受容体を1個も追加することなく、既存の受容体を放出部位の「真向かいのスイートスポット」に素早く「再配置」させるだけで、その応答強度を劇的に向上させることができるはずです。この「配置のチューニング(Alignment Tuning)」41 と呼ばれるメカニズムは、LTP/LTDの全く新しい形態である可能性があります。そして、PSDの「ナノブロック」構造 34 は、この動的かつ迅速な再配置を容易にするための、交換可能な「モジュール」として機能しているのかもしれないのです 40。
第5部:最新の研究動向(1) — シナプス可塑性の「異常」と脳疾患
シナプス可塑性が学習と記憶の基盤であるならば、そのメカニズムの「異常」や「破綻」は、深刻な認知機能や精神機能の障害を引き起こすはずです。近年、「シナプス病(Synaptopathy)」42 という概念が主流になっているように、アルツハイマー病(AD)や自閉症スペクトラム障害(ASD)といった多くの脳疾患が、本質的にシナプス機能と可塑性の障害であるという証拠が集積しています。
5.1. アルツハイマー病(AD):失われるシナプスと記憶
アルツハイマー病(AD)は、記憶障害を中核症状とする進行性の神経変性疾患です。長年、アミロイドβ($\text{A}\beta$)プラークや神経原線維変化(タウタンパク質)といった「ゴミ」の蓄積が原因とされてきましたが、近年の研究は、より根本的な原因を明らかにしています。
ADにおける認知機能の低下(特に新しい記憶の障害)は、ニューロン(神経細胞)そのものが死滅するよりもはるか以前の段階で起こる、「シナプスの機能不全と喪失」と極めて強く相関していることがわかっています 43。このため、ADは本質的に「シナプス病」であるという見方が、現在のコンセンサスとなっています 42。
ADの原因物質とされる $\text{A}\beta$ の可溶性オリゴマー(小さな凝集塊)や異常なタウタンパク質は、まさにシナプス可塑性のメカニズムを直接攻撃します。
具体的には、$\text{A}\beta$ オリゴマーは、AMPA受容体が存在する樹状突起スパインに直接結合し 43、LTP(記憶の強化)の誘導に不可欠なCaMKIIなどの分子経路を阻害します 24。さらに悪いことに、$\text{A}\beta$ はAMPA受容体のシナプスからの除去を促進し、LTPの「逆」、すなわちLTD(記憶の弱化)を異常に促進することが知られています 42。
この知見は、ADの症状(特に、古い記憶は比較的保たれるのに、新しいことが全く覚えられない)を、分子レベルで鮮やかに説明します。
ADとは、単に古い記憶が「失われる(忘却)」病気というよりも、まず第一に「新しいことを学習する(LTP)」能力が $\text{A}\beta$ によって強力にブロックされる病気なのです 45。さらに、$\text{A}\beta$ はLTD(シナプスを弱めるプロセス)を異常に促進する 45 ため、既存の記憶を保持している健康なシナプス結合まで、積極的に「解体」してしまうと考えられます。
つまり、ADの脳では、「学習」のアクセルが踏めなくなり、同時に「脱学習(忘却)」のブレーキが踏みっぱなしにさせられる。これがADのシナプスレベルでの実体です。この「シナプス可塑性の異常」こそが根本原因であるという理解に基づき、2024年から2025年にかけての最新の治療戦略は、単に $\text{A}\beta$ を除去するだけでなく、シナプスの機能不全を直接ターゲットにし、「ニューロプラスティシティ(神経可塑性)を高める」ことを目的とした新しい薬剤(例:LTPを促進する薬剤やカルシニューリン阻害剤)の開発へとシフトしており、有望な結果が報告され始めています 44。
5.2. 自閉症スペクトラム障害(ASD):つながりの「異常」
自閉症スペクトラム障害(ASD)もまた、その中核にシナプス機能の障害(シナプス病)があると広く考えられている、主要な神経発達障害の一つです 46。
ASDの特有の症状、すなわち社会的コミュニケーションの困難、限定された興味や反復行動、そして特異な感覚処理(感覚過敏や鈍麻)は、脳の発達期における「異常なニューロプラスティシティ」に起因する、神経回路の「接続異常」によって説明される、という仮説が有力です 46。
2024年に発表された最新のシステマティックレビュー(複数の研究を統合した分析)によると、ASDの脳では、脳領域間の機能的な接続性が、健常者と比較して「高すぎる(ハイパーコネクティビティ)」領域と、「低すぎる(ハイポコネクティビティ)」領域が混在していることが一貫して示されています 46。
この接続のアンバランスは、LTPとLTDのバランスが崩れ、正常な発達期に起こるべきシナプスの「刈り込み(Pruning)」(=不要なシナプス結合がLTDなどによって除去され、回路が洗練されていくプロセス)2 が適切に行われなかった結果である可能性が指摘されています。
この「ASD=シナプス病」仮説を強力に裏付けているのが、遺伝学的知見です。ASDの発症リスクと関連する遺伝子(SHANKファミリー, NLGN, NRXNなど)の多くが、まさにLTPとLTDの舞台となるシナプス後肥厚部(PSD)の構造を支える「足場タンパク質」や、シナプス同士を接着させる「接着分子」をコードしていることが判明しているのです 47。
これらの知見は、ASDの本質についての新たな視点を提供します。ASDにおける問題は、単に接続が「多すぎる」か「少すぎる」かという静的な問題ではなく、「適応的」あるいは「柔軟」な可塑性が失われているという動的な問題である可能性が示唆されます。
健康な脳は、予測不可能な社会的シグナルや、刻々と変化する感覚入力(音、光、触覚)に応じて、常にLTPとLTDを駆使してシナプス結合の強度をリアルタイムで「微調整」し、環境に「適応」しています 46。しかし、ASDの脳は、これらの研究知見 46 に基づけば、より「固直的(rigid)」な接続状態に陥っており、新しい社会的合図や予期せぬ感覚入力に対して、シナプス強度を柔軟に「適応(adapt)」させることが困難になっているのかもしれません 46。その結果として、感覚入力の処理がうまくいかず(感覚過敏)、あるいは他者の意図を読み取る社会的認知が困難になるといった症状が発現するのではないか、と考えられています。
第6部:最新の研究動向(2) — AIとニューロモルフィック・コンピューティング
シナプス可塑性の研究は、医学だけでなく、全く異なる分野、すなわち人工知能(AI)とコンピュータ・アーキテクチャの未来にも、決定的な影響を与えようとしています。
6.1. なぜAIは「生物の脳」を目指すのか?
現代のAI、特にディープニューラルネットワーク(ANN)は、画像認識や自然言語処理で驚異的な成功を収めています。しかし、その「学習」と「推論」は、膨大な教師データと、データセンターのサーバー群が消費する莫大な電力を必要とする、非常に「リソース集約型」のプロセスです 49。
対照的に、私たち生物の脳は、わずか20ワット程度(電球一個分)の消費電力で、ANNを遥かに凌駕する複雑な情報処理、リアルタイムでの学習、そして環境への適応を実現しています 50。
この圧倒的な「エネルギー効率」と「適応性」のギャップを埋めるために、工学者たちはAIの設計思想を根本から見直し、生物の脳の構造と動作原理を模倣するアプローチへと向かっています。それが「ニューロモルフィック・コンピューティング(Neuromorphic Computing)」です 50。
このアプローチの中核を成すのが、従来のANNとは異なる「スパイキングニューラルネットワーク(SNN)」です 49。SNNは、生物のニューロンが「0か1か」のデジタルな電気信号である「スパイク(活動電位)」を使って、非同期的に(必要な時だけ)通信する様式を模倣します 53。これにより、原理的に極めて低消費電力な情報処理が可能になると期待されています 49。
AI研究の目標は、単に「知能」のスコアを模倣することから、脳の持つ「効率性」と「適応性」を模倣することへと、大きくシフトしつつあります。その究極の目標は、もはやデータセンターに繋がれた巨大なAIではなく、ロボットの制御システムや、体内に埋め込む医療インプラント 50 のような「エッジ」デバイス上で、周囲の環境からリアルタイムに「オンチップ学習(On-chip learning)」できる、真に適応的なAIを実現することにあるのです。
6.2. AIに「シナプス可塑性」を実装する
この「オンチップ学習」を実現するための鍵こそが、生物の脳から学ぶべき最大の秘訣、すなわち「シナプス可塑性」の実装です。
従来のANNでは、一度「学習」が完了すると、ニューロン間の結合の重み(ウェイト)は「静的(static)」に固定されます。しかし、生物の脳は、生まれてから死ぬまで、環境の変化に応じて常に学習(可塑性)を続けています 54。
ニューロモルフィック・コンピューティングの核心は、この生物学的な「シナプス可塑性」のルール、すなわち「学習則」を、AIのアルゴリズムや、それを動かす専用のハードウェア(ReRAMやメモリスタといった、シナプスの可塑的な抵抗変化を物理的にエミュレートできる新しいデバイス)52 に、直接実装することです 53。
最も注目されている生物学的な学習則が、二つあります。
- STDP (Spike-Timing-Dependent Plasticity / スパイクタイミング依存性可塑性): これは、第1部で触れたヘブの法則 8 を、時間的に極めて洗練させたルールです 53。STDPが重視するのは、発火の「タイミング」と「順序(因果関係)」です。
- もし、シナプス前ニューロンAの発火が、シナプス後ニューロンBの発火の直前(数ミリ秒前)に起これば(=AがBの原因となった)、そのシナプス結合は**強化(LTP)**されます。
- 逆に、もしBの発火がAの発火の直後に起これば(=因果関係がない、または逆)、その結合は**弱化(LTD)**されます 53。
この単純な「タイミング」のルールだけで、SNNは入力データの時間的なパターンや因果関係を、教師なしで(自律的に)学習できることが示されています。
- BCMルール (Bienenstock-Cooper-Munro Rule): これは、第2部で触れたホメオスタティック可塑性 19 の一種です。BCMルールは、ニューロンの全体的な活動レベルが高くなりすぎると、LTPが起こる閾値を自動的に引き上げ(=LTPを起こりにくくし)、LTDを起こりやすくします。逆に活動レベルが低すぎると、LTPを起こりやすくします。これにより、STDPによる学習が「暴走」するのを防ぎ、ネットワーク全体の活動を安定に保ちながら学習を進めることができます 53。
しかし、AI研究の最先端は、単に生物学のルール(STDPやBCM)をハードウェアにコピーするだけでは満足しません。生物学的なルールの「適応性」と、現代AI(深層学習)の最大の武器である「勾配降下法(バックプロパゲーション)」という強力な最適化手法を、どうにかして融合できないか、という研究が進んでいます。
その答えが、「微分可能な可塑性(Differentiable Plasticity)」というハイブリッドなアプローチです 54。
これは、SNNのシナプス結合の重みを固定するのではなく、「可塑性のルール自体(例:STDPのLTPが起こる条件や強さのパラメーター)」を、勾配降下法によって学習可能にしてしまう、という画期的なアイデアです 54。AIは、ある特定のタスク(例:ロボットの歩行制御)を最も効率的に解くために、「自分はどのような学習則(可塑性ルール)を持つべきか」を、学習によって自ら見つけ出すのです 54。
このアプローチにより、SNNは、生物学的なSTDPやBCMのパラメーターを最適化することもできれば 54、時には生物学では(まだ)見つかっていないような、全く新しい可塑性ルールを「発明」することさえできます。
これは、生物学的な脳の「適応性・効率性」と、深層学習の「強力な最適化能力」を融合させる、まさに最先端の架け橋です。この「微分可能な可塑性」を搭載したSNNは、従来の静的なネットワークでは解くことが極めて困難であった、ノイズの多い複雑な「時間的タスク」を見事に解決できることが示されており 54、次世代AIの姿を予感させます。
第7部:結論 — シナプス可塑性が拓く未来
本レポートでは、「シナプス可塑性」という、神経科学の核心を成す概念の全貌を、その誕生から最先端の応用まで、包括的に解説してきました。
その物語は、1949年のドナルド・ヘブによる「共に発火するニューロンは結びつく」という、心理学的な「理論的予言」から始まりました 8。
その予言は、1973年、ブリスとローモによるウサギの海馬での「LTP(長期増強)」という物理現象の「実験的発見」によって、見事に成就しました 12。
その後の分子生物学の爆発的な進展は、LTPとLTDという現象が、「NMDA受容体」という偶然の一致検出センサーと、「AMPA受容体」という実行部隊の絶妙な連携プレイによって引き起こされることを明らかにしました 21。
私たちは、このシナプス可塑性というメカニズムこそが、特定のニューロン集団「エングラム」間の接続パターンを物理的に書き換えることで、「記憶」という高次の精神活動を符号化するプロセスそのものであることを理解しました 27。
そして、私たちの「目」は、技術の進歩と共に、その解像度を飛躍的に高め続けています。電気生理学 32 がその「機能」を捉え、オプトジェネティクス 35 がその「因果」を証明し、オールオプティカル・イメージング 38 が生きた脳での「動態」を暴き、そしてクライオ電子トモグラフィー(Cryo-ET)34 が、受容体の「ナノスケールの配置」41 という、可塑性の新たな次元を切り拓いています。
このシナプス可塑性という、脳の最も基本的な動作原理の深い理解は、今、二つの大きな未来へと応用されようとしています。
一つは、「医学」への応用です。アルツハイマー病 44 や自閉症スペクトラム障害 46 といった難治性の脳疾患を、シナプス可塑性の「異常(シナプス病)」として捉え直し、そのメカニズムを正常化することで根本的な治療を目指す道です。
もう一つは、「工学」への応用です。生物の脳が持つ「学習(可塑性)」の原理を、STDPや微分可能な可塑性といった形でハードウェアに実装し、エネルギー効率が高く、真に「適応的」な次世代AI(ニューロモルフィック・コンピューティング)を創り出す道です 50。
シナプス可塑性の研究とは、本質的に「過去の経験(=発火パターン)が、どのようにして脳という物理的な構造(=シナプス強度)を書き換え、未来の行動(=情報処理)を決定するのか」という、因果の連鎖を解明する壮大な試みです。
それは、一瞬の「思考」や「経験」という非物質的だったものが、AMPA受容体の挿入 23 やシナプススパインの成長 3 といった「物質」へと変換されるプロセスを記述する、生命の物理法則です。
この法則の理解こそが、私たちが「私たち」である理由、すなわち「なぜ学習し、記憶し、環境に適応できるのか」という、生命科学における最も根本的な問いへの、現時点での最も深く、かつ美しい答えなのです。
引用文献
- What is synaptic plasticity? – Queensland Brain Institute – University …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://qbi.uq.edu.au/brain-basics/brain/brain-physiology/what-synaptic-plasticity
- How Neuroplasticity Works – Verywell Mind, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.verywellmind.com/what-is-brain-plasticity-2794886
- Synaptic plasticity – Wikipedia, 11月 9, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Synaptic_plasticity
- Long-term potentiation – Wikipedia, 11月 9, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Long-term_potentiation
- The Learning Science Behind Analogies – Edutopia, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.edutopia.org/article/using-analogies-teaching/
- Synaptic Plasticity (Section 1, Chapter 7) Neuroscience Online: An Electronic Textbook for the Neurosciences | Department of Neurobiology and Anatomy – The University of Texas Medical School at Houston, 11月 9, 2025にアクセス、 https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/m/s1/chapter07.html
- 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.amed.go.jp/news/release_20181009-02.html#:~:text=%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%97%E3%82%B9%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E4%BC%9D%E9%81%94%E3%81%8C,%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%97%E3%82%B9%E5%8F%AF%E5%A1%91%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- Hebbian theory – Wikipedia, 11月 9, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Hebbian_theory
- Donald Hebb – The Decision Lab, 11月 9, 2025にアクセス、 https://thedecisionlab.com/thinkers/neuroscience/donald-hebb
- Donald Hebb Formulates the “Hebb Synapse” in Neuropsychological Theory, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=3902
- The History of Neuroscience in Autobiography Volume 7 Terje Lømo – SfN, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.sfn.org/-/media/SfN/Documents/TheHistoryofNeuroscience/Volume-7/c9.pdf
- The discovery of long-term potentiation – PMC, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1693150/
- Long-Term Potentiation: The Accidental Discovery – PubMed, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39648690/
- Bliss, T. V. P., Collingridge, G., Morris, R. G. M., & Reymann, K. G. (2018). Long-term potentiation in the hippocampus: dis, 11月 9, 2025にアクセス、 https://research-information.bris.ac.uk/files/169826095/_Neuroforum_Long_term_potentiation_in_the_hippocampus_discovery_mechanisms_and_function.pdf
- The discovery of long-term potentiation – ResearchGate, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/10766327_The_discovery_of_long-term_potentiation
- The history of long-term potentiation as a memory mechanism: Controversies, confirmation, and some lessons to remember – PubMed, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32442358/
- Synaptic plasticity: LTP and LTD – PubMed, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7919934/
- Synaptic Plasticity Review – Hello Bio, 11月 9, 2025にアクセス、 https://hellobio.com/synaptic-plasticity-review
- Synaptic plasticity: taming the beast – Columbia University, 11月 9, 2025にアクセス、 http://www.columbia.edu/cu/neurotheory/Larry/AbbottNatNeuro00.pdf
- Developmental Changes in Synaptic AMPA and NMDA Receptor Distribution and AMPA Receptor Subunit Composition in Living Hippocampal Neurons | Journal of Neuroscience, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.jneurosci.org/content/20/21/7922
- Synaptic Plasticity 101: The Story of the AMPA Receptor for the …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10479373/
- Synaptic plasticity of NMDA receptors: mechanisms and functional implications – PMC, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3482462/
- Synaptic Plasticity: The Role of Learning and Unlearning in Addiction and Beyond – PMC, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5347979/
- Long-Term Potentiation and Depression as Putative Mechanisms for Memory Formation, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3912/
- The role of AMPA receptors in postsynaptic mechanisms of synaptic plasticity – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/cellular-neuroscience/articles/10.3389/fncel.2014.00401/full
- A potential mechanism for the first-person inner sensation of memory provides evidence for a relationship between learning and LTP induction | bioRxiv, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/085589v2.full-text
- Memory engrams: Recalling the past and imagining the future – PMC, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7577560/
- A Synaptic Framework for the Persistence of Memory Engrams – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/synaptic-neuroscience/articles/10.3389/fnsyn.2021.661476/full
- Synaptic Plasticity, Engrams, and Network Oscillations in Amygdala Circuits for Storage and Retrieval of Emotional Memories – PubMed, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28521127/
- Interrogating structural plasticity among synaptic engrams – PubMed, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35598549/
- The Role of Intrinsic Plasticity in Engram Physiology and Temporal Memory Linking, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.jneurosci.org/content/44/37/e1160242024
- Approaches and Limitations in the Investigation of … – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/synaptic-neuroscience/articles/10.3389/fnsyn.2019.00020/full
- Approaches and Limitations in the Investigation of Synaptic Transmission and Plasticity – PMC – PubMed Central, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6667546/
- Cryo-electron tomography reveals postsynaptic nanoblocks in …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.05.12.540562v2.full-text
- Two-photon optogenetics-based assessment of neuronal connectivity in healthy and chronic hypoperfusion mice – PubMed Central, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11436461/
- Simultaneous two-photon imaging and two-photon optogenetics of cortical circuits in three dimensions | eLife, 11月 9, 2025にアクセス、 https://elifesciences.org/articles/32671
- Two-photon single-cell optogenetic control of neuronal activity by sculpted light | PNAS, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1006620107
- All-optical voltage interrogation for probing synaptic plasticity in vivo …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12494759/
- Neuronal synaptic architecture revealed by cryo-correlative light and electron microscopy, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12213663/
- Cryo-EM tomography and automatic segmentation delineate modular structures in the postsynaptic density – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/synaptic-neuroscience/articles/10.3389/fnsyn.2023.1123564/full
- Nanoscale architecture of synaptic vesicles and scaffolding … – PNAS, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2403136121
- Alzheimer’s disease as a synaptopathy: Evidence for dysfunction of synapses during disease progression – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/synaptic-neuroscience/articles/10.3389/fnsyn.2023.1129036/full
- Synaptic Compensatory Plasticity in Alzheimer’s Disease – Journal of Neuroscience, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.jneurosci.org/content/43/41/6833
- A review on recent advances in Alzheimer’s disease: The role of …, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12287638/
- Synaptic Plasticity and Oscillations in Alzheimer’s Disease: A Complex Picture of a Multifaceted Disease – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/molecular-neuroscience/articles/10.3389/fnmol.2021.696476/full
- Neuroplasticity of children in autism spectrum disorder – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2024.1362288/full
- Key Synaptic Pathology in Autism Spectrum Disorder: Genetic Mechanisms and Recent Advances – IMR Press, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.imrpress.com/journal/JIN/23/10/10.31083/j.jin2310184/htm
- Neuroplasticity in autism spectrum disorder: a systematic review, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.demneuropsy.org/article/neuroplasticity-in-autism-spectrum-disorder-a-systematic-review/
- Spiking Neural Networks and Their Applications: A Review – PMC – PubMed Central – NIH, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9313413/
- Neuromorphic algorithms for brain implants: a review – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2025.1570104/full
- Recent advances in fluidic neuromorphic computing – AIP Publishing, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pubs.aip.org/aip/apr/article/12/2/021309/3344844/Recent-advances-in-fluidic-neuromorphic-computing
- ニューロモルフィックハードウェアの神経可塑性実装|最新レビュー論文まとめ(2020-2025年), 11月 9, 2025にアクセス、 https://research.smeai.org/neuromorphic-synaptic-plasticity-review-2020-2025/
- A Quarter of a Century of Neuromorphic Architectures on FPGAs – an Overview – arXiv, 11月 9, 2025にアクセス、 https://arxiv.org/html/2502.20415v3
- SpikePropamine: Differentiable Plasticity in Spiking … – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/neurorobotics/articles/10.3389/fnbot.2021.629210/full
- Synaptic Plasticity in Memristive Artificial Synapses and Their Robustness Against Noisy Inputs – Frontiers, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2021.660894/full
- Brain-inspired learning in artificial neural networks: A review – AIP Publishing, 11月 9, 2025にアクセス、 https://pubs.aip.org/aip/aml/article/2/2/021501/3291446/Brain-inspired-learning-in-artificial-neural
- A triplet spike-timing–dependent plasticity model generalizes the Bienenstock–Cooper–Munro rule to higher-order spatiotemporal correlations | PNAS, 11月 9, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1105933108