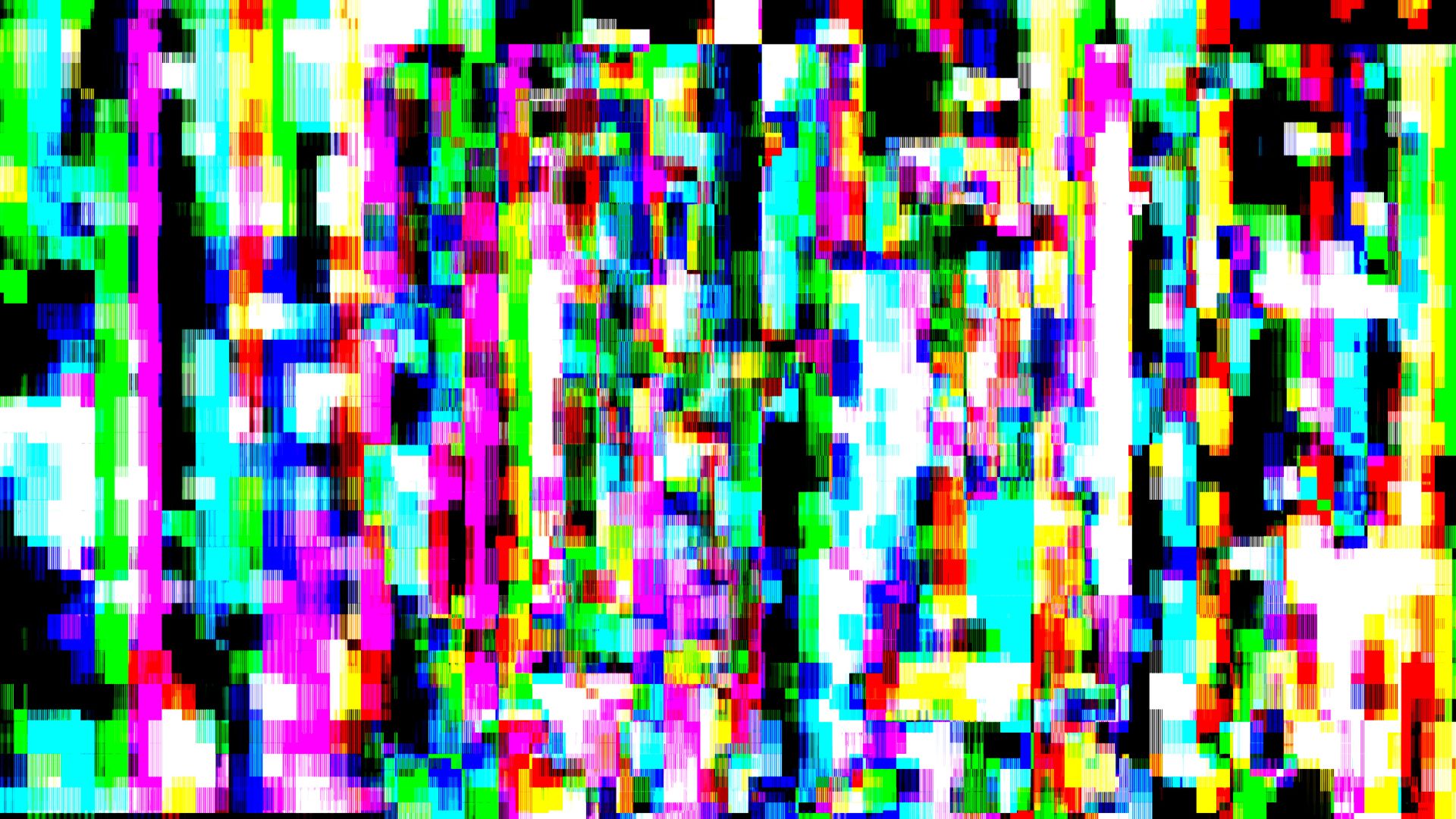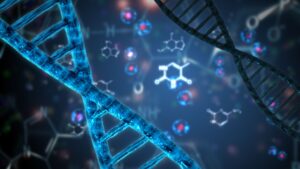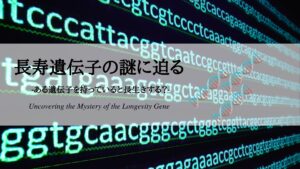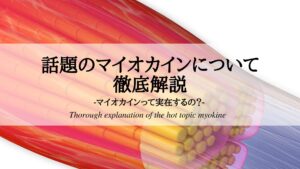1. 序論:生命における「情報処理」の精緻なシステム
生命とは、物質そのものではなく、物質を介して流れる「情報」の動的な平衡状態であると定義することができます。単一の受精卵から複雑な多細胞生物へと発生し、恒常性を維持し、環境の変化に適応して生存するためには、細胞間および細胞内における精緻かつ堅牢な通信ネットワークが不可欠です。この生物学的通信インフラストラクチャこそが**細胞内情報伝達系(Intracellular Signal Transduction)**です。
細胞膜という境界において、外部からの化学的・物理的シグナル(リガンド)が受容体(レセプター)によって感知され、その情報が細胞内部の生化学的反応経路(パスウェイ)を通じて変換・増幅・統合され、最終的に遺伝子発現や代謝変化といった細胞応答(レスポンス)へと出力されます。
本レポートでは、システム生物学の観点から、細胞内情報伝達系の全貌を、その物理化学的メカニズム、発見の歴史、実験手法の進化、そして2024年から2025年にかけての最先端の研究トレンド(液-液相分離、空間的トランスクリプトミクス、AIによる構造予測)に至るまで、網羅的かつ詳細に解説します。
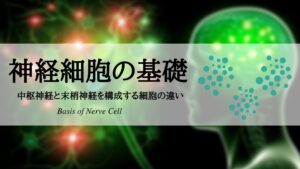
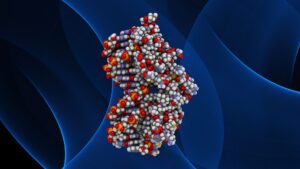
2. 細胞内情報伝達系の基盤メカニズム:分子レベルの論理回路
細胞内情報伝達は、単なる分子のドミノ倒しではありません。それは、情報の特異性(Specificity)、増幅(Amplification)、脱感作(Desensitization/Adaptation)、そして統合(Integration)という高度な制御特性を備えたシステムです。これらの特性は、電子回路における論理ゲート(AND, OR, NOT, NANDなど)やフィードバックループとして機能し、細胞がノイズの多い環境下でも正確な意思決定を行うことを可能にしています 1。
2.1 受容(Reception):シグナル識別の熱力学
情報伝達の第一歩は、細胞外のシグナル分子(リガンド)と細胞膜上の受容体タンパク質との特異的な結合から始まります。この結合は、共有結合のような不可逆的なものではなく、水素結合、イオン結合、ファンデルワールス力などの非共有結合による可逆的な平衡反応です。受容体は、リガンドに対して極めて高い親和性(Affinity)を持ち、ピコモル($10^{-12}$ M)からナノモル($10^{-9}$ M)オーダーの低濃度でもシグナルを捕捉します 2。
膜受容体の主要ファミリーとその作動原理
細胞膜を通過できない親水性シグナル分子(ペプチドホルモン、神経伝達物質など)は、細胞表面の受容体を介して情報を伝達します。これらは主に3つのクラスに大別されます。
| 受容体の種類 | 構造的特徴 | 作動メカニズム | 代表的なリガンドと生理機能 |
| Gタンパク質共役型受容体 (GPCR) | 7回膜貫通型 $\alpha$ ヘリックス構造を持つ最大ファミリー。 | リガンド結合により構造変化(コンフォメーション変化)を起こし、細胞内の三量体Gタンパク質($\alpha, \beta, \gamma$)のGDPをGTPに交換して活性化させる 3。 | アドレナリン(闘争・逃走反応)、光(ロドプシン/視覚)、匂い分子(嗅覚)、ケモカイン(免疫)。創薬ターゲットの約30-40%を占める 3。 |
| 酵素連結型受容体 (Enzyme-Linked Receptors) | 1回膜貫通型。細胞内ドメインに酵素活性を持つか、酵素と会合する。 | リガンド結合により二量体化し、相互リン酸化(オートフォスフォリレーション)を引き起こす。これによりシグナル伝達複合体のドッキングサイトが形成される 2。 | インスリン(代謝制御)、EGF(上皮成長因子/細胞増殖)、VEGF(血管新生)。がん研究における主要ターゲット。 |
| イオンチャネル型受容体 (Ligand-Gated Ion Channels) | 多量体からなる膜孔形成タンパク質。 | リガンド結合がゲートの開閉を直接制御し、イオン($Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-$)の流束を変化させ、膜電位を瞬時に変える 2。 | アセチルコリン(神経筋接合部)、グルタミン酸(中枢神経興奮)、GABA(抑制性伝達)。ミリ秒単位の高速伝達を担う。 |
また、脂溶性のシグナル分子(ステロイドホルモン、甲状腺ホルモン、一酸化窒素など)は、細胞膜を直接透過し、細胞質または核内に存在する**核内受容体(Nuclear Receptors)**に結合します。これらは受容体自身が転写因子として機能し、DNA上のホルモン応答配列(HRE)に結合して遺伝子発現を直接制御します 2。
2.2 変換(Transduction):分子スイッチとセカンドメッセンジャー
受容体が受け取った情報は、細胞内で扱いやすい形式に「変換」され、拡散されます。ここで中心的な役割を果たすのが、Gタンパク質やリン酸化酵素による分子スイッチ機構と、セカンドメッセンジャーシステムです。
Gタンパク質のサイクルと分子スイッチ
Gタンパク質は、GTP結合状態(ON)とGDP結合状態(OFF)を行き来する分子タイマーとして機能します。活性化したGPCRは、Gタンパク質の $\alpha$ サブユニットに結合しているGDPを放出し、細胞内に豊富なGTPを結合させます。これにより、$\alpha$ サブユニットと $\beta\gamma$ 複合体が解離し、それぞれが下流のエフェクター(酵素やイオンチャネル)を制御します。重要なのは、$\alpha$ サブユニット自身がGTP加水分解酵素(GTPase)活性を持っており、一定時間後にGTPをGDPに戻して自らを不活性化することです。この自動停止機構が、シグナルの暴走を防いでいます 3。
セカンドメッセンジャーの拡散と増幅
受容体活性化の結果、細胞内で合成または放出される低分子物質がセカンドメッセンジャーです。
- サイクリックAMP (cAMP): アデニル酸シクラーゼによってATPから合成されます。cAMPはプロテインキナーゼA (PKA) を活性化し、代謝や遺伝子発現を調節します。この経路の発見は、ホルモン作用の分子的理解の端緒となりました 2。
- イノシトールリン脂質とカルシウム: ホスホリパーゼC (PLC) が膜脂質のPIP2を分解し、IP3とDAG(ジアシルグリセロール)を生成します。IP3は小胞体(ER)上の受容体に結合し、細胞内カルシウムストアから $Ca^{2+}$ を放出させます 8。細胞質内の $Ca^{2+}$ 濃度上昇は、カルモジュリンなどの結合タンパク質を介して、筋収縮、分泌、受精など多岐にわたる反応のトリガーとなります 2。
2.3 増幅(Amplification)とリン酸化カスケード
シグナル伝達の真骨頂は「増幅」にあります。たった1分子のリガンド受容体複合体が、数百のGタンパク質を活性化し、それが数千のcAMPを生成し、最終的に数万、数百万の酵素分子を活性化するという指数関数的な増大を引き起こします 7。
この増幅を担う主要な機構がリン酸化カスケードです。プロテインキナーゼ(リン酸化酵素)が次の段のキナーゼをリン酸化して活性化し、それがさらに次を…という連鎖反応です(MAPキナーゼ経路などが代表例)。リン酸化は、タンパク質に負電荷とかさ高い基を付加することでその立体構造を劇的に変化させ、活性のON/OFFを切り替えます 7。
逆に、プロテインホスファターゼ(脱リン酸化酵素)がリン酸基を除去することで、系を初期状態にリセットします。このキナーゼとホスファターゼのバランスこそが、細胞の状態を決定する動的な均衡点となります 9。
3. 研究の歴史:生命の暗号を解読した巨人たち
現在の精緻な理解に至るまでには、20世紀を通じて積み重ねられた数々の発見がありました。それは、「細胞はどのように環境を知るのか?」という問いに対する答えの探求史です。
3.1 黎明期から可逆的リン酸化の発見(1950年代)
19世紀から20世紀初頭にかけて、生理学や薬理学の分野では、細胞が化学物質(ホルモンや薬物)に反応することは知られていましたが、その細胞内部のメカニズムは「ブラックボックス」でした。
1950年代半ば、エドモンド・フィッシャー (Edmond H. Fischer) と エドウィン・クレブス (Edwin G. Krebs) は、ワシントン大学での共同研究において、骨格筋のグリコーゲン分解酵素(グリコーゲンホスホリラーゼ)の活性制御機構を解析していました。彼らは、ATPからのリン酸基転移反応によって酵素が不活性型(b型)から活性型(a型)へと変換されることを発見しました 9。
さらに重要なことに、彼らはこのリン酸化が不可逆な分解ではなく、脱リン酸化酵素によって可逆的に元に戻る「調節スイッチ」であることを突き止めました。この「可逆的タンパク質リン酸化」の概念は、代謝調節のみならず、細胞周期、がん化、神経機能など、あらゆる生命現象の根幹に関わる普遍的な原理であることが後に明らかになり、彼らは1992年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました 12。
3.2 Gタンパク質と「変換器」の概念(1960-70年代)
1960年代後半、マーティン・ロッドベル (Martin Rodbell) は、ホルモンによる細胞応答には3つの異なる機能単位が必要であるという理論モデルを提唱しました 3。
- 識別器 (Discriminator): リガンドを特異的に認識する受容体。
- 変換器 (Transducer): シグナルを膜の反対側へ伝える仲介役。
- 増幅器 (Amplifier): 実際にcAMPなどを産生する酵素(アデニル酸シクラーゼなど)。
ロッドベルは、この「変換器」の機能にGTP(グアノシン三リン酸)が不可欠であることを発見しました。これを受けて、アルフレッド・ギルマン (Alfred G. Gilman) は、遺伝的にcAMP応答を欠損した変異白血病細胞(cyc-変異株)を用いた巧妙な実験を行いました。彼は、正常細胞から抽出した膜タンパク質成分を欠損細胞に加えることで機能を回復(再構成)させることに成功し、ついにその実体であるタンパク質を精製しました 3。GTP結合能を持つことから「Gタンパク質」と名付けられたこの分子の発見により、ロッドベルとギルマンは1994年にノーベル賞を受賞しました。彼らの研究は、細胞膜が単なる障壁ではなく、情報の演算処理装置であることを決定づけました。
3.3 神経系におけるシグナル伝達の統合(2000年代)
シグナル伝達の研究は、脳神経科学の分野でも大きな結実を見ました。2000年のノーベル賞は、アービド・カールソン、ポール・グリーングラス、エリック・カンデルに授与されました 14。
- カールソンはドーパミンが独立した神経伝達物質であることを証明しました。
- グリーングラスは、ドーパミンなどの「遅い」神経伝達が、イオンチャネルの直接開閉ではなく、細胞内のcAMP上昇とそれに続くタンパク質リン酸化(DARPP-32などの基質)を介して行われることを解明しました。
- カンデルは、アメフラシを用いた研究で、このcAMP依存的なリン酸化経路と新たなタンパク質合成が、シナプスの可塑性変化、すなわち「記憶の形成(短期記憶から長期記憶への固定)」の分子的実体であることを示しました 14。
4. 実験手法の進化:破壊的分析からライブイメージング、そしてオミクスへ
シグナル伝達の研究手法は、技術革新とともに解像度と次元を飛躍的に高めてきました。
4.1 古典的生化学から「見える化」へ
初期の研究では、組織や多数の細胞を破砕(lysis)して抽出液を作り、ウェスタンブロット法や酵素活性測定を行うのが主流でした 16。これは特定のタンパク質の存在量や平均的なリン酸化レベルを知るには強力ですが、細胞ごとのばらつき(不均一性)や、生きた細胞内でのダイナミックな時間変化(空間的・時間的情報)は失われていました。
4.2 FRETバイオセンサーとライブセルイメージング
1990年代、下村脩らによるGFP(緑色蛍光タンパク質)の発見と、ロジャー・チェン (Roger Tsien) らによるその改良は、細胞生物学に革命をもたらしました 17。特に、**FRET(蛍光共鳴エネルギー移動)**を利用した遺伝子コード型バイオセンサーの開発は、シグナル伝達の「可視化」を可能にしました。
FRETは、2つの蛍光タンパク質(例えばCFPとYFP)が近接したときにエネルギー移動が起こる物理現象です。チェンらは、キナーゼによってリン酸化されると構造変化を起こし、蛍光色が変化するセンサー(例:PKA活性を測るAKAR、Ca2+を測るCameleonなど)を設計しました 18。これにより、研究者は顕微鏡を通して、「今、細胞の先端部分でPKAが活性化した」といった現象を、生きたままリアルタイムで観察できるようになりました。これはシグナル伝達が場所と時間に依存した(spatiotemporal)現象であることを鮮烈に示しました 20。
4.3 オプトジェネティクス(光遺伝学):因果関係の証明
「観察」から「操作」への転換をもたらしたのがオプトジェネティクスです。2000年代初頭、カール・ダイゼロス、エド・ボイデン、ゲオルク・ナーゲルらは、藻類由来の光感受性イオンチャネル(チャネルロドプシン)を神経細胞に発現させ、光照射によって神経活動をミリ秒単位で制御することに成功しました 21。
さらに、この技術はイオン輸送だけでなく、細胞内シグナルの操作にも応用されています(Opto-SOSやOpto-cAMPなど)。特定のシグナル経路を光で強制的にON/OFFすることで、そのシグナルが特定の細胞応答の「原因」であるかを直接的に証明することが可能になりました 23。
4.4 シングルセル解析とシステム生物学
細胞集団の平均ではなく、個々の細胞の振る舞いを解析する技術も進化しています。scWestern (Single-Cell Western) は、微細加工されたスライド上で数千個の細胞を個別に溶解・電気泳動し、タンパク質発現を解析する技術です 24。また、InTraSeqのような技術は、単一細胞内でRNA発現とタンパク質シグナルを同時に測定することを可能にしました 25。
得られた膨大な多次元データは、数理モデリング(Mathematical Modeling)とシステム生物学の手法で統合されます。ブール論理モデルや微分方程式を用いてシグナルネットワークのトポロジーを記述し、フィードバック制御やクロストーク(経路間の相互干渉)をシミュレーションすることで、複雑系としての細胞の振る舞いを予測する試みが進んでいます 4。
5. 最新の研究動向(2024-2025):相分離と空間オミクスが拓く新地平
2024年から2025年にかけて、細胞内情報伝達の研究は、従来の「鍵と鍵穴(特異的結合)」モデルに加え、「場と空間(相分離・位置情報)」の重要性を組み込んだ新しいパラダイムへと移行しています。
5.1 液-液相分離 (LLPS) によるシグナル制御の再定義
近年、細胞生物学最大のトピックとなっているのが**液-液相分離(Liquid-Liquid Phase Separation: LLPS)**です。これは、タンパク質やRNAが細胞内で液滴(コンデンセート)を形成し、周囲の細胞質から物理的に分離された「膜のないオルガネラ(Membrane-less Organelles: MLOs)」を作る現象です 26。
- 反応の場としての凝縮体: 従来、シグナル伝達は希薄な溶液中での確率的な衝突と考えられていましたが、LLPSにより、酵素と基質が局所的に高濃度に濃縮され、反応速度が爆発的に加速されることが分かってきました 27。
- cGAS-STING経路の発見: DNAセンサーであるcGASは、細胞質内のDNAと結合して相分離し、液滴を形成します。この液滴内部でのみ、cGASは活性化され、セカンドメッセンジャー(cGAMP)を生成します。興味深いことに、この液滴の外殻にはTREX1(DNA分解酵素)が排除されており、シグナル伝達のための安全地帯が形成されています 27。
- 疾患との関連: がんや神経変性疾患では、このLLPSの制御不全(液滴が固化してアミロイド化するなど)が病態に関与していることが明らかになりつつあり、2025年の創薬研究の最前線となっています 28。
5.2 空間的トランスクリプトミクスと細胞間ニッチ解析
シングルセル解析に「位置情報」を付加した**空間的トランスクリプトミクス(Spatial Transcriptomics)**が爆発的に普及しています。組織切片上の位置情報を保ったまま全遺伝子の発現を解析することで、隣り合う細胞同士がどのようなシグナル(リガンドと受容体のペア)をやり取りしているかを推定できるようになりました 30。
- NICHESとTG-ME: 2024-2025年にかけて、NICHESのような解析ツールが登場し、細胞単体ではなく、細胞間の相互作用ユニット(ニッチ)を可視化することが可能になりました 31。また、AI(トランスフォーマーとグラフ変分オートエンコーダ)を活用したTG-MEというフレームワークは、がん組織内の微小環境(TME)における免疫細胞とがん細胞の複雑なクロストークを高精度にクラスタリングし、予後予測に応用されています 32。
- 多臓器・発生への応用: この技術は、肝がんの微小環境解析や、初期卵形成過程における細胞間シグナルの解明など、発生生物学から病理学まで幅広く応用されています 34。
5.3 AlphaFold 3 による構造予測の到達点
Google DeepMindとIsomorphic Labsが2024年に発表したAlphaFold 3は、タンパク質単体だけでなく、タンパク質-タンパク質相互作用(PPI)、タンパク質とDNA/RNA、さらには低分子リガンドとの複合体構造までも、かつてない精度で予測することを可能にしました 35。
特にシグナル伝達においては、一過性の弱い相互作用や、天然変性領域(IDR)を介した結合が重要ですが、AlphaFold 3はこれらの相互作用における変異の影響(結合自由エネルギー変化)の予測においても実験値に近い精度を達成しつつあります 36。これにより、実験が困難なシグナル伝達複合体の動的構造モデリングや、それを標的としたドラッグデザインが加速しています 38。
6. 結論:複雑系としての生命と情報ネットワーク
本レポートでは、細胞内情報伝達系の精緻なメカニズムとその研究の歴史、そして最新の空間オミクスや構造生物学によるブレイクスルーを詳述しました。Gタンパク質という分子スイッチから、液-液相分離による反応場の形成に至るまで、細胞は物理化学的な法則を巧みに利用して、ノイズの中から意味のある情報を抽出し、生存という目的のために統合しています。
研究において重要なのは**「シグナルの質(Specificity & Quality)」と「伝達経路の最適化(Connectivity)」**です。細胞生物学の知見は、単なる医学・薬学の基礎であるだけでなく、複雑な情報ネットワークを理解し、最適化するための深遠な示唆を与えてくれます。2025年以降、AIとバイオロジーの融合(AlphaFoldや空間解析)が生命の謎をさらに解き明かす鍵となるでしょう。
引用文献
- 28.1: General Features of Signal Transduction – Biology LibreTexts, 11月 19, 2025にアクセス、 https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Fundamentals_of_Biochemistry_(Jakubowski_and_Flatt)/Unit_IV_-_Special_Topics/28%3A_Biosignaling_-_Capstone_Volume_I/28.01%3A_General_Features_of_Signal_Transduction
- 4. Intracellular Signalling – Communication Systems in the Animal Body – Saskoer, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.saskoer.ca/communicationsystems/chapter/chapter-4-intracellular-signalling/
- The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1994 – Press release …, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1994/press-release/
- Conceptual Evolution of Cell Signaling – MDPI, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/1422-0067/20/13/3292
- Pathways of Intracellular Signal Transduction – The Cell – NCBI Bookshelf – NIH, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9870/
- Signal Transduction and the Discovery of G-Proteins, 1969-1980 | Martin Rodbell, 11月 19, 2025にアクセス、 https://profiles.nlm.nih.gov/spotlight/gg/feature/discovery
- Introduction to Signal Transduction – AP Bio Study Guide – Fiveable, 11月 19, 2025にアクセス、 https://fiveable.me/ap-bio/unit-4/intro-signal-transduction/study-guide/VAotQCiNsYQzCcmUBt3D
- Cell Signaling and Signal Transduction: Communication Between Cells, 11月 19, 2025にアクセス、 https://dosequis.colorado.edu/Courses/MCDB3145/Docs/Karp-617-660.pdf
- The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1992 – Illustrated information – NobelPrize.org, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1992/illustrated-information/
- 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1992/press-release/#:~:text=The%20discoveries%20of%20Fischer%20and,of%20a%20special%20muscle%20system.
- The Process of Reversible Phosphorylation: the Work of Edmond H. Fischer – PMC – NIH, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3023531/
- The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1992 – Press release – NobelPrize.org, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1992/press-release/
- Edmond H. Fischer – National Academy of Sciences, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.nasonline.org/wp-content/uploads/2024/06/fischer-edmond.pdf
- The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2000 – NobelPrize.org, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2000/7621-the-nobel-prize-in-physiology-or-medicine-2000/
- Nobel prize winners Arvid Carlsson, Paul Greengard and Eric Kandel: the research of signal transduction in the nervous system | The Ukrainian Biochemical Journal, 11月 19, 2025にアクセス、 http://ukrbiochemjournal.org/2023/06/nobel-prize-winners-arvid-carlsson-paul-greengard-and-eric-kandel-the-research-of-signal-transduction-in-the-nervous-system.html
- Western Blotting Protocol – Cell Signaling Technology, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.cellsignal.com/learn-and-support/protocols/protocol-western
- MILESTONES IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF FRET-BASED SENSORS OF INTRACELLULAR SIGNALS: A BIOLOGICAL PERSPECTIVE OF THE HISTORY OF FRET – NIH, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7679057/
- Two Decades of Genetically Encoded Biosensors Based on Förster Resonance Energy Transfer – J-Stage, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.jstage.jst.go.jp/article/csf/44/2/44_18035/_html/-char/ja
- Visualizing Dynamic Activities of Signaling Enzymes Using Genetically Encodable FRET-Based Biosensors: From Designs to Applications – NIH, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4384881/
- Nobel Lecture by Roger Y. Tsien, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/tsien_lecture.pdf
- Optogenetics – Wikipedia, 11月 19, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Optogenetics
- Optogenetics: 10 years after ChR2 in neurons – Views from the community – ResearchGate, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/281343026_Optogenetics_10_years_after_ChR2_in_neurons_-_Views_from_the_community
- Two Decades of Optogenetic Tools: A Retrospective and a Look Ahead – PMC, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12482941/
- Single-cell western blotting – PMC – NIH, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4077215/
- InTraSeq™ Single Cell Analysis: A Multimodal Single-Cell Method for Simultaneous Measurement of RNA and Proteins to Uncover New Single-Cell Biology | Cell Signaling Technology, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.cellsignal.com/learn-and-support/videos-and-webinars/intraseq-technology-poster
- Liquid-liquid phase separation of membrane-less condensates: from biogenesis to function – Frontiers, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/cell-and-developmental-biology/articles/10.3389/fcell.2025.1600430/full
- Liquid-liquid phase separation: Orchestrating cell signaling through …, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8541918/
- Liquid-liquid phase separation in cell physiology and cancer biology: recent advances and therapeutic implications – Frontiers, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2025.1540427/full
- Investigating Liquid–Liquid Phase Separation in Lung Adenocarcinoma to Improve Prognostic Accuracy and Treatment Efficacy – PubMed Central, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12372984/
- Mapping cellular interactions from spatially resolved transcriptomics data – PubMed – NIH, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39227721/
- Comprehensive visualization of cell–cell interactions in single-cell …, 11月 19, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/bioinformatics/article/39/1/btac775/6865029
- Dissection of tumoral niches using spatial transcriptomics and deep learning – PMC – NIH, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11994907/
- stClinic dissects clinically relevant niches by integrating spatial multi-slice multi-omics data in dynamic graphs – PMC – PubMed Central, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12170857/
- Mapping cellular interactions from spatially resolved transcriptomics data | Springer Nature Experiments, 11月 19, 2025にアクセス、 https://experiments.springernature.com/articles/10.1038/s41592-024-02408-1
- Google DeepMind and Isomorphic Labs introduce AlphaFold 3 AI …, 11月 19, 2025にアクセス、 https://blog.google/technology/ai/google-deepmind-isomorphic-alphafold-3-ai-model/
- AlphaFold3, a secret sauce for predicting mutational effects on protein-protein interactions, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.05.25.595871v1
- AlphaFold-Multimer accurately captures interactions and dynamics of intrinsically disordered protein regions | PNAS, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2406407121
- AlphaFold3: An Overview of Applications and Performance Insights – PMC – PubMed Central, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12027460/