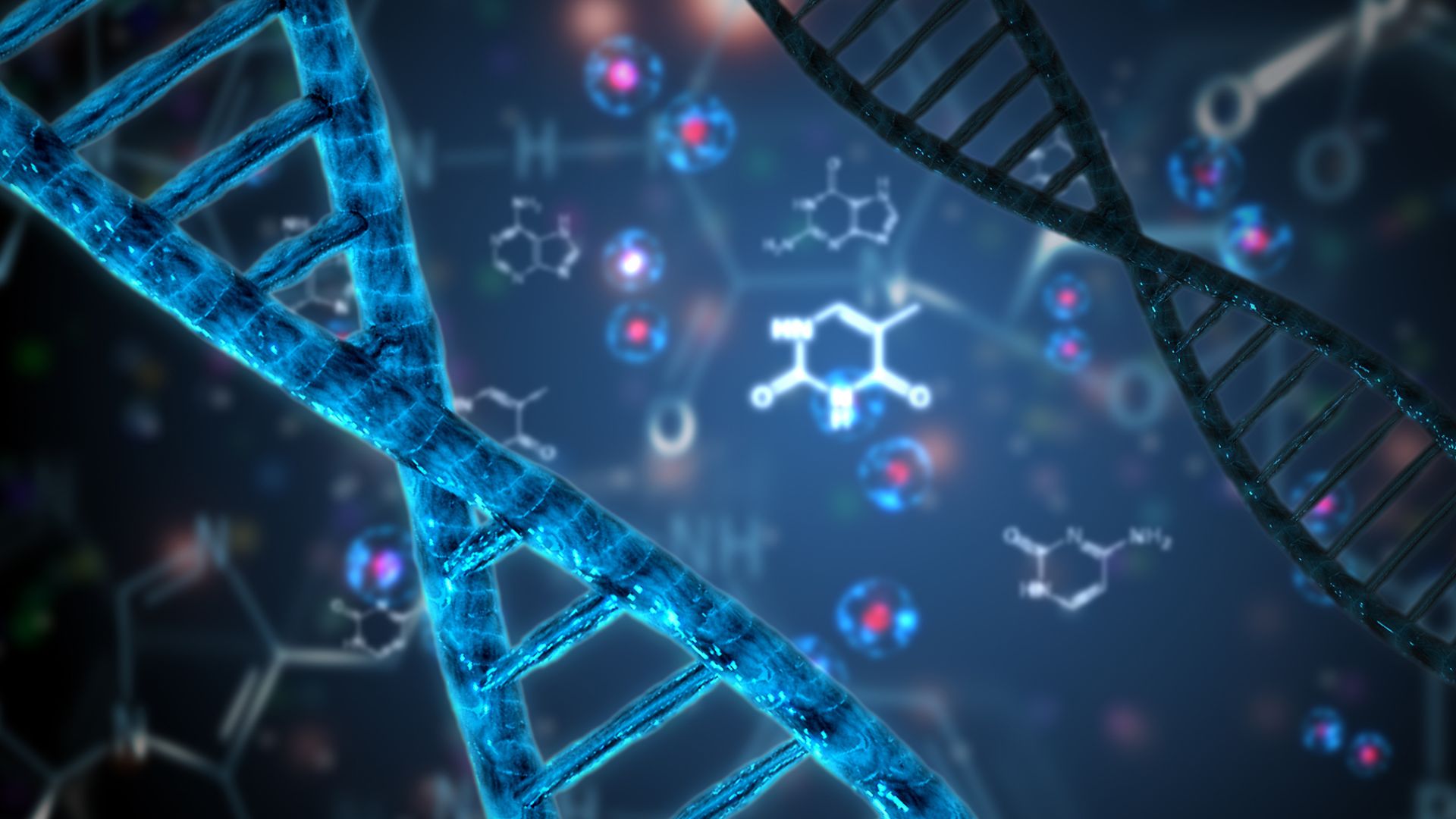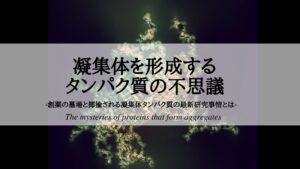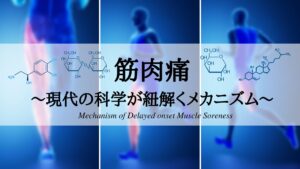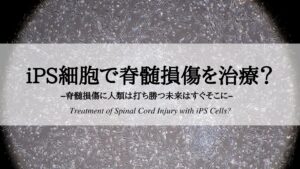1. 序論
核酸(Nucleic Acid)は、地球上の既知の全生命体において、遺伝情報の保存、伝達、および発現を司る最も根源的な生体高分子である。1869年にフリードリッヒ・ミーシャーによって細胞核内から初めて単離されたこの物質は、当初その機能が謎に包まれていたが、20世紀を通じて分子生物学の中心概念(セントラルドグマ)としての地位を確立した。そして21世紀、特に2024年から2025年にかけての技術革新により、核酸は単なる「生命の設計図」という受動的な役割を超え、難治性疾患を治療するモダリティ、あるいはデジタルデータを数千年にわたって保存可能な次世代ストレージ媒体として、産業構造を変革しつつある1。
本報告書は、分子生物学の専門的知見に基づき、核酸の基礎構造と生体内生成プロセス(De novo合成およびサルベージ経路)の詳細なメカニズムを解き明かすことから始まる。続いて、科学史上の重要なマイルストーンを俯瞰し、CRISPR技術の進化形であるエピジェネティック編集やRNA編集といった2025年時点での最新の研究動向と臨床試験結果を網羅的に分析する。本報告書は、生命科学の基礎から産業応用に至るまで、その全容を解き明かす包括的なレビューである。


2. 核酸の生化学的構造と機能特性
核酸は、ヌクレオチドと呼ばれる構成単位がリン酸ジエステル結合によって重合したポリヌクレオチド鎖である。その構造的特性は、生命情報の長期保存と、必要に応じた情報の読み出し・実行という相反する要求を同時に満たすために極めて精巧に設計されている。
2.1 構成要素と化学的性質
ヌクレオチドは、五炭糖(ペントース)、リン酸基、および窒素含有塩基の3つの部分から構成される。この基本構造の違いにより、核酸はデオキシリボ核酸(DNA)とリボ核酸(RNA)の2種類に大別される3。
2.1.1 デオキシリボ核酸(DNA)
DNAの糖部分は2′-デオキシリボースであり、リボースの2’位のヒドロキシ基(-OH)が水素原子(-H)に置換されている。この化学的修飾により、DNAは加水分解に対する耐性が高く、アルカリ性条件下でも極めて安定である。これは、遺伝情報を生涯、あるいは世代を超えて保存するために不可欠な特性である4。DNAの塩基はアデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)の4種で構成され、アデニンはチミンと、グアニンはシトシンと特異的な水素結合を形成する(シャルガフの法則)。ワトソンとクリックによって提唱された二重らせん構造は、疎水性の塩基対を内側に、親水性の糖リン酸骨格を外側に配置することで、水溶液中での安定性を最大化している5。
2.1.2 リボ核酸(RNA)
RNAは糖部分としてリボースを持ち、2’位に反応性の高いヒドロキシ基を有する。この構造的特徴により、RNAはDNAよりも化学的に不安定であり、一時的な情報の伝達体としての役割に適している。また、塩基としてチミンの代わりにウラシル(U)を使用する4。RNAは通常一本鎖として存在するが、分子内で塩基対を形成することで、ヘアピンループやバルジなどの複雑な三次構造をとることが可能である。この構造的多様性が、mRNA(情報の伝達)、tRNA(アミノ酸の運搬)、rRNA(リボソームの構成)、さらにはリボザイム(酵素活性)といった多岐にわたる機能を可能にしている7。
| 特性 | DNA (デオキシリボ核酸) | RNA (リボ核酸) |
| 糖骨格 | 2′-デオキシリボース | リボース (2′-OH基あり) |
| 塩基構成 | アデニン(A), グアニン(G), シトシン(C), チミン(T) | アデニン(A), グアニン(G), シトシン(C), ウラシル(U) |
| 分子構造 | 右巻き二重らせん (B型が一般的) | 通常一本鎖 (A型らせんに似た局所構造) |
| 化学的安定性 | 高い (長期保存に適する) | 低い (一時的な利用に適する) |
| 主な機能 | 遺伝情報の保存、複製 | タンパク質合成の媒介、遺伝子発現制御、触媒作用 |
3. 生体内における核酸生成の代謝経路
細胞が増殖し、その機能を維持するためには、DNA複製やRNA転写に必要なヌクレオチド(dNTPsおよびNTPs)が常に供給されなければならない。生体は、この需要を満たすために「De novo合成経路」と「サルベージ(再利用)経路」という二つの洗練された代謝経路を進化させてきた3。
3.1 De novo合成経路:基礎からの構築
De novo(新規)合成経路は、アミノ酸、リボース-5-リン酸、二酸化炭素、アンモニアなどの単純な前駆体分子から、多段階の酵素反応を経てヌクレオチドを一から構築するプロセスである。この経路はほぼすべての生物で高度に保存されているが、エネルギーコストが極めて高いという特徴を持つ3。
3.1.1 プリンヌクレオチドの生合成
プリン環(アデニン、グアニン)の合成は、リボース-5-リン酸から生成されるホスホリボシルピロリン酸(PRPP)を土台として行われる。この過程には、グルタミン、グリシン、アスパラギン酸、および葉酸誘導体(N10-ホルミルテトラヒドロ葉酸)が炭素および窒素の供与体として関与する3。
プリン環の構築には少なくとも6分子のATPが必要とされ、エネルギー的に非常に高価なプロセスである。生成されたイノシン一リン酸(IMP)は、さらにアデニル酸(AMP)とグアニル酸(GMP)へと変換される。この分岐点における調節機構は、細胞内のATPとGTPのバランスを保つために厳密に制御されている8。
3.1.2 ピリミジンヌクレオチドの生合成とチミンの生成
ピリミジン環(シトシン、ウラシル、チミン)の合成では、まず細胞質で遊離のピリミジン環が形成され、その後にPRPPと結合してヌクレオチドとなる。ここで特筆すべきは、DNA特有の塩基であるチミン(dTMP)の生成過程である。
チミジンヌクレオチドはDNAにのみ存在するため、その前駆体はウリジンヌクレオチドである。まず、リボヌクレオチド還元酵素(Ribonucleotide Reductase: RR)がUDPの2’位のヒドロキシ基を除去し、dUDP(デオキシウリジン二リン酸)を生成する。その後、dUDPはdUMPに変換され、チミジル酸合成酵素によってメチル化されることでdTMPとなる5。この経路の律速段階であるリボヌクレオチド還元酵素の活性は、細胞周期と連動して厳密に制御されており、抗がん剤の標的としても重要である。
3.2 サルベージ経路:効率的なリサイクル
サルベージ経路は、細胞内で核酸(RNAやDNA)が分解されて生じた遊離塩基(アデニン、グアニン、ヒポキサンチンなど)やヌクレオシドを回収し、再びヌクレオチドとして再利用する経路である。
- 酵素反応のメカニズム: この経路の中心となるのは、ホスホリボシルトランスフェラーゼ(PRT)ファミリーである。具体的には、ヒポキサンチン-グアニン ホスホリボシルトランスフェラーゼ(HGPRT)やアデニン ホスホリボシルトランスフェラーゼ(APRT)が、PRPPをリボース供与体として使用し、遊離塩基に直接リボース-5-リン酸基を付加してヌクレオチド(IMP, GMP, AMP)を再合成する8。
- エネルギー効率: De novo合成が環構造を一から構築するために大量のATPを消費するのに対し、サルベージ経路は既存の環構造を利用するため、ATP消費量を劇的に削減できる。したがって、エネルギー効率の観点から、多くの組織にとって経済的な経路である8。
3.3 がん代謝におけるパラダイムシフト
長年の定説では、「増殖の活発な細胞(がん細胞など)はDe novo合成に依存し、分化した組織はサルベージ経路に依存する」と考えられてきた10。しかし、近年の同位体トレーサーを用いた定量的代謝解析はこの見解を覆しつつある。
最新の研究によれば、腫瘍組織においてもサルベージ経路がプリンヌクレオチドプールの維持に極めて重要な役割を果たしていることが判明した。特に、血中のアデニンやイノシンといった前駆体が腫瘍に取り込まれ、効率的に利用されている。マウスモデルを用いた実験では、ヌクレオチドを外部から投与すると腫瘍増殖が加速し、逆にサルベージ経路を阻害すると腫瘍の進行が抑制されることが示された11。この発見は、従来のDe novo経路阻害剤(メトトレキサートなど)に加え、サルベージ経路を標的とした新規抗がん戦略の可能性を示唆している。
4. 核酸研究の歴史的変遷:発見から操作へ
核酸科学の歴史は、生命の神秘を物質レベルで解明しようとした人類の知的探究の軌跡である。19世紀の発見から21世紀のゲノム編集に至るまで、その進展は加速し続けている。
4.1 黎明期:ヌクレインの発見と遺伝物質の特定(1860年代〜1940年代)
- 1863年: グレゴール・メンデルがエンドウ豆を用いた実験から遺伝の法則を発見し、遺伝要素の存在を示唆した1。
- 1869年: スイスの生化学者フリードリッヒ・ミーシャーが、膿(白血球)の核からリンを豊富に含む酸性物質を単離し、「ヌクレイン(nuclein)」と命名した6。これがDNA発見の瞬間であったが、当時その重要性は認識されなかった。
- 1889年: リヒャルト・アルトマンがヌクレインの性質を詳しく調べ、「核酸(nucleic acid)」という用語を初めて使用した7。
- 1909年: フィーバス・レヴィーンが、RNAがリボース、リン酸、窒素塩基から構成されていることを加水分解実験によって決定した7。
- 1944年: オズワルド・アベリーらの研究チームが、肺炎双球菌の形質転換を引き起こす物質(形質転換原理)がタンパク質ではなくDNAであることを証明し、遺伝情報の本体がDNAであることを決定づけた6。
4.2 構造生物学の黄金期とセントラルドグマ(1950年代〜1970年代)
- 1953年: ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックが、ロザリンド・フランクリンとモーリス・ウィルキンスによるX線回折画像(フォト51)のデータに基づき、DNAの二重らせん構造モデルを『Nature』誌に発表した1。この発見は、遺伝情報がどのようにコピーされ、次世代に受け継がれるかの物理的メカニズムを明示した点で生物学史上最大のマイルストーンとされる。1962年、彼ら(フランクリンを除く)はこの功績によりノーベル生理学・医学賞を受賞した5。
- 1958年: メセルソンとスタールが、DNAの複製が「半保存的」に行われることを実験的に証明した12。
- 1967年: ハワード・テミンとデビッド・ボルティモアが、RNAからDNAを合成する酵素「逆転写酵素」を発見し、セントラルドグマ(DNA→RNA→タンパク質)の一方向性に例外があることを示した7。
4.3 ゲノム工学と解析技術の革新(1980年代〜現在)
- 1977年: フレデリック・サンガーがDNAの塩基配列決定法(サンガー法)を開発し、遺伝情報の「解読」を可能にした1。
- 1983年: キャリー・マリスがポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を発明。微量のDNAを短時間で数百万倍に増幅可能となり、診断や法医学に革命をもたらした1。
- 2012年: ジェニファー・ダウドナとエマニュエル・シャルパンティエらが、細菌の免疫システム「CRISPR-Cas9」を利用したゲノム編集技術を発表14。これにより、DNAを「読む」時代から「書き換える」時代へと突入した。
5. 実験手法とテクノロジーの進化
核酸を解析・操作するための技術は、基礎研究のみならず、医療、農業、データストレージなど多岐にわたる分野で不可欠なツールとなっている。
5.1 増幅と検出:PCRとその応用
PCR法は、特定のDNA領域を挟むプライマーと耐熱性DNAポリメラーゼを用い、熱変性、アニーリング、伸長のサイクルを繰り返すことで標的配列を指数関数的に増幅する12。
- RFLP (制限酵素断片長多型): 1980年に開発され、DNA配列の違いを制限酵素による切断パターンの違いとして検出する方法。遺伝病の診断や親子鑑定の初期に用いられた1。
- STR (ショートタンデムリピート) 解析: 1991年頃から利用され、現在もDNA鑑定の主流である。マイクロサテライト領域の繰り返し回数の違いを利用する1。
5.2 シーケンシング技術の変遷
- サンガー法(第一世代): クローン化されたDNA集団を電気泳動で分離して解読する。精度は高いがスループットに限界があった13。
- 次世代シーケンシング(NGS): 数百万から数十億のDNA断片を並列に解読する技術。Illumina社のプラットフォームなどが主流であり、全ゲノム解析のコストを数億円から数万円単位にまで低下させた。CRISPRによる編集結果の検証(オンターゲットおよびオフターゲット変異の解析)においても、NGSによる定量的評価が標準となっている15。
5.3 ゲノム編集技術:CRISPR-Cas9のメカニズム
CRISPR-Cas9システムは、二つの主要コンポーネントから成る。
- ガイドRNA (gRNA): 標的とするDNA配列(約20塩基)に相補的なスペーサー配列と、Cas9酵素と結合するためのスキャフォールド配列を持つRNA14。
- Cas9ヌクレアーゼ: DNAを切断する酵素。
Cas9はgRNAに誘導されて標的DNAに結合し、標的配列の直後にあるPAM(Protospacer Adjacent Motif)配列(通常NGG)を認識してDNAの二本鎖を切断する。この切断部位が細胞の修復機構によって修復される際に、遺伝子のノックアウト(破壊)や、新たな配列のノックイン(挿入)が行われる17。
6. 2024-2025年の研究動向と臨床応用の最前線
2025年現在、核酸科学は単なるゲノム編集を超え、RNA編集やエピジェネティック制御といった、より精緻で安全性の高いモダリティへと進化している。以下に、最新の海外文献および臨床試験データを基にした主要なトレンドを詳述する。
6.1 RNA編集療法(RNA Editing):DNAを傷つけない治療
従来の遺伝子治療がDNAを恒久的に書き換えるのに対し、RNA編集は一時的な転写産物(mRNA)を修飾する。これにより、永続的なオフターゲット変異のリスクを回避できる。
- Wave Life SciencesとWVE-006の躍進:
2025年9月、Wave Life Sciences社は、α1-アンチトリプシン欠損症(AATD)に対するRNA編集治療薬「WVE-006」の第1b/2a相臨床試験(RestorAATion-2 study)において、画期的な成果を発表した18。
- 技術的特徴: WVE-006は、GalNAc(N-アセチルガラクトサミン)を結合させたオリゴヌクレオチド(AIMer)であり、肝細胞内のmRNA上の特定のアデノシンをイノシンに変換(A-to-I編集)することで変異を修正する。
- 臨床データ: 200mgの反復投与を受けたコホートにおいて、血中の正常型タンパク質(M-AAT)レベルは平均7.2 µMに達し、これは総AATの約60%以上を占めた。また、疾患原因となる変異型タンパク質(Z-AAT)はベースラインから60.3%減少した。このデータは、ヒトにおいて治療的に意味のあるレベルでRNA編集が成功したことを示す世界初の実証例である18。
6.2 エピジェネティック編集:遺伝子発現のスイッチ操作
DNA配列を変えずに、遺伝子の発現のみを制御する技術も2025年に大きな進展を見せた。
- CRISPRoffによる永続的サイレンシング:
2025年10月、『Nature Biotechnology』誌に掲載された研究において、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)のチームは「CRISPRoff」と呼ばれる技術の詳細を発表した20。
- メカニズム: 切断能力を持たないdCas9に、DNAメチル化酵素(DNMT3A)や転写抑制ドメイン(KRAB)を融合させた複合体を用いる。これを全RNAデリバリーシステム(mRNAベース)で細胞に導入する。
- 成果: ヒトT細胞において、FAS、PTPN2、TIGIT、Zetaなどの遺伝子を標的とした際、細胞毒性を伴わずに最大99%のサイレンシング効率を達成した。特筆すべきは、この抑制効果が細胞分裂を経ても長期間(in vitroで30〜80回の細胞分裂、in vivoで14日間以上)維持された点である。これにより、DNA切断を伴わずにCAR-T細胞の機能を強化することが可能となった20。
6.3 環状RNA(Circular RNA)と次世代ワクチン
直鎖状のmRNAワクチンは分解されやすいという課題があったが、末端を持たない環状RNA(circRNA)はエキソヌクレアーゼによる分解に耐性があり、安定性が極めて高い22。
- Orna Therapeuticsの展開: 同社は合成環状RNA(oRNA)を脂質ナノ粒子(LNP)に封入した治療薬を開発中である。2025年12月の米国血液学会(ASH)において、oRNAを用いたIn vivo CAR療法が、非ヒト霊長類を用いた実験でB細胞性自己免疫疾患に対して強力かつ持続的な効果を示したことを発表予定である24。また、2025年には放射線誘発性口腔乾燥症などを対象とした複数の臨床試験(NCT06714253等)が進行中または募集開始されている25。
7. 生物学の枠を超えて:DNAデータストレージの商用化
核酸のもう一つの革命的応用は、デジタル情報の保存媒体としての利用である。DNAは既存のハードディスクやテープと比較して、圧倒的な記録密度と耐久性を持つ。理論上、1グラムのDNAには約455エクサバイト(4.55億テラバイト)のデータを保存可能である26。
- 技術的進歩と市場動向:
2025年、Twist Bioscience社はDNAデータストレージ部門を独立させ、「Atlas Data Storage」を設立した。この新会社はマイクロソフトなどから1億5500万ドルのシード資金を調達している27。酵素を用いたDNA合成技術の改良により、書き込みコストと速度の課題が急速に解決されつつあり、DNAストレージ市場は2025年の1億5000万ドル規模から、2034年には440億ドル規模へと、年平均成長率(CAGR)88%で爆発的に拡大すると予測されている28。
マイクロソフトとワシントン大学の共同研究では、DNAプールから目的のファイル(画像など)を類似性検索で直接抽出する技術も開発されており、ランダムアクセス性の問題も克服されつつある29。
8. エピジェネティクスと老化逆転(リジュビネーション)
2025年の研究は、老化の本質に迫る新たな知見をもたらした。
カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)の研究チームは、遺伝子変異とエピジェネティックな老化時計(Epigenetic Clock)の間に未解明のリンクがあることを発見した。これまで「老化は変異の蓄積によるもの(変異説)」と「エピジェネティックな変化によるもの(プログラム説)」が対立していたが、変異がエピジェネティックな変化を引き起こす根本原因である可能性が示唆された30。
また、山中因子(OSK)などを用いた部分的リプログラミングにより、細胞の年齢を若返らせる研究も進んでおり、2025年にはサルを用いた実験での視力回復や組織再生の報告が続いている31。これは、核酸のエピジェネティックな状態を操作することで、生物学的年齢を「逆転」させる未来を示唆している。
9. 核酸の栄養学的側面:食事とサプリメントの科学
一般消費者の関心が高い「核酸を含む食品」やサプリメントの効果についても、科学的エビデンスに基づいて解説する。
- 消化と吸収: 食品(肉、魚、豆類、キノコなど)に含まれる核酸は、胃酸や膵臓のヌクレアーゼによってヌクレオチドやヌクレオシド、さらには遊離塩基へと分解されて吸収される33。そのままの形で遺伝子が取り込まれるわけではない。
- 健康効果の可能性: 健常な成人であれば、体内のDe novo合成によって十分な核酸が供給されるため、通常は外部からの摂取は必須ではない34。しかし、急激な成長期、怪我や手術からの回復期、あるいは免疫系へのストレスがかかった状態など、代謝要求が増大する局面では、食事由来のヌクレオチド(サルベージ経路の基質)が有益に働くことが示唆されている。研究では、ヌクレオチドの補給が腸管絨毛の高さや粘膜タンパク質の増加を促進し、免疫機能や消化管の回復を助ける効果が報告されている35。
- 注意点: 核酸(特にプリン体)の過剰摂取は、代謝産物である尿酸の蓄積を招き、痛風のリスクを高める可能性があるため、摂取量には注意が必要である。
10. 結論
核酸(DNAおよびRNA)は、19世紀後半の「ヌクレイン」の発見以来、生命科学の中心課題であり続けてきた。その理解は、静的な「遺伝情報の保管庫」から、細胞機能を動的に制御する「実行部隊」へと深まり、現在ではCRISPR技術やRNA編集、環状RNAといった革新的な技術によって、人類が自らの設計図を修復・改良するためのツールとなっている。
特に2025年の進展は目覚ましく、Wave Life SciencesによるRNA編集の実証や、CRISPRoffによるエピジェネティックな制御の成功は、従来の遺伝子治療が抱えていた永続的な変異リスクという課題を克服しつつあることを示している。同時に、DNAデータストレージの実用化に向けた動きは、核酸が生物学の枠を超え、デジタル社会のインフラストラクチャとなる未来を予見させる。
本報告書で示した詳細なメカニズムや最新の臨床データ、そして産業界の動向は、核酸がもはや教科書の中だけの存在ではなく、我々の生活と健康を根本から変えうる「生きた技術」であることを証明している。
引用文献
- Timeline: History of DNA | National Institute of Justice, 11月 19, 2025にアクセス、 https://nij.ojp.gov/media/image/49031
- Emerging Approaches to DNA Data Storage: Challenges and Prospects – PMC, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9706676/
- De novo nucleotide biosynthetic pathway and cancer – PMC – NIH, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10404870/
- DNAとRNAの違い | 遺伝子検査(解析)ならジーンクエスト, 11月 19, 2025にアクセス、 https://genequest.jp/glossary/dna_rna
- Nucleotide Metabolism – PMC – NIH, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8247561/
- The History of DNA Timeline, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.dna-worldwide.com/resource/160/history-dna-timeline
- The evolution of knowledge about RNA: from its discovery to the present day – Oligofastx, 11月 19, 2025にアクセス、 https://oligofastx.com/the-evolution-of-knowledge-about-rna-from-its-discovery-to-the-present-day/
- Nucleotide metabolism and salvage pathways | Biological Chemistry I Class Notes, 11月 19, 2025にアクセス、 https://fiveable.me/biological-chemistry-i/unit-11/nucleotide-metabolism-salvage-pathways/study-guide/uHJ9gaOCnE4XW9js
- 22.4: Biosynthesis and Degradation of Nucleotides – Biology LibreTexts, 11月 19, 2025にアクセス、 https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Fundamentals_of_Biochemistry_(Jakubowski_and_Flatt)/02%3A_Unit_II-_Bioenergetics_and_Metabolism/22%3A_Biosynthesis_of_Amino_Acids_Nucleotides_and_Related_Molecules/22.04%3A_Biosynthesis_and_Degradation_of_Nucleotides
- De novo and salvage purine synthesis pathways across tissues and tumors – PubMed – NIH, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38823389/
- De novo and Salvage Purine Synthesis Pathways Across Tissues and Tumors – PMC, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11246224/
- Genetic Timeline – Genome.gov, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.genome.gov/Pages/Education/GeneticTimeline.pdf
- The sequence of sequencers: The history of sequencing DNA – PMC – NIH, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4727787/
- What is CRISPR: Your Ultimate Guide | Synthego, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.synthego.com/learn/crispr/
- CRISPR Genome Editing & NGS | Off-target analysis and knockout confirmation – Illumina, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.illumina.com/techniques/popular-applications/genome-editing.html
- Technologies and Computational Analysis Strategies for CRISPR Applications – PMC – NIH, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7497852/
- CRISPR Guide – Addgene, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.addgene.org/guides/crispr/
- Wave Life Sciences Announces Positive Update from Ongoing …, 11月 19, 2025にアクセス、 https://ir.wavelifesciences.com/news-releases/news-release-details/wave-life-sciences-announces-positive-update-ongoing
- Wave RNA editing restores enzyme in genetic condition but underwhelms investors – Fierce Biotech, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.fiercebiotech.com/biotech/wave-rna-editing-restores-enzyme-alpha-1antitrypsin-deficiency-trial-investors-unimpressed
- News: CRISPR Epigenetic Editing Delivers Durable Multiplexed …, 11月 19, 2025にアクセス、 https://crisprmedicinenews.com/news/crispr-epigenetic-editing-delivers-durable-multiplexed-gene-silencing-in-t-cells/
- CRISPR epigenome editor offers potential gene therapies – ASBMB, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.asbmb.org/asbmb-today/science/042525/crispr-epigenome-editor-treat-neuro-disorders
- Current Progress and Future Perspectives of RNA-Based Cancer Vaccines: A 2025 Update, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12153701/
- CircRNA therapeutics: The next leap after mRNA – Abcam, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.abcam.com/en-us/stories/articles/circrna-therapeutics-the-next-leap-after-mrna
- Orna Therapeutics – Ahead of the Curve, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.ornatx.com/
- Harnessing the Loop: The Perspective of Circular RNA in Modern Therapeutics – PMC, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12389747/
- DNA data storage could arrive within 3–5 years – Future Timeline, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.futuretimeline.net/blog/2025/09/30-dna-data-storage-future-timeline.htm
- Twist Bioscience Spins Out DNA Data Storage as Independent Company, 11月 19, 2025にアクセス、 https://investors.twistbioscience.com/news-releases/news-release-details/twist-bioscience-spins-out-dna-data-storage-independent-company/
- DNA Data Storage Market Size, Share and Trends 2025 to 2034 – Precedence Research, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.precedenceresearch.com/dna-data-storage-market
- Is DNA the future of computer storage? – HSBC Private Bank, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.privatebanking.hsbc.com/individual-investors/frontiers-series/is-dna-the-future-of-computer-storage/
- Breakthrough study links genetic mutations to epigenetic changes in aging, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.news-medical.net/news/20250121/Breakthrough-study-links-genetic-mutations-to-epigenetic-changes-in-aging.aspx
- Age Reversal Technology: Top 5 Breakthroughs – Generation Lab, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.generationlab.com/blog/age-reversal-technology
- Anti-Aging Breakthrough? Harvard’s David Sinclair Predicts Age-Reversing Pill by 2035, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.nad.com/news/anti-aging-breakthrough-dr-david-sinclair-predicts-age-reversing-pill-by-2035
- Compounds from Nucleic Acids in Food Show Anticancer Effects, 11月 19, 2025にアクセス、 https://crohnscolitisprofessional.org/news/compounds-from-nucleic-acids-in-food-show-anticancer-effects/2468053/
- 7 Healthy Foods That Are High in Nucleic Acid, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.healthline.com/nutrition/nucleic-acid-foods
- All About Nucleic Acid Foods and Functions – Everyday Health, 11月 19, 2025にアクセス、 https://www.everydayhealth.com/food-ingredients/foods-high-in-nucleic-acid/
- Nucleotide supplementation: a randomised double-blind placebo controlled trial of IntestAidIB in people with Irritable Bowel Syndrome [ISRCTN67764449] – PubMed Central, 11月 19, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1513247/