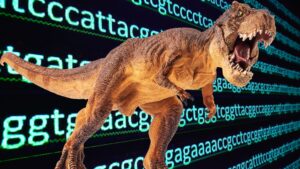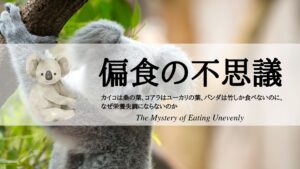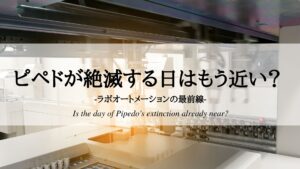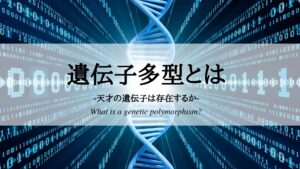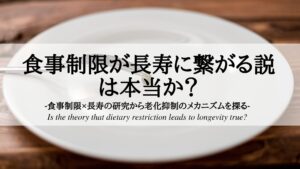I. はじめに:2型糖尿病治療への新たな光とベータトロフィンの衝撃的デビュー
2型糖尿病は、インスリン抵抗性(インスリンの効きが悪くなる状態)と膵臓のβ細胞機能の低下を特徴とし、世界中で患者数が増加し続けている深刻な健康問題です 1。現在の治療法は、血糖値を管理し合併症の進行を遅らせることが主眼であり、失われたβ細胞の量や機能を回復させる根本的な治療法は確立されていません。そのため、糖尿病研究の世界では、インスリンを産生するβ細胞を補充、あるいは再生させる治療法の開発が長年にわたり切望されてきました 2。
このような背景の中、数年前に「ベータトロフィン (betatrophin)」という分子が医学界に彗星のごとく登場し、2型糖尿病治療に革命をもたらすかもしれないと、大きな期待を集めました。科学者たちは、妊娠中やインスリン抵抗性が高まった際にβ細胞が増加する現象に着目し、そのメカニズムを解明しようと研究を進めていました 5。ベータトロフィンは、まさにそのようなβ細胞増加を促す「奇跡の候補」として脚光を浴びたのです。
ベータトロフィンの発見がこれほどまでに注目された背景には、その物語性の強さがありました。糖尿病という広く深刻な問題に対し、「失われたインスリン工場(β細胞)を再生させる」という単純明快かつ希望に満ちた解決策を提示したように見えたからです 5。特に、マウスでの実験とはいえ、β細胞が劇的に増殖するという報告は衝撃的でした 3。この「夢のようなホルモン」の発見は、ハーバード大学という権威ある研究機関から、Cellというトップジャーナルを通じて発表されたこともあり、瞬く間に世界中の研究者やメディア、そして患者たちの期待を煽りました。しかし、この熱狂は、科学的発見が時に性急な期待を生み出し、厳密な検証プロセスを経る前に社会に広まってしまう危険性も示唆していました。
II. ベータトロフィン発見:夢のホルモンは膵β細胞を再生するのか?
ベータトロフィンに関する興奮の震源地となったのは、2013年にハーバード大学のダグラス・メルトン教授の研究室から発表された画期的な論文でした 3。研究チームは、インスリン受容体拮抗薬S961をマウスに投与して人為的にインスリン抵抗性状態を作り出し、その際にβ細胞の増殖を促す因子を探索しました 3。
この研究における主要な発見は以下の通りです。
- 新たなホルモン「ベータトロフィン」の同定:主に肝臓と脂肪組織で発現する、これまで知られていなかった新しいホルモンが同定され、「ベータトロフィン」と名付けられました 3。この名前は、β細胞 (beta cell) を養い増やす (trophin) という期待を込めて付けられたものです。
- マウスにおけるβ細胞増殖効果:マウスの肝臓でベータトロフィンを過剰発現させると、膵β細胞の増殖が劇的に、かつ特異的に促進され(報告によれば最大で17倍から30倍の分裂率増加)、β細胞量が増加し、血糖コントロールが改善したと報告されました 3。さらに、妊娠中のマウスでもベータトロフィンの血中濃度が上昇することも見出され、これはβ細胞への需要が高まる生理的な状態と一致するものでした 5。
提唱された作用機序は、非常に魅力的でした。ベータトロフィンは肝臓や脂肪組織から分泌されるホルモンとして血流に乗り、膵臓のβ細胞に特異的に作用して自己複製を促すというものです 3。これがもし人間でも同様に機能するならば、ベータトロフィンを投与するだけで患者自身のβ細胞を再生させ、インスリン注射の回数を減らしたり、あるいは不要にしたりできるかもしれないという、まさに「夢の治療法」への道が開ける可能性が示唆されたのです 4。
この発見は世界中で熱狂的に報道され、「2型糖尿病治療のあり方を変える可能性」5、「インスリン注射の終わりか?」6 といった見出しがメディアを飾りました。製薬企業も迅速に反応し、ベータトロフィンを基盤とした治療薬開発のための共同研究契約が結ばれました 5。
2型糖尿病は、遺伝的要因、生活習慣、複数の細胞機能不全が複雑に絡み合って発症する疾患です 1。それに対し、ベータトロフィンという単一のホルモンが、β細胞の欠損という核心的な問題を解決するという仮説は、その単純さゆえに非常に魅力的でした。特に、ベータトロフィンがβ細胞にのみ特異的に作用するという主張は 3、副作用の少ない理想的な治療法への期待を大きく膨らませました。しかし、複雑な疾患が単一分子で解決することは稀であり、この「銀の弾丸」のような期待感は、後の展開を考えると、初期段階の研究成果に対する過度な楽観主義であったと言えるかもしれません。
III. 科学的検証の嵐:再現性の壁と失速する期待
華々しいデビューを飾ったベータトロフィンでしたが、その熱狂は長くは続きませんでした。科学の世界では、新たな発見は他の研究者による追試や検証を経て初めて確固たるものとなります。ベータトロフィンの場合、この検証プロセスで深刻な問題が浮上しました。
発表直後から、他の研究グループがメルトン教授らの結果を再現し、さらに研究を発展させようと試みました。しかし、ほどなくして、特にヒトのβ細胞に対する効果について疑問符がつく報告が出始めます。マウスのベータトロフィンは、ヒトのβ細胞の増殖を促さないという研究結果が示されたのです 1。中でも、2014年に発表されたジャオ (Jiao)氏らの研究は大きな影響を与えました。彼らは、メルトン教授らの研究でベータトロフィン産生を誘導するために用いられたS961を投与したマウスにおいて、マウス自身のβ細胞は増殖するものの、同じマウスに移植されたヒトのβ細胞は増殖しなかったことを報告しました 10。これは、ベータトロフィンのヒトへの治療応用という希望に冷や水を浴びせる結果でした。
決定打となったのは、2014年に同じくCell誌に掲載されたグサロヴァ (Gusarova)氏らによる論文でした 1。この研究は、メルトン教授らの当初の主張に真っ向から異議を唱えるものでした。
- β細胞増殖効果の否定:マウスの肝臓でANGPTL8/ベータトロフィンを過剰発現させても、血中の中性脂肪値は上昇するものの(これはANGPTL8の脂質代謝における既知の役割と一致)、β細胞の増殖やβ細胞量の増加は見られなかったと報告しました 7。
- ANGPTL8非必須説:ANGPTL8遺伝子を欠損させたマウス(ノックアウトマウス)でも、高脂肪食やS961投与によるインスリン抵抗性状態において、β細胞は正常に代償性の増殖を示しました。これは、ANGPTL8がβ細胞の増殖に必須ではないことを意味します 7。
これらの反証的なデータや、メルトン教授自身の研究室での追試結果を踏まえ、彼らは当初の結論を再評価せざるを得なくなりました。2014年にはCell誌にレターを発表し、ANGPTL8ノックアウトマウスでもβ細胞増殖が正常であること、また過剰発現実験では「有意かつ不満足なばらつき」が見られたことを認めました 7。実験手技(特に過剰発現に用いたハイドロダイナミック尾静脈注射法)に起因する肝臓の炎症などが、結果のばらつきの一因となった可能性も示唆されました 9。より多くの実験個体数を含めて再解析すると、β細胞の増殖率は当初報告された値よりも大幅に低下しました 13。
そしてついに2016年、大きな注目を集めた2013年のCell論文は正式に撤回されました 5。撤回理由には、「ANGPTL8/ベータトロフィンが特異的なβ細胞複製を引き起こすという我々の結論は誤りであり、支持できない」と明記されました 9。
このベータトロフィンを巡る一連の出来事から、科学界はいくつかの重要な教訓を得ました 7。第一に、新たな増殖因子に関する強い主張を行う際には、遺伝学的証拠(例えば、その因子を欠損させた場合の影響を調べる研究)がいかに重要であるかということです 7。第二に、マウスモデルでの結果をヒトの生理機能、特にβ細胞の増殖能に安易に外挿することの難しさです。ヒトのβ細胞は、げっ歯類のβ細胞に比べてはるかに増殖しにくいことが知られています 10。第三に、科学の自己修正プロセスは、時に痛みを伴うものの、進歩のためには不可欠であるということです。注目度の高い論文の撤回は稀ですが、それ自体が科学の健全性を示す証左とも言えます。そして最後に、初期段階の研究成果を公表する際には、誤った希望を抱かせないよう慎重さが求められるという点です 7。
以下の表は、ベータトロフィン(ANGPTL8)研究における主要なマイルストーンをまとめたものです。
表1:ベータトロフィン(ANGPTL8)研究の主なマイルストーン
| 年 | 主要な発見/出来事 | 参考文献 | 意義/影響 |
| 2013 | ベータトロフィン発見。マウスβ細胞増殖を劇的に増加させると報告 | Yi et al., Cell 3 | 世界的な興奮、糖尿病治療への期待 |
| 2013/2014 | マウスベータトロフィンはヒトβ細胞の増殖を刺激しないとの報告 (Jiao et al.など) | Jiao et al., Diabetes 10 | ヒトへの応用に関する最初の大きな疑問 |
| 2014 | ANGPTL8/ベータトロフィン過剰発現はマウスβ細胞増殖を引き起こさず、ノックアウトマウスは正常なβ細胞代償能を示すと報告 | Gusarova et al., Cell 7 | 当初の主要な発見を直接的に否定 |
| 2014 | 原著論文著者らが再現性の問題と、ANGPTL8単独ではS961誘発性増殖を説明できないことを認めるレターを発表 | Yi et al., Cell 9 | 原著チームによる問題点の認識 |
| 2016 | 2013年のYi et al.によるCell論文が正式に撤回 | 5 | β細胞増殖に関する当初の主張の正式な取り下げ |
この表は、発見から挑戦、そして修正へと至るベータトロフィンのβ細胞増殖に関する物語の主要な出来事を時系列で示しており、科学的理解が急速に進展し、初期の主張がどのように検証され、最終的に修正されたかの過程を理解する助けとなります。
ベータトロフィンの初期の有望性が揺らいだ大きな理由の一つは、マウスでの有望な結果にもかかわらず、ヒトのβ細胞に対して効果がなかったことです 1。マウスは、そのコスト、遺伝子操作の容易さ、寿命の短さから、前臨床研究で頻繁に用いられるモデル動物です。しかし、マウスとヒトの間には、特にβ細胞の生物学や再生能力において、重要な生理学的・代謝的差異が存在します 10。ベータトロフィンに関する初期の研究はマウスモデルに大きく依存していましたが 3、ヒトβ細胞を用いた系で検証した際には、期待された増殖効果は確認できませんでした 10。この事実は、トランスレーショナルリサーチ(基礎研究の成果を臨床応用へと橋渡しする研究)における根源的な課題、「マウスで効果があっても、ヒトで効果があるとは限らない」という現実を浮き彫りにします。ベータトロフィンの物語は、動物実験のデータ解釈の慎重さと、ヒトでの検証の早期実施の重要性を改めて示す教訓となりました。
一方で、ベータトロフィンに関する当初の華々しい主張が厳密に検証され、最終的には原著者らによって撤回されたという一連の経緯は 5、一見「失敗」と映るかもしれませんが、実は科学的方法論の強さを示すものです。査読、追試、そして公開討論といったプロセスを経て、たとえそれが論文撤回という形であっても、科学的知識は時間をかけて精査され、修正されていくのです。これは、科学の誠実さを示す前向きなメッセージとして捉えるべきでしょう。
IV. ベータトロフィン(ANGPTL8)の真実:脂質代謝のキープレイヤーとして
β細胞増殖の夢は潰えましたが、ベータトロフィンの物語はそこで終わりではありませんでした。実は、「ベータトロフィン」と名付けられたこのタンパク質は、アンジオポエチン様タンパク質8(Angiopoietin-like protein 8、ANGPTL8)という名前で既に知られていた、あるいは研究が進められていた分子だったのです 2。他にも、リパシン (lipasin)、RIFL (Refeeding-Induced Fat and Liver protein)、TD26といった複数の名前で呼ばれていました 2。
ANGPTL8は、アンジオポエチン様タンパク質(ANGPTL)ファミリーに属し、このファミリーのタンパク質は、特に脂質代謝を含む様々な代謝プロセスに関与しています 2。そして、ANGPTL8の真の役割は、主に脂質代謝の調節にあることが、その後の研究で確固たるものとなっていきました。
ANGPTL8の最もよく確立された機能は、血中の中性脂肪(トリグリセリド、TG)濃度の調節です 2。ANGPTL8は、しばしば同じファミリーのANGPTL3やANGPTL4と協調して、リポタンパク質リパーゼ(LPL)という酵素の活性を阻害します。LPLは、血中から中性脂肪を取り込む上で非常に重要な役割を担っています 15。ANGPTL8の発現量は栄養状態によって調節され、摂食によって上昇し、絶食によって抑制されることがわかっています 2。これは、食後の脂質負荷を管理するタンパク質としては理にかなった挙動です。
ANGPTL8遺伝子を欠損させたマウス(Angptl8-/- マウス)を用いた研究は、β細胞を巡る論争とは独立して、ANGPTL8の脂質代謝における役割を強力に裏付けました。これらのマウスは、中性脂肪代謝の異常を示しました。具体的には、摂食後に血漿中の中性脂肪値が逆説的に低下し(LPL活性の亢進とVLDL分泌低下による)、脂肪組織への脂肪蓄積が減少しました 14。つまり、食後に中性脂肪を効率的に脂肪組織に貯蔵できなかったのです 16。
そして極めて重要なことに、これらのAngptl8-/- マウスは、通常食でも高脂肪食でも、糖代謝やインスリン感受性に顕著な異常を示しませんでした 2。この事実は、当初期待されたような糖代謝やβ細胞機能における主要な役割というよりは、むしろ脂質代謝がANGPTL8の主戦場であることを強く示唆していました。
「ベータトロフィン」という名前で呼ばれたタンパク質が、ANGPTL8として既に脂質代謝との関連で研究されていたという事実は 2、科学における命名や既存知識の重要性を示唆しています。「ベータトロフィン」という名称は、その(当時期待された)β細胞への効果に注目を集中させ、ANGPTL8やそのファミリータンパク質の脂質調節における既存の知見から一時的に切り離してしまった可能性があります。最終的にこれらの研究ラインが収束し、ベータトロフィンがANGPTL8であると認識されたことで、その真の生理機能がより明確になりました。これは、科学的な命名がいかに認識や研究の焦点を形成しうるか、そして新しい発見を既存の知識体系と統合することの価値を示しています。この物語は、再発見あるいは再特性評価が、最終的にはANGPTLに関する以前の研究と整合した例と言えるでしょう。
V. ベータトロフィンの「今」:糖尿病との新たな接点と今後の展望
β細胞の再生因子としての期待は裏切られたものの、ANGPTL8/ベータトロフィンは代謝疾患の研究対象としての価値を失ったわけではありません。むしろ、その後の研究により、脂質代謝のキープレイヤーとしての役割が確立されるとともに、糖尿病やその他の代謝性疾患との新たな接点が見出されつつあります。
代謝性疾患のバイオマーカーとしてのANGPTL8/ベータトロフィン
ANGPTL8の血中濃度は、様々な代謝性疾患において変動することが報告されており、バイオマーカーとしての可能性が探られています。
- 2型糖尿病:複数の研究で、新たに2型糖尿病と診断された患者、特に肥満を伴う患者において、血中ベータトロフィン濃度が上昇していることが示されています 1。2型糖尿病の診断バイオマーカー候補としても注目されています 1。
- メタボリックシンドロームと肥満:肥満やメタボリックシンドロームの患者でも血中濃度の上昇が見られ 1、BMI(体格指数)や空腹時血糖値といった指標との相関も報告されています 20。
- NAFLD/MAFLD/MASLD(非アルコール性脂肪性肝疾患/代謝機能障害関連脂肪性肝疾患/代謝機能障害関連脂肪肝疾患):非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)や、その新しい疾患概念であるMAFLD/MASLDの患者では、健常者と比較して血中ANGPTL8濃度が有意に高いことが複数の研究で示されています 22。脂肪肝や脂肪性肝炎のバイオマーカーとしての有用性が検討されています 23。
- HDLコレステロールとの負の相関:ベータトロフィン濃度は、善玉コレステロールとして知られるHDLコレステロール値と負の相関を示すことも報告されています 1。
炎症や糖尿病合併症における新たな役割
- 炎症:ANGPTL8は、代謝性疾患の重要な構成要素である炎症との関連も指摘されています 17。その役割は複雑で、文脈によっては炎症促進的に、またある文脈では抗炎症的に働く可能性も示唆されています 17。
- 糖尿病関連認知機能障害(DACD):ごく最近の研究(Meng et al., 2024)では、ANGPTL8がDACDにおいて有害な役割を果たす可能性が示唆されています 26。糖尿病モデルマウスの脳では、海馬の神経細胞から分泌されるANGPTL8が、PirBという受容体を介して神経炎症やシナプスの損傷を引き起こす可能性が報告されました。中枢神経系特異的にAngptl8を欠損させたマウスでは、これらの問題が抑制されたことから 26、ANGPTL8が糖尿病による認知機能低下に関与する新たな経路として注目されます。
- その他の合併症:高血圧や心筋症との関連も研究されています 22。
現在の治療ポテンシャル:より多角的な視点
ベータトロフィンを用いてβ細胞を再生させるという夢は消えましたが、脂質代謝における役割や代謝性疾患との関連から、依然として関心の高い分子です。ANGPTL8の機能を阻害することが、特定の状況下で有益となる可能性も考えられます。例えば、ANGPTL8が望ましくない形での脂質蓄積を促進したり、DACDのような合併症に関与したりする場合です 26。治療標的としての可能性は複雑であり、文脈依存的であると考えられます 23。MASLDに関しては、バイオマーカーとしての可能性はあるものの、治療標的としての役割は未解明で、病期によっても異なる可能性があります 23。
今後の研究の方向性
今後の研究では、ANGPTL8が様々な代謝性疾患やその合併症にどのように関与するのか、その詳細なメカニズムの解明が求められます(例:DACDにおける神経細胞でのANGPTL8発現調節機構など 26)。また、2型糖尿病やMASLDなどに対する堅牢なバイオマーカーとしての有用性を、大規模な前向き臨床研究で検証する必要があります 23。さらに、ANGPTL8の多面的な役割を明確に理解した上で、特定の病態におけるANGPTL8活性の調節(促進または抑制)が治療に結びつくかどうかの検討も重要となるでしょう 22。
ANGPTL8/ベータトロフィンに関する研究の焦点は、β細胞増殖から、脂質代謝を中心とする代謝調節因子、バイオマーカー、そして糖尿病合併症における潜在的役割へと劇的にシフトしました。これは、科学的探求のダイナミックな性質を示しています。当初の仮説が否定されたとしても、その分子の他の、時には予期せぬ役割が明らかになることがあります。ANGPTL8の物語はまだ終わっておらず、異なる道を辿りながら、その複雑な姿を私たちに見せ続けています。
ANGPTL8が様々な代謝性疾患のバイオマーカーとして注目され、しばしば疾患状態でその濃度が上昇しているという事実は 1、治療標的としての可能性を考える上で慎重な検討を要します。ある分子の濃度が疾患状態で上昇している場合、それが疾患の原因の一部なのか、結果なのか、あるいは代償的な反応なのかを区別する必要があります。例えば、初期のNAFLDではANGPTL8濃度の上昇がインスリン分泌を促進するための代償機構である可能性が示唆されていますが 23、DACDでは脳内で直接的に病態を悪化させる因子として働いているように見えます 26。また、LPL阻害作用を持つことから 15、その濃度上昇が脂質異常症を悪化させる可能性も考えられます。このように、ある分子が「バイオマーカー」であるからといって、その活性を上げれば良いのか下げれば良いのかは一概には言えません。その役割は、組織や病期、疾患の状況によって異なり、時には相反することもあるため、治療介入を検討する前に、これらの複雑な関係性を慎重に解き明かす必要があります。
VI. 結論:ベータトロフィン物語が私たちに問いかけるもの
ベータトロフィンの物語は、まさにドラマチックな展開を辿りました。糖尿病治療の「奇跡のホルモン」としての衝撃的な発見と熱狂的な期待、その後の厳密な科学的検証による疑念の噴出、そして主要な主張の撤回。現在は、主に脂質代謝に関与する複雑なタンパク質ANGPTL8として、炎症や糖尿病合併症との新たな関連性が探求されています。
本稿のタイトルでもある「2型糖尿病の根本治療が可能?」という問いに対して、ベータトロフィンが当初期待されたようなβ細胞再生による根本治療の鍵とはならなかった、というのが現時点での答えです。しかし、根本治療への探求そのものが終わったわけではありません。ベータトロフィンの物語は、ある側面では期待外れに終わったかもしれませんが、代謝調節やβ細胞生物学に関するより広範な知識体系に貢献しました。科学は、このような仮説、検証、そして修正のサイクルを通じて進歩していくのです。
ベータトロフィンを巡る一連の出来事は、科学の失敗物語ではなく、むしろ科学の自己修正能力の証左と言えます。エキサイティングではあったものの、最終的に正しくないと判断された仮説が、厳密な検証プロセスを経て修正されたのです。再現性の確認、批判的評価、そして必要であれば撤回する勇気。これらはすべて、科学の健全性を支える重要な要素です。
医学研究は長く、漸進的なプロセスです。画期的な進歩は稀であり、多くの場合、それほど華々しくはない基礎研究の長年の積み重ねの上に成り立っています。一般社会やメディアは、初期の科学的発表に対して、希望とともに健全な批判的意識を持って接することが求められます。
ANGPTL8の研究は、β細胞の救世主とはならなかったものの、脂質異常症やメタボリックシンドロームの理解、そして特定の合併症のバイオマーカーや治療標的としての可能性を探る上で、依然として重要な研究対象であり続けています。その物語は、形を変えて今もなお紡がれているのです。
ベータトロフィンの物語が示すように、科学の進歩は必ずしも直線的ではありません。当初の道筋は、発見から検証、そして治療法開発へと直接的に進むように見えました。しかし、主要な主張に関する検証段階でつまずき、分子の基本的な役割の再評価へと繋がりました。そして今、バイオマーカーとしての利用や合併症への関与といった、よりニュアンスに富んだ新たな研究の道筋が生まれつつあります。仮説の「失敗」や否定は行き止まりではなく、研究を方向転換させ、最終的により正確な理解へと導く重要なデータポイントなのです。これは、科学がどのように機能するのかをより現実的に理解する上で、一般の読者にも伝えるべき洗練された概念と言えるでしょう。
引用文献
- Betatrophin Acts as a Diagnostic Biomarker in Type 2 Diabetes Mellitus and Is Negatively Associated with HDL-Cholesterol – PMC, 5月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4706922/
- Betatrophin provides a new insight into diabetes treatment and lipid metabolism (Review), 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.spandidos-publications.com/10.3892/br.2014.284
- Betatrophin: a hormone that controls pancreatic β cell proliferation …, 5月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3756510/
- Betatrophin fuels β cell proliferation: first step toward regenerative therapy? – PubMed, 5月 8, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23823472/
- Diabetes treatment discovery by Harvard scientists Douglas Melton and Peng Yi, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.harvardmagazine.com/2013/04/potential-diabetes-treatment-discovered
- The End of Insulin? – Time, 5月 8, 2025にアクセス、 https://time.com/archive/6643474/the-end-of-insulin/
- Betatrophin—Promises Fading and Lessons Learned – PMC, 5月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4410809/
- HSCI co-director Douglas Melton and Evotec collaborate on diabetes – Harvard Stem Cell Institute, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.hsci.harvard.edu/news/hsci-co-director-douglas-melton-and-evotech-collaborate-diabetes
- ‘Breakthrough’ Diabetes Article Retracted – Medscape, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.medscape.com/viewarticle/873863
- Betatrophin Versus Bitter-Trophin and the Elephant in the Room: Time for a New Normal in β-Cell Regeneration Research – American Diabetes Association, 5月 8, 2025にアクセス、 https://diabetesjournals.org/diabetes/article/63/4/1198/15104/Betatrophin-Versus-Bitter-Trophin-and-the-Elephant
- Elevated Mouse Hepatic Betatrophin Expression Does Not Increase Human β-Cell Replication in the Transplant Setting – American Diabetes Association, 5月 8, 2025にアクセス、 https://diabetesjournals.org/diabetes/article/63/4/1283/15354/Elevated-Mouse-Hepatic-Betatrophin-Expression-Does
- Retraction Notice to: Betatrophin: A Hormone that Controls Pancreatic β Cell Proliferation, 5月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5287220/
- Perspectives on the Activities of ANGPTL8/Betatrophin – CORE, 5月 8, 2025にアクセス、 https://core.ac.uk/download/pdf/82746286.pdf
- ANGPTL8 (Betatrophin) Does Not Control Pancreatic Beta Cell Expansion – PMC, 5月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4243040/
- ANGPTL8: An Important Regulator in Metabolic Disorders – Frontiers, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/articles/10.3389/fendo.2018.00169/full
- Mice lacking ANGPTL8 (Betatrophin) manifest disrupted triglyceride metabolism without impaired glucose homeostasis | PNAS, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1315292110
- The Proinflammatory Role of ANGPTL8 R59W Variant in Modulating Inflammation through NF-κB Signaling Pathway under TNFα Stimulation – MDPI, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2073-4409/12/21/2563
- Angiopoietin-Like Protein Family-Mediated Functions in Modulating Triglyceride Metabolism and Related Metabolic Diseases – IMR Press, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.imrpress.com/journal/FBL/30/4/10.31083/FBL25862/htm
- Mice lacking ANGPTL8 (Betatrophin) manifest disrupted triglyceride …, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1315292110
- Betatrophin: A promising biomarker for metabolic syndrome and diabetes mellitus risk screening in teenagers – JOURNAL OF UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA, 5月 8, 2025にアクセス、 https://journal2.unusa.ac.id/index.php/IJMLST/article/download/6028/2754
- Betatrophin: A promising biomarker for metabolic syndrome and diabetes mellitus risk screening in teenagers – ResearchGate, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/390641961_Betatrophin_A_promising_biomarker_for_metabolic_syndrome_and_diabetes_mellitus_risk_screening_in_teenagers
- Emerging insights into the roles of ANGPTL8 beyond glucose and …, 5月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10722441/
- Circulating angiopoietin-like protein 8 (ANGPTL8) and steatotic liver …, 5月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12018230/
- Circulating angiopoietin-like protein 8 (ANGPTL8) and steatotic liver disease related to metabolic dysfunction: an updated systematic review and meta-analysis – PubMed, 5月 8, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40276549/
- Circulating angiopoietin-like protein 8 (ANGPTL8) and steatotic liver disease related to metabolic dysfunction: an updated systematic review and meta-analysis – Frontiers, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/articles/1574842
- Inhibition of ANGPTL8 protects against diabetes-associated …, 5月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11297729/