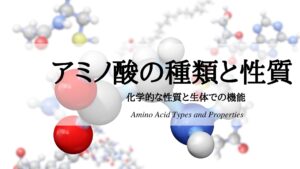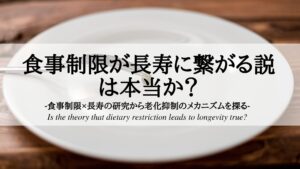1. はじめに
インパクトファクター(IF)は、学術界、とりわけ研究者にとって、そのキャリアを通じて意識せざるを得ない指標として、長年にわたり大きな影響力を持ってきた。論文を発表する学術雑誌の選定から、研究機関における業績評価、さらには研究資金の獲得に至るまで、IFの数値が様々な場面で判断材料の一つとして用いられている現状がある。多くの研究者が、自らの研究成果をどのジャーナルに投稿すべきか、そしてその選択が自身の評価にどう影響するのかを常に考慮していると言っても過言ではないだろう。
本記事では、このインパクトファクターについて、その基本的な定義や計算方法、歴史的背景から説き起こし、学術界で評価されてきた側面(「功績」)と、その一方で多くの批判や問題点を抱える側面(「罪過」)を、国内外の文献を参照しつつ多角的に検証する。さらに、IFを巡る現状、特にIFの数値を過度に重視する「インパクトファクター至上主義」とも言える風潮が、研究活動や学術界全体にどのような歪みをもたらしているのかについて、筆者自身の見解も交えながら論じる。本記事が、読者である研究者諸氏にとって、インパクトファクターという指標をより深く、批判的に理解し、自身の研究活動のあり方や学術界の動向を考察する上での一助となることを目指す。この指標が持つ意味合いや、それに伴う期待と懸念を明らかにすることで、より建設的な議論のきっかけを提供したい。
2. インパクトファクターとは? – 基本を理解する
インパクトファクター(IF)を巡る議論を深める前に、まずはその基本的な定義、計算方法、歴史的背景、そして関連する指標について正確に理解しておく必要がある。
2.1. 定義と計算方法
インパクトファクターとは、特定の学術雑誌に掲載された論文が、ある一定期間(通常は過去2年間)において、平均してどれだけ他の学術論文に引用されたかを示す指標である 1。この数値は、その雑誌が当該分野において持つ影響力や注目度を相対的に示すものとして解釈されることが多い 3。
具体的な計算方法は以下の通りである 1。
IF (ある年の値)=対象年の前2年間に掲載された「引用可能な」論文総数対象年の前2年間に掲載された論文が対象年に引用された総回数
例えば、2023年のIFを計算する場合、2021年と2022年にその雑誌に掲載された論文が、2023年中に引用された総回数を、2021年と2022年に掲載された「引用可能な論文(citable items)」の総数で割ることによって算出される 1。
ここで重要なのは「引用可能なアイテム」の定義である。一般的には、原著論文(original research articles)やレビュー論文(review articles)がこれに該当し、編集後記(editorials)、レター(letters to the editor)、ニュース記事などは分母の論文数から除外されることが多い 6。しかし、これらの除外された記事タイプも引用されることはあり、分子の引用回数にはカウントされる場合がある。この分子と分母のアイテムタイプの非対称性が、IFの値を実際よりも高く見せる可能性については認識しておく必要がある 7。この定義の曖昧さや運用が、IFという指標の客観性に対する一つの潜在的な脆弱性とも言える。
2.2. 歴史的背景と開発者
インパクトファクターの概念を考案したのは、米国のユージン・ガーフィールド博士(Dr. Eugene Garfield)である 2。彼は、自身が設立した科学情報研究所(Institute for Scientific Information, ISI)を通じて、学術文献のデータベース化と引用情報の分析に尽力した 4。
IFが考案された当初の主な目的は、図書館員が限られた予算の中で購読する学術雑誌を選定する際に、客観的な判断材料を提供することであった 5。増え続ける学術雑誌の中から、より影響力が高く、研究者コミュニティにとって重要な雑誌を効率的に見分けるためのツールとして期待されたのである 11。この本来の限定的な目的を理解することは、後に詳述するIFの誤用やそれに伴う問題を考察する上で極めて重要となる。
インパクトファクターは、1975年からISIが発行する「ジャーナルサイテーションレポート(Journal Citation Reports, JCR)」において、毎年提供されるようになった 9。
2.3. 提供元と関連指標
現在、インパクトファクターの算出と提供を行っているのは、クラリベイト・アナリティクス社(Clarivate Analytics)である 13。同社が提供する大規模学術文献データベース「Web of Science (WoS)」に収録された論文の引用データに基づいてIFは計算されている 15。したがって、WoSの収録範囲(対象ジャーナルや分野)が、IFが付与されるジャーナルの範囲やその数値の基盤となっている。
IF以外にも、ジャーナルの影響力や特性を測るための関連指標がいくつか存在する。
- 5-year Impact Factor(5年インパクトファクター): 通常のIFが過去2年間のデータを基にするのに対し、過去5年間のデータを基に算出される。これにより、引用されるまでに時間がかかる分野や、長期的な影響力を持つ論文の評価に適しているとされる 2。
- Immediacy Index(最新文献指数): 論文が発行されたその年のうちにどれだけ迅速に引用されるかを示す指標で、特に速報性が重視される研究分野のジャーナル比較に用いられることがある 2。
- Eigenfactor Score / Article Influence Score: GoogleのPageRankアルゴリズムに類似した考え方を取り入れ、引用元のジャーナルの影響力も考慮してジャーナルの影響度を評価する指標群である 2。
これらの代替指標の存在は、IFがジャーナルを評価するための唯一絶対の指標ではないことを示唆している。IFが持つ本来の目的や計算方法、そしてその限界を理解することは、学術界におけるその役割と影響を正しく評価するための第一歩である。当初、図書館のコレクション管理という実用的なニーズから生まれたこの指標が、今日のように研究者評価にまで広範に用いられるようになった背景には、学術界や研究機関における評価の客観性や効率性への希求があったと考えられる 11。しかし、その過程で、指標の持つ意味や限界が十分に理解されないまま利用が拡大したことが、後に議論する多くの問題点を生む一因となった。
3. インパクトファクターの「功」 – なぜ評価されてきたのか
インパクトファクター(IF)が長年にわたり学術界で重視され、広く用いられてきた背景には、いくつかの肯定的な側面、すなわち「功績」として認識される理由が存在する。これらの点を理解することは、IFがなぜこれほどまでに普及したのか、そしてなぜ多くの研究者がそれを意識するのかを把握する上で不可欠である。
客観的な比較指標としての価値
IFの最大の功績の一つは、学術雑誌の影響力や相対的な重要性を、分野内である程度客観的かつ定量的に比較するための簡便な指標を提供した点にある 3。特に、同一の研究分野に属する多数のジャーナルの中から、より影響力の高いとされるものを識別する際の一助として機能してきた 10。研究者にとっては、自身の研究成果を発表するジャーナルを選定する際の参考情報となり 4、図書館にとっては、購読するジャーナルを選定する際の判断材料の一つとして活用されてきた歴史がある 5。この「比較の容易さ」は、情報が氾濫する現代において、一つの指針を求める声に応えるものであった。
研究の可視性・認知度向上への期待
研究者にとって、IFの高いジャーナルに論文が掲載されることは、その研究成果がより多くの研究者の目に触れ、広く認知され、そして引用される可能性を高めるという期待に繋がってきた 3。高IFジャーナルは一般的に購読者数が多く、国際的なリーチも広いため、そこに掲載されることで研究の「可視性」が向上すると考えられている 16。
この期待は、研究者個人のキャリア形成とも密接に関連している。高IFジャーナルへの掲載実績は、就職、昇進、テニュア(終身在職権)の獲得、さらには研究資金の獲得競争において有利に働くという認識が広く浸透している 3。実際に、研究費の申請書において、成果発表予定のジャーナルとして高IF誌を挙げることで、採択の可能性を高める戦略を取る研究者もいると指摘されている 17。
学術雑誌の質や影響力の代理指標
IFが高いジャーナルは、一般的にその分野をリードする質の高い研究が掲載され、厳格な査読プロセスを経ているという信頼感と結びつけられてきた 3。編集体制が優れており、掲載される論文の新規性や学術界への影響力が高いという認識が、IFの数値を一種の「品質保証マーク」のように機能させてきた側面がある 19。
これらの「功績」とされる点は、IFが持つ「平均引用頻度が高いジャーナルは、より重要で質の高い研究を掲載しているはずだ」という根本的な仮定に基づいている 3。この仮定の妥当性については後に詳述するが、IFが提供する数値の簡便さと、それがもたらす「権威」や「名声」への期待が、IFを学術界における重要な評価指標の一つへと押し上げた原動力であったと言える。高IFジャーナルが持つとされる権威は、さらに多くの優れた(あるいはそう見込まれる)論文投稿を引き寄せ、その結果としてIFが維持・向上するという好循環(あるいは既得権益の強化)を生み出し、既存のジャーナル階層を固定化させる力学も働いてきた。学術機関や資金配分機関が、多数の研究成果を迅速に評価する必要に迫られる中で、IFのような定量的な指標は、その利便性から重宝され、その地位を確固たるものにしてきたのである 5。
4. インパクトファクターの「罪」 – 批判と問題点
インパクトファクター(IF)が学術界にもたらした「功績」とされる側面がある一方で、その利用方法や指標自体の限界から生じる「罪過」、すなわち多くの批判や問題点が存在する。これらを理解することは、IFという指標をめぐる議論の核心に迫る上で不可欠である。
4.1. 本来の目的からの逸脱と誤用
IFに関する最も根本的かつ重大な問題点は、その本来の目的からの逸脱と、それに伴う広範な誤用である。前述の通り、IFは元来、図書館員が雑誌の購読を選定する際の補助的なツールとして考案されたものであり、ジャーナル全体の相対的な影響力を示す指標であった 5。しかし、いつしかこのジャーナルレベルの指標が、個々の論文の質や、さらには研究者個人の業績を評価するための直接的な尺度として短絡的に用いられるようになった 3。
この誤用は、「IFが高い雑誌に掲載された論文は、すなわち質の高い論文である」「その論文の著者は、すなわち優れた研究者である」という安易な等式化を学術界に蔓延させた 10。IFの考案者であるユージン・ガーフィールド自身も、IFを個々の研究者評価に用いることは不適切であると繰り返し警告していたにもかかわらず、この傾向は止まらなかった 5。この「目的外利用」こそが、IFを巡る多くの問題の根源となっている。
4.2. IF指標自体の限界と脆弱性
IFという指標自体も、その算出方法や特性に起因する多くの限界と脆弱性を抱えている。
- 分野による引用習慣の大きな違い: 研究分野によって論文の引用パターンや頻度は大きく異なる。例えば、医学や生命科学分野では一般的に引用数が多くIFが高くなる傾向があるのに対し、人文科学・社会科学や数学などの分野では引用数が比較的少なくIFも低くなる傾向がある 3。17では、医学・生命科学分野でIFが5.0以上で高評価とされる一方、人文・社会科学分野では1.0以上で高評価とされるなど、具体的な数値の目安が分野によって大きく異なることが示されている。したがって、異なる分野間でのIFの単純比較は全く意味をなさず、誤った評価を導く危険性がある 6。
- 引用分布の歪み(Skewed Citation Distribution): IFはあくまでジャーナルに掲載された論文の「平均」被引用回数を示すものであるが、実際にはジャーナル内の論文の被引用数は極めて歪んだ分布を示すことが多い 3。つまり、ごく一部の非常によく引用される論文(スター論文)がジャーナル全体のIF値を大きく引き上げている一方で、掲載されている論文の大部分は、そのジャーナルのIF値ほどには引用されていないというケースが頻繁に見られる 7。このため、IF値だけを見て、そのジャーナルの全ての論文が等しく高い影響力を持つと考えるのは誤りである。
- 短期間の評価: IFは通常、過去2年間の引用データに基づいて算出されるため、成果が引用されるまでに時間を要する分野や、長期にわたって影響力を持ち続けるような研究の評価には不向きである 22。例えば、基礎研究や、じっくりと時間をかけて吟味されるような理論研究などは、この短期間の評価ウィンドウでは過小評価される可能性がある 8。
- レビュー論文や総説の影響: レビュー論文(総説)は、特定の研究テーマに関する既存の知見をまとめたものであり、多くの研究者にとって参照価値が高いため、一般的に原著論文よりも多く引用される傾向がある 10。そのため、レビュー論文を多く掲載するジャーナルは、IFが高くなる傾向があり、これが必ずしもそのジャーナルが革新的なオリジナル研究を多く生み出していることを意味するわけではない 5。
- 自己引用・相互引用・引用カクテルによる操作可能性: ジャーナルの編集者や論文の著者が、意図的に自誌の論文や自身の過去の論文を引用する(自己引用)ことで、IFを人為的につり上げる行為が指摘されている 10。さらに悪質なケースとしては、複数のジャーナル編集部が共謀し、互いのジャーナルに掲載された論文を組織的に引用し合う「引用カクテル(citation cartels)」と呼ばれる不正行為も報告されており、IFの信頼性を著しく損なう要因となっている 3。
- 「引用可能なアイテム」の定義の曖昧さ: IF算出の分母となる「引用可能なアイテム」の定義が、出版社やジャーナルによって微妙に異なる場合があり、これがIF値に影響を与える可能性がある 6。例えば、引用されやすいレターやエディトリアルを分母から除外しつつ、それらへの引用を分子に含めることでIFが高く見えるように操作される余地がある。
- 新しいジャーナルへの不利: 新たに創刊されたジャーナルは、引用実績を蓄積するのに一定の時間を要するため、IFに基づく評価では必然的に不利な立場に置かれる 7。これにより、革新的な分野や新しいアプローチを試みるジャーナルの成長が阻害される可能性も懸念される。
これらの限界と脆弱性は、IFが研究の質や影響力を測る万能の指標ではあり得ないことを明確に示している。特に、個々の研究者や論文の評価にIFを用いることの危険性は、これらの指標自体の問題点によってさらに増幅される。IFが高いステークスを持つ評価(昇進、資金配分など)に誤用されることが、ジャーナルや研究者によるIF操作のインセンティブを生み出し、結果として学術界全体の健全性を損なうという悪循環に繋がりかねない。IFが「平均値」であるという統計学的な事実はしばしば忘れ去られ、個々の事例に不適切に適用される「平均の罠」に陥っていると言えるだろう。さらに、高IFジャーナルが特定の種類の研究(例えば、流行のトピックやセンセーショナルな発見)を好む傾向 25 があるとすれば、研究者はより安全でIF誌に掲載されやすいテーマを選ぶようになり、結果として研究の多様性や独創性が損なわれるリスクも考えられる。
以下に、インパクトファクターの主な功績と罪過をまとめた表を示す。
表1: インパクトファクターの主な功績と罪過
| 側面 (Aspect) | 功 (Merits) | 罪 (Sins) |
| 比較容易性 | 同一分野内のジャーナル影響力を簡便に比較可能 3 | 分野横断的な比較は無意味 3。引用分布の歪みにより平均値が実態を反映しない可能性 8。 |
| 研究者・論文評価への利用 | (誤用であるが)キャリア形成や資金獲得に有利との期待 3 | 本来の目的外利用。個々の論文の質や研究者の能力を正しく反映しない 5。考案者も警告 5。 |
| 指標の頑健性・信頼性 | 長年の利用実績と広範な認知 3 | 自己引用・相互引用・引用カクテル等による操作が可能 22。短期間評価の限界 8。レビュー論文の影響 5。 |
| 学術雑誌選定 | 図書館の雑誌購読選定や研究者の投稿先選定の一助 10 | 新規ジャーナルに不利 7。ジャーナルの多様性を損なう可能性。 |
| 研究の方向性への影響 | (間接的に)質の高い研究を奨励するとの期待 3 | 高IF獲得が目的化し、研究テーマの狭隘化やリスク回避を助長する可能性 25。 |
この表は、IFが持つ二面性を簡潔に示している。その利便性から広く受け入れられてきた一方で、その限界と誤用が深刻な問題を引き起こしている現状を理解する必要がある。
5. 現状への警鐘:インパクトファクター至上主義がもたらす歪み
インパクトファクター(IF)が本来の目的を離れて誤用され、その数値が過度に重視される「インパクトファクター至上主義」とも呼べる風潮は、学術界に深刻な歪みをもたらしている。この現状は、研究の本質を見失わせ、研究者や研究システム全体に負の影響を及ぼしている。
5.1. 「高IFジャーナルへの論文掲載」が目的化する現状
多くの研究機関や資金配分機関において、IFが高いジャーナルへの論文掲載実績が、研究成果の質や重要性を測る主要な指標として扱われるようになった結果、研究者自身も「いかにして高IFジャーナルに論文をアクセプトさせるか」という点に過剰なエネルギーを注ぐようになった 26。研究の本来の目的である真理の探究や社会への貢献よりも、高IFジャーナルという「器」に論文を掲載すること自体が目的化してしまう本末転倒な状況が生まれている 5。
このようなIF至上主義は、研究者の研究テーマ選択にも影響を及ぼす。斬新ではあるが成果が出るまでに時間がかかる研究や、ニッチではあるが重要な研究よりも、短期間で成果が出やすく、かつ高IFジャーナルが好むとされる「流行の」あるいは「センセーショナルな」テーマが優先される傾向が強まる可能性がある 25。結果として、学術研究全体の多様性や長期的な発展が阻害される危険性も指摘されている。
5.2. 「Publish or Perish」文化の激化とIF
学術界には古くから「Publish or Perish(出版か死か)」という言葉で表現される、論文出版への強いプレッシャーが存在する 27。この厳しい競争環境が、IFという分かりやすい序列化指標の登場によって、さらに激化している。テニュアの獲得、昇進、研究資金の配分といった研究者のキャリアにおける重要な局面で、発表論文の数だけでなく、掲載されたジャーナルのIFが主要な評価軸として機能するようになったためである 4。
この結果、研究者は常にIFを意識し、より高いIFを持つジャーナルへの投稿を目指すというプレッシャーに晒され続けることになる 9。このような状況は、特に若手研究者にとっては大きな負担となり、自由な発想に基づく挑戦的な研究を萎縮させる可能性も否定できない。
5.3. 研究の質・健全性への悪影響
過度なIF追求は、研究の質そのものにも悪影響を及ぼしかねない。一つの研究成果を細切れにして複数の論文として発表する「サラミ出版(least publishable unit)」や、質の低い研究でもとにかく数を稼ごうとする動きを助長する可能性がある 28。
さらに深刻なのは、研究不正行為との関連である。高IFジャーナルへの掲載が極めて高い評価に繋がるという認識が、一部の研究者に対して、データの捏造、改ざんといった不正行為に手を染める誘惑となる危険性がある 26。実際に、国内外で、論文発表のプレッシャーや高IFジャーナルへの掲載願望が背景にあるとされる研究不正事例が報告されている 5。日本においても、論文の捏造や改ざんが発覚し、その背景に過度な業績主義があったとされるケースは後を絶たない 32。58では、高IFジャーナルと捏造の多さの間に正の相関関係があるという研究結果も指摘されている。STAP細胞事件のような国際的にも注目された日本の事例も、このような文脈で語られることがある 34。
また、IF至上主義は、高IFジャーナルに掲載された論文の内容を盲信する危険性も孕んでいる 26。ノーベル賞受賞者である本庶佑氏が「Natureに載っている論文でも9割は怪しい研究」と発言したとされるように 26、高IFジャーナルだからといって、その内容が全て真実であるとは限らない。しかし、IFの権威を過度に信奉するあまり、批判的な吟味を怠り、誤った情報や再現性のない研究成果を鵜呑みにしてしまうリスクがある。これは科学の進歩にとって極めて有害である。
5.4. 研究者個人への影響
IF至上主義は、研究者個人に対しても具体的な負の影響を及ぼす。
- 学位取得の遅延: 高IFジャーナルは一般的に査読プロセスが長く、論文がアクセプトされるまでに長期間を要する傾向がある 26。特に博士課程の学生など、限られた期間内に業績を上げる必要がある研究者にとっては、これが学位取得の遅れに繋がる可能性がある。
- 偏った研究観の形成: 指導教員や研究室の雰囲気によって、「高IFジャーナルこそが全てであり、低IFジャーナルに価値はない」といった偏った価値観が刷り込まれ、IFの低いジャーナルやそこで活動する研究者を見下すような歪んだ研究観を形成してしまう危険性がある 26。
- 精神的プレッシャーとキャリアへの不安: 常にIFを意識し、高IFジャーナルへの掲載を目指さなければならないというプレッシャーは、研究者にとって大きな精神的負担となる。また、IFに左右される評価システムは、キャリアパスに対する過度な不安感を生み出し、研究活動への意欲を削ぐことにも繋がりかねない。
このように、IF至上主義は、研究活動の目的を歪め、研究の質を低下させ、さらには研究不正の温床となり得るなど、学術界の健全な発展を脅かす多くの問題点を内包している。IFが高いジャーナルが注目を集めやすいという事実はあるものの、それが自動的に個々の論文の質の高さや研究者の能力の優秀さを保証するものではないという認識を、研究者自身も、そして研究を評価する側も強く持つ必要がある。高IFジャーナルへの掲載という「結果」に目を奪われるあまり、科学的探究という「プロセス」の重要性や、多様な研究アプローチの価値が見失われてはならない。IFの呪縛から解き放たれ、より本質的な価値基準に基づいた研究活動が奨励される環境の構築が求められている。
6. 研究評価の新しい波:国内外の改革動向
インパクトファクター(IF)を巡る問題意識の高まりとともに、研究評価のあり方を見直そうとする動きが国内外で活発化している。IF偏重の評価システムから脱却し、より多角的で責任ある研究評価(Responsible Research Assessment, RRA)を実現するための国際的な提言や、代替的な評価指標の模索が進められている。
6.1. 国際的な改革への呼びかけ
研究評価改革の国際的な潮流において、特に重要な役割を果たしているのが、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言(DORA)」と「ライデン・マニフェスト」である。
- 研究評価に関するサンフランシスコ宣言(DORA: San Francisco Declaration on Research Assessment):
2012年に米国細胞生物学会(ASCB)の年次大会で提唱されたDORAは、研究評価の改善を目的とした世界的なイニシアチブである 8。その中核的な勧告は、IFのようなジャーナルベースの指標を、個々の研究論文の質、個々の科学者の貢献度、あるいは採用、昇進、資金提供の決定における代理的な尺度として用いないことである 5。DORAは、論文の科学的内容が、掲載雑誌のIFや知名度よりもはるかに重要であると強調し、研究論文だけでなく、データセットやソフトウェアを含むあらゆる研究成果の価値と影響を考慮し、政策や実務への影響といった質的な指標を含む幅広い影響指標を評価に取り入れることを推奨している 36。 - ライデン・マニフェスト(Leiden Manifesto for Research Metrics):
2015年に発表されたライデン・マニフェストは、研究評価における計量書誌学的指標の責任ある使用のための10の原則を提言している 12。これらの原則には、「定量的評価は、専門家による定性的評価を支援するものであるべき」「研究機関、グループ、または研究者の研究ミッションに照らしてパフォーマンスを測定する」「地域的に関連性の高い研究における卓越性を保護する」「データ収集と分析プロセスを開かれた、透明で、単純なものに保つ」などが含まれる 12。ライデン・マニフェストは、IFのような単一の指標に依存するのではなく、研究の文脈や多様性を考慮した評価の重要性を訴えている。
これらの国際的な提言は、IFを中心とした従来の評価方法が持つ限界と弊害を克服し、より公正で建設的な研究評価システムを構築するための重要な指針となっている。
6.2. 日本における動向と課題
国際的な研究評価改革の動きに対し、日本国内の対応はこれまで比較的緩やかであった。DORAへの署名機関数は、国際的に見ても少ない状況が続いていた 40。その背景には、日本の大学評価においては伝統的にピアレビューが重視されてきたことや、国立大学法人化後も教員の業績評価が必ずしも直接的な人事考課とは強く結びついてこなかったことなどが指摘されている 41。
しかし、近年では日本国内でも変化の兆しが見られる。特筆すべきは、2023年12月に東京大学が日本の大学として初めてDORAに署名したことである 37。これは、日本の学術界における研究評価のあり方に対する意識の変化を示す象徴的な出来事であり、他の大学や研究機関への波及効果も期待される 37。文部科学省や日本学術会議などにおいても、研究評価のあり方に関する議論は継続的に行われており、オープンサイエンスの推進と連携した新しい評価軸の検討なども進められている 5。
それでもなお、DORAやライデン・マニフェストの理念を具体的な評価制度に落とし込み、学術界全体に浸透させていくには、多くの課題が残されている。既存の評価文化や制度を変革することの難しさ、そして新しい評価手法を導入・運用するためのリソースや専門知識の確保などが、今後の課題として挙げられる。
6.3. 代替指標の模索
IFの限界を補い、より多角的な研究評価を実現するために、様々な代替指標が提案され、利用され始めている。
- h-index:
2005年に物理学者のJ. E. Hirschによって提案されたh-indexは、研究者個人の研究生産性と被引用数のバランスを示す指標である 43。ある研究者のh-indexが「h」であるとは、その研究者が発表した論文のうち、h回以上引用された論文がh報あることを意味する 5。計算が比較的簡便であり、論文数だけでなくその影響力も考慮できる点が利点とされる 46。しかし、h-indexも万能ではなく、研究分野による引用文化の違い、研究キャリアの長さによる影響、共著者数の多い論文の扱いの難しさ、少数の極めて被引用数の多い論文の影響を十分に反映できないなどの限界も指摘されている 43。 - Altmetrics(オルタメトリクス):
Altmetricsは、「alternative metrics」の略で、従来の引用数ベースの評価とは異なり、学術論文やその他の研究成果(データセット、ソフトウェア、プレゼンテーション資料など)が、オンライン上でどれだけ注目され、議論され、利用されているかを測定する新しい指標群である 17。具体的には、ニュース記事での言及、ブログやX(旧Twitter)、Facebookなどのソーシャルメディアでの共有やコメント、Mendeleyなどの文献管理ツールでのブックマーク数、論文のダウンロード数などが含まれる 48。Altmetricsの利点は、研究成果の影響を迅速に把握できること、学術コミュニティ内部だけでなく、一般社会や政策立案者など、より広範なステークホルダーからの注目度を可視化できる可能性があることである 48。代表的なツールとして、Altmetric.comが提供する「Altmetric Attention Score(カラフルなドーナツ状の図で示されることが多い)」や、Plum Analyticsが提供するPlumX Metricsなどがある 51。一方で、Altmetricsはあくまで「注目度」を測るものであり、必ずしも研究の「質」や「重要性」を直接示すものではない点、ポジティブな注目とネガティブな注目の区別が難しい点、オンライン上での活動に偏るため操作される可能性もある点などが課題として挙げられる 48。 - 論文単位の指標(Article-Level Metrics – ALMs):
ALMsは、ジャーナル全体の平均的な影響力(IFなど)ではなく、個々の論文が持つ影響力や価値を直接的に評価しようとするアプローチである 10。これには、個々の論文の被引用数、ダウンロード数、オンラインでの閲覧数、ソーシャルメディアでの言及数などが含まれる。ALMsは、研究成果をよりきめ細かく評価できる可能性を秘めているが、指標が利用可能なデータベースに論文が収録されている必要があることや、引用の文脈(肯定的か否定的かなど)が不明確であること、新しい論文の評価には依然として時間が必要であることなどの限界も存在する 53。
これらの代替指標は、それぞれに利点と限界を抱えており、IFに完全に取って代わる万能な解決策とは言えない。しかし、これらの指標を組み合わせ、研究の文脈や目的に応じて適切に活用することで、IF偏重の評価から脱却し、より多角的でバランスの取れた研究評価へと移行する道筋が見えてくる。この動きは、研究の価値を単一の数字で測ろうとする単純化から、研究活動の多様性や複雑性をより深く理解しようとする学術界の成熟を示しているのかもしれない。
以下に、インパクトファクターと主要な代替指標を比較した表を示す。
表2: インパクトファクターと主要な代替指標の比較
| 指標名 (Metric Name) | 評価対象 (Evaluation Target) | 主な測定内容 (Primary Measurement) | 主な利点 (Key Advantages) | 主な欠点/限界 (Key Disadvantages/Limitations) |
| インパクトファクター (IF) | ジャーナル | 過去2年間の論文の平均被引用数 1 | ジャーナル間の相対的影響力の簡便な比較(同一分野内) 3 | 分野差大、引用分布の歪み、操作可能性、個々の論文/研究者評価への誤用 5 |
| h-index | 研究者 | 論文数と各論文の被引用数のバランス 43 | 研究者の生産性と影響力を単一指標で表現、計算の簡便さ 46 | 分野差、キャリアステージの影響、共著者の扱い、質の高い論文が少なくてもhが高くなる可能性 43 |
| Altmetrics (例: Altmetric Attention Score) | 論文・研究成果 | オンライン上での注目度(SNS、ニュース、ブログ等) 48 | 影響の迅速な把握、学術界外への波及効果の可視化 48 | 「注目度」であり「質」ではない、肯定的/否定的注目の区別困難、操作可能性、分野差 48 |
| 論文単位の指標 (ALMs) | 論文 | 個々の論文の被引用数、利用状況等 53 | 個々の研究成果を直接的に評価 53 | データベース依存、引用理由の不明確さ、新しい論文の評価には時間 53 |
この表からもわかるように、それぞれの指標は異なる側面を捉えており、研究評価の際には、これらの特性を理解した上で、目的に応じて使い分ける、あるいは組み合わせて用いることが重要である。IFの「罪」は、その指標自体よりも、むしろそれを絶対視し、不適切に用いてきた人間側の問題であるとも言える。
7. 提言:インパクトファクターと研究の未来
インパクトファクター(IF)を巡る功罪の議論と、国内外の研究評価改革の動向を踏まえ、今後の研究と研究評価のあり方についていくつかの提言を行いたい。これらの提言は、IFという指標に振り回されることなく、より健全で生産的な研究環境を醸成するための一助となることを目指すものである。
IFの限定的・補助的な利用の推奨
まず基本として、IFは学術雑誌の特性や傾向を理解するための一つの参考情報として、限定的かつ補助的に利用するに留めるべきである。DORAの勧告にもあるように、個々の研究論文の質や研究者個人の貢献度を評価する際に、IFを主要な、あるいは唯一の代理指標として用いるべきではないという原則を徹底する必要がある 5。IFの数値を見る際には、その算出方法の限界(分野差、引用分布の歪み、操作可能性など)を常に意識し、批判的な視点を持つことが求められる。
研究評価システムの多角的・総合的アプローチへの移行
IF偏重の評価から脱却し、より公正で質の高い研究を奨励するためには、研究評価システム全体を多角的かつ総合的なアプローチへと移行させる必要がある。
- 研究内容の質を重視したピアレビューの強化: 論文の新規性、独創性、方法論の妥当性、結果の信頼性、そして再現性といった、研究内容そのものの質を評価するピアレビューの機能を一層強化することが不可欠である。
- 多様な研究成果の評価: 伝統的な学術論文だけでなく、書籍、研究データセット、ソフトウェア、特許、さらには社会貢献活動や教育への貢献など、研究者が生み出す多様なアウトプットを評価の対象とすることが望ましい。
- 定量的指標と定性的評価のバランス: ライデン・マニフェストの第一原則が示すように、定量的指標はあくまで専門家による定性的評価を「支援」するものであり、両者をバランス良く組み合わせることが重要である 12。数値データだけに頼るのではなく、研究の文脈や意義を深く理解しようとする姿勢が求められる。
- 研究分野の特性の考慮: 研究分野によって研究の進め方、成果の形態、引用の慣習などが大きく異なるため、画一的な評価基準を適用するのではなく、各分野の特性を十分に考慮した評価基準を設定する必要がある。ライデン・マニフェストの第六原則もこの点を強調している 12。
各主体への具体的な行動提案
研究評価改革は、研究エコシステムに関わる全てのステークホルダーの協力なしには達成できない。
- 研究者: IF至上主義的な風潮に流されることなく、自らの研究テーマの重要性や社会的な意義を信じ、本質的な研究価値を追求する姿勢を貫くべきである。また、IF以外の多様な評価指標(h-index、Altmetrics、論文単位の指標など)についても理解を深め、自身の業績や研究のインパクトを多角的にアピールする能力を養うことも重要となる。
- 大学・研究機関: DORAやライデン・マニフェストの理念に沿った研究評価制度の改革に積極的に取り組むべきである。特に、若手研究者がIFのプレッシャーに過度に晒されることなく、自由な発想で挑戦的な研究に取り組めるような支援策や評価制度を構築することが求められる 55。評価プロセスの透明性を高め、研究者が納得感を持てるような評価の実施も不可欠である。東京大学のDORA署名 42 は、こうした動きの先駆けとなることが期待される。
- 資金配分機関: 研究助成の審査において、申請者の過去の論文掲載ジャーナルのIFに偏重した評価を見直し、研究提案そのものの科学的メリット、独創性、実現可能性、そして期待される学術的・社会的インパクトを重視する審査へと転換する必要がある 4。特に、萌芽的な研究や分野横断的な研究、社会課題の解決に資する研究など、多様な価値を持つ研究が適切に評価され、支援されるような仕組み作りが求められる。
- 学術出版社: IFの値を過度に宣伝するような行為を控え、ジャーナルの特性を多角的に示す多様な指標(編集・出版プロセスにかかる時間、アクセプト率、論文単位のメトリクスなど)を積極的に提供すべきである 36。また、自己引用の強要や引用カクテルのようなIF操作に繋がる行為を厳しく戒め、責任ある出版慣行を推進する役割を担う必要がある 4。
オープンサイエンスの推進と研究評価との連携
研究データの公開・共有、研究プロセスの透明化といったオープンサイエンスの動向は、研究評価のあり方とも密接に関連している。研究成果だけでなく、その基盤となるデータや方法論がオープンにされ、検証可能となることは、研究の信頼性と再現性を高める上で極めて重要である。このようなオープンな研究活動が、研究評価においても適切に認識され、奨励されるような文化を醸成していく必要がある 57。
これらの提言は、IFという単一の指標が支配する現状から、より多様で、本質的で、公正な研究評価システムへと移行するための道筋を示すものである。その実現には時間がかかり、多くの困難も伴うであろうが、学術研究の健全な発展のためには避けて通れない課題である。重要なのは、評価のための評価に陥るのではなく、研究そのものの価値をいかに見出し、育んでいくかという視点を常に持ち続けることである。
8. おわりに
本記事では、研究者にとって馴染み深いと同時に、その功罪を巡って長年議論が絶えないインパクトファクター(IF)について、その定義、歴史、利点、そして数多くの問題点を国内外の文献を基に解説し、現状のIF至上主義がもたらす歪みと、それに対する改革の動きを概観した。
IFは、元来、学術雑誌の相対的な影響力を測るための一つの指標として開発され、特定の文脈においては一定の有用性を持つ。しかし、その簡便さゆえに、いつしか個々の論文の質や研究者個人の能力を測る万能の尺度であるかのように誤用・過信されるようになり、学術界に多くの負の影響をもたらしてきた。研究の本質的な価値よりも掲載ジャーナルのIFが優先される風潮、過度な出版プレッシャー、「Publish or Perish」文化の助長、さらには研究不正の誘因となり得る危険性など、その「罪」は決して軽くない。
重要なのは、IFという指標そのものが絶対的な悪なのではなく、それをどのように解釈し、どのように利用するのかという人間側、システム側の問題であるという認識である。IFの限界を正しく理解し、その利用を本来の目的に即した限定的なものに留め、研究評価においては、DORAやライデン・マニフェストが提唱するように、研究内容そのものの質、多様な研究成果、そして分野の特性を考慮した多角的かつ総合的なアプローチを採用することが求められる。
学術研究の本来の目的は、未知の探求、真理の発見、新たな知識の創造、そしてそれらを通じた社会への貢献や知の継承にあるはずである。IFという一つの指標に研究活動が過度に左右される現状は、これらの崇高な目的を見失わせかねない。
インパクトファクターを巡る議論は、単なる一指標の是非を超えて、我々がどのような学術研究を価値あるものとし、どのようにしてそれを育んでいくべきかという、より根源的な問いを投げかけている。この問いに対する完璧な答えは未だ見出されていないかもしれないが、学術界に関わる全ての者が、IFの功罪を冷静に見極め、指標に振り回されることなく、真に価値ある研究とは何かを問い続け、健全な研究文化を醸成していくための不断の議論と努力を重ねていくことが、今まさに求められている。この小さな記事が、その一助となれば幸いである。
引用文献
- インパクトファクターの調べ方。学術論文の評価基準と計算方法を徹底解説, 5月 8, 2025にアクセス、 https://letterpress.minibird.jp/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%AA%BF%E3%81%B9%E6%96%B9/
- Bibliometrics and Citation Tracking: Impact Factor – Oxford LibGuides, 5月 8, 2025にアクセス、 https://libguides.bodleian.ox.ac.uk/c.php?g=422992&p=2890486
- Understanding Impact Factor and What Makes a Good Score – Jenni AI, 5月 8, 2025にアクセス、 https://jenni.ai/blog/whats-a-good-impact-factor
- Understanding Impact Factor – Rovedar Publication Services, 5月 8, 2025にアクセス、 https://ps.rovedar.com/understanding-impact-factor/
- core.ac.uk, 5月 8, 2025にアクセス、 https://core.ac.uk/download/pdf/56654781.pdf
- LibGuides: Journal Evaluation & Measuring Author Impact: Journal Metrics, 5月 8, 2025にアクセス、 https://jefflibraries.libguides.com/JournalEvaluation/AuthorImpact/JournalMetrics
- Impact factors – Assessing Journal Quality – Libraries at Boston College – Research Guides, 5月 8, 2025にアクセス、 https://libguides.bc.edu/journalqual/impact
- www.jstage.jst.go.jp, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.jstage.jst.go.jp/static/files/ja/pub_20230905_jifseminar_document.pdf
- インパクトファクター – Wikipedia, 5月 8, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC
- Making an impact: Pros and cons to impact factor – Bitesize Bio, 5月 8, 2025にアクセス、 https://bitesizebio.com/25124/making-an-impact-pros-and-cons-to-impact-factor/
- www.cshe.nagoya-u.ac.jp, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/journal/no6/10.pdf
- Leiden Manifesto – Wikipedia, 5月 8, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Leiden_Manifesto
- ジャーナル影響度指標(インパクトファクター) – Hokkaido University Library – 北海道大学, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.lib.hokudai.ac.jp/support/journal_inpact_facter/
- How do I find a journal’s Impact Factor? – Mayo Clinic Library Answers, 5月 8, 2025にアクセス、 https://libraryanswers.mayo.edu/faq/395668
- SAE Earns New Impact Factors from Clarivate Analytics’ Institute of Scientific Information, 5月 8, 2025にアクセス、 https://sae.org/blog/2024-impact-factors
- 【2024年版】インパクトファクターとは?調べ方や目安、注意点をわかりやすく解説!, 5月 8, 2025にアクセス、 https://raku-con.com/column/IF
- インパクトファクターとは?調べ方、評価指標、注意点を徹底解説 – Readable’s Compass, 5月 8, 2025にアクセス、 https://compass.readable.jp/2024/12/26/post-420/
- Impact Factors – Graduate Research Portal – LibGuides at University of Lethbridge, 5月 8, 2025にアクセス、 https://library.ulethbridge.ca/gradresearch/impact-factors
- Impact Factor: What It Is and Why It Matters? – Ref-n-Write, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.ref-n-write.com/blog/impact-factor-what-it-is-and-why-it-matters/
- Understanding Impact Factors: Evaluating Journal Influence – Falcon Scientific Editing, 5月 8, 2025にアクセス、 https://falconediting.com/en/blog/understanding-impact-factors-evaluating-journal-influence/
- インパクトファクターとは?概要と注意点を解説, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.med-english.com/news/vol153.php
- Journal Impact Factor – Effective Database Searching – Guides at Mayo Clinic, 5月 8, 2025にアクセス、 https://libraryguides.mayo.edu/effectivedatabasesearching?p=1868134
- The Impact Factor Debate: Assessing Journal Prestige and …, 5月 8, 2025にアクセス、 https://eikipub.com/index.php/learning-resources/the-impact-factor-debate-assessing-journal-prestige-and-research-quality
- The Journal Impact Factor: A Brief History, Critique, and Discussion of Adverse Effects, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/364826182_The_journal_impact_factor_A_brief_history_critique_and_discussion_of_adverse_effects
- The misalignment of incentives in academic publishing and implications for journal reform | PNAS, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2401231121
- 【論文】インパクトファクター至上主義の3つの問題点 – 札幌デンドライト, 5月 8, 2025にアクセス、 https://sapporodendrite.com/?p=6101
- IU researchers co-author study challenging ‘publish or perish’ culture, call for overhaul of academic publishing: College of Arts + Sciences – News at IU, 5月 8, 2025にアクセス、 https://news.iu.edu/college/live/news/45216-iu-researchers-co-author-study-challenging-publish
- Publish or perish – Wikipedia, 5月 8, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Publish_or_perish
- ハゲタカジャーナルに引っかからない秘訣 – 学術英語アカデミー – エナゴ, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.enago.jp/academy/the-perils-of-predatory-publishing-2/
- 研究界でのインパクトファクターの役割とは | ターンイットイン, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.turnitin.jp/blog/what-is-the-big-deal-about-impact-factor-jp
- 学術論文の大量出版――信頼性と誠実さの問題 – フォルテ英文校正, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.forte-science.co.jp/articles/edita-no-shiten/1297-2024-01-16-02-10-19.html
- 医学・生命科学における研究不正の現状と研究公正に向けた取り組み, 5月 8, 2025にアクセス、 https://kindai.repo.nii.ac.jp/record/19175/files/AN00063584-20171220-9A.pdf
- 研究不正ー事例の分析から対策を考える, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.jsps.go.jp/file/storage/general/j-kousei/data/2016_2.pdf
- Publish and Perish – Issues in Science and Technology, 5月 8, 2025にアクセス、 https://issues.org/perspective-publish-and-perish/
- San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), 5月 8, 2025にアクセス、 https://sfdora.org/
- The San Francisco Declaration on Research Assessment – PMC, 5月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3701204/
- 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」への署名 | 東京大学, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z0701_00004.html
- 研究評価改革に関する国際動向, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.jst.go.jp/osirase/2023/pdf/20240229-2.pdf
- Responsible approach to research evaluation • City St George’s, University of London, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.citystgeorges.ac.uk/about/governance/policies/responsible-approach-to-research-evaluation
- 研究開発機関の評価 – 文部科学省, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.mext.go.jp/content/20210226-mxt_chousei02-000012849_5.pdf
- CA2005 – DORAから「責任ある研究評価」へ:研究評価指標の新た …, 5月 8, 2025にアクセス、 https://current.ndl.go.jp/ca2005
- Regarding the Signing of the San Francisco Declaration on …, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.u-tokyo.ac.jp/en/about/dora.html
- The Journal Impact Factor and alternatives | ZB MED – PUBLISSO, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.publisso.de/en/advice/publishing-advice-faqs/the-journal-impact-factor-and-alternatives
- The h-Index: Understanding its predictors, significance, and criticism – PMC, 5月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10771139/
- Calculate your h-index – UQ Library guides – The University of Queensland, 5月 8, 2025にアクセス、 https://guides.library.uq.edu.au/for-researchers/h-index
- 研究の質と量をバランスよく評価するh-index, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.med-english.com/news/vol33.php
- h-indexとは何か、その定義と計算方法について詳しく解説, 5月 8, 2025にアクセス、 https://letterpress.minibird.jp/h-index%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B/
- altmetrics(オルトメトリクス)の意味: 論文の影響度をWebでの反応で評価する | 学術情報発信ラボ, 5月 8, 2025にアクセス、 https://letterpress.minibird.jp/altmetrics%EF%BC%88%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%EF%BC%89-%E8%AB%96%E6%96%87%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E5%BA%A6%E3%82%92web%E3%81%AE%E5%8F%8D%E5%BF%9C/
- 論文を取り上げたニュース報道や読者のツイートが分かる、Altmetric(オルトメトリック)の活用法, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.wiley.co.jp/blog/pse/p_34984/
- Measure Your Research Impact: Altmetrics, 5月 8, 2025にアクセス、 https://guides.lib.unc.edu/measure-impact/alt-metrics
- Beyond the Impact Factor: Alternative Metrics for Measuring Research Impact in 2024, 5月 8, 2025にアクセス、 https://editverse.com/beyond-the-impact-factor-alternative-metrics-for-research-in-2024/
- Altmetrics – Research Impact at Purdue, 5月 8, 2025にアクセス、 https://guides.lib.purdue.edu/c.php?g=1387025&p=10266254
- Article Level Metrics – Research Metrics – LibGuides at University of Hong Kong, 5月 8, 2025にアクセス、 https://libguides.lib.hku.hk/researchmetrics/article-metrics
- Journal and Article-level Metrics – Research Impact – Resource Guides, 5月 8, 2025にアクセス、 https://libraryguides.umassmed.edu/research_impact/impact_factor
- DORA to Launch Practical Guide to Responsible Research Assessment, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.socialsciencespace.com/2025/04/dora-to-launch-practical-guide-to-responsible-research-assessment/
- Blog – Leiden manifesto for research Metrics, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.leidenmanifesto.org/blog.html
- 研究開発評価を巡る国内外の状況 – 文部科学省, 5月 8, 2025にアクセス、 https://www.mext.go.jp/content/20221114-mxt_chousei02-000025612_4-3-1_2.pdf
- インパクトファクター至上主義の弊害 – ScienceTalks, 5月 8, 2025にアクセス、 https://sciencetalks.org/ja/impact-factor-supremacist/