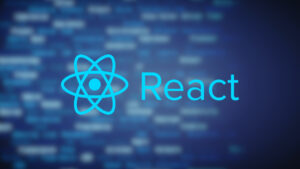I. はじめに
A. 「レイテンシ」って何?~インターネットの「待ち時間」を理解しよう~
インターネットを使っていると、ウェブページがなかなか表示されなかったり、オンラインゲームのキャラクターが思い通りに動かなかったりすることがあります。このような「待ち時間」や「反応の遅さ」の背景には、「レイテンシ」というIT用語が深く関わっています。
レイテンシとは、簡単に言うと、ユーザーが何か操作をしてから、その結果が画面に表示されるまでの「通信にかかる待ち時間」や「遅延時間」のことです 1。例えば、ウェブサイトのリンクをクリックしてから、次のページが表示されるまでのわずかな時間もレイテンシの一種です 1。この時間が短ければ短いほど、私たちはストレスを感じることなく、快適に情報にアクセスしたり、サービスを利用したりできます 1。
ITの世界、特にインターネットサービスにおいては、この「待ち時間」がサービスの使いやすさ、つまりユーザーエクスペリエンス(UX)や顧客満足度に直接影響を与えるため、非常に重要な指標とされています 4。技術的な数値でありながら、その影響は私たちの「体感時間」や心理状態にまで及ぶのです。例えば、「このサイトはいつも表示が速いな」と感じれば好印象を持ちますが、「また遅いな」と感じれば、そのサービス自体への評価が下がってしまうかもしれません 4。このように、レイテンシは単なる技術的な遅延ではなく、私たちのサービスに対する印象や満足感を左右する、人間的で心理的な側面も持っているのです。IT初学者の方にとっては、多くの専門用語に戸惑うかもしれませんが、レイテンシを「体感的な待ち時間」と捉えることで、より身近な問題として理解しやすくなるでしょう。
B. なぜIT初学者がレイテンシを知っておくべきなの?
では、なぜITを学び始めたばかりの方が、この「レイテンシ」という概念を知っておく必要があるのでしょうか。その理由は、私たちの日常生活や、これからのIT業界での活動に密接に関わってくるからです。
まず、オンラインゲームでのキャラクターの動きの遅れ(ラグ)、ビデオ会議での映像や音声の途切れ、動画サイトでの読み込みの遅さといった、日常生活で体験するインターネットの「遅い」「固まる」といった問題の多くに、レイテンシが原因の一つとして潜んでいます 6。レイテンシを理解することで、これらの問題がなぜ起きるのか、その一端を掴むことができます。
また、IT業界で働く上では、ウェブサイトやアプリケーションがどれだけ快適に動作するか(パフォーマンス)を理解するための基礎知識となります 8。将来、ウェブサイトを作ったり、システムを開発したりする際には、このレイテンシをいかに小さくするかが、利用者にとって使いやすいサービスを提供するための重要な鍵となります。
さらに、レイテンシとその測定方法を知ることは、インターネット利用時のトラブル解決のヒントを得たり、より快適なインターネット回線やプロバイダーを選ぶ際の判断材料になったりもします 10。つまり、レイテンシの知識は、私たちがITサービスの単なる消費者から一歩進んで、その仕組みを理解し、より賢くIT技術と付き合っていくための基本的な視点を提供してくれるのです。この理解は、将来的にITシステムの開発や運用に携わる際に、ユーザーにとって本当に価値のあるサービスとは何かを考える上での土台となるでしょう。技術への興味を深め、より能動的に学習に取り組むきっかけにも繋がるはずです。
II. レイテンシとは?~もっと詳しく知ろう~
A. レイテンシの正確な定義:データが届くまでの時間
レイテンシとは、より正確には、データ転送のリクエスト(要求)を出してから、実際にデータが送られてくるまで、あるいはサーバーでの処理が完了して応答が返ってくるまでに生じる「時間的な遅延」を指します 1。
具体的には、データのかたまりである「パケット」が、あなたのパソコンやスマートフォン(送信元)から、ウェブサイトのデータが置かれているサーバー(宛先)まで移動するのにかかる時間と考えることができます 6。多くの場合、リクエストを送信してからサーバーからの応答が完全に返ってくるまでの往復時間(RTT: Round Trip Time)を指してレイテンシと呼ぶことが一般的です 6。
この遅延時間が短いほど「レイテンシが低い(小さい)」と表現し、通信が速く快適であることを意味します。逆に、遅延時間が長いほど「レイテンシが高い(大きい)」と表現し、通信が遅くストレスを感じやすい状態を示します 14。
レイテンシは、単一の要因で決まるわけではありません。リクエストの送信、サーバー側でのデータ処理、そして処理結果(レスポンス)の返信という一連のプロセスの合計時間であり、これらの各段階で遅延が発生する可能性があります。特に、初めてウェブサイトにアクセスする際には、ウェブサイトのアドレスを実際のサーバーのIPアドレスに変換する「DNSルックアップ」、安全な通信経路を確立するための「TCPハンドシェイク」や「TLSネゴシエーション」といった、いわば「通信の準備時間」もレイテンシに含まれます 8。これらの処理はユーザーからは直接見えませんが、体感するレイテンシ、特に初回のアクセス時の「待たされる感じ」に大きく影響を与えるのです。普段何気なく行っているクリック操作の裏側で、このような複数のステップが実行されていることを知ると、なぜ特定の状況で遅延が大きくなるのか、その理由をより深く理解できるようになります。
B. レイテンシの単位:ミリ秒(ms)ってどのくらい?
レイテンシの大きさを表す際には、通常「ミリ秒(ms)」という単位が用いられます 5。1ミリ秒は、1秒の1000分の1という非常に短い時間です 13。
この「ミリ秒」という単位は、日常生活ではあまり馴染みがなく、その短さを具体的にイメージするのは難しいかもしれません。そこで、人間の反応速度と比較してみましょう。例えば、人間がまばたきをするのにかかる時間は、平均で約100ミリ秒から150ミリ秒と言われています 6。つまり、レイテンシの値が50msであれば、まばたきよりも速い応答速度ということになりますし、200msであれば、まばたきよりも遅い反応ということになります。このように、非常に小さな単位であるミリ秒も、人間の体感と比較することで、その数値が持つ意味や、インターネット利用時の快適さにどれほど影響を与えるのかを具体的にイメージしやすくなります。
C. 「Ping値」とレイテンシの関係:Pingはレイテンシを測る道具
レイテンシについて調べていると、「Ping値(ピンち、またはピングち)」という言葉を目にすることがよくあります。このPing値とレイテンシは、非常によく似た意味で使われますが、厳密には少し異なります。
「Ping」とは、特定の相手(例えば、ウェブサイトのサーバー)との間でネットワークが正常に繋がっているかを確認したり、その相手からの応答時間を測定したりするためのコマンド(コンピューターへの命令)またはツールのことです 7。このPingコマンドを実行すると、データが相手に届いてから自分の元に戻ってくるまでの往復時間(RTT)が、例えば「time=25ms」のように表示されます。この表示された応答時間の数値を「Ping値」と呼びます。
そして、このPing値が、レイテンシの具体的な数値として扱われるのが一般的です 6。つまり、Ping値はレイテンシ(通信の遅延時間という現象そのもの)を測定し、数値として可視化したものの一つと考えることができます 7。
IT初学者の方は、「レイテンシ」と「Ping値」がしばしば同じ意味で使われること 6 に戸惑うかもしれませんが、「レイテンシ」が遅延時間という現象そのものを指し、「Ping値」はその現象を測るための一つの道具(Pingコマンド)を使って得られた測定結果である、という区別を頭の片隅に置いておくと、技術的な解説を読む際に混乱を避けやすくなります。用語の正確な使い分けを理解することは、今後の学習において非常に重要です。
D. レイテンシと「帯域幅(スループット)」の違い:道路の広さと車の速さで例えると?
レイテンシと共によく聞くネットワーク性能の指標に「帯域幅(たいきはば)」や「スループット」があります。これらはレイテンシと混同されやすいのですが、意味するものが異なります。
レイテンシが「時間」、つまり「応答速度」を表すのに対し、帯域幅やスループットは「量」、つまり「単位時間あたりに転送できるデータ量」を示します 1。
この違いを理解するために、よく使われる例えが「道路と車」です。
- 帯域幅(スループット):道路の「広さ」や「車線の数」に例えられます。道が広ければ広いほど(帯域幅が広ければ広いほど)、一度にたくさんの車が通れる(大量のデータを送受信できる)ことになります。
- レイテンシ:道路を走る車の「速さ」や、目的地に着くまでの「信号の数や渋滞の状況」に例えられます。
いくら道路が広くても(帯域幅が広くても)、車の速度が遅かったり(レイテンシが高かったり)、途中に信号がたくさんあったり渋滞していたりすれば、目的地に到着するまでに時間がかかってしまいます 1。逆に、道が狭くても(帯域幅が狭くても)、車が非常に速く、信号も渋滞もなければ(レイテンシが低ければ)、比較的早く目的地に着けるかもしれません。
別の例えでは、水道管に例えることもできます。帯域幅は「水道管の太さ」、レイテンシは「蛇口をひねってから実際に水が出てくるまでの時間」です。どんなに太い水道管(高帯域幅)でも、蛇口をひねってから水が出てくるまでに時間がかかってしまっては(高レイテンシ)、すぐに水を使うことはできません。
このように、レイテンシと帯域幅は、どちらもインターネットの快適さに関わる重要な要素ですが、それぞれ異なる側面を表しています。両者の違いをしっかり理解することが、ネットワークの性能を正しく評価する第一歩となります。このアナロジーを深く理解することで、単に「違うもの」と覚えるだけでなく、両者がどのように相互作用して体感速度に影響を与えるのかを把握することができます。
III. なぜレイテンシ測定が重要なの?
レイテンシが「通信の待ち時間」であることは分かりましたが、なぜこのレイテンシを測定し、気にかける必要があるのでしょうか。その重要性は、私たちのインターネット利用体験の質や、さらにはビジネスの成果にまで及ぶからです。
A. ウェブサイトやアプリの使い心地(ユーザーエクスペリエンス)への影響
レイテンシの高さは、ウェブサイトやアプリケーションの使い心地、すなわちユーザーエクスペリエンス(UX)に直接的な悪影響を与えます。レイテンシが高いと、ウェブページの読み込みに時間がかかったり、アプリケーションのボタンを押してもなかなか反応しなかったりといった事態が発生します 1。
このような体験は、利用者に大きなストレスや不満を与えます。結果として、利用者はそのウェブサイトから離脱してしまったり(いわゆる「直帰」)、アプリケーションをアンインストールしてしまったりする可能性が高まります 1。現代のインターネット利用者は非常にせっかちであり、少しの待ち時間も許容しづらくなっている傾向があります。
逆に、レイテンシが低く、応答が速いウェブサービスやモバイルアプリケーションは、利用者にとって快適で使いやすいため、成功に繋がりやすいと言えます 1。ユーザーエクスペリエンスの低下は、単に「使いにくい」という問題に留まりません。例えば、ECサイトであれば、ページの表示が遅いことで購入意欲が削がれ、カートに入れた商品を購入せずに離脱してしまう「カゴ落ち」による売上減少に繋がる可能性があります 5。また、サービスの反応が悪いと、そのサービスや提供企業に対するブランドイメージの低下を招くこともあります 4。さらに、ウェブサイトの表示速度は検索エンジンの評価にも影響するため(後述)、SEO(検索エンジン最適化)の観点からもレイテンシは無視できない要素なのです 11。このように、レイテンシは技術的な指標でありながら、ビジネスの機会損失やブランド価値、さらには集客戦略にまで波及する多層的な影響力を持っています。
B. こんな場面で困る!高レイテンシの影響例:
高レイテンシが具体的にどのような問題を引き起こすのか、いくつかの場面を例に見ていきましょう。
1. オンラインゲーム:操作が遅れる、カクカクする
オンラインゲームは、レイテンシの影響が最も顕著に現れる分野の一つです。レイテンシが高いと、プレイヤーがコントローラーで行った操作(例えば、キャラクターを動かす、攻撃する)が、ゲーム画面に反映されるまでに遅れが生じます 1。また、キャラクターが瞬間移動したり、カクカクした不自然な動きをしたり、ひどい場合には予期しない動作が発生することもあります。これは一般的に「ラグ」と呼ばれ、特に一瞬の判断や精密な操作が求められる対戦型のゲームなどでは、勝敗に直接影響を与える深刻な問題となります 6。オンラインゲーム、特に競技レベルのものは、プレイヤーとサーバー双方に非常に速い応答時間を要求するため 6、ミリ秒単位の遅延が致命的となるのです。この極端な例は、他のアプリケーションにおけるレイテンシの重要性を理解する上でも参考になります。
2. ビデオ会議:映像や音声が途切れる、遅れる
ビジネスシーンやプライベートで利用する機会が増えたビデオ会議も、レイテンシの影響を受けやすいアプリケーションです。レイテンシが高いと、相手の映像や音声が途切れたり、遅れて届いたりします 6。自分の発言が相手に届くまでに時間がかかると、会話のテンポが悪くなり、相手が意図せず話に割り込んでしまうような気まずい状況も生まれかねません 6。これにより、スムーズなコミュニケーションが阻害され、会議の効率が低下したり、重要な情報が正確に伝わらなかったりする可能性があります。ビデオ会議における高レイテンシは、単なる技術的な不具合ではなく、コミュニケーションの質そのものを低下させ、誤解やフラストレーションを生む原因となるのです。
3. 動画視聴:読み込みが遅い、再生が止まる
映画やドラマ、アニメなどの動画をインターネットで視聴する際も、レイテンシは快適さに影響します。特に高画質の動画を視聴しているときにレイテンシが高いと、映像の読み込みに時間がかかってなかなか再生が始まらなかったり、再生中に映像がカクカクしたり、突然再生が止まってしまったり(バッファリング)、音声だけが先行して映像が追いつかないといった現象が発生することがあります 7。
ただし、Netflixのようなビデオオンデマンド(VoD)サービスの場合、通常は再生開始前に動画データの一部をあらかじめ読み込んでおく「プリロード」または「バッファリング」という仕組みがあるため、ある程度のレイテンシ変動は吸収され、視聴中に問題を感じにくいこともあります 6。しかし、根本的にレイテンシが高すぎたり、インターネット回線の帯域幅(通信速度)が不足していたりすると、このバッファリングが追いつかず、やはり快適な視聴体験は損なわれてしまいます。特に、スポーツ中継やゲーム実況などのライブストリーミングでは、このバッファリングによる遅延吸収が難しいため、レイテンシの影響がよりシビアに現れやすい傾向があります 6。
C. 低レイテンシのメリット:快適なインターネット利用のために
これまで見てきたように、高レイテンシは様々な問題を引き起こしますが、逆にレイテンシが低いことには多くのメリットがあります。
まず、利用者にとっては、サービスがサクサクと快適に利用できるようになり、満足度が大幅に向上します 11。ウェブページの表示は一瞬で完了し、オンラインゲームではキャラクターが思い通りに動き、ビデオ会議では相手の表情や声がリアルタイムに伝わります。
サービス提供者にとっては、利用者の満足度向上は、サービスの継続利用や口コミによる新規顧客の獲得に繋がり、結果として収益向上に貢献します 11。また、オンラインゲームや動画配信サービスでは、遅延(時差)が限りなく少なくなることで臨場感が増し、より没入感のある体験を提供できるようになるため、利用者の定着率向上も期待できます 11。
さらに、ウェブサイトのページの読み込み時間が速くなることは、Googleなどの検索エンジンからの評価を高め、検索結果で上位に表示されやすくなる(SEOに良い影響を及ぼす)というメリットもあります 11。
ビジネス全般においては、社内システムやクラウドサービスの応答性が向上することで、従業員の生産性が上がり、より効率的な業務運営が可能になります 9。
これらのメリットは独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。例えば、低レイテンシによってユーザー満足度が向上すると、そのサービスはより多くの人に利用され、良い評判が広まります。これがサービス提供者の収益向上やブランド価値の向上に繋がり、その結果、さらなるサービス改善のための投資が可能になり、より一層低いレイテンシの実現へと繋がる、というような好循環を生み出す可能性を秘めているのです。この視点を持つと、レイテンシの改善は単なるコストではなく、将来への重要な投資であると理解できるでしょう。
IV. レイテンシが高くなるのはなぜ?主な原因を探る
レイテンシが高くなる、つまり通信に時間がかかってしまう原因は一つではありません。様々な要因が複雑に絡み合って発生します。ここでは、主な原因をいくつか見ていきましょう。
A. サーバーまでの物理的な距離:遠いほど時間がかかる
最も基本的で分かりやすい原因の一つが、データをやり取りする相手(例えばウェブサイトのサーバー)との「物理的な距離」です。データは光や電気信号として通信ケーブルの中を伝わりますが、どんなに速い光の速さであっても、距離が長ければ長いほど、信号が目的地に到達するまでに時間がかかってしまいます 1。
例えば、日本国内にあるサーバーにアクセスする場合と、アメリカやヨーロッパなど海外にあるサーバーにアクセスする場合とでは、後者の方が物理的な距離が格段に遠いため、一般的にレイテンシは高くなる傾向があります 4。光ファイバーケーブルの中を光が伝わる速度は1秒間に地球を約7周半すると言われていますが、それでも数千キロメートル、数万キロメートルという距離になれば、無視できない遅延が発生するのです 9。
この物理的距離は、レイテンシの最も根本的で、ある程度は避けられない要因と言えます。光速という物理法則の限界があるため、どんなに通信技術が進歩しても、距離による遅延を完全にゼロにすることはできません。この制約があるからこそ、後述するCDN(コンテンツデリバリーネットワーク)のような、ユーザーに近い場所にデータのコピーを配置して物理的距離を短縮する技術が重要になってくるのです。
B. ネットワークの混雑:道が混んでいると進めない
インターネット回線やネットワークは、多くの人や機器が共同で利用する「共有リソース」です。そのため、特定の時間帯に多くのユーザーが同時に大容量のデータ通信を行ったり(例えば、夜間に多くの人が動画を視聴したり、大きなファイルをダウンロードしたりする)、特定のウェブサイトにアクセスが集中したりすると、ネットワークが混雑し、いわゆる「渋滞」のような状態(専門用語では「輻輳(ふくそう)」と言います)が発生します 1。
道路が混雑していると車の進みが遅くなるのと同じように、ネットワークが混雑すると、データのかたまり(パケット)がスムーズに流れず、ルーターなどのネットワーク機器で処理待ちが発生し、結果としてレイテンシが増加します。特に、マンションなどで共有されているインターネット回線や、駅やカフェなどで提供されているフリーWi-Fiなどでは、利用者が集中する時間帯になると急に通信が遅くなったり、繋がりにくくなったりすることがありますが、これはネットワークの混雑が原因であることが多いです 19。ネットワークは共有リソースであり、その処理能力には限界があります。混雑は、この共有リソースに対する需要が供給(キャパシティ)を上回ったときに発生する典型的な現象であり、レイテンシの増加はその直接的な結果なのです。
C. 通信回線の種類と品質:光回線、無線LAN、LANケーブルなど
私たちがインターネットに接続するために利用している通信回線の種類やその品質も、レイテンシに大きく影響します。
現在、家庭用のインターネット回線として主流の「光ファイバー回線」は、光信号を使って高速にデータを伝送するため、一般的にレイテンシが低いとされています 1。一方、Wi-Fi(無線LAN)やスマートフォンのモバイルデータ通信(4G/5Gなど)といった「無線通信」は、電波を使ってデータをやり取りするため、壁などの障害物や、電子レンジなどの他の電化製品が発する電波との干渉、あるいは単純に電波が弱いといった理由で通信が不安定になりやすく、レイテンシが高くなることがあります 1。
また、パソコンを有線でルーターに接続する際に使う「LANケーブル」も、その規格が古いと通信速度が十分に発揮されず、レイテンシの悪化に繋がることがあります 7。例えば、「カテゴリ5(CAT5)」といった古い規格のLANケーブルを使用している場合は、より新しい「カテゴリ5e(CAT5e)」や「カテゴリ6(CAT6)」以上の規格のケーブルに交換することで、レイテンシが改善する可能性があります。
このように、通信の物理的な経路(伝送媒体)そのものが、レイテンシのベースラインを大きく左右します。ソフトウェア的な最適化だけでは超えられない物理的な制約が存在するため、ネットワーク環境を構築・選択する際には、この物理層の選択がいかに重要であるかを理解しておく必要があります。
D. ルーターやパソコン・スマホの性能
インターネットの出入り口となる「ルーター」や、実際にインターネットを利用する「パソコン」「スマートフォン」といった機器自体の性能も、レイテンシに影響を与える要因です。
ルーターの処理性能が低い場合や、ファームウェア(ルーターを制御するソフトウェア)が古い場合、あるいはルーターに接続されている機器の数が多すぎて処理能力の限界を超えているような場合には、データの処理に時間がかかり、レイテンシが増加することがあります 1。
同様に、パソコンやスマートフォン自体の性能、例えばCPU(中央処理装置)の処理速度が遅い、メモリ容量が不足している、OS(オペレーティングシステム)のバージョンが古い、あるいはバックグラウンドで多くの不要なソフトウェアが動作していてリソースを消費しているといった状況も、全体の応答速度を低下させ、結果としてレイテンシが高いと感じる原因になることがあります 5。
レイテンシは、単にインターネット回線だけの問題ではなく、通信の始点(あなたのデバイス)と終点(相手のサーバー)、そしてその経路の途中にあるルーターなど、エンドツーエンドの全ての機器の性能が相互に影響し合って決まります。どこか一つでも性能が低い「ボトルネック」となる箇所があれば、全体のレイテンシは悪化してしまうのです。
E. 経由する機器の数(ネットワークホップ)
私たちがインターネットで情報をやり取りする際、データは送信元から宛先まで一直線に届くわけではありません。多くの場合、途中で複数のルーターなどのネットワーク機器を経由して、バケツリレーのようにデータが転送されていきます。この経由するネットワーク機器のことを「ホップ(hop)」と呼びます。
データが目的地に到達するまでに経由するホップの数が多いほど、各機器でのデータチェックや次の転送先の決定といった処理時間が積み重なっていきます。一つ一つの機器での処理時間はごくわずかでも、経由する機器の数が多くなればなるほど、その遅延が蓄積され、全体のレイテンシが増加する原因となります 9。まさに「ちりも積もれば山となる」という言葉が当てはまる現象で、ネットワーク経路の複雑性がレイテンシに直接影響することを示しています。
F. その他(データ量、パケットサイズ、パケット損失など簡単に)
上記以外にも、レイテンシに影響を与える要因はいくつかあります。
- 一度に送受信するデータ量: 例えば、非常に大きなサイズのファイルをダウンロードしたり、高画質の動画をストリーミングしたりする場合など、一度に送受信するデータ量が多いと、単純にそのデータを送り終えるまでに時間がかかります。これは厳密にはレイテンシそのものではありませんが、体感として「遅い」「待たされる」と感じる原因になります 1。
- パケットサイズ: インターネットでデータが送られる際、データは「パケット」という小さな単位に分割されます。このパケットのサイズが大きいと、一つのパケットを送信したり、ネットワーク機器で処理したりするのに必要な時間も長くなり、結果としてレイテンシが増加する傾向があります 1。
- パケット損失: 通信途中で何らかの理由(例えばネットワークの混雑や電波状態の悪化など)により、送信したパケットの一部が宛先に正しく届かないことがあります。これを「パケット損失」と呼びます。パケット損失が発生すると、失われたパケットを再送信する必要が生じるため、余計な時間がかかり、全体の遅延、つまりレイテンシが増加する原因となります 1。
これらの要因は、それぞれ独立しているように見えても、実際には相互に関連し合い、複合的にレイテンシに影響を与えます。例えば、ネットワークが混雑している(原因B)と、パケット損失が発生しやすくなり(原因F)、それがさらなる遅延を引き起こす、といった具合です。これらの要因は、ネットワークの効率性や信頼性と密接に関連しており、レイテンシの問題を診断する際には、多角的に原因を探ることが重要になります。
V. レイテンシを測ってみよう!初学者向け測定方法
自分のインターネット環境のレイテンシがどの程度なのか、気になってきませんか?幸い、専門的な知識がなくてもレイテンシを測定する方法はいくつかあります。ここでは、IT初学者の方でも簡単に試せる代表的な測定方法を紹介します。
A. 簡単な測定方法:オンラインスピードテストサイト
最も手軽にレイテンシを測定できるのが、インターネット上で提供されている「スピードテストサイト」を利用する方法です。これらのサイトは、特別なソフトウェアをインストールする必要がなく、ウェブブラウザからアクセスするだけで簡単に利用できます。
代表的なスピードテストサイトとしては、以下のようなものがあります。
- Google スピードテスト: Googleの検索画面で「スピードテスト」と検索すると、検索結果の上部に表示される「速度テストを実行」ボタンを押すだけで測定が開始されます 7。
- USEN GATE 02 法人向け回線スピードテスト (旧 USEN インターネット回線スピードテスト): サイトにアクセスし、「測定開始」ボタンを押すと測定が始まります 16。
- Fast.com (Netflix提供): Netflixが提供しているスピードテストサイトです。サイトにアクセスすると自動的にダウンロード速度の測定が始まり、測定後に「詳細を表示」ボタンを押すと、レイテンシ(「アンロード済み」と「ロード済み」の2種類)を確認できます 16。
これらのサイトでは、通常、レイテンシ(多くの場合「Ping値」や「応答時間」として表示されます)に加えて、インターネット回線の通信速度である「下り速度(ダウンロード速度)」や「上り速度(アップロード速度)」も同時に測定してくれます 7。
オンラインスピードテストは、専門知識やコマンド操作が一切不要なため、IT初学者の方がレイテンシという概念を最初に体験し、ご自身のインターネット環境がどの程度の応答速度を持っているのかを把握するための、最も手軽で有効な入口と言えるでしょう。技術的なハードルを感じることなく、誰でも自分の回線の「応答速度」を数値で確認できるため、レイテンシへの関心を高める良いきっかけになります。
B. 基本的な測定方法:Pingコマンドを使ってみる
もう少し本格的にレイテンシを測定したい場合や、特定のサーバーまでの応答時間を知りたい場合には、「Ping(ピン)」コマンドを利用する方法があります。Pingは、指定したIPアドレスやホスト名(ウェブサイトのアドレスなど。例:www.google.com)までのネットワークの接続性を確認し、データパケットが往復するのにかかった時間(RTT: Round Trip Time)を測定するための基本的なコマンドです 6。
Windowsでの使い方:
- 画面左下のスタートボタンを右クリックし、「ファイル名を指定して実行」を選択するか、キーボードの Windowsキー + Rキー を同時に押します。
- 表示されたウィンドウに「cmd」と入力し、Enterキーを押すと、「コマンドプロンプト」という黒い画面が表示されます。
- コマンドプロンプトに、例えば ping www.google.com のように「ping」と入力し、続けて半角スペースを空けてから、応答時間を確認したいウェブサイトのアドレス(ホスト名)やIPアドレスを入力し、Enterキーを押します 12。
Macでの使い方:
- 画面右上の虫眼鏡アイコン(Spotlight検索)をクリックし、検索ボックスに「ターミナル」と入力して「ターミナル」アプリケーションを起動します。
- ターミナルに、例えば ping www.google.com のように「ping」と入力し、続けて半角スペースを空けてから、応答時間を確認したいウェブサイトのアドレス(ホスト名)やIPアドレスを入力し、Enterキーを押します 25。
- (補足:古いバージョンのmacOSでは「ネットワークユーティリティ」というツールからもPingを実行できましたが、新しいバージョンではターミナルを使用します 25。)
Ping結果の読み方:
Pingコマンドを実行すると、通常4回(設定による)のパケットが送信され、それぞれの応答時間が表示されます。結果の中に、「時間=XXms」や「time=XXms」(XXは数値)といった部分があれば、それがその宛先までの1回ごとのレイテンシ(Ping値)です 11。最後に、これらの平均値などが表示されることもあります。
Pingコマンドは、レイテンシ測定の基本であり、ネットワークの基本的な接続性や応答性を確認するための普遍的なツールです。多くの資料で言及されているように 6、その基本的な役割を理解し、使い方を覚えることは、ネットワークのトラブルシューティングを行う上での第一歩となります。コマンド操作に慣れることは、ITスキル全体の向上にも繋がるでしょう。
C. (発展) ブラウザのデベロッパーツールで見る方法
ウェブサイトの表示が遅いと感じる場合、その原因がどこにあるのかをより詳しく調べるためには、ウェブブラウザに搭載されている「デベロッパーツール」が役立ちます。これは主にウェブ開発者向けの機能ですが、IT初学者の方でも基本的な見方を知っておくと便利です。
Google Chrome, Microsoft Edge, Firefoxといった主要なウェブブラウザには、このデベロッパーツールが標準で搭載されています。通常、ウェブページ上で F12 キーを押すか、右クリックして「検証」や「要素を調査」などを選択すると起動できます。
デベロッパーツールの「ネットワーク」タブ(または「Network」タブ)を選択すると、そのウェブページを表示するためにブラウザが送受信したすべてのリクエスト(HTMLファイル、画像ファイル、CSSファイル、JavaScriptファイルなど)の一覧と、それぞれの読み込みにかかった時間などを時系列で確認することができます 8。
ここで特に注目したいのが、「TTFB(Time To First Byte)」という指標です。これは、ブラウザがサーバーにリクエストを送信してから、サーバーがそのリクエストを処理し、応答の最初の1バイト目がブラウザに到着するまでにかかった時間を示します 8。TTFBは、主にサーバー側の処理速度やネットワーク経路のレイテンシを反映する指標とされています。
さらに、ネットワークタブでは、個々のリクエストが完了するまでの内訳、例えば、DNSサーバーに問い合わせてIPアドレスを取得するのにかかった時間(DNS解決)、サーバーとの接続を確立するのにかかった時間(接続確立)、暗号化通信(HTTPS)のための準備にかかった時間(TLSハンドシェイク)なども詳細に確認できます 8。
Pingコマンドが特定のサーバーとの間の往復時間という全体像を示すのに対し、ブラウザのデベロッパーツールは、ウェブページが表示されるまでの一連の通信の中で、具体的にどの部分で時間がかかっているのか(レイテンシの「内訳」)を可視化してくれます。これにより、表示遅延の原因がネットワーク経路の問題なのか、サーバー側の処理の問題なのか、あるいは特定の大きな画像ファイルの読み込みに時間がかかっているのか、といったことをより詳細に切り分ける手がかりが得られます。初学者の方がすぐに全てを使いこなすのは難しいかもしれませんが、このようなツールが存在することを知っておくことは、将来的な学習や問題解決のステップとして非常に有益です。
VI. レイテンシの測定結果、どう見ればいいの?目安を紹介
さて、スピードテストサイトやPingコマンドでレイテンシを測定してみたものの、その結果の数値が「速い」のか「遅い」のか、いまいちピンとこないかもしれません。ここでは、測定結果をどのように解釈すればよいのか、一般的な目安を紹介します。
A. 「速い」「遅い」の基準は?一般的な目安
まず基本的なこととして、レイテンシの値は、低い(小さい)ほど応答が速く、一般的に良い状態であると言えます 6。数値が大きければ大きいほど、遅延が大きいということです。
では、具体的にどのくらいの数値なら「速い」と言えるのでしょうか。これは利用するアプリケーションや個人の感覚によっても異なりますが、一般的なウェブサイトの閲覧であれば、
- 50ms(ミリ秒)以下: かなり快適に感じられるでしょう。ページの切り替えもスムーズです。
- 50ms ~ 100ms: ストレスを感じるほどではありませんが、時々わずかな「間」を感じることがあるかもしれません。
- 100ms を超える: ページの表示が「少し遅いな」と感じ始めることが多い数値です。
- 200ms を超える: 明らかに遅延を感じ、ストレスを感じやすくなるでしょう。
ただし、これはあくまで大まかな目安です。レイテンシの「良い」「悪い」は絶対的なものではなく、どのような目的でインターネットを利用するか(用途)や、個人の許容度によっても変わってきます。それでも、一定の目安を知っておくことで、ご自身のインターネット環境が一般的な水準と比較してどうなのかを客観的に評価するのに役立ちます。初心者は特に「測定した数値が良いのか悪いのか」が分かりにくいため、具体的な目安を参考にすることが重要です 11。
B. 用途別の快適なレイテンシ値(ウェブ閲覧、ゲーム、動画など)
インターネットの用途によって、求められるレイテンシの快適ラインは異なります。リアルタイム性が重要になるほど、より低いレイテンシ値が求められる傾向にあります。
| レイテンシ値 (ms) | ウェブサイト閲覧 | オンラインゲーム (特にFPSなど) | 動画視聴(ライブ) | ビデオ会議 |
| ~20ms | 非常に快適、サクサク表示 | 理想的、操作がほぼ遅延なく反映 | ほぼ遅延なし、映像と音声が完全に一致 | 非常にスムーズ、リアルタイムな会話が可能 |
| 20ms~50ms | 快適、ほぼ問題なし | ほぼ問題なし、快適にプレイ可能 | 快適、わずかな遅延を感じることは稀 | スムーズ、快適な会話が可能 |
| 50ms~100ms | 普通、時々わずかな遅延を感じることも | プレイは可能だが、反応の速いゲームでは不利になることも | 視聴可能だが、場面によりわずかなカクつきの可能性 | 会話は可能だが、若干の間や音声の遅れを感じることも |
| 100ms~ | 遅いと感じる、ページの切り替えにストレスを感じやすい | プレイに支障、ラグが目立ち不利になる | 読み込みに時間がかかったり、途中で止まる可能性あり | 会話が途切れがち、ストレスを感じやすい |
表1:レイテンシ値の目安と主な用途への影響
6
オンラインゲーム: 特に一瞬の反応が勝敗を分けるようなFPS(ファーストパーソン・シューティングゲーム)や格闘ゲームなどでは、20ms以下が理想とされ、50msを超えると不利を感じ始め、100msを超えるとまともにプレイするのが難しくなることがあります 6。
VoIP(音声通話)/ ビデオ会議: 相手とのスムーズな会話のためには、150ms以内が望ましいとされています。300msを超えると、声が大幅に遅れたり途切れたりして、コミュニケーションに支障が出始めます 6。
動画視聴(ライブ以外): あらかじめデータを読み込むバッファリング機能があるため、オンラインゲームほどシビアではありませんが、一般的に15ms~30ms程度であれば高画質の動画でも問題なく視聴できることが多いでしょう 6。ただし、スポーツ中継などのライブストリーミングの場合は、リアルタイム性が重要になるため、より低いレイテンシが求められます 6。
一般的なウェブサイト閲覧: 50ms以下であれば非常に快適で、100msを超えると表示が遅いと感じやすくなります 6。
この表は、測定したレイテンシ値が具体的にどのような意味を持つのかを、日常的なインターネット活動に照らして直感的に理解するのに役立ちます。数値だけではピンとこない「体感」と結びつけることで、ご自身の環境の評価や改善目標の設定が容易になります。アプリケーションの種類によって、レイテンシに対する「感度」が大きく異なることを理解し、自分の主な用途に合わせてレイテンシ目標を設定したり、問題の深刻度を判断したりすることが大切です。
VII. レイテンシを改善するための簡単なヒント
レイテンシが高いと感じた場合、専門的な知識がなくても試せる簡単な改善策がいくつかあります。ここでは、利用者自身ができることと、参考としてウェブサイト運営者向けのヒントを紹介します。
A. 自分でできること(利用者向け)
まず、ご自身で試せる簡単な対処法です。これらの方法で必ず改善するとは限りませんが、試してみる価値はあります。
- ルーターやモデムを再起動する: ルーターやモデム(光回線終端装置など)は、長時間連続して稼働していると、内部に不要なデータが溜まったり、一時的な不具合が発生したりすることがあります。電源を一度切り、数分待ってから再度電源を入れる「再起動」を行うことで、これらの問題が解消され、通信状態がリフレッシュされてレイテンシが改善することがあります 1。
- 有線LAN接続を試す: もし無線LAN(Wi-Fi)でインターネットに接続している場合は、可能であればLANケーブルを使った有線接続を試してみてください。一般的に、無線LANよりも有線LANの方が通信が安定しており、外部からの電波干渉も受けにくいため、レイテンシが低くなる傾向があります 1。
- LANケーブルの種類を確認・交換する: 有線LAN接続で使用しているLANケーブルが古い規格(例えば「CAT5(カテゴリ5)」など)の場合、通信速度が十分に発揮されず、レイテンシにも悪影響を与えている可能性があります。LANケーブルには「カテゴリ」という規格があり、数字が大きいほど新しい規格で高性能です。現在では「CAT5e(カテゴリ5e)」以上、できれば「CAT6(カテゴリ6)」以上の規格のLANケーブルを使用することが推奨されています 1。ケーブル自体に規格名が印字されていることが多いので、確認してみましょう。
- 同時に使う機器を減らしてみる: 同じインターネット回線を共有して、家族が同時に動画を視聴したり、複数のパソコンやスマートフォンで大容量のデータを送受信したりしていると、回線が混雑し、それぞれの機器のレイテンシが悪化することがあります 6。一時的に他の機器の利用を控えてみることで、改善が見られるか確認してみましょう。
- 不要なアプリやブラウザのタブを閉じる: パソコンやスマートフォンで、バックグラウンドで動作しているアプリケーションや、ウェブブラウザで開いたままになっている多数のタブの中には、気づかないうちに通信を行っているものがあります。これらがCPUやメモリといった端末のリソースを消費したり、ネットワーク帯域を圧迫したりして、遅延の原因になっていることがあります 7。不要なアプリやタブはこまめに閉じるようにしましょう。
- (無線LANの場合) ルーターの設置場所や設定を見直す: 無線LAN(Wi-Fi)を利用している場合、ルーターの設置場所がレイテンシに影響することがあります。電子レンジやコードレス電話機など、電波干渉を起こしやすい家電製品の近くは避けましょう。また、ルーターと利用するデバイス(パソコンやスマホ)の間に壁や金属製の家具などの障害物があると電波が弱まりやすいため、できるだけ見通しの良い場所に設置するのが理想です 1。ルーターのファームウェア(制御用ソフトウェア)が古い場合は、メーカーのウェブサイトから最新版をダウンロードして更新することで、性能が改善されることもあります。
これらの簡単な対処法を試すことで、IT初学者の方でも「自分でも何かできるかもしれない」という感覚を持ち、問題解決への積極性を促すことができます。これらの「応急処置」的な方法を知っているだけで、日常的なインターネットの不調に対する安心感が変わるはずです。
B. (参考) ウェブサイト運営者向けのヒント(SEOとの関連で簡単に)
レイテンシの改善は、利用者側の努力だけでは限界があり、ウェブサイトやオンラインサービスを提供する側による最適化も非常に重要です。もし将来的にウェブサイトの運営に関わる機会があれば、以下のような点が役立つかもしれません。これらはユーザー体験を向上させるだけでなく、SEO(検索エンジン最適化)にも繋がるため、ビジネス的にも重要です。
- 画像の最適化: ウェブページに含まれる画像のファイルサイズが大きいと、読み込みに時間がかかり、レイテンシが高いと感じる原因になります。画像を圧縮してファイルサイズを小さくするなどの最適化を行います 18。
- CDN (コンテンツデリバリーネットワーク) の利用: CDNは、世界各地に分散配置されたサーバー群にウェブサイトのコンテンツのコピーを置き、利用者に最も近いサーバーからコンテンツを配信する仕組みです。これにより、利用者とサーバーとの物理的な距離が短縮され、表示速度の向上(低レイテンシ化)が期待できます 1。
- ブラウザキャッシュの活用: 一度利用者がアクセスしたウェブサイトのデータ(画像やCSSファイルなど)を、利用者のブラウザに一時的に保存しておく仕組みです。再度同じページにアクセスした際に、保存されたデータを利用することで、サーバーとの通信量を減らし、表示を高速化できます 1。
- サーバーの性能向上や場所の選択: ウェブサイトを置くサーバー自体の処理能力を高めたり、より高速な回線に接続されたサーバーを選んだりします。また、主なターゲットユーザーが日本国内であれば、国内にあるサーバーを選ぶなど、ユーザーに近い地域のサーバーを利用することも物理的な距離を縮め、レイテンシ改善に繋がります 1。
- HTTP/2(またはHTTP/3)の利用: HTTPはウェブブラウザとサーバーが通信するためのプロトコル(通信規約)です。HTTP/2やその後継のHTTP/3は、従来のHTTP/1.1に比べて、複数のリクエストを並行して効率的に処理できるなどの改善がされており、ウェブページの表示速度向上に貢献します 1。
- オフスクリーン画像の遅延読み込み: ウェブページの中でも、最初に画面に表示されていない部分(スクロールしないと見えない部分)の画像は、すぐに読み込まず、利用者がスクロールしてその部分が表示されそうになったタイミングで読み込むようにする技術です。HTMLのimgタグに loading=”lazy” という属性を追加するだけで簡単に実装できる場合もあります 18。これにより、初期表示の高速化が期待できます。
これらの施策は、ウェブサイトやサービスの提供者側が行うべき努力であり、利用者側でできることには限りがあります。しかし、普段利用しているサービスがどのような努力によって快適さを提供しているのか、という視点を持つことは、ITへの理解を深める上で役立つでしょう。
VIII. レイテンシとSEO:ウェブサイト表示速度の重要性
レイテンシ、特にそれが影響するウェブサイトの表示速度は、実は検索エンジンのランキング、つまりSEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)にも関わってくる重要な要素です。
A. ウェブサイトの表示が遅いと検索順位に影響?
Googleをはじめとする主要な検索エンジンは、ユーザーにとってより価値のある情報を提供することを目指しています。その一環として、ウェブサイトの「表示速度」を検索結果のランキングを決定する要因の一つとして考慮しています 11。
表示が遅いウェブサイトは、ユーザーにストレスを与え、離脱されやすいため、「ユーザー体験が悪いサイト」と検索エンジンに判断される可能性があります。その結果、検索結果で他のサイトよりも不利な順位になってしまうことがあるのです。
近年、Googleは「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」という、ウェブサイトのユーザー体験を測るための具体的な指標群を提唱し、これをランキング要因として重視するようになっています 26。Core Web Vitalsには、ページの主要コンテンツが読み込まれる速度を示す「LCP (Largest Contentful Paint)」、ユーザーの最初の操作に対するブラウザの応答性を示す「FID (First Input Delay)」(現在は「INP (Interaction to Next Paint)」に置き換わる動きがあります)、ページの視覚的な安定性を示す「CLS (Cumulative Layout Shift)」といった指標が含まれます。これらの指標の多くは、レイテンシと密接に関連しています。
つまり、高レイテンシが原因でウェブサイトの表示速度が低下すると、ユーザー体験が悪化し(例えば、直帰率の増加やサイト滞在時間の減少など)、その結果として検索エンジンから「質の低いサイト」と評価され、SEOの順位が低下するという、間接的な影響の連鎖が発生しうるのです。
B. ユーザー体験とSEOの関係
検索エンジンは、ユーザーにとって使いやすく、情報が探しやすく、そして満足度の高いウェブサイトを高く評価する傾向にあります。レイテンシが低く、表示が速いウェブサイトは、まさにそのような「ユーザーにとって価値のあるサイト」と言えるでしょう 1。
したがって、レイテンシを改善し、ウェブサイトの表示速度を高めることは、単に技術的なパフォーマンスを向上させるだけでなく、ユーザー体験そのものを向上させることに繋がります。そして、この優れたユーザー体験が、間接的に検索エンジンからの評価を高め、SEO対策としても有効に機能するのです。
現代のSEOは、検索エンジンを騙すような小手先のテクニックではなく、いかにユーザーに価値を提供し、満足させるかという「ユーザーファースト」の視点が非常に重要になっています。レイテンシの改善は、まさにそのユーザーファーストの考え方を体現する具体的な行動の一つと言えるでしょう。この点を理解することで、単なるテクニカルな施策に終始するのではなく、本質的なウェブサイト改善に取り組む意義をIT初学者の方にも感じていただけるはずです。
IX. まとめ
A. レイテンシ測定のポイントをおさらい
この記事では、「レイテンシ測定とは何か」というテーマを中心に、IT初学者の方にも分かりやすく解説してきました。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- レイテンシとは「応答時間」や「通信の遅延時間」のことであり、この値が低い(小さい)ほど、インターネットは快適に利用できます。
- レイテンシは、オンラインのスピードテストサイトや、パソコンのPingコマンドなどを使って比較的簡単に測定することができます。
- レイテンシが高くなる原因は、サーバーまでの物理的な距離、ネットワークの混雑、通信回線や機器の性能など様々ですが、ルーターの再起動やLANケーブルの見直しなど、利用者側で試せる簡単な改善策もあります。
- レイテンシは、オンラインゲームや動画視聴、ビデオ会議といった日常的なインターネット利用の快適さはもちろん、ウェブサイトの表示速度を通じてSEO(検索エンジン最適化)にも関わる重要な指標です。
B. 快適なIT活用のために
レイテンシという概念を理解し、その測定方法や原因、改善策について知ることは、皆さんが今後インターネットを利用したり、IT関連の学習や業務に取り組んだりする上で、きっと役立つはずです。
例えば、自宅のインターネット回線が遅いと感じたときに、ただ不満に思うだけでなく、「もしかしたらレイテンシが高いのかもしれない。一度測定してみよう」と考え、原因を探るきっかけになるかもしれません。また、新しいインターネット回線を契約する際に、通信速度だけでなくレイテンシの評判も気にしてみる、といった視点も持てるようになるでしょう。
この記事で得た知識は、IT初学者の方が今後遭遇するであろう様々なネットワーク関連の問題や、より深い技術を学ぶ上での基礎的な理解を助け、主体的な行動を促す「種」となることを願っています。レイテンシについて学んだことが、皆さんのこれからの快適なIT活用や、さらなるステップアップの一助となれば幸いです。
引用文献
- レイテンシとは? わかりやすく10分で解説 – ネットアテスト, 5月 18, 2025にアクセス、 https://www.netattest.com/latency-2024_mkt_tst
- レイテンシとは。Ping値や遅い場合の改善法を徹底解説! | Winserverのススメ, 5月 18, 2025にアクセス、 https://www.winserver.ne.jp/column/about_latency/
- レイテンシとは | クラウド・データセンター用語集 – IDCフロンティア, 5月 18, 2025にアクセス、 https://www.idcf.jp/words/latency.html
- 低レイテンシー(レイテンシ)とは? その意味と重要性、実現方法を解説 – Catch On Hub Column, 5月 18, 2025にアクセス、 https://catchon-hub.com/blog/202405_2
- ネットワーク性能の重要指標「レイテンシ」とは? – ManageEngine ブログ, 5月 18, 2025にアクセス、 https://blogs.manageengine.jp/itom_what_is_latency/
- Latency simply explained: How to improve your ping – devolo, 5月 18, 2025にアクセス、 https://www.devolo.global/guide/latency-explained-improve-ping
- レイテンシとping値の違いとは?数値が悪くなる原因と改善方法 – eo光, 5月 18, 2025にアクセス、 https://eonet.jp/column/line-speed/latency-ping.html
- Understanding latency – Web performance | MDN, 5月 18, 2025にアクセス、 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Performance/Guides/Understanding_latency
- What is Latency? – Latency Explained – AWS, 5月 18, 2025にアクセス、 https://aws.amazon.com/what-is/latency/
- レイテンシーとは?遅延の原因から改善方法まで一挙解説! | LISKUL, 5月 18, 2025にアクセス、 https://liskul.com/latency-138747
- レイテンシは低さを目指しましょう! – カゴヤのサーバー研究室, 5月 18, 2025にアクセス、 https://www.kagoya.jp/howto/it-glossary/network/latency/
- ジッター(ジッタ)とレイテンシー(レイテンシ):違い・原因・解決方法|Agora Go Real – ブイキューブ, 5月 18, 2025にアクセス、 https://jp.vcube.com/sdk/blog/jitter-vs-latency
- スループットとは? 意味やレイテンシとの違い、種類、単位、測定方法を解説, 5月 18, 2025にアクセス、 https://www.ntt.com/business/services/rink/knowledge/archive_06.html
- ネットワークレイテンシとは? – JPNAP, 5月 18, 2025にアクセス、 https://www.jpnap.net/internet-fundamentals/latency
- DTM用語:レイテンシとは|ツキシロ – note, 5月 18, 2025にアクセス、 https://note.com/moonwhite/n/ncbee9d656808
- Pingの測定方法!オンラインゲーム/トレードに必要な目安や、Ping値を改善する方法も解説, 5月 18, 2025にアクセス、 https://special.goo.ne.jp/internet/knowledge/howtomeasureping/
- Understanding the Impact of Latency on Network Performance | Kentik, 5月 18, 2025にアクセス、 https://www.kentik.com/kentipedia/network-latency-understanding-impacts-on-network-performance/
- レイテンシとは? その改善方法とは? – ASCII.jp, 5月 18, 2025にアクセス、 https://ascii.jp/elem/000/004/092/4092877/
- 【初心者向け】急にインターネットが遅くなる11の原因と対処法をわかりやすく解説 – DoRACOON, 5月 18, 2025にアクセス、 https://www.doracoon.net/navi/solutions/solutions-1122/
- 社内ネットワークが遅い原因とは?改善策や調査方法を解説 – ケイティケイ, 5月 18, 2025にアクセス、 https://ktk.gr.jp/forbiz/it-solution/internal-network-is-slow/
- 社内のネットワークが遅い原因は?改善方法や調査方法を解説 – NTTコミュニケーションズ, 5月 18, 2025にアクセス、 https://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/bocn/knowledge/archive_163.html
- ネットワークが遅い原因と改善方法について解説 | BizDrive(ビズドライブ), 5月 18, 2025にアクセス、 https://business.ntt-east.co.jp/bizdrive/column/dr00101-014.html
- Understanding Network Latency: A Guide for Beginners – Globalping Blog, 5月 18, 2025にアクセス、 https://blog.globalping.io/understanding-network-latency-a-guide-for-beginners/
- Measuring latency, 5月 18, 2025にアクセス、 https://docs.eseye.com/Content/Connectivity/MeasureLatency.htm
- Pingテストを実行する方法(レイテンシを確認する方法) – Remo.co, 5月 18, 2025にアクセス、 https://help.remo.co/ja-JP/support/solutions/articles/63000253809-ping%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%89
- コアウェブバイタル(Core Web Vitals)とは?SEOに与える影響と対策方法についてわかりやすく解説します! – デジタルアイデンティティ, 5月 18, 2025にアクセス、 https://digitalidentity.co.jp/blog/seo/core-web-vitals-2.html