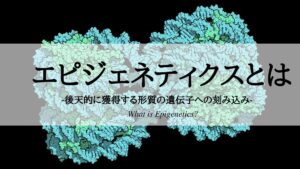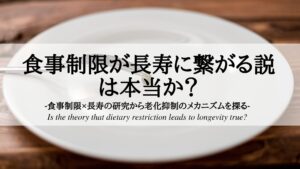序論:黒豹(ブラックパンサー)の謎
漆黒の体毛、しなやかな筋肉、そして闇に紛れて獲物を狙う神秘的な姿。多くの人々が「黒豹(ブラックパンサー)」という言葉に、畏敬の念と強烈な魅力を感じます 1。この黒光りする姿は、まさに「かっこいい」という言葉がふさわしく、数々の物語や文化の中で力と神秘の象徴として描かれてきました。しかし、この黒豹という存在、実は生物学的な「種」として存在するわけではありません 2。
この衝撃的な事実こそが、私たちがこれから探求する驚異的な生命現象、「メラニズム(黒化症)」への入り口です。「黒豹」とは、アジアやアフリカに生息するヒョウ(学名: Panthera pardus)や、南北アメリカ大陸に生息するジャガー(学名: Panthera onca)が、ある遺伝的な要因によって全身黒く変異した個体を指す通称なのです 4。よく見ると、その漆黒の毛皮の下には、ヒョウやジャガー特有の斑紋(ロゼット模様)がうっすらと浮かび上がっていることもあります 4。
この現象、メラニズムは、生物の体内でメラニンと呼ばれる黒い色素が過剰に生成されることによって引き起こされる遺伝的な形質です 6。体毛や皮膚、羽毛が黒くなるこの現象は、白化するアルビニズム(白化症)とは正反対の現象として知られています 3。
では、なぜ一部の動物だけが、このような漆黒の姿を手に入れるのでしょうか?その背後には、どのような遺伝子のスイッチが働いているのでしょう?そして、この目立つ「黒」という色は、厳しい自然界を生き抜く上で、どのような意味を持つのでしょうか?
本稿では、この「黒光り」の謎を解き明かすため、国外の最新の研究成果を基に、メラニズムの正体に迫ります。単なる色の違いに留まらない、その背後にある分子生物学的な精緻なメカニズムから、生存をかけた壮大な進化のドラマまで、メラニズムのすべてを包括的に解説していきます。黒豹の謎から始まるこの旅は、生命の多様性と適応の巧みさを浮き彫りにする、知的好奇心を満たす冒険となるでしょう。


第1章 色の科学:メラニズムとその仲間たちの定義
動物たちの多彩な体色を理解するためには、まずその基本となる色素について知る必要があります。メラニズムを正確に理解するために、まずは色素の科学と、関連する他の現象との違いを明確にしていきましょう。
色を生み出す基本要素
動物の体色、特に黒や茶色、赤や黄色といった色は、主に「メラニン」という色素によって作られています。メラニンは、メラノサイトと呼ばれる特殊な細胞内で合成され、大きく分けて2つのタイプが存在します 2。
- ユーメラニン(Eumelanin): 黒色や褐色の色素です。この色素が多いほど、体色は暗くなります 8。
- フェオメラニン(Pheomelanin): 赤色や黄色の色素です。この色素が多いと、体色は明るく、赤みがかった色合いになります 8。
動物の最終的な体色は、これら2種類のメラニンがどのような比率で、体のどの部分に分布するかによって決まります。そして、この比率と分布は、遺伝子によって厳密にコントロールされているのです。メラニズムとは、このバランスが大きくユーメラニン側に傾いた状態と言えます。
正確な言葉で理解する:色素異常の分類
一般的に「色が普通と違う」現象は混同されがちですが、科学的にはそれぞれ明確に区別されます。専門的な報告書として、これらの用語を正確に使い分けることは極めて重要です。
- メラニズム(Melanism / 黒化症): 本稿の主題であるこの現象は、遺伝的な要因により、黒い色素であるユーメラニンが「過剰」に生成される状態を指します 6。これは先天的な形質であり、病気ではありません。
- アルビニズム(Albinism / 白化症): メラニズムとは対照的に、遺伝的な要因でメラニンを「全く、あるいはほとんど生成できない」状態です。これにより、体毛や羽毛は白く、メラニン色素がないために血管が透けて見えることで目は赤色やピンク色に見えます 2。
- リューシズム(Leucism / 白変症): 全身または体の一部で「すべての」種類の色素が減少する状態です。アルビニズムと混同されやすいですが、リューシズムでは目の色は正常であることが多く、この点で区別されます。メラニンを全く作れないわけではないため、完全に真っ白ではなく、淡い色合いになることもあります 6。
- シュードメラニズム(Pseudomelanism / 偽黒化症)またはアバンディズム(Abundism): これは、体表の黒い斑点や縞模様が通常よりも大きく、また密になることで、全体として黒っぽく「見える」状態です。完全に均一な黒ではなく、模様が拡大・融合した結果である点が、真のメラニズムとは異なります 2。例えば、斑点が密になりすぎて黒く見えるヒョウなどがこれにあたります 4。
- メラノーシス(Melanosis / 黒色症): これが最も重要な区別かもしれません。メラニズムが遺伝的な「形質」であるのに対し、メラノーシスは黒色色素が沈着する「病的」な状態を指します。多くの場合、腫瘍や何らかの疾患に関連して発生する後天的な変化であり、生物の正常な変異であるメラニズムとは根本的に異なります 6。
このように、単に「黒い」といっても、その背景にある生物学的なメカニズムは様々です。メラニズムは、あくまで遺伝子によって制御された、自然界における多様性の一つの現れです。この正確な定義を理解することが、続く遺伝的、進化的議論の基礎となります。ある動物が黒い理由を考えるとき、それが自然な遺伝的多様性なのか、それとも病的な兆候なのかを区別することは、生物学的な探求において不可欠な第一歩なのです。
第2章 遺伝子のスイッチボード:メラニズムの分子的メカニズム
動物の体がなぜ黒くなるのか、その答えは細胞の中、遺伝子のレベルに隠されています。ここでは、体を「色素工場」に例えて、メラニズムを引き起こす分子レベルのスイッチの仕組みを解き明かしていきましょう。この工場の中心には、黒いユーメラニンを生産するか、それとも明るいフェオメラニンを生産するかを決定する、極めて重要な「色素スイッチ」が存在します。そして、このスイッチを操作しているのが、MC1RとASIPという2つの鍵となる遺伝子です。
「黒色ON」シグナル:メラノコルチン1受容体(MC1R)経路
色素を生産する細胞(メラノサイト)の表面には、「メラノコルチン1受容体(Melanocortin 1 Receptor、以下MC1R)」というタンパク質が存在します 9。これは、工場の生産ラインを起動させるメインスイッチのようなものです。
α-メラノサイト刺激ホルモン(α-MSH)というホルモンがこのMC1Rに結合すると、受容体が活性化されます。すると、細胞内でcAMP(サイクリックAMP)経路と呼ばれる一連の化学反応が連鎖的に起こり、「黒いユーメラニンを生産せよ」という命令が下されます 9。つまり、MC1Rが活性化されることが、黒い色素を生産するための基本的な「ON」の状態なのです。
「黒色OFF」シグナル:アグーチシグナルタンパク質(ASIP)の拮抗作用
一方で、この「ON」スイッチを意図的に止める役割を持つのが、「アグーチシグナルタンパク質(Agouti Signaling Protein、以下ASIP)」です。このタンパク質はASIP遺伝子によって作られ、MC1Rに対する「拮抗阻害剤」として機能します 13。
ASIPの役割は、MC1R受容体に結合し、α-MSHが結合するのを「ブロック」することです。このブロックにより、ユーメラニン生産の命令系統は遮断され、工場は代わりに明るい色のフェオメラニンを生産するように切り替わります 13。したがって、ASIPは黒色色素生産の「OFF」スイッチとして機能しているのです。
黒い毛皮への二つの道:二頭の黒豹の物語
この遺伝子のスイッチボードを操作することで、進化はどのようにして同じ「黒い毛皮」という表現型を生み出してきたのでしょうか。ここで、ジャガーとヒョウという、近縁ながらも異なる大陸に生息する二頭の「黒豹」をケーススタディとして見てみましょう。驚くべきことに、彼らは全く異なる遺伝的アプローチで、同じ漆黒の姿を手に入れていました。
ケーススタディ1:ジャガー — 壊れた「ON」スイッチ(優性メラニズム)
ジャガーのメラニズムは、色素生産の「ON」スイッチであるMC1R遺伝子そのものの変異によって引き起こされます 4。
具体的には、MC1R遺伝子内で15塩基対が欠失する変異が起きています 6。この変異により、MC1R受容体はα-MSHホルモンの有無にかかわらず、常に活性化し続ける「機能獲得型変異(gain-of-function)」の状態に陥ります。つまり、工場の「ON」スイッチが壊れて、常にオンのまま固まってしまったような状態です。
この「常にON」というシグナルは非常に強力で、正常な状態を上書きしてしまうため、この形質は優性遺伝します。つまり、親からこの変異遺伝子を一つ受け継ぐだけで、その個体は黒い毛皮を持つことになるのです 4。
ケーススタディ2:ヒョウ — 壊れた「OFF」スイッチ(劣性メラニズム)
一方、ヒョウのメラニズムは、「OFF」スイッチであるASIP遺伝子の変異によって引き起こされます 15。
ヒョウの変異は、ASIP遺伝子の途中に終止コドン(タンパク質合成を停止させる信号)が出現してしまう変異です。これにより、正常に機能するASIPタンパク質が作られなくなります(「機能喪失型変異(loss-of-function)」) 17。つまり、「OFF」スイッチ自体が壊れてしまった状態です。
MC1RをブロックするASIPタンパク質が存在しないため、MC1R受容体はデフォルトの状態、すなわちユーメラニンを生産する状態になります。
しかし、この場合、両親から正常なASIP遺伝子を一つでも受け継いでいれば、その個体は正常なブロッカーを少量でも生産できるため、通常の斑紋模様の毛皮になります。全身が黒くなるためには、両親から壊れたASIP遺伝子を一つずつ、合計二つ受け継ぐ必要があります。このため、ヒョウのメラニズムは劣性遺伝するのです 4。
この二つの事例は、生物進化の驚くべき柔軟性を示しています。ジャガーとヒョウという近縁種が、同じ「黒い毛皮」という表現型を獲得するために、一方は「ONスイッチを壊し」、もう一方は「OFFスイッチを壊す」という、全く異なる分子レベルの戦略をとったのです。これは、同じ目的地に異なる道筋でたどり着く「収斂進化」の好例です。進化の過程で、色素生成経路には複数の「弱点」が存在し、偶然生じた突然変異がどの遺伝子を標的とするかによって、多様な解決策が生まれることを示唆しています。「黒くなるための遺伝子」は一つではなく、環境に応じて様々な方法で操作されうる複雑なシステムなのです。
表1:ジャガーとヒョウにおけるメラニズムの遺伝的比較
この複雑な遺伝的メカニズムをまとめるため、以下の表にジャガーとヒョウのメラニズムの違いを示します。この比較により、同じ「黒豹」という見た目の裏にある、二つの異なる進化的ストーリーが一目でわかります。
| 特徴 | ジャガー (Panthera onca) | ヒョウ (Panthera pardus) |
| 通称 | ブラックジャガー | ブラックパンサー、クロヒョウ |
| 原因遺伝子 | メラノコルチン1受容体 (MC1R) | アグーチシグナルタンパク質 (ASIP) |
| 遺伝子の役割 | ユーメラニン(黒色色素)の生産を「活性化」する | MC1Rを阻害し、フェオメラニン(淡色色素)への生産を促す |
| 変異の種類 | 機能獲得型変異(15塩基対の欠失)。受容体が常に「ON」の状態。 | 機能喪失型変異(早期終止コドン)。阻害因子が機能しない。 |
| 遺伝形式 | 優性 | 劣性 |
第3章 最も黒き者の生存:黒という色の進化的パワー
遺伝子のスイッチがどのようにして黒い体色を生み出すのかを見てきましたが、次なる疑問は「なぜその形質が自然界で生き残るのか?」ということです。この章では、遺伝学から進化生物学へと視点を移し、黒い色がもたらす様々な生存上の利点を探ります。黒という色は単なる偶然の産物ではなく、特定の環境下で強力な武器となりうるのです。その理由は一つではなく、状況に応じて変化する複数の利点の組み合わせによって説明されます。
ケーススタディ1:工業暗化 — ダーウィンの蛾がリアルタイムで見せた進化
自然選択がどのように働くかを示す最も有名で劇的な例が、オオシモフリエダシャク(学名: Biston betularia)という蛾に見られる「工業暗化(Industrial Melanism)」です 19。
産業革命以前のイギリスでは、この蛾のほとんどは、木の幹に生える地衣類に紛れることができる、白地に黒い斑点のある淡色型(typica)でした 22。黒い暗色型(
carbonaria)は非常に珍しい存在でした。
しかし、19世紀に産業革命が本格化すると、工場から排出される石炭の煤煙が田園地帯を覆い、木の幹を黒く汚し、地衣類を死滅させました。この環境の激変により、これまで完璧な保護色であった淡色型は、黒い木の幹の上で鳥などの捕食者にとって非常によく目立つ存在となってしまったのです 19。
一方で、それまで目立っていた暗色型は、煤で黒くなった木の幹に対して完璧な保護色を得ることになりました。この選択圧の逆転を説明するのが、J. W. Tuttが提唱し、後にバーナード・ケトルウェルの有名な実験によって裏付けられた「鳥による選択的捕食仮説」です 19。この仮説は、鳥がより目立つ色の蛾を選択的に捕食するため、環境に合った保護色を持つ個体が生き残りやすいと説明します。結果として、暗色型の個体数が爆発的に増加し、マンチェスターでは1895年までに個体数の98%を占めるに至りました 19。
この物語にはさらに後日談があります。20世紀後半になると、大気汚染防止法の制定により大気が浄化され、木の幹は元の色を取り戻し始めました。すると、今度は暗色型が目立つようになり、再び淡色型の個体数が増加するという、進化の逆転現象が観察されたのです 19。これは、自然選択が環境の変化に応じてリアルタイムで作用することを証明する、他に類を見ない事例です。
興味深いことに、この蛾の工業暗化を引き起こした遺伝子は、ネコ科動物のMC1RやASIPとは全く異なるcortexという遺伝子でした。その変異は、「トランスポゾン(転移因子)」または「動く遺伝子」と呼ばれるDNA断片が遺伝子内に挿入されることによって引き起こされたものでした 26。これは、進化が同じ表現型(黒化)を生み出すために、全く異なる遺伝的経路を利用しうることを示す、さらなる証拠です。
ケーススタディ2:熱的メラニズム仮説(TMH) — 太陽光を利用したアドバンテージ
「熱的メラニズム仮説(Thermal Melanism Hypothesis、TMH)」は、特に変温動物において、黒い色がもたらす利点を説明する有力な理論です 8。この仮説によれば、寒冷な環境に生息する動物にとって、黒い体は太陽放射をより効率的に吸収し、体温を迅速に上昇させるのに役立ちます。
体温が上昇すれば、活動できる時間が長くなり、採餌や繁殖の機会が増えるため、これは直接的な適応度(生存と繁殖の成功)の向上につながります 8。この仮説を裏付けるように、クサリヘビ科のヘビなど多くの爬虫類では、メラニズム個体の出現頻度が、より寒冷な高緯度・高標高地域で高くなる傾向が見られます 8。
しかし、科学的な探求は、仮説の限界を試すことでもあります。TMHは強力な説明ですが、万能ではありません。例えば、夜行性で太陽光ではなく地面からの伝導熱で体温を調節するヒョウモントカゲモドキのような動物では、体色の黒さが体温上昇率に影響を与えないことが示されています 29。さらに、一部の昆虫では、TMHの予測とは逆に、高温環境で黒化が進むという研究結果も報告されています 31。これらの事実は、メラニズムの利点が、生物の生態や行動(例えば、昼行性か夜行性か)に大きく依存することを示唆しています。進化は普遍的な法則の適用ではなく、それぞれの生物が置かれた特定の文脈における最適化のプロセスなのです。
ケーススタディ3:隠された利点 — 色以上のもの
メラニズムの利点は、保護色や体温調節だけにとどまりません。色素に関わる遺伝子は、しばしば他の生命現象にも影響を及ぼすことがあります。
森林でのカモフラージュ
ヒョウやジャガーのような捕食者にとって、黒い毛皮がもたらす最も直感的な利点は、獲物から身を隠すためのカモフラージュです。特に、光量の少ない鬱蒼とした湿潤な森林では、黒い体は影に溶け込み、獲物に気づかれずに忍び寄る上で絶大な効果を発揮します。実際に、これらの種でメラニズム個体が多く見つかるのは、まさにそうした環境です 4。
免疫系との深いつながり
色素を制御する遺伝子は、独立して存在するわけではありません。特に、MC1Rが関わるシグナル伝達経路は、免疫系を含む他の重要な生理システムと深く結びついています。これは「多面発現(pleiotropy)」と呼ばれる現象で、一つの遺伝子が複数の、一見無関係に見える形質に影響を与えることを指します。この隠された利点が、メラニズムを強力に後押ししている可能性があります。
この関連性は、様々な生物群で示唆されています。ネコ科動物では、メラニズムがウイルス感染への抵抗性と関連している可能性が指摘されています 6。昆虫では、メラニン合成の生化学的経路(フェノールオキシダーゼ経路)が、病原体に対する免疫応答に直接関与しています 28。さらに、メラノコルチン受容体自体が、ヒトを含む脊椎動物において免疫調節機能を持つことが知られています 35。
これらの異なる分野(ネコ科の遺伝学、昆虫学、ヒトの医学)からの証拠をつなぎ合わせると、深遠な生物学的原理が浮かび上がってきます。黒いジャガーが生き残る理由は、単にカモフラージュに優れているからだけではないかもしれません。同じ遺伝子変異が、より強固な免疫システムをもたらし、捕食と病気の両方に対する二重の利点を提供している可能性があるのです。
進化におけるトレードオフ
進化において「完璧な」形質というものは存在せず、すべての適応には何らかの代償(コスト)が伴います。メラニズムは、この「進化的トレードオフ」を説明する典型的な例です。もしメラニズムが純粋に有益なだけであれば、もっと多くの種で、より一般的に見られるはずですが、実際はそうではありません 8。
このトレードオフは、昆虫の研究で明確に示されています。ある種のコオロギでは、オスは繁殖ディスプレイや体温調節のために体表の黒化に多くのリソースを投資しますが、その代償として免疫機能が低下します。一方でメスはその逆の戦略をとります 33。また、バッタの研究では、温暖な気候で体色を薄くすることは体温の過度な上昇を防ぐのに有効ですが、その代償として真菌感染に対する抵抗力が弱まることが示されています 34。
これらの例を総合すると、現代進化生物学の中心的な概念が明らかになります。すなわち、生物の適応度とは、絶えず変化する環境の中で、利益とコストの複雑な予算を最適化するプロセスなのです。黒いという形質は、ある状況下では大きな利益をもたらしますが、別の状況下では不利に働くこともある、まさに諸刃の剣なのです。
第4章 黒のギャラリー:自然界の黒いパレット
メラニズムという現象は、特定の種に限られたものではなく、動物界全体に広く見られます。この章では、自然が描いた黒の多様な作品たちを鑑賞し、異なる系統の生物が独立して同じ形質を獲得する「収斂進化」の広がりを実感してみましょう。
- 哺乳類: 北米の五大湖周辺でよく見られるクロリス(トウブハイイロリスの黒変種) 6、ギンギツネ(アカギツネの黒変種) 2、そして非常に珍しい黒いシカの報告もあります 3。これらはすべて、それぞれの種内で独立して生じたメラニズムの例です。
- 鳥類: 特に注目すべきは、インドネシア原産の鶏「アヤム・セマニ」です。この鶏は「線維性メラノーシス(Fibromelanosis)」という優性遺伝子を持ち、その影響で羽毛、くちばし、皮膚だけでなく、肉や内臓、骨に至るまで全身が真っ黒になります 6。これはメラニズムの一つの極端な形と言えるでしょう。その他にも、黒いペンギンやキジの存在も報告されています 2。
- 爬虫類: ヨーロッパアダー(クサリヘビの一種)やガータースネークなどのヘビ類では、黒い個体がしばしば観察されます。これらの変温動物にとって、黒い体色は第3章で述べた「熱的メラニズム仮説」による体温調節の利点が、生存における重要な選択要因となっていると考えられています 2。
ヒトにおけるメラニズムについて
ここで、私たちヒトについて触れておくことは重要です。動物で見られるような、単一の遺伝子変異によって全身が黒くなる完全なメラニズムは、ヒトには存在しません。ヒトの肌の色は「多因子遺伝」であり、多数の遺伝子が複雑に関与し合って決まる、連続的なスペクトラム(色の濃淡)として現れます 6。したがって、「メラニズムの人間」という概念は生物学的には当てはまりません。ただし、ポイツ・ジェガース症候群のように、特定の遺伝性疾患によって唇や口腔粘膜に色素斑(メラノーシス)が現れることはありますが、これは全身の黒化とは異なる病的な状態です 6。
結論:進化が描いた黒という筆跡
本稿では、多くの人々を魅了する「黒光り」の現象、メラニズムの謎を、遺伝子のスイッチから進化の戦略まで、多角的に解き明かしてきました。黒豹という神秘的な存在が、実は特定の種ではなく、ヒョウやジャガーに見られる遺伝的な色彩変異であることを出発点に、その背後にある科学的真実を探求してきました。
その核心には、精巧な分子メカニズムがありました。MC1R受容体を「ON」に、ASIPタンパク質を「OFF」にするという色素生成のスイッチボードがあり、進化はこのシステムの異なる部分を操作することで、同じ「黒」という表現型を繰り返し生み出してきたのです。ジャガーはMC1Rを恒常的にONにすることで、ヒョウはASIPというOFFスイッチを壊すことで、そしてオオシモフリエダシャクは全く別のcortex遺伝子へのトランスポゾンの挿入によって、それぞれ黒い姿を獲得しました。これは、異なる系統が独立して同じような形質を獲得する「収斂進化」の力強さを物語っています。自然選択は、環境という課題に対し、一つの決まった答えではなく、複数の解決策を見つけ出すことができるのです。
そして、その「黒」という色が持つ意味は、決して一様ではありませんでした。工業地帯の蛾にとっては鳥の目から逃れるための「保護色」であり、寒冷地のヘビにとっては太陽熱を効率的に吸収するための「ソーラーパネル」であり、そして密林の捕食者にとっては獲物に忍び寄るための「ステルス迷彩」でした。さらに、その背後には免疫力の向上といった、目には見えない「隠れた利点」が潜んでいる可能性も示唆されました。
しかし、進化の物語は単純な成功譚ではありません。あらゆる利点にはコストが伴い、メラニズムもまた、環境との間で繰り広げられる「トレードオフ」の産物です。ある状況で有利な形質が、別の状況では不利になりうる。この絶え間ないバランス調整こそが、生命の多様性を生み出す原動力なのです。
私たちが「かっこいい」と感嘆するその漆黒の輝きは、単なる美的な魅力に留まりません。それは、目には見えない遺伝子の変異と、何百万年にもわたる生存競争という、壮大な進化のサーガが刻み込まれた、生きた証なのです。進化という偉大な芸術家が、DNAという普遍的な言語を用いて描いた、力強く、そして美しい一筆。それが、メラニズムの正体と言えるでしょう。
引用文献
- Unveiling the Myth: Black Panthers Revealed as Mystical Melanistic Leopards and Jaguars, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.turpentinecreek.org/unveiling-the-myth-black-panthers-revealed-as-mystical-melanistic-leopards-and-jaguars/
- Melanistic Animals Pictures & Facts, What Is Melanism In Animals? – Active Wild, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.activewild.com/melanistic-animals/
- 10 Incredible Melanistic (All Black) Animals – TwistedSifter, 7月 20, 2025にアクセス、 https://twistedsifter.com/2012/02/10-incredible-melanistc-all-black-animals/
- Black panther – Wikipedia, 7月 20, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Black_panther
- Panther vs. Jaguar: Kind of Like Saying ‘Apple vs. Granny Smith’ – Animals | HowStuffWorks, 7月 20, 2025にアクセス、 https://animals.howstuffworks.com/mammals/panther-vs-jaguar.htm
- Melanism – Wikipedia, 7月 20, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Melanism
- Melanism Definition and Examples – Biology Online Dictionary, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.biologyonline.com/dictionary/melanism
- Evolutionary History and Climatic Correlates of Hypermelanism in …, 7月 20, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12000682/
- MC1R, the cAMP pathway and the response to solar UV: Extending the horizon beyond pigmentation – PubMed Central, 7月 20, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4150834/
- What decides between the synthesis of eumelanin and pheomelanin on a biochemical level? – Biology Stack Exchange, 7月 20, 2025にアクセス、 https://biology.stackexchange.com/questions/49291/what-decides-between-the-synthesis-of-eumelanin-and-pheomelanin-on-a-biochemical
- The dark side of birds: melanism—facts and fiction – BioOne Complete, 7月 20, 2025にアクセス、 https://bioone.org/journals/bulletin-of-the-british-ornithologists-club/volume-137/issue-1/bboc.v137i1.2017.a9/The-dark-side-of-birds-melanismfacts-and-fiction/10.25226/bboc.v137i1.2017.a9.full
- MC1R gene: MedlinePlus Genetics, 7月 20, 2025にアクセス、 https://medlineplus.gov/genetics/gene/mc1r/
- Agouti-signaling protein – Wikipedia, 7月 20, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Agouti-signaling_protein
- Loop Swapped Chimeras of the Agouti-related Protein (AgRP) and the Agouti Signaling Protein (ASIP) Identify Contacts Required for Melanocortin 1 Receptor (MC1R) Selectivity and Antagonism – PubMed Central, 7月 20, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2972358/
- How Often Can Big Cats Be Black? | Panthera, 7月 20, 2025にアクセス、 https://panthera.org/blog-post/how-often-can-big-cats-be-black
- Black Panthers are not separate species, but simply Leopards or Jaguars (Pictured) born with an increased amount of dark pigments. In Jaguars these melanistic genes can be inherited & even passed down if said gene is dominant. Thus siblings in the same litter can be born with different coloured fur. : r/Awwducational – Reddit, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/Awwducational/comments/jcqkvg/black_panthers_are_not_separate_species_but/
- How the Leopard Hides Its Spots: ASIP Mutations and Melanism in Wild Cats | PLOS One, 7月 20, 2025にアクセス、 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0050386
- Panthers & Pumas Explained | Big Cat Conversations, 7月 20, 2025にアクセス、 https://bigcatconversations.com/panthers-pumas-explained/
- Peppered moth evolution – Wikipedia, 7月 20, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Peppered_moth_evolution
- Peppered Moths: Natural Selection – Ask A Biologist, 7月 20, 2025にアクセス、 https://askabiologist.asu.edu/games-sims/peppered-moths-game/natural-selection.html
- Peppered Moth and natural selection | Butterfly Conservation, 7月 20, 2025にアクセス、 https://butterfly-conservation.org/moths/why-moths-matter/amazing-moths/peppered-moth-and-natural-selection
- Industrial Melanism – UCL, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.ucl.ac.uk/~ucbhdjm/courses/b242/OneGene/peppered.html
- Science as Process or Dogma? The Case of the Peppered Moth – The Nature Institute, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.natureinstitute.org/article/craig-holdrege/science-as-process-or-dogma-the-case-of-the-peppered-moth
- Peppered moth | Industrial Melanism, Camouflage, Evolution | Britannica, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.britannica.com/animal/peppered-moth
- Darwin’s Moth: Classic Textbook Example of ‘Evolution in Action’ Confirmed | Sci.News, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.sci.news/biology/industrial-melanism-06329.html
- The industrial melanism mutation in British peppered moths is a …, 7月 20, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27251284/
- Melanism: Evolution in Action – ResearchGate, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/375309468_Melanism_Evolution_in_Action
- Thermal environment shapes cuticle melanism and melanin-based immunity in the ground cricket Allonemobius socius – ResearchGate, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/257561612_Thermal_environment_shapes_cuticle_melanism_and_melanin-based_immunity_in_the_ground_cricket_Allonemobius_socius
- On the role of melanistic coloration on thermoregulation in the crepuscular gecko Eublepharis macularius | bioRxiv, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.05.18.541382v1.full-text
- On the role of melanistic coloration on thermoregulation in the crepuscular gecko Eublepharis macularius | bioRxiv, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.05.18.541382v1
- An Opposite Pattern to the Conventional Thermal Hypothesis: Temperature-Dependent Variation in Coloration of Adults of Saccharosydne procerus (Homoptera: Delphacidae) | PLOS One, 7月 20, 2025にアクセス、 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0128859
- Molecular Genetics and Evolution of Melanism in the Cat Family – ResearchGate, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/10871226_Molecular_Genetics_and_Evolution_of_Melanism_in_the_Cat_Family
- Paling in Comparison: The Role of Sex and Temperature in Melanin-Based Immune Function – University Digital Conservancy, 7月 20, 2025にアクセス、 https://conservancy.umn.edu/items/2ccbb9c8-fb6a-485c-a194-c02ba97c1bb2
- Increasing temperature reduces cuticular melanism and immunity to fungal infection in a migratory insect | Request PDF – ResearchGate, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/354602174_Increasing_temperature_reduces_cuticular_melanism_and_immunity_to_fungal_infection_in_a_migratory_insect
- Melanotan 1 peptide: Exploring its potential in scientific research – Roya News, 7月 20, 2025にアクセス、 https://en.royanews.tv/news/61343
- Melanocortin 1 Receptor (MC1R): Pharmacological and Therapeutic Aspects – PMC, 7月 20, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10418475/
- Where is Black an Advantage? | Geography of Melanistic Animals – YouTube, 7月 20, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=lBiNWCkzsSI
- 10 Incredible Melanistic (All Black) Animals – Pinterest, 7月 20, 2025にアクセス、 https://fr.pinterest.com/pin/492018328024446276/