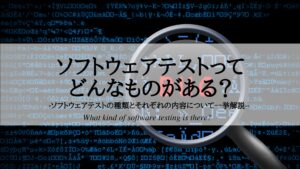序章:なぜ今、データフェッチ戦略がビジネスの成否を分けるのか
現代のデジタル社会において、アプリケーションの成功はユーザーエクスペリエンス (UX) に大きく依存しています。そのUXの中核を成すのが、アプリケーションがいかに迅速かつスムーズに情報を提示できるか、という点です。この情報の提示を技術的に支えているのが「データフェッチ」と呼ばれるプロセスです。
データフェッチとは、アプリケーションが必要な情報を取得するための行為です 1。例えば、ソーシャルメディアアプリが新しい投稿を読み込んだり、Eコマースサイトが商品リストを表示したりする、その裏側では必ずデータフェッチが行われています。このプロセスは、単なる技術的な実装の詳細にとどまらず、ビジネスの成果に直接的な影響を及ぼす重要な戦略的要素となっています 2。
効率的なデータフェッチ戦略は、ページの読み込み時間を短縮し、アプリケーションの応答性を高めます。これにより、ユーザーはストレスなくサービスを利用でき、エンゲージメント率やコンバージョン率の向上に繋がります 3。反対に、非効率な戦略は、遅延やもたつきを生み出し、ユーザーの離脱を招く最大の要因となり得ます 4。
この現象の根底にあるのは、「体感パフォーマンス」という概念です。ユーザーがアプリケーションを「速い」と感じるかどうかは、実際のデータ転送速度だけでなく、情報が提示されるまでの「待ち時間」をいかに感じさせないかにかかっています。例えば、画像が必要になる直前に読み込む「遅延読み込み (Lazy Loading)」や、ユーザーが要求する前にデータを先読みする「プリフェッチ (Prefetching)」といった技術は、まさにこの体感パフォーマンスを向上させるための戦略です 2。これらの戦略は、データフェッチという技術的な選択が、いかにユーザーの心理と密接に結びついているかを示しています。
しかし、最適なデータフェッチ戦略の選択は容易ではありません。開発者体験 (DX)、アプリケーションのパフォーマンス、そしてアーキテクチャの複雑さとの間には、常にトレードオフの関係が存在します。本稿では、この複雑な領域を解き明かすことを目指します。基本的な概念から最先端の技術、そして未来の展望までを網羅的に解説し、プロジェクトマネージャー、エンジニアリングマネージャー、エンジニア、そしてビジネスサイドのステークホルダーまで、あらゆる立場の方々が自社のプロジェクトに最適な意思決定を下すための一助となることを目的とします。


第1部:データフェッチの基本原理とAPIの世界
データフェッチ戦略を理解するためには、まずその根幹をなす技術的な対話の仕組み、すなわちAPIの役割を把握する必要があります。ここでは、非技術者にも分かりやすいアナロジーを交えながら、その基本原理を解説します。
1.1. クライアントとサーバーの対話:APIとは何か?
API (Application Programming Interface) とは、異なるソフトウェアアプリケーション同士が情報を交換し、連携するための「見えない橋渡し役」や「デジタル世界のウェイター」に例えることができます 6。ユーザーがレストランでウェイターに注文を伝えると、ウェイターが厨房にその注文を届け、完成した料理を席まで運んでくるように、APIはアプリケーションからの要求(リクエスト)を受け取り、それを別のシステムに伝達し、結果(レスポンス)を返す役割を担います 6。
この対話には、主に二つの登場人物が存在します。
- クライアント (Client): 情報を「求める側」です。私たちが日常的に使用するウェブブラウザやスマートフォンアプリがこれにあたります 7。
- サーバー (Server): 情報を「提供する側」であり、データベースなどの情報源を管理しています。クライアントからの要求を処理し、必要なデータを返します 7。
このクライアントとサーバー間のやり取りは、一般的に以下のステップで構成されます 6。
- APIリクエスト (Request): クライアントが、特定の情報を求めてサーバーに「注文」を出します。
- 処理 (Processing): サーバーがそのリクエストを受け取り、内容を解釈して必要な処理(データの検索など)を実行します。
- APIレスポンス (Response): サーバーが処理結果をクライアントに返します。これには要求されたデータや、処理が成功したかどうかの情報が含まれます。
- エラーハンドリング (Error Handling): もしリクエストが失敗した場合(例:要求された情報が存在しない)、サーバーはエラー情報を返し、クライアントはそれに応じて適切な対応(エラーメッセージの表示など)を行います。
この一連の対話の中で、いくつかの重要な専門用語が登場します。
- エンドポイント (Endpoint): APIがリクエストを受け付ける特定のURLのことです。大きな建物に複数のドアがあり、それぞれが異なる部屋に通じているように、APIもエンドポイントごとに異なる機能やリソースへの入り口を提供します 7。
- ペイロード (Payload): リクエストやレスポンスに含まれる主要なデータ本体のことです。運送業界でトラックが運ぶ「積み荷」に由来する言葉です 7。
1.2. Webの共通言語:HTTPメソッドとステータスコード
APIを介したクライアントとサーバーの対話は、HTTP (Hypertext Transfer Protocol) という共通のプロトコル(通信規約)に則って行われます 7。この対話で使われるのが「HTTPメソッド」と「HTTPステータスコード」です。
HTTPメソッドは、クライアントがサーバーに「何をしてほしいか」を伝える動詞のような役割を果たします。主なメソッドには以下のようなものがあります 7。
- GET: サーバーからデータを取得する(読み取り)。
- POST: サーバーに新しいデータを追加する(作成)。
- PUT / PATCH: サーバー上の既存のデータを更新する(PUTは全体置換、PATCHは部分修正)。
- DELETE: サーバー上のデータを削除する。
HTTPステータスコードは、サーバーからのレスポンスに含まれる3桁の数字で、リクエストが成功したか、失敗したか、その理由を示します。これにより、クライアントは機械的に処理結果を判断できます 8。
- 2xx (成功): 200 OK など。リクエストが成功したことを示します。
- 4xx (クライアントエラー): 404 Not Found(要求されたリソースが見つからない)、401 Unauthorized(認証が必要)など。クライアント側の問題を示します。
- 5xx (サーバーエラー): 500 Internal Server Error など。サーバー側で予期せぬエラーが発生したことを示します。
これらの基本的なルールを理解することは、データフェッチの挙動を把握し、問題が発生した際のトラブルシューティングを行う上で不可欠です。
1.3. JavaScriptの標準機能:Fetch APIの役割と限界
Webフロントエンド開発において、データフェッチを実行するための最も基本的なツールが、JavaScriptに標準で組み込まれているFetch APIです 1。これは、
XMLHttpRequestに代わる現代的なインターフェースであり、非同期処理をより扱いやすくするPromiseベースで設計されています 10。
fetch()関数は、指定されたURLに対してネットワークリクエストを非同期で行います。非同期であるため、データの取得中にブラウザのUIが固まってしまう(ブロッキング)のを防ぎ、ユーザー体験を損なうことなくバックグラウンドで処理を実行できます 1。
基本的な使用法は非常にシンプルです。
JavaScript
fetch(‘https://api.example.com/data’)
.then(response => response.json()) // レスポンスをJSON形式に変換
.then(data => console.log(data)) // データを処理
.catch(error => console.error(‘Error:’, error)); // ネットワークエラーを処理
このfetch()はデータフェッチのまさに土台となる機能ですが、これ単体で複雑なアプリケーションを構築するにはいくつかの限界があります。この限界こそが、後述する高度なデータフェッチライブラリやアーキテクチャが登場した背景を物語っています。
fetch()の主な限界点:
- 手動の状態管理: データの読み込み中 (loading)、成功 (success)、失敗 (error) といった状態を、開発者が手動で管理する必要があります(例:useStateフックなどを使用) 11。
- エラーハンドリングの煩雑さ: fetch()は、サーバーが404 Not Foundや500 Internal Server Errorのようなエラーレスポンスを返した場合でも、ネットワークエラーとは見なさず、Promiseをrejectしません。そのため、開発者はレスポンスのokプロパティなどをチェックして、手動でエラー処理を実装する必要があります 9。
- キャッシュ機能の欠如: fetch()には、取得したデータをキャッシュする機能が組み込まれていません。同じデータを再度要求すると、その都度ネットワークリクエストが発生してしまいます 12。
- リクエストの重複排除 (Deduplication) がない: 複数のコンポーネントが短時間に同じデータを要求した場合、fetch()はそれぞれの要求に対して個別のリクエストを送信してしまいます 13。
これらの課題は、アプリケーションが大規模かつ複雑になるにつれて、コードの冗長化やバグの温床となります。fetch()が提供するのは、あくまで一度きりのデータ取得という「点」の機能です。しかし、実際のアプリケーションでは、データは「時間とともに変化する状態(サーバー状態)」として存在します。データが古くなったり、他のユーザーによって更新されたり、複数の場所で必要とされたりします。この「サーバー状態」のライフサイクル全体を管理するという「線」や「面」の課題を解決するために、より高度なツールが必要とされるのです。
第2部:APIアーキテクチャの三大潮流:REST, GraphQL, tRPC
データフェッチ戦略を決定する上で、クライアントとサーバーがどのようなルール(アーキテクチャ)で対話するかは極めて重要です。この選択は、開発効率、パフォーマンス、そして将来のスケーラビリティに大きな影響を与えます。ここでは、現代のAPI設計における三大潮流であるREST、GraphQL、そしてtRPCを比較検討します。
これらのアーキテクチャの選択は、本質的に「クライアントとサーバー間の契約を、どこに、どのように定義し管理するか」という問題に帰結します。この視点を持つことで、技術的な選択がプロジェクトのプロセスやチーム構造にどう影響するかを理解できます。
2.1. 伝統的な巨人:REST API
REST (Representational State Transfer) は、長年にわたりWeb APIの設計における事実上の標準とされてきたアーキテクチャスタイルです 14。その中心的な思想は、すべての情報を「リソース」として扱い、それぞれに一意のURL(エンドポイント)を割り当てるというものです 7。例えば、
/users/123は特定のユーザーを、/productsは商品の一覧を表します。
RESTはHTTPメソッド(GET, POST, PUT, DELETE)を直感的に利用し、そのシンプルさと広く普及している点から、多くの開発者にとって馴染み深い存在です。フロントエンドとバックエンドが明確に分離されたプロジェクトや、既存の外部APIを利用する際には、依然として非常に有効な選択肢です 14。
しかし、クライアントアプリケーションが多様化し、要求が複雑化するにつれて、RESTの硬直的な構造が引き起こす二つの大きな課題が浮き彫りになりました。「オーバーフェッチング」と「アンダーフェッチング」です。
- オーバーフェッチング (Over-fetching): クライアントが必要とする以上のデータをAPIが返してしまう問題です 15。例えば、ユーザーの名前とプロフィール画像だけを表示したいモバイルアプリが
/api/users/123というエンドポイントを叩いたとします。このエンドポイントがユーザーの住所、購入履歴、電話番号など、全ての情報を含む巨大なオブジェクトを返すように設計されている場合、アプリは不要なデータを大量に受信することになります。これは特にモバイルのような帯域幅が限られた環境では、パフォーマンスの低下に直結します 17。 - アンダーフェッチング (Under-fetching): 一つの画面を表示するために、クライアントが複数のAPIリクエストを送信しなければならない問題です 16。例えば、ユーザーのプロフィールページにそのユーザーの投稿一覧も表示したい場合を考えます。まず
GET /api/users/123でユーザー情報を取得し、そのレスポンスを待ってから、次にGET /api/users/123/postsで投稿一覧を取得する必要があります。このように、リクエストが連鎖的に発生する現象は「リクエストウォーターフォール」と呼ばれ、ページの表示完了までの時間を著しく増加させます 18。
RESTにおける「契約」は、各エンドポイントの仕様として暗黙的に存在し、Swagger/OpenAPIのような外部ツールによって文書化されます。クライアントは、この固定された契約に一方的に従う必要があり、その柔軟性のなさが上記の問題を引き起こす根源となっています。
2.2. 柔軟性の革命:GraphQL
GraphQLは、Facebook(現Meta)によって開発され、2015年にオープンソース化されたAPIのためのクエリ言語です 19。RESTが抱えるオーバーフェッチングとアンダーフェッチングの問題を解決するために生まれました。
GraphQLの最大の特徴は、クライアントにデータの要求権限を委譲する点にあります 20。RESTのようにサーバー側が固定のデータ構造を返すのではなく、クライアントが必要なデータの構造を「クエリ」として記述し、送信します。サーバーは、そのクエリを解釈し、要求されたデータだけを、要求された通りの構造で返すのです 19。これにより、単一のリクエストで複数のリソースから必要なデータだけを効率的に取得でき、オーバー/アンダーフェッチングの問題が原理的に解決されます 15。
GraphQLのアーキテクチャは、以下の三つの核となる要素で構成されます。
- スキーマ (Schema): APIで利用可能なデータの型や関係性を定義した、厳密な「契約書」です。このスキーマが、クライアントとサーバー間の唯一の真実の情報源 (Single Source of Truth) となります 19。
- クエリ (Query): クライアントがデータを要求するために使用する言語です。スキーマに定義された構造に従って、欲しいデータを指定します。
- リゾルバ (Resolver): スキーマの各フィールドに対応するサーバー側の関数で、実際にデータを取得または加工するロジックが記述されます 19。
GraphQLにおける「契約」は、schema.graphqlという単一の、明確で、機械可読なファイルに集約されます。この強力な契約システムが柔軟性を生み出す一方で、新たな種類の複雑性ももたらします。その代表例が「N+1問題」です。
- N+1問題: GraphQLの柔軟なクエリが、意図せずして大量のデータベースアクセスを引き起こすパフォーマンス問題です 21。例えば、「10件のブログ投稿と、それぞれの投稿者名を取得する」というクエリを考えます。ナイーブな実装では、まず投稿を取得するために1回のデータベースクエリが実行され(これが「1」)、次に取得した10件の投稿それぞれに対して投稿者情報を取得するために10回の追加クエリが実行されます(これが「N」)。結果として、合計11回 (N+1) のデータベースアクセスが発生し、パフォーマンスが著しく劣化します 23。
この問題に対する標準的な解決策がDataLoaderというユーティリティです 21。DataLoaderは、同一リクエストサイクル内で発生した複数のデータ要求を一時的に集約(バッチ処理)し、一括でデータベースに問い合わせる仕組みを提供します。上記の例では、10人分の投稿者IDを一度に収集し、
SELECT * FROM users WHERE id IN (…)のような単一のクエリで解決することで、N+1問題を回避します 21。
GraphQLは、データの要求が複雑なアプリケーション、多様なクライアント(Web、iOS、Android)を持つサービス、あるいは複数のマイクロサービスからデータを集約するようなバックエンド・フォー・フロントエンド (BFF) 層の構築に特に適しています 14。
2.3. 型安全の究極形:tRPC
tRPC (TypeScript Remote Procedure Call) は、近年のフロントエンド開発、特にTypeScriptエコシステムにおいて急速に支持を広げている新しいAPI構築手法です 25。その最大の特徴は、
スキーマ定義やコード生成を一切行わずに、エンドツーエンドでの型安全性を実現する点にあります 26。
tRPCの「魔法」は、TypeScriptの強力な型推論機能を最大限に活用することにあります 25。開発者は、サーバー側でTypeScriptの関数としてAPIのロジック(プロシージャと呼ばれる)を定義します。するとtRPCは、その関数の型定義を自動的に推論し、クライアント側でそのプロシージャを呼び出す際に、引数や返り値の型が完全に保証された状態で利用できるようにします 28。
TypeScript
// — サーバーサイド (例: Next.js API Route) —
import { initTRPC } from ‘@trpc/server’;
import { z } from ‘zod’;
const t = initTRPC.create();
export const appRouter = t.router({
getUser: t.procedure
.input(z.object({ userId: z.string() }))
.query(({ input }) => {
// データベースからユーザーを取得するロジック
return { id: input.userId, name: ‘John Doe’ };
}),
});
export type AppRouter = typeof appRouter;
// — クライアントサイド (例: React Component) —
import { createTRPCReact } from ‘@trpc/react-query’;
import type { AppRouter } from ‘./server’; // サーバーから型定義をインポート
const trpc = createTRPCReact<AppRouter>();
function UserProfile() {
// `userId`がstringでないとコンパイルエラーになる
// `data`は`{ id: string; name: string } | undefined`型として推論される
const { data, isLoading } = trpc.getUser.useQuery({ userId: ‘123’ });
if (isLoading) return <div>Loading…</div>;
return <div>User: {data?.name}</div>;
}
このアプローチがもたらす開発者体験 (DX) は絶大です 26。
- 究極のオートコンプリート: クライアント側でAPIを呼び出す際、エディタがプロシージャ名、引数、その型を完璧に補完します。
- リファクタリングの安全性: サーバー側のプロシージャ名を変更したり、引数の型を変えたりすると、即座にクライアント側のコードでコンパイルエラーが発生します。これにより、APIの仕様変更に起因するランタイムエラーを撲滅できます。
- ボイラープレートの削減: スキーマ定義ファイルや、それを基にしたコード生成のステップが不要になり、開発プロセスが大幅に簡素化されます 27。
tRPCにおける「契約」は、TypeScriptの型システムそのものです。クライアントとサーバーは型を通じて密結合し、その契約はコンパイラによって開発時に強制されます。この仕組みは驚異的な開発速度をもたらしますが、その代償としてアーキテクチャの柔軟性が失われます。
tRPCは、フロントエンドとバックエンドの両方をTypeScriptで開発し、かつそれらが単一のリポジトリ(モノレポ)で管理されているプロジェクトに最適です 14。逆に、公開APIの提供や、フロントエンドとバックエンドで異なるプログラミング言語を使用するような、疎結合が求められるアーキテクチャには不向きです 28。
第3部:クライアントサイドの覇権争い:React Query vs. SWR
APIアーキテクチャが定まっても、クライアント側でのデータフェッチの課題がすべて解決するわけではありません。むしろ、取得したデータをいかに効率的に管理し、UIに反映させるかという新たな課題が生まれます。この領域は「サーバー状態管理 (Server State Management)」と呼ばれ、React QueryとSWRという二つのライブラリがデファクトスタンダードの地位を巡って競い合っています。
3.1. サーバー状態管理という課題
まず、なぜこれらのライブラリが必要なのかを理解することが重要です。前述の通り、fetch APIだけでは、データのライフサイクル全体を管理するのは困難です。この「サーバーから取得した状態」は、UIを操作するためのクライアント内部の状態(例:モーダルの開閉状態)とは根本的に性質が異なります 13。
サーバー状態の主な特徴 13:
- リモートに存在する: データはクライアントの管理外の場所に永続化されている。
- 非同期で取得・更新される: データのやり取りにはネットワーク遅延が伴う。
- 所有権が共有されている: 他のユーザーやシステムによって、いつデータが変更されるか分からない。
- 古くなる可能性がある: クライアントが保持しているデータは、サーバー上の最新の状態と乖離する可能性がある。
これらの特性に対処するため、開発者は通常、以下のような複雑なロジックを自前で実装する必要がありました 13。
- キャッシュ管理
- リクエストの重複排除
- バックグラウンドでのデータ更新
- ページネーションや無限スクロールの実装
- UIの楽観的更新 (Optimistic Updates)
React QueryやSWRは、これらの定型的で複雑な処理を抽象化し、堅牢なフックベースのAPIとして提供することで、開発者をサーバー状態管理の苦悩から解放します。
3.2. SWR:Vercelが提唱する「stale-while-revalidate」哲学
SWRは、Next.jsを開発するVercel社によって作られた、軽量なデータフェッチのためのReactフックライブラリです 29。その名称は、HTTPのキャッシュ戦略の一つである
stale-while-revalidate (RFC 5861) に由来しており、この哲学がライブラリの核となっています 31。
stale-while-revalidateの動作フローは以下の通りです 31。
- Stale (古いデータ) を返す: コンポーネントがマウントされると、まずキャッシュ内にデータがあれば、その「古い (stale)」データを即座に返してUIを描画します。これにより、ユーザーはローディング画面を待つことなく、すぐに何らかのコンテンツを見ることができます。
- Revalidate (再検証): 同時に、バックグラウンドでデータ取得リクエスト(fetcher関数)を送信し、データが最新であるかを「再検証 (revalidate)」します。
- 最新データを返す: リクエストが完了し、新しいデータが取得できれば、キャッシュを更新し、UIを最新の状態に再レンダリングします。
このアプローチにより、アプリケーションの応答性とデータの一貫性を高いレベルで両立させることができます。ユーザーは常に高速なUIを体験しつつ、データは自動的に最新の状態に保たれます 31。
SWRの主な特徴 29:
- シンプルなAPI: useSWR(key, fetcher)という非常にシンプルなフックで利用を開始できます。
- 軽量: バンドルサイズが比較的小さく、パフォーマンスを重視するプロジェクトに適しています 33。
- 自動再検証: 画面にフォーカスが戻った時や、ネットワーク接続が回復した際に、自動的にデータを再検証する機能が組み込まれています。
- リクエストの重複排除: 同じkeyを持つuseSWRフックが短時間に複数回呼び出されても、リクエストは一つにまとめられます。
3.3. React Query (TanStack Query):機能豊富なデータ管理のデファクトスタンダード
React Query(現在はTanStack Queryとしてフレームワーク非依存のライブラリに進化)は、SWRよりも包括的で機能豊富なサーバー状態管理ライブラリです 13。単なるデータフェッチにとどまらず、「サーバー状態を管理するための完全なツールキット」と位置づけられています 30。
React Queryは、SWRが提供する基本的な機能に加え、より複雑なユースケースに対応するための高度な機能を多数搭載しています。
- 強力なミューテーション (Mutation) 機能: useMutationフックは、データの作成・更新・削除 (CRUD) 処理を扱うために設計されています。楽観的更新(サーバーの応答を待たずにUIを先行して更新する機能)、エラーハンドリング、成功時や失敗時のコールバック処理などを宣言的に記述できます 33。
- 柔軟なクエリ無効化 (Query Invalidation): ミューテーションが成功した後、関連するどのデータを「古くなった」とみなし、再取得(リフェッチ)させるかを柔軟に制御できます。これにより、UI全体でデータの一貫性を保つことが容易になります 33。
- 高度なページネーションと無限スクロール: useInfiniteQueryフックは、ページネーションや「もっと見る」形式の無限スクロールを実装するための専用APIを提供しており、複雑なページ管理ロジックを大幅に簡素化します 30。
- DevTools: 開発中にクエリの状態、キャッシュの内容、データの更新履歴などを視覚的に確認できる専用の開発ツールが提供されています。これは、複雑なデータフローのデバッグにおいて非常に強力な武器となります 35。
React Queryの設計思想は、ライブラリというよりも「フレームワーク」に近いです。サーバー状態の管理方法について独自の意見(例:クエリキーを依存配列として扱う、staleTimeとcacheTimeによるキャッシュのライフサイクル管理など)を持っており、開発者はそのレールに乗ることで、ベストプラクティスに沿った堅牢な実装を効率的に進めることができます 13。
3.4. 徹底比較:あなたのプロジェクトに最適なのはどちらか?
SWRとReact Queryは、どちらも優れたライブラリですが、その設計思想と機能セットには明確な違いがあります。プロジェクトの要件に応じて適切なツールを選択することが重要です。以下の比較表は、その意思決定を支援するためのものです 30。
| 特徴 | SWR | React Query (TanStack Query) |
| バンドルサイズ | 比較的小さい (約15KB) 33 | 比較的大きい (約50KB) 33 |
| 基本思想 | stale-while-revalidateによるシンプルさと高速なUI応答 30 | 包括的なサーバー状態管理フレームワーク 13 |
| キャッシュ戦略 | シンプルなキャッシュと自動再検証 32 | staleTimeとcacheTimeによる詳細なキャッシュライフサイクル制御が可能 36 |
| ミューテーション | 手動での実装が必要。mutate APIは提供されるが、ロジックは開発者が記述 33 | useMutationフックによる組み込みサポート。楽観的更新、ロールバック機能も提供 35 |
| ページネーション | 基本的なサポート。無限スクロールはuseSWRInfiniteで可能だが、より手動のロジックが必要 38 | useInfiniteQueryによる高度な組み込みサポート。ページ管理が容易 30 |
| 開発ツール | 組み込みのDevToolsはなし 35 | 強力で視覚的な専用DevToolsが付属 35 |
| 学習コスト | 緩やか。APIがシンプルで覚えやすい 33 | やや急。機能が豊富なため、概念の理解に時間が必要 33 |
| 最適な用途 | シンプルなアプリケーション、読み取り中心のデータ、Next.jsとの親和性 30 | 複雑なアプリケーション、データの更新が頻繁、堅牢な状態管理やデバッグ機能が必要な場合 30 |
この比較から分かるように、SWRは「ライブラリ」として、データフェッチの強力な基本機能を提供し、開発者に実装の自由度を与えます。一方、React Queryは「フレームワーク」として、サーバー状態管理に関する一般的な課題に対する網羅的な解決策を、ある程度「型にはまった」形で提供します。
したがって、技術選定の際には、「我々のチームは、定型的な課題に対して確立されたベストプラクティスに乗りたいのか(→React Query)、それとも独自の要件に合わせて柔軟に構築できる最小限のツールを求めているのか(→SWR)」という、チームの文化やプロジェクトの性質を問うことが重要になります。
第4部:パラダイムシフト:サーバーコンポーネントと未来のデータフェッチ
これまで議論してきたデータフェッチ戦略は、主にクライアントサイドで実行されることを前提としていました。しかし、Reactエコシステムは今、大きなパラダイムシフトの最中にあります。React Server Components (RSC) の登場により、データフェッチが行われる「場所」と「タイミング」が根本的に変わりつつあります。この変化は、フロントエンドアプリケーションのアーキテクチャそのものを再定義する可能性を秘めています。
このパラダイムシフトは、従来のフロントエンドのモノリシックな構造を「解体 (Unbundling)」する動きと捉えることができます。これまでクライアントに一括で送られていた描画ロジック、データフェッチロジック、インタラクションロジックを分離し、それぞれを最適な場所で実行することで、パフォーマンスと開発者体験の双方を向上させることを目指しています。
4.1. React Server Components (RSC)の登場
React Server Components (RSC) とは、その名の通り、サーバー上でのみ実行されるように設計された新しいタイプのReactコンポーネントです 11。RSCのコードはクライアントに送信されるJavaScriptバンドルに一切含まれず、インタラクティブな機能(
useStateやuseEffectなどのフック、イベントハンドラなど)を持つことはできません 41。
RSCがもたらす主な利点は以下の通りです。
- クライアントバンドルサイズの削減: コンポーネントのロジックがクライアントに送られないため、ダウンロードとパースが必要なJavaScriptの量を大幅に削減できます。これにより、特に低速なネットワークや低スペックなデバイスでの初期表示速度が劇的に向上します 11。
- バックエンドへの直接アクセス: RSCはサーバー環境で実行されるため、API層を介さずにデータベース、内部サービス、ファイルシステム、あるいは環境変数などのバックエンドリソースに安全に直接アクセスできます。これにより、データ取得のためのAPIを別途用意する必要がなくなり、アーキテクチャがシンプルになります 41。
- パフォーマンスの向上: データフェッチとコンポーネントのレンダリングがサーバーサイドで完結し、生成されたHTMLがクライアントに送信されます。これにより、クライアント側でのデータ取得に起因するリクエストウォーターフォールを回避し、初期表示までの時間を短縮できます 11。
4.2. Next.jsにおけるデータフェッチの進化
このRSCという新しいパラダイムを、本番環境で利用可能な形で強力に推進しているのが、ReactフレームワークのNext.jsです。Next.js 13で導入されたApp Routerは、RSCをデフォルトのコンポーネントモデルとして採用し、データフェッチの方法を根本から変えました 41。
従来のPages Routerでは、getServerSidePropsやgetStaticPropsといった特別な関数をページ単位でエクスポートしてサーバーサイドでのデータ取得を行っていました 46。しかし、App Routerでは、コンポーネント自体を
async関数として定義し、その中でawaitを使って直接データフェッチを行うのが標準的なスタイルとなります 43。
TypeScript
// app/blog/page.tsx (React Server Component)
async function getPosts() {
const res = await fetch(‘https://api.example.com/posts’, { cache: ‘no-store’ });
return res.json();
}
export default async function BlogPage() {
const posts = await getPosts(); // サーバーサイドでデータを直接フェッチ
return (
<ul>
{posts.map(post => (
<li key={post.id}>{post.title}</li>
))}
</ul>
);
}
この新しいモデルでは、データ依存関係の管理がより重要になります。特に、「逐次フェッチ」と「並列フェッチ」の使い分けがパフォーマンスに大きく影響します。
- 逐次データフェッチ (Sequential Data Fetching): あるコンポーネント内で複数のawaitを順番に記述すると、リクエストはウォーターフォールとなり、前のリクエストが完了するまで次のリクエストは開始されません 43。これは、あるフェッチが別のフェッチの結果に依存する場合に意図的に使用されますが、意図せず行うと不要な待機時間を生み出します 44。
- 並列データフェッチ (Parallel Data Fetching): 複数のデータ取得を同時に開始することで、全体の読み込み時間を短縮するパターンです。Promise.allを使用したり、データ取得の開始をコンポーネントの外で行ったりすることで実現できます 43。
TypeScript
// 並列フェッチの例
async function Page() {
// 両方のリクエストを同時に開始
const artistData = getArtist(‘…’);
const albumsData = getAlbums(‘…’);
// 両方の完了を待つ
const [artist, albums] = await Promise.all();
return <>…</>;
}
さらにNext.jsは、標準のfetch APIを拡張し、cacheオプションやnext: { revalidate: 3600 }といったプロパティを通じて、きめ細やかなキャッシュ戦略(永続的なキャッシュ、時間ベースの再検証など)を宣言的に指定できるようにしています 45。Vercelのプラットフォーム上では、このキャッシュがグローバルに分散されたData Cacheに保存され、さらなる高速化を実現します 48。
4.3. クライアントサイドフェッチの新たな役割
RSCの登場によって、クライアントサイドでのデータフェッチが不要になったわけではありません。むしろ、その役割がより専門的かつ明確になりました。
RSCが担うのは、主にページの初期表示に必要な、静的または非インタラクティブなデータの取得です。一方で、ユーザーの操作に応じて動的に変化するデータ、例えば検索結果、フィルターの適用、フォームの送信といったインタラクティブな処理には、依然としてクライアントサイドでのデータフェッチが必要です 47。
このハイブリッドモデルでは、”use client”ディレクティブをファイルの先頭に記述することで、コンポーネントをクライアントコンポーネントとして指定します。そして、そのクライアントコンポーネントの内部で、SWRやReact Queryといったライブラリを従来通り使用して、インタラクティブなデータフェッチを実装します 46。
つまり、現代のNext.jsアプリケーションは、以下のような構成を取ることが一般的です。
- ページの骨格や静的コンテンツ: RSCで構築し、サーバーサイドでデータフェッチとレンダリングを行う。
- インタラクティブな部分(島): クライアントコンポーネントで構築し、SWRやReact Queryを用いてクライアントサイドで動的なデータフェッチを行う。
このアーキテクチャは、サーバーレンダリングの高速な初期表示性能と、シングルページアプリケーション (SPA) の豊かなインタラクティビティを両立させるための、洗練された解決策と言えます。フロントエンド開発者は、サーバー環境で実行されるコードとクライアント環境で実行されるコードの両方を意識する必要があり、これはフロントエンドとバックエンドの境界線がますます曖昧になっていることを示唆しています。
第5部:包括的な意思決定フレームワークと戦略的提言
これまで、データフェッチに関する様々な技術やアーキテクチャを詳細に見てきました。しかし、最も重要なのは、これらの選択肢の中から自身のプロジェクトに最適な戦略をいかにして選び出すかです。この最終部では、技術選定のための意思決定フレームワークを提示し、未来のトレンドを展望します。
5.1. プロジェクト要件に応じた戦略選択
「最高のデータフェッチ戦略」というものは存在しません。最適な戦略は、プロジェクトのコンテキストに深く依存します。技術リーダーやマネージャーは、技術的な優劣だけでなく、ビジネスやチームの状況を踏まえた上で、以下のような問いを自問する必要があります 14。
- チーム構造と所有権 (Team & Ownership)
- フロントエンドとバックエンドを同じチームがTypeScriptで開発し、モノレポで管理しているか? → tRPCが強力な選択肢となる可能性があります。
- フロントエンドとバックエンドは別々のチームで、異なる言語やリポジトリで開発されているか? → RESTやGraphQLのような疎結合なアーキテクチャが適しています。
- APIの複雑性とデータ要件 (API Complexity & Data Requirements)
- 利用するのは、仕様が固定されたシンプルな既存のREST APIか? → REST API + React Query/SWRが現実的な構成です。
- 複数のマイクロサービスからデータを集約するような、複雑なBFF (Backend for Frontend) を新規に構築する必要があるか? → データの要求を柔軟に扱えるGraphQLが有力候補となります。
- アプリケーションの特性 (Application Type)
- ユーザーの操作に応じて頻繁にデータが更新される、インタラクティブなダッシュボードが中心か? → React Query/SWRを用いたクライアント中心の戦略が重要になります。
- ブログ、ニュースサイト、Eコマースの商品一覧ページなど、コンテンツの表示が中心か? → 初期表示速度に優れるRSC (React Server Components) を中心としたサーバー中心の戦略が効果的です。
- パフォーマンス目標 (Performance Goals)
- 最初のコンテンツが表示されるまでの時間 (TTFB, Time to First Byte) が最優先事項か? → RSC/SSR (Server-Side Rendering) が有利です。
- ユーザー操作後の応答性や体感パフォーマンスがより重要か? → 楽観的更新などが可能なクライアント中心の戦略が強みを発揮します。
これらの問いに答えることで、数ある選択肢の中から、プロジェクトの成功確率を最も高める戦略へと絞り込んでいくことができます 12。
5.2. 戦略比較マトリクス
個々の技術だけでなく、それらを組み合わせた全体的なアーキテクチャを比較することは、長期的な視点での意思決定に不可欠です。以下のマトリクスは、代表的な4つの戦略スタックを、技術リーダーが重視すべき戦略的な観点から比較したものです。
| 観点 | スタック1: REST + RQ/SWR | スタック2: GraphQL + Client | スタック3: tRPC | スタック4: RSC-First (Next.js) |
| 主要な特徴 | 伝統的で疎結合なSPAアーキテクチャ。クライアント側で高度な状態管理を行う。 | スキーマ駆動で柔軟なデータ取得が可能。クライアントがデータの主導権を握る。 | TypeScriptによるエンドツーエンドの型安全性を実現。開発者体験を最優先。 | サーバー中心のハイブリッドモデル。初期ロードはサーバー、インタラクションはクライアント。 |
| Over/Under-fetching | 発生する。 API設計に依存。クライアントライブラリでは解決不可。 | 解決される。 GraphQLの核となる機能。 | 発生しない。 プロシージャ呼び出しであり、エンドポイントの概念が異なる。 | 部分的に解決。 初期ロードはサーバーで最適化可能。クライアントフェッチでは発生しうる。 |
| エンドツーエンド型安全性 | 低い。 OpenAPI/Swagger等での手動連携が必要。 | 高い。 スキーマとコード生成により実現。 | 最高。 スキーマレスで、TypeScriptの型システムがそのまま契約となる。 | 高い。 Server ActionsやtRPCとの連携で実現可能。 |
| キャッシュの複雑性 | クライアント側に集中。 RQ/SWRが大部分を担う。HTTPキャッシュも利用可能。 | クライアント/ゲートウェイ。 Apollo/Relay等のクライアントが高度な正規化キャッシュを持つ。 | クライアント/サーバー。 RQ連携が一般的。サーバー側での実装も可能。 | サーバー側にシフト。 Next.jsのData Cacheが強力。クライアントキャッシュも併用。 |
| 開発者体験 (DX) | 中程度。 APIの仕様変更に弱いが、RQ/SWRのツールは強力。 | 高い。 スキーマがドキュメントとなり、ツールも豊富。ただしN+1問題など考慮点が多い。 | 最高。 圧倒的な補完機能とリファクタリング耐性。 | 高い。 ただしサーバーとクライアントの境界を意識する必要があり、学習コストがかかる。 |
| サーバー/クライアント結合度 | 低い。 明確に分離されており、独立して開発・デプロイ可能。 | 中程度。 スキーマという共有の契約を通じて結合。 | 高い。 型レベルで密結合。モノレポでの運用が前提。 | 高い。 サーバーとクライアントのコンポーネントが密接に連携する。 |
| 最適なプロジェクト | 標準的なSPA、バックエンドチームが別、既存APIの利用。 | 複雑なデータ要求、多様なクライアント、マイクロサービス集約。 | フルスタックTypeScript、モノレポ、高速なプロトタイピング。 | コンテンツ主体のサイト、Eコマース、パフォーマンスを最優先する新規プロジェクト。 |
5.3. 未来展望:エッジコンピューティングとAIによる最適化
データフェッチの世界は、今もなお進化を続けています。その進化の方向性は、「よりユーザーに近く、よりインテリジェントに」という言葉に集約できます。
- エッジでのデータフェッチ (Data Fetching at the Edge): 従来のサーバーは特定のデータセンターに置かれていましたが、エッジコンピューティングは、データフェッチのロジックを世界中に分散配置されたエッジサーバー(ユーザーに物理的に最も近いサーバー)で実行します 48。VercelやCloudflareのようなプラットフォームは、このエッジコンピューティングを容易に利用できるようにしており、物理的な距離に起因するネットワーク遅延を最小限に抑えることができます。これは、RSCのようなサーバー中心のアーキテクチャの自然な延長線上にあります 41。
- AIによる最適化 (AI-driven Optimization): 人工知能 (AI) は、フロントエンド開発、特にデータフェッチの最適化において、革命的な役割を果たすと期待されています。
- 予測フェッチ (Predictive Fetching): AIがユーザーの行動パターンを分析し、次に必要となるであろうデータを予測して事前に読み込むことで、体感的な待ち時間をゼロに近づけることができます 54。
- スマートキャッシング (Smart Caching): リアルタイムの利用状況に基づいて、キャッシュの有効期間 (TTL) や無効化のタイミングをAIが動的に調整し、常に最適なキャッシュ効率を維持します 55。
- 自動最適化とコード生成 (Automated Optimization & Code Generation): AIツールがコード内のデータフェッチパターンを解析し、逐次フェッチを並列フェッチに変換する提案をしたり、N+1問題の潜在的なリスクを自動で検出したりすることが可能になります 57。また、Vercelの
v0のようなツールは、自然言語のプロンプトからデータフェッチロジックを含むUIコンポーネントを生成し、開発の初速を劇的に向上させます 58。
これらの技術が目指す未来は、データフェッチという行為そのものが、開発者の意識から「消える」世界です。開発者は、コンポーネントが「どのデータを必要とするか」を宣言的に記述するだけでよくなります。そのデータを、いつ、どこから、どのように取得するのが最も効率的かという複雑な判断は、フレームワーク、プラットフォーム、そしてAIが協調して担うインフラストラクチャ層に委ねられていくでしょう。これは、開発者体験とユーザー体験の双方を究極的に向上させるという、データフェッチ戦略が追い求めてきた目標の、一つの到達点と言えるのかもしれません。
結論
本稿では、フロントエンドのデータフェッチ戦略について、その基本原理から最新のアーキテクチャ、クライアントサイドのライブラリ、そして未来の展望までを包括的に解説しました。
データフェッチはもはや単なる技術実装ではなく、ユーザー体験、アプリケーションパフォーマンス、ひいてはビジネスの成功を左右する戦略的な要諦です。その選択は、REST、GraphQL、tRPCといったAPIアーキテクチャの選定から、React QueryやSWRといったクライアントサイドでの状態管理、そしてReact Server Componentsがもたらすサーバー中心のパラダイムシフトまで、多岐にわたるトレードオフの考慮を必要とします。
- RESTは依然としてシンプルで堅牢な選択肢ですが、GraphQLは複雑なデータ要求に対する柔軟性を提供します。tRPCはTypeScriptエコシステム内での開発速度を極限まで高めます。
- クライアントサイドでは、SWRがシンプルさと高速な体感パフォーマンスを、React Queryが機能豊富な総合的なサーバー状態管理を提供します。
- そしてReact Server Componentsは、初期表示パフォーマンスを劇的に改善し、フロントエンドとバックエンドの境界を再定義する、最も注目すべき変化です。
最適な戦略は、プロジェクトの要件、チームのスキルセット、そして将来の拡張性といったコンテキストによって常に変化します。本稿で提示した意思決定フレームワークと戦略比較マトリクスが、読者の皆様が自身のプロジェクトにとって最良の道筋を見出すための一助となれば幸いです。
エッジコンピューティングとAIの台頭が示すように、データフェッチの未来は、より自動化され、よりインテリジェントな方向へと進んでいます。この絶え間ない進化の潮流を理解し、適切に対応していくことが、これからのフロントエンド開発において、競争優位性を確立するための鍵となるでしょう。
引用文献
- Learn Fetch API In 6 Minutes – YouTube, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=cuEtnrL9-H0
- Understanding Fetch in Web Development | Lenovo US, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.lenovo.com/us/en/glossary/what-is-fetch/
- How to Leverage Data for Better UX Design – PixelFreeStudio Blog, 7月 21, 2025にアクセス、 https://blog.pixelfreestudio.com/how-to-leverage-data-for-better-ux-design/
- How Do APIS Affect User Flow and UX? – Bliss Drive, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.blissdrive.com/people-also-asked/how-do-apis-affect-user-flow-and-ux/
- tagged by: front-end – Martin Fowler, 7月 21, 2025にアクセス、 https://martinfowler.com/tags/front-end.html
- API Integration for non-technical people: A Guide – Konnectify, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.konnectify.co/blogs/api-integration-non-technical-people-a-guide
- APIs: A Breakdown for Non Technical Product Managers | by Seyifunmi Olafioye – Medium, 7月 21, 2025にアクセス、 https://medium.com/design-bootcamp/apis-a-breakdown-for-non-technical-product-managers-6c3d7051107d
- A guide to API integrations for non-technical people – Hyperswitch, 7月 21, 2025にアクセス、 https://hyperswitch.io/blog/a-guide-to-api-integrations-for-non-technical-people
- Everything about Data Fetching & the JavaScript Fetch API. – DEV Community, 7月 21, 2025にアクセス、 https://dev.to/sammaji/everything-about-data-fetching-the-javascript-fetch-api-478
- Using the Fetch API – MDN Web Docs, 7月 21, 2025にアクセス、 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch
- use() and data fetching – Flavio Copes, 7月 21, 2025にアクセス、 https://flaviocopes.com/use-and-data-fetching/
- The Evolution of Data Fetching in React: Best Practices and Modern Approaches – Medium, 7月 21, 2025にアクセス、 https://medium.com/@roman_j/the-evolution-of-data-fetching-in-react-best-practices-and-modern-approaches-12614e5ffde2
- Overview | TanStack Query React Docs, 7月 21, 2025にアクセス、 https://tanstack.com/query/v5/docs/react/overview
- Data Fetching in React at Scale – Frontend Engineer Handbook, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.fe.engineer/handbook/data-fetching
- What Are Over-Fetching and Under-Fetching? – GeeksforGeeks, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.geeksforgeeks.org/graphql/what-are-over-fetching-and-under-fetching/
- What is Over-fetching and Under-fetching in APIs? | by Mukesh Rajput – Medium, 7月 21, 2025にアクセス、 https://medium.com/@rajputmukesh748/what-is-over-fetching-and-under-fetching-in-apis-96628332c64c
- Master GraphQL: Solve Overfetching & Underfetching – Expeed Software, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.expeed.com/mastering-data-fetching-with-graphql-overcome-over-fetching-under-fetching/
- GraphQL Doesn’t Solve Under & Overfetching – HackerNoon, 7月 21, 2025にアクセス、 https://hackernoon.com/graphql-doesnt-solve-under-and-overfetching
- Introduction to GraphQL | GraphQL, 7月 21, 2025にアクセス、 https://graphql.org/learn/
- GraphQL | A query language for your API, 7月 21, 2025にアクセス、 https://graphql.org/
- How to solve the graphql n+1 problem | Hygraph, 7月 21, 2025にアクセス、 https://hygraph.com/blog/graphql-n-1-problem
- The n+1 problem – GraphQL Tutorials, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.apollographql.com/tutorials/dataloaders-dgs/02-the-n-plus-1-problem
- The GraphQL performance killer (N+1 Problem) – Overstacked, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.overstacked.io/articles/why-you-need-graphql-dataloaders
- Solving the N+1 Problem with DataLoader – GraphQL.js, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.graphql-js.org/docs/n1-dataloader/
- tRPC – Starter Kit – Open Government Products, 7月 21, 2025にアクセス、 https://start.open.gov.sg/docs/concepts/trpc
- tRPC – Move Fast and Break Nothing. End-to-end typesafe APIs made easy. | tRPC, 7月 21, 2025にアクセス、 https://trpc.io/
- Understanding tRPC: Building Type-Safe APIs in TypeScript – Medium, 7月 21, 2025にアクセス、 https://medium.com/@ignatovich.dm/understanding-trpc-building-type-safe-apis-in-typescript-45258c6c3b73
- tRPC | tRPC, 7月 21, 2025にアクセス、 https://trpc.io/docs/
- Efficient Data Fetching in Next.js with SWR: A Comprehensive Guide | by @rnab | May, 2025, 7月 21, 2025にアクセス、 https://arnab-k.medium.com/using-swr-for-data-fetching-in-next-js-6e264a95c0e7
- React Query or SWR: Which is best in 2025? – DEV Community, 7月 21, 2025にアクセス、 https://dev.to/rigalpatel001/react-query-or-swr-which-is-best-in-2025-2oa3
- vercel/swr: React Hooks for Data Fetching – GitHub, 7月 21, 2025にアクセス、 https://github.com/vercel/swr
- Getting Started – SWR, 7月 21, 2025にアクセス、 https://swr.vercel.app/docs/getting-started
- SWR vs React Query: Choosing the Right Data Fetching Library …, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.gperrucci.com/en/blog/react/swr-vs-react-query
- react-query – NPM, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.npmjs.com/package/react-query
- Using SWR and React Query for Efficient Data Fetching in React – Medium, 7月 21, 2025にアクセス、 https://medium.com/@ignatovich.dm/using-swr-and-react-query-for-efficient-data-fetching-in-react-87f4256910f0
- useQuery | TanStack Query React Docs, 7月 21, 2025にアクセス、 https://tanstack.com/query/v4/docs/react/reference/useQuery
- Comparison | React Query vs SWR vs Apollo vs RTK Query vs React Router – TanStack, 7月 21, 2025にアクセス、 https://tanstack.com/query/v5/docs/react/comparison
- react-query swrjs alova In-Depth Comparison – DEV Community, 7月 21, 2025にアクセス、 https://dev.to/coderhu/in-depth-comparison-how-to-choose-the-most-suitable-enhanced-request-library-2p29
- Data on Demand: A Smackdown of SWR Vs. React Query – DhiWise, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.dhiwise.com/post/data-on-demand-a-smackdown-of-swr-vs-react-query
- Making Sense of React Server Components – Josh Comeau, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.joshwcomeau.com/react/server-components/
- The Future of Frontend: Why Server Components in Next.js Matter | by Sonila – Medium, 7月 21, 2025にアクセス、 https://medium.com/@sonilamohanty26/the-future-of-frontend-why-server-components-in-next-js-matter-e3e817618efa
- Boost Performance With React Server Components and Next.js – The New Stack, 7月 21, 2025にアクセス、 https://thenewstack.io/boost-performance-with-react-server-components-and-next-js/
- Data Fetching Patterns and Best Practices – Next.js, 7月 21, 2025にアクセス、 https://nextjs.org/docs/14/app/building-your-application/data-fetching/patterns
- Getting Started: Fetching Data | Next.js, 7月 21, 2025にアクセス、 https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/data-fetching/patterns
- Less code, better UX: Fetching data faster with the Next.js 13 App Router – Vercel, 7月 21, 2025にアクセス、 https://vercel.com/blog/nextjs-app-router-data-fetching
- Pre-Rendering and Data Fetching Strategies in Next.js – Telerik.com, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.telerik.com/blogs/pre-rendering-data-fetching-strategies-next-js
- Getting Started: Fetching Data – Next.js, 7月 21, 2025にアクセス、 https://nextjs.org/docs/app/getting-started/fetching-data
- Vercel Data Cache, 7月 21, 2025にアクセス、 https://vercel.com/docs/data-cache
- Next.js 14 Data Fetching with Images: A Comprehensive Guide – DEV Community, 7月 21, 2025にアクセス、 https://dev.to/wadizaatour/nextjs-data-fetching-with-images-a-comprehensive-guide-1061
- What’s your preferred way to fetch in client component fetching? : r/nextjs – Reddit, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/nextjs/comments/1efgyqt/whats_your_preferred_way_to_fetch_in_client/
- Comprehensive Guide to Data Fetching in Next.js – Fishtank, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.getfishtank.com/insights/comprehensive-guide-to-data-fetching-in-nextjs
- How to Implement Efficient Data Fetching between Client, API, and Database?, 7月 21, 2025にアクセス、 https://stackoverflow.com/questions/78996717/how-to-implement-efficient-data-fetching-between-client-api-and-database
- Should data transformation be on the front or on the back end in this scenario? – Software Engineering Stack Exchange, 7月 21, 2025にアクセス、 https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/400595/should-data-transformation-be-on-the-front-or-on-the-back-end-in-this-scenario
- How AI-Powered Optimization Can Solve Slow Web App Load Times? | by A Smith | Medium, 7月 21, 2025にアクセス、 https://web-and-mobile-development.medium.com/how-ai-powered-optimization-can-solve-slow-web-app-load-times-0aa68e8ea5e1
- Modern Frontend Development: AI Integration and Tools | A… | Anshad Ameenza, 7月 21, 2025にアクセス、 https://anshadameenza.com/blog/technology/frontend-ai/
- How can AI improve web development efficiency? – Quora, 7月 21, 2025にアクセス、 https://www.quora.com/How-can-AI-improve-web-development-efficiency
- AI for App Performance: Faster Apps – DEV Community, 7月 21, 2025にアクセス、 https://dev.to/sushan_dristi_ab98c07ea8f/ai-for-app-performance-faster-apps-2kkd
- Maximizing outputs with v0: From UI generation to code creation – Vercel, 7月 21, 2025にアクセス、 https://vercel.com/blog/maximizing-outputs-with-v0-from-ui-generation-to-code-creation