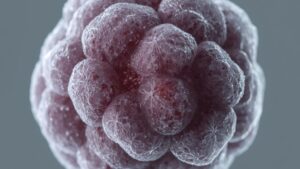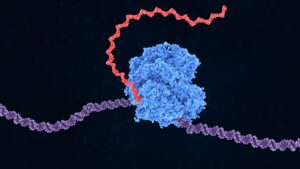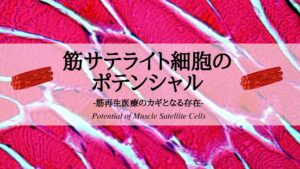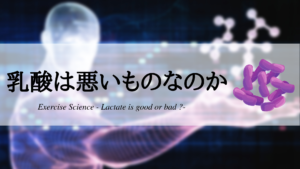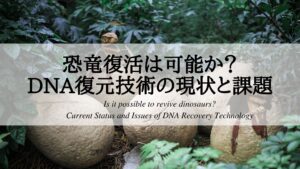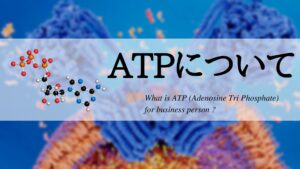はじめに:細胞培養とは?生命科学を支える基盤技術
細胞培養とは、生物の体から細胞を取り出し、管理された人工的な環境下で増殖・維持する技術のことです 1。この技術は、生命科学のあらゆる分野を支える根幹をなすものであり、その本質は、細胞にとって最適な「住まい」(培養容器)と「食事」(培地)を提供し、体内に近い環境を体外で再現することにあります 4。
この技術を理解するためには、まずいくつかの基本的な用語を知る必要があります。
- 初代培養 (Primary Culture):生体組織から直接細胞を分離して行う最初の培養を指します。これらの細胞は、元の組織の性質を色濃く反映していますが、分裂できる回数には限りがあります 2。
- 細胞株 (Cell Line):初代培養の細胞を新しい培養容器に移し替える「継代(けいだい)」という操作を初めて行うと、それは「細胞株」と呼ばれます 7。
- 有限細胞株と不死化細胞株 (Finite vs. Continuous Cell Lines):ほとんどの正常な細胞は、遺伝的に定められた回数しか分裂できず、やがて増殖を停止します。これを細胞老化(セネッセンス)と呼び、このような性質を持つ細胞株を「有限細胞株」と言います。一方、がん細胞のように無限に増殖し続ける能力を獲得した細胞もあり、これを「不死化」と呼びます。不死化した細胞株は「連続細胞株」または「株化細胞」として、世界中の研究室で利用されています 7。
- 接着培養と浮遊培養 (Adherent vs. Suspension Culture):細胞の培養方法には大きく分けて2種類あります。皮膚や臓器の細胞のように、体の組織に付着していた細胞は、培養ディッシュの底面に張り付いて増殖します(接着培養)。一方、血液細胞のように体内で浮遊していた細胞は、培地の中で浮いたまま増殖します(浮遊培養)。これは、細胞が元々体内でどのような環境にいたかを再現しようとする試みの一環です 2。
では、なぜ研究者たちはこれほどまでに細胞培養に注力するのでしょうか。その理由は、細胞培養が持つ「再現性」と「一貫性」にあります 2。同じ種類の細胞を大量に増やすことで、研究者は均一な条件下で実験を行うことができ、信頼性の高いデータを得ることが可能になります。これにより、細胞の正常な働きや病気のメカニズムの解明、新薬の効果や毒性の評価、さらにはワクチンや抗体医薬品といった生物学的製剤の大量生産など、その応用範囲は計り知れません 2。
しかし、細胞は非常にデリケートで、環境の変化に敏感です。そのため、細胞培養は厳密な管理下で行われなければなりません。細菌やカビなどの微生物による汚染(コンタミネーション)を防ぐための無菌操作(アセプティックテクニック)は絶対不可欠であり、クリーンベンチと呼ばれる無菌空間での作業が求められます 2。また、細胞の成長に最適な温度(通常は哺乳類細胞で37°C)、湿度、そして二酸化炭素($CO_2$)濃度を一定に保つための培養器(インキュベーター)も必須の設備です 2。
このように、細胞培養の基本原理は「生体内の環境をいかに忠実に再現するか」という点に集約されます。この一見単純な目標を追求する過程こそが、本稿で解説する細胞培養技術の進化の歴史そのものであり、平面的な培養から立体的な組織の構築へと至る、驚くべきイノベーションの原動力となっているのです。
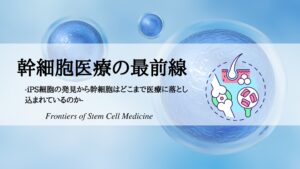
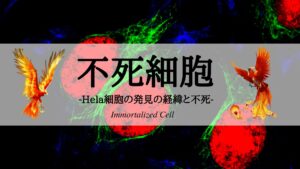
第1部 細胞培養の夜明けから現代まで:140年の探求史
今日の生命科学の根幹をなす細胞培養技術は、一朝一夕に生まれたものではありません。それは、140年以上にわたる科学者たちの飽くなき探求心と、試行錯誤の積み重ねによって築き上げられてきました。その歴史は、生物の最も基本的な単位である「細胞」を、生体という複雑なシステムから切り離し、実験室の管理下で生かし続けようとする挑戦の物語です。
黎明期(1860年代~1880年代):器官培養と生命を支える「水」の発見
細胞培養の最も古いルーツは、個々の細胞ではなく、心臓などの「器官」全体を体外で生かそうとする試みに遡ります。1866年、カール・ルートヴィヒは灌流システムを開発し、カエルの心臓に血漿を流し込むことで、体外で拍動を維持させることに世界で初めて成功しました 12。これは、生命活動を体外で再現するという壮大な目標に向けた、記念すべき第一歩でした。
しかし、器官を生かし続けるためには、単に液体を流すだけでは不十分でした。1882年、イギリスの生理学者シドニー・リンガーは、食塩水にカルシウムやカリウムなどのイオンを加えた「リンガー液」を開発しました 12。このバランスの取れた塩類溶液(等張液)は、細胞内外の浸透圧を一定に保ち、細胞が破裂したり萎んだりするのを防ぎます。リンガー液に浸されたカエルの心臓は、数日間にわたって拍動を続け、生命維持における化学的環境の重要性を明らかにしました 12。この発見は、後のあらゆる細胞培養研究の基礎となる、培地の原型を生み出したのです。
組織培養の誕生(1885年~1910年代):細胞が「生きる」瞬間を捉える
器官全体の長期培養が栄養供給の問題で難航する中、研究者たちの関心はより小さな単位である「組織」へと移っていきます。1885年、ヴィルヘルム・ルーは、ニワトリ胚の組織片を温めた食塩水の中で数日間生かすことに成功し、「組織培養」の原理を確立しました 12。
そして1907年、後に「細胞培養の父」と称されるロス・グランビル・ハリソンが、歴史的な実験を行います。彼はカエルの神経組織を凝固したリンパ液の中で培養し、神経細胞から神経線維が伸びていく様子を顕微鏡下で直接観察することに成功したのです 13。これは、体外で細胞が「成長」し、その振る舞いを観察できた最初の事例であり、現代に続く細胞培養技術の実質的な幕開けとなりました 12。
ハリソンの成功を受け、アレクシス・カレルとモントローズ・バロウらは、ニワトリ胚の抽出液などを培地に加えることで、細胞の増殖をさらに促進させる方法を開発しました 12。これにより、細胞を長期間にわたって培養し続ける「連続培養」の概念が生まれ、細胞培養は単なる観察技術から、生命現象を能動的に探求するための強力な実験ツールへと進化を遂げたのです。
現代への飛躍(1940年代~1950年代):抗生物質、そして「HeLa細胞」革命
細胞培養研究における長年の課題は、細菌やカビによる汚染でした。どんなに注意深く操作しても、目に見えない微生物が混入し、貴重な培養細胞を全滅させてしまうことが頻繁にありました。この状況を一変させたのが、1940年代に導入されたペニシリンやストレプトマイシンといった抗生物質です 17。抗生物質を培地に添加することで、細菌汚染のリスクが劇的に低下し、研究者は安定して長期的な培養実験を行えるようになりました。
そして1951年、細胞培養の歴史を塗り替える、画期的な出来事が起こります。ジョージ・ゲイ博士の研究室で、ヘンリエッタ・ラックスというアフリカ系アメリカ人女性の子宮頸がん組織から、世界初のヒト由来の不死化細胞株が樹立されたのです 17。彼女の名前にちなんで「HeLa(ヒーラ)細胞」と名付けられたこの細胞は、正常細胞と異なり、無限に分裂・増殖する能力を持っていました 17。
HeLa細胞の登場は、生物学・医学研究に革命をもたらしました。その不死性と驚異的な増殖力により、HeLa細胞は世界中の研究室に配布され、初めて「標準化されたヒト細胞」として利用されることになったのです 21。これにより、異なる研究者が同じ細胞を用いて実験結果を比較できるようになり、生物学はより定量的で再現性の高い科学へと変貌しました。ポリオワクチンの開発や、がん研究、遺伝子解析など、HeLa細胞が貢献した研究分野は枚挙にいとまがありません 17。
しかし、この科学的偉業には暗い影が伴います。HeLa細胞は、ヘンリエッタ・ラックス本人やその家族の同意なしに採取・培養されたものでした 17。彼女の細胞が世界中で商業的に利用され、莫大な利益を生み出している事実を、遺族は数十年もの間知らされませんでした 17。HeLa細胞の物語は、科学の進歩がもたらす恩恵と同時に、研究倫理、インフォームド・コンセント、そして人種的公平性といった、現代の生命科学が直面する重い課題を私たちに突きつけています。
HeLa細胞の樹立以降、細胞の栄養要求性の体系的な解明(イーグル、1955年)、無血清培地の開発(ハム、1965年)、そしてあらゆる細胞に分化できる能力を持つ幹細胞の発見(1981年)やiPS細胞の樹立(山中伸弥、2006年)など、技術は飛躍的な進歩を遂げます 16。
この歴史を俯瞰すると、一つの明確な流れが見えてきます。それは、生命の複雑性を犠牲にしてでも、「制御可能性」と「再現性」を追求する道のりです。巨大で複雑な「器官」から、より単純な「組織」へ、そして最終的には均一で無限に増殖する「細胞株」へ。このスケールダウンと標準化こそが、細胞培養を一部の研究者の特殊技術から、現代科学に不可欠な基盤ツールへと変貌させたのです。そして現代の最先端研究は、この過程で一度失われた「生体内の複雑性」を、今度は制御された形でいかにして再構築するかに焦点を当てています。
第2部 細胞の「住まい」と「食事」:培養ディッシュと培地の科学
細胞培養の成否は、細胞がいかに快適な環境で過ごせるかにかかっています。その環境を構成する二大要素が、細胞の足場となる「培養ディッシュ(培養容器)」と、栄養源となる「培地」です。これらは単なる容器と液体ではなく、細胞の生死、増殖、さらには運命までも左右する、極めて高度に設計された科学技術の結晶です。
2.1 培養培地:栄養スープに隠された秘密
培養培地は、細胞が生きていくために必要なすべての栄養素を供給する、生命のスープです 23。その基本的な構成要素と役割は以下の通りです。
- 無機塩類:ナトリウム、カリウム、カルシウムといったイオンを供給し、細胞内外の浸透圧を体液と同じレベルに保ちます。これにより、細胞が正常な形と機能を維持できます 23。
- 緩衝系:細胞は代謝活動に伴い酸性物質を産生するため、培地のpHは酸性に傾きがちです。pHが至適範囲(通常はpH 7.2~7.4)から外れると細胞は死んでしまうため、pHを一定に保つ緩衝作用が不可欠です。多くの培地では、インキュベーター内の$CO_2$ガスと培地中の重炭酸ナトリウムが反応するシステムを利用しています。また、HEPESのような化学的な緩衝剤が加えられることもあります 3。培地にはしばしば「フェノールレッド」というpH指示薬が含まれており、pHが酸性に傾くと黄色に、アルカリ性に傾くと紫色に変化するため、培養環境の状態を視覚的に確認できます 10。
- 炭水化物:主にグルコース(ブドウ糖)が、細胞の主要なエネルギー源として供給されます 25。
- アミノ酸:タンパク質の構成要素であるアミノ酸は、細胞の構造や酵素を作るために必須です。細胞が自身で合成できない必須アミノ酸は、培地から供給されなければなりません 25。
- ビタミン:様々な酵素反応の補因子として働き、細胞の代謝を円滑に進めるために微量ながら不可欠な要素です 23。
血清、特にウシ胎児血清(FBS)の役割と問題点
基本的な培地だけでは、多くの細胞はうまく増殖できません。そこで、最も一般的に添加されるのが「ウシ胎児血清(Fetal Bovine Serum, FBS)」です 23。FBSは、成長因子、ホルモン、接着因子、脂質など、細胞の増殖と生存に必要な1,000種類以上の成分を含む、まさに「魔法のカクテル」です 31。多種多様な細胞の培養を可能にし、毒性物質から細胞を保護する緩衝作用も持つため、長年にわたり細胞培養に不可欠な存在とされてきました 31。
しかし、この万能サプリメントには、科学の進歩とともに看過できなくなった深刻な問題がいくつも存在します。
- 科学的な問題:FBSの最大の問題点は、その成分が完全には解明されておらず、製造ロットごとに組成が大きく異なる「未定義」な混合物であることです 32。この「ロット差」は実験の再現性を著しく損なう原因となり、科学的な厳密性が求められる現代の研究において大きな障害となります 35。
- バイオセーフティのリスク:動物由来の生物学的製剤であるため、ウイルスやマイコプラズマ、さらにはBSE(牛海綿状脳症)の原因となるプリオンといった病原体が混入するリスクを常に抱えています 32。
- 倫理的な懸念:FBSは、屠殺された妊娠牛から取り出された胎児の心臓から、麻酔なしで血液を採取して作られます。この採取方法が非人道的であるとして、動物福祉の観点から強い批判があります 38。
- 供給とコストの問題:FBSは食肉・酪農業の副産物であるため、その供給量は牛の消費量や飼料価格、干ばつなどの環境要因、さらには口蹄疫のような家畜伝染病の発生に大きく左右されます 32。需要の増加と不安定な供給により価格は高騰を続けており、産地の偽装といった不正行為も問題となっています 31。
定義済み培地への移行
FBSが抱えるこれらの問題は、細胞培養技術のパラダイムシフトを促しました。そのゴールは、FBSのような「ブラックボックス」に頼るのではなく、すべての成分とその濃度が明確にわかっている「定義済み」の培地を開発することです。この流れは、生物学がより定量的で工学的なアプローチを取り入れる大きな潮流と一致しています。
- 無血清培地 (Serum-Free Media, SFM):FBSを完全に排除し、代わりに精製された成長因子やホルモンなどを添加した培地です 37。これにより、ロット差の問題が解消され、実験の再現性が向上します。また、下流工程での精製が容易になる、汚染リスクが低減するといった利点もあります。一方で、細胞種ごとに最適な組成を開発する必要がある、細胞の増殖速度が遅くなることがある、といった課題も存在します 35。
- 化学的無血清培地 (Chemically Defined Media, CD Media):無血清培地をさらに一歩進め、タンパク質水解物のような未定義な成分も一切含まない、純粋な化学物質のみで構成された培地です 42。成分が完全に明確であるため、最高の再現性と安全性を実現します。特に、再生医療製品やバイオ医薬品など、ヒトへの応用を前提とした製品の製造においては、規制当局からこのような動物由来成分を含まない、完全に定義された培地の使用が強く推奨されており、商業的・法的な必須要件となりつつあります 37。
この培地開発の歴史は、細胞培養における「複雑性」と「制御性」の間の絶え間ない葛藤を象徴しています。FBSは、その生物学的な複雑性ゆえに効果的でしたが、その複雑性が科学的な制御を妨げました。化学的無血清培地への移行は、血清の複雑性を一度分解し、既知の部品から再構築することで、生物学的機能を損なうことなく、完全な制御性を手に入れようとする壮大な試みなのです。
| 特徴 | 血清含有培地(FBSなど) | 無血清/化学的無血清培地 |
| 組成 | 未定義。成長因子、ホルモンなど1,000種以上の成分を含む複雑な混合物 31。 | 定義済み。すべての成分と濃度が既知の化学物質で構成される [43, 44]。 |
| 一貫性/再現性 | 低い。ロット間のばらつきが大きく、実験の再現性を損なう [34, 35, 36]。 | 高い。バッチ間のばらつきがなく、一貫した実験結果が得られる [41, 45]。 |
| 生物学的性能 | 高い。多種多様な細胞の増殖を強力にサポートする 31。 | 細胞種に特異的。特定の細胞には最適化が必要で、増殖が遅くなる場合がある [36, 40, 41]。 |
| 下流工程(精製) | 複雑。血清由来の大量のタンパク質を除去する必要がある [37]。 | 容易。不純物が少なく、目的産物の精製が簡単かつ低コスト [37, 41]。 |
| 汚染リスク | 高い。ウイルスやプリオンなど、動物由来の病原体混入のリスクがある 32。 | 低い。動物由来成分を排除することで、汚染リスクを大幅に低減できる [37, 41]。 |
| 倫理的懸念 | あり。ウシ胎児からの非人道的な採取方法が問題視されている 38。 | なし。動物由来成分を使用しないため、倫理的な問題が解消される [36]。 |
| コスト | 初期コストは比較的低いが、価格変動が激しく、品質テストにコストがかかる [24, 32]。 | 初期コストは高いが、精製コストの削減や品質の安定性により、長期的にはコスト効率が良い場合がある [35, 37]。 |
2.2 培養表面:細胞の足場が運命を決める
接着培養される細胞にとって、足場となる培養容器の表面は単なる「床」ではありません。それは細胞の形、動き、さらには遺伝子発現にまで影響を与える重要な環境因子です。
- 標準的な2D表面:現在、一般的に使用されているペトリディッシュやフラスコは、ポリスチレンというプラスチックでできています。この表面は、細胞が接着しやすいように特殊な表面処理(親水化処理)が施されており、細胞はこの上で平たく伸展し、単層(モノレイヤー)を形成して増殖します 11。
- 細胞外マトリックス(ECM)コーティング:しかし、実際の生体内では、細胞はプラスチックの上ではなく、「細胞外マトリックス(Extracellular Matrix, ECM)」と呼ばれる、コラーゲンやフィブロネクチン、ラミニンといったタンパク質でできた足場の上に存在しています 6。そこで、培養ディッシュの表面をこれらのECMタンパク質でコーティングすることで、より生体内に近い環境を再現し、細胞の接着、増殖、分化を促進する試みが行われています 6。これは、単純なプラスチック表面の限界を認め、より生物学的なリアリティを追求する第一歩と言えます。
- 2D培養の根本的な限界:ECMコーティングを施したとしても、細胞を不自然に硬い平面上に押し付けて培養する2D(2次元)培養には、根本的な限界があります。生体内で立体的な構造を持つ細胞は、2D環境では平たく引き伸ばされ、本来の形や極性(細胞内の構造的な方向性)を失ってしまいます。この形態の変化は、細胞間のコミュニケーションを阻害し、遺伝子発現パターンを変化させ、薬物に対する応答性をも変えてしまうことが明らかになっています 11。創薬の過程で、2D培養の実験では有望だった候補化合物が、後の動物実験や臨床試験で効果を示さずに失敗するケースが後を絶ちませんが、その大きな原因の一つが、この2D培養と生体内環境との間の大きな隔たりにあると考えられています 48。この深刻な問題意識こそが、次章で詳述する3D(3次元)培養技術へのパラダイムシフトを駆動する最大の力となったのです。
第3部 3次元へ:生体内環境を再現する3D細胞培養技術
長年にわたり生命科学研究の主役であった2D(2次元)培養は、その簡便さと高い再現性から数多くの発見をもたらしてきました。しかし、細胞をプラスチックという硬く平坦な異物の上で培養するこの手法は、生体内の複雑な環境とはあまりにもかけ離れています。この「in vitro(試験管内)」と「in vivo(生体内)」のギャップを埋めるべく、研究者たちは細胞培養を新たな次元、すなわち3D(3次元)へと引き上げる挑戦を始めました。
3.1 なぜ3Dなのか?2D培養との決定的違い
2D培養から3D培養への移行は、単なる見た目の変化ではありません。それは、細胞の振る舞いや機能を、より忠実に生体内の状態に近づけるための、根本的なパラダイムシフトです。
- 生体内状態の再現:生体内では、細胞は他の細胞や細胞外マトリックス(ECM)に囲まれた3次元空間に存在しています。3D培養はこの環境を模倣することで、細胞が本来の立体的な形を取り戻し、隣接する細胞やECMと自然な相互作用を築くことを可能にします 11。さらに、3D構造の内部では、酸素や栄養、細胞から分泌されるシグナル分子の濃度勾配が自然に形成されます。これは、組織の中心部が低酸素状態になるがん組織など、生体内の多くの組織で見られる特徴を再現する上で極めて重要です 53。
- 細胞の振る舞いへの影響:このような、より生理学的に妥当な環境は、細胞の振る舞いに劇的な変化をもたらします。2D培養された細胞と比較して、3D培養された細胞は、遺伝子発現、増殖パターン、分化能力、そして薬物への応答性において、生体内の細胞により近い挙動を示すことが数多くの研究で報告されています 47。特に創薬研究において、2Dモデルの予測性の低さが臨床試験での高い失敗率の一因とされてきたことから、より正確な薬効や毒性を予測できる3Dモデルへの期待は非常に高まっています 47。
| 特徴 | 2D培養 | 3D培養 |
| 細胞形態 | 平たく伸展し、非生理的な形状になる [11, 57]。 | 生体内に近い、自然な立体構造を維持する [48, 57]。 |
| 細胞間/細胞-ECM相互作用 | 制限的。底面との相互作用が支配的 [47, 53]。 | 全方向的。生体内に近い複雑な相互作用を再現する [52, 58]。 |
| 生理的勾配 | ほぼ均一。酸素や栄養へのアクセスが平等 [11, 54]。 | 形成される。酸素、栄養、シグナル分子の自然な濃度勾配が生じる 53。 |
| 遺伝子/タンパク質発現 | 生体内とは異なる発現プロファイルを示すことがある [11, 55]。 | 生体内の発現プロファイルにより近いパターンを示す [47, 56]。 |
| 薬物応答の予測性 | 低い。生体内での反応を正確に予測できないことが多い [48, 50]。 | 高い。臨床結果との相関性が高く、より正確な薬効・毒性評価が可能 [47, 54]。 |
| コスト | 低い [11, 58]。 | 高い [53, 59]。 |
| スループット | 高い。ハイスループットスクリーニングに適している [60]。 | 低い~中程度。手法によるが、一般に2Dより手間がかかる [61, 62]。 |
| 解析の容易さ | 容易。顕微鏡観察や画像解析が簡単 [58, 61]。 | 困難。構造が厚く不透明なため、特殊なイメージング技術が必要になることがある [58]。 |
3.2 主要な3D培養法
3D培養環境を構築するための技術は多岐にわたりますが、大きく「足場(スキャフォールド)を用いる方法」と「足場を用いない方法」に分類できます。
足場(スキャフォールド)を用いる手法
これらの手法は、細胞外マトリックス(ECM)を模倣した構造的な支持体を提供し、その中で細胞を培養します。
- ハイドロゲル:高含水性の高分子ネットワークで、ゼリーのように柔らかく、細胞が内部で3次元的に増殖できる環境を提供します 49。
- 天然由来ハイドロゲル:コラーゲン、アルギン酸、あるいはマウスの腫瘍から抽出されたECM成分を主とする「マトリゲル®」などが代表例です 60。生体親和性が高い一方で、成分が未定義であったり、ロット間のばらつきがあったりする点が課題です 62。
- 合成ハイドロゲル:ポリエチレングリコール(PEG)などの化学的に合成されたポリマーから作られます。成分が明確で、硬さなどの物理的特性を自由に調整できる利点がありますが、細胞接着部位などの生物学的な機能を持たせるために改変が必要な場合があります 63。
- 多孔質固体足場:ポリスチレンなどの生体適合性材料で作られた、スポンジのような多孔質の固体構造体です 57。細胞はこの内部に入り込み、立体的な組織様の塊を形成します。ハイドロゲルよりも硬く、安定した構造を提供できます 57。
足場を用いない手法
これらの手法は、細胞が自然に凝集する性質を利用して、細胞自身の力で3次元構造を形成させます。
- ハンギングドロップ(懸滴)法:培養ディッシュの蓋の裏側に細胞懸濁液の小さな液滴をつけ、蓋を逆さにして培養します。重力によって細胞が液滴の底に集まり、球状の細胞塊(スフェロイド)を形成します 57。
- 低接着プレート法:表面が特殊なポリマーでコーティングされており、細胞が接着できないように加工されたプレートです。足場を失った細胞は、互いに接着し合うことで凝集し、スフェロイドを形成します 70。ハイスループット化が容易なため、創薬スクリーニングなどで広く利用されています。
- 攪拌培養法:スピナーフラスコやシェーカーを用いて培地を常に攪拌し、細胞を浮遊状態に保つことで、細胞同士の衝突と凝集を促す方法です。大量のスフェロイドを一度に作製するのに適しています 60。
3.3 スフェロイドとオルガノイド:単純な細胞塊からミニ臓器へ
3D培養によって形成される細胞構造体の中でも、特に重要なのが「スフェロイド」と「オルガノイド」です。両者はしばしば混同されますが、その成り立ちと複雑性において明確な違いがあります。
- スフェロイド (Spheroid):比較的単純な球状の細胞凝集塊で、多くはがん細胞株などの単一種類の細胞から形成されます 69。作製が比較的容易で、均一なサイズのスフェロイドを大量に調製できるため、多数の薬剤候補を評価するハイスループットスクリーニングに非常に適しています 59。
- オルガノイド (Organoid):スフェロイドよりもはるかに複雑な3D構造体で、iPS細胞や組織幹細胞(成体幹細胞)といった幹細胞から作られます 59。オルガノイドの最大の特徴は、幹細胞が自律的に増殖・分化し、特定の臓器に特有の複数の細胞種を組織化して、元の臓器の構造と機能の一部を模倣する「自己組織化」能力にあります 14。これにより、研究室のディッシュの中に「ミニ腸」や「ミニ脳」といった、本物の臓器の縮小版(ミニ臓器)を作り出すことが可能になりました 16。
この成り立ちの違いは、培養方法にも決定的な差をもたらします。スフェロイドは低接着プレートのような比較的単純な環境でも形成できますが、オルガノイドが複雑な自己組織化を遂げるためには、生体内のECMの役割を果たすマトリゲル®のようなハイドロゲルの中に包み込み、適切な成長因子やシグナル分子を供給することがほぼ必須となります 59。
3D培養技術の登場は、細胞培養の歴史における大きな転換点です。かつて、再現性を求めて生物の複雑性を削ぎ落としてきた科学は、今、その複雑性を制御された形で実験室に呼び戻そうとしています。スフェロイドやオルガノイドといったツールは、その最前線にあり、生命の設計図がどのようにして機能的な組織を構築するのか、その根源的な問いに迫るための強力な武器となっているのです。
| 特徴 | スフェロイド (Spheroid) | オルガノイド (Organoid) |
| 細胞の由来 | 主にがん細胞株や初代細胞など、単一または少数の細胞種 [70, 72]。 | 幹細胞(iPS細胞、成体幹細胞) [59, 72, 73]。 |
| 複雑性と細胞多様性 | 低い。主に単一の細胞種からなる単純な凝集塊 [70, 72]。 | 高い。複数の臓器特異的な細胞種を含み、複雑な組織構造を持つ [70, 73]。 |
| 自己組織化 | 限定的。細胞が凝集するが、高度な組織化は見られない [59]。 | 顕著。幹細胞が自律的に分化・組織化し、臓器様の構造を形成する [14, 72]。 |
| 培養方法 | 足場なし(低接着プレート、懸滴法)または足場あり(ハイドロゲル包埋) 69。 | ほぼ必須で足場(マトリゲル®などのECM様ハイドロゲル)内での培養が必要 70。 |
| 主な応用 | ハイスループットな創薬スクリーニング、がん研究 [59, 69]。 | 疾患モデリング、発生生物学、再生医療、個別化医療 [16, 69, 76]。 |
第4部 細胞培養のフロンティア:最先端プラットフォームと応用技術
3D培養技術が細胞に、より生体に近い「環境」を与えたとすれば、現代の最先端技術は、その環境をさらに動的かつ精密に制御し、さらには細胞の設計図そのものを書き換えることさえ可能にしました。マイクロ流体技術、3Dバイオプリンティング、そしてCRISPR-Cas9ゲノム編集。これらの工学的手法の融合により、細胞培養は「観察」の科学から「構築」の科学へと、その姿を大きく変えつつあります。
4.1 マイクロ流体技術と「臓器チップ(Organ-on-a-Chip)」
マイクロ流体技術(マイクロフルイディクス)とは、マイクロメートル(1000分の1ミリメートル)スケールの微細な流路内で、ごく少量の液体を精密に操作する技術です 77。この技術を細胞培養に応用することで、従来のディッシュ培養では不可能だった、極めて高度な環境制御が実現します。例えば、薬剤や栄養素の濃度勾配を安定的に作り出して細胞の応答を観察したり、血流のような流体せん断応力を細胞に与えたりすることが可能です 78。
このマイクロ流体技術の粋を集めたものが、「臓器チップ(Organ-on-a-Chip, OOC)」です 80。これは、マイクロチップ上にヒトの臓器の最小機能単位を再構築したもので、まさに「チップ上の臓器」と呼ぶべきデバイスです 83。
例えば、2010年に発表され大きな注目を集めた「肺チップ(Lung-on-a-Chip)」は、微細な流路を多孔質膜で上下に分け、上側に肺の肺胞上皮細胞を、下側に血管内皮細胞を培養しています。上側の流路に空気を、下側の流路に培地を流すことで「空気と血液の境界」を再現。さらに、チップの側面に周期的な真空をかけることで膜を伸縮させ、呼吸による物理的な伸び縮みまでも模倣しています 85。
このような臓器チップは、動物実験に代わる、よりヒトに近い創薬スクリーニングモデルとして絶大な期待を集めています 80。動物とヒトとでは薬物への応答が異なるため、動物実験で有効性や安全性が確認された薬でも、ヒトの臨床試験で失敗するケースは少なくありません。ヒト細胞を用いた臓器チップは、この「種の壁」を乗り越え、創薬の成功率を向上させ、開発コストを削減する可能性を秘めています 81。米国では2022年に、新薬承認の要件から動物実験を必須としない「FDA近代化法2.0」が成立し、臓器チップのような代替法の開発が法制度の面からも後押しされています 58。
さらに研究は、単一の臓器チップから、複数の臓器チップを流路で連結した「ボディオンチップ(Body-on-a-Chip)」へと進化しています 80。例えば、腸チップ(薬物吸収)、肝臓チップ(薬物代謝)、腎臓チップ(薬物排泄)を連結することで、投与された薬が体内でどのように吸収・代謝・排泄されるか(ADME)という一連の動態を、チップ上でシミュレートすることが可能になります 86。
4.2 3Dバイオプリンティング:生命を「印刷」する技術
3Dバイオプリンティングは、3Dプリンターの技術を応用し、生きた細胞を含む「バイオインク」をインクとして用いて、コンピューターの設計図通りに立体的な組織構造を一層ずつ積み上げて造形する技術です 89。
この技術の核心は、以下の2つの要素にあります。
- 印刷技術:バイオインクを吐出する方法にはいくつかの種類があります。歯磨き粉を絞り出すように材料を押し出す「押出方式(Extrusion)」、インクジェットプリンターのように微小な液滴を噴射する「インクジェット方式」、レーザー光を用いてインクを転写する「レーザーアシスト方式」などがあり、それぞれ解像度、印刷速度、コスト、そして細胞へのダメージの度合いが異なります 91。
- バイオインク:細胞を混ぜ込むための材料で、多くはハイドロゲルがベースとなります 89。細胞が生き続け、正しく機能するための足場となるため、生体適合性や適切な硬さ、そしてプリンターで安定して吐出できる「印刷適性」が求められます 93。
3Dバイオプリンティングの応用は、すでに始まっています。皮膚、軟骨、骨といった比較的単純な組織を再生するための研究や、より複雑な構造を持つがんモデルをチップ上に作製して薬剤評価に用いる研究などが活発に進められています 91。
そして、この技術が目指す究極の目標は、移植医療に用いるための完全な機能を持つ臓器、すなわち「プリント臓器」の創出です 93。臓器内部の複雑な血管網や神経網をいかにして再現するかなど、乗り越えるべき技術的課題は極めて大きいものの、実現すればドナー不足という深刻な問題を根本的に解決できる可能性があります。
| 印刷技術 | 原理 | 解像度 | コスト | 速度 | 細胞生存率 | 対応材料(粘度) |
| 押出方式 (Extrusion) | 空気圧やピストンでバイオインクを連続的に押し出す | 低~中 (100 µm~) | 低 | 遅い | 高 (89%~) | 広範囲 (30 mPa·s ~) |
| インクジェット方式 (Inkjet) | 熱や圧電素子でインクの微小な液滴を噴射する | 中~高 (50 µm~) | 低 | 速い | 比較的高 (80-95%) | 低 (< 10 mPa·s) |
| レーザーアシスト方式 (Laser-assisted) | レーザーパルスでインクを基盤に転写する | 高 (1 µm~) | 高 | 中 | 比較的低 (< 85%) | 広範囲 |
| 光造形方式 (Stereolithography) | 光(UVなど)を照射して液状の樹脂を層状に硬化させる | 高 (100 µm~) | 中~高 | 速い | 高 (> 90%) | 粘度の制限なし |
出典: 90 に基づき作成
4.3 CRISPR-Cas9ゲノム編集:疾患モデルを自在に創出する
CRISPR-Cas9(クリスパー・キャスナイン)は、2012年に開発された画期的なゲノム編集技術で、DNAの特定の配列を狙って切断・改変することができる「分子のハサミ」に例えられます 22。
この技術がオルガノイドのような先進的な培養モデルと組み合わさることで、疾患研究に革命が起きています。従来、遺伝性疾患の研究は、患者から得られる限られた細胞や、ヒトとは異なる動物モデルに頼らざるを得ませんでした。しかし現在では、健常者由来のiPS細胞にCRISPR-Cas9を用いて特定の遺伝子変異を導入し、そのiPS細胞から疾患オルガノイドを作製することができます 100。
この手法の最大の利点は、遺伝的背景が全く同じ細胞で、「変異がある場合(疾患)」と「変異がない場合(正常)」のオルガノイドを比較できる「アイソジェニック(同質遺伝子)モデル」を構築できる点です 100。これにより、特定の遺伝子変異が、細胞や組織の機能にどのような異常を引き起こすのかを、他の遺伝的要因に邪魔されることなく、極めて正確に解析することが可能になります。
このCRISPRとオルガノイドの組み合わせは、遺伝性疾患のメカニズム解明、遺伝子治療法の開発、さらには特定の遺伝子変異を持つ患者に効果的な薬を見つけ出すための個別化医療への応用など、計り知れない可能性を秘めています 101。
これらフロンティア技術に共通するのは、生物学と工学の深い融合です。細胞培養はもはや、単に細胞を「育てる」だけの技術ではありません。マイクロ流体技術で「環境を設計」し、3Dバイオプリンティングで「構造を構築」し、ゲノム編集で「遺伝情報を改変」する。生命の構成要素を自在に操り、目的の機能を持つ生体システムを能動的に作り上げる「生命工学」の時代が、本格的に到来しているのです。
第5部 細胞培養が拓く未来:再生医療から食料安全保障まで
細胞培養技術の進化は、研究室の壁を越え、私たちの医療、食、そして社会のあり方そのものを変革する大きな可能性を秘めています。個別化医療の実現から、持続可能な食料生産システムの構築まで、細胞培養が描く未来像は多岐にわたります。
5.1 再生医療と個別化医療
臓器の修復と再生
再生医療は、失われた組織や臓器の機能を、細胞を用いて回復させることを目指す医療分野です。ここで中心的な役割を果たすのが、幹細胞から作製されたオルガノイドです。実験室で育てた「ミニ臓器」を、損傷した組織に移植することで、その機能を補完・再生させようという試みが進められています。例えば、腸の幹細胞から作製した腸オルガノイドを、炎症性腸疾患(IBD)などで損傷した腸管に移植し、粘膜のバリア機能を回復させる研究が、動物モデルで有望な結果を示しており、臨床応用への期待が高まっています 76。
患者由来オルガノイド(PDO)による個別化医療
細胞培養技術がもたらす医療における最も大きな変革の一つが、「個別化医療」の実現です。その鍵を握るのが、患者自身の細胞(特にがん組織)から直接作製される「患者由来オルガノイド(Patient-Derived Organoid, PDO)」です 107。
PDOは、患者一人ひとりの腫瘍の遺伝的特徴や不均一性を、驚くほど忠実に体外で再現します 75。これにより、PDOは患者の「アバター」や「分身」として機能します。医師は、実際に患者に抗がん剤を投与する前に、研究室でその患者のPDOに複数の薬剤を試し、どの薬が最も効果的で、どの薬が効かないのかを予測することができます 108。
実際に、希少な肝がんの一種と診断された患者のケースでは、切除された腫瘍からPDOが作製され、薬剤感受性試験が行われました。その結果に基づき治療方針が決定され、このアプローチが個別化医療において原理的に有効であることが示されました。ただし、このケースでは治療効果が限定的であり、臨床応用に向けた課題も浮き彫りになっています 113。
さらに、世界中の研究機関では、様々な種類のがん患者から提供されたPDOを収集・保存する「リビングバイオバンク」の構築が進められています 104。このバイオバンクは、多様な患者集団を代表する膨大な数の「がんアバター」のコレクションであり、新薬開発や治療効果を予測するバイオマーカーの探索において、これまでにない強力なプラットフォームとなることが期待されています。
5.2 細胞農業と培養肉
細胞培養技術は、医療分野だけでなく、食料生産という人類の根源的な課題にも応用されようとしています。それが「細胞農業(Cellular Agriculture)」であり、その代表例が「培養肉(Cultured Meat)」です。
細胞農業は、家畜を飼育する代わりに、動物の細胞を培養することで食肉や牛乳などの畜産物を生産する技術です 114。培養肉のプロセスは、まず動物から少量の細胞(主に筋肉の幹細胞である衛星細胞)を採取し、それをバイオリアクターと呼ばれる巨大な培養タンクの中で増殖させ、最終的に筋肉や脂肪の組織へと分化させることで成り立っています 115。
この技術が注目される背景には、従来の畜産業が抱える環境負荷、動物福祉、食料安全保障といった深刻な問題があります 114。細胞農業は、土地や水の使用量を大幅に削減し、温室効果ガスの排出を抑制し、抗生物質の使用を減らすことができる、より持続可能な食料生産システムとなる可能性を秘めています 116。
しかし、培養肉がスーパーマーケットに並ぶまでには、乗り越えるべき巨大なハードルが存在します。
- スケールアップ:研究室レベルのフラスコ培養から、数トン単位の肉を生産する工業規模のバイオリアクターへと移行することは、極めて困難な技術的挑戦です。動物細胞の増殖速度は、ビール醸造などに使われる酵母菌などと比べて格段に遅いため、巨大な設備が必要となります 116。
- コスト:現状では、培養肉の生産コストの大部分を、栄養源である培地が占めています。特に高価なウシ胎児血清(FBS)に代わる、安全で低コストな食品グレードの無血清培地の開発が、商業化に向けた最大の鍵となります 115。
- 食感と構造:ミンチ肉のような単純な細胞の塊を作ることは比較的容易ですが、ステーキのような複雑な食感や構造を持つ肉を作ることははるかに困難です。そのためには、筋肉繊維や脂肪組織を立体的に配置し、栄養を供給するための血管網を模倣する高度な組織工学技術が必要となります 119。
- 規制と社会受容性:培養肉を食品として販売するための法規制の整備や、消費者からの安全性への懸念や心理的な抵抗感をいかにして払拭するかといった、社会的な課題も重要です 115。
5.3 2025年以降の展望:最新の研究動向と未来予測
細胞培養技術は、今この瞬間も進化を続けています。再生医療分野における細胞培養培地の市場は、2024年の46億8,000万米ドルから2029年には82億4,000万米ドルへと、年率11.9%の急成長が見込まれており、この分野への期待の大きさを物語っています 121。
具体的な研究目標も設定されており、例えば日本では、培養肉の構造化に関する課題克服を目指し、「2025年までに100gサイズのステーキ肉を作製する」という目標が掲げられています 119。これは、大阪・関西万博での展示も視野に入れた、技術の社会実装に向けた意欲的な取り組みです 120。
さらに、オルガノイドや臓器チップから得られる膨大な画像データや測定データを解析するために、AI(人工知能)や機械学習を活用する動きも活発化しています 85。AIは、最適な培地組成の発見や、薬剤応答性の予測モデル構築などを通じて、研究開発を加速させることが期待されています。
そして、その視線は地球上だけにとどまりません。宇宙探査における長期滞在を見据え、微小重力環境が人体に与える影響をオルガノイドを用いて研究するなど、未来の健康課題に対応するための新たな応用も始まっています 65。
細胞培養技術は、もはや単なる実験手法ではありません。それは、個別化医療という「一人ひとりに最適化された医療」と、細胞農業という「持続可能な食料生産」という、人類の未来を左右する二つの大きな潮流の原動力となっています。前者は極めて高価値な製品を少量生産し、後者は低価格な商品を大量生産するという、対照的な目標を掲げていますが、その根底にあるのは同じ細胞培養という基盤技術なのです。この技術の進化が、私たちの未来をどのように形作っていくのか、その動向から目が離せません。
結論:生命の設計図を書き換える技術の未来
本稿では、細胞培養技術の基礎から、その140年以上にわたる歴史、そして2D培養から3D培養へのパラダイムシフト、さらにはオルガノイド、臓器チップ、3Dバイオプリンティングといった最先端技術、そして再生医療や培養肉といった未来の応用までを包括的に解説してきました。
この壮大な技術の進化を貫くテーマは、一貫して「生体内環境の忠実な再現」への飽くなき追求です。初期の研究者たちが、生命を支える最小限の化学的環境(リンガー液)を発見したことから始まったこの旅は、未定義ながらも万能な血清(FBS)の利用を経て、やがてその「ブラックボックス」を排し、すべての成分が既知である化学的無血清培地へと至りました。これは、科学が「制御可能性」と「再現性」を極限まで求める必然的な流れでした。
同時に、平坦なディッシュの上で細胞を培養するという2Dの手法が、生体内の細胞の真の姿を歪めているという認識が広まるにつれ、技術は失われた「3次元性」と「複雑性」を取り戻す方向へと舵を切りました。スフェロイド、オルガノイド、そして臓器チップといった3Dモデルは、細胞に本来の立体構造と、細胞同士や周囲の環境との相互作用を取り戻させ、生命現象をより正確に映し出す鏡となりました。
そして今、細胞培養は、マイクロ流体技術、3Dバイオプリンティング、ゲノム編集といった工学的手法と深く融合し、単に生命を「観察」する技術から、生命システムを「設計・構築」する技術へと変貌を遂げています。
この変革は、私たちの社会に計り知れない影響を与えようとしています。医療の分野では、患者由来オルガノイドが一人ひとりの体質や病状に合わせた「個別化医療」を現実のものとし、創薬のあり方を根本から変える可能性があります。食の分野では、細胞農業が、環境負荷や倫理的な問題を乗り越え、持続可能な食料安全保障への道を拓くかもしれません。
しかし、その輝かしい未来への道のりは平坦ではありません。コスト、スケールアップ、法規制、そして社会的な受容性といった、科学技術だけでは解決できない巨大な壁が立ちはだかっています。特に、ゲノム編集の応用や患者由来の生体材料の利用、培養肉の社会実装といったテーマは、私たちに深い倫理的・社会的な議論を求めています。
細胞培養は、もはや単なる研究室の一技術ではありません。それは、生命の設計図を読み解き、そして書き換える力を人類に与えつつある、現代科学の最もダイナミックなフロンティアの一つです。これから先、この技術がもたらす変革に、私たちは賢明に向き合っていく必要があります。その挑戦の先に、より健康で、より持続可能な未来が待っていると信じて。
引用文献
- 細胞培養(セルカルチャー)|用語集|細胞×画像ラボ – Nikon Healthcare, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.healthcare.nikon.com/ja/ss/cell-image-lab/glossary/cell-culture.html
- 細胞培養とは|研究用語辞典 – 研究ネット – WDB, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.wdb.com/kenq/dictionary/cell-culture
- Introduction to Cell Culture | Proteintech Group, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.ptglab.com/support/cell-culture-protocol/introduction-to-cell-culture/
- 細胞を培養するってどういうこと? | 幹細胞情報データベースプロジェクトSKIP (Stemcell Knowledge & Information Portal), 11月 3, 2025にアクセス、 https://saiseiiryo.jp/skip_archive/knowledge/cellresearch/01/
- そもそも細胞培養とは何でしょう | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング(J-TEC), 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.jpte.co.jp/columns/details/327
- Primary Cell Culture Basics – Sigma-Aldrich, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/primary-cell-culture/primary-cell-culture
- Cell Culture Introduction | Thermo Fisher Scientific – US, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.thermofisher.com/us/en/home/references/gibco-cell-culture-basics/introduction-to-cell-culture.html
- Applied Biological Materials(APB)社 細胞培養 入門 | コスモ・バイオ株式会社, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.cosmobio.co.jp/support/technology/a/about-cell-culture.asp
- Cell Culture Basics: Equipment, Fundamentals and Protocols – Technology Networks, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.technologynetworks.com/cell-science/articles/cell-culture-basics-equipment-fundamentals-and-protocols-348413
- Introductory Guide to Cell Culture Basics, 11月 3, 2025にアクセス、 https://info.biotechniques.com/hubfs/Corning/Content%20Hosting/introductory-guide-cell-culture-basics-cls-an-724.pdf
- 2D and 3D cell cultures – a comparison of different types of cancer cell cultures – PMC, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6040128/
- 器官培養の挑戦、等張液の発明(1860~80年代) | 幹細胞情報 …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://saiseiiryo.jp/skip_archive/knowledge/cellresearch/02/01/
- Cell culture – Wikipedia, 11月 3, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_culture
- A Brief History of Cell Culture: From Harrison to Organs-on-a-Chip – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11674496/
- 第8回「細胞培養の歴史」, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.saibou.jp/technology/know/210/
- A Brief History of Cell Culture: From Harrison to Organs-on-a-Chip – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39768159/
- What is cell culture, and how has it evolved? – VIROLOGY …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://virologyresearchservices.com/2024/07/07/what-is-cell-culture-and-how-has-it-evolved/
- 組織培養の成立―細胞培養誕生前夜 – Learning at the Bench – Thermo Fisher Scientific, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.thermofisher.com/blog/learning-at-the-bench/cell_culture_history_1_bid_ts_4/
- History of Cell Biology: Timeline of Important Discoveries – Bitesize Bio, 11月 3, 2025にアクセス、 https://bitesizebio.com/166/history-of-cell-biology/
- 細胞培養はいつから始まった?(細胞培養の歴史~器官培養からiPS細胞まで~) | 再生医療ポータル, 11月 3, 2025にアクセス、 https://saiseiiryo.jp/basic/detail/cellresearch_02.html
- 3D Cell Cultures: Evolution of an Ancient Tool for New Applications – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2022.836480/full
- Cell History Timeline | Preceden, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.preceden.com/timeline/cell-history
- Cell Culture Media: A Review – Labome, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.labome.com/method/Cell-Culture-Media-A-Review.html
- CELL CULTURE BASICS Handbook, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.vanderbilt.edu/viibre/CellCultureBasicsEU.pdf
- CELL CULTURE MEDIA: A REVIEW – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/profile/Vani-Madaan/publication/383575660_CELL_CULTURE_MEDIA_A_REVIEW/links/66d2d2edf84dd1716c74e5e5/CELL-CULTURE-MEDIA-A-REVIEW.pdf
- 細菌学の基本を教えてください, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.kanazawa-med.ac.jp/~kansen/situmon/saikin_kihon.html
- Breaking Down Cell Culture Media – Captivate Bio, 11月 3, 2025にアクセス、 https://captivatebio.com/breaking-down-cell-culture-media/
- Cell Culture Medium: 6 Critical Components to Include – Bitesize Bio, 11月 3, 2025にアクセス、 https://bitesizebio.com/37034/cell-culture-medium/
- 1から分かる細胞培養における培養環境 – Learning at the Bench – Thermo Fisher Scientific, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.thermofisher.com/blog/learning-at-the-bench/cell-culture-environment/
- Cell Culture Media Formulation: Components You Can’t Ignore – Patsnap Synapse, 11月 3, 2025にアクセス、 https://synapse.patsnap.com/article/cell-culture-media-formulation-components-you-cant-ignore
- The Basics of Fetal Bovine Serum Use | Thermo Fisher Scientific – US, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.thermofisher.com/us/en/home/references/gibco-cell-culture-basics/cell-culture-environment/fbs-basics.html
- A plea to reduce or replace fetal bovine serum in cell culture media …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3967615/
- Fetal Bovine Serum (FBS) – What You Need to Know – Sigma-Aldrich, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/serum-university
- Fetal bovine serum – Wikipedia, 11月 3, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Fetal_bovine_serum
- Serum-Free vs. Serum-Containing Media: Which Works Better?, 11月 3, 2025にアクセス、 https://synapse.patsnap.com/article/serum-free-vs-serum-containing-media-which-works-better
- Going Serum-Free: The How and Why of Removing Serum From Your Media – Bitesize Bio, 11月 3, 2025にアクセス、 https://bitesizebio.com/46997/removing-serum-from-your-media/
- Understanding Serum-Free Media: Balancing Benefits and Limitations in Cell Culture?, 11月 3, 2025にアクセス、 https://yoconcelltherapy.com/serum-free-media-benefits-and-limitations/
- The Use of Fetal Bovine Serum: Ethical or Scientific Problem? – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/11396187_The_Use_of_Fetal_Bovine_Serum_Ethical_or_Scientific_Problem
- The use of fetal bovine serum: ethical or scientific problem? – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11971757/
- Basics of Culture Media | Thermo Fisher Scientific – US, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.thermofisher.com/us/en/home/references/gibco-cell-culture-basics/cell-culture-environment/culture-media.html
- What are the advantages and disadvantages of serum-free media in cell culture?, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.aatbio.com/resources/faq-frequently-asked-questions/What-are-the-advantages-and-disadvantages-of-serum-free-media-in-cell-culture
- Systematic Approaches to Develop Chemically Defined Cell Culture …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.biopharminternational.com/view/systematic-approaches-develop-chemically-defined-cell-culture-feed-media
- Chemically defined media – Knowledge and References – Taylor & Francis, 11月 3, 2025にアクセス、 https://taylorandfrancis.com/knowledge/Engineering_and_technology/Biomedical_engineering/Chemically_defined_media/
- Animal‐cell culture media: History, characteristics, and current issues – PMC, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5661806/
- Serum-free media: ask the experts – RegMedNet, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.regmednet.com/serum-free-media-ask-the-experts/
- Extracellular matrix Pre-coated Plates – R&D Systems, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.rndsystems.com/products/extracellular-matrix-pre-coated-plates
- 3D vs 2D Cell Culture: A Comprehensive Comparison and Review, 11月 3, 2025にアクセス、 https://cellculturecollective.com/blog/3d-cell-culture-vs-2d-cell-culture/
- Three-Dimensional Cell Culture Systems and Their Applications in Drug Discovery and Cell-Based Biosensors – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4026212/
- A Practical Guide to Hydrogels for Cell Culture – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5800304/
- 注目される3D細胞培養 – Corning, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.corning.com/jp/jp/products/life-sciences/applications/cell-culture/3D-cell-culture/case-for-3D-cell-culture.html
- What is scaffold-based 3D culture? – Cell Guidance Systems, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.cellgs.com/blog/what-is-scaffold-based-3d-culture.html
- Is It Time to Start Transitioning From 2D to 3D Cell Culture? – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/molecular-biosciences/articles/10.3389/fmolb.2020.00033/full
- 3D Cell Culture vs. Traditional 2D Cell Culture Explained – Mimetas, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mimetas.com/en/blogs/345/3d-cell-culture-vs–traditional-2d-cell-culture-explained.html
- 3D 細胞培養入門 – プロメガ, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.promega.jp/resources/guides/cell-biology/3d-cell-culture-guide/
- 3D細胞培養ツールおよび技術 – Sigma-Aldrich, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/3d-cell-culture/3d-cell-culture-technology
- 3D Cell Culture: Recent Development in Materials with Tunable Stiffness – ACS Publications, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsabm.0c01472
- Advances in 3D cell culture technologies enabling tissue‐like …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4694114/
- 2D vs 3D Cell Cultures | FluoroFinder, 11月 3, 2025にアクセス、 https://fluorofinder.com/2d-vs-3d-cell-cultures/
- Organoid and Spheroid Tumor Models: Techniques and …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7922036/
- Hydrogels for 3D cell culture in microfluidics: a review, 11月 3, 2025にアクセス、 https://blog.darwin-microfluidics.com/hydrogels-for-3d-cell-culture-in-microfluidics-a-review/
- Stiffness-Controlled Hydrogels for 3D Cell Culture Models – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2073-4360/14/24/5530
- Hydrogels as Extracellular Matrix Mimics for 3D Cell Culture – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2997742/
- Review of 3D cell culture with analysis in microfluidic systems – RSC Publishing, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2019/ay/c9ay01328h
- 3D cell culture model: From ground experiment to … – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2023.1136583/full
- 3D Cell Culture Methods and Applications – Elveflow, 11月 3, 2025にアクセス、 https://elveflow.com/microfluidic-reviews/3d-cell-culture-methods-and-applications-a-short-review/
- Scaffolds for 3D Cell Culture – Sigma-Aldrich, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/cell-culture-and-analysis/3d-cell-culture/scaffolds
- Advancement of Scaffold-Based 3D Cellular Models in Cancer Tissue Engineering: An Update – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2021.733652/full
- An Overview on Spheroid and Organoid Models in Applied Studies – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2413-4155/7/1/27
- Cell Culture Protocol: Best Practice in Spheroid and Organoid Cultures, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.corning.com/worldwide/en/products/life-sciences/resources/stories/at-the-bench/cell-culture-protocol-best-practices-in-spheroid-and-organoid-cultures.html
- (PDF) An Overview on Spheroid and Organoid Models in Applied Studies – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/389572173_An_Overview_on_Spheroid_and_Organoid_Models_in_Applied_Studies
- Spheroids and 3D Organoids Cell Cultures: The Main Differences, 11月 3, 2025にアクセス、 https://blog.darwin-microfluidics.com/spheroids-and-3d-organoids-cell-cultures-the-main-differences/
- A Concise Review of Organoid Tissue Engineering: Regenerative Applications and Precision Medicine – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2674-1172/4/3/16
- Careers | Novartis, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.novartis.com/careers
- Advancing Cancer Drug Discovery with Exclusive Organoid Technology Using Adult Stem Cells – Crown Bioscience Blog, 11月 3, 2025にアクセス、 https://blog.crownbio.com/advancing-cancer-drug-discovery-with-exclusive-organoid-technology-using-adult-stem-cells
- Clinical applications of human organoids – PubMed, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39901045/
- Microfluidics for cell-cell interactions: A review – Hep Journals, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journal.hep.com.cn/fcse/EN/10.1007/s11705-015-1550-2
- Microfluidic devices for cell cultivation and proliferation – PMC, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3829894/
- Fundamentals of microfluidic cell culture in controlled microenvironments – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2967183/
- Application of Organ-on-Chip in Drug Discovery – Scirp.org., 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=98810
- Organs-on-chips at the frontiers of drug discovery – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4826389/
- A Comprehensive Review of Organ-on-a-Chip Technology and Its Applications – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2079-6374/14/5/225
- (PDF) Organ-on-chip technology’s development and usages: A comprehensive review, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/378768053_Organ-on-chip_technology’s_development_and_usages_A_comprehensive_review
- Organ-on-a-chip technology: innovations, applications, and future horizons, 11月 3, 2025にアクセス、 https://microfluidics-innovation-center.com/reviews/organ-on-a-chip-technology-innovations-applications/
- Theranostics Organ-on-a-chip meets artificial intelligence in drug evaluation, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.thno.org/v13p4526.pdf
- Organ-on-a-Chip: A new paradigm for drug development – PMC, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7990030/
- Organs-on-a-chip for drug discovery | Request PDF – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/249319211_Organs-on-a-chip_for_drug_discovery
- Drug Toxicity Evaluation Based on Organ-on-a-Chip Technology: A Review, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.semanticscholar.org/paper/Drug-Toxicity-Evaluation-Based-on-Organ-on-a-Chip-A-Cong-Han/fe6db26b26de85d38eebb25d0bcc374e87921cca
- 3D Printing for Tissue Engineering: Printing Techniques, Biomaterials, Challenges, and the Emerging Role of 4D Bioprinting – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2306-5354/12/9/936
- 3D Bioprinting in Tissue Engineering for Medical Applications: The Classic and the Hybrid, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7464247/
- Full article: Recent advances in 3D bioprinting of tissues and organs for transplantation and drug screening – Taylor & Francis Online, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17452759.2024.2384662
- 3D Bioprinting for Tissue Engineering Application Review – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/profile/Maged-Nasr/publication/350739606_3D_Bioprinting_for_Tissue_Engineering_Application_Review/links/606f40a692851c8a7bb2d126/3D-Bioprinting-for-Tissue-Engineering-Application-Review.pdf
- 3D Bioprinting: A Systematic Review for Future Research Direction …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10673757/
- 3D Bioprinting Technologies for Tissue Engineering: A Mini Review, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.heraldopenaccess.us/openaccess/3d-bioprinting-technologies-for-tissue-engineering-a-mini-review
- Progress of 3D Bioprinting in Organ Manufacturing – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2073-4360/13/18/3178
- 3D bioprinting of functional tissue models for personalized drug …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6226327/
- 3D Bioprinting for Organ Regeneration – PMC – PubMed Central, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5313259/
- Modeling disease in vivo with CRISPR/Cas9 – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4592741/
- CRISPR-Cas9: A Preclinical and Clinical Perspective for the Treatment of Human Diseases, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7854284/
- CRISPR/Cas9 Editing for Gaucher Disease Modelling – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/1422-0067/21/9/3268
- Genome engineering of stem cell organoids for disease modeling, 11月 3, 2025にアクセス、 https://journal.hep.com.cn/pac/EN/10.1007/s13238-016-0368-0
- Exploiting CRISPR Cas9 in Three-Dimensional Stem Cell … – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2020.00692/full
- pmc.ncbi.nlm.nih.gov, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5459481/#:~:text=CRISPR%2DCas%20gene%20editing%20expedites,pre%2Dclinical%20drug%20development%20campaign.
- Tumor organoids for cancer research and personalized medicine, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.cancerbiomed.org/content/19/3/319
- Current status and prospects of organoid-based regenerative medicine – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9887105/
- Organoid Medicine Milestone Reported in Cell Stem Cell – Research …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://scienceblog.cincinnatichildrens.org/organoid-medicine-milestone-reported-in-cell-stem-cell/
- Patient-Derived Organoid Biobanks for Translational Research and Precision Medicine: Challenges and Future Perspectives – MDPI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2075-4426/15/8/394
- Patient-Derived Organoids as a Model for Cancer Drug Discovery …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8038043/
- Organoid-based personalized medicine: from tumor outcome prediction to autologous transplantation | Stem Cells | Oxford Academic, 11月 3, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/stmcls/article/42/6/499/7634513
- Patient-derived organoids in human cancer: a platform for fundamental research and precision medicine – PMC – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10859360/
- Patient-Derived Organoids in Precision Medicine: Drug Screening, Organoid-on-a-Chip and Living Organoid Biobank – Frontiers, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2021.762184/full
- Patient-derived Tumor Organoids: Generation and Applications in Disease Modeling and Personalized Therapy – Nature Cell and Science, 11月 3, 2025にアクセス、 https://cellnatsci.com/2958-695X/article/10-61474-ncs-2024-00008
- (PDF) Patient-derived tumor organoids for personalized medicine in …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/361686871_Patient-derived_tumor_organoids_for_personalized_medicine_in_a_patient_with_rare_hepatocellular_carcinoma_with_neuroendocrine_differentiation_a_case_report
- Cellular Agriculture: Opportunities and Challenges – Annual Reviews, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-food-063020-123940
- Scientific, sustainability and regulatory challenges of cultured meat – ResearchGate, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/342991858_Scientific_sustainability_and_regulatory_challenges_of_cultured_meat
- Scientific, sustainability and regulatory challenges of cultured meat, 11月 3, 2025にアクセス、 https://researchportal.bath.ac.uk/files/211126211/natfood_review_cultured_meat2020_1_.pdf
- Meating the moment: Challenges and opportunities for cellular agriculture to produce the foods of the future – NIH, 11月 3, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12238250/
- “Cellular agriculture”: current gaps between facts and claims regarding “cell-based meat” | Animal Frontiers | Oxford Academic, 11月 3, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/af/article/13/2/68/7123477
- 世界が注目する培養肉とは?海外の動向と日本の現状を紹介 – プルーヴ株式会社, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.provej.jp/column/na/cultured-meat/
- 2025年版 代替タンパク質 <代替肉(植物由来肉・培養肉)・昆虫食>の将来展望 ~フードテックで実現する持続可能な食の未来~ | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.yano.co.jp/market_reports/C67102400
- 再生医療向け細胞培養培地の世界市場レポート 2025年 – グローバルインフォメーション, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.gii.co.jp/report/tbrc1830725-cell-culture-media-market-regenerative-medicines.html