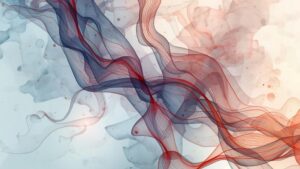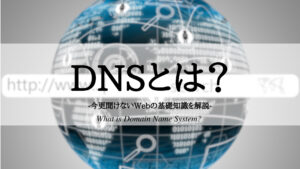序章:なぜ今、ステーブルコインが注目されるのか? JPYCの登場を切り口に
金融テクノロジーの世界で、今「ステーブルコイン」が大きな注目を集めている。2023年の改正資金決済法の施行を受け、日本国内で初めて法的に認められた日本円連動ステーブルコイン「JPYC」が2025年10月より正式に発行を開始したことは、多くのメディアで報じられた 1。この出来事は、これまで暗号資産(仮想通貨)に馴染みの薄かった層にも、ステーブルコインという言葉を広く知らしめるきっかけとなった。
しかし、JPYCの登場は、単なる国内発の新しいデジタルマネーの誕生というだけではない。これは、過去10年以上にわたり世界中で発展し、今やその市場規模が2,000億ドル(約30兆円)を超える巨大な金融イノベーションの波が、日本の厳格な法規制の枠組みの中に本格的に到達したことを示す象徴的な出来事である 4。
ステーブルコインは、ビットコインのような価格が激しく変動する暗号資産とは一線を画し、その価値を米ドルや日本円といった法定通貨に「ペッグ(固定)」することで安定性を図るデジタル資産だ 7。この「価値の安定性」という特性が、単なる投機の対象ではなく、決済、送金、そして新たな金融サービス(DeFi、分散型金融)の基盤として、その可能性を大きく広げている。
この現象は、いわば「デジタルマネーのグローカライゼーション」と呼ぶことができる。もともとステーブルコインは、国境を越えたグローバルな暗号資産市場のニーズに応える形で、規制が比較的緩やかな環境で急速に成長してきた 4。しかし、その規模が拡大するにつれ、マネーロンダリングや金融システムの不安定化といったリスクも顕在化し、各国の金融当局は警戒を強めてきた 10。
こうした中、日本が選択したのは、ステーブルコインを禁止するのではなく、「電子決済手段」という新たな法的カテゴリーを設けて国内の規制下に置くという、世界でも先進的なアプローチだった 12。JPYCの登場は、この日本独自の規制アプローチの下で、グローバルな金融テクノロジーをいかに国内の経済活動に安全に取り込んでいくかという壮大な社会実験の始まりを意味する。
本稿では、このJPYCの登場を切り口に、ステーブルコインという金融イノベーションの本質を多角的に解き明かしていく。まず、ステーブルコインがなぜ生まれ、どのような問題を解決するのかという基本的な概念から説き起こす。次に、その誕生から今日に至るまでの波乱に満ちた歴史を辿り、価値を安定させるための様々な技術的仕組みを詳細に解説する。さらに、過去に世界を震撼させた大規模な破綻事例を分析し、その光と影の両面に迫る。そして、日本の現在地であるJPYCの仕組みと法的位置付けを詳述した後、世界各国の規制動向や最新の学術研究にも触れ、ステーブルコインが切り拓く金融の未来を展望する。
この包括的な解説を通じて、読者はステーブルコインが単なる一過性のブームではなく、私たちの生活や経済のあり方を根底から変えうる、重要かつ不可逆的な変化の潮流であることを理解するだろう。
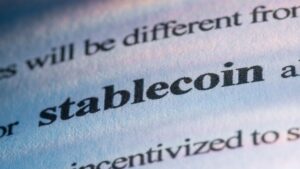

第1章:ステーブルコインの基本 — 価値が安定した「デジタルドル」の誕生
ステーブルコインを理解するためには、まずその前身であるビットコインなどの初期の暗号資産が抱えていた根本的な課題から始める必要がある。
1.1. 暗号資産の「価格変動」というジレンマ
2009年に登場したビットコインは、国家や中央銀行を介さずに価値を直接やり取りできるという点で画期的な発明だった。しかし、その価値は市場の需要と供給のみによって決まるため、極めて激しい価格変動(ボラティリティ)に常に晒されている 8。この性質は、ビットコインを「お金」として日常的に使用することを困難にした。
伝統的に、お金には三つの主要な機能があるとされる。「価値の保存」「交換の媒体」「価値の尺度」である 8。しかし、価格が不安定な資産は、これらの機能を十分に果たすことができない。例えば、1杯500円のコーヒーをビットコインで支払う場合を考えてみよう。ある日の価格では0.00005 BTCだったものが、翌日にはビットコインの価格が30%下落し、0.000065 BTCになるかもしれない。これでは、店側は安心して価格を設定できず、消費者も将来の価値が不確かな資産を支払いに使おうとは考えにくい。このように、高いボラティリティは、暗号資産が投機的な資産の域を超え、実用的な決済手段として普及する上での最大の障壁となっていた 15。
1.2. ステーブルコインの定義と目的
この「価格変動」というジレンマを解決するために生まれたのが、ステーブルコインである。ステーブルコインは、「その価値を米ドルや日本円のような法定通貨、あるいは金のような他の安定した資産に連動(ペッグ)させるように設計されたデジタル資産」と定義される 7。
その最大の目的は、ブロックチェーン技術がもたらす利点(24時間365日稼働するグローバルなネットワーク、仲介者を排除したことによる高速かつ低コストな送金、スマートコントラクトによるプログラム可能性)と、伝統的な通貨が持つ「価値の安定性」を融合させることにある 4。
言い換えれば、ステーブルコインは、伝統的金融(TradFi)の世界と、暗号資産を中心とするデジタル金融の世界とを繋ぐ、極めて重要な「橋渡し(ブリッジ)」としての役割を担っている 7。この橋の存在によって、人々は法定通貨の安定性を維持したまま、ブロックチェーンが提供する革新的な金融サービスの世界へと足を踏み入れることが可能になったのである 20。
1.3. 主な利用シーン
ステーブルコインの急速な成長は、その多様なユースケースによって支えられてきた。主な利用シーンは以下の4つに大別される。
- 暗号資産取引の円滑化
ステーブルコインが最初に普及した最大の理由は、暗号資産取引所での利用だった。価格変動の激しいビットコインやイーサリアムを取引する際、トレーダーは利益を確定したり、一時的にリスクを回避したりするために、保有資産を安定した価値を持つ資産に交換する必要がある。従来は、その都度、法定通貨(米ドルや日本円)に交換する必要があったが、これには時間と手数料がかかり、銀行の営業時間にも制約された。ステーブルコインは、取引所内で使える「デジタルドル」として機能し、トレーダーが24時間いつでも、迅速かつ低コストでボラティリティの高い資産から安全な資産へと退避することを可能にした 4。 - 決済と国際送金
従来の国際送金は、SWIFT(国際銀行間通信協会)のネットワークを通じて複数の銀行を経由するため、着金までに数日を要し、手数料も高額になることが多かった。ステーブルコインは、ブロックチェーン上で国境を越えて直接送金できるため、このプロセスを劇的に効率化する可能性を秘めている。数秒から数分で送金が完了し、手数料も従来の数分の一に抑えることができるため、特に個人間の国際送金(レミタンス)や、企業間の貿易決済などでの活用が期待されている 4。 - DeFi(分散型金融)の基盤
DeFiは、銀行や証券会社といった伝統的な金融仲介機関を介さずに、貸し借り(レンディング)、交換(DEX)、利回り獲得(イールドファーミング)などの金融サービスをスマートコントラクト上で実現するエコシステムである。このDeFiの世界において、ステーブルコインは血液のような役割を果たしている。価値が安定しているため、貸し借りの際の基準通貨として、また、流動性供給の際の主要な資産として不可欠な存在となっている 9。 - インフレヘッジと金融包摂
自国の通貨価値が不安定で、高いインフレに苦しむ国々の人々にとって、米ドルなどの安定した通貨へのアクセスは生活を守る上で極めて重要である。しかし、政府による資本規制などにより、公式なルートで外貨を保有することが困難な場合も少なくない。ステーブルコインは、スマートフォンさえあれば誰でも米ドルに連動したデジタル資産を保有できる手段を提供し、インフレからの資産防衛を可能にする 11。また、銀行口座を持たない人々にとっても、基本的な金融サービスへのアクセスを提供する金融包摂のツールとしての側面も持つ。
これらのユースケースは、ステーブルコインが単なるデジタル資産の一つではなく、新しい金融サービスを構築するための基盤、すなわち「プラットフォーム通貨」としての性質を持つことを示している。ビットコインが「新しい通貨」の可能性を提示し、イーサリアムが「スマートコントラクト」というプログラム可能なプラットフォームを提供したのに対し、ステーブルコインは、そのプラットフォーム上で実際に機能する「安定したプログラム可能な通貨」を提供した。この「マネーレゴ」とも呼ばれる構成要素の登場こそが、DeFiのような複雑な金融アプリケーションの発展を可能にした真のブレークスルーだったのである 9。

第2章:ステーブルコインの歴史的変遷 — 投機ツールから次世代決済インフラへ
ステーブルコインの歴史は、まだ10年余りと短いが、その道のりは決して平坦ではなかった。それは、技術的な試行錯誤、市場の熱狂と崩壊、そして規制当局との緊張関係が織りなす、金融イノベーションの典型的な物語である。
2.1. 2014-2017年:黎明期と最初の試み
ステーブルコインという概念が形になったのは2014年のことである。この年、後にイーサリアムの共同創設者となるチャールズ・ホスキンソンらが関わった「BitUSD」が、世界初のステーブルコインとして登場した 26。BitUSDは、米ドルではなく他の暗号資産を担保とする「暗号資産担保型」の先駆けであったが、その仕組みは複雑で、広く普及するには至らなかった。
同じく2014年、「Realcoin」という名前で産声を上げ、後に「Tether(USDT)」と改名されるプロジェクトが立ち上がった 29。Tetherは、1トークンを1米ドルと等価とし、その裏付けとして同額の米ドルを銀行口座に保有するという「法定通貨担保型」のシンプルなモデルを提示した。このモデルは、当時の暗号資産取引所が抱えていた大きな課題を解決した。多くの取引所は、規制上の問題から伝統的な銀行との関係を維持することが難しく、法定通貨の入出金に常に困難を抱えていた 4。Tetherは、銀行システムを介さずに米ドル相当の価値を取引所間で移動できる手段を提供し、暗号資産トレーダーにとって不可欠なツールとして急速にその地位を確立していった 32。この時期のステーブルコインは、まさに暗号資産市場という閉じた世界のための、ニッチな金融ツールであった。
2.2. 2018-2021年:成長と多様化の時代
Tetherが市場を独占する中、2018年に大きな転機が訪れる。米国の有力な暗号資産関連企業であるCircle社とCoinbase社が共同で、新たな法定通貨担保型ステーブルコイン「USD Coin(USDC)」を立ち上げたのだ 34。USDCは、準備資産の透明性を重視し、大手監査法人による月次の証明書を公開することで、不透明性が指摘されていたTetherとの差別化を図った。規制に準拠したクリーンなイメージを打ち出したUSDCは、機関投資家やコンプライアンスを重視する企業からの信頼を獲得し、Tetherの強力なライバルへと成長していく。
時を同じくして、もう一つの革新的なモデルが登場する。2017年末にローンチされたMakerDAOの「Dai」である 28。Daiは、特定の企業が発行・管理する中央集権的なステーブルコインとは異なり、イーサリアムなどの暗号資産を担保として、スマートコントラクトを通じて分散的に発行される「暗号資産担保型」のステーブルコインであった。これは、誰の許可も必要とせず、検閲されることのない、真に分散化されたステーブルコインの最初の成功例となった。
USDCとDaiの登場により、ステーブルコイン市場は多様化の時代を迎える。そして、2020年の「DeFiサマー」と呼ばれる分散型金融ブームの到来とともに、その市場規模は爆発的に拡大した。DeFiプロトコルにおいて、USDCやDaiは貸し借りや流動性供給の基軸通貨として利用され、その需要は飛躍的に高まった。2020年初頭には50億ドル程度だったステーブルコインの総時価総額は、わずか2年足らずで1,500億ドルを超える規模にまで膨れ上がった 30。
2.3. 2022-2023年:試練の時 — Terraショックと銀行危機
順風満帆に見えたステーブルコイン市場は、2022年から2023年にかけて、その存在意義を揺るがす二つの大きな試練に見舞われる。
最初の衝撃は、2022年5月に起きた「Terra(UST)ショック」である。TerraUSD(UST)は、準備資産を持たず、アルゴリズムによって供給量を調整することで1ドルの価値を維持しようとする「アルゴリズム型」ステーブルコインの代表格だった。一時は時価総額で第3位にまで上り詰めたが、市場の不安をきっかけに大規模な売りが発生すると、その価値維持メカニズムが破綻。USTとその連動トークンであるLUNAの価格はわずか数日でほぼ無価値となり、約450億ドル(当時のレートで6兆円以上)もの市場価値が消失した 24。この事件は、担保を持たないアルゴリズム型モデルの構造的な脆弱性を白日の下に晒し、市場全体に深刻な不信感を植え付けた。
二つ目の試練は、2023年3月に発生した。米国のシリコンバレーバンク(SVB)が経営破綻したことを受け、最も安全と見なされていたステーブルコインの一つであるUSDCが、一時的に1ドルのペッグを割り込み、約0.88ドルまで急落したのだ 22。原因は、USDCの発行元であるCircle社が、準備資産の一部である約33億ドルの現金をSVBに預けていたことにあった。この出来事は、たとえ100%の準備資産を持つ法定通貨担保型であっても、その資産を預かる伝統的な金融機関の破綻リスク(カウンターパーティリスク)と無縁ではないという厳しい現実を突きつけた。最終的に、米国規制当局がSVBの預金を全額保護することを発表したため、USDCのペッグは回復したが、ステーブルコインエコシステムが伝統的金融システムといかに密接に結びついているかを浮き彫りにした。
2.4. 2024年以降:制度化と規制の本格化
これらの危機は、ステーブルコインの歴史における重要な転換点となった。それは、金融イノベーションの歴史において繰り返されてきた「危機が成熟を促す」というパターンそのものであった。Terraの崩壊は、ステーブルコインの「設計」そのものに内在するリスクを、USDCのペッグ外れは、伝統的金融システムへの「依存」がもたらすリスクをそれぞれ明らかにした。これらの手痛い教訓は、業界に自己改革を促すと同時に、規制当局が本格的に介入する必要性を強く認識させることになった。
その結果、2024年以降のステーブルコイン市場は、「制度化」と「規制の本格化」という新たな時代に突入する。2023年8月には、決済大手のPayPalが独自のステーブルコイン「PYUSD」を発行し、JPモルガンなどの大手金融機関も独自のデジタルコインの活用を進めるなど、伝統的な金融プレーヤーの本格参入が相次いだ 34。
そして、法整備の面でも決定的な動きがあった。欧州連合(EU)では、包括的な暗号資産規制法である「MiCA(Markets in Crypto-Assets Regulation)」が2024年6月から段階的に施行され、ステーブルコイン発行者に厳格な準備資産管理やガバナンスを義務付けた 14。米国でも、2025年7月に超党派の支持を得て「GENIUS Act」が成立し、連邦レベルで初めてステーブルコインの監督・規制の枠組みが定められた 5。
これらの動きは、ステーブルコインがかつての「ワイルド・ウエスト(無法地帯)」から、法規制に則った金融システムの正式な構成要素へと移行しつつあることを明確に示している。
| 年月 | 出来事 | 意義 | 関連資料 |
| 2014年10月 | Tether(当初はRealcoin)がローンチ | 広く普及した最初の法定通貨担保型ステーブルコインの誕生 | [29, 35] |
| 2017年12月 | MakerDAOがDaiをローンチ | 最初の成功した分散型(暗号資産担保型)ステーブルコインの登場 | [36, 37] |
| 2018年9月 | Circle/CoinbaseがUSDCをローンチ | 規制準拠と透明性を重視したTetherの競合が出現 | 34 |
| 2022年5月 | TerraUSD (UST) が崩壊 | 約450億ドル規模の崩壊。アルゴリズム型モデルの信頼性が失墜 | [24, 40] |
| 2023年3月 | USDCが一時的にデペッグ | シリコンバレーバンク破綻により、準備資産のカウンターパーティリスクが顕在化 | [22, 42] |
| 2023年8月 | PayPalがPYUSDをローンチ | 大手伝統的金融企業が市場に参入し、メインストリーム化が加速 | [34, 46] |
| 2024年6月 | EUのMiCA規制が施行開始 | 主要経済圏で初の包括的なステーブルコイン規制が導入 | 14 |
| 2025年7月 | 米国でGENIUS Actが成立 | 世界最大の経済国でステーブルコインに関する連邦レベルの規制枠組みが確立 | 28 |
第3章:ステーブルコインの仕組み — 価値を支える4つのモデル
ステーブルコインがその「安定した価値」をどのように維持しているのか。その核心は、裏付けとなる資産(あるいはその代替メカニズム)にある。現在、ステーブルコインの価値維持メカニズムは、大きく分けて4つのモデルに分類される。
3.1. 法定通貨担保型 (Fiat-Collateralized)
これは最も一般的で、直感的に理解しやすいモデルである 5。このモデルでは、ステーブルコインの発行体(例えば、USDCを発行するCircle社やJPYCを発行するJPYC社)が、発行したステーブルコインの総額と等価かそれ以上の法定通貨(米ドルや日本円)や、それに準ずる極めて安全かつ流動性の高い資産(短期国債など)を「準備資産」として銀行や信託会社に保管する 15。
例えば、利用者が100ドルをCircle社に支払うと、Circle社はその100ドルを準備資産に加え、新たに100 USDCを発行して利用者に渡す。逆に、利用者が100 USDCをCircle社に持ち込むと、Circle社は準備資産から100ドルを利用者に払い戻し、その100 USDCを消滅(バーン)させる。この「1対1での償還可能性」が保証されている限り、市場におけるUSDCの価値は理論上1ドルに保たれる 17。
このモデルの利点は、そのシンプルさと安定性にある。裏付けが明確であるため、信頼性が高い。一方で、発行体を信頼する必要があるという中央集権的な構造を持ち、発行体や準備資産を保管する銀行が破綻するリスク(カウンターパーティリスク)を内包している。代表的な例として、USDT(Tether)、USDC(USD Coin)、そして日本のJPYCが挙げられる 19。
3.2. コモディティ担保型 (Commodity-Collateralized)
このモデルは法定通貨担保型の変種であり、裏付け資産として法定通貨の代わりに金(ゴールド)や銀、石油といった現物商品(コモディティ)を用いる 15。発行体は、発行したトークン1枚あたり、特定の量(例:金1グラム)の現物商品を安全な保管庫(ヴォールト)に保管する。
これにより、利用者は物理的な商品を直接保有することなく、その価値に連動したデジタルトークンをブロックチェーン上で手軽に取引できるようになる。これは、伝統的な金融商品である金ETF(上場投資信託)のデジタル版と考えることができる。このモデルは、インフレヘッジや貴金属への投資手段として利用されることが多い。代表例には、PAX Gold (PAXG)やTether Gold (XAUT)がある 19。
3.3. 暗号資産担保型 (Crypto-Collateralized)
このモデルは、中央集権的な発行体を介さずに、分散的な方法でステーブルコインを発行することを目指す。その裏付け資産として、法定通貨ではなく、イーサリアム(ETH)のような他の暗号資産を用いる 15。
しかし、担保となる暗号資産自体が大きな価格変動リスクを抱えている。この問題を解決するため、このモデルでは「過剰担保」という仕組みが採用されている 9。これは、発行したいステーブルコインの価値を大幅に上回る価値の暗号資産を担保としてスマートコントラクトに預け入れる(ロックする)ことを意味する。
例えば、MakerDAOが発行するDaiの場合、100ドル相当のDaiを発行するためには、150ドル相当のイーサリアムを担保として預け入れる必要がある(担保率150%) 15。もしイーサリアムの価格が下落し、担保価値が一定の基準(例えば120ドル)を下回ると、システムは自動的にその担保を清算(売却)し、発行されたDaiの価値を保全する仕組みになっている 50。
このモデルの最大の利点は、特定の企業に依存しない分散性と、ブロックチェーン上で全ての取引と担保状況が公開される透明性にある。一方で、過剰担保が必要なため資本効率が悪く、担保資産の価格が暴落した場合にはシステム全体がリスクに晒される可能性がある。代表例はMakerDAOのDaiである 51。
3.4. アルゴリズム型 (Algorithmic)
4つのモデルの中で最も野心的かつ、最も危険であることが証明されたのがこのアルゴリズム型である。このモデルは、法定通貨や暗号資産といった直接的な担保資産(準備資産)を持たない 5。その代わりに、スマートコントラクトによって実行されるアルゴリズムが、市場の需要と供給に応じてトークンの発行量(サプライ)を自動的に調整することで、価格を1ドルに維持しようと試みる 7。
その仕組みは、中央銀行が行う金融政策に似ている。もしステーブルコインの市場価格が1ドルを上回った場合(需要過多)、アルゴリズムは新たなトークンを発行(ミント)して市場供給を増やし、価格を押し下げる。逆に、価格が1ドルを下回った場合(供給過多)、アルゴリズムは市場からトークンを買い戻して消滅(バーン)させ、供給を減らして価格を押し上げる 5。この買い戻しの原資として、しばしば連動する別のトークン(シニョリッジシェア・トークン)が用いられた。TerraUSD(UST)におけるLUNAトークンがその例である 24。
このモデルの理論上の利点は、担保が不要なため資本効率が非常に高く、完全に分散化されたスケーラブルな通貨システムを構築できる可能性にあった。しかし、その価値は「将来にわたってアルゴリズムが機能し続ける」という市場参加者の信頼のみに支えられており、一度その信頼が崩れると、自己増殖的な価格の暴落(デス・スパイラル)を引き起こすという致命的な脆弱性を抱えていた 11。Terra/LUNAの崩壊以降、純粋なアルゴリズム型ステーブルコインは、極めてリスクの高いモデルと見なされている。
これら4つのモデルは、それぞれが「安定性」「分散性」「資本効率性」という3つの要素の間で異なるトレードオフを選択している。法定通貨担保型は安定性と資本効率性を優先する代わりに分散性を犠牲にし、暗号資産担保型は分散性と安定性を追求する代わりに資本効率性を犠牲にする。そして、アルゴリズム型は分散性と資本効率性の両立を目指したが、結果的に最も重要な安定性を確保できなかった。このトレードオフを理解することは、各ステーブルコインのリスクと特性を評価する上で不可欠である。
| 種類 | 仕組み | 主な例 | メリット | 主なリスク |
| 法定通貨担保型 | 法定通貨やそれに準ずる資産を1対1で準備金として保有 | USDC, USDT, JPYC | シンプルで直感的。準備資産が健全であれば高い安定性を持つ | 中央集権性、発行体や保管銀行の破綻リスク(カウンターパーティリスク)、準備資産の透明性に関する問題 |
| コモディティ担保型 | 金などの現物資産を裏付けとして保有 | PAXG, XAUT | 現物資産へのトークン化されたアクセスを提供。インフレヘッジの可能性 | 保管(カストディ)リスク、コモディティ自体の価格変動リスク、流動性の低さ |
| 暗号資産担保型 | 他の暗号資産を過剰に担保として預け入れる | DAI | 分散化されており、検閲耐性が高い。オンチェーンでの透明性 | 資本効率が悪い。市場暴落時の連鎖的な清算リスク。仕組みの複雑さ |
| アルゴリズム型 | アルゴリズムが供給量を調整して価格を維持 | TerraUSD (UST) (崩壊) | (理論上)分散化されており、資本効率が高く、スケーラブル | 極めて脆弱。「デス・スパイラル」に陥りやすい。市場の信頼に完全に依存 |
第4章:光と影 — ステーブルコインに潜むリスクと歴史的失敗
ステーブルコインは金融の効率性を飛躍的に高める可能性を秘めている一方で、その歴史は数々の失敗と危機によって彩られている。これらの失敗事例は、ステーブルコインに内在するリスクを理解するための貴重な教訓となる。リスクは決して排除されるのではなく、その形態を変えて存在する。理論から実践へと視点を移し、ステーブルコインが直面してきた具体的なリスクとその事例を深掘りする。
4.1. リスクの全体像
ステーブルコインに関連するリスクは多岐にわたるが、主に以下のカテゴリーに分類できる。
- ペッグ乖離リスク(取り付けリスク): ステーブルコインの価値が、目標とする1ドルや1円といった価格から乖離するリスク。特に、価格が目標値を下回ると、保有者の間で不安が広がり、償還請求が殺到する「取り付け騒ぎ(バンク・ラン)」に発展する可能性がある。発行体が償還要求に応えきれなくなると、ペッグは完全に崩壊する 10。
- 準備資産リスク: 法定通貨担保型ステーブルコインの根幹を揺るがすリスク。準備資産の透明性が欠如していたり、公表されている内容が虚偽であったりする場合、また、準備資産が現金や短期国債のような安全資産ではなく、リスクの高い資産で構成されている場合、市場のストレス時に価値が下落し、ステーブルコインの価値を支えきれなくなる 7。
- オペレーショナルリスク: システムの技術的な欠陥に起因するリスク。ハッキングによる資産の盗難、スマートコントラクトのバグの悪用、サイバー攻撃によるサービス停止などが含まれる 14。
- 不正金融リスク: ステーブルコインの匿名性や国境を越えた送金の容易さが、マネーロンダリング(資金洗浄、AML)やテロ資金供与(CFT)といった不正な金融活動に悪用されるリスク。規制当局が最も懸念する点の一つである 10。
- 金融システムリスク: 大規模なステーブルコインが破綻した場合、その影響が暗号資産市場に留まらず、伝統的な金融システム全体に波及するリスク。例えば、発行体が準備資産として保有する短期国債やコマーシャルペーパーを大量に売却せざるを得なくなった場合、金融市場に深刻な混乱を引き起こす可能性がある 10。
4.2. ケーススタディ1:アルゴリズムの崩壊 — Terra/LUNAショック
ステーブルコインの歴史上、最も壊滅的な失敗事例が、2022年5月のTerraUSD(UST)の崩壊である。これは、ステーブルコインの「設計」そのものに内在するリスクが、いかに catastrophic な結果を招くかを示した。
USTは、連動トークンであるLUNAとの間の裁定取引(アービトラージ)のインセンティブを利用して、1ドルの価値を維持するアルゴリズム型ステーブルコインだった。仕組みはこうだ。USTの価格が1ドルを下回ると、裁定取引者が安く買ったUSTをプロトコルに持ち込み、1ドル相当のLUNAと交換できる。この過程でUSTは消滅(バーン)し、供給量が減ることで価格が1ドルに戻るはずだった。逆にUSTが1ドルを上回ると、1ドル相当のLUNAをプロトコルに持ち込んで1USTを発行でき、USTの供給量が増えることで価格が下がる、という設計だった 24。
このシステムは、LUNAの価値が十分に高く、市場に参加者がいる限り機能するように見えた。しかし、2022年5月、何者かによる大規模なUSTの売却をきっかけに、USTの価格がわずかに1ドルを割り込んだ。これが引き金となり、市場の不安が連鎖的なパニックを引き起こした。USTを売る動きが加速し、価格がさらに下落。裁定取引者がUSTをバーンしてLUNAを大量に発行したが、市場はそれを吸収しきれず、今度はLUNAの価格が暴落した。LUNAの価値が下落すると、USTを支える信頼性がさらに失われ、さらなるUSTの売りを呼ぶという「デス・スパイラル(死の螺旋)」に陥った 39。わずか1週間で、USTとLUNAを合わせた約450億ドル(約6兆円)の時価総額がほぼゼロになった 41。
Terraの崩壊は、準備資産という実体的な価値の裏付けを持たないアルゴリズム型ステーブルコインが、市場の信頼という一点のみに依存しており、その信頼が失われた時にいかに脆いかを証明した。
4.3. ケーススタディ2:準備資産の信頼性 — USDCとシリコンバレーバンク
Terraの失敗が設計上のリスクであったのに対し、2023年3月のUSDCのペッグ外れは、伝統的金融システムに起因する「カウンターパーティリスク」を浮き彫りにした。
USDCは、準備資産を現金と短期米国債で保有する、最も安全なステーブルコインの一つと見なされていた。しかし、その発行元であるCircle社は、準備資産のうち33億ドルをシリコンバレーバンク(SVB)に現金預金として預けていた 22。2023年3月10日、金利の急上昇により多額の含み損を抱えていたSVBが経営破綻。Circle社が預けていた33億ドルが引き出せなくなるのではないかという懸念が市場に広がり、USDCに対するパニック売りが発生した 42。
その結果、USDCの価格は一時0.88ドルまで急落した 43。これは、USDCの仕組み自体に欠陥があったわけではなく、準備資産の保管先という、外部の伝統的金融機関の健全性に依存していたが故に引き起こされた危機であった。最終的に、米国の金融当局が介入し、SVBの預金を全額保護すると発表したことで市場の不安は収まり、USDCは速やかに1ドルのペッグを回復した 60。
この事件は、ステーブルコインがいかに安全な設計であっても、伝統的金融システムとの接点において予期せぬリスクに晒されることを示した。リスクは、暗号資産の世界から伝統金融の世界へと「変形」して存在していたのである。
4.4. ケーススタディ3:透明性を巡る長年の論争 — Tether (USDT)
最大の時価総額を誇るTether(USDT)は、その準備資産の透明性を巡って長年にわたり論争の的となってきた。これは「オペレーショナルリスク」および「透明性リスク」の典型例である。
Tether社は当初、発行したUSDTと同額の米ドルを100%現金で保有していると主張していた。しかし、2019年にニューヨーク州司法長官事務所(NYAG)が行った調査により、Tether社が準備金を姉妹会社である暗号資産取引所Bitfinexの損失補填に流用していたことや、準備資産が100%現金ではなく、コマーシャルペーパーやその他の資産を含んでいたことが明らかになった 29。Tether社とBitfinexは、最終的にNYAGと和解し、罰金を支払うとともに、準備資産の内訳を四半期ごとに公表することを義務付けられた。
その後、Tether社は準備資産の質を改善し、コマーシャルペーパーの保有をゼロにして短期米国債の割合を増やすなど、透明性向上に努めている。しかし、依然として完全な監査報告書は公開されておらず、その準備資産の全体像や流動性については疑問視する声も根強い。2018年10月には、準備資産への懸念から一時0.88ドルまで価格が下落するなど、過去に何度か小規模なデペッグを経験している 29。
Tetherの事例は、ステーブルコインの安定性が、発行体の誠実さと透明性にいかに大きく依存しているかを示している。利用者は、プロトコルの設計だけでなく、それを運営する組織そのものの信頼性(信用リスク)を評価する必要がある。
これらの歴史的失敗から得られる最大の教訓は、ステーブルコインは金融リスクを消し去る魔法の杖ではないということだ。それは、ビットコインが持つ「価格リスク」を、別の形態のリスク—すなわち、Terraの「設計リスク」、USDCの「カウンターパーティリスク」、Tetherの「透明性・信用リスク」—へと「変換」する技術なのである。どのステーブルコインを利用するかという選択は、どの種類のリスクを受け入れるかという選択に他ならない。
第5章:日本の現在地 — 改正資金決済法と「JPYC」のすべて
世界中でステーブルコインの規制に関する議論が白熱する中、日本は独自の法整備によって世界に先駆けたアプローチを示した。その中心にあるのが、2023年6月1日に施行された改正資金決済法と、その枠組みの下で誕生した日本初のステーブルコイン「JPYC」である。
5.1. 世界に先駆けた法整備:改正資金決済法
Terraショックなどを受け、ステーブルコインのリスクが世界的に認識される中、日本は迅速に法整備を進めた。2023年の資金決済法改正の最大のポイントは、ステーブルコインを「電子決済手段」として法的に明確に定義したことである 1。
この定義の核心は、ステーブルコインをビットコインのような投機目的の「暗号資産」とは明確に区別し、あくまで決済や送金に用いる「支払い手段」として位置付けた点にある 12。これにより、ステーブルコインは暗号資産交換業の規制ではなく、既存の資金移動業(送金サービス)や銀行業の規制の延長線上で扱われることになった。
この法律の下では、日本円に連動するステーブルコインを発行できるのは、以下の3種類のライセンスを持つ事業者に限定される 12。
- 銀行
- 信託会社
- 資金移動業者
さらに、発行者には、発行したステーブルコインと同額以上の資産を、預金や国債といった安全な形で国内で保全することが義務付けられている。これにより、利用者の資産保護が徹底され、万が一発行者が破綻した場合でも、利用者は預けた資産を取り戻せる仕組みが構築された。
5.2. JPYCとは何か?
JPYCは、この改正資金決済法の枠組みに基づき、日本で初めて「電子決済手段」として発行された日本円連動ステーブルコインである。その発行主体であるJPYC株式会社は、資金移動業者としてのライセンスを金融庁から取得している 1。
実は、JPYCには前身となるモデルが存在する。2021年から発行されていた旧JPYCは、法律上「前払式支払手段」として扱われていた 63。これは、SuicaやPASMOのような交通系ICカードや、商品券と同様の位置付けであり、一度購入すると日本円に払い戻す(償還する)ことが原則としてできなかった 13。
しかし、改正資金決済法に基づく新たな「電子決済手段」としてのJPYCは、この点が大きく異なる。現在のJPYCは、利用者がいつでも「1 JPYC = 1円」で日本円への償還を請求できる権利が法的に保証されている 1。これにより、JPYCは単なるプリペイド式の電子マネーから、銀行預金に近い性質を持つ、より信頼性の高いデジタル通貨へと進化したのである。
5.3. JPYCの仕組みと安全性
JPYCは、第3章で解説した分類のうち、「法定通貨担保型」に該当する。その仕組みは非常に堅牢に設計されている。
- 完全な裏付け資産: JPYC株式会社は、発行したJPYCの総額と100%同額の日本円を、銀行預金および国債という形で国内の金融機関に保全している 2。これにより、常に1 JPYC = 1円での償還が保証される。
- 発行と償還のプロセス: 利用者は、JPYC株式会社が提供するプラットフォーム「JPYC EX」を通じて、銀行振込で日本円を入金することでJPYCを発行(購入)できる。逆に、保有するJPYCをJPYC EXで償還申請すれば、指定した銀行口座に日本円が振り込まれる 1。
- 対応ブロックチェーン: JPYCは、イーサリアム(Ethereum)、ポリゴン(Polygon)、アバランチ(Avalanche)といった複数の主要なパブリックブロックチェーン上で発行されており、利用者は用途に応じて使い分けることができる 12。
- ノンカストディ型: JPYCの大きな特徴の一つが、利用者が自身の資産を完全に自己管理する「ノンカストディ型」である点だ 69。利用者は、取引所のような第三者に資産を預けるのではなく、MetaMaskなどの自身のデジタルウォレットでJPYCを直接保有・管理する。これにより、取引所のハッキングや破綻といったリスクから資産を保護できる一方、ウォレットの秘密鍵を自己責任で厳重に管理する必要がある 68。
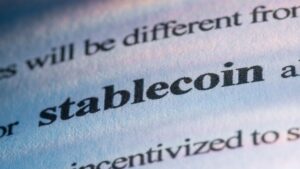
5.4. JPYCのユースケースと将来性
法的に裏付けられた安定性と安全性を備えたJPYCは、日本国内で多様なユースケースを切り拓く可能性を秘めている。
- 個人・法人間の送金・決済: ブロックチェーンを利用することで、銀行の営業時間に関わらず、24時間365日、ほぼリアルタイムかつ低コストでの送金が可能になる。特に、従来の銀行送金では手数料が高額になりがちな少額の送金や、国際送金において大きなメリットを発揮する 1。
- Web3サービスとの連携: NFTマーケットプレイスでの売買代金の決済、ブロックチェーンゲーム内でのアイテム購入、DAO(自律分散型組織)の運営資金管理など、Web3エコシステムにおける日本円建ての基軸通貨としての役割が期待される 68。
- オープンな金融インフラ: JPYCの最も重要な側面は、特定のサービスに閉じることなく、誰でも自由に自社のサービスに組み込める「オープンな金融インフラ」である点だ 68。これにより、開発者はJPYCを決済機能として自社のアプリケーションに容易に統合でき、ECサイトでの支払いや、クリエイターへの投げ銭、B2Bの請求書払いなど、革新的なサービスが次々と生まれる土壌となる 74。
日本の規制アプローチは、いわば「ウォールド・ガーデン(壁に囲まれた庭)」戦略と見ることができる。暗号資産市場が持つ投機性や規制の不確実性といったリスクを国内に持ち込むことを避けつつ、ステーブルコインが持つ「決済手段」としての利便性や効率性という果実だけを安全に享受しようという意図がうかがえる。この戦略は、イノベーションを促進しつつも金融システムの安定を最優先する、日本らしい慎重かつ戦略的な選択と言えるだろう。JPYCは、この日本独自の「庭」の中で、デジタル円インフラのスタンダードとなることを目指している。
第6章:世界の規制動向と未来への展望
日本のJPYCが国内の法整備を背景に歩み始めた一方で、世界の主要国もまた、ステーブルコインという新たな金融形態にいかに向き合うか、それぞれの戦略を描いている。ステーブルコインの未来は、こうしたグローバルな規制の潮流と、国家が発行するデジタル通貨(CBDC)との関係性の中で形作られていく。
6.1. 各国の規制アプローチ
ステーブルコインに対する規制のアプローチは、国や地域によって異なるが、利用者保護と金融システムの安定という共通の目標に向かって収斂しつつある。
- 欧州連合(EU):MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation)
EUは、世界に先駆けて包括的な暗号資産規制の枠組みであるMiCAを導入した。2024年6月からステーブルコインに関する規定が施行され、発行者に対して厳格な要件を課している 14。具体的には、十分な流動性を持つ準備資産の保有、明確なガバナンス体制の構築、利用者に対する償還権の保証、そして規制当局からの認可取得などが義務付けられている 4。MiCAは、27の加盟国に共通のルールを提供することで、域内でのイノベーションを促進しつつ、Terraショックのような失敗の再発を防ぐことを目指している。 - 米国:GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)
米国では長らく連邦レベルでの統一された規制が存在しなかったが、2025年7月に画期的な法律「GENIUS Act」が成立した 28。この法律は、「決済ステーブルコイン」というカテゴリーを創設し、その発行者を連邦政府の監督下にある銀行や、適格と認められたノンバンク事業者に限定した 22。また、準備資産は現金や短期米国債など、高品質かつ流動性の高い資産で1対1の裏付けを行うことを厳格に義務付けている。これにより、ステーブルコインは証券や商品(コモディティ)とは異なる、決済手段としての法的地位を明確に得た。 - 国際機関(FSB、IMF)の役割
ステーブルコインは本質的にグローバルな性質を持つため、一国だけの規制では不十分である。国境を越えた規制の抜け穴(規制アービトラージ)を防ぎ、国際的な金融システムの安定を維持するため、金融安定理事会(FSB)や国際通貨基金(IMF)といった国際機関が重要な役割を果たしている。FSBは、各国が導入すべき規制のハイレベルな原則(例:包括的な監督、強固なガバナンス、適切なリスク管理)を策定し、加盟国にその一貫した実施を促している 77。IMFは、特に新興国において、米ドル建てステーブルコインの普及が自国の金融政策や通貨主権に与える影響(いわゆる「デジタル・ドル化」)について警鐘を鳴らし、マクロ経済の安定性を考慮した慎重な対応を求めている 80。
6.2. ステーブルコイン vs. CBDC
ステーブルコインの台頭と並行して、世界中の中央銀行が研究・開発を進めているのが「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」である。この二つは、しばしば混同されるが、その本質は根本的に異なる。
- 発行主体の違い: ステーブルコインは、Circle社やJPYC社のような民間企業が発行する「民間の負債」である。一方、CBDCは、日本銀行のような中央銀行が直接発行する「中央銀行の負債」であり、現金(銀行券)のデジタル版に相当する 20。
- 信用の根拠: ステーブルコインの信用は、発行体の健全性やその準備資産の質に依存する。発行体が破綻すれば、その価値は失われる可能性がある。対照的に、CBDCの信用は国家そのものであり、究極的にリスクフリーな決済手段となる。
では、この二つは競合するのだろうか、それとも共存するのだろうか。多くの専門家は、両者が互いに補完し合う未来を描いている。CBDCが、金融システム全体の決済を支える究極の決済資産(ホールセール型CBDC)や、国民全体に提供される安全なデジタル通貨(リテール型CBDC)として機能する一方で、ステーブルコインはその上で動く、より多様で革新的な金融サービスを民間企業が提供するためのツールとして活用される可能性がある 20。例えば、プログラム可能な決済や、特定の商取引に特化した支払いなど、ステーブルコインならではの柔軟性が活かされる場面は多い。
このグローバルな規制競争の背景には、単なる金融安定化を超えた、地政学的な思惑も存在する。ステーブルコイン市場の圧倒的多数は米ドルにペッグされており、その取引の多くは米国外で行われている 17。これは、民間主導の「デジタル・ドル化」が世界中で静かに進行していることを意味する。この現象は、準備資産としての米国債への巨大な需要を生み出し、結果として米ドルの基軸通貨としての地位をデジタル時代においても強化する効果を持つ 18。
この文脈で米国のGENIUS Actを見ると、その戦略的な意図が浮かび上がってくる。この法律は、米ドル建てステーブルコインに明確で安全な法的枠組みを与えることで、その国際的な普及を後押しするものである。つまり、これは単なる国内規制ではなく、デジタル経済時代の新たな金融覇権を巡る、高度な国家戦略の一環と捉えることができる。米国は、次世代の金融インフラが、規制された安全な「デジタル・ドル」を基盤として構築されることを目指しているのである 24。

第7章:最新研究動向 — ステーブルコインは金融をどう変えるか?
ステーブルコインは、単なる便利な決済手段に留まらない。その影響は金融市場の根幹にまで及び、学術界や金融業界の最先端では、ステーブルコインがもたらす構造的な変化に関する研究が活発に進められている。
7.1. 金融市場へのインパクト:米国債市場の新たな買い手
ステーブルコインエコシステムの拡大が、伝統的な金融市場、特に世界で最も重要な安全資産である米国債の市場に、直接的かつ測定可能な影響を与えていることが、近年の研究で明らかになってきている。
ステーブルコイン発行体、特にTether社やCircle社は、その巨額の準備資産を運用するために、短期米国債(T-Bill)の主要な買い手となっている。その保有額は、もはや一国に匹敵する規模に達しており、サウジアラビアなどの主要な米国債保有国を上回ることもある 18。
国際決済銀行(BIS)や学術機関による計量分析によれば、ステーブルコインへの資金流入は、短期米国債の利回りを有意に低下させる効果があることが示されている 85。ある研究では、2標準偏差に相当する規模の資金流入(約35億ドル)が、3ヶ月物T-Billの利回りを10日以内に2〜2.5ベーシスポイント押し下げると推定されている 86。これは、ステーブルコインへの需要が、米国政府の資金調達コストを実際に引き下げていることを意味する。逆に、資金流出時には利回りを押し上げる効果が流入時の2〜3倍大きく、市場ストレス時の潜在的な不安定要因にもなり得ることが指摘されている 85。
この事実は、これまで別世界のものと見なされてきた暗号資産エコシステムが、いかに深くグローバルなマクロ経済と金融政策の領域に組み込まれつつあるかを示している。
7.2. RWA(現実世界資産)のトークン化:次のフロンティア
ステーブルコインが切り拓く未来として、現在最も注目されているのが「RWA(Real-World Asset)のトークン化」という分野である 88。
RWAトークン化とは、不動産、美術品、株式、債券、プライベートクレジットといった、現実世界に存在する有形・無形の資産を、ブロックチェーン上でデジタルトークンとして表現し、取引可能にすることを指す 7。これにより、従来は流動性が低く、取引が困難だった資産を細分化し、グローバルな市場で24時間取引することが可能になる。
このRWAエコシステムにおいて、ステーブルコインは決定的に重要な役割を果たす。それは、トークン化された現実資産を売買、担保、貸借するための「決済・精算レイヤー」としての機能である。プログラム可能な「デジタル・キャッシュ」であるステーブルコインがあるからこそ、RWAの取引をスマートコントラクトで自動化し、効率的かつ透明性の高い金融市場を構築できる。ブラックロックのような世界最大の資産運用会社もこの分野に参入しており、RWAトークン化は、DeFiと伝統的金融(TradFi)を本格的に融合させ、数兆ドル規模の新たな市場を創出する可能性を秘めている 89。
7.3. 技術革新の最前線
ステーブルコインを巡る技術革新もまた、日進月歩で進んでいる。現在の研究開発は、既存の課題を解決し、新たな可能性を拓くことに焦点が当てられている。
- プライバシーとコンプライアンスの両立: ステーブルコインの課題の一つに、利用者のプライバシー保護と、マネーロンダリング対策(AML)などの規制遵守との間の緊張関係がある。この問題を解決する技術として、「ゼロ知識証明(Zero-Knowledge Proofs)」を活用した「zkKYC」といったコンセプトが研究されている 90。これは、利用者が自身の詳細な個人情報を明かすことなく、規制上必要な条件(例:本人確認済みであること、18歳以上であることなど)を満たしていることだけを暗号学的に証明する技術である。これにより、プライバシーを保護しながら、コンプライアンスを設計段階からシステムに組み込む「コンプライアンス・バイ・デザイン」が実現できると期待されている。
- 新たなステーブルコインモデルの探求: 学術界では、さらに進んだステーブルコインのモデルも提案されている。例えば、「時間制限付きステーブルコイン(Time-bound stablecoins)」という概念がある 91。これは、株式などの伝統的な証券が取引所の閉場時間中に取引できないという「時間の非効率性」に着目し、その時間帯に限り証券を一時的にトークン化して、24時間流動性を提供しようという試みである。
これらの研究動向が示す未来像は、ステーブルコインが単に伝統的金融システムを模倣したり、代替したりするものではないという点である。むしろ、その最終的な到達点は、両システムの融合にある。ステーブルコインは、伝統的な資産をブロックチェーンという現代的で効率的なレールに乗せるための触媒として機能し、その過程で、それ自身もまた米国債市場のように伝統的金融システムの根幹に深く組み込まれていく。それは、二つの世界のどちらかが勝利するのではなく、ステーブルコインを共通言語および決済レイヤーとして、両者が一体となったハイブリッドな金融システムが誕生する未来を示唆している。
結論:ステーブルコインが拓く金融の未来と残された課題
本稿では、日本におけるJPYCの登場を機に、ステーブルコインという金融イノベーションの全体像を、その基本概念から歴史、仕組み、リスク、そして未来の展望に至るまで、多角的に掘り下げてきた。
ステーブルコインの物語は、ビットコインが抱えていた「価格変動」という根源的な課題を克服しようとする試みから始まった。当初は暗号資産トレーダーのためのニッチなツールであったが、やがてその安定性とブロックチェーン技術の利便性が融合することで、国際送金、DeFiの基盤、インフレからの資産防衛など、多様なユースケースを切り拓き、瞬く間に世界的な金融現象へと発展した 4。
しかし、その道のりは栄光ばかりではなかった。Terra/LUNAの劇的な崩壊はアルゴリズム型モデルの設計上の脆弱性を、USDCの一時的なペッグ外れは伝統的金融システムへの依存というカウンターパーティリスクを、そしてTetherを巡る長年の論争は発行体の透明性というガバナンス上の課題を、それぞれ白日の下に晒した。これらの危機を通じて、我々はステーブルコインが金融リスクを消滅させるのではなく、新たな形態へと「変換」する技術であることを学んだ。
こうした試練の時を経て、ステーブルコインは今、無法地帯の時代を終え、制度化の時代へと移行しつつある。EUのMiCA、米国のGENIUS Act、そして日本の改正資金決済法といった包括的な規制の枠組みは、イノベーションの火を消すことなく、利用者保護と金融システムの安定を確保しようとする各国の強い意志の表れである 92。日本が選択した、ステーブルコインを「電子決済手段」と位置付け、厳格な監督下に置くというアプローチは、このグローバルなテクノロジーを国内で安全に活用するための、慎重かつ戦略的な一歩と言えるだろう。
未来を見据えれば、ステーブルコインの可能性は決済の効率化に留まらない。現実世界資産(RWA)のトークン化における基盤通貨としての役割や、米国債市場への影響力に見られるように、伝統的金融とデジタル金融を融合させる触媒としてのポテンシャルは計り知れない 10。それは、国家が発行するCBDCと時に競合し、時に補完し合いながら、21世紀の通貨システムのあり方を形作っていくことになるだろう。
残された課題は依然として大きい。マネーロンダリング対策とプライバシー保護の両立、国境を越えた規制の調和、そして大規模なステーブルコインが破綻した際のシステミックリスクへの備えなど、解決すべき問題は山積している 10。
日本のJPYCの歩みは、この壮大な物語の新たな一章の始まりである。ステーブルコインがもたらす革新の恩恵を最大限に引き出しつつ、その影に潜むリスクをいかに賢明に管理していくか。その答えを探す旅は、まだ始まったばかりだ。確かなことは、ステーブルコインが、デジタル時代における「お金」そのものの進化の最前線にいるということである。
引用文献
- JPYCとは?特徴や将来性、注意点やリスクを徹底解説! | CRYPTO INSIGHT powered by ダイヤモンド・ザイ, 11月 3, 2025にアクセス、 https://diamond.jp/crypto/market/jpyc/
- 円ステーブルコインJPYC、発行額1億円突破|ローンチから7日, 11月 3, 2025にアクセス、 https://cryptodnes.bg/jp/japan-stablecoin-jpyc-surpasses-100-million-issuance/
- JPYC stablecoin launches in Japan. Has a fraud compensation policy, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.ledgerinsights.com/jpyc-stablecoin-launches-in-japan-has-a-fraud-compensation-policy/
- Stablecoins: The future of money? | Roland Berger, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/Roland_Berger_Stablecoins-_The_future_of-_money.pdf?v=1314188
- What to Know About Stablecoins | J.P. Morgan Global Research, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/currencies/stablecoins
- [2507.13883] Stablecoins: Fundamentals, Emerging Issues, and Open Challenges – arXiv, 11月 3, 2025にアクセス、 https://arxiv.org/abs/2507.13883
- Stablecoins: Market Developments, Risks and Regulation, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2022/dec/pdf/stablecoins-market-developments-risks-and-regulation.pdf
- STABLECOINS IN CRYPTOECONOMICS: FROM INITIAL COIN OFFERINGS TO CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES – N.Y.U. Journal of Legislation & Public Policy, 11月 3, 2025にアクセス、 https://nyujlpp.org/wp-content/uploads/2019/12/DellErba-Stablecoins-in-Cryptoeconomics-22-nyujllp-1.pdf
- Stablecoins vs. Bitcoin: 7 Major Differences Explained – Transak, 11月 3, 2025にアクセス、 https://transak.com/blog/stablecoins-vs-bitcoin
- Report on Stablecoins – Treasury, 11月 3, 2025にアクセス、 https://home.treasury.gov/system/files/136/StableCoinReport_Nov1_508.pdf
- Crypto’s Conservative Coins – International Monetary Fund (IMF), 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/09/Basics-Crypto-conservative-coins-Bains-Singh
- 【国内初】日本円建ステーブルコイン発行へ-資金移動業者の登録を取得 – JPYC株式会社, 11月 3, 2025にアクセス、 https://corporate.jpyc.co.jp/news/posts/first-yen-stablecoin-jpyc
- ステーブルコイン・暗号資産・電子決済手段・前払式支払手段、今さら聞けない それらの違いは?, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.neweconomy.jp/features/stablecoin/496234
- Stablecoins – European Parliament, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698803/EPRS_BRI(2021)698803_EN.pdf
- Stablecoins vs bitcoin: The 3 major differences explained | BVNK Blog, 11月 3, 2025にアクセス、 https://bvnk.com/blog/stablecoins-vs-bitcoin
- JPYCoin (JPYC)WhitePaper, 11月 3, 2025にアクセス、 https://jpyc.jp/white-paper.pdf
- Stablecoins: Growth Potential and Impact on Banking – Federal …, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.federalreserve.gov/econres/ifdp/files/ifdp1334.pdf
- Stablecoins, Tokens, and Global Dominance – International Monetary Fund (IMF), 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2025/09/stablecoins-tokens-global-dominance-helene-rey
- Understanding Stablecoins and their Mechanisms (24.03.2025)|Crypto, Markets – ECEBiS, 11月 3, 2025にアクセス、 https://ecebis.com/posts/understanding-stablecoins-and-their-mechanisms-24032025crypto-markets
- What is a stablecoin? – McKinsey, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-a-stablecoin
- Stablecoin Companies Are Worth Billions. But What Do They Actually Do? – Investopedia, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.investopedia.com/stablecoin-companies-are-worth-billions-but-what-do-they-actually-do-11821909
- How Will the International Financial Institutions Manage the Stablecoin Stampede?, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.cgdev.org/blog/how-will-international-financial-institutions-manage-stablecoin-stampede
- Speech by Governor Barr on stablecoins – Federal Reserve Board, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/barr20251016a.htm
- Stablecoin – Wikipedia, 11月 3, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Stablecoin
- What are stablecoins, and how are they regulated? – Brookings Institution, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.brookings.edu/articles/what-are-stablecoins-and-how-are-they-regulated/
- The History of Stablecoins – Deltec Bank and Trust, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.deltecbank.com/news-and-insights/the-history-of-stablecoins/
- What is a stablecoin? | Hedera, 11月 3, 2025にアクセス、 https://hedera.com/learning/tokens/what-is-a-stablecoin
- The Evolution and Impact of Stablecoins in Global Markets, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.capgemini.com/us-en/wp-content/uploads/sites/30/2025/08/Evolution-and-Impact-of-Stablecoins-in-Global-Markets-POV.pdf
- Tether (cryptocurrency) – Wikipedia, 11月 3, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Tether_(cryptocurrency)
- An Introduction to Stablecoins | Advisories – Arnold & Porter, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.arnoldporter.com/en/perspectives/advisories/2025/05/an-introduction-to-stablecoins
- What is cryptocurrency Tether (USDT) and how does it work? – Kriptomat, 11月 3, 2025にアクセス、 https://kriptomat.io/cryptocurrency-prices/tether-usdt-price/what-is/
- About Tether, 11月 3, 2025にアクセス、 https://tether.to/ru/about-us/
- Tether – Overview, History, Stablecoins, Supply – Corporate Finance Institute, 11月 3, 2025にアクセス、 https://corporatefinanceinstitute.com/resources/cryptocurrency/tether/
- Stablecoin Evolution: Milestones up to the New GENIUS Act ✍️ – Voronoi, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.voronoiapp.com/money/Stablecoin-Evolution-Milestones-up-to-the-New-GENIUS-Act–5942
- Stablecoin Evolution: Milestones of the New Payment Rail – Visual Capitalist, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.visualcapitalist.com/sp/pla01-stablecoin-evolution-milestones-of-the-new-payment-rail/
- en.wikipedia.org, 11月 3, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Dai_(cryptocurrency)#:~:text=from%20lending%20DAI.-,History,on%20the%20main%20Ethereum%20network.
- DeFi Weekly: MakerDAO — The Protocol That Created Decentralized Money | by Ferdi Kurt | Coinmonks | Medium, 11月 3, 2025にアクセス、 https://medium.com/coinmonks/defi-weekly-makerdao-the-protocol-that-created-decentralized-money-41058b3b0a50
- The State of Stablecoin Regulation and Emergence of Global Principles, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.americanbar.org/groups/business_law/resources/business-law-today/2024-september/state-stablecoin-regulation-emergence-global-principles/
- LUNA’s Collapse: A Detailed Timeline | MyLens AI, 11月 3, 2025にアクセス、 https://mylens.ai/space/d-glendinnings-workspace-gowd8q/lunas-collapse-detailed-timeline-z0b0cr
- Terra (blockchain) – Wikipedia, 11月 3, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Terra_(blockchain)
- finance.unibocconi.eu, 11月 3, 2025にアクセス、 https://finance.unibocconi.eu/sites/default/files/files/media/attachments/terralunacrash_april202320230516135124.pdf
- Collapse of Silicon Valley Bank and USDC Depegging: A Machine Learning Experiment, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2674-1032/3/4/30
- USDC stablecoin depegs 12% on SVB collapse – ETF Stream, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.etfstream.com/articles/usdc-stablecoin-depegs-12-on-svb-collapse
- Crypto Market Reaction to Silicon Valley Bank and USDC Depeg – Chainalysis, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.chainalysis.com/blog/crypto-market-usdc-silicon-valley-bank/
- Stablecoins 101: A Payments Professional’s Guide to Fiat-Backed Crypto | Fireblocks, 11月 3, 2025にアクセス、 https://fireblocks.com/report/stablecoins-101/
- Stablecoins explained: A primer on these digital assets – Mastercard, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.mastercard.com/global/en/news-and-trends/stories/2025/what-is-a-stablecoin.html
- A Historical Perspective on Stablecoins – Liberty Street Economics, 11月 3, 2025にアクセス、 https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2025/10/a-historical-perspective-on-stablecoins/
- STABLECOIN SUMMER | Goldman Sachs, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.goldmansachs.com/pdfs/insights/goldman-sachs-research/stablecoin-summer/TopOfMind.pdf
- Stablecoins Explained: Definitions, Mechanisms, and Types, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.investopedia.com/terms/s/stablecoin.asp
- Maker – Blockchain.com, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.blockchain.com/learning-portal/tokens/maker-explained
- Maker – Whitepaper – MakerDAO, 11月 3, 2025にアクセス、 https://makerdao.com/da/whitepaper/
- MakerDAO Overview – Reflexivity Research, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.reflexivityresearch.com/free-reports/makerdao-overview
- Why do stablecoins depeg? – Coinbase, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/why-do-stablecoins-depeg
- Exploring the Tether Controversy: A Comprehensive History of Stablecoins in Cryptocurrency – BlockApps Inc., 11月 3, 2025にアクセス、 https://blockapps.net/blog/exploring-the-tether-controversy-a-comprehensive-history-of-stablecoins-in-cryptocurrency/
- III. The next-generation monetary and financial system – Bank for International Settlements, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2025e3.htm
- New BIS report raises concerns with stablecoins – ICBA, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.icba.org/newsroom/news-and-articles/2025/06/25/new-bis-report-raises-concerns-with-stablecoins
- The Financial Stability Implications of Digital Assets – Federal Reserve Bank of New York, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/2024/EPR_2024_digital-assets_azar.pdf
- Terra (LUNA): Blockchain and Algorithmic Stablecoins – ECOS, 11月 3, 2025にアクセス、 https://ecos.am/en/blog/terra-luna/
- How algorithmic stablecoins fail – Swiss National Bank, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.snb.ch/dam/jcr:5140cb30-3c8c-433d-8619-0354b8f1036e/sem_2023_05_26_rostova.n.pdf
- The USDC De-Peg Explained – YouTube, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=q19SYmnaXh0
- What Is Tether (USDT)? Understanding Its Importance and Uses – Investopedia, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.investopedia.com/terms/t/tether-usdt.asp
- Stablecoin depegging: The what and why | Kraken Learn Center, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.kraken.com/learn/stablecoin-depegging
- 日本円ステーブルコイン「JPYC」とは?仕組みと注意点を解説 | クリプタクト, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.cryptact.com/blog/jpyc-features
- 改正資金決済法内閣府令案についてのJPYCとしての考え方, 11月 3, 2025にアクセス、 https://corporate.jpyc.co.jp/news/posts/BusinessStrategy202302
- 日本初ステーブルコイン「JPYC」、新規発行額が1億円突破、リリース後6日で, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.neweconomy.jp/posts/511975
- JPYCが国内初の「円建てステーブルコイン」発行へ。岡部社長が「暗号資産」との違いを強調, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.businessinsider.jp/article/2508-jpyc-yen-denominated-stablecoin/
- JPY Coin(JPYC)とは?特徴や購入方法・今後の見通しや将来性を徹底解説, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.for-it.co.jp/mediverse/cryptocurrency/jpycoin-jpyc/
- JPYCの買い方・使い方まとめ|何ができる?今後の活用法・注意点を徹底解説 – CoinPost, 11月 3, 2025にアクセス、 https://coinpost.jp/?p=643693
- JPYC株式会社, 11月 3, 2025にアクセス、 https://jpyc.co.jp/
- 国内初の日本円建ステーブルコイン「JPYC」の発行・償還サービスに「ICおまかせパック」で公的個人認証(JPKI)を提供 – PR TIMES, 11月 3, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000061051.html
- 【本日発行】国内初の円ステーブルコインJPYC、今日からどう使う? 入手方法から活用法まで岡部代表が語った「最速スタートガイド」 – CoinDesk Japan, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.coindeskjapan.com/320855/
- JPYCとは?ステーブルコインの特徴・使い方・投資の可能性を解説 – Mediverse, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.for-it.co.jp/mediverse/cryptocurrency/jpyc/
- 【国内初】日本円ステーブルコイン「JPYC」および発行・償還プラットフォーム「JPYC EX」を正式リリース – PR TIMES, 11月 3, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000283.000054018.html
- 本日開始「JPYC」は「PayPay」と何がちがうの?―ステーブルコインはAIと組み合わさることで最強へ|Jun Ikematsu / 池松潤 – note, 11月 3, 2025にアクセス、 https://note.com/ikematsu/n/n7151dfb1e8ab
- JPYC関数 完全ガイド 〜ステーブルコイン決済の機能とユースケース〜 – Zenn, 11月 3, 2025にアクセス、 https://zenn.dev/mameta29/articles/4dcb803377b4ae
- Stablecoins: Issues for regulators as they implement GENIUS Act – Brookings Institution, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.brookings.edu/articles/stablecoins-issues-for-regulators-as-they-implement-genius-act/
- FSB finds significant gaps and inconsistencies in implementation of crypto and stablecoin recommendations – Financial Stability Board, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.fsb.org/2025/10/fsb-finds-significant-gaps-and-inconsistencies-in-implementation-of-crypto-and-stablecoin-recommendations/
- Thematic Review on FSB Global Regulatory Framework for Crypto-asset Activities, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.fsb.org/2025/10/thematic-review-on-fsb-global-regulatory-framework-for-crypto-asset-activities/
- IMF-FSB Joint Report: G20 Crypto Asset Policy Implementation Roadmap, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/-/media/Files/Research/imf-and-g20/2024/imf-fsb-g20-crypto-asset-policy-implementation-roadmap.ashx
- The Changing Landscape of Crypto Assets—Considerations for Regulatory and Supervisory Authorities, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/02/23/sp022324-changing-landscape-crypto-assets-considerations-regulatory-and-supervisory-authorities
- How are CBDCs different from cryptocurrencies and stablecoins? | World Economic Forum, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.weforum.org/stories/2023/11/cbdcs-how-different-cryptocurrency-stablecoin/
- Central Bank Digital Currencies: Policy Issues | Congress.gov, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.congress.gov/crs-product/R46850
- Central Bank Digital Currency, Design Choices, and Impacts on Currency Internationalization – CSIS, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.csis.org/analysis/central-bank-digital-currency-design-choices-and-impacts-currency-internationalization
- The rise of stablecoins and implications for Treasury markets – Brookings Institution, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.brookings.edu/articles/the-rise-of-stablecoins-and-implications-for-treasury-markets/
- Stablecoins and safe asset prices – Bank for International Settlements, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.bis.org/publ/work1270.htm
- BIS Working Papers No 1270 – Stablecoins and safe asset prices – Bank for International Settlements, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.bis.org/publ/work1270.pdf
- [2505.12413] The Stablecoin Discount: Evidence of Tether’s U.S. Treasury Bill Market Share in Lowering Yields – arXiv, 11月 3, 2025にアクセス、 https://arxiv.org/abs/2505.12413
- [2508.02403] SoK: Stablecoins for Digital Transformation — Design, Metrics, and Application with Real World Asset Tokenization as a Case Study – arXiv, 11月 3, 2025にアクセス、 https://arxiv.org/abs/2508.02403
- Even BlackRock is Investing in RWA. What is it? MEMO Explains from a Data Perspective., 11月 3, 2025にアクセス、 https://memolabs.medium.com/even-blackrock-is-investing-in-rwa-what-is-it-memo-explains-from-a-data-perspective-bbfc1b59e86c
- The Stablecoin Balancing Act – International Monetary Fund (IMF), 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2025/09/the-stablecoin-balancing-act-darrell-duffie
- Intertemporal Pricing of Time-Bound Stablecoins: Measuring and Controlling the Liquidity-of-Time Premium – arXiv, 11月 3, 2025にアクセス、 https://arxiv.org/html/2510.05711v1
- How Stablecoins and Other Financial Innovations May Reshape the Global Economy, 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2025/09/04/how-stablecoins-and-other-financial-innovations-may-reshape-the-global-economy
- STABLECOINS AND THE FUTURE OF FINANCE – International Monetary Fund (IMF), 11月 3, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/Fandd/Article/2025/09/fd-september-2025.ashx