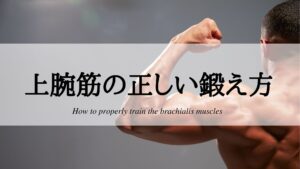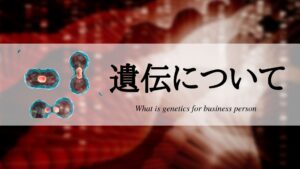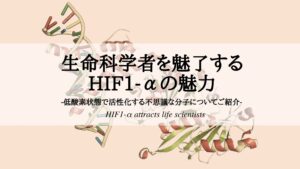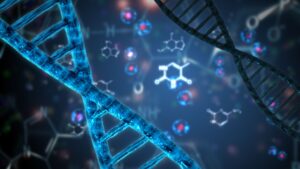【第1章】生命を「透かす」技術、CUBICへようこそ
導入:なぜ「透明化」が必要なのか?
私たちの体や臓器は、当たり前ですが不透明です。この不透明性こそが、生命の複雑な構造を理解する上で、長らく生物学者や医師の前に立ちはだかる最大の壁となってきました。
(一般読者向け解説)私たちの体や臓器はなぜ不透明か?
生物の組織が不透明なのには、大きく分けて二つの理由があります。
- 光の散乱:これが不透明であることの最大の理由です。私たちの組織は、細胞、水、タンパク質、そして脂質など、様々な成分でできています。光は、異なる「屈折率」を持つ物質の境界面を通過するたびに、進路を曲げられ、乱反射します。これを「散乱」と呼びます。組織内にはこの境界面がナノメートルスケールで無数に存在するため、光は内部までまっすぐ届かず、組織は白く濁って見えます 1。
- 光の吸収:組織には、特定の色の光を吸収する「色素」が存在します。最も代表的なものは、血液の赤色のもとである「ヘモグロビン」や、皮膚や毛髪の色素である「メラニン」です 2。これらの色素が光を吸収してしまうため、組織の奥深くまで光が届きません。
(一般読者向け解説)すりガラスが水で濡れると透明になる原理
この「光の散乱」の問題は、すりガラスの例で考えると直感的に理解できます。すりガラスの表面は、目に見えないレベルでザラザラ(凹凸)になっています 3。空気(屈折率 $1.0$)とガラス(屈折率 $1.5$)では屈折率が大きく異なるため、光が表面の凹凸で乱反射し、向こう側が見えなくなります。
しかし、このすりガラスに水を垂らすとどうなるでしょうか。ザラザラした表面の凹凸が水(屈折率 $1.33$)で満たされ、空気の代わりに水がガラスに接します。水とガラスの屈折率の「差」は、空気とガラスの「差」よりもずっと小さくなります。これにより、光の乱反射(散乱)が劇的に減少し、透明度が増して向こう側が透けて見えるようになります 4。
組織透明化の原理も、これと全く同じです。組織内の脂質(光散乱の主原因)を取り除き、組織全体を「屈折率が均一な液体」で満たすことで、光の散乱をなくし、組織を透明にすることができるのです 1。
透明化が拓く「3D組織学」のインパクト
従来、私たちが臓器の内部構造を調べる唯一の方法は、臓器を固定し、パラフィンなどに埋め、ミクロン単位の非常に薄い切片(スライス)を作成して顕微鏡で観察することでした。これは「組織学」や「病理診断」の基本です 5。
しかし、この2D(二次元)スライスでは、脳の複雑な神経ネットワークが三次元空間でどう繋がっているのか、あるいは、がんが臓器全体にどのように微小に転移しているのか、その全体像を把握することは不可能でした 7。
組織透明化技術は、この根本的な問題を解決しました。臓器を「丸ごと」透明にし、あたかもゼリーのように透けた状態にすることで、内部の構造をスライスすることなく、ありのままの3D(三次元)のまま観察することを可能にしたのです。これは、生命科学に「3D組織学」という革命的な新しい分野を誕生させました 8。
CUBICとは何か?
この3D組織学の革命をリードする技術の一つが、本レポートの主題である**CUBIC(キュービック)**です。
CUBICの正式名称は “Clear, Unobstructed Brain/Body Imaging Cocktails and Computational analysis” 9。日本語に直訳すれば、「透明で、遮るもののない脳・身体イメージングのためのカクテル(試薬)と、計算論的解析」となります。
この名称には、CUBICという技術の本質がすべて詰まっています。CUBICは、単に「臓器を透明にする試薬(Cocktails)」であるだけではありません。それは、**「① 化学(Cocktails)」で丸ごと透明にし、「② 工学(Imaging)」で高速な顕微鏡(ライトシート顕微鏡など)を用いてその膨大な3D画像を撮像し、そして「③ 情報科学(Computational analysis)」でAIなどを用いてテラバイト級の画像データを解析する、という「三位一体のシステム(パイプライン)」**として設計された技術です 9。
開発当初から「透明にした後の膨大なデータをどう解析し、生物学的な知見を得るか」までを見据えて設計されている点こそが、CUBICの最大の強みであり、革新性なのです。
CUBICの核心的な特徴は、水ベース(Aqueous-based)の安全な試薬を用い、「脱脂(光の散乱をなくす)」「脱色(光の吸収をなくす)」「屈折率マッチング(均一化する)」という3つのステップを、極めて高効率で行う点にあります 1。
【第2章】CUBIC開発の歴史:日本人研究者による革新
CUBICは、日本の研究者によって生み出され、世界に発信された画期的な技術です。その開発は、一人の研究者の明確なビジョンから始まりました。
CUBICの誕生:上田泰己教授の挑戦
CUBICは、理化学研究所(当時)および東京大学大学院医学系研究科の**上田 泰己(Hiroki R. Ueda)**教授の研究室によって開発されました 1。
上田教授は、生命現象を個々の分子や細胞レベルだけでなく、臓器全体、さらには個体全体の相互作用の「システム」として理解する**「個体レベルのシステム生物学(Organism-level systems biology)」**という新しい研究分野を提唱しています 10。
しかし、個体丸ごとのシステムを理解するには、個体丸ごとのデータを取得する技術が必要です。従来の2Dスライスによる観察では、このビジョンの実現は不可能でした。CUBICは、この「個体丸ごと」のデータを取得するという壮大なビジョンを実現するために、まさに必要不可欠な核心的ツールとして生み出されたのです。
着想からブレイクスルーへ(2014年)
開発チームは、先行する水ベースの透明化技術「Scale」(尿素やグリセロール、界面活性剤を使用)に着想を得ました 1。Scaleが持つ「簡便さ」や「蛍光タンパク質(GFPなど)との親和性」といった利点を維持しつつ、より強力で、より高速な透明化を実現する新しい試薬の開発を目指しました 1。
チームは40種類以上の化合物を体系的にスクリーニングする中で、**「アミノアルコール」**という分類の化学物質が、組織の主成分であるタンパク質(特に蛍光タンパク質のシグナル)を温存しつつ、光散乱の最大の原因である「脂質」を極めて効率的に除去(脱脂)できることを発見しました 1。
この発見は、CUBICの化学的原理の根幹をなすブレイクスルーでした。そして2014年、CUBICの基礎を確立する2つの画期的な論文が、立て続けにトップジャーナルで発表されます。
- Susaki et al. (2014):主にマウスの「脳」を対象に、CUBICの基本プロトコルとイメージング手法を確立しました。
- Tainaka et al. (Cell, 2014):CUBICの技術をさらに発展させ、世界で初めて**「マウスの全身透明化」**に成功したことを報告しました 18。透明になったマウスの全身を、1細胞の解像度で丸ごとイメージングするという衝撃的な成果 18 は、世界中の生命科学者に驚きを与え、CUBICの名を一躍有名にしました。
プロトコルの確立と普及:Advanced CUBIC(2015年)
翌2015年、研究チームは、この革新的な技術を世界中の研究者が利用できるように、プロトコルをさらに最適化・標準化した**「Advanced CUBIC」**を、実験手法の標準的教科書とも言える Nature Protocols 誌で発表しました 9。
このプロトコルでは、サンプルを試薬に浸すだけの「浸漬(immersion)法」や、全身の血管網を利用して試薬を灌流させる「CB-perfusion(灌流)法」など、サンプルの種類や目的に応じた複数の手順が詳細に記載されました 9。これにより、CUBICは「誰でも使える」汎用的な技術として世界中に急速に普及していきました。
AIとの融合:CUBIC-XとCUBIC-Atlas(2018年)
CUBICの開発は止まりません。チームはCUBICの化学をさらに進化させ、透明化と同時に組織を物理的に膨潤させることで、顕微鏡で見る際の解像度を擬似的に向上させる「CUBIC-X」という技術を開発します 12。
そして2018年、CUBICは、その名称に込められた最後のピース、すなわち「Computational analysis(計算論的解析)」と本格的に融合します。
CUBIC-Xによる膨潤・透明化技術と、AI(人工知能)による高度な画像解析技術を組み合わせることで、マウスの全脳に存在する約1億個の細胞すべての位置情報をマッピングした、三次元のデジタルアトラス**「CUBIC-Atlas(点描脳アトラス)」**を Nature Neuroscience 誌で発表しました 12。
これは、CUBICが当初から目指していた「化学」「工学」「情報科学」の三位一体のシステムが完成したことを示す、歴史的な成果となりました。
【第3章】CUBICの化学的原理:なぜ透明になるのか?
CUBICが、なぜ脳だけでなく、血液の多い臓器や個体丸ごとまでも透明にできるのか。その秘密は、巧妙に設計された2種類の「カクテル」(試薬)にあります。
CUBICの「カクテル」の秘密
CUBICのプロトコルは、大きく分けて2種類の試薬(カクテル)を順番に使用します 13。
- CUBIC-L (または Reagent-1):
- 脱脂(Lipid removal:脂質除去)と脱色(Decoloration:色素除去)を担当します 13。
- CUBIC-R+ (または Reagent-2):
- 屈折率(Refractive Index)のマッチング(均一化)を担当します 13。
ステップ1:脱脂と脱色(CUBIC-L)
CUBICの化学的革新性は、まさにこのCUBIC-Lにあります。CUBIC-Lの主成分は、Quadrol(N,N,N’,N’-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine)やトリエタノールアミンといった**「アミノアルコール」**と呼ばれる化学物質群です 1。
このアミノアルコールが、従来の透明化技術が抱えていた2つの大きな問題を同時に解決しました。
- 「光の散乱」の解決(=脱脂):
光散乱の最大の原因は、細胞膜や神経の髄鞘などに豊富に含まれる「脂質(リン脂質)」です。アミノアルコールは、そのアミノ基の作用により、この脂質を効率的に組織から溶かし出します(脱脂) 1。 - 「光の吸収」の解決(=脱色):
もう一つの不透明化の原因は、血液中の「ヘモグロビン」に含まれる赤色の色素「ヘム」です。アミノアルコールは、このヘムを効率的に溶出し、洗い流す「脱色」作用も併せ持っています 2。
従来の透明化法の多くは、この「脱色」が苦手でした。特にCLARITYなどの技術では、血液の多い臓器はヘム色素が残り、透明化が不十分になることがありました 9。
CUBICは、「脱脂(散乱の除去)」と「脱色(吸収の除去)」という二大障壁を、アミノアルコールという一つの化学的アプローチによって同時に、かつ効率的に突破しました。これこそが、CUBICが脳だけでなく、心臓、肝臓、腎臓といった血液豊富な臓器 11、さらにはマウスの全身透明化 20 という偉業を達成できた化学的な鍵なのです。
ステップ2:屈折率マッチング(CUBIC-R+)
CUBIC-Lによる処理が終わった組織は、脂質や色素が抜け落ち、タンパク質(と水分)が主体の「骨格」のような状態になっています。しかし、このままではまだ不透明です。なぜなら、組織に残った水(屈折率 $1.33$)とタンパク質(屈折率 $1.55$)の間には、依然として大きな屈折率の「差」が残っているからです。
ここで、第2の試薬であるCUBIC-R+が登場します。CUBIC-R+は、アンチピリンやニコチンアミド、N-ブチルジエタノールアミンといった複数の化学物質を絶妙な比率で混合したカクテルであり、それ自体が非常に高い屈折率(RI $1.47$〜$1.52$)を持つ液体です 21。
このCUBIC-R+に組織を浸すと、組織内の水分がCUBIC-R+の液体に置き換わっていきます。最終的に、タンパク質の骨格も、その隙間を埋める液体も、すべてがほぼ同じ屈折率(例:RI $1.52$)で均一化されます 13。
こうなると、組織の内部にはもはや「屈折率の境界面」が存在しなくなります。光は散乱することなく組織内をまっすぐ突き進むことができるため、組織は「透明」になるのです。CUBIC-R+は、顕微鏡で観察する際に用いるイマージョンオイル(観察用オイル)と屈折率が一致するように設計されており、これにより高画質な画像取得が可能になります 30。
CUBICの特徴:組織膨潤(Expansion)
CUBICは、尿素やアミノアルコールなどを含む水ベースの試薬(Aqueous hyper-hydrating)を用いる手法に分類されます 14。これらの手法の共通の特徴として、処理の過程で組織が水を吸って**膨潤(Expansion)**する傾向があります 14。
CUBIC-R試薬は、組織を各辺 $1.5$倍程度に膨潤させると報告されています 29。これは一見、元の形が崩れるデメリットのように思えるかもしれません。しかし、この膨潤は、組織の「密度」が下がり、内部の構造的な隙間が広がることを意味します。その結果、抗体のような大きな分子が組織の深部まで浸透しやすくなるという、3D免疫染色(組織を丸ごと染めること)において非常に有利な点も生み出しています 29。
【第4章】実験手法:CUBICプロトコルの実践ガイド
CUBICのプロトコルは、基本的には「試薬に浸けて、待つ」という非常にシンプルなステップで構成されています。ここでは、代表的な例として、マウスの臓器(脳など)を透明化する際の基本的な流れを紹介します。
(注:本ガイドは一般的な解説を目的としたものです。実際の実験には、専門の機器、試薬、動物実験に関する倫理規定の遵守、および安全管理が必須です。)
基本的な流れ(マウス臓器の例)
- 組織の固定 (Fixation):
マウスに麻酔をかけ、心臓からPBS(リン酸緩衝生理食塩水)を灌流させて全身の血液を洗い流します。続けて、4% PFA(パラホルムアルデヒド)という固定液を灌流し、全身のタンパク質をその場で固定します。その後、目的の臓器(脳、心臓など)を摘出し、再度4% PFAに一晩(8〜24時間)浸して、中心部までしっかりと固定します 13。 - 洗浄 (Wash):
PBSで数回(例:2時間×3回)洗浄し、組織内に残った余分な固定液を洗い流します 13。 - 脱脂・脱色 (Delipidation & Decoloration):
- (オプション)まず、CUBIC-Lと水を1:1で混合した $0.5\times$ CUBIC-L に一晩浸します。これにより、高濃度の試薬に急に晒すことなく、徐々に組織に浸透させることができます 29。
- $1\times$ CUBIC-L(原液)に交換し、37℃で穏やかに振りながら(振盪させながら)数日間(例:2〜7日)浸漬します。サンプルの大きさや脂質の多さに応じて、組織が透明になり、色素が抜けるまで続けます 13。
- 重要:この間、試薬は組織から溶け出した脂質や色素で飽和していきます。透明化の効率を維持するため、CUBIC-Lは数日おき(例:2日ごと)に新しいものに交換(Refresh)する必要があります 13。
- 洗浄 (Wash):
脱脂・脱色が完了したら、PBSで再度、数時間かけて組織深部のCUBIC-L試薬をしっかり洗い流します 13。 - (オプション)免疫染色 (Staining):
この脱脂後のステップで、抗体を用いた3D免疫染色が可能です 13。CUBICプロトコル専用に最適化された3D染色キット(CUBIC-HV™ など)も市販されており、抗体や核染色試薬を組織深部まで効率的に浸透させることができます 21。 - 屈折率マッチング (RI matching):
- まず、CUBIC-R+と水を1:1で混合した $50\%$ CUBIC-R+ に一晩浸し、組織を高屈折率の溶液に徐々に慣らします 13。
- $100\%$ CUBIC-R+(原液)に交換し、室温で1〜2日浸漬します。これで組織は完全に透明になります 13。
- イメージング (Imaging):
透明化したサンプルを、専用のチャンバーに入れ、ライトシート蛍光顕微鏡(LSFM)などで3D撮像を行います 9。
【表1】CUBIC試薬ファミリーの使い分け
CUBICは、その後の研究の発展に伴い、様々な目的に最適化された派生試薬が開発されています。これらの試薬は、研究者が自分のサンプルや目的に応じて最適なプロトコルを組むことを可能にする「モジュール」として機能します 35。
| 試薬名 | 主な機能・目的 | 推奨される用途・サンプル | 関連スニペット |
| CUBIC-L | 脱脂 および 脱色 | マウスの脳、各種臓器(心臓、肺、腎臓など)の基本的な透明化処理(ステップ1)。 | [13, 21, 29] |
| CUBIC-R+(N) / R+(M) | 屈折率 (RI) マッチング (RI $1.52$) | CUBIC-Lで処理したサンプルの最終的な透明化(ステップ2)。顕微鏡観察用。 | [13, 21, 29, 30] |
| CUBIC-B | 脱灰 (Decalcification) | 骨組織(例:頭蓋骨、大腿骨)を含むサンプルの透明化。骨の主成分であるカルシウムを除去する。 | [13, 21, 29] |
| CUBIC-Lf / CUBIC-Rf | 脱脂・脱色 (Lf) / RIマッチング (Rf) | オルガノイド、スフェロイド、動物の初期胚など、小さく繊細なサンプルに最適化された試薬。 | 29 |
| CUBIC-X1 / CUBIC-X2 | 組織膨潤 (X1) / 膨潤状態でのRIマッチング (X2) | 超解像イメージングのため、組織を物理的に膨潤させ(膨潤顕微鏡法)、解像度を向上させる。CUBIC-Atlasで使用。 | 12 |
| CUBIC-HL | 脂肪組織の透明化、自家蛍光の抑制 | 脂肪の多い組織(例:脂肪組織、ヒトの脳サンプルなど)に特化。 | [21] |
| F-CUBIC | 迅速透明化 (Formamide-CUBIC) | ミリメートル厚の組織を数分〜数十分で透明化。臨床応用(3D生検)を想定。 | [36, 37] |
| CUBIC-HV™ | 3D免疫染色、3D核染色 | 脱脂後のサンプルに対し、抗体や核染色試薬を組織深部まで効率的に浸透させるための専用バッファー。 | 21 |
【第5章】CUBICと他の透明化技術:徹底比較
CUBICは数ある透明化技術の一つに過ぎません。その立ち位置を正しく理解するために、他の主要な技術と比較することは非常に重要です。
透明化技術の「三大潮流」
組織透明化技術は、使用する試薬の化学的性質によって、大きく3つのグループに分類されます。
- 有機溶媒ベース (Organic solvent-based)
- 代表例:BABB, 3DISCO, uDISCO 14
- 特徴:組織をエタノールなどで脱水した後、BABB(ベンジルアルコール/安息香酸ベンジル)のような高屈折率の有機溶媒に浸します 14。
- 長所:透明化が非常に高速(数時間〜1日)で、脱脂能力も強力です 14。
- 短所:最大の欠点は、GFPなどの蛍光タンパク質のシグナルを消光させてしまう(消してしまう)ことです 14。また、組織が収縮する傾向があり、使用する試薬の毒性や引火性も高いです 14。
- 水和ベース (Aqueous hyper-hydrating)
- 代表例:CUBIC, Scale, SeeDB 14
- 特徴:尿素、グリセロール、アミノアルコール、高濃度の糖など、水ベース(水溶性)の試薬に浸します 1。
- 長所:最大の利点は、蛍光タンパク質のシグナル保持に優れていることです 14。免疫染色との両立も可能で、試薬の毒性が低く安全です 14。
- 短所:透明化に時間がかかります(数日〜数週間) 28。また、CUBICやScaleのように、組織が膨潤する傾向があります 14。
- ハイドロゲルベース (Hydrogel-embedding)
- 代表例:CLARITY, PACT, SHIELD 14
- 特徴:組織をアクリルアミドなどのハイドロゲル(ゲル)で固め、タンパク質や核酸をその場に架橋(固定)します。その後、SDS(強力な界面活性剤)で脂質だけを徹底的に洗い流します 14。
- 長所:タンパク質やRNA/DNAを強力に保持するため、多重免疫染色やFISH(遺伝子発現解析)に最適です 14。
- 短所:プロトコルが非常に複雑で、技術的な難易度が高いです。脂質を除去するために電気泳動(electrophoresis)のための特殊な装置を必要とすることが多く、時間もかかります 14。
CUBICを選ぶ理由(メリットとデメリット)
この3つの潮流の中で、CUBIC(水和ベース)を選ぶ理由は非常に明確です。
CUBICの最大のメリット(選ばれる理由):
- 蛍光シグナルの保持:蛍光タンパク質(FP)を明るく保てるため、GFPやRFPなどで特定の細胞集団を可視化している遺伝子改変マウス(レポーターマウス)を用いた研究に最適です 14。
- 強力な脱色能力:アミノアルコールがヘム(色素)を除去するため、他の水和ベース技術(ScaleやSeeDB)が苦手とする、血液や色素の多い臓器(心臓、肝臓、腎臓、肺)の透明化に極めて優れています 1。
- 操作の簡便さ:基本は「試薬に浸けて待つだけ」のシンプルなプロトコルであり、CLARITYのような特殊な装置や電気泳動が不要です 1。
- 汎用性(モジュール性):CUBIC試薬は、それ単体で使うだけでなく、CLARITYで処理したサンプルの屈折率マッチング液として使うこともできます。これにより、CLARITYの弱点であった「脱色能力の低さ」をCUBICが補完するという、ハイブリッドな使い方も可能です 1。
主なデメリット(注意点):
- 処理時間:有機溶媒法(DISCOなど)と比べると、透明化に時間がかかります(数日〜数週間) 38。
- 組織膨潤:サンプルが膨潤するため、元の形態やサイズを厳密に保ちたい形態学的な解析には注意が必要です 28。
- 試薬の非互換性:蛍光タンパク質には強い一方で、一部の蛍光色素(特にDAPIやAlexa 488など緑色系統の色素)とは相性が悪く、蛍光が失われる場合があると報告されています 26。
【表2】主要な透明化技術の比較
研究者が自分の目的に合わせて最適な手法を選択できるよう、主要な技術の特性を比較表にまとめます。
| 項目 | CUBIC (水和ベース) | CLARITY (ハイドロゲル) | SeeDB (水和ベース) | 3DISCO (有機溶媒) |
| 透明化の原理 | アミノアルコールで脱脂・脱色 | ハイドロゲルで固定、SDSで脱脂 | 高濃度の糖(フルクトース)で脱水 | 有機溶媒で脱水・脱脂 |
| 蛍光タンパク質 (FP) 保持 | ◎ 非常に良い | ◎ 非常に良い | ◎ 非常に良い | × 不可(消光する) |
| 免疫染色 (抗体) 適性 | ○ 可能 (膨潤により浸透性良) | ◎ 非常に良い (タンパク質保持) | × 不可 (または困難) | △ 可能 (工夫が必要) |
| 処理時間 | △ 遅い (数日〜数週間) | △ 遅い (数日〜数週間) | ○ 中程度 (数日) | ◎ 速い (数時間〜1日) |
| 形態の変化 | 膨潤 (Expansion) | 膨潤 (Expansion) | わずかに収縮 | 収縮 (Shrinkage) |
| 技術的難易度 | ◎ 容易 (浸漬のみ) | △ 難しい (電気泳動・特殊装置) | ◎ 容易 (浸漬のみ) | ○ 中程度 (毒性・引火性) |
| 主な短所 | 時間がかかる、膨潤、一部の色素が使えない 30 | プロトコルが複雑 14 | 免疫染色不可、透明化能は中程度 [38] | FPが消える、毒性 14 |
| 主な長所 | FP保持・脱色・簡便さのバランス | タンパク質・核酸の完全な保持 | 簡便、形態保持が良い | 圧倒的なスピード |
(出典:14 の情報を基に作成)
【第6章】最新研究動向(1) 脳科学とAI:CUBIC-Atlasが拓いた新時代
CUBICの「本領」とも言えるのが、神経科学の分野です。もともと複雑な神経ネットワークの解明を目指して開発された経緯もあり、CUBICの強力な透明化能力と蛍光タンパク質(FP)の保持能は、脳研究と非常に相性が良いのです 1。
CUBICと高速なライトシート蛍光顕微鏡(LSFM)を組み合わせることで、マウスの全脳や、より高等なマーモセット(小型サル)の脳半球までも、1細胞の解像度で高速に3Dイメージングすることが可能になりました 11。
例えば、Arc-dVenusという特殊なレポーターマウス(神経細胞が活動するとGFPが発現するマウス) 10 を使うことで、「脳のどの領域の、どの細胞が、いつ活動したか」という情報を、全脳レベルで3Dマッピングすることが可能になります 10。
CUBIC-Atlas(2018年)の衝撃:1億個の細胞を全マッピング
このCUBICと脳科学の融合を象徴する成果が、2018年に発表された**「CUBIC-Atlas」**です 12。
CUBICは、それ自体がテラバイト級の膨大な3D画像データを生成する「強力な眼」です。しかし、その画像データを生物学的な「知見」に変えるには、データを解析する「脳」が必要でした。CUBIC-Atlasは、CUBICという「眼」と、AI(計算論的解析)という「脳」を初めて本格的に融合させたプロジェクトです。
研究チームは、マウスの全脳(約1億個の細胞を含む 12)をCUBIC-Xで膨潤・透明化し、核染色(すべての細胞核を染める)を行いました。そして、自作の高速LSFMで全脳の3Dデータを取得しました 12。
しかし、1億個の細胞が映った3D画像など、人間が見ても「点の集まり」にしか見えません。そこでAIの登場です。
- AIによる細胞の自動検出:まず、AI(情報解析技術)がこの膨大な3D画像データをスキャンし、**「全細胞核を正確に抽出し(自動検出)」**ます 12。
- AIによる位置情報の付与:次に、検出したすべての細胞(点)の3D座標に対して、「その細胞が、脳のどの解剖学的な領域に属するか(例:海馬、視覚野、など)」という位置情報(アノテーション)を自動で与えます 12。
こうして完成したのが、CUBIC-Atlas(点描脳アトラス)です。これは、ジョルジュ・スーラの点描画のように、1億個の「細胞の点」の集合体として脳全体をデジタル空間に再構築した、1細胞解像度の「脳の地図」です 12。
CUBIC-Atlasの意義
この「地図」は、単なる美しい画像ではありません。それは、定量的な解析が可能なデータベースであることにこそ、真の価値があります。
- 正確な細胞数のカウント:AIが全自動で細胞を数えるため、「大脳の視覚野や体性感覚野では、生後1週から3週にかけて(神経回路が成熟する「臨界期」に)、細胞数が有意に減少する」といった、発生段階での精密な細胞数の変化を、初めて全脳レベルで定量的に捉えることに成功しました 12。
- 活動マッピング:特定の薬物(MK-801、NMDA受容体アンタゴニスト)を投与したマウスの脳で「活動した細胞」だけをAIで検出し、その情報をCUBIC-Atlasの地図上にマッピングしました。その結果、海馬の歯状回という領域で、「活性化した細胞群」と「抑制された細胞群」が、空間的に別々の場所に局在していることを発見しました。これは、同じ領域に見えても機能的に異なる細胞集団が存在することを示唆する、1細胞レベルでの重要な発見です 12。
2023年-2024年以降の脳科学の動向
2024年現在、この「透明化+AI」による脳マッピングの取り組みは世界的に加速しています 43。CUBIC-Atlasのような技術パイプラインは、脳の完全な配線図(コネクトーム)を解明しようとする米国などの巨大プロジェクト(BRAIN Initiative)においても、不可欠な技術となっています 43。
最新のトレンドは、CUBICのような透明化技術と、深層学習(ディープラーニング)などのAIを組み合わせた「3Dデジタル病理学」であり 6、アルツハイマー病などの神経変性疾患のメカニズム解明など、これまで不可能だった大規模な3D空間での神経回路や病態の解析が進んでいます 8。
【第7章】最新研究動向(2) がん研究と3D病理診断
CUBICの応用は、脳科学だけにとどまりません。近年、急速に応用が広がっているのが、がん研究と病理診断の分野です。
がん微小環境(TME)を3Dで解明する
がんは、がん細胞だけの塊ではありません。がん細胞は、自らの増殖を助けるために、周囲の正常な細胞(血管、免疫細胞、線維芽細胞など)を巧みに操り、「がん微小環境(Tumor Microenvironment; TME)」と呼ばれる複雑な生態系を作り上げます 7。
このTME内の複雑な3D空間的な相互作用を理解することは、がんの進展や治療抵抗性のメカニズムを解明する上で不可欠です。CUBICは、この複雑なTMEの構造を「丸ごと」3Dで可視化できるため、がん研究の分野で強力な武器となっています 7。
がん転移の「単一細胞」レベルでの追跡
がん研究においてCUBICがもたらした最大のインパクトは、「がん転移」のメカニズム解明にあります。がんが致死的となる最大の理由は、原発巣から他の臓器へ「転移」することです。しかし、広大な全身のどこに、どれだけの転移巣が潜んでいるのか、特に1細胞レベルの微小な転移を捉えることは、従来の技術では不可能でした。
CUBICの「全身・単一細胞解像度イメージング」 48 は、この長年の課題を打ち破りました。
- 転移の「定量化」:
従来、転移の度合いは「転移巣の数」などで大まかにしか評価できませんでした。ある研究では、ヒト肺がん細胞(A549)をマウスに注射し、肺転移モデルを作成しました。CUBICを用いてマウスの肺を丸ごと透明化し、転移したがん細胞をAIで解析したところ、肺全体に生着した**がん細胞の総数を「1細胞レベルで正確にカウント」**することに成功しました 48。
この「定量化」により、例えば「あらかじめTGF-β(がん細胞を間葉系細胞のように変化させる因子)で処理した細胞は、転移先(肺)での生存・増殖能力が有意に高い」ことを、客観的な数値(細胞数)として初めて証明できました 48。 - 転移メカニズムの解明(EMT/MET):
さらに、CUBICで透明化した後の肺を3D免疫染色で調べたところ、驚くべきことが分かりました。転移元で間葉系(EMT)の性質を獲得していたがん細胞が、転移先の肺で増殖する際には、再び上皮系(E-カドヘリンを発現)の性質を取り戻す**「MET(間葉上皮転換)」**を起こしていたのです 48。がん細胞が、転移のプロセス(移動)と生着のプロセス(増殖)で、自らの性質をダイナミックに変化させる「可塑性」を持つことを、3D空間で鮮やかに証明した重要な発見です 48。 - 3D転移パターンの認識:
2Dスライスでは「がん細胞が血管の近くにある」という事実しか分かりません。しかし、CUBICで脳転移巣を3Dで可視化したところ、乳がん細胞(MDA-MB-231)は「血管に沿って這うように」転移するのに対し、腎細胞がん(OS-RC-2)は「血管とは無関係に塊(体積的)」を形成するという、がん種による転移パターンの決定的な違いが初めて明らかになりました。これは2Dスライスでは決して分からなかった知見です 48。
CUBIC病理学 (CUBIC-Pathology):臨床検体への応用
CUBICの応用は、マウスモデル(基礎研究)から、ヒトの臨床検体(病理診断)へと拡大しています 5。
**CUBIC病理学(CUBIC-Pathology)**と呼ばれるこの分野では、ヒトの患者から手術で摘出された「がん組織(悪性リンパ腫など)」や「正常な」肺、リンパ節のサンプルにCUBICを適用し、3Dでの病理診断に応用する試みが報告されています 5。
特に期待されているのが、がんのステージ診断(病期分類)です。従来の病理診断では、摘出したリンパ節を数枚スライスして「転移があるか」を調べます。しかし、CUBICでリンパ節を丸ごと透明化して3Dで観察したところ、従来の2Dスライス法では見逃されていた可能性のある、ごく微小な(minor)転移巣を検出する感度が劇的に向上することが示されました 5。これは、より正確な病期診断と、その後の治療方針の決定に大きく貢献する可能性があります。
さらに、F-CUBIC 36 という、数分〜数十分で透明化を完了できる迅速プロトコルも開発されています。これを用いれば、ヒトの大腸内視鏡で採取された生検(biopsy)標本を迅速に透明化し、3Dで観察できる可能性が示されています 37。将来的には、生検サンプルをその場で3D解析し、即座に診断を下す**「迅速3D病理診断(instant histopathological examinations)」** 37 という、新しい臨床検査の形が生まれるかもしれません。
【第8章】最新研究動向(3) 発生生物学と再生医療
生命がいかにして形作られるかを探る「発生生物学」は、本質的に三次元の学問です。一個の受精卵が、細胞分裂、移動、分化をダイナミックに繰り返しながら、複雑な立体構造を持つ個体へと発生していくプロセス 53 は、CUBICの格好のターゲットです。
CUBICやその他の透明化技術は、マウスの全胚(Embryo) 55 や、ゼブラフィッシュなどの魚類 56、さらにはヒトの貴重な初期胚サンプル 25 の発生過程を、その立体構造を保ったまま詳細に追跡する研究に不可欠なツールとなっています 57。
生殖器系(子宮・卵巣)への応用
特に、子宮や卵巣といった生殖器系の臓器は、月経周期、妊娠、着床といったダイナミックなイベントに伴い、その3D構造が劇的に変化する臓器です 56。
従来の2D切片では、この複雑な3D構造の変化を正しく理解することは困難でした。CUBICを含む透明化技術は、これらの臓器の複雑な3D構造、例えば「卵巣内での卵胞の立体的な配置」や「着床時における胎盤と子宮壁の3D的な境界関係」などを、高解像度でマッピングすることを可能にしました 56。
具体的な応用例として、マウスの子宮内胚と胎盤、子宮組織の3D関係性をマッピングした研究 60 や、魚類の卵巣における卵胞の数を3Dで正確に解析した研究 56 などが報告されています。これらの知見は、不妊治療や発生異常の研究、再生医療の分野に新たな光を当てるものとして期待されています 60。
【第9章】CUBICの未来:空間オミクスとデータ駆動型科学
CUBICは、生命科学に革命をもたらしましたが、もちろん万能ではなく、新たな課題も生み出しています。
CUBICの課題と限界
- ヒト臓器への挑戦:
CUBICはマウスの臓器や、小さなヒト組織片の透明化には非常に有効です。しかし、サイズが桁違いに大きく、結合組織や脂質(特にミエリン)が非常に豊富な「ヒトの成人の臓器」、特に「脳」を丸ごと透明化することは、依然として技術的に大きな課題です 22。 - データ解析のボトルネック:
CUBICは、それ自体が「成功の証」として新たな問題を生み出しました。それは、CUBICとLSFMの組み合わせが、テラバイト級の膨大な画像データをあまりにも簡単に生成してしまうことです。この膨大なデータを保存し、処理・解析するための計算論的リソース(高性能コンピューター、大容量ストレージ、AIアルゴリズム)が、次のボトルネックになっています 22。 - 化学的な互換性:
全ての染色試薬や抗体と適合するわけではなく、特定の蛍光色素(Alexa 488など)を消光させてしまう場合があります 30。また、3D細胞培養モデル(スフェロイド)の免疫染色では、他の手法に比べてシグナル対ノイズ比が低い場合があるという報告もあり 61、用途に応じたプロトコルの最適化が継続的に必要です。
次なるフロンティア:3D空間オミクス
CUBIC-Atlasが示した「AIによる1億細胞の位置情報のマッピング」 12 は、CUBICの未来を示す上で非常に重要です。CUBICが明らかにしたのは、細胞の「構造」と「位置(どこにいるか)」でした。しかし、生命を真に理解するには、その細胞が「何をしているか(どの遺伝子が発現しているか)」という**「機能情報」**を、位置情報と同時に知る必要があります。
この「位置情報」と「機能情報」を同じ組織切片上で同時に解析する技術が、近年爆発的に進展している**「空間オミクス(Spatial Omics)」**(特に空間トランスクリプトミクス)です 46。
CUBICの真価が発揮される未来、それは、この**「3D透明化技術」と「空間オミクス」**が融合する地点にあります。
最新の研究トレンドは、CUBICのような透明化技術で得られた3Dの「構造(アトラス)」に、空間オミクスで得られた「遺伝子発現(トランスクリプトーム)」や「タンパク質(プロテオーム)」の情報を、AIを用いてマッピング(統合)することです 59。
これにより、例えば「がん微小環境(TME)において、特定のがん細胞と特定の免疫細胞が3D空間で隣り合っている時、それらはどのような遺伝子を発現させ、どのような”会話”(細胞間相互作用)をしているのか」といった、これまで知り得なかった生命の設計図を、「3D空間」で丸ごと解読することが可能になります 65。
結論:CUBICがもたらしたパラダイムシフト
本レポートで見てきたように、CUBICは単なる「臓器を透明にする試薬」ではありません。
それは、化学(Cocktails)、工学(Imaging)、情報科学(Computational analysis)を三位一体で融合させ、生命を「スライス(2D)」の集合体としてではなく、一個のつながった「システム(3D)」として捉え直すという、上田泰己教授が提唱する**「個体レベルのシステム生物学 (Organism-level systems biology)」** 10 を実現するための強力なプラットフォームです。
脳科学における1億細胞のアトラス構築から、がんの3D病理診断、そして未来の3D空間オミクスに至るまで、CUBICは、私たちが生命を「見る」方法そのものを変革し、生命科学のフロンティアを押し広げ続けています。
引用文献
- CUBIC – Wikipedia, 11月 5, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/CUBIC
- TISSUE CLEARING – PMC – PubMed Central, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8815095/
- すりガラスと半透明ガラスの究極のガイド, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.mornglass.com/ja/the-ultimate-guide-for-frosted-glass-translucent-glass.html
- 複屈折の原理 – Nikon’s MicroscopyU, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.microscopyu.com/ja/techniques/polarized-light/principles-of-birefringence
- (PDF) CUBIC pathology: Three-dimensional imaging for pathological diagnosis – ResearchGate, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/319267708_CUBIC_pathology_Three-dimensional_imaging_for_pathological_diagnosis
- Blueprints from plane to space: outlook of next‐generation three‐dimensional histopathology – PMC – NIH, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11006986/
- Volume imaging to interrogate cancer cell-tumor microenvironment interactions in space and time – Frontiers, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2023.1176594/full
- Tissue clearing and its applications in human tissues: A review – ResearchGate, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/377429715_Tissue_clearing_and_its_applications_in_human_tissues_A_review
- Advanced CUBIC protocols for whole-brain and whole-body clearing and imaging, 11月 5, 2025にアクセス、 https://sys-pharm.m.u-tokyo.ac.jp/pdf/Susaki_2015.pdf
- Advanced CUBIC protocols for whole-brain and whole-body clearing and imaging – PubMed, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26448360/
- (PDF) Advanced CUBIC protocols for whole-brain and whole-body clearing and imaging, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/283154769_Advanced_CUBIC_protocols_for_whole-brain_and_whole-body_clearing_and_imaging
- 1細胞解像度を有する点描脳アトラスの創出―組織の膨潤および透明 …, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.amed.go.jp/news/release_20180306-05.html
- CUBIC Animal Tissue Clearing Reagents Technical Guidebook – Chemie Brunschwig AG, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.chemie-brunschwig.ch/documents/suppliers-information/tci/CUBIC-Animal-Tissue-Clearing-Reagents-Technical-Guidebook.pdf
- Tissue Clearing Methods and Applications for Fluorescence Imaging …, 11月 5, 2025にアクセス、 https://andor.oxinst.com/learning/view/article/overview-of-tissue-clearing-methods-and-applications
- KAKEN — 研究者をさがす | 上田 泰己 (20373277), 11月 5, 2025にアクセス、 https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000020373277/
- Hiroki UEDA – 東京カレッジ, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.tc.u-tokyo.ac.jp/en/members/15021/
- Hiroki Ueda | Laboratory for Synthetic Biology | RIKEN BDR, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.bdr.riken.jp/en/research/labs/ueda-h/index.html
- Hiroki R. Ueda – Google Scholar, 11月 5, 2025にアクセス、 https://scholar.google.com/citations?user=PITvW4wAAAAJ&hl=en
- Whole-body and Whole-Organ Clearing and Imaging Techniques with Single-Cell Resolution, 11月 5, 2025にアクセス、 https://sys-pharm.m.u-tokyo.ac.jp/pdf/Susaki_2016.pdf
- Clearing and Labeling Techniques for Large-Scale Biological Tissues – ResearchGate, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/303687084_Clearing_and_Labeling_Techniques_for_Large-Scale_Biological_Tissues
- Animal Tissue-Clearing Reagents | TCI AMERICA, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.tcichemicals.com/US/en/c/10431
- Tissue clearing technique: Recent progress and biomedical applications – PMC – NIH, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7812135/
- Unlocking the potential of large-scale 3D imaging with tissue clearing techniques – PMC, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12203224/
- A guide to the BRAIN Initiative Cell Census Network data ecosystem – PMC, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10313015/
- Tissue clearing and its applications in neuroscience – PMC, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8121164/
- Tissue Clearing Reagents | Imaging | [Life Science] – FUJIFILM Wako Chemicals, 11月 5, 2025にアクセス、 https://labchem-wako.fujifilm.com/us/category/lifescience/tissue_clearing_imaging/tissue_clearing/index.html
- 11月 5, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/CUBIC#:~:text=Besides%20its%20use%20as%20standalone,of%20their%20pigmentation%20by%20hemoglobin.
- Tissue Clearing Comparison – Visikol, 11月 5, 2025にアクセス、 https://visikol.com/tissue-clearing-comparison/
- Tissue Clearing and 3D Staining Kits – Technical … – CUBICStars, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.cubicstars.com/assets/pdf/technical-guidebook-en.pdf
- Protocol for Imaging and Analysis of Mouse Tumor Models with CUBIC Tissue Clearing, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7757565/
- Biomedical Applications of Tissue Clearing and Three-Dimensional Imaging in Health and Disease – PubMed Central, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7452225/
- CUBIC-HV(TM)2_protocol(general purpose)_ver202403 – CUBICStars, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.cubicstars.com/assets/pdf/protocol.pdf
- CUBIC Tissue Clearing Protocol – NICHD, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/inline-files/CUBIC_Tissue_Clearing.pdf
- An end-to-end workflow for non-destructive 3D pathology – PMC – NIH, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10418226/
- Tissue clearing and 3D imaging in developmental biology – PMC – PubMed Central, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8497915/
- F-CUBIC: a rapid optical clearing method optimized by quantitative evaluation – PMC – NIH, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8803013/
- F-CUBIC: a rapid optical clearing method optimized by quantitative evaluation, 11月 5, 2025にアクセス、 https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=boe-13-1-237
- Evaluation of seven optical clearing methods in mouse brain – PMC – PubMed Central, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6109056/
- CLARITY techniques based tissue clearing: types and differences – Via Medica Journals, 11月 5, 2025にアクセス、 https://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/view/71860
- Fast 3D Clear: A Fast, Aqueous, Reversible Three-Day Tissue Clearing Method for Adult and Embryonic Mouse Brain and Whole Body | bioRxiv, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.06.25.449994v2.full-text
- Immunolabeling-compatible PEGASOS tissue clearing for high-resolution whole mouse brain imaging – Frontiers, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/neural-circuits/articles/10.3389/fncir.2024.1345692/full
- 成体の脳を透明化し1細胞解像度で観察する新技術を開発~アミノアルコールを含む化合物カクテルと画像解析に基づく「CUBIC」技術を実現, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.jst.go.jp/pr/announce/20140418/index.html
- A look back on the BRAIN Initiative in 2024 (and what’s coming in 2025!), 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.braininitiative.org/achievements/a-look-back-on-the-brain-initiative-in-2024-and-whats-coming-in-2025/
- From the BRAIN Director: How a Cubic Millimeter of Brain Can Change Neuroscience, 11月 5, 2025にアクセス、 https://braininitiative.nih.gov/news-events/blog/brain-director-how-cubic-millimeter-brain-can-change-neuroscience
- Researchers publish largest-ever dataset of neural connections – Harvard Gazette, 11月 5, 2025にアクセス、 https://news.harvard.edu/gazette/story/2024/05/the-brain-as-weve-never-seen-it/
- Unlocking the potential of large-scale 3D imaging with tissue clearing techniques | Microscopy | Oxford Academic, 11月 5, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/jmicro/article/74/3/179/7786569
- New AI model efficiently reaches clinical-expert-level accuracy in complex medical scans, 11月 5, 2025にアクセス、 https://compmed.ucla.edu/news/207
- Tissue clearing method in visualization of cancer progression and …, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11075440/
- Tissue clearing method in visualization of cancer progression and metastasis, 11月 5, 2025にアクセス、 https://ujms.net/index.php/ujms/article/view/10634
- View of Tissue clearing method in visualization of cancer progression and metastasis, 11月 5, 2025にアクセス、 https://ujms.net/index.php/ujms/article/view/10634/17115
- Beyond 2D: A scalable and highly sensitive method for a comprehensive 3D analysis of kidney biopsy tissue | PNAS Nexus | Oxford Academic, 11月 5, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/pnasnexus/article/3/1/pgad433/7512762
- F-CUBIC is compatible with various staining techniques. (a) Images, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/figure/F-CUBIC-is-compatible-with-various-staining-techniques-a-Images-of-human-intestine-and_fig7_356511195
- Functional imaging of whole mouse embryonic development in utero – bioRxiv, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.06.07.596778v1
- Embryonic development grand challenge: crosslinking advances – Frontiers, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/cell-and-developmental-biology/articles/10.3389/fcell.2024.1467261/pdf
- Three-dimension transcriptomics maps of whole mouse embryo during organogenesis, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.08.17.608366v1.full-text
- Tissue clearing and imaging approaches for in toto analysis of the …, 11月 5, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/biolreprod/article/110/6/1041/7504711
- Volumetric trans-scale imaging of massive quantity of heterogeneous cell populations in centimeter-wide tissue and embryo | eLife, 11月 5, 2025にアクセス、 https://elifesciences.org/articles/93633
- Nuclear instance segmentation and tracking for preimplantation mouse embryos | Development – Company of Biologists journals, 11月 5, 2025にアクセス、 https://journals.biologists.com/dev/article/151/21/dev202817/362603/Nuclear-instance-segmentation-and-tracking-for
- 3D visualization of uterus and ovary: tissue clearing techniques and biomedical applications, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12277315/
- 3D visualization of uterus and ovary: tissue clearing … – Frontiers, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2025.1610539/full
- CUBIC and Scale Tissue Clearing | Visikol, 11月 5, 2025にアクセス、 https://visikol.com/blog/2019/02/18/cubic-and-scale-tissue-clearing-for-3d-cell-culture-models/
- Spatial multiplexing and omics – Springer Nature Experiments, 11月 5, 2025にアクセス、 https://experiments.springernature.com/nature/primers/10.1038/s43586-024-00330-6
- A comprehensive review of spatial transcriptomics data alignment and integration – PMC, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12199153/
- Spatial Omics in Clinical Research: A Comprehensive Review of Technologies and Guidelines for Applications – PubMed, 11月 5, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40362187/
- Spatial Integration of Multi-Omics Data using the novel Multi-Omics Imaging Integration Toolset | bioRxiv, 11月 5, 2025にアクセス、 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.06.11.598306v1