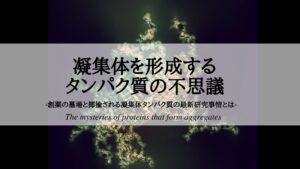セクション1:序論 — 脳の中心に潜む「タツノオトシゴ」
1.1. 脳の「主役」ではないが、最も「重要」な領域の一つ
脳について考えるとき、多くの人がまず思い浮かべるのは、思考や理性を司る表面の「大脳皮質」や、運動を制御する「小脳」かもしれません 1。しかし、近年の脳科学において最も集中的に研究され、私たちが「自分である」という感覚を形成する上で中核的な役割を担っているのが、脳の奥深くに隠された「海馬(hippocampus)」です。
この記事の目的は、なぜこの比較的小さな脳領域が、私たちの「何を記憶し、どこにいたか」という自己の物語を紡ぐ上で不可欠なのかを、最新の海外文献に基づき、ゼロから徹底的に解説することです。海馬は、単なる「記憶の箱」ではありません。それは、経験を未来の行動指針に変える、ダイナミックな処理装置なのです。
1.2. 海馬(ヒポカンポス)とは:名前の由来と基本機能
海馬(Hippocampus)という名前は、その特徴的な形状から来ています。このS字型に湾曲した構造が、古代ギリシャ語で「タツノオトシゴ(Hippokampos)」を意味する言葉から名付けられました 3。
この「タツノオトシゴ」は、脳の中心部、耳の近くにある「側頭葉」の内側に、左右一対で存在しています 3。その基本的な機能は、一般的に三つの主要な役割で知られています。
- 記憶の作成工場: 新しい出来事や情報を「短期記憶」から「長期記憶」へと変換するプロセスに不可欠です 3。
- 脳内のGPS: 私たちが環境内で自分の位置を把握し、目的地まで移動するための「空間ナビゲーション」を司ります 8。
- 感情とストレスの調整役: 感情の処理やストレス応答の制御にも深く関与しています 7。
1.3. なぜ海馬が重要なのか?
海馬の重要性は、それが機能しなくなった時に最も顕著に現れます。もし海馬が損傷すると、私たちは新しいことを学ぶ能力、過去の経験を思い出す能力、そして未来を計画する能力の根幹を失うことになります 11。アルツハイマー病のような疾患では、この領域が最初に影響を受けることが多く 12、また、慢性的なストレスは海馬を物理的に萎縮させることが知られています 10。
このように、海馬は私たちの認知機能の根幹を支える、非常に繊細かつ強力な領域です。本稿では、この海馬がどのように「発見」され、どのような仕組みで機能し、他の脳領域とどう異なり、そして最新の研究が何を明らかにしているのかを、順を追って解き明かしていきます。
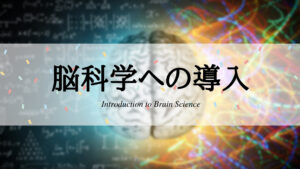
セクション2:海馬の「発見」— 記憶を失った男、H.M.が科学に遺したもの
2.1. H.M.以前の記憶研究:ラシュレーの「エングラム」
20世紀半ばまで、科学者たちは「記憶は脳のどこにあるのか?」という問いに明確に答えられませんでした。当時の有力な説は、記憶は脳全体に分散して保存されているというものでした 13。
著名な心理学者カール・ラシュレーは、ラットの脳の様々な部分を切除し、迷路学習の記憶がどこにあるかを探る実験を行いました 13。しかし、彼は脳の特定の場所を破壊しても、特定の記憶だけを消去することに失敗しました。この結果から、彼は記憶の物理的な痕跡、いわゆる「エングラム(engram)」の特定の局在を見つけることはできず、記憶は脳全体に広がっていると結論付けました 2。
2.2. 運命の手術:患者ヘンリー・モレイソン (H.M.)
この「記憶=脳全体」という考えを根本から覆したのが、神経科学の歴史上、最も有名な患者であるヘンリー・モレイソン、通称「H.M.」の症例です 11。
H.M.は、10歳から続く重度のてんかんに苦しんでいました 11。薬物治療では抑えきれない発作に悩まされ、1953年、27歳の時に彼は実験的な脳外科手術を受けることに同意しました。担当した神経外科医ウィリアム・スコヴィルは、てんかんの焦点と考えられた脳の深部、「内側側頭葉」を両側にわたって切除しました 11。この切除範囲には、海馬の大部分、扁桃体、そして嗅内野が含まれていました 11。
2.3. H.M.に起きたこと:「順行性健忘」
手術の結果、H.M.のてんかん発作は劇的に改善しました。しかし、その代償はあまりにも大きいものでした。彼は、手術以降の新しい出来事を一切記憶できなくなってしまったのです 11。これは「重度の順行性健忘(anterograde amnesia)」と呼ばれる症状です。
彼は毎日会う医師や研究者の顔を覚えられず、数分前に交わした会話の内容も忘れてしまいました。彼の時間は、実質的に手術が行われた1953年で止まってしまったのです 11。
一方で、彼の手術前の記憶(子供時代の出来事など)は比較的保たれており、数秒間の情報を保持する「短期記憶」も正常でした 11。この事実は、海馬が記憶の「貯蔵庫」そのものではなく、短期記憶を長期記憶へと「書き込む」ための重要な処理装置であることを示していました。
2.4. H.M.が解き明かした「記憶の多元性」
H.M.の症例がもたらした最大の発見は、彼が失った能力と保持していた能力の明確な分離でした。
研究者(特にブレンダ・ミルナー)は、H.M.に「星型描写課題(star-tracing task)」というテストを行いました。これは、鏡に映った星形を見ながら、その枠線をペンでなぞるというものです 11。
最初、彼はうまくできませんでした。しかし、驚くべきことに、練習を繰り返すたびに、彼の成績は健常者と同じように上達していきました。しかし、H.M.自身は、そのテスト用紙を見るたびに「こんな課題は初めてだ」と主張し、自分が以前に練習したという記憶は一切ありませんでした 11。
この結果は、科学界に衝撃を与えました。それは、「記憶」が単一のものではないことを決定的に証明したからです。
- 宣言的記憶 (Declarative Memory): 「いつ、どこで、何をしたか」という事実や出来事に関する意識的な記憶。これはH.M.が失ったものであり、海馬が不可欠であることが示されました 11。
- 手続き記憶 (Procedural Memory): 自転車の乗り方や楽器の演奏、あるいは星型描写課題のような「スキル」に関する無意識的な記憶。これはH.M.が保持しており、学習も可能でした。これは海馬以外の領域(小脳や大脳基底核など)が担っていることが示唆されました 11。
H.M.の悲劇的な症例は、ラシュレーが見つけられなかった「記憶のありか」について、海馬が「宣言的記憶」の形成に特化した決定的な役割を担っていることを、初めて明らかにしたのです 16。
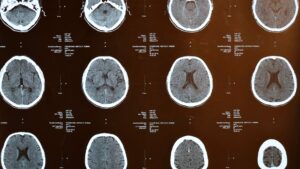
セクション3:海馬の解剖学 — 「記憶の回路」はどのように配線されているか
H.M.の症例により、海馬が「記憶のエンコーダー(符号化装置)」として機能することが明らかになりました。では、その機能はどのような物理的構造によって支えられているのでしょうか。
3.1. 脳内の位置:辺縁系の一部
海馬は、大脳の「側頭葉(Temporal Lobe)」の内側深くに位置しています 3。
海馬は、「大脳辺縁系(Limbic System)」と呼ばれる、より古い脳領域グループの主要な構成要素の一つです 3。辺縁系は、感情の処理を担う「扁桃体(Amygdala)」7 や、自律神経系を制御する「視床下部(Hypothalamus)」3 などを含み、進化的に古い、本能、感情、そして記憶を司るネットワークを形成しています。
3.2. 海馬「体」の構造:タツノオトシゴの「部品」
私たちが「海馬」と呼ぶとき、それは多くの場合、単一の組織ではなく、密接に関連する複数の領域からなる「海馬体(Hippocampal Formation)」と呼ばれる複合体を指します 3。この複合体は、記憶処理という一つのタスクを達成するために、異なる役割を持つ「部品」から構成されています 3。
この構造を理解する鍵は、海馬の機能が「一方向性の情報フロー」によって支えられている点にあります。情報は特定の経路を順々に流れて処理されます。
| 領域 | 主要な役割 | 関連する機能 |
| 嗅内野 (Entorhinal Cortex) | 「大脳皮質とのゲートウェイ」 | 大脳皮質からの全ての感覚情報を海馬へ送る「メインゲート」。グリッド細胞(後述)が存在する 3。 |
| 歯状回 (Dentate Gyrus, DG) | 「新規情報の符号化/パターン分離」 | 嗅内野からの情報を最初に受け取る。新しい記憶を形成し、似たような出来事(例:昨日停めた駐車場と今日停めた駐車場)を区別する「パターン分離」に重要 3。 |
| アンモン角 CA3 (Cornu Ammonis 3) | 「記憶の連合/パターン完成」 | 歯状回からの情報を受け取る。様々な情報を結びつけて「連合記憶」を作る。一部の手がかりから全体を思い出す「パターン完成」に関わる 3。 |
| アンモン角 CA1 (Cornu Ammonis 1) | 「主要な出力ハブ/比較」 | CA3からの情報と、嗅内野からの「バイパス」情報を比較・統合する。海馬からの主要な出力であり、記憶処理の「最終段階」を担う 3。 |
| 海馬台 (Subiculum) | 「辺縁系への出力」 | CA1からの情報を受け取り、再び嗅内野や他の脳領域(扁桃体など)へ送り返す「最終出口」。記憶の検索(Retrieval)に関わる 3。 |
3.3. 情報の流れ:海馬の「三シナプス回路」
上記の表が示すように、海馬内の情報処理は、ランダムではなく、厳密に制御された回路(「三シナプス回路」として知られる)を流れます。
(1)嗅内野 → (2)歯状回 → (3)CA3 → (4)CA1 → (5)海馬台 → (6)大脳皮質へ
この解剖学的な「配線」こそが、海馬が記憶を効率的に処理する計算基盤となっています。情報はまず歯状回で「新規性」がチェックされ(パターン分離)、次にCA3で既存の記憶と「関連付け」られ(パターン完成)、最後にCA1で「統合・出力」されます。この一連の流れが、単なる経験を意味のある記憶へと変換しているのです。


セクション4:機能的差異 — 海馬は他の脳領域とどう違うのか?
海馬は単独で機能しているわけではなく、脳内の広範なネットワークの一部です。その役割をより深く理解するために、他の主要な脳領域との「役割分担」を見ていきましょう。
4.1. 海馬 vs. 大脳新皮質:「司書」と「図書館」
H.M.の症例 11 で明らかになったように、海馬は記憶を「作る」場所ですが、記憶を「永久に保存する」場所ではありません。この関係は、「司書(海馬)」と「図書館(大脳新皮質)」の比喩でよく説明されます 17。
- 古典的モデル(システム統合): このモデルでは、海馬は「司書」として、図書館に新しく届いた本(=経験)を受け取り、それを素早く分類し、一時的に保持します 17。大脳新皮質は「図書館の書棚」であり、本が最終的に収められる場所です 17。海馬(司書)は、睡眠中などに、この新しい本の情報を繰り返し新皮質(書棚)に「リプレイ」して整理します 19。このプロセスを「システム統合」と呼び、十分な時間が経過すると、記憶は海馬から独立し、新皮質だけでアクセスできるようになります 17。
- 最新の知見(H.M.の謎の答え): この古典的モデルは、なぜH.M.が手術以前の記憶(特に手術直前の11年間)も一部失ったのか 11 を完全には説明できませんでした。
- 2017年の利根川進博士の研究室からの画期的な報告 18 は、このモデルに重要な修正を加えました。それによると、記憶は「転送」されるのではなく、経験の瞬間から、海馬と大脳新皮質(長期保存場所)の両方に同時に書き込まれます。
- ただし、新皮質に書き込まれた記憶は、最初は「サイレント(沈黙)」状態にあります。海馬の役割は、この「サイレントな記憶」を繰り返し活性化させ、成熟させる「家庭教師」のようなものです 18。この訓練期間(数週間から数年)が終了して初めて、記憶は海馬なしで新皮質から直接アクセス可能になります。
- この「同時符号化+成熟」モデルは、H.M.がなぜ手術直前の記憶を失ったのかをうまく説明します。それらの記憶は、まだ新皮質に存在はしていましたが、「サイレント」状態であり、訓練役である海馬が失われたため、成熟できずにアクセス不能になったと考えられるのです。
4.2. 海馬 vs. 扁桃体:「出来事」と「感情」
海馬と扁桃体は、辺縁系の中で隣り合って存在し、密接に連携しています 7。記憶において、両者は「事実」と「感情」という異なる側面を担当します。
- 海馬: 記憶の「文脈(Context)」を担います。「いつ、どこで、誰と、何が起こったか」という、エピソード記憶の骨格(宣言的記憶)を記録します 3。
- 扁桃体: 記憶の「情動(Emotion)」を担います。その出来事が「どれほど怖かったか」「どれほど嬉しかったか」という感情的な「色付け」を行います 7。
扁桃体は、まるで「感情的なハイライター」のように機能します 24。ある出来事が強い感情(特に恐怖や喜び)を引き起こすと、扁桃体が強く活動します 23。この扁桃体の活動が、海馬で行われている記憶形成プロセスを「強化」する信号を送ります 25。その結果、感情を伴う出来事は、そうでない出来事よりも、はるかに鮮明に、そして長期間にわたって記憶されるのです 22。心的外傷後ストレス障害(PTSD) 27 などは、この扁桃体と海馬の連携が過剰に、そして永続的に働いてしまう状態の一側面とも考えられています。
4.3. 海馬 vs. 小脳:「知っていること」と「できること」
この二つの領域の違いは、H.M.の症例 11 で示された「宣言的記憶」と「手続き記憶」の分離 2 に直接対応します。
- 海馬: 「宣言的記憶( knowing that)」を担います 2。これは、「自転車の乗り方を言葉で説明する」ために必要な知識や、「昨日自転車に乗った」という出来事の記憶です。
- 小脳: 「手続き記憶( knowing how)」を担います 2。これは、「実際に自転車に乗る」ために必要な、無意識的で自動化された運動スキルやバランス感覚です 28。
H.M.は海馬を失ったため、新しい「宣言的記憶」は作れませんでしたが、小脳は無傷だったため、星型描写課題のような新しい「手続き記憶」は学習できたのです 11。
しかし、この明確な二分法は、脳機能の基本的な理解には役立ちますが、現実の複雑な行動を説明するには単純化しすぎている可能性があります。最新の研究では、従来は分離していると考えられていた海馬(認知)と小脳(運動)が、「双方向に機能的に接続している」ことが示されています 29。例えば、楽器の演奏やスポーツのような高度なスキルでは、両者が協調し、海馬が「認知的なタイミング」を、小脳が「運動的なタイミング」を制御するために相互に情報をやり取りしている可能性が示唆されています 30。
セクション5:『内なるGPS』— ノーベル賞が解き明かした空間ナビゲーション
海馬のもう一つの重要な機能は、「空間認識」です。H.M.の発見から約20年後、この分野で革命的な発見がなされました。
5.1. ジョン・オキーフと「場所細胞」
1971年、ロンドン大学のジョン・オキーフは、自由に動き回るラットの海馬から神経活動を記録していました。彼は、ラットが特定の場所(例えば、ケージの北東の角)を通過したときにのみ、強く発火する神経細胞を発見しました 31。ラットが他の場所にいるとき、その細胞は沈黙しています。
オキーフはこれを「場所細胞(Place Cells)」と名付けました 31。これは、海馬が単に視覚情報に反応しているのではなく、環境の「内的な地図(cognitive map)」を脳内に構築していることを示す、最初の直接的な証拠でした 32。海馬の中には無数の場所細胞があり、それらが集合的に活動することで、ラットは「今、自分がどこにいるか」を認識していると考えられたのです。
5.2. モーザー夫妻と「グリッド細胞」
オキーフの発見から30年以上が経過した2005年、ノルウェー科学技術大学のエドヴァルド・モーザーとマイブリット・モーザー夫妻は、この「脳内地図」がどのように作られているのかを研究していました。彼らは、場所細胞が存在する海馬の「入口」、すなわち「嗅内野」の活動を記録し、さらに驚くべき発見をしました 33。
彼らが見つけた「グリッド細胞(Grid Cells)」は、場所細胞のように1ヶ所の特定の場所で発火するのではありませんでした。その代わり、ラットが環境内を動き回ると、まるで空間に目に見えない六角形の格子(grid)が敷き詰められているかのように、その格子の頂点にあたる複数の場所を通過するたびに発火したのです 33。
この発見の重要性は計り知れません。場所細胞が地図上の「特定の住所(あなたはここにいる)」を示すとすれば、グリッド細胞は地図そのものに引かれた「座標系(緯度と経度)」を提供するものです 33。
この解剖学的な位置関係は決定的です。セクション3で見たように、嗅内野(グリッド細胞の場所)は、海馬(場所細胞の場所)への主要な入力ゲートです 3。これは、脳がまず嗅内野で「座標系(グラフ用紙)」を生成し、その情報を海馬に送り、海馬がその座標系を使って特定の環境の「地図(場所細胞)」を描き出している、という機能的な情報の流れを意味しています。
5.3. 空間から「概念」へ:認知地図の拡張
オキーフとモーザー夫妻は、この「脳内の位置情報システム(内なるGPS)」の発見により、2014年のノーベル生理学・医学賞を共同受賞しました 33。
しかし、最新の理論的神経科学は、この発見をさらに一歩先へと進めています。海馬の真の機能は、単なる「物理的な空間」のマッピング(GPS)35 に留まらないのではないか、という考えです。
海馬の核となる能力は、物理空間で培った「A地点とB地点の位置関係」や「A地点からC地点への距離」といった関係性をマッピングする能力です。そして、脳はこの強力なマッピング能力を応用して、物理空間だけでなく、あらゆる「抽象的な空間(概念空間)」のマッピングにも利用している、とされています 8。
例えば、以下のようなものです。
- 「家族の家系図」(AさんとBさんの関係性)
- 「会社の組織図」(AさんとBさんの社会的地位の上下関係)
- 「物語のプロット」(Aという出来事とBという出来事の順序と関係性)
これら全ては、海馬が処理する「関係性の地図」です。この観点から見ると、海馬の真の役割は「関係性の記憶(Relational Memory)」であり、私たちが日常的に行う空間ナビゲーションは、その能力の最も顕著で、最も理解しやすい応用例(あるいはメタファー)に過ぎないのです 8。これが、海馬が単なる「道案内」を超えて、私たちの宣言的記憶(事実や出来事)全般に不可欠である理由です。
セクション6:研究の最前線 — 現代科学は「記憶」の何を解明したか
海馬の研究は、H.M.の時代から劇的に進化しました。その進化は、脳を調査するための「道具」の進化と密接に関連しています。
6.1. 研究手法の進化:ラシュレーのメスから「光遺伝学」へ
海馬の機能解明は、技術の進歩と共に進んできました。
- 第1世代(破壊と観察): ラシュレーのメスによる「病変(lesion)」研究や、H.M.のような脳損傷患者の症例研究 11。脳の一部を失うと、何を失うかを調べる受動的な手法です。
- 第2世代(行動課題): 1980年代に開発された「水迷路(Water Maze)」37。ラットを水のプールに入れ、水面下に隠されたゴール(足場)を記憶させます。海馬に障害を持つラットは、このゴールの場所を空間的に記憶できません 37。
- 第3世代(非侵襲的イメージング): 「fMRI(機能的磁気共鳴画像法)」。ヒトが記憶課題(例:単語リストを覚える)を行っている間に脳をスキャンし、血流の変化から「脳のどの領域が活動しているか」をリアルタイムで可視化します 13。
- 第4世代(能動的操作): 「オプトジェネティクス(光遺伝学)」。これは現代の神経科学における革命的な技術です。特定の神経細胞(例:海馬CA1の細胞)に、光に反応する特殊なタンパク質を遺伝子工学的に導入します 39。そして、脳に挿入した光ファイバーを通じて光を当てるだけで、その細胞群の活動をミリ秒単位で「オン」または「オフ」にできます 40。
- オプトジェネティクスの登場により、科学者は「fMRIで海馬が活動した(相関)」から一歩進み、「海馬のこの回路をオンにしたら、この記憶が想起された(因果)」という、記憶と脳回路の直接的な因果関係を証明できるようになりました 40。
6.2. 睡眠と「海馬リプレイ」:記憶の夜間メンテナンス
なぜ睡眠は記憶の定着に重要なのでしょうか? 41。この問いの答えも、最新の技術によって解明されつつあります。
海馬は、私たちが起きている間に経験した出来事を、睡眠中(特に深いノンレム睡眠中)に「再生」していることが発見されました 43。この再生は、「シャープウェーブ・リップル(SWR)」と呼ばれる海馬特有の非常に速い脳波活動中に起こります 44。
この「海馬リプレイ」では、その日に経験した出来事(例:場所細胞A→B→Cの発火順序)が、元の10~20倍の速さで「早送り再生」されます 45。この超高速リプレイこそが、セクション4.1で述べた、海馬が新皮質を「訓練」し、記憶を統合するプロセス(システム統合)の正体であると考えられています 19。
最新知見 (2024年):
さらに最近の研究 (2024年) では、この睡眠中のリプレイが、より精巧なメカニズムで制御されていることが示唆されました 44。マウスを用いた研究で、ノンレム睡眠中の「瞳孔」のわずかな大きさの変化(睡眠の微細構造)を監視したところ、リプレイされる記憶の種類が異なることが発見されたのです。
- 瞳孔が縮小している (Contracted pupil) 期間: 主に「新しい記憶(その日の経験)」がリプレイされていました。
- 瞳孔が散大している (Dilated pupil) 期間: 主に「古い記憶(過去の経験)」がリプレイされていました。
これは驚くべき発見です。脳は睡眠中に、「新しい記憶を固定する作業」と「古い記憶を維持・関連付ける作業」という、性質の異なるタスクを、瞳孔の状態という異なる生理学的サブステートで時間的に「分離」して(多重化して)処理している可能性を示しています。これにより、新しい記憶が古い記憶を上書きしてしまう「記憶の干渉」を防ぎながら、効率的に学習を進めていると考えられます 44。
6.3. 「大人の脳でもニューロンは生まれる」:成人海馬ニューロン新生(AHN)
長らく、神経科学の「ドグマ(定説)」は、「大人の脳の神経細胞(ニューロン)は、一度死んだら二度と新しく生まれることはない」というものでした 48。
しかし、この定説は1990年代に覆されました。海馬の「歯状回(DG)」3 においては、生涯を通じて新しい神経細胞が生まれ続けていることが、げっ歯類や霊長類で確認されたのです 49。これを「成人海馬ニューロン新生(Adult Hippocampal Neurogenesis, AHN)」と呼びます。
ヒトにおける大論争:
問題は、ヒトの脳でも、このAHNが意味のあるレベルで起きているのかどうかでした。げっ歯類では活発なAHNが、ヒトでは乳幼児期以降、ほぼゼロになるのではないか、という報告が2018年頃になされ、科学界に大きな論争を巻き起こしました 51。
論争の決着 (2018年~2025年):
この論争は、その後のより精緻な研究によって決着がつきつつあります。Boldrini氏やMoreno-Jiménez氏らの研究グループによる最新(2018年~2025年)の報告では、ヒトの死後脳を詳細に分析した結果、90代の高齢者においても、健康な脳であればAHNが持続していることが確認されました 51。
2018年の否定的な報告 51 との食い違いは、死後脳組織の保存状態や、新しいニューロンを検出するマーカー(タンパク質)の感度といった、「技術的・方法論的な違い」に起因するものだったと結論付けられています 51。
現在では、ヒトの海馬も生涯を通じて新しいニューロンを生み出す能力(可塑性)を保持している、という見解が主流となっています。これらの新しいニューロンは、学習の柔軟性(古い情報と新しい情報の区別)や、気分の調節、ストレスからの回復に重要な役割を果たしていると考えられています 48。
セクション7:脆弱な海馬 — ストレス、加齢、そして病
海馬は、生涯を通じて変化し続ける「可塑性」を持つ一方で、脳内で最もストレスや病の影響を受けやすい、「脆弱な」領域の一つでもあります 10。
7.1. ストレスと精神疾患:コルチゾールが海馬を「削る」
私たちが慢性的なストレス(過重な仕事、人間関係の悩み、あるいはトラウマ体験)にさらされると、体内の「視床下部-下垂体-副腎系(HPA軸)」と呼ばれるストレス応答システムが活性化し、副腎から「コルチゾール」というストレスホルモンが過剰に分泌されます 54。
海馬は、このコルチゾールの影響を最も強く受ける領域の一つです。コルチゾールは、海馬の神経細胞(特にCA3領域)の「樹状突起」(他の細胞から情報を受け取るアンテナ)を文字通り萎縮させ、シナプスの接続を減少させます 54。さらに、セクション6.3で述べたAHN(ニューロン新生)を強力に抑制します 54。
その結果、慢性的なストレス下では、海馬の体積が物理的に縮小することが、多くの研究で示されています 54。これが、うつ病 54 やPTSD 27 の患者に見られる、記憶障害や感情調節の困難(例:過去のトラウマ記憶のフラッシュバック)の神経生物学的な基盤の一つと考えられています。
さらに深刻なのは、このプロセスが「悪循環」を生む点です。海馬には本来、HPA軸(ストレス応答)に対して「もう十分だ」とブレーキをかけ、コルチゾールの分泌を「停止」させる重要な役割があります 10。しかし、そのコルチゾール自体によって海馬が損傷を受けると 54、この「ブレーキ」が効かなくなってしまいます。ブレーキが壊れた結果、ストレス応答はさらに暴走し、コルチゾールが分泌され続け、それがさらに海馬を損傷させる… 55 この負のスパイラルこそが、慢性ストレス障害の「なかなか治らない」状態を生み出す一因と考えられています。
7.2. アルツハイマー病(AD):最初に狙われる記憶の砦
アルツハイマー病(AD)の最も初期の症状が、新しい出来事を覚えられない「物忘れ」である理由は、この病気の初期の病変が、真っ先に「海馬」およびその入口である「嗅内野」を攻撃するためです 56。
ADの診断において、MRIを用いて海馬の「萎縮(atrophy)」の程度を測定することは、病気の進行度を示す重要なバイオマーカー(指標)となっています 56。
ADと海馬の関係において、最新の研究が注目しているのが、再び「AHN(ニューロン新生)」です。AD患者の脳では、健康な同年齢の高齢者と比較して、このAHNが劇的に減少し、ほとんど停止していることが示されています 57。
ここで重要なのは、「AHNの停止は、ADの結果なのか、それとも原因なのか」という問いです。最新の仮説(2023年-2025年)では、このAHNの障害は、アミロイドβやタウといったADの古典的な病理(脳のゴミ)が蓄積するよりも前に起こる、早期の現象である可能性が示唆されています 57。これは、海馬が持つ本来の「自己修復能力(ニューロン新生)」が何らかの理由で損なわれることが、AD発症の最初の引き金の一つになっている可能性を意味します。この仮説が正しければ、将来のAD治療は、「脳のゴミを取り除く」だけでなく、「海馬の修復能力(AHN)を高める」という新しいアプローチが必要になるかもしれません 57。
セクション8:海馬を守り、育むための科学的戦略
海馬は脆弱ですが、同時に生涯を通じて変化し続ける「可塑性」も備えています。最新の研究は、私たちが日常生活の中で海馬の健康を守り、その機能を高めるためにできる、科学的根拠に基づいた戦略を提示しています。
8.1. 戦略1:運動(最も強力な介入)
海馬の健康を維持・向上させるために、現在知られている最も強力で一貫した方法は「有酸素運動」です(ウォーキング、ジョギング、水泳など) 58。
- メカニズム(BDNF): 運動は、神経細胞の成長と可塑性(柔軟性)を促す「BDNF(脳由来神経栄養因子)」と呼ばれるタンパク質の血中濃度を高めることが知られています 60。
- 海馬の「成長」: このBDNFの増加は、海馬の体積増加と直接関連していることが示されています 62。ある有名な研究 62 では、それまで座りがちだった高齢者が1年間の有酸素運動(ウォーキング)を行った結果、通常は加齢と共に萎縮するはずの海馬の体積が、逆に増加(約2%)し、記憶テストの成績も改善しました。これは、運動が加齢による脳の萎縮を「逆転」させる可能性を示しています。
- AHNの促進: 運動はまた、セクション6.3で述べたAHN(ニューロン新生)を強力に促進することが、動物実験で一貫して示されています 63。
- 運動の強度: 最近の研究では、中程度の運動だけでなく、HIIT(高強度インターバルトレーニング)を6ヶ月間行った高齢者群でも、海馬に依存する認知機能(記憶力)が大幅に改善したことが報告されています 64。
8.2. 戦略2:睡眠(記憶の定着と清掃)
良質な睡眠は、海馬の機能にとって不可欠です。それは、セクション6.2で詳述した「海馬リプレイ」と、それに続く新皮質への「記憶の統合(システム統合)」が、主に睡眠中に起こるためです 42。
睡眠不足は、海馬に二重の打撃を与えます。
- 直接的な打撃: 睡眠不足は、海馬が記憶を形成する基礎となる「シナプス可塑性(LTP)」を直接的に阻害し、新しいことを学ぶ能力を低下させます 42。
- 間接的な打撃: 睡眠不足は、セクション7.1で述べたストレスホルモン「コルチゾール」のレベルを上昇させ 66、ニューロン新生を抑制し、海馬をストレスに対して脆弱にします 66。研究によれば、一晩4時間未満の睡眠でも、海馬と前頭前野の機能に悪影響が及ぶとされています 41。
8.3. 戦略3:精神的健康(マインドフルネスと瞑想)
瞑想やマインドフルネスは、セクション7.1で述べた「ストレスの悪循環」を断ち切るための有効な手段となり得ます。
- 物理的な変化: 8週間の「マインドフルネス・ストレス低減法(MBSR)」プログラムに参加した人々をMRIでスキャンした研究 67 では、対照群と比較して、「左海馬」の灰白質密度が増加するという驚くべき結果が報告されました。
- メカニズム: この変化は、瞑想の実践がストレス応答を鎮め、コルチゾールの過剰な分泌を抑制すること 68 で、コルチゾールによる海馬の萎縮を防ぎ、むしろ海馬の可塑性を高めている可能性を示唆しています 67。
8.4. 戦略4:食事と栄養(議論の余地と最新の仮説)
食事と海馬の健康に関する研究は、現在進行中であり、最も複雑な分野の一つです。
- 期待される栄養素: フラボノイド(ベリー類、カカオ、緑茶などに含まれるポリフェノール)69 や、オメガ3脂肪酸(青魚に含まれるEPA/DHA)70 は、抗炎症作用、脳血流の改善、あるいはBDNFの促進などを通じて、認知機能に良い影響を与えると期待されています 72。
- 相反するエビデンス: 数万人を対象とした長期的な「観察研究」では、これらの食品を多く摂取する人は認知機能が高い傾向が示されています。しかし、サプリメントなどを用いて特定の栄養素だけを投与する、より厳密な「ランダム化比較試験(RCT)」では、結果が相反しており、多くの研究で明確な認知機能の改善効果は示されていません 72。
最新仮説(腸脳相関):
なぜ、食事の介入研究の結果は一貫しないのでしょうか? その答えとして現在注目されているのが、「腸内細菌叢(Gut Microbiome)」の役割です 73。
この仮説によれば、私たちが摂取するフラボノイドの多く(90%以上)は、そのままでは体に吸収されません。それらはまず、腸内細菌によって代謝・分解されて初めて、脳に有益な「生理活性代謝物」に変わります 73。さらに、運動が、これらの腸由来の代謝物を血中に効率よく放出させることを促進する可能性も示されています 73。
つまり、「フラボノイドの豊富な食事」+「それを代謝できる健康な腸内細菌」+「代謝物を循環させるための運動」という三つの要素が組み合わさって、初めて海馬へのポジティブな効果が最大化される可能性があるのです 73。単にサプリメントを飲むだけでは効果が出にくい理由は、この複雑な相互作用にあるのかもしれません。
セクション9:結論 — 海馬は、生涯を通じて変化し続ける「可塑的な」パートナーである
9.1. H.M.から現代へ:解き明かされた謎
患者H.M.の悲劇的な手術から始まった海馬の研究 11 は、半世紀以上の時を経て、私たちの自己認識を根本から変えました。
私たちは、記憶が「宣言的記憶」と「手続き記憶」という異なるシステムで動いていること 16、海馬が「司書」として新しい記憶を「訓練」していること 18 を知りました。
また、海馬が「内なるGPS」として、物理的な空間だけでなく、抽象的な概念や社会的な関係性までもマッピングしていること 8 を発見しました。
そして、その記憶が睡眠中の「リプレイ」によって夜通しメンテナンスされていること 44、さらには、大人の脳でも新しい神経細胞が生まれ続けていること 51 を突き止めました。
9.2. 脆弱であり、強靭である
本稿で概観してきたように、海馬は二つの相反する側面を持っています。
それは、慢性的なストレス 54 やアルツハイマー病 57 によって、脳内で真っ先にダメージを受ける「脆弱さ」です。
しかし同時に、成人になっても新しい神経細胞を生み出し(AHN)51、日々の運動 62、学習 74、そして瞑想 67 といったポジティブな介入によって、その構造と機能を生涯にわたって変化させ続ける「可塑性(Plasticity)」という「強靭さ」も備えています。
9.3. 結びの言葉
海馬は、私たちが経験したことを記録し、それらを結びつけ、「私」という存在を定義する連続した物語を紡ぐ、中心的な役割を担っています。
新しい記憶を作れなくなり、「今、この瞬間」に永遠に閉じ込められたH.M. 11 とは対照的に、健康な海馬を持つ私たちは、過去の記憶を未来の計画へと結びつけ、時間の中を自由に旅することができます。
海馬の健康は、単なる「記憶力」の問題ではありません。それは、私たちが学び、適応し、成長し続ける能力、すなわち「生き方」そのものに関わる問題です。日々の積極的な運動、良質な睡眠、そしてストレスの賢明な管理こそが、この「脳の航海士」を、生涯にわたる最良のパートナーにするための鍵となるのです。
引用文献
- How the Human Brain Works – Dummies, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.dummies.com/article/academics-the-arts/science/neuroscience/how-the-human-brain-works-194615/
- Parts of the Brain Involved with Memory | Introduction to Psychology – Lumen Learning, 11月 8, 2025にアクセス、 https://courses.lumenlearning.com/waymaker-psychology/chapter/parts-of-the-brain-involved-with-memory/
- Hippocampus: What It Is, Function, Location & Damage, 11月 8, 2025にアクセス、 https://my.clevelandclinic.org/health/body/hippocampus
- Hippocampus anatomy – Wikipedia, 11月 8, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus_anatomy
- Limbic System: Hippocampus (Section 4, Chapter 5) Neuroscience Online – Department of Neurobiology & Anatomy, 11月 8, 2025にアクセス、 https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/m/s4/chapter05.html
- Neuroanatomy, Hippocampus – StatPearls – NCBI Bookshelf, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482171/
- Neuroscience For Dummies Cheat Sheet, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.dummies.com/article/academics-the-arts/science/neuroscience/neuroscience-for-dummies-cheat-sheet-207385/
- The role of the hippocampus in navigation is memory – PMC – PubMed Central, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5384971/
- Viewpoints: how the hippocampus contributes to memory, navigation and cognition – PMC, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5943637/
- Musical memory and hippocampus revisited: Evidence from a musical layperson with highly selective hippocampal damage | Request PDF – ResearchGate, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/330732132_Musical_memory_and_hippocampus_revisited_Evidence_from_a_musical_layperson_with_highly_selective_hippocampal_damage
- Patient H.M. Case Study In Psychology: Henry Gustav Molaison, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.simplypsychology.org/henry-molaison-patient-hm.html
- Hippocampus | Radiology Reference Article | Radiopaedia.org, 11月 8, 2025にアクセス、 https://radiopaedia.org/articles/hippocampus
- Identification and optogenetic manipulation of memory engrams in the hippocampus – PMC, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3894458/
- Henry Molaison – Wikipedia, 11月 8, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Molaison
- 11月 8, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Molaison#:~:text=Henry%20Gustav%20Molaison%20(February%2026,cortices%2C%20entorhinal%20cortices%2C%20piriform%20cortices
- The Legacy of Patient H.M. for Neuroscience – PMC – NIH, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2649674/
- Shift from Hippocampal to Neocortical Centered Retrieval Network …, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6664975/
- Neuroscientists identify brain circuit necessary for memory formation | MIT News, 11月 8, 2025にアクセス、 https://news.mit.edu/2017/neuroscientists-identify-brain-circuit-necessary-memory-formation-0406
- Memory Consolidation – PMC – NIH, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4526749/
- Rhythmic Memory Consolidation in the Hippocampus – Frontiers, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/neural-circuits/articles/10.3389/fncir.2022.885684/full
- From Structure to Behavior in Basolateral Amygdala … – Frontiers, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/neural-circuits/articles/10.3389/fncir.2017.00086/full
- Amygdala-hippocampus dynamic interaction in relation to memory – PubMed, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11414274/
- Amygdala: What It Is and What It Controls – Cleveland Clinic, 11月 8, 2025にアクセス、 https://my.clevelandclinic.org/health/body/24894-amygdala
- 10 Ways To Improve Your Hippocampus Function – Growth Engineering, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.growthengineering.co.uk/improve-your-hippocampus-function/
- The amygdala, the hippocampus, and emotional modulation of memory – PubMed, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14987446/
- 8.2 Parts of the Brain Involved in Memory – Introductory Psychology – Open Text WSU, 11月 8, 2025にアクセス、 https://opentext.wsu.edu/psych105/chapter/8-3-parts-of-the-brain-involved-in-memory/
- Post-traumatic stress disorder: clinical and translational neuroscience from cells to circuits, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9682920/
- Procedural memory – Wikipedia, 11月 8, 2025にアクセス、 https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_memory
- The little brain and the seahorse: Cerebellar-hippocampal interactions – Frontiers, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/systems-neuroscience/articles/10.3389/fnsys.2023.1158492/full
- The hippocampus and cerebellum in adaptively timed learning, recognition, and movement, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23968151/
- Scientific Background – The Brains Navigational Place and Grid Cell System – Nobel Prize, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-medicineprize2014.pdf
- Place Cells, Grid Cells, and Memory – PMC – PubMed Central – NIH, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4315928/
- The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2014 – Press release …, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2014/press-release/
- Human Grid Cells – SfN, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.sfn.org/sitecore/content/home/brainfacts2/brain-anatomy-and-function/anatomy/2013/human-grid-cells
- Space, Time and Episodic Memory: the Hippocampus is all over the Cognitive Map | bioRxiv, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/150177v1.full-text
- 9 The hippocampus, memory, and spatial function – Oxford Academic, 11月 8, 2025にアクセス、 https://academic.oup.com/book/46855/chapter/413760472/chapter-pdf/51093486/oso-9780198887911-chapter-9.pdf
- Reversible hippocampal lesions disrupt water maze performance during both recent and remote memory tests – NIH, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1409837/
- Learning to Learn, an Optical Imaging Study of Hippocampal Representations During Learning and Generalization. – UCL Discovery, 11月 8, 2025にアクセス、 https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10168809/1/O%27Leary__thesis.pdf
- Optogenetic Activation of CA1 Pyramidal Neurons at the Dorsal and Ventral Hippocampus Evokes Distinct Brain-Wide Responses Revealed by Mouse fMRI – ResearchGate, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.researchgate.net/publication/276910988_Optogenetic_Activation_of_CA1_Pyramidal_Neurons_at_the_Dorsal_and_Ventral_Hippocampus_Evokes_Distinct_Brain-Wide_Responses_Revealed_by_Mouse_fMRI
- Optogenetic fMRI reveals distinct, frequency-dependent networks recruited by dorsal and intermediate hippocampus stimulations – NIH, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4409430/
- Apollo neurologist warns: Less than 4 hours of sleep can harm your brain and memory. What are the side effects?, 11月 8, 2025にアクセス、 https://m.economictimes.com/magazines/panache/apollo-neurologist-warns-less-than-4-hours-of-sleep-can-harm-your-brain-and-memory-what-are-the-side-effects/articleshow/125092332.cms
- The impact of sleep loss on hippocampal function – PMC – NIH, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3768199/
- The evolving view of replay and its functions in wake and sleep – PMC – PubMed Central, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7898724/
- Sleep micro-structure organizes memory replay – PMC, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12107872/
- A model of hippocampal replay driven by experience and environmental structure facilitates spatial learning | eLife, 11月 8, 2025にアクセス、 https://elifesciences.org/articles/82301
- Memory consolidation from a reinforcement learning perspective – Frontiers, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/computational-neuroscience/articles/10.3389/fncom.2024.1538741/full
- Sleep deprivation and hippocampal ripple disruption after one-session learning eliminate memory expression the next day | PNAS, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2123424119
- Extent and Activity of Adult Hippocampal Neurogenesis – Frontiers, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2025.1709208/full
- Adult hippocampal neurogenesis: New avenues for treatment of brain disorders – PMC, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12447344/
- What Is Adult Hippocampal Neurogenesis Good for? – Frontiers, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2022.852680/full
- Evidences for Adult Hippocampal Neurogenesis in Humans …, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.jneurosci.org/content/41/12/2541
- Human adult hippocampal neurogenesis in health and disease – PubMed, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40735066/
- 海馬 – 日本学術会議_おもしろ情報館, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.scj.go.jp/omoshiro/kioku3/kioku3_1.html
- Chronic Stress-Associated Depressive Disorders: The Impact of …, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/1422-0067/26/7/2940
- Neurobiology and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder – Psychiatry Online, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.20240536
- Alzheimer’s disease: a review on the current trends of the effective diagnosis and therapeutics – Frontiers, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience/articles/10.3389/fnagi.2024.1429211/full
- Hippocampal Neurogenesis in Alzheimer’s Disease: Multimodal …, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/1422-0067/26/13/6105
- 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5306252/#:~:text=Research%20involving%20animals%20and%20humans,and%20upregulation%20of%20growth%20factors.
- Aerobic Exercise as a Tool to Improve Hippocampal Plasticity and Function in Humans: Practical Implications for Mental Health Treatment – Frontiers, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2016.00373/full
- Exercise Influence on Hippocampal Function: Possible Involvement of Orexin-A – PMC, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5306252/
- Effects of Physical Exercise on Neuroplasticity and Brain Function: A Systematic Review in Human and Animal Studies – PubMed Central, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7752270/
- Exercise training increases size of hippocampus and improves … – NIH, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3041121/
- On the Run for Hippocampal Plasticity – PMC – PubMed Central – NIH, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5880155/
- Long-Term Improvement in Hippocampal-Dependent Learning …, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2024.0642
- The tired hippocampus: The molecular impact of sleep deprivation on hippocampal function – PMC – NIH, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5511071/
- Sleep Restriction Suppresses Neurogenesis Induced by Hippocampus-Dependent Learning | Journal of Neurophysiology | American Physiological Society, 11月 8, 2025にアクセス、 https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jn.00218.2005
- Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter …, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3004979/
- Unleashing the Mind: The Neuroscience of Meditation and its Impact on Memory, 11月 8, 2025にアクセス、 https://neurosciencenews.com/memory-meditation-23414/
- Dietary Flavonoids and Adult Neurogenesis: Potential Implications for Brain Aging – PMC, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10207917/
- Effects of Dietary Interventions on Cognitive Outcomes – MDPI, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.mdpi.com/2072-6643/17/12/1964
- The intricate interplay between dietary habits and cognitive function: insights from the gut-brain axis – Frontiers, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2025.1539355/full
- A combined DHA-rich fish oil and cocoa flavanols intervention does …, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10447509/
- Enhancing the Cognitive Effects of Flavonoids With Physical Activity …, 11月 8, 2025にアクセス、 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8902155/
- Characterizing Strategy Use During the Performance of Hippocampal-Dependent Tasks, 11月 8, 2025にアクセス、 https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.02119/full