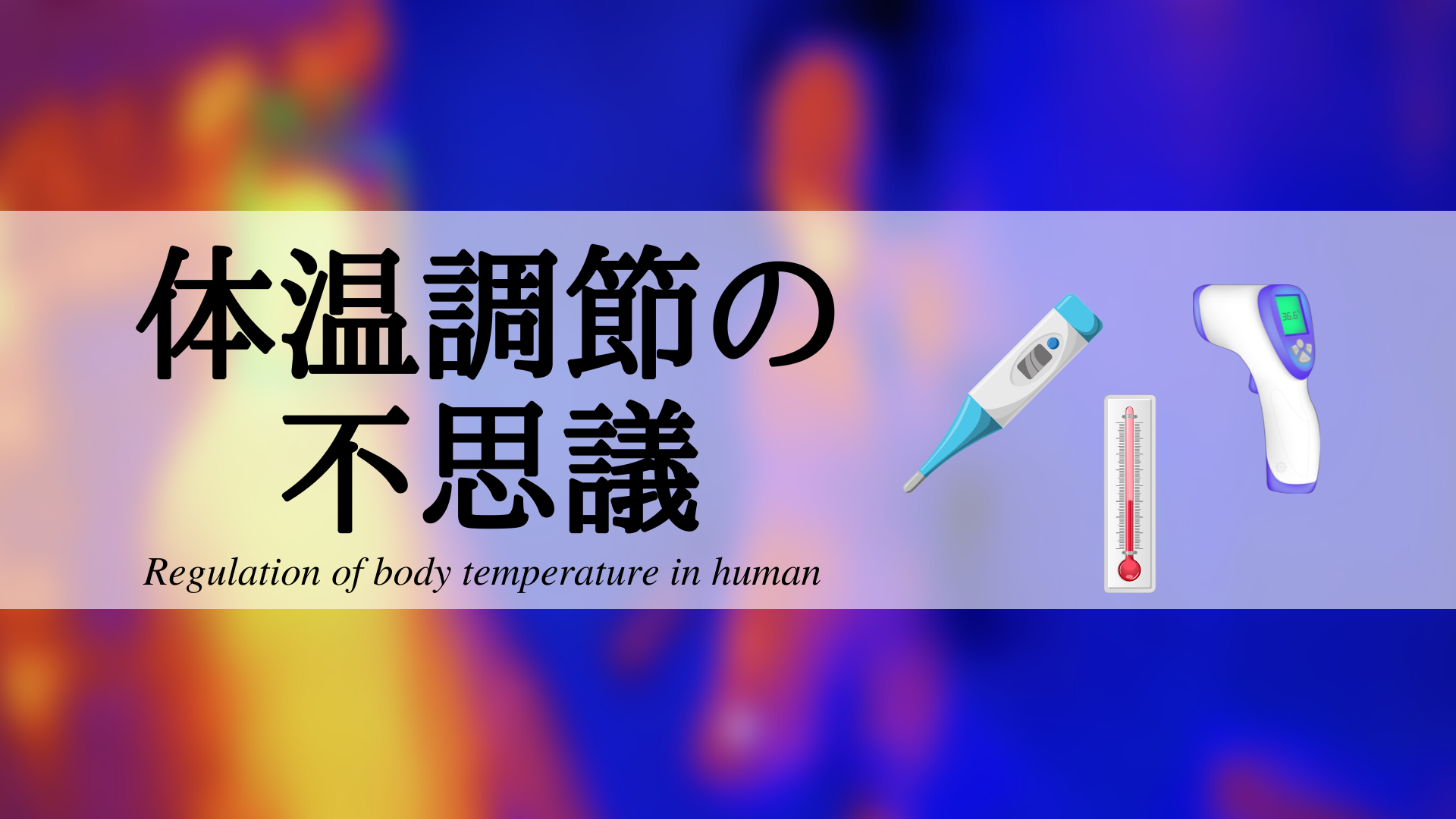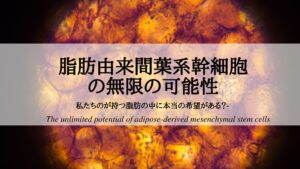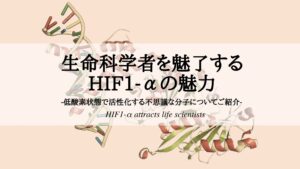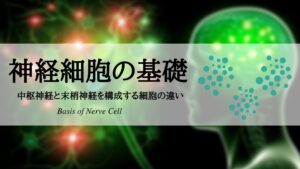体温ってなんだろう
深部体温とシェル温

動物の体は、脳や心臓、肝臓などの内臓がある「中心(コア)」と、筋肉や脂肪組織、皮膚といった「被殻(シェル)」からなると考えることができます。
動物の体の温度には、体の中心の温度である「深部体温」(または「コア温」)と、体表近くの温度である「シェル温」があります。
動物にとって重要な温度は、中心の温度、つまりコア温で、ヒトのコア温は37℃前後です。
体温の維持はなぜ必要?
生物の体内では、さまざまな化学変化が起きています。この化学変化を進める「触媒」として働くのが、タンパク質の一種である酵素です。酵素の活性(触媒作用)が最大になる温度を「至適温度」と言い、概ね体温より少し高いです。
このため、酵素活動とそれに基づく生命活動には、体温が強い影響を及ぼしています。また、酵素の至適温度は、生化学的な影響だけではなく、神経の伝達速度や筋肉の収縮にも強い影響を及ぼします。
酵素活動はアクティブな生命活動であり、生命維持に欠かせません。したがって、体温を高く維持することは、生命活動にとって非常に重要なのです。
体温調節のしくみ

自立性体温調節と行動性体温調節
体温調節反応には、自律性体温調節反応と行動性体温調節があります。
自律性体温調節
自律性体温調節は主に自律神経に支配される臓器・器官を、熱を逃がしたり産み出したりする「効果器」(エフェクター)とする生理反応です。
自律性体温調節は基本的に意識的に制御することができない不随意反応で、体内で熱を産み出す「熱産生反応」と、環境中への体熱の放散を調節する「熱放散反応」があります。
熱産生反応は、化学反応や筋運動の副産物として熱を産み出すことに加えて、体温調節を目的として積極的に熱を産みだします。
熱産生反応はさらに主に二つに大別されます。
交感神経系の支配を受ける褐色脂肪組織で起こる代謝による熱産生(非ふるえによる熱産生)と、骨格筋で起こる体性運動神経を介したふるえ熱産生(シバリング)です。
非ふるえによる熱産生は褐色脂肪組織のUCP1という蛋白質に依存的に生じるとされています。また、褐色脂肪組織は幼少時は肩甲骨周囲がメインで、成長後にはより範囲が広くなると報告されています。
UCP1についての論文:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005272800002474
褐色脂肪組織の局在についての論文:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7330484/
非ふるえによる熱産生とふるえによる熱産生はいずれも神経系から指令が出され、それぞれ細かなメカニズムで管理されていることが知られています。
京都大学の研究グループが2011年にふるえによる熱産生の新規メカニズムを報告しているのでリンクをご紹介しておきます。
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/archive/prev/news_data/h/h1/news6/2011/110531_1
脳科学辞典の体温調節の神経回路の説明:
https://bsd.neuroinf.jp/w/index.php?title=%E4%BD%93%E6%B8%A9%E8%AA%BF%E7%AF%80%E3%81%AE%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%9B%9E%E8%B7%AF&mobileaction=toggle_view_desktop&printable=yes#cite_note-2
熱放散反応も二つに大別されます。
ひとつは蒸散性熱放散です。体表面の水分が蒸発する際に気化熱として体熱を奪うことを利用するもので、汗をかくこともその一つです。
もう一つは、水分の蒸発を伴わず、体表面から環境中へ伝導や放射・対流を通じて熱が移動する現象による非蒸散性熱放散です。
行動性体温調節
意識的な行動によって体温の維持・調節を行うことを、行動性体温調節と言います。
「体温の維持に適した温度環境に移動する」という行動のほか、「寒いので上着を着る」「暑いので冷房のスイッチを入れる」などの行動も含まれます。
自律性体温調節と行動生体温調節を下の図にまとめてみました。
いずれも、生理学の教科書的な内容ですが、私たちの身体と直結するところなので身に覚えがあることが多く理解しやすいですね。

セットポイント体温
体温調節の大きな目標は、酵素活動に適したコア温を維持することです。
恒温動物の体温調節には、エアコンが室温を一定に保つのと同じようなしくみが働いています。
体温調節の目標温度を「セットポイント体温」(設定温度)と言い、エアコンの設定温度と同様のものと考えることができます。
体温調節は、セットポイント体温と実際の体温のズレを感知して、体に備わっているヒーターやクーラー機能を動かしているという概念で捉えることができるのです。
セットポイント体温は、単一ではないと考えられています。深部体温と抹消温度(主に皮ふ温度)の情報が体温調節中枢で統合されて、これに基づき適切な体温調節反応の種類と強度が決定され、実際に体温が調節されるという考え方が主流です。
温度を感知するメカニズムと体温調節

体の中心の温度受容メカニズム
コア温のセンサーは、比較的多くの場所に存在していると言われています。特に脳の間脳と呼ばれる部位に存在する視床下部には、暑さに対する皮膚血管拡張や発汗、寒さに対するふるえや代謝の増加をコントロールする神経(温度感受性ニューロン)が多く存在しています。
視床下部には脳の組織の温度が上昇すると反応する温ニューロンが多く、その活動レベルが皮膚血管の拡張を引き起こします。
このため、体温調節の中枢は視床下部であると考えられています。
この体温調節様式では、コア温の感知が起点となり、体温が変化してから体温調節が行われるので、フィードバック調節と言います。
皮膚の温度受容メカニズム
皮膚は、触覚、圧覚などを感知する受容部位ですが、環境温度を感知する受容部位でもあります。
皮膚で感知した温度の情報は、感覚神経によって脳に伝えられます。この神経は、特定の温度域に反応するサブグループに分類でき、また極度の高温や低温に対して反応する神経があることも分かってきました。
それぞれの神経の細胞膜上には、「サーモTRP」と呼ばれるタンパク質が存在し、温度受容センサーとして働いています。
サーモTRPが特定の温度に対して開くことで神経細胞に電気的な活動が起こり、脳に伝達されていくのです。
皮ふによる環境温度の感知を起点として、コア温が変化する前に体温調節が行われるため、フィードフォワード調節と言います。
2021年のノーベル生理学医学賞にTRPV1チャネルを発見したデヴィッド・ジェイ・ジュリアスが選ばれています。

おもしろい体温調節
アクティブな生命活動には体温の調節・維持が必須であり、体温調節には自律性体温調節と行動性体温調節があります。
人間は、複雑な自律性体温調節のしくみを持つ一方で、暑さ寒さをしのぐ住居や空調の発明など、文明の発達による行動性体温調節を手に入れました。
生物の体温調節の中でもっともおもしろいのは、この空調の発明かもしれません。
今回はざっくり体温調節について説明させていただきました。
こちらも非常にざっくりとした説明で、まだまだ複雑でおもしろい体温に関する話がいっぱいあります。
そのあたりはまた次回執筆させていただきます。
乞うご期待ください。