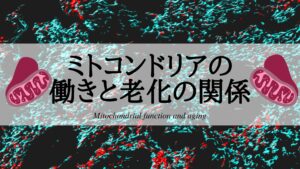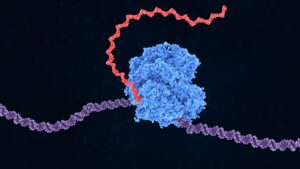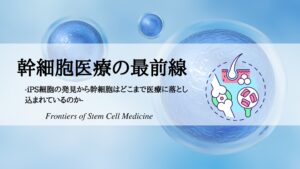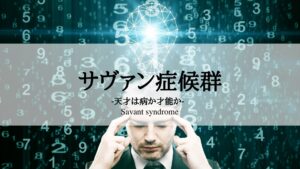スポーツに一生懸命取り組んでいる人でも「オーバートレーニング症候群」について知らないという人は多いのではないでしょうか。
本記事ではオーバートレーニング症候群がどのようなものなのか、そして治療法や予防などについて解説していきます。
本記事は厚生労働省e-ヘルスネットの情報と健康長寿ネットの情報、そしていくつかの論文の情報をもとに執筆していますが、医師監修ではありませんのでご了承ください。

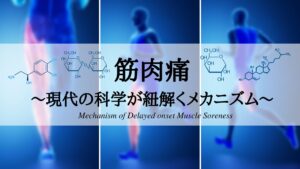
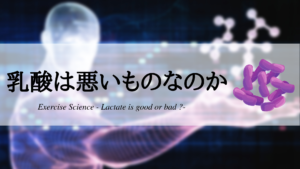
オーバートレーニング症候群とは?

オーバートレーニング症候群について、厚生労働省のe-ヘルスネットの該当ページでは以下のように定義されています。
スポーツなどによって生じた生理的な疲労が十分に回復しないまま積み重なって引き起こされる慢性疲労状態。
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-016.html
スポーツでは、選手は日常生活よりも激しい運動トレーニングを行うことでパフォーマンスを高めていくわけですが、オーバートレーニング症候群の状態になると、むしろパフォーマンスの低下やトレーニング効果の低下を招くことがあります。
オーバートレーニング症候群は定義にあるように慢性的な疲労状態であって、一度に激しい運動をすることで生じる疲労や過労の状態とは明確に区別されます。
では、オーバートレーニング症候群は精神的な問題なのでしょうか?それとも生理学的に何か異変があって起こるものなのでしょうか。
オーバートレーニング症候群は、生理学的には慢性的な心身のストレスによって、脳の視床下部-下垂体系のストレス反応に関連する部位の機能障害やホルモンのバランスが壊れることによって引き起こされると考えられています。
つまり、オーバートレーニング症候群の状態では、ただ単に精神的に慢性疲労状態になっているだけではなく、生理学的にも心身に異常をきたしているのです。
オーバートレーニング症候群の診断

オーバートレーニング症候群は過酷なトレーニングを行うアスリートの天敵です。
しかしながら、アスリート本人がオーバートレーニング状態であることを理解することは容易ではありません。
一般に、オーバートレーニング症候群と診断されるときは、トレーニングを行っているにもかかわらず競技成績が低下することや、疲れやすさ、食欲不振、体重減少などが判断のきっかけとなります。
厚生労働省のe-ヘルスネットの情報によると、オーバートレーニングとは
大きな過負荷を続けると同時に、疲労回復に必要な栄養と休養が不十分であった場合には、かえって競技の成績やトレーニングの効果が低下してしまいます。このような状態をオーバートレーニング症候群といいます。
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-016.html
このような記載があります。また、続けてオーバートレーニング症候群の際には
競技成績の低下だけでなく、疲れやすくなる・全身の倦怠感や睡眠障害・食欲不振・体重の減少・集中力の欠如・安静時の心拍数や血圧の上昇・運動後に安静時の血圧に戻る時間が遅くなるなどの症状がみられます。特に疲労症状が高まるにつれて起床時の心拍数が増加するといわれており、オーバートレーニング症候群を早期発見する目安となります。
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-016.html
と記載があります。
以下に簡単にまとめてみます。
オーバートレーニング症候群を疑うべき項目
- トレーニングをしているにもかかわらず競技成績が低下する
- 疲れやすくなる
- 全身の倦怠感
- 睡眠障害
- 食欲不振
- 体重の減少
- 集中力の欠如
- 安静時心拍数、血圧の上昇
- 運動後安静時血圧への戻りの遅延
- 起床時心拍数の増加
つまり、オーバートレーニング症候群は単にトレーニングによって疲れている状態ではなく、疲労しすぎていて、通常の状態からは程遠い状態であることがわかります。
オーバートレーニング症候群の治療
オーバートレーニング症候群は「トレーニングのしすぎ」によって生じるわけなので、トレーニングから離れることが最も優先されるべき治療です。また、栄養バランスにも気を遣い、身体を作り直すことは治療を助けてくれるでしょう。
アスリートとって、最も難しいことがこの休息を取ることですが、オーバートレーニング症候群への対応としては休息を取ることこそが最大の治療なのです。
軽い有酸素運動がオーバートレーニング症候群の治療を助けるという話もありますが、管理者がいない状況でオーバートレーニング症候群の治療を行う際には細心の注意を払うべきでしょう。むしろ、何もしないほうがよいかもしれません。
オーバートレーニング症候群の回復において、生理的な指標が通常状態に戻ることが重要です。安静時心拍数や起床時心拍、血圧は通常時から把握しておき、回復指標として取り入れると自身の体調管理に役立てることができますね。
オーバートレーニング症候群の予防
トレーニングからの回復が充分でなく、慢性的な疲労状態となってしまうオーバートレーニング症候群はどのように予防出来るでしょうか。
まず基本的な心構えとして、運動トレーニングに精神論を持ち込みすぎないことが大切です。もちろん、アスリートでも最後のところに気持ちが関わってくることは否定できませんが、科学的なエビデンスが無いトレーニングを過度に行うことはオーバートレーニング症候群に限らず、怪我のリスクを高めます。
極力自身でも何らかの生理学的な指標(血圧、心拍数など)を把握した上でトレーニング計画を立てましょう。毎朝の血圧、心拍数の測定を日課にするのもよいかもしれません。
また、先に述べたようにオーバートレーニング症候群はストレス反応とも密接に関わっています。
そのため、ストレスを溜め込みすぎると、やがてオーバートレーニング症候群を引き起こす可能性があると言え、ストレス発散を行うことも予防になります。
日常生活でのストレス管理も重要で、特に激しいトレーニングの後は、しっかりとした休憩を取ることが大切です。
オーバートレーニング症候群の最近の研究

オーバートレーニング症候群はスポーツ科学の最新の知見を持ってしても未だ全容は解明されていません。ここでは最新の研究からオーバートレーニング症候群について明らかになっていることを紹介していきます。
以下の論文はオーバートレーニング症候群の診断方法について調査した論文(2022年)です。
この論文では過去のオーバートレーニング症候群の診断方法について検討した研究を遡って、データをピックアップし、彼らの基準で解析しなおすことで新しい示唆を与えています。
筆者らはオーバートレーニング症候群の診断における新しい方法として、EROS-CLINICAL, EROS-SIMPLIFIED, and EROS-COMPLETE scores (EROS = Endocrine and Metabolic Responses on Overtraining Syndrome study)の3つを同定し、その上で解析を試みています。
それぞれ、3つの方法は以下のようにEROS-CLINICAL→EROS-SIMPLIFIED→EROS-COMPLETEの順に検査項目が増えていきます。
| EROS-CLINICAL | 臨床項目のみでの診断 |
| EROS-SIMPLIFIED | 臨床に加えて、生化学的なテストも加えた診断 |
| EROS-COMPLETE | 臨床に加えて、生化学的なテスト、インスリン抵抗性のテスト、体組成変数テストも加えた診断 |
前提、オーバートレーニング症候群の診断には特定のホルモン、神経伝達物質、代謝物質、心電計や脳波計に表れるような異常や、免疫系の異常パターンを含めて、オーバートレーニング症候群は多システムに反映されると言及しています。今回彼らが同定した3つの新しい方法を活用して段階的にオーバートレーニング症候群を診断出来るようになると良さそうです。なお、彼らは今後さらに解析するサンプルが必要であろうとも述べています。
少し調査してみたところ、オーバートレーニング症候群は他のスポーツ科学の分野と比較しても、研究が盛んに行われている印象を受けました。公開後も調査を続け、記事を更新していきます。
まとめ
今回はオーバートレーニング症候群について詳しく解説してきました。
何かスポーツに取り組んでいている人は是非参考にして、自分のトレーニング計画や身体の管理に活かしてみてはいかがでしょうか。
公開後も文献の解読が終わり次第、どんどんアップデートしていきます。
引き続きよろしくお願いいたします。