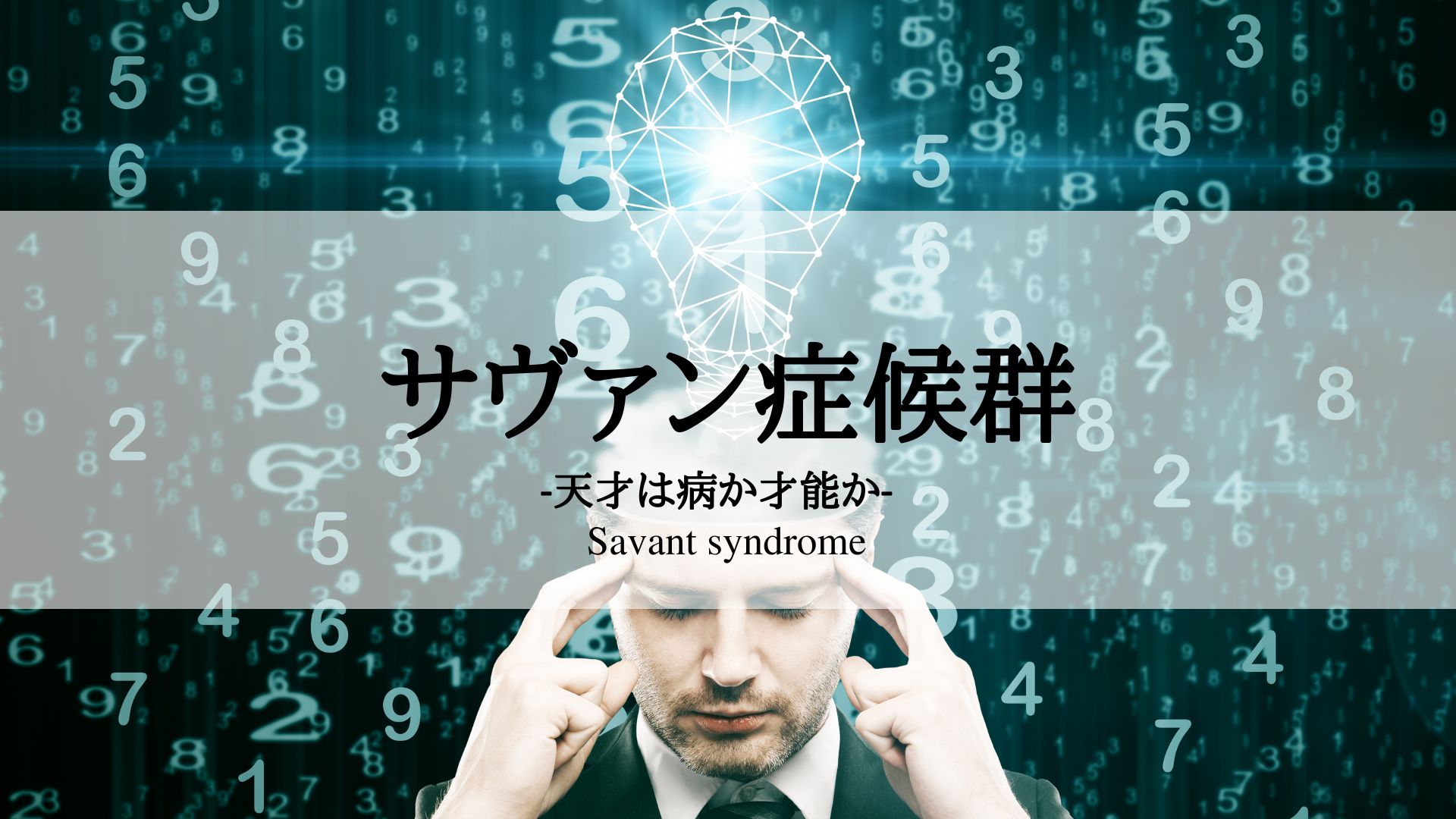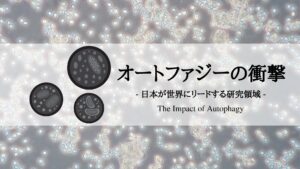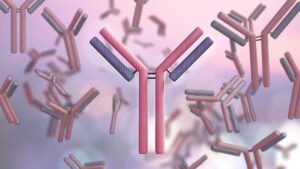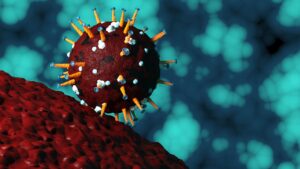驚異的な記憶力、精密な描画力、超人的な計算能力―サヴァン症候群の人々は「本当の天才」と呼ばれるほどの特異な才能を持つ。その驚くべき能力の秘密はどこにあるのか?最新の脳科学研究やAIとの関連性から、その謎に迫る。
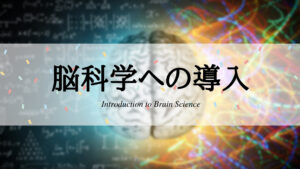
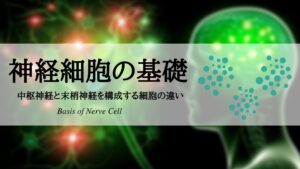

1. サヴァン症候群とは?
サヴァン症候群とは、知的障害や発達障害(自閉症など)を抱える人が、ある特定の分野において非常に優れた才能(「驚異的な才能の島」)を示す、きわめてまれな症候群です ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )。たとえば、自閉症の人のおよそ10人に1人が何らかの驚異的な能力を持つとされます ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )。サヴァンの才能は記憶力に強く支えられており、どの分野の才能であっても驚異的な記憶力が不可欠な要素となっています ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )。
サヴァン症候群で見られる才能の多くは、非常に限られた特定領域に集中しています。典型的な能力のカテゴリーは大きく5つに絞られており、音楽(特にピアノ演奏で絶対音感を持つ場合が多い)、美術(精密な描画や絵画、彫刻)、暦計算(カレンダー計算と呼ばれる特殊な日付計算能力)、数学(桁外れに速い暗算や巨大な素数の判定など、日常的な算数能力を超えた計算力)、そして機械・空間把握(測量器具なしに正確な寸法を測ったり、複雑な模型を正確に組み立てたり、地図を記憶して方向感覚に優れる能力)といった分野です ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )。この他にも、稀ではありますが語学の天才(多数の言語を操る/polyglot)、感覚の特殊能力(匂いや触覚、視覚の極端な識別能力や共感覚)、時間の正確な知覚(時計を見なくても正確に時間経過がわかる)などが報告されています ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )。一般には一人のサヴァンが持つ特別な才能は一分野のみですが、中には複数の才能を併せ持つ例もあります ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )。いずれにせよ、それらの才能はいずれも驚異的な記憶力に支えられており、記憶力そのものをサヴァンの特殊技能と見なす専門家もいるほどです ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )。
2. 著名なサヴァン症候群の事例
(File:Stephen Wiltshire IMG 3910 (30308695430).jpg – Wikimedia Commons)
図:自閉症のサヴァン症候群の芸術家が、記憶だけを頼りに都市のパノラマ風景を大型キャンバスに描いている様子。卓越した映像記憶と描画能力を示す一例(2016年、メキシコシティでのライブドローイングイベントにて)。
サヴァン症候群の実例として、歴史的にも現代にも驚異的な才能を示した人物が数多く報告されています。以下では、その中でも特に著名な例を紹介します。
- キム・ピーク(Kim Peek) – 映画『レインマン』のモデルにもなった人物です。彼は自閉症ではありませんでしたが、生涯で読んだ約9,000冊もの本の内容をほぼ完全に記憶し、全て暗唱できたとされています ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )。彼は本を異常な速さで読破し、左目で左ページを、右目で右ページを同時に読んで記憶するといった特異な読書法が可能でした ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )。地理や歴史、音楽、文学など十数分野にわたる百科事典的知識を持ち、アメリカ国内の市外局番や郵便番号をすべて暗記していたほか、地図帳を記憶して「ある都市から別の都市への正確な経路と、その目的地の市内の道順」を即座に答えることができました ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )。暦計算(任意の過去未来の曜日を即答する)にも長けており、晩年にはピアノによる高度な音楽的才能も発揮しています ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )。
- スティーブン・ウィルシャー(Stephen Wiltshire) – イギリス出身の自閉症サヴァンで、建築物や都市景観の記憶描写で世界的に有名です。ウィルシャーは一度見た景色を写真のように詳細まで記憶し、後から正確に描き起こすことができます。その才能は幼少期から顕著で、ヘリコプターで上空から短時間見渡した都市の風景を、帰還後に何も見ずに巨大なパノラマ絵図として描き上げるという公開実演を各地で行ってきました。例えば2005年には東京で30分間ヘリコプター遊覧した後、下書きも参照資料も一切なく、7日間かけて幅10メートルにも及ぶ東京の360度パノラマ街並み画を完成させています (Stephen Wiltshire – memory drawing – Lines and Colors)。ウィルシャーは「一度見ただけの光景を記憶で描くことができる」才能で知られており、その緻密で正確な描写力は専門家をも驚嘆させました (Stephen Wiltshire – Wikipedia)。彼の描いたロンドン、ニューヨーク、東京などの大都市の記憶画は世界中で展示・出版され、高い評価を得ています。
- レスリー・レンケ(Leslie Lemke) – 目が見えず重度の障害がありながら、驚異的な音楽の才能を発揮したアメリカのサヴァンです。レンケは赤ん坊のときに眼球を摘出され知的障害も抱えていましたが、16歳のある夜、家族が驚くような出来事が起こりました。彼がそれまで一度も弾いたことのないピアノで、チャイコフスキー作曲の『ピアノ協奏曲第1番』を完璧に演奏してみせたのです。彼はその直前にテレビでこの曲を一度聴いただけでした (Leslie Lemke – Simple English Wikipedia, the free encyclopedia)。以後、彼はラグタイムからクラシックまであらゆる曲を耳で聴いただけで再現できるようになり、各地でコンサート活動を行うようになりました (Leslie Lemke – Simple English Wikipedia, the free encyclopedia)。これは「音楽のサヴァン」の典型例で、一度聞いた複雑な楽曲を即座に再現できるという常人離れした才能を示しています。
- ダニエル・タメット(Daniel Tammet) – イギリス出身のサヴァンで、数学と語学の才能で知られます。彼は22,514桁に及ぶ円周率を暗唱するヨーロッパ記録を保持しており、その暗記と朗唱は5時間以上に及びました (Daniel Tammet – Wikipedia)。タメットはまた生来の高機能自閉症でもあり、共感覚によって数字を独特の色や形として捉えることで計算や記憶を行っています。さらに彼は語学の天才でもあり、アイスランド語をわずか1週間でマスターしてテレビ番組のインタビューにアイスランド語で応じたという逸話も残しています (Daniel Tammet – Wikipedia)。彼の場合、自身の才能を言語化して説明することができる数少ないサヴァンの一人であり、数字を「美しい形や色」のイメージで感じるといった内面的体験を著書の中で語っています。
これらの事例は、サヴァン症候群の才能が記憶力を基盤としつつ、音楽・美術・計算・語学など多岐にわたる分野で発揮されうることを示しています。それぞれのサヴァンが示す能力は、その人の障害の程度や個性によって様々ですが、いずれも通常では考えられないレベルの**「真の天才」**的パフォーマンスであり、我々の脳の潜在能力について大きな示唆を与えてくれます。
3. 最新の研究動向
脳神経科学: サヴァン症候群の脳メカニズム
サヴァン症候群の謎に迫るため、脳神経科学の分野では近年そのメカニズム解明に向けた研究が進んでいます。多くの研究者が注目する仮説の一つに、「脳の左半球機能の異常と右半球の代償」があります。サヴァン症候群ではしばしば左脳の一部に障害や抑制がある一方、右脳の機能が相対的に解放・強化されるという現象が指摘されています ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )。これは、脳卒中や外傷で左脳にダメージを負った後に芸術的才能が開花する「後天性サヴァン症候群」の事例などから支持されており、左脳が担う論理的・言語的処理が低下すると、右脳による空間認知や芸術性、記憶力といった領域が活性化される可能性があります (The Mystery of Sudden Genius | Psychology Today)。実際、左前側頭葉(言語や意味処理に関与)の活動を経頭蓋磁気刺激(TMS)で一時的に抑制すると、健常者でも一時的に描画や記憶の精密さが増すなど「プチ・サヴァン」のような能力向上が起きる場合があることが報告されています ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )。これは、脳内の通常は抑制されている低次情報への「特権的アクセス」が可能になるためではないかと考えられています ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )。サヴァン症候群の人々は、このように脳内のフィルターが外れ、生の情報処理に直接アクセスできている可能性があり、それが常人には到達し得ない正確さや記憶容量をもたらしているのかもしれません。
実際の脳構造の研究からも興味深い知見が得られています。先述のキム・ピークの例では、MRI脳画像により脳梁(左右の大脳半球をつなぐ太い神経束)が完全に欠如していることが明らかになりました (The Brain Of The Real Rain Man | Psychology Today)。さらに脳梁以外の前交連や海馬交連も欠如しており、左右の脳が独立して機能している構造でした (The Brain Of The Real Rain Man | Psychology Today)。この生得的な脳形成異常により、左右の脳の情報干渉が起きにくくなり、ピーク氏は左目と右目で別々のページを同時に読めるような特殊な情報処理が可能になったと推測されています (The Brain Of The Real Rain Man | Psychology Today)。また、このような脳梁欠損(脳梁欠損症; ACC)は自閉症の一因ともなり得る遺伝的な脳奇形ですが、それを持つ人々の脳内ネットワークを調べた研究では、脳内の帯状束(左右をつなぐ代替経路となる神経束)が通常より細く接続も少ないこと、さらに脳全体のネットワークトポロジー(接続構造)が一般より可変的であることが報告されています (‘Rain Man’-like Brains Mapped with Network Analysis | UC San Francisco)。これは、脳梁が無い場合に脳が別の経路で再配線するものの、情報のやり取りが特殊化・限定化されている可能性を示唆します。
他の研究では、自閉症者の情報処理スタイルである「弱い中心的統合」(細部志向で全体の文脈把握が弱い傾向)が、サヴァンの優れた記憶力・パターン認識力に関与しているという見解もあります。実際、自閉症サヴァンの脳では局所的な脳活動が過剰で、大域的なネットワーク結合が弱い傾向が見られるとの報告もあります (The Mystery of Sudden Genius | Psychology Today) (The Mystery of Sudden Genius | Psychology Today)。こうした脳内配線の偏りが、通常は埋もれてしまう微細な情報にまで意識を向けさせ、驚異的な記憶や計算能力を可能にしているのかもしれません。
遺伝的要因: サヴァン症候群に関与する遺伝子
サヴァン症候群の才能が生まれる背景には、遺伝的な素因も考えられています。生まれつきサヴァン症候群の能力を示す先天性の例があることから、何らかの遺伝的要因が関与している可能性が指摘されています (Savant syndrome: What it is, symptoms, and links to autism)。実際、自閉症や関連疾患の遺伝研究において、サヴァン的技能との関連が示唆された遺伝子も存在します。その一つがGABRB3遺伝子で、この遺伝子の変異がサヴァン症候群の才能発現に関与している可能性が報告されています (Heritability of autism – Wikipedia)。GABRB3は脳内の抑制性神経伝達物質(GABA)の受容体サブユニットをコードする遺伝子で、変異マウスは自閉症様の行動を示すモデルにもなっています (Heritability of autism – Wikipedia)。このことは、前述した「脳の抑制解除による低次情報へのアクセス」という仮説とも符合し、遺伝子レベルで脳の興奮/抑制バランスに変化が生じることでサヴァン能力が発現しやすくなる可能性があります。
また、「レインマン脳」とも呼ばれるキム・ピークの脳梁欠損症の原因として16番染色体の一部欠失が知られており(これは自閉症リスク因子でもあります (‘Rain Man’-like Brains Mapped with Network Analysis | UC San Francisco))、このような大きな遺伝的変異が脳構造を変化させ結果的にサヴァン能力につながった例もあります。さらに、家族歴の研究では、サヴァン症候群者の親族に特殊な記憶力や才能を持つ人が見られるケースも報告されています (The Mystery of Sudden Genius | Psychology Today)。ただし、現時点で特定の遺伝子があれば必ずサヴァン才能が現れるという単純なものではなく、遺伝要因は下地を作る一方で、実際の才能発現には脳の発達過程や環境要因との相互作用が重要だと考えられています (The Mystery of Sudden Genius | Psychology Today)。言い換えれば、「サヴァンの才能」を決定づける遺伝子の組み合わせがあったとしても、それだけで自動的にサヴァン症候群になるわけではなく、脳の可塑性や他の要因が組み合わさって初めてあの独特な才能が形作られるのでしょう。
AIとの関連性: 人工知能から見るサヴァンの知能
近年、人工知能(AI)研究の発展により、サヴァン症候群の持つ特殊な知能とAIシステムとの類似性にも注目が集まっています。一見、人間のサヴァンとAIは全く別物に思えますが、興味深いパラレルがあります。それは「特定領域における卓越した性能と、他の領域での弱さ」という特徴です。例えば、大規模言語モデル(LLM)と呼ばれる最新のAI(ChatGPTなど)は、人間さながらに流暢な文章を作成したり会話したりすることができますが、常識的な推論や文脈の理解で的外れな回答をしたり、事実と異なる出力をしてしまうことがあります (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today)。これは、サヴァン症候群の人が特定の才能(例えば高度な計算)では天才的能力を示す一方で、日常の社会的理解や抽象的思考が苦手であるケースによく似ています (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today)。言い換えれば、LLMは言語という狭い領域で「人間離れした才能」を発揮する一種の人工的サヴァンだと見ることもでき、その突出ぶりとアンバランスさは人間のサヴァンの知能プロフィールと共通する部分があるのです (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today) (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today)。
この類似性から、サヴァン症候群とAIの比較研究は「知能とは何か」を考える上で新たな視点を提供しています。人間社会では一般に、幅広い認知能力や適応力を備えた知性が重視されます。しかし、サヴァンやAIの例は、極端に偏った形でも知能が成立し得ることを示しています。巨大なデータからパターンを抽出して動作するAIモデルは、文脈や意味を理解していないにもかかわらず言語という領域で高度な成果を出します。同様に、サヴァン症候群の人は直感的に「生のデータ」にアクセスし、特殊才能を発揮していると考えられます (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today)。これらは、私たちが従来考えてきた「知能」の概念を再考させます。知能は単一の尺度では測れず、多様な形態がありうること、そして専門特化型の知能と汎用型の知能はトレードオフ関係にある可能性を示唆しています (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today)。
もっとも、人間のサヴァンとAIには本質的な違いもあります。サヴァン症候群の人々は生身の人間であり、個々に異なる人生経験や内面世界を持ちます。一方、AIモデルは人間が目的に合わせて設計したツールであり、感情や自我を持ちません (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today)。サヴァン能力と機械学習のメカニズムは根本的には異なるものの、結果として現れる「偏った天才性」に共通点がある点が興味深いのです。今後、サヴァンの脳研究とAI研究が連携することで、人間の脳がいかにして高度な情報処理を行っているのか、その一端が解明されるかもしれません。
4. サヴァン症候群と一般の才能の違い
サヴァン症候群の才能は一見、私たちが「天才」や「才能」と呼ぶものと似ているようにも思えます。しかし、その質や現れ方は一般の人々の才能とは大きく異なります。ここでは、サヴァン症候群の才能と一般的な才能の違いをいくつかの観点から比較します。
- 生得的・突発的な才能 vs. 環境に磨かれた才能: 一般的な才能や技能は、多くの場合幼少期からの教育や訓練、練習によって徐々に伸ばされていくものです。ところがサヴァン症候群では、そうした外部からの訓練なしに 幼児期から突然高度な才能が現れる ことが珍しくありません ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )。サヴァンの才能は「天から降ってきたよう」に発現し、本人もその才能をどのように行使しているか言語化できない場合が多いのです ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )。例えば先述のレスリー・レンケは正式な音楽教育を受けていないにもかかわらずある日突然ピアノの名手となりましたし、スティーブン・ウィルシャーも幼少期に誰から教わるでもなく精密なスケッチを描き始めました。才能のコア部分が最初から完成された形で現れる点が、積み重ねによって向上していく一般の才能と大きく異なります ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )。一方で、サヴァンの才能は必ずしも練習によって大幅に向上しないとも言われます ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )。むしろ幼少期に既に卓越しており、その後は技能が洗練されることはあっても、質的に全く次元の違う段階に進化するわけではないケースが多いようです。この点も、努力と経験によって成長していく通常の才能とは対照的です。
- 才能の偏り(専門特化) vs. バランスの取れた知能: サヴァン症候群では、その人の知能の中で特定の能力だけが飛び抜けて発達し、他の能力とのアンバランスが顕著です (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today)。例えば、あるカレンダー計算のサヴァンは驚異的な暗算力で有名でしたが、日常会話や自立生活は困難だったといった報告があります。一方、一般的な「天才」と呼ばれる人々(高いIQや広範な才能を持つ人)の多くは、特定分野に秀でつつも社会生活や他の認知能力とのバランスが取れていることが普通です。サヴァンの才能は島のように孤立して突出しており、それ以外の領域は障害レベルで苦手という極端さがあります (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today)。これはサヴァン症候群という現象を特徴づける重要なポイントであり、才能の「幅広さ」で勝る一般の才能とは質的に異なるものです。
- 創造性と模倣性: 一般の才能あるアーティストや科学者は、既存の情報をもとに新たな作品や理論を生み出す創造性を発揮します。ところが、サヴァン症候群の場合、その才能は模倣や再現に偏る傾向があります。例えば、絵を描くサヴァンは見たものを写真のように再現しますが、全く架空の構図をゼロから描くことは少ないと言われます。また音楽のサヴァンも、一度聴いた曲を完璧に再生することは得意でも、自ら作曲する例は多くありません。ただ近年では、サヴァンの中にも一定の創造性を発揮する例が報告されています ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC ) ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )。日本の盲目の音楽サヴァンで作曲家として活躍した人のように、サヴァンであっても新しいアウトプットを生み出すケースもあり、創造性が皆無とは言い切れないものの、やはりその多くは非常に文字通り・忠実なスタイルに留まるとされています ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )。一方、一般の才能ある人々は模倣から出発しても最終的には独自性や創意工夫を加えていく点で、サヴァン的才能とは区別できます。
- 環境要因と動機づけ: 一般の才能開花には、家庭環境や教育、人との交流が大きく影響します。例えば音楽的才能を持つ子供が専門の先生につき練習を積むことでプロの演奏家になる、といった道筋です。しかしサヴァン症候群では、必ずしも環境が才能を育てたわけではない場合が多々あります。むしろ、自閉症に伴う強い没頭傾向や反復行動が結果的に才能の研鑽につながっている可能性が指摘されています (Savant syndrome: What it is, symptoms, and links to autism)。自閉症のサヴァン児は社会的な関心が低いため、幼少期から興味のある対象(数字や絵、音など)に何時間でも没頭し続けます。その結果、誰にも強いられずとも膨大な時間を才能の対象に費やし、周囲が気づいたときには大人顔負けの腕前になっていた、ということが起こり得ます (Savant syndrome: What it is, symptoms, and links to autism)。このようにサヴァンの環境要因は内的動機づけ(当人の興味やこだわり)であり、外的な教育や訓練ではありません。一方で、全く環境の役割がないわけでもなく、才能を伸ばすための機会(例えば楽器に触れる、描画道具を与えるなど)を与えたことで才能が顕在化した例もあります。いずれにせよ、「適切な環境や指導があれば誰でも才能を伸ばせる」という一般論はサヴァンには当てはまらず、才能の種そのものは環境に先立って内在している点が大きな違いです ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )。
以上のように、サヴァン症候群の才能は、その発現の仕方や知能全体との関係において、私たちが通常考える「才能」「天才」とは異質です。サヴァン症候群は、能力の凹凸が極端であるがゆえに、人間の脳の特化能力と汎用能力の違いを浮き彫りにしています。この違いを理解することは、サヴァンの支援だけでなく、人間の知能の本質を理解する上でも重要です。
5. まとめと今後の展望
サヴァン症候群は、その驚異的な才能ゆえに我々の好奇心をかき立てるだけでなく、脳科学や心理学、教育学、そして人工知能研究にまで示唆を与える興味深い現象です。本記事で述べたように、サヴァンの才能は脳の特殊な情報処理に起因する可能性が高く、そこには人間の脳に秘められた未開発のポテンシャルが垣間見えます。今後の研究では、この「脳の潜在能力」を健常者にも引き出せるのか、という点が一つの焦点になるでしょう。実際、経頭蓋磁気刺激によって一時的にサヴァン様能力を引き出す試みは成功例があり ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )、将来的にはリハビリテーションや認知トレーニングへの応用につながるかもしれません。
また、サヴァン症候群の研究は知能の多様性を再評価する流れにも寄与しています。従来、知能はIQなどで一本的に測られる傾向がありましたが、サヴァンの存在は「偏った天才」もまた価値ある知能の形であることを示しました (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today)。これにより、教育の現場でも発達障害を持つ子供たちの強みの部分に着目した支援が重要視されるようになるなど、社会的な意識も変わりつつあります。事実、多くのサヴァンたちが適切な環境の中で才能を発揮し、画家やミュージシャン、計算のエキスパートなどとして社会に貢献しています。社会としては、サヴァン症候群の人々が能力を活かせる場を提供し、その才能を共有してもらうことで、我々全体の文化や知識の豊かさが増すことでしょう。
さらに、サヴァン症候群の解明は人工知能の発展にもインスピレーションを与えています。人間の脳が持つ驚異的な記憶術や計算能力の断片を理解することで、AIアルゴリズムの設計に活かせるヒントが得られる可能性があります。逆に、AIの研究から得た知見でサヴァン脳の振る舞いをモデル化し、シミュレーションすることで脳内メカニズムの仮説検証を行う、といった学際的なアプローチも考えられます。知能研究という大きな流れの中で、サヴァン症候群は人間の知能の可能性と限界を教えてくれる特異な鏡と言えるでしょう。
最後に、サヴァン症候群への社会のまなざしも触れておきます。かつては「異端」「奇人」と見られたサヴァンたちも、現在ではその才能が正当に評価され、尊重される方向にあります。彼らから学べることは、「人はそれぞれ異なる才能の形を持つ」という多様性の尊重と、人間の潜在能力への畏敬です。サヴァン症候群の研究がさらに進めば、記憶術の開発や創造性の啓発など一般人への応用も見えてくるかもしれません ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )。そして何より、彼らの存在自体が我々に問いかけます――「私たちの脳にも、眠っている本当の天才がいるのではないか?」と。 ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )
人類が自らの脳と知能について理解を深めていく中で、サヴァン症候群という現象はこれからも重要な研究対象であり続けるでしょう。その類まれな能力の謎を解き明かすことは、我々自身のポテンシャルを解き明かすことにもつながるのです。今後の研究と社会の取り組みにより、サヴァン症候群の人々がさらに活躍し、その才能が社会に活かされる未来に期待したいと思います。
【参考文献】サヴァン症候群の定義と歴史 ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC ) ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )、典型的才能の分類 ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC )、キム・ピークの能力と脳構造 ( The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future – PMC ) (The Brain Of The Real Rain Man | Psychology Today)、スティーブン・ウィルシャーの記憶描画 (Stephen Wiltshire – memory drawing – Lines and Colors) (Stephen Wiltshire – Wikipedia)、レスリー・レンケの音楽再現例 (Leslie Lemke – Simple English Wikipedia, the free encyclopedia)、ダニエル・タメットの記憶と言語才能 (Daniel Tammet – Wikipedia) (Daniel Tammet – Wikipedia)、サヴァンの左脳機能低下と右脳補償の仮説 ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC ) (The Mystery of Sudden Genius | Psychology Today)、TMSによる一時的サヴァン能力誘発 ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )、サヴァンの低次処理への直接アクセス仮説 ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )、脳梁欠損症のネットワーク研究 (‘Rain Man’-like Brains Mapped with Network Analysis | UC San Francisco)、遺伝的要因と候補遺伝子 (Heritability of autism – Wikipedia) (The Mystery of Sudden Genius | Psychology Today)、自閉症特性と才能発現 (Savant syndrome: What it is, symptoms, and links to autism)、AIとサヴァンの類似性・相違性 (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today) (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today) (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today) (The Quirky Brilliance of Large Language Models | Psychology Today)、才能の自発性と模倣性 ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC ) ( Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information – PMC )など。