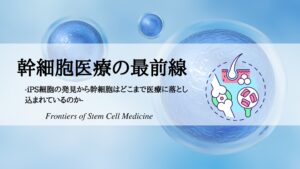タンパク質の構造を解き明かすことは、生物学における最重要課題の一つであり、人類は長年その解析技術を進化させてきました。X線結晶解析やNMR解析などの従来技術では限界があった分子構造の解像度や試料条件の壁を突破したのが、クライオ電子顕微鏡(cryo-EM)です。本記事ではcryo-EM登場の革新性を、構造解析の歴史を辿りながら明らかにします。


タンパク質構造解析の歴史
タンパク質の立体構造を初めて原子レベルで解明したのはX線結晶構造解析法です。1958年、ケンドルーらによってタンパク質・ミオグロビンの低解像度モデルが発表され、さらに1960年には同ミオグロビンの原子分解能構造が報告されました ( John Kendrew and myoglobin: Protein structure determination in the 1950s – PMC )。この成果により、ケンドルーとパーutzは1962年にノーベル化学賞を受賞しています ( John Kendrew and myoglobin: Protein structure determination in the 1950s – PMC )。その後、多くのタンパク質構造がX線結晶解析で明らかにされ、X線法は長らく構造生物学の主要手法となりました。
1980年代には核磁気共鳴法(NMR)によるタンパク質構造決定が確立されました。1985年にはウートリッヒらによってNMRで初めてタンパク質の全構造が決定され (Kurt Wüthrich | Nobel Prize, Protein Structure & Biochemistry | Britannica)、この業績は2002年のノーベル化学賞で評価されました。NMRは溶液中で分子を観測できるため、生理的環境に近い条件で構造や動的挙動を解析できる利点があります。しかし扱える分子サイズに限界があり、大きな複合体の解析は困難でした。それでも2002年時点で、構造データバンクに登録されたタンパク質構造の約20%はNMRによって決定されたものでした (Kurt Wüthrich | Nobel Prize, Protein Structure & Biochemistry | Britannica)。
電子線を用いた構造解析の試みも1970年代から始まっていました。1975年には電子線回折により膜タンパク質であるバクテリオロドプシンの構造が約7Åの分解能で解明され、生体高分子を電子顕微鏡で観察できる可能性を示しました ( Cryo-electron microscopy: A primer for the non-microscopist – PMC )。これらの先駆的研究により、後に同タンパク質で原子に迫る高解像度マップが得られ、アクアポリンなど他の膜タンパク質やウイルス粒子でも電子線による構造解析が進みました ( Cryo-electron microscopy: A primer for the non-microscopist – PMC )。ただし当時の電子顕微鏡解析では放射線ダメージを避けるため試料に重金属染色を施す必要があり、得られる像は20〜40Å程度の解像度に留まっていました ( Cryo-electron microscopy: A primer for the non-microscopist – PMC ) ( Cryo-electron microscopy: A primer for the non-microscopist – PMC )。タンパク質を生理的な水和状態のまま観察するという点で、電子顕微鏡法は長らく課題を抱えていたのです。
構造解析手法の比較
タンパク質構造解析に用いられる主な手法であるX線結晶解析、NMR、クライオ電子顕微鏡(cryo-EM)にはそれぞれ長所と短所があります (Comparing Analytical Techniques for Structural Biology) (Comparing Analytical Techniques for Structural Biology)。以下に各手法の特徴を比較表にまとめます。
| 手法 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| X線結晶構造解析 | ・原子分解能の高精度構造が得られる (Comparing Analytical Techniques for Structural Biology)・確立された手法で装置や解析手法が洗練 | ・良質な結晶が必要で、全てのタンパク質が結晶化できるわけではない (Comparing Analytical Techniques for Structural Biology)・結晶中の静的構造しか得られず、大きな動的複合体や膜タンパク質には不向き (Comparing Analytical Techniques for Structural Biology) |
| NMR解析 | ・溶液中で測定でき、生理的環境下の構造や動態情報が得られる (Comparing Analytical Techniques for Structural Biology)・非破壊的で小~中分子の解析に適する | ・高濃度かつ同位体標識試料が必要で調製が複雑 (Comparing Analytical Techniques for Structural Biology)・分子サイズが数万Da程度までと限定され、大きな複合体の高分解能解析は困難 (Comparing Analytical Techniques for Structural Biology) |
| クライオ電子顕微鏡 | ・結晶化不要で試料を急速凍結することで自然に近い水和状態を保ったまま観察可能 (Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure)・巨大な複合体や可塑的な分子集合体でも立体構造解析が可能 ([ How Cryo-EM Became so Hot – PMC ](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6186021/#:~:text=%E2%80%9Cnative%2C%E2%80%9D%20i,be%20too%20difficult%20to%20crystalize)) ([ How Cryo-EM Became so Hot – PMC ](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6186021/#:~:text=for%20macromolecules%20that%20previously%20had,24%20Khoshouei%20et%20al)) | ・高度な電子顕微鏡設備と専門的な試料調製技術が必要 ([Comparing Analytical Techniques for Structural Biology](https://www.nanoimagingservices.com/about/blog/unraveling-the-mysteries-of-the-molecular-world-structural-biology-techniques#:~:text=Disadvantages))・長らく分解能が低く「ボヤけた」像しか得られなかった(近年の技術革新により原子分解能に達しつつある) ([Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure](https://www.creative-biostructure.com/comparison-of-crystallography-nmr-and-em_6.htm#:~:text=match%20at%20L820%20In%20recent,macromolecular%20complexes%2C%20such%20as%20ribosomes)) |
※表中のcryo-EMの短所「分解能が低い」は、2010年代以降の“解像度革命”によって大きく改善されています (Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM - Creative Biostructure)。クライオ電子顕微鏡(cryo-EM)の技術革新
1980年代に入り、クライオ電子顕微鏡法(cryo-EM)によって試料を低温下で観察する技術が確立しました。最大のブレイクスルーは1984年頃にデュボシェらが開発した急速凍結法で、試料中の水を非結晶性のガラス状氷(ビトリス氷)に凍らせる手法です ( How Cryo-EM Became so Hot – PMC )。これによりタンパク質など生体高分子を水溶液中の自然な形態で凍結固定し、強力な電子線による損傷を抑えつつ観察することが可能になりました ( How Cryo-EM Became so Hot – PMC )。重金属による染色に頼らずに高分子複合体の内部構造まで可視化できるこの手法は、まさに画期的な技術革新でした (Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure)。
(File:Cryogenic electron microscopy workflow.svg – Wikimedia Commons) 図1:クライオ電子顕微鏡による単粒子解析のワークフロー模式図。試料を薄い氷膜中に封入して急速凍結し(1〜3)、電子顕微鏡で多数の粒子像を取得する(4)。得られた2次元像から粒子を検出・分類し(4〜5)、計算機上で平均化・立体再構成することで3次元マップが得られる(6)。最後にマップに原子モデルを当てはめて構造が決定される(7) (Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure)。
クライオ法の登場により、電子顕微鏡で生体高分子を直接その溶液中の構造で観察できるようになりました (Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure)。試料を液体窒素温度で保持することで電子線照射による構造崩壊を防ぎ、分子の水和殻も保持されます。これにより結晶化できない巨大タンパク質複合体や一過的な構造状態を含む試料でも、その立体構造を「ありのまま」に観察する道が開けたのです ( How Cryo-EM Became so Hot – PMC ) ( How Cryo-EM Became so Hot – PMC )。例えば結晶化が難しかったリボソームや膜タンパク質複合体の構造解析にcryo-EMが威力を発揮し、機能状態の異なる複数のコンフォメーションを同一試料中から同定することも可能となりました ( How Cryo-EM Became so Hot – PMC ) ( How Cryo-EM Became so Hot – PMC )。必要な試料量も数µL程度と比較的少なくて済み、濃度が低くても解析できる点も大きな利点です ( How Cryo-EM Became so Hot – PMC )。
こうした功績により、2017年には「生体溶液中で高分解能構造を決定できるクライオ電子顕微鏡の開発」に対してデュボシェ、フランク、ヘンダーソンの3氏にノーベル化学賞が授与されました ( How Cryo-EM Became so Hot – PMC )。彼らの先駆的研究(それぞれ試料凍結法、画像解析法、電子回折による高分解能構造解析の開拓)は、クライオEMを実用的な構造生物学ツールへと押し上げ、まさにタンパク質構造解析の新時代を切り拓いたのです。
最新の研究動向とクライオEMの威力
解像度革命と高解像度化の進展
2010年代半ば以降、クライオEMによるいわゆる「解像度革命」によって、この手法の解像能は飛躍的に向上しました (Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure)。鍵となったのは、電子を直接検出できる新型ディテクター(直接検電型カメラ)の導入と高度な画像処理アルゴリズムの発展です (Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure) ( How Cryo-EM Became so Hot – PMC )。2013年頃から実用化された電子検出器はそれまでのCCDを凌駕する高S/N比を実現し、個々の電子をカウントすることでブレやノイズを大幅に低減しました ( How Cryo-EM Became so Hot – PMC )。またBayesian統計に基づく画像解析ソフトウェア「RELION」の開発(2012年) ( RELION: Implementation of a Bayesian approach to cryo-EM structure determination – PMC )に代表される計算手法の進歩も、高精度な3D再構成に貢献しました。RELIONのアルゴリズムにより、ユーザーの熟練度に依存せず自動で最適化された再構成が可能となり、過剰なパラメータ調整なしで高品質なマップが得られるようになっています ( RELION: Implementation of a Bayesian approach to cryo-EM structure determination – PMC )。これら技術革新の結果、クライオEMではリボソームのような巨大複合体から膜タンパク質、果ては数十kDa程度の小さなタンパク質に至るまで原子分解能の構造決定例が相次ぎました ( How Cryo-EM Became so Hot – PMC )。実際、近年では分解能2〜3Åで原子モデルを構築できるケースも増え、2015年には膜タンパク質複合体で2.2Åの高解像度構造が報告されています ( How Cryo-EM Became so Hot – PMC )。かつて「ぼんやり」だったクライオEM像が、今やX線結晶解析に匹敵する細部まで見える時代となったのです。
(Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure) 図2:1976年から2024年にかけて主要手法で構造決定された件数の推移(ログスケール)。赤=X線、青=NMR、黄=電子顕微鏡(EM)、緑=複数手法の併用を示す。X線が依然多数を占めるが、2015年以降にクライオEM(黄)が急増し近年では新規構造の約40%を占めるまでになっている (Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure)。
上図が示すように、近年PDBに登録される新規構造の手法別割合は大きく変化しました。かつて全体の数%にも満たなかったクライオEM構造の占める割合は急伸し、2023年には全体の約3割強(31.7%)に達しています (Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure)。一方でX線解析が約66%と依然主流ではあるものの比率は低下傾向にあり、NMRは2%前後と限定的になっています (Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure)。この動向は、クライオEMが構造生物学において主役級の手法へと成長したことを物語っています。
AIを活用した構造解析と今後
近年、人工知能(AI)の活用もタンパク質構造解析に革新をもたらしています。とりわけDeepMind社の「AlphaFold2」は2020年のCASP14大会で画期的な構造予測精度を示し、2021年にはその手法が論文発表されました。AlphaFoldは配列からタンパク質の立体構造を高精度に予測でき、公開データベースには2億件を超えるタンパク質の予測構造モデルが登録されています (AlphaFold two years on: Validation and impact | PNAS)。これは実験手法では到底カバーしきれない膨大な数であり、未知タンパク質の構造予測に飛躍的進歩をもたらしました。
興味深いことに、AlphaFoldなどAIの台頭は実験的構造解析と競合するどころか相互補完的に機能しています。例えば実験で得られた低分解能のcryo-EMマップに対し、AlphaFoldの予測モデルを当てはめて細部を補完するアプローチが取られています (AlphaFold two years on: Validation and impact | PNAS)。実験データが予測構造の信頼性を検証し大まかなドメイン配置を与える一方、予測モデルはマップでは判別しにくい原子レベルの詳細を提供しうるからです (AlphaFold two years on: Validation and impact | PNAS)。実際、最近ではクライオEMマップ中の未識別密度に対応する未知タンパク質サブユニットを、AlphaFoldで予測した構造とのマッチングによって特定するケースも報告されています (AlphaFold two years on: Validation and impact | PNAS)。またAlphaFold予測構造はX線結晶解析でも分子置換のモデルとして活用され、実験相位決定を容易にするなど幅広く貢献しています (AlphaFold two years on: Validation and impact | PNAS)。このようにAIと実験手法の融合は構造生物学の新たな潮流となっており、クライオEMもその恩恵を受けてさらなる高解像度化・高速化が進むと期待されます。
シングルパーティクル解析技術の向上と今後
クライオEMの主流手法である単粒子解析も、アルゴリズムの改良により飛躍的な進歩を遂げました。単粒子解析では多数の粒子画像の平均化によりノイズを低減し高解像度の3D構造を再構成しますが、近年の計算能力向上と手法開発により、構造の微小な差異を分類して複数の状態を同時に解析できるようになりました。例えばRELIONによる3次元分類では、混合状態の試料から異なる構造コンフォメーションを自動抽出することができます。この技術により、従来は見過ごされていた機能中間状態や複合体の部分的会合/解離といった動的な構造変化も捉えられるようになりました。単粒子解析の精度向上と相まって、クライオEMは静的な構造モデルの提供に留まらず、生体分子マシナリーの動態や相互作用の解明へと貢献しつつあります。
今やクライオ電子顕微鏡はX線結晶解析・NMRと並ぶ構造生物学の柱であり、それぞれの手法を組み合わせることで相乗効果も発揮されています (Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure) (Comparison of X-ray Crystallography, NMR and EM – Creative Biostructure)。クライオEMで得た低温下の大まかなマップにX線やNMRの高精度部分構造を当てはめたり、逆にX線で難航する巨大複合体にクライオEMで見通しを立てる、といったハイブリッド戦略も一般的です。また、前述のAI技術との融合により、これからのタンパク質構造解析はますます高速かつ包括的になるでしょう。タンパク質構造解析の歴史を振り返れば、クライオ電子顕微鏡の登場はまさに革命的な転機であり、今なおその技術革新は現在進行形で進んでいるのです。