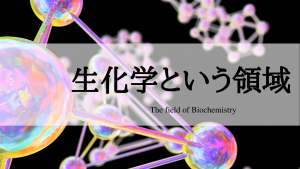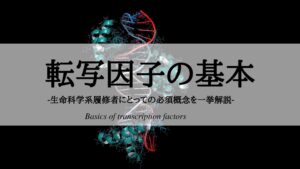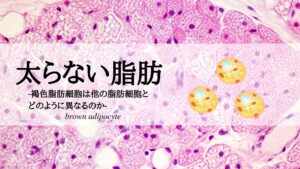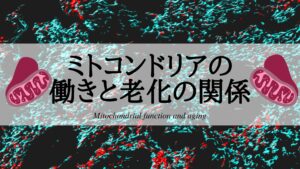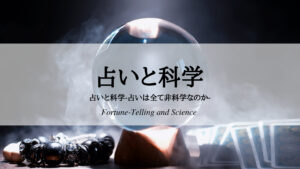DNAは今の世の中で様々な場面で聞くことになった物質です。
犯罪捜査に使われるDNA鑑定、コロナで話題のPCR検査なんかもDNAと関わりがあります。
そんなDNAが遺伝物質として理解され始めたのは1920年代で、まだその頃から100年も経っていません。
生物の教科書を開くとDNAを含めた核酸分子に関わる現象のほとんど全てが明らかにされているようにも感じますが、実際にはまだまだよくわかっていないことが多くあります。
本記事ではDNAが遺伝物質として発見された歴史から最先端の研究についてまで記載していきます。

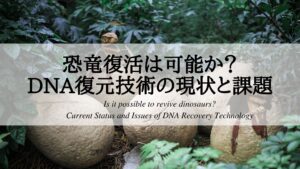
DNA発見の歴史概観
まずはDNA発見の歴史をざっと見ていきましょう。
正確にはDNAが遺伝子の本体であることが明らかになっていく歴史です。
これは高校の生物の内容でもあるので様々な場所で同じことが書かれているかと思います。
ただ、生命科学を語るにあたってこの内容を除外することは難しいため、あえてこのサイトでも取り扱いました。
大きくは以下の流れで進んでいきます。次の項目以降で一つずつサラッと説明していきます。

遺伝情報を握る本体を探る話 -タンパク質なのかDNAなのか-

グリフィスの実験
生命科学で最も有名な実験の一つにグリフィスの実験(1928年)と呼ばれるものがあります。
グリフィスは病原性がないR型菌と病原性があるS型菌を用いて菌の形質転換(病原性なし→病原性あり)を示しました。
具体的には、加熱処理によって感染性が失われたS型菌に対して、病原性が存在しないはずのR型菌を混ぜ合わせると実験マウスが肺炎で死亡することを示したのです。
実際のグリフィスの実験はこんなに単純ではありません。生物の教科書の挿絵などでは、グリフィスはこのページにも記載がある4つくらいしか実験を行っていないように書かれていますが、実際はグリフィスは40ページ以上に渡る論文内で行ったいくつもの実験と結果の解説を詳細に行っています。
グリフィスの元論文:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2167760/pdf/jhyg00267-0003.pdf
グリフィスの実験の結果
グリフィスの実験のイメージをまとめた図を作成しました。

グリフィスによって、何か生命情報を転換するためのコアとなるような物質が存在することは示唆されましたが、その実体はしばらくの間は不明でした。
当時の学会としては、タンパク質こそが遺伝子(生命情報を転換する物質)の本体であるという流れが主流だったようです。
参考:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2167760/pdf/jhyg00267-0003.pdf
エイブリーの実験
生命情報を転換する物質の本体は蛋白質かもしくはDNAが当時候補として上がっていました。
どちらかというと当時の学会の流れとしては蛋白質が生命情報を転換する物質と理解されていたようです。
その流れに反して、1944年にオズワルドエイブリー、コリンマンロマクラウド、マクリンマッカーティはDNAこそが細菌の形質転換を起こす物質である(エイブリーの実験)と示しました。
彼らは非病原性のR型菌がS型菌を砕いたものによって病原性を獲得する(形質転換される)ことを利用して、形質転換を握る物質である遺伝子の本体に迫りました(タンパク質なのかDNAなのか)。
具体的には、エイブリーらはS型菌を破壊したものにタンパク質分解酵素とDNA分解酵素それぞれを反応させ、その後R型菌に加える実験を行ったのです。
結果、S型菌を砕いたものによるR型菌の形質転換はDNA分解酵素での処理によって失われたことが示されました。
つまり、DNAこそが病原性の形質転換の鍵を握っていた物質ということになります。
実験の結果の概要は以下のようになります。
エイブリーの実験結果のイメージ

エイブリーの実験によって、肺炎双球菌の感染性の形質転換を握る鍵は蛋白質ではなくDNAであることが示されました。
出典:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2135445/pdf/137.pdf
ハーシーとチェイスの実験

ハーシーとチェイスもまた、T2ファージと呼ばれるバクテリオファージを用いて遺伝情報の実体がDNAなのかタンパク質なのかに迫りました。
T2ファージの構成要素はほとんどが蛋白質と核酸(主にDNA)です。
また、T2ファージは大腸菌に感染し、大腸菌を宿主として増殖することが出来るので、この検討にうってつけでした。
彼らはタンパク質(S32)とDNA(P35)のそれぞれを放射性同位体でラベル付けした上で、どちらの物質がT2ファージの大腸菌への感染に利用されているかを調べました。
ハーシーとチェイスの実験の結果
結果はT2ファージに感染した大腸菌は放射線同位体P35で標識された物質、つまり核酸(DNA)を持っていることが示されました。
つまり、T2ファージの感染能(遺伝物質)の中心は核酸(DNA)であることが示されたのです。
もちろん、この実験だけではあくまでT2ファージに限った結果ですが、先のグリフィスの実験、そしてエイブリーの実験を踏まえると、遺伝情報の本体がDNAであると実証されたと言えるでしょう。

・ハーシーは1969年にこの成果でノーベル生理学・医学賞を受賞するに至りました。
・エイブリーは遺伝子の本体がDNAであろうことを示したが、最終的に決定づけたのはハーシーとチェイスの実験というような説明をネットのところどころで見ましたが、明確にそのような根拠となる文章を公式な発行物から見つけることが出来ませんでした。具体的には、例えばエイブリーらの論文では1ページ目にグリフィスの名前が出てきますが、ハーシーとチェイスの論文中にエイブリーの名前は確認した限り出てきません。このあたりの研究史は引き続いて調べて行きたいと思います。
参考:https://rupress.org/jgp/article-pdf/36/1/39/1240738/39.pdf
ワトソンとクリックによるDNAの二重らせん構造の発見

生物に全く興味がない人でもワトソン博士とクリック博士については名前くらい聞いたことがあるという方は多いのではないでしょうか。
当時の科学界はグリフィス、エイブリー、そしてハーシーとチェイスの研究から遺伝子の本体はDNAであると信じられるようになっていました。
しかしながら、依然としてDNAの構造やDNAと蛋白質の関わりは不明でした。
当時、生物学者のワトソン博士と、化学者のクリック博士はロックフェラー研究所であぁでもないこうでもないとDNAの構造を議論していたと言います。
仮説はあるものの決定的なデータが無く、どうしたものかと困っていたところでウィルキンス博士という構造屋さんの研究室で一つのX線写真を目にします。
これこそがかの有名なフランクリンという結晶学者によるDNAのX線回折像です。
ワトソンとクリックはフランクリンに話を通すことなく、フランクリンの研究室のボスのウィルキンスからの許可のみで自身たちの仮説を後押しする根拠としてフランクリンのデータを利用してしまいます。
結果、論文は世界的に有名な科学雑誌であるNatureに受理され、この研究をきっかけにワトソンとクリック、そしてウィルキンスはノーベル医学生理学賞を受賞するに至るのです。
ノーベル賞の一度の受賞人数が3名であることも理由でしょうが、フランクリンの名前は表舞台に出ることはなく、X線による被爆も影響してフランクリンは38歳の若さでこの世を去りました。
このエピソードはワトソン自身も語っているので概ね事実でしょうが、今後の科学界に様々な影響を及ぼしていくことになります。
当のワトソン博士はと言うと、ノーベル賞のメダルをオークションに出したり、プライベートでも世間をたくさん賑わしたようです。TEDの話を聞いてると、軽快な喋り口であるため、愛される性格であったことは間違いないでしょう。

・X線結晶構造解析は大雑把に以下の流れで進みます。
1. 蛋白質の結晶化
2. X線照射
3. 回折像の入手
4. 構造解析
それぞれにかなり高度な専門的な知識・技術が必要です。これらもまた別の機会に詳細を執筆したいと思います。
分子生物学界のセントラル・ドグマへの道
セントラル・ドグマ(central dogma)をそのまま日本語に訳するとき、「中心定理」という言葉が用いられます。
ある事象の中心に存在する揺るがない法則とでも解釈しましょうか。
当時、DNA、RNA、そして蛋白質と当時役者は揃っていましたが、どのようにそれぞれが関係しあって生体内で働いているかよくわかっていなかったのです。
ワトソン博士とクリック博士の思考
ワトソン博士は1953年の自身の論文の中で遺伝情報(genetic information)という言葉を用いており、当時遺伝情報をDNAが何らかの形で司っているという考え方が広く受け入れられるのに時間はかからなかったようです。
しかしながら、具体的に遺伝情報がどのようなものによって構成されているか、そのアイディアは誰もわかっていなかったことも伺えます。
RNAとDNAの関係性も当時よくわかっておらず、ワトソンは一時はDNAがRNAに構造変換されるというような考えも持っていたようです。
DNA、RNA、蛋白質と役者は揃っているものの、なかなか関係性が明らかにならない中で、ジョージ・ガモフ博士とワトソン博士はRNAタイクラブ(RNA Tie Club)を立ち上げました。
RNAタイクラブ(RNA Tie Club)はRNAから蛋白質が生み出される仕組みの解明を目的とした科学コミュニティーで、メンバーにはクリック博士はもちろん、ブレナー博士、リチャード・ファインマン博士といったノーベル賞受賞者も含む名だたる学者(数学者、物理学者等)が参加していました。
暗雲めいていた生命現象の複雑性に世界屈指の頭脳が集うことで大きな活路を見出していくのです。
実際にRNAタイクラブでの議論に着想を得て、クリック博士はDNA→RNA→蛋白質の流れを図式化してまとめることに至ります。
そう、それが2023年の今日も語り継がれる分子生物学界のセントラル・ドグマです。
ちなみに「セントラル・ドグマ」という言葉はクリック博士が1956年に自身の未発表のノートの中で初めて用いたとされています。

こちら(https://journals.plos.org/plosbiology/article/figure?id=10.1371/journal.pbio.2003243.g001)のクリック手書きの図を参考にnicorasにて作成。Created with BioRender.com
クリック博士が提唱したセントラル・ドグマは科学界に衝撃を与え、2023年現在どの国でも生物の教科書に載るほど一般的な存在として認知されています。クリック博士が提唱した当初はRNA→DNAへの逆向きの転写は可能性としては生じうるものの、生物学的な現象としては想定できるものが無いとされていました。クリック博士がセントラル・ドグマを提唱した15年以上後の1970年にハワード・マーティン・テミン博士とデビッド・バルティモア博士によって、RNAからDNAに向けて転写が行われる逆転写酵素が発見されたのです。なお、逆転写酵素の発見によって両者は1975年にノーベル賞を受賞しています。
※逆転写酵素の発見をクリックが提唱したセントラル・ドグマを覆す発見と表現している記載が一部ありますが、それは間違いのようです。クリック博士は当時からRNA→DNAの逆転写が生物学的な現象として起きうることを想定していたとのことです。実際この言説通り、当初クリックが手書きで書いたセントラル・ドグマの図式の段階で点線ではありますが、RNA→DNAのラインが存在します。
参考:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5602739/pdf/pbio.2003243.pdf
DNA研究の最先端

あまりにも数多くある核酸分子。過去、DNAは遺伝情報を持っているだけと考えられていましたが、そうではないということが近年強調されてきました。
ヒトゲノム計画が思い出されます。
ヒトゲノム計画とは1990年にアメリカ政府によって始められた研究計画で、ヒト細胞の核内にあるDNAの全塩基配列を解読することを目的として始められたものです。
その期間は15年間で、当時の予算で30億ドルもの金額が注ぎ込まれた研究計画となりました。

ヒトゲノム計画は当初の計画を5年前倒して2000年に完成し、2003年にはヒトの全遺伝子の99%の配列が99.99%の正確さで含んだ完成版が公開されました。
しかしながら、全て読み終えた後にそもそもタンパク質に翻訳されない非コード領域と呼ばれる領域がDNAには多く存在することがわかったのです。
驚くべきことに、ヒトゲノム計画で明らかとなったDNA配列のほとんど(98%)は、遺伝子ではなく非コード領域だったとも言われています。
また、近年DNAの転写制御は後天的にも多くの制御を受けることもわかってきました(エピジェネティクスと呼ばれる領域も含みます)。
分子生物界のセントラル・ドグマと呼ばれるDNA→RNA→タンパク質の流れはあまりにも基礎的なもので、生命の複雑性を理解するにはまだ人間はその山の全貌すらも確認出来ていないような状態だったとも言えるかもしれません。
本記事はあくまで基礎的なDNAの発見の歴史と最先端研究の触りということで、今後それぞれ細かく区切ってより詳細に解説していきます。
乞うご期待ください。